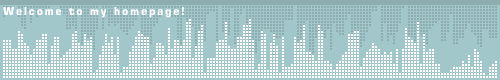音円盤アーカイブス(2005年9,10月)

王道テナーカルテットの作品で、選曲がこれまた王道で「TENOR MADNESS」「YOU'VE CHANGED」「YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS」「EVERYTHING HAPPENS TO ME」など、嬉しい事に「BLUE SEVEN」「BEATRICE」も演っているでないか。
ジョシア・レッドマン、クリス・ポッタ、エリック・アレキサンダー、マーク・ターナーなんかが野球に例えたらメジャーリーグの中堅スター選手というところだと思うのだけれど、このTIM ZANNESはさしずめマイナーリーグで八面六臂の活躍をしている注目の選手と言ったところだろう。
インナースリーブには自主製作の為か、紙一枚のものでレコーデイングに関するクレジットのみで本人のバイオグラフィーには一切触れられていない。
自身のHPもないみたいなので、年齢や出身地、音楽的な経歴等一切わからないのだけど、写真から判断すると30代か?
TIM ZANNESはオーソドックスなストレートジャズを追求している。
バラードナンバーでは抑制されたセンチメンタリズムを感じさせるビターテイストなテナーサックスを聴かせ、ミディアム、アップテンポの曲ではひたすらスイングして歌うことに専念する。
自分の追求するジャズを心の底から信望しているのでプレイに迷いや邪念がなく出てくる音にも説得力がある。
最近のスタイルや奏法に色目を使わず、一徹に歌うことに専念するプレイは頑固さとともに意志の強さを感じさせる。
ジュニア・クックやジョージ・コールマンなどに通じるテナーサックスの王道的スタイルは現代ジャズ界において逆に貴重なのかもしれない。
注文もある。オリジナリティーの問題。
決まったスタイルの中でいかに人とは違う個性、独自の音作りをやっていくか?
ローカルではこれで充分いいのかもしれないがジャズのセンターコートではそういう訳にはいかないだろう。
もっとも本人はそんなことにはとんと無頓着なのかもしれないが・・・
メンバーはTIM ZANNES(TS)BERT DALTON(P)JOHN BELZAGUY(B)RICKY MALACHI(DS)
1996年作品
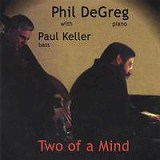
シンシナティで活躍するピアニスト、PHIL DeGREGの新作でPAUL KELLER(B)とのDUO作品。
PHIL DeGREGはシンシナティ音楽大学のジャズ部門の教授で作曲とピアノを教えている傍ら、地元のジャズクラブ「THE BLUE WISP JAZZ CLUB」で演奏活動を行っている。
このライブアルバムはそこではなく、「82 HUNDRED GRILL」という場所で2003年冬に録音されたもので、全体的にリラックスした雰囲気の中にも演奏の隅々にまで心の行き届いた工夫が随所に感じられ、メリハリのついた一本筋の通ったプレイとなっている。
ベースのPAUL KELLERはミシガン出身で、デトロイト地区のスモールコンボやビッグバンドの作編曲家としても活躍している。
ダイアン・クラ-ルやラッセル・マローンのアルバムに参加していることで知られている。
ソリッドでピッチの非常に安定した奏法はこういうデュオ作品でひときわ際立ち、
木の質感がよく出たピッチカートの音はまさに隠れた名手と言った感じがする。
二人のコンビネーションはとても良くて、アルバムを通してだれることがなくいい意味での緊張関係が維持される。
決して冒険するようなタイプの演奏を二人ともおこなうわけではないが、決められたルールの中で濃密なインタープレイがおこなわれた内容の濃いデュオ作品として
お薦めしたい。
二人ともどちらかと言うと地味なミュージシャンなので、演奏に派手さや華を追い求めている方にはすこしもの足りなさを感じるかも知れないが、アメリカのローカルシーンではこういう実力派の演奏が日常的に聴けるのだなぁと思った次第。
メンバーは、PHIL DeGREG(P)PAUL KELLER(B)
録音は2003年 冬

ちょうど昨年の今頃、このブログに書いたと思うのだけど、このNITA SELLの唄に一辺に惚れ込んでしまった。
もしパソコンでREAL AUDIOがインストールされているのだったら今直ぐにでも1曲目の「TIME SUSPENDS」と6曲目「SPANISH BLUE」を聴いてみて欲しい。
スローなラテンリズムに乗って緩やかに滑り込んできたNITAの声のファンに一目惚れならず、一聴惚れしてしまったというところで、その声質はアイリーン・クラール系のもの。
心の奥に強い意志を持っているのを感じさせるのと同時に女性らしい細やかな心遣いを持ち合わせ、そこはかとない哀愁味にコーティングされた声が、とても素晴らしい。
押し付けがましさや媚を売るといった風情は一切なく、あくまでもナチュラルに自分のボーカルを披露している点にとても好感が持てる。
作曲能力にも恵まれておりこのアルバム中11曲中7曲が自身のオリジナル。
今月号のSJに寺島さんが書いていたけど、NITAも「つぶやき派」「自然派」にはいるだろう。間違っても「絶唱派」ではない。
ボーカルに関しては、好みで聴く度合いが強いと思われるがわたしの場合もそうで
好き嫌いを判断基準にしている。
この前10数年ぶりに、怪物ビリー・ホリデイを聴いたけどやっぱり駄目だった。
好きな人には申し訳ないが私は駄目である。
逆に言うとエラ、サラ、カーメン、ホリデイを受け付けない方にはお薦めのアルバムといえるのかも知れない。
アメリカの地方都市のジャズクラブで深夜聴いている様な気分にさせてくれるジャズボーカルアルバムだと思う。
2002年作品

「世紀の大発見! 幻のレコーディングが遂に蘇る!」
これ、今月号SJ巻頭見開きカラーページ、東芝EMIの同作キャッチコピーなんですが、これに思わず心踊らされてタワーレコードに買いに行ってきました。
モンクとコルトレーンの1957年の共演テープがどこかに存在するのは、昔から有名な話だったけれども、いざ、それがこうして現実のものとなり、録音自体もほぼパーフェクトと言ってよい状態で発表されると素直に感動してしまう。
そう言えば、オーネット・コールマンとコルトレーンの共演テープもどこかに存在する話を同じ頃聞いた記憶があるので、いつかはそれも発表されるかもしれない。
実際の内容は、既存の音源がかすんでしまうと言ってよい素晴らしい内容の演奏で、4曲目「NUTTY」から7曲目「SWEET AND LOVELY」のところを特に繰り返し聴いている。昨日からもう5回くらいCDトレイに載せていて、こんなにコルトレーンの演奏を集中して聴くのはたぶん、四半世紀以上前の高校生の頃以来のことではないかと思う。
それくらいここでのコルトレーンの演奏は素晴らしい。
今年度の未発表作品のNO1候補の最右翼作だと思う。
冒頭のキャッチコピーに偽りはない。
全てのジャズファンの方に聴いてもらいたい一作だと思う。
メンバーはTHELONIUS MONK(P)JOHN COLTRANE(TS)AHMED ABDUL-MALIK(B)SHADOW WILSON(DS)
録音は1957年11月29日 CARNEIE HALL, NYC

あまり有名ではないというかほとんど知っている人がいないと思われるALLEN MEZQUIDAのアルトサックスが聴きたくて手に入れたCD。
自分がもし、プロのサックス奏者で聴衆の前で演奏するとすれば、さしずめメスキダの様な音色で吹いてみたいと思わせるような理想的な音色の持ち主なんですね。
アルトサックス本来の音をとても大切にしているミュージシャンだと思うのだ。
サックスの中でも最も肉声に近い帯域を持ち合わせているアルトサックスの特性を最近のミュージシャンの中で最も上手く自身のスタイルに取り込んでいる奏者の一人だと思う。そこには、大森明の名前も思い浮かぶ。
レ二ー・ニーハウスじゃないが、水晶の輝きを思わせる倍音が豊かに含まれた高音域とビターテイストでありながらほのかな哀愁味を感じさせる滑らかな中域。
ジャズは勿論個性の音楽だから、各々のミュージシャンが自分の音色、スタイルを確立していってオリジナルな音楽を作り上げていく。
その過程で当然、捨て去る部分もでてくるわけで、現代のミュージシャンの中にはこうしたアルトサックス本来の美しい響きをある程度犠牲にして自身の音楽を確立しているプレイヤーが少なからずいるのは確固たる事実だと思う。
人によってはメスキダのプレイを線が細いとか、個性に乏しいといったもの足りなさを感じる方がいるかも知れない。
本人がどちらかと言うと自己主張の強いタイプのミュージシャンではないし、
売らんかなの上昇志向の強いタイプでもないので、上辺だけを聴いているとメスキダの良さに気が付かずに通りすぎてしまうかもしれない。
何回か繰り返し聴いてみて欲しい。メスキダの良さに必ず気が付くはずだから。
メスキダのことばかり書いていまったけど、このアルバムのリーダーSEAN SMITHは
メスキダとの活動歴が長い中堅のベーシストで、全曲をオリジナルで固めている。
カルテットで演奏されていてピアノにはBILL CHARLAPが参加、ギターをいれたカルテットバージョン使い分けてバラエティーを持たせている。
メンバーはSEAN SMITH(B)ALLEN MEZQUIDA(AS)BILL CHARLAP(P)KEITH GANZ(G)RUSSELL MEISSNER(DS)
録音は2001年2月26,27日 STAMFORD
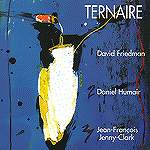
DUEX Zから1992年にリリースされたハイブロウな秀作。
2000年にイブ・ロベールの幻視的な名作「LETE」を購入して以来このレーベルもとんと情報がはいってこないのだけど、活動しているのだろうか?
90年初頭はこの作品以外に、ヨアヒム~バーガンジィー、アラン・ジャン・マリー~バルネなど力作を発表していた時期でこのアルバムも期待して聴いてみた。
DAVID FRIEDMANのバイブもJENNY-CLARKのベースも勿論素晴らしいのだが、耳を捕らえて離さないのが、DANIEL HUMAIRのドラミング。
風貌だけで判断するとそこら辺の酒好きの気さくなおっちゃんといった感じだけど、一旦ドラムの前に座ると待ったなしの真剣勝負が繰りひろげられるといった印象を抱き続けてきた。
鋭い刃物のように空間を切り裂く的確でタイトなドラムは、共演者に嫌が上でもリアルファイトを仕掛けるかのよう。
ユメールがドラムだと引き締まった演奏になるのは、間違いない。
一昨年SKETCHからリリースされた自身のクインテットアルバムなど、あまりにも緊張感に溢れすぎて聴いているこちらが息切れしてしまい、よほど集中して聴かないと取り残されてしまうほどテンションの高い作品だった。
ユメールには音の求道者といったイメージを抱いている。
ヨアヒム・キューンのトリオでも「ラスト・タンゴ・イン・パリ」など1曲だけ甘口の演奏を入れてアルバム全体の仕上がりを中和する手法をとっていたが、このアルバムではその役目をDAVID FRIEDMANが担っていると言っても良いのではないか。
バイブラフォンという楽器特性そのものから生まれる硬質でありながらも、サウンドのニュアンスは清涼感溢れる食後の砂糖菓子みたいなDAVIDのプレイはいい意味でこの作品を緊張感溢れるエンターテイメント作品に中和する役割を果たしていると思うのだ。
これがウォルト・ディッカーソンなんかだったらそういう訳にはいかなかっただろう。最後まで何でも有りのバーリ・トゥードの勝負がおこなわれて最後は奏者も聴衆も全員ノックアウトだったかもしれない。
最後まで緊張感を持続させつつ聴衆とライブ空間を見事に共有し、お互いに楽しんだ素晴らしいライブ作品だと思う。
メンバーはDAVID FRIEDMAN(VIB)DANIEL HUMAIR(DS)JEAN-FRANCOIS JENNY-CLARK(B)
録音は1992年1月15,16,17日 PARIS

1999年にPADDLE WHEELからリリースされた宮之上貴昭の完全ギターソロ作品。
発売されて直ぐに入手した記憶がある。
本人の生演奏を聴いた事はないのですが、昔から親しみのあるミュージシャンで、
学生時代の行きつけのジャズ喫茶「JOKE」でも何回か聴いたと思う。
それより、K原君からその頃、スイングジャーナルの読者売買欄に宮之上貴昭がウェス・モンゴメリーのレコードを買います(だったと思う?)と投稿しているのを見たという話を聞いた。
「プロのミュージシャンでもそんなことするんだ」とその時思ったを覚えている。
もっとも70年代初頭の頃の話なので、宮之上が正式なプロ活動する前のことかもしれない・・・
このCD,宮之上自身のレコーディング談がライナーノーツに書かれているが、集中と忍耐の賜物による一作だと言える。
レコーディングはベストのテイクを取る為に何日にも分けられ1日、10時間以上に及んだこともあるらしい。
苦労して録音されたナンバーがこうして一枚の作品に編集されているわけだが、緊張感とリラクゼーションが見事に交錯した素晴らしいライブ感覚に富んだアルバムとなっていることを絶賛したい。
作品としてのストーリーが出来ているし、ライブでの疾走感、スピード感といったものがCD上でリアルに再現されているのだ。
ソロギターの作品は数あれどこれほで生々しい雰囲気が記録された作品を私は聴いた事がない。
深夜、ウイスキーを舐めながら聴くと、宮之上がスピーカーとスピーカーの間にポッカリと浮き出てギターをつま弾き始めてくれていると錯覚するするぐらい臨場感溢れた録音にも満点を献上したい。
宮之上 貴昭ソロギター
録音は1999年2月1-7日

ロングアイランドで活躍しているテナー奏者PAUL KENDALLのワンホーンもの。
10曲中7曲MATTHEW FRIESがピアノを担当している。
同じく1999年にリリースされたBROWNSTONE盤をずっと探していたのだけどこちらが先に手に入ってしまった。
季節はめっきり秋めいてきて、晴れた日にも乾いた涼しい風が吹いてとても気持ちのいい気候となった。
今はクーラーが自室にもついているので、夏もジャズ鑑賞は快適なんだけど、以前はこうはいかなかった。10分も聴いていると全身から汗が吹き出し、タオル片手によく聴いたもんだ。部屋の明かりが間接照明なので、10数個の電球とアンプの発する熱だけで、室内はまるでストーブを焚いているかのように温度が上昇するのだ。
そんな中で聴くジャズは我慢大会しているようなもんで、我ながらそんな中でよく聴いていたと思う。さすがに電球の点灯の数は減らしていたけれども・・・
関係の無い話を最初からしてしまったけど、このPAUL KENDALLの作品など、今日のような穏やかな秋の1日に戸外で聴くのに最適な一枚だと思う。
風通しのよい聴いていて確実にスイングさせてくれるジャズ。
シダー・ウォルトン「FIRM ROOTS」コルトレーン「IMPRESSIONS」ジョー・ヘン「RECORDAME」(蛇足だが私のアドレスはここから頂いている。)シルバーの「BARBARA」とジャズオリジナルを散りばめながらスタンダードを数曲、半々くらいの配分で演奏。このペース配分も非常に良い。
鑑賞が進むにつれこちらの気分がどんどん高揚する仕掛けになっていて、プロフェッショナルな仕事がなされている。
変にアーティスティックにならずに日常のプレイにメンバー全員が徹しているのも気負いがなくて良いと思う。
メンバーはPAUL KENDALL(TS)MATTHEW FRIES(P)DAVE JACKSON(B)SKIP SCOTT(DS)ALVESTER GARNETT(DS)TIM REGUSIS(P)
録音は1998年 NYC
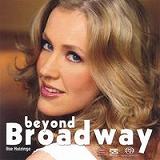
思わずジャケ買いしてしまった一作。
残念ながらまだどこの店にも売っていないと思う。
海外の通販サイトから自分用にまず仕入れて聴いてみようと思ったのです。
値段がやけに高いなぁと思っていたら、ハイブリッドSACDでした。
どうです?彼女、美人でしょう?
自身のHPでは、特大のポートレートがダウンロードできて、是非ご覧になってみてください。 http://www.ilsehuizinga.com/
残念ながら結婚していて、旦那はちなみにこの作品でもピアノを弾いているERIK VAN DER LUIT。2000年に子供も生まれてれっきとしたお母さんでもある。
このアルバムは5枚目の作品のようで、地元アムステルダムでは人気急上昇中の美人ジャズボーカリストといった位置づけのようだ。
夫が率いるピアノトリオをバックに有名曲が次々と唄われる。
「I LOVE YOU,PORGY」「SOMEONE TO WATCH OVER ME」「GOODBYE」「MAD ABOUT THE BOY」「ON THE STREET WHERE YOU LIVE」「I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT」「I'LL CLOSE MY EYES」「YOU AND NIGHT AND THE MUSIC」「EV'RYTIME WE SAY GOODBYE」「MANHATTAN」など。
数曲でサックスが間奏を受け持つ。
素直な歌唱はとても好感を感じるし、唄の深みといった点ではまだまだ物足らないところが多々見受けられるけど、応援していこうという気持ちになるのも確か。
部屋のディスプレイなんかにも良いジャケットだしね。
50年代から白人系ボーカルには、こうした視覚的要素の部分がとても大きくて、
人によってはそちらの方が大部分をしめている方も実際いるわけで、それはそれで全く正解なのである。
だって趣味であり、言ったら道楽なんだからね!
お遊びの部分がないと面白くないし、そういう余裕がなければ、何十年もひとつの趣味を続けれる訳がないと思っている。
あっー、けっしてILSE HUIZINGAの唄が不味いと言ってるんじゃありませんよ!私は。
メンバーはILSE HUIZINGA(VO)ERIK VAN DER LUIJT(P)BRANKO TEUWEN(B)VICTOR DE BOO(DS)ENNO SPAANDERMAN(SAX)
録音は2005年2月17,18日

これは、川崎燎のMPSに吹き込まれた一作で、今から四半世紀以上前の録音で個人的にはとても懐かしい。
大学一年の時に、日本盤がでて直ぐに買ったと思う。
DAVE LIEBNANが自分のHP上の完全ディスコグラフィーでこの作品のことを忘れていたのか、この作品が抜けていた。今はアップされているけど。
この頃の川崎は、ジャケットを見てもらえばわかる様に後のロングヘアーではなくショートカットのサーファー風のルックス。
レーベルもRCA,キュアロスキューロ、当作品のMPSと海外のレーベルから作品を発表し、ギル・エバンスのレコーディングやTIMELESSからジョアン・ブラッキーンやクリント・ヒューストンのレコーディングに参加したりと世界を股にかけて八面六臂の活動をしていた油ののっていた時期の一枚で、最もジャズテイストの強い作品。
川崎というと、このレコーデイングでもたびたび聴かれるペンタトニックを基調とした手癖フレーズ。妙に印象に残る耳についていつまでも離れないフレーズだ。
川崎の昔のインタビューの内容を今、思い出したのだが影響を最も受けたギタリストの名前に、ウェス~ジョージ・ベンソン、ジョン・マクラフリン、ジミ・ヘンドリックス、ヴィラ・ロボスやクラッシックのギタリストの名前も上がっていた様な気がする・・・
この作品を聴いてなるほど、なるほどなぁと思いを新たにした。
私のフェバレットソングはA面4曲目「THE STRAW THAT BROKE THE LION'S BACK」B面1曲目「THUNDERFUNK」。
これ以降も素晴らしい作品をリリースしているが、この作品を機に川崎のファンになったのでひときわ思い入れが深い作品です。
いまのところ未CD化のはずだけど、中古レコードでそんなにしないと思うので是非聴いてもらいたい作品。
メンバーは川崎燎(G)DAVE LIEBMAN(TS,SS)ALEX BLAKE(ELB)BUDDY WILLIAMS(DS,PER)
録音は1978年3月 STUTTGART

この作品は4年前の春先に仙台DISK NOTEから購入した。
当時は(今でもそうなのだが)ノルウェージャズに疎く、ノルウェージャズの大家M,I.Z.さんのHPでよく勉強させてもらっていた。
このアルバムもM.I.Z.さんが紹介されているのを見て、関心を持ち購入にいたったもの。
JACOB YOUNGをはじめとしてARVEHENRIKSEN,TRYGVE SEIM,HAKON KORNSTAD,CHRISTIAN WALLUMRODなど今でこそ耳馴染みのミュージシャンだけど、
その頃はそれこそジャズを聴き始めた頃の様にミュージシャンの名前と演奏を頭の中にインプットしていく作業を繰り返して、現代ノルウェージャズの勉強をしたように思う。JACOBのギターは昨年ECMからリリースされた新作よりも、ずっとジャズテイストが強めで、パット・メセニーやジョン・スコフィールド、アバクロンビーを連想させるサウンドも聴かれ耳に入りやすい。
ARVE HENRIKSENはこのころから独創的な音色でユニークなトランペットが聴かれる。様々な音楽的要素の入りこんだ楽曲を無理なく一枚のアルバムの中にスムースな流れで聴かせる手腕はギタープレイと並んで評価できると思う。
そしてノルウェーのヤングジェネレーションの音楽的レベルの高さも体験できるエポックメイキングな一枚と言えるのではないだろうか?
YACOB YOUNG(G)TRYGVE SEIM(TS)HAKON KORNSTAD(TS)OYVIND BRAKKE(TB)MATTS EILERTSEN(B)JARLE VESPESTAD(DS)CHRITIAN WALLUMROD(EP)他
録音は1999年10、12月、2000年3,4月、2001年2月

VINCENT COURTOIS,MARC DUCRET,DOMINIQUE PIFARELY弦楽器奏者3人によるアルバムで、魅力的なメンバーがどんな音楽を展開しているかは勿論、デジパックのジャケットのモノクロ写真が素晴らしかったので購入したCD。
譜面をもとに演奏されているところもあるのだろうけど、基本的に三者のインプロヴィゼーションから成り立っている音楽。
メロディー、ハーモニー、リズムの音楽三大要素って言葉があるけど、この3人のミュージシャンは変幻自在にその役どころを行きかいして、暗闇に隠れた音の素粒子を手繰り寄せ増幅し音の実像を映し出す鏡のように音のフォルムを映し出し、形成する。
お互いの発する音に、新たな化学反応が起こり、新たに融合されたサウンドカラーが生み出される。そこに再び新たな音が加わりと演奏の進行とともに次々と音のコラージュが作られると言った按配。
聴く人を選ぶ類の音楽だとは思うけど、心を真っ白にして一度耳にしてもらいたい音楽。
メンバーはVINCENT COURTOIS(CELLO)MARC DUCRET(G)DOMINIQUE PIFARELY(VLN)
録音は2000年12月

N山さんからお借りした一枚、注文しようと思っていたCDだったのでとてもラッキー。 メンバーが最高なので、嫌が上でも期待が盛り上がる一作。
2曲目「BRIGHT IDEA」が良い。TIM BERNEの集中力に富んだコクのブルースフィーリングに溢れ自由に飛翔するソロ、RALPH ALESSIの均整の取れたスタイリッシュでクールな表情を見せつつ揺らぎを感じさせるソロ、CRAIG TABORNのジャズの伝統を押さえつつ自由に鍵盤上を煌びやかに駆け巡るソロが続き、リーダーのDREWGRESSとTOM RAINEYがしっかりとリズムの屋台骨をキープ。
ここには、ミュージシャンのリアルな解釈のストレートジャズがある。
レコード会社が(特に日本の数社)プロデュースしたというより、ミュージシャンの演奏を日本仕様に仕立て上げたと言ったら言葉が悪すぎるかも知れないが、日本企画の作品は人工的な匂いがして私はあまり進んで聴く気になれない。
販売戦略と予算をもとに、マーケティングの匂いがぷんぷんと鼻についたジャズ。
これが悲しいかなお金をかけた以上マーケットで最も幅を利かせているし、実際最も売れている。
この図式は何十年も前から音楽産業の一部であるジャズマーケットもそれに巻き込まれているわけだけど、昔はまだましだった。現在の日本のジャズマーケットは最悪だと思う。同じ作品を毎月のようにゴールド仕様や紙ジャケや重量盤LPとどんどんリリースし、広告出しまくり音といえば安物のオーディオ装置やラジカセでもそこそこの音で聴こえるようにレベルとハイとロウを強調して録音、ミキシングされた最悪の録音。
パッケージングや旬のミュージシャンを捕まえてくるテクニックには長けている。
ここまで書いたらどこのレーベルのことかこのブログを読んでいる皆さんもお分かりだと思うのだけど、私ははっきり言います。
「嫌い」です。
買おうと思って試聴機で試聴するとそのひどさに買う気がうせてしまう。
もっとも頭に来るのは「4ビートジャズ」頑張ってます!みたいな善人づらして業界のオピニオンリーダー、イニシアチブを取っているかのような取り扱われ方。
もっともこのティム・バーンやマシュー・シップの新作をだしたら土下座してあやまりますけどね。
そんなことは100%ないから断言しても大丈夫なのであーる。
今日は何時になく喧嘩吹っかけてるかのような過激なVENTO AZULでした。
別に家庭が上手く言ってないわけではないのでね。
メンバーはDREW GRESS(B)RALPH ALESSI(TP)TIM BERNE(AS)TOM RAINEY(DS)CRAIG TABORN(P)
2005年作品

BOBBY WATSONとVINCENT HERRINGが共演しているJOHN HICKSの1996年作品。
残念ながらヴィンセントの方は5曲でテナーを受け持ち、アルトサックスで正面きってのバトルは一曲のみ。
ソロオーダーの途中、大抵フルートのELISE WOODが中入りみたいな形といっては、本人に気の毒だけど、入るのは作品としての焦点をぼやかせる結果となったのかも知れない。
ELISEを入れずにサックス二人のバトルにもっとフォーカスして、ソロのコーラス数を増やした方が良い作品になった様な気がする。
もっとも、狙いはサックスバトルを指向した作品でもなんでもないので、こちらが見当はずれのことを言っている可能性が高いのだけど・・・
ファンとしてはゴリゴリ、バリバリのバトルをついつい期待してしまう。
JOHN HICKSがTS,AS,FLの3菅編成の音が欲しかったというのが実状だろう。
そんなシチエーションの元、ヴィンセント・ハーリングもボビー・ワトソンもプロとしての仕事は十二分すぎるぐらい演っているのだけど、演奏自体がスパークしてミラクルが起きるような場面は残念ながら起こらない。
ふたりとも、根はエビセン体質(やりだしたら止まらない?)なので、あまり編曲を加えないでヘッドアレンジだけで、思いっきりブローさせた作品にすれば、もっと良い作品になったと思う。
アルバムでは9曲目「MY SHINIG HOUR」が現に一番良い出来に聴こえるのだ私だけだろうか?
3、4曲目がピアノトリオで演奏されるのけど、ミンガスの「DIANE」が結構聴き物であることを付け加えておきたい。
メンバーはJOHN HICKS(P)BOBBY WATSON(AS)VINCENT HERRING(TS,AS)ELISE WOOD(FL)CURTIS LUNDY(B)CECIL BROOKS(DS)
1996年作品
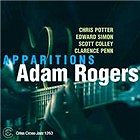
ADAM ROGERSの2005年CRISS CROSSからの作品で、今回もメンバーにクリス・ポッターが参加している。
アダム・ロジャースは井上陽介のアルバムに参加して以来、そのプレイに注目してきたけど、リーダーアルバムも既にこれで3枚目。 今回もサイドメンはポッターはじめ名うてのメンバーがラインナップされているが、堂々としたリーダーシップを発揮しており作曲、演奏とも充実した出来映えだ。
アダムのプレイは若手ギタリストのなかでカート・ローゼンウィンクル、ベン・モンダー、スティーブ・カルディナスなんかよりもう少しストレートでオーソドックスなスタイルに私には聴こえる。かといってパット・マルティーノ、ジャック・ウィルキンス、ルイス・スチュアートほどメインストリーマーのテクニシャンでもない。マイク・スターンやジョン・スコフィールドほど、バックボーンにロックテイストを盛り込むわけでもない。
均等な音圧で速いパッセージを弾き通す技術はやはり、マルティーノの影響が最も強いと思うけど、音色的にはジャズ系セッションでのパット・メセニーに最も近い感じもする。
作曲はウネウネ感の強い、「揺らぎ」をイメージさせる曲が多いのだけど、アダム自身の演奏は結構直線的でホリゾンタルなフレーズ中心で、先のローゼンウィンクル達ほど寄り道をしないプレイだと思う。
一見、曲とプレイスタイルがミスマッチを起こしそうだが意外にしっくりフィットしていて、ここがおそらくアダム・ロジャースの売りであり、聴きどころなのではないかと思っている。
メンバーはADAM ROGERS(G)CHRIS POTTER(TS)EDWARD SIMON(P)SCOTT COLLEY(B)CLARENCE PENN(DS)
録音は2004年4月26日 SYSTEM TWO RECORDING STUDIO , BROOKLYN

アルゼンチンからまたまた凄い女性アーチストを発見した。
「ザビエルレコード」から通販で今週届いたCDなのだけど、これが凄いのです。
1968年生まれの彼女は30歳の時に初リーダー作を録音し、この「VERDE」は第3作目。
現在既に6枚発表している。
ピアノとボーカルが主だが、なんと言ってもユニークな作曲に驚かされる。
リズミックで躍動感に溢れ、メランコリックな表情やほのぼのとしたナチュラリティーなども持ち合わせる個性的で魅力的なナンバーの数々。
エルメート・パスコールやギンガと同じ様にとても個性的でワン&オンリーな和声感覚に溢れた楽曲と自身のヴォイスとピアノが高度なレベルで融合していて無限の才能を感じさせるほど素晴らしい。
ジャズ、ロック、タンゴ、クラッシック、ブラジル音楽、その他様々なヨーロッパの音楽の影響も感じさせる汎地球的規模の音楽と言ったら表現がオーバー過ぎるだろうか?
この作品はバリトンサックスやクラリネット、彼女のピアノソロやバンドネオンなどが各所に散りばめられていてジャズファンにも聴きやすい作品になっていると思う。
現代ジャズがある意味失ってしまった生命の鼓動、躍動感がアルバム通してフルボリュームで展開されていることを絶賛したい。
音楽聴いていてこういう素晴らしい才能のアーチストとの出会いほど嬉しい事はないのである。

今年の春、ニューヨークで録音された菊地雅章の新作で、グレッグ・オズビーとのデュオ作品。
プーさん(知り合いでもないのにジャズファンは、親しみをこめて昔からこう呼ぶのが正しいあり方?)のサックスとのDUO作品としては、峰さんとのもの以来だと思う。
菊地雅章の70年代の名作に「イエロー・カルカス・イン・ザ・ブルー」という曲があるが、この曲は東洋人から見た黒人のブルースの精神を菊地なりに解釈した作品だったと記憶している。
このアルバムの2曲目「SEPIA TONES」、この曲は菊地の作品ではなくてGREG OSBYの曲なのだけど、聴いていてとても東洋的、日本的なイメージのする作品で先の「イエロー」を思い出してしまったのだ。
グレッグ・オズビーはおぼろ月夜の浮ぶ小道を歩き進む虚無僧のような雰囲気を漂わせていて、ソプラノサックスの音色も非常にマチュアーで魅力的。
音色で言えば少しキャノンボール・アダレイを連想させるところがあり、倍音成分に富んだ高音域が特に似ていると思う。
この作品、全部がデュオで演奏されているわけではなくて、菊地のソロとオズビーのソロが2曲づつ収録されている。
デュオの部分は、インタープレイ重視の演奏というよりも、事前のミーティングで菊地の意図していることがオズビーに伝えられ、実際のプレイの間菊地のデッサン画のようなピアノによるディレクションのもとにオズビーがオリジナルな解釈を加味して演奏されていったように聴こえる。
あくまでも推測にすぎないのだが・・・
どちらにせよ、丁々発止の手に汗握る技の攻防といった演奏でないのは確かで、
ジョン・ルイスのようにどんどん音数の少なくなる菊地の静謐なピアノプレイと現代黒人アルトの代表的存在のオズビーのコラボレーションは、ピアノトリオで実践している「テザードムーン」の変形ヴァージョンのようにも解釈できるのではないかと思っている。
メンバーは菊地雅章(P)GREG OSBY(AS,SS)
録音は2005年3月24,25日 AVTAR STUDIO , NYC

2ヶ月くらい前、DUから買ったノルウェーのドラム奏者の初リーダーアルバム。
購入の決め手は最近めきめきと頭角を表しているニューカマーALTE NYMOが参加していたから。
バンドサウンド重視のプロデュースがなされていて、ことさら本人のドラムが強調された作品になっていないのは、正解だと思う。
ソロフューチャーが最も多いのはALTE NYMOとギターのJON EBERSONで2人はリーダーの期待通りの働きをこなしているといえる。
ALTEは現代のテナー奏者らしく様々なプレイヤーの影響(ブレッカー、ロバーノや同年代のブルックリン派のテナー奏者)を受けていると思うが、ウォーン・マーシュのピッチのずらし具合やコルトレーンのハーモニクスの使い方をさりげなくプレイに導入していてニヤリとさせられるところがある。
ギターのJON EBERSONもコンテンポラリー系のプレイで清涼感溢れるスタイリッシュなスタイルは様々な音楽にフッットするとても柔軟性に富んだもの。
アルバム途中で入るボーカル曲も自然な流れで、無理がなく好印象。
エレクトロニカ、フューチャージャズ、轟音フリージャズ、トラディショナルジャズ、ハードバップ、勿論ECMも・・・ノルウェーという国は人口に比べ非常にミュージシャンの人材が豊富で、様々なスタイルのジャズが同時進行的に演奏されているイメージを抱いているのだけど、こういうポストバップ、ネオバップスタイルの演奏でも素晴らしいアルバムを発見したという感じだ。
個人的には3曲目「QUIET PIECE」ラスト「EVENING SONG」がお薦め!
EBERSONのギターがメロディーをとる「DEAR OLD STOCKHOLM」も甘く柔らかな肌触りが北欧の空気感をだしていて良い。
メンバーはALTE NYMO(TS)JON EBERSON(G)MARIT SANDVIK(VO)OLE MORTEN VAGAN(B)ROGER JOHANSEN(DS)
録音は2004年12月

言わずと知れた80年代テナートリオの名盤!
私のサイトではあまりこういった評価の決まった作品やアーティストの歴史的作品(つまりこれまで本にたびたび書かれてきたことだとか、語り尽くされた事は意識的に取り上げないようにしている。何故ならその本を読めば充分事足りると思うからです。)は取り上げないというポリシーから外れるのですがたまにはこういう作品を聴き返してみるのも良いかなと思い、セレクトしました。
1989年にCBS/SONYからでた国内盤で買ったのだけど、2枚組仕様になっていて、片面はミニディスクに日本盤だけのボーナストラック「STARDUST」が収められているというもの。(だったと思う?記憶が定かでない。)
今だったらこんなコスト増のこと不況のレコード会社、絶対しないんじゃないかと思う。
このCD,ジャズ録音のお手本になるような仕上り。
三者の楽器の音がほぼパーフェクトと言ってよい状態で収録されているのはもちろん、プレゼンスがものすごく良いのだ。
三人が会話をかわしながらセッションを進め、ハプニングを楽しんでるミュージシャンの目配せや息使いまで見てとれるような録音。
ミルト・ヒントン(1910年生まれ)のベースがこんなに良い音で収録された作品を私はこれ以外に知らない。
まだ、30歳そこそこだったブランフォード(蛇足だけど私とブランフォードは同い年)やジェフ・ワッツが、ジャズ界の長老ミルト・ヒントンと心暖まる交流をした(と言っても手抜き一切なしの真剣勝負)エポックメイキングな一作。
お互いにこのセッションでそれこそ長年の親友のように、音楽面で共感しあい、リスペクトし合えたのじゃないかなと想像する。
最近のブランフォードは、力作を発表し続けているけど、この作品のようなちょっと肩の力を抜いたユーモアの精神も感じさせる作品もたまにはリリースしてもらいたいと願うのはファンの勝手な願いだろうか?
メンバーはBRANFORD MARSALIS(TS)MILT HINTON(B)JEFF WATTS(S)
録音は1988年1月3,4日
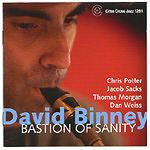
DAVID BINNEYの最新アルバムは今年の春、CRISS CROSSからリリースされた。
DAVID BINNEYの名前は1997年にFREELANCEからでたスコット・コリーのアルバムの中に参加していてちょっと面白い新人サックスが参加しているなぁと思っていたのだけど、こんなに頭角を表す存在になるとはその時思わなかった。
サックスにはCHRIS POTTERが参加していてクインテット編成となっている。
前作やRED,ACT時代の作品よりもレーベルカラーもあるのかストレートな演奏になっていて1曲目ショーターの「LESTER LEFT TOWN」から疾走感のあるダイナミックなアルトを吹いていていつもとちょっと違うなぁという印象を受ける。
サックスの音もこころなし逞しくて大きい感じがするのは気のせいだろうか?
BINNEYからの影響だろうか、クリス・ポッターのテナーも低域がいつもより、男性的なトーンでまるで、デクスター・ゴードンの音色のようだ。
アルバム中7曲はBINNEYの作曲で、オリジナルはいつもの如く少し抽象度高めの観念的なメロディーの曲が多いけど、ストレートなアドリブ主体の仕上がりで聴き応えがある。
現代のサックス業界を代表する二人のサックスバトルを純粋に楽しめば良いアルバムだと思う。
メンバーはDAVID BINNEY(AS)CHRIS POTTER(TS)JACOB SACKS(P)THOMAS MORGAN(B)DAN WEISS(DS)
録音は2004年4月28日 BROOKLYN , NYC

名前を全然知らなかったアーティストの作品だったが、バックのメンバーの名前で買ったCD。DANIEL HUMAIR,RECARDO DEL FRA,PETER GRITZが参加してるのだもの、買っても悪くないだろうというところ・・・
家に帰って、ネットで検索してみたら、「オラシオさん」が自身のブログで既にこの作品のことを書かれていた。
俄然、期待感が高まる。
聴いてみた。
やっぱり、・・・勘は当たっていた。
休日に散歩していてふと、道端に咲いている見たことの無い可愛らしい野花を発見したような気分だ。
傷つけないようにそっと摘み取って、家に持ち帰りお気に入りのフラワーベースにアレンジする。折に触れて見やり、写真に撮ったりして一人楽しむ。
このCD、まさにこんな感じで、出来たら誰にも教えず一人、楽しみたい作品。
ひっそり隠匿して、独り占めしてその素晴らしさを楽しみたい作品だ。
作曲が素晴らしい。1曲、1曲ごとの解説はここでは省略するけど、生き生きとした躍動感、色彩感、叙情性、ペーソス、生きる喜び、悲しみ、・・・MARIO STANTCHEVという生身の人間が自身を等身大で最大限に表現しきった音楽が一枚のCDに記録されていると思うのだ。
リズム隊が申し分ないのは言うまでもなく、ソロがフューチャーされるJEAN-LOUIS ALMOSNINOやLAURENT BLUMENTHALらサイドメンも好演。
MARIO STANCHEVのピアノは、歯切れの良い硬質なタッチが特徴だが、リリシズム溢れる表現やジャージーでスインギ―な感覚も持ち合わせる柔軟でオールラウンドな表現もバッチリできる万能型。
全曲素晴らしいけど、個人的には1曲目「TINKO」6曲目「DO-DO」7曲目「LITTLE GIPSY」が最も気に入っている。
オラシオさんも言ってたかも知れないけど、12曲目「ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET」は必要なかったかもしれない。
メンバーはMARIO STANTCHEV(P)LAURENT BLUMENTHAL(AS,SS)HERVE GOURDIKIAN(TS)JEAN-LOUIS ALMOSNINO)G)RICCARDO DEL FRA(B)PETER GRITZ(DS)DANIEL HUMAIR(DS)SILVIA STANCHEV(CELLO)
録音は1990年2月 PARIS

最近亡くなってしまったGEORGES ARVANITASの1987年録音で、CDは1枚だがLPでは2枚組で発売された。
アルバニタというと、やはり「3AM」や「IN CONCERT」が思い出深い。
80年初頭に「3AM」が再発された時は感激した。
学生時代、なかなかこのレコード聴けるジャズ喫茶がなく、確か今はなき大阪太融寺の名店「JOJO」で初めて聴いたと思う。「IN CONCERT」は「JOKE」でよく聴いた記憶がある。「3AM」はその後、澤野工房でより素晴らしい復刻盤が出たので入手された方も多いと思う。
ジャズを感じさせる素晴らしいジャケットで、「VENTO AZUL JAZZ ROOM」の壁にもちろんディスプレイしております。
80年も後半にさしかかってCARREREから2枚組のピアノトリオ「ROUND ABOUT MIDNIGHT」が発売された。その頃デクスター・ゴードン主演「ラウンド・ミッドナイト」が公開された矢先のこと。
このテナーカルテット盤も選曲の雰囲気が少し似通っているのは気のせいだろうか?そう思って聴いているとMICHEL GOLDBERGのサックスがデクスターぽく聴こえてくるものだから不思議だ。
この作品、日常的に行われているセッションの断片が切り取られたような仕上がりで決して名盤ではないけれども、普段着のアルバニタが聴ける好セッションで結構CDトレイに入れ込んで聴いている。
メンバーはGEORGE ARVANITAS(P)JACKY SAMSON(B)CHARLES SAUDRAIS(DS)
MICHEL GOLDBERG(TS,SS)
録音は1987年3月25~28日

EGEAのCDが昨日まとめて5枚届いた。
オーソドックスなJAZZとは、結構離れている音楽がこのレーベルでは、展開されているのだけどどの作品も個性豊かなオリジナルなサウンドが詰まっていて聴き応えがあり、注目している。まず最初は最もジャズっぽいと思われる作品を聴いてみようと思う。
メンバーの中で、GIL GOLDSTEINは別にしてESSIET ESSIET(蛇足だけどエド・マクベインの87分署シリーズにマイヤー・マイヤーという刑事をいつも思い出す。)や
JOE CHAMBERSの名前がこのレーベルからは異色で新鮮な響き。
アルバムタイトル通りイタリアの美曲がまとめられたものだけど、ジャズ度が高くアロド・ロマーノやステファーノ・ボラーニにも同種の企画作品があったと思うがそれに勝るとも劣らない作品。
ギル・ゴールドスタインがアコーディオン、ピアノ両方でリリシズム溢れたとても良い仕事をしている。
PIETRO TONOROの少しハスキーな成分を含むテナーやガルバレグの様なマチュアーで丸みを帯びたソプラノの音色とGIL GOLDSTEINのアコーディオンが絡み合い甘く豊穣な響きが音楽に生命を吹き込む。
晴れ渡った空、石畳、教会の鐘、裏通りのバール、夕暮れ時の港町、高い天井の駅舎、雨に濡れた落ち葉、丘陵地帯に咲き乱れる花々・・・走馬灯のように映像が浮んでくる。
5曲目モリコーネの「METTI UNA SERA A CENA」ではジョー・チェンバースのバイブラフォンがフューチャーされ、いつもの如く清涼感溢れた氷菓子のような響きはこのアルバムでも良いアクセントになっていると思う。
全体に甘口の仕上りだけど、べたついた甘さはなく上品でかといって気取っているわけでもない、あたかも下町で思わぬ美味い料理を出すレストランを見つけたような気分だ。
休みの日にゆったりとした気分で聴いてもらいたいアルバムだ。
メンバーはPIETRO TNOLO(TS,SS)GIL GOLDSTEIN(P,ACCODION)ESSIET ESSIET(B)
JOE CHAMBERS(DS,VIB)
録音は2004年5月23,24日

今や我が国でも人気ミュージシャンの二人が1993年に吹き込んだDUO作品。
作曲はPIERANUNZIが5曲、RAVAが4曲、二人の共作が1曲とほぼイーブンに分け合っている。
陽だまりの中の古城を散策したり、流れ行く雲を眺めやるような穏やかで緩やかな時間が流れていくいかにもヨーロッパ然とした楽曲が1曲目から3曲目まで続くのだけど巨匠二人のこと、それだけには終わらない。
エンリコはピアニスティックな切れ技を時折披露するし、ラヴァはパッショネートな吹奏で素早く反応を見せる。
「詩情豊かな」という言葉だけでは言い表せない自由なジャズの精神がその音楽の行間から嫌が上でも漂ってくるのだ。
昔、ナベサダが「飯食ってる時もジャズなんだよねぇ。」と言った有名な言葉があるけど、まさにこの二人もそう。
どんな種類の音楽を演奏しても、隠し通せないジャズミュージシャンとしての血が音となって表出されていると思う。
そんな二人の会話にひたすら聞き惚れる一作だと思う。
メンバーはENRICO RAVA(TP)ENRICO PIERANUNZI(P)
録音は1993年3月29,30日
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- やっぱりジャニーズ
- 楽天ブックス予約開始!ドラマ「マウ…
- (2024-09-16 22:53:26)
-
-
-

- 気になる売れ筋CD・DVD
- ラルクアンシエル L'Arc〜en〜Ciel…
- (2024-11-29 10:26:37)
-
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪中西アルノ『のぎおび◢』S…
- (2024-11-30 05:43:51)
-
© Rakuten Group, Inc.