2-66 掴むべきもの
気付くと、朝子は自宅の玄関に帰り着いていた。心ここにあらずの状態で歩いてきた彼女は、もう自分がどうやってあのホテルから帰ってきたのかも覚えていなかった。
一人になったと悟った途端、朝子は玄関に倒れた。フローリングの床が頬に当たり、冷たいはずなのに何も感じられない。
有芯は行ってしまった。
私と離れ、私を忘れ、歩くことを選んだ。
当然ね。いつまでもこんな優柔不断な人妻を好きでなんていてくれるわけがない・・・!
ミシミシって音が聞こえる。・・・心が割れる音がする。血も流れない。乾いた心。
有芯と抱き合ったとき・・・余計なことは何も考えられなかった。
ただ、彼が欲しかった。愛しかった。それだけ。
私は思い知らされたんだ。自分の持論が間違っていたことを。
子供のためならなんだって犠牲にできると思ってた。でもそれは違った。有芯に初めて身体を許した時も、昨夜抱かれた時だって、いちひとのことなんて思い出しもしなかった。
やっぱりどうしたって私は有芯を愛してる。いちひとはもちろん大切だけど、それでも私は、彼を忘れるなんてできない。
ごめん、いちひと。あなたのパパは大好きよ。でも、有芯を想う気持ちとその感情は、明らかに違う―――。
朝子は何をすればいいのかもわからないまま起き上がり、リビングに入った。ふと鏡が目に入ったので見ると、我ながらひどい顔だと思い、朝子は笑った。しかしうまく笑うことができず、すでに頬にくっきりとついている涙の跡の上をまた涙が流れた。
“俺を捨てて選んだ家族だろ。もっと自分を大事にしろよ”
『家族』? 家族・・・・・。
朝子は有芯の言葉に誘導されるように、携帯を手に取った。篤といちひとが家族なら―――お腹の子だって、家族だもの。これからみんなで、家族になるんだもの・・・。
有芯のように愛せなくても、篤が子供達の―――お腹の子の父親になってくれるなら・・・。
鼓動が高まり苦しくなる胸を押さえながら、朝子は篤に電話をかけた。
「・・・もしもし!?」篤は不機嫌そうだ。
彼はただでさえ仕事中に電話されることを嫌う。そのうえ今は出張中で、慣れない職場で奔走しているのだ、イライラしないわけがない。
朝子は篤の態度に怯み、しばらく言葉に詰まってしまった。篤が怒ったように聞いてくる。
「もしもし?! ママ?! 何なの?」
「あのね、友達のお母さんなんだけど・・・。旦那さんとは違う男性の子供を妊娠したらしいの」
言いながら朝子は情けなさのあまり死にたくなった。私・・・何やってるんだろう?!
篤は面倒くさそうに言った。「は? それって遠藤さん? 向かいの」
篤はイラつくとすぐに向かいの遠藤さんの話を持ち出す。朝子は内心うんざりしながら答えた。
「違うわよ。・・・あなたの知らない人。中学の同級生なの」
朝子の言葉に、篤はイライラした口調で答えた。「じゃあ別に俺には関係ないじゃない」
「あなたはそうかもしれないけど、私はそうもいかないの。ねぇ、あなたが旦那さんだったら、どうすると思う?」
篤は相変わらずイライラした口調で、当然のように「俺なら腹の子を始末するな」と即答し、「ねぇ、用はそれだけ? 俺今本当に忙しいんだ。話なら帰ってから聞くから。切るよ!」
そして、電話は切れた。
動かない朝子を取り巻く空間で、しばらく時間が止まったかのようだった。
ただ携帯のツーツーという音と、時計が時を刻むチッチッという音だけが、彼女のいる部屋で時が進行していることを告げていた。
「嘘よ・・・・・」
朝子は床に崩れるように座った。携帯が手から滑り落ちたが、次にその手に掴むべきものが朝子には思いつかなかった。
「あなたが帰ってから話なんて・・・・・聞いてくれたこと、ないじゃない・・・・・」
呟きながら、朝子ははっきりと悟った。
みんなごめん。やっぱりもう・・・ここにはいられない。
67へ
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ミキハウスにはまりました
- ミキハウス好き限定!P5倍😀公式ショッ…
- (2025-11-26 15:40:05)
-
-
-

- 0歳児のママ集まれ~
- 20%Pバック😀【1種類を選べる】メリ…
- (2025-11-25 19:30:04)
-
-
-
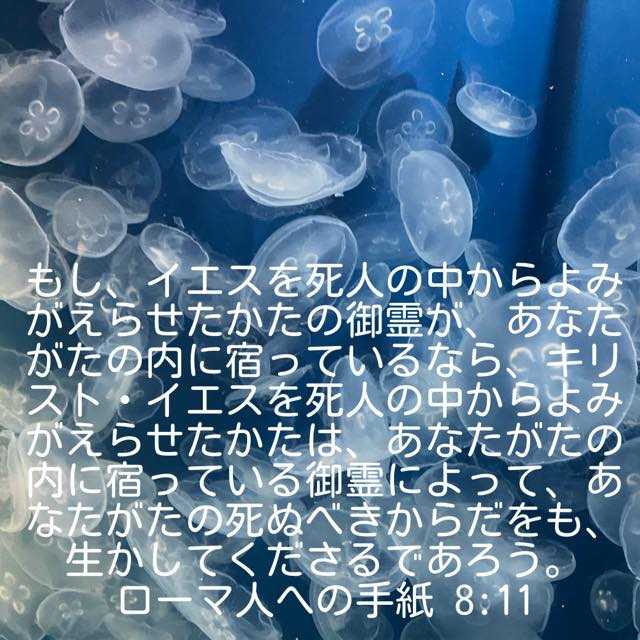
- 共に成長する家族!子供と親の成長日…
- 我が家の「沈黙の戦隊」
- (2025-10-24 09:33:10)
-
© Rakuten Group, Inc.



