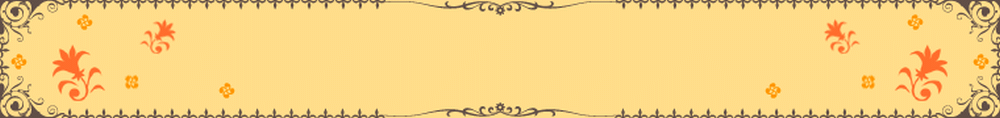PR
X
Calendar
Freepage List
人名索引(旧監督リスト)

監督/外国名/ア~コ

監督/外国名/サ~ト

監督/外国名/ナ~モ

監督/外国名/ヤ~ン

監督/日本字/あ~こ

監督/日本字/さ~の

監督/日本字/は~ん

スタッフ/外国名/ア~コ

スタッフ/外国名/サ~ト

スタッフ/外国名/ナ~モ

スタッフ/外国名/ヤ~ン

スタッフ/日本字/あ~こ

スタッフ/日本字/さ~の

スタッフ/日本字/は~ん

出演/外国名/ア~コ

出演/外国名/サ~ト

出演/外国名/ナ~モ

出演/外国名/ヤ~ン

出演/日本字/あ~こ

出演/日本字/さ~の

出演/日本字/は~ん

テスト(工事中)
映画雑文リスト
作品名(ア行、カ行)

(サ行~ナ行)

(ハ行~英数字)
Comments
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 映画レビュー(888)
カテゴリ: フランス映画
『ゴダールのマリア』の本編
Jean-Luc Godard
80min
(所有VHS)

日本では『ゴダールのマリア』というタイトルでまとめられている映画は2編からなる構成で、最初がアンヌ=マリー・ミエヴィル監督の27分の短編『マリアの本』、それと切れ目なく連続して後に続く80分のジャン=リュック・ゴダールの『こんにちは、マリア』。第一部ミエヴィルの27分の短編『マリアの本』については 1月31日の日記 を参照して下さい。

ゴダールの作品は、いま作品一覧を見て数えたら少なくとも25本は見てます。好きな映画監督か?、ときかれたら決して「ハイ」とは言えないかも知れないけれど、やはりこの人は一つの文化現象であり、20世紀後半の映画史や文化史を考えるときこの人を無視することは出来ませんね。比べればトリュフォーなんかはそれほど重要ではないと思います。ゴダールの作品でボクが好きなのは『はなればなれに』、『男性・女性』、この『ゴダールのマリア』、それとオムニバス映画『愛すべき女・女たち』の中の一編『未来展望、あるいは二〇〇一年愛の交換』です。場面場面で好きなシーンは多いのですが、1本まるごととなるとこんなところです。

正直に白状するとゴダールは苦手だったのですが、『カルメンという名の女』を見てからこの人の映画の見方がわかり(あくまで自己流の、ですが)、それまで駄目だった作品も楽しく(?)見られるようになりました。それは映画にそのまま身を任せて、その場でも、見た直後も、あまり無理に考えようとしないことです。もちろんごく普通の映画だって文学や芝居とは違うけれど、言語的論理に還元できるならば映画である必要はないんですね。言語的論理による分析等は、映画そのものとはまた別なものなわけです。映画を作っているゴダールにとってはなるほど周到な表現的計算があります。この映画では月、太陽、バスケットのボール、照明機具、その他 丸い

映画は聖書のマリアの処女懐胎とイエス出産の物語を現代に置き換えたものだ。同様の映画としてはポランスキーの『ローズマリーの赤ちゃん』が思い起こされる。マリー、つまりマリアは父親の経営するガソリンスタンドを手伝うバスケットボールの選手。ジョゼフ、つまりマリアの婚約者ヨゼフはタクシーの運転手。ある夜空港に着いた天使ガブリエルはマリーを訪れ、彼女が妊娠することを告げ、彼女は聖霊により懐胎する。聖書の世界ではなく現代の物語だから、当然にジョゼフは自分とは肉体関係を持とうとしなかったマリーが誰か別の男と寝たのであろうと疑う。マリーももちろん身におぼえのないことで、医師に診察してもらうとやはりマリーは処女で、やはり妊娠していた。彼女は自分に課されたこの事実を受け入れるのに苦悶する。やがてジョゼフはジュリエットの求愛をはねつけてマリアを受け入れ、マリアは冬のある夜男児を出産。少年に成長した子供はある日両親を残して野原の方へ去っていき、マリーはジョゼフに「復活祭か三位一体の祝日には戻ってくるわよ」と言う。最後の方でガブリエルに呼び止められて「Je vous salue, Marie.」(こんにちは、マリア)と言われ、これが映画のタイトルなわけだけれど、これは普通に言えば「アヴェ・マリア」だ。これはマリーがすべての女性の唯一的象徴であるということでもある。

この映画はもちろんいわゆる宗教映画ではない。では何故にマリアの処女懐胎がテーマか。それはゴダールという男性の眼で見た女性性、あるいは妊娠、あるいは愛を考察するのに、性愛と妊娠を一度分離する必要があったのだと思う。宗教性を除いてもマリアの処女懐胎の物語は現代でも意味を持ちうるということだ。一つには愛と性的欲望の関係があり(この点に関してはミリエム・ルーセルのヌードや局部を段階的に見せるという形でゴダールは男性観客の興味を操る巧さを使っている)、もう一つは愛の、あるいは性の行為を取り払った形での「妊娠」そのものの意味がある。映画の構成はおおよそ広い空間から狭い室内へという流れを持っているのだけれど、これは通常的・社会的思い込み・解釈から、女性(マリー)の内面へという流れにも対応している。愛の行為から分離した形でマリーが妊娠し、自分の女性性を消化して受け入れていく過程でもある。眠っているマリーのお腹が寝息に合わせて上下するシーンが2回あるが、ふくれてはしぼむお腹は妊娠・出産を象徴しているかのようであり、生命の誕生と死の永久なる繰り返しである。そして最後の方でマリーは「神は con なのだ」と認識する。con とはもともと女陰のことであり、転じてバカ者、愚か者の意味をも持つ語だ。この映画に対してカトリック教会や保守的信者層を怒らせたのはとりわけこのセリフだろう。ジョゼフに代表される男の存在はいわば神の影であり、妊娠・出産(種の保存)という意味での母性はこの con によりセックスと統合される。マリーがジョゼフに教える「愛してる」という言葉の使い方は、ジョゼフの手が伸ばされてマリーのお腹に触れるのではなく、反対にお腹から手が引き離されるとき、正当な意味を持つ。

ゴダールはマリーを診察する医師に「女性は謎で解らない」というようなセリフを言わせているが、これは結局のところゴダールの正直なる告白であり、この映画は男性ゴダールの眼から見た女性、男性の立場で考察された妊娠を描いていたものだ。しかし映画とは多重性を持つものであり、ゴダールが象徴や記号としてマリーの役を使い、それに沿って女優は演技しているわけだけれど、演じている女性であるミリエム・ルーセルの彼女の心理によるマリーの理解、あるいは女性の理解、さらに本音や生理が絡んでいるわけであり、そういう意味でのミリエム・ルーセルがとても美しく、そしてそれは実はゴダールの意図にもあることで、そんなミリエムを見るだけでも魅力的な映画だ。

監督別作品リストはここから
アイウエオ順作品リストはここから
映画に関する雑文リストはここから
Jean-Luc Godard
80min
(所有VHS)

日本では『ゴダールのマリア』というタイトルでまとめられている映画は2編からなる構成で、最初がアンヌ=マリー・ミエヴィル監督の27分の短編『マリアの本』、それと切れ目なく連続して後に続く80分のジャン=リュック・ゴダールの『こんにちは、マリア』。第一部ミエヴィルの27分の短編『マリアの本』については 1月31日の日記 を参照して下さい。

ゴダールの作品は、いま作品一覧を見て数えたら少なくとも25本は見てます。好きな映画監督か?、ときかれたら決して「ハイ」とは言えないかも知れないけれど、やはりこの人は一つの文化現象であり、20世紀後半の映画史や文化史を考えるときこの人を無視することは出来ませんね。比べればトリュフォーなんかはそれほど重要ではないと思います。ゴダールの作品でボクが好きなのは『はなればなれに』、『男性・女性』、この『ゴダールのマリア』、それとオムニバス映画『愛すべき女・女たち』の中の一編『未来展望、あるいは二〇〇一年愛の交換』です。場面場面で好きなシーンは多いのですが、1本まるごととなるとこんなところです。

正直に白状するとゴダールは苦手だったのですが、『カルメンという名の女』を見てからこの人の映画の見方がわかり(あくまで自己流の、ですが)、それまで駄目だった作品も楽しく(?)見られるようになりました。それは映画にそのまま身を任せて、その場でも、見た直後も、あまり無理に考えようとしないことです。もちろんごく普通の映画だって文学や芝居とは違うけれど、言語的論理に還元できるならば映画である必要はないんですね。言語的論理による分析等は、映画そのものとはまた別なものなわけです。映画を作っているゴダールにとってはなるほど周到な表現的計算があります。この映画では月、太陽、バスケットのボール、照明機具、その他 丸い

映画は聖書のマリアの処女懐胎とイエス出産の物語を現代に置き換えたものだ。同様の映画としてはポランスキーの『ローズマリーの赤ちゃん』が思い起こされる。マリー、つまりマリアは父親の経営するガソリンスタンドを手伝うバスケットボールの選手。ジョゼフ、つまりマリアの婚約者ヨゼフはタクシーの運転手。ある夜空港に着いた天使ガブリエルはマリーを訪れ、彼女が妊娠することを告げ、彼女は聖霊により懐胎する。聖書の世界ではなく現代の物語だから、当然にジョゼフは自分とは肉体関係を持とうとしなかったマリーが誰か別の男と寝たのであろうと疑う。マリーももちろん身におぼえのないことで、医師に診察してもらうとやはりマリーは処女で、やはり妊娠していた。彼女は自分に課されたこの事実を受け入れるのに苦悶する。やがてジョゼフはジュリエットの求愛をはねつけてマリアを受け入れ、マリアは冬のある夜男児を出産。少年に成長した子供はある日両親を残して野原の方へ去っていき、マリーはジョゼフに「復活祭か三位一体の祝日には戻ってくるわよ」と言う。最後の方でガブリエルに呼び止められて「Je vous salue, Marie.」(こんにちは、マリア)と言われ、これが映画のタイトルなわけだけれど、これは普通に言えば「アヴェ・マリア」だ。これはマリーがすべての女性の唯一的象徴であるということでもある。

この映画はもちろんいわゆる宗教映画ではない。では何故にマリアの処女懐胎がテーマか。それはゴダールという男性の眼で見た女性性、あるいは妊娠、あるいは愛を考察するのに、性愛と妊娠を一度分離する必要があったのだと思う。宗教性を除いてもマリアの処女懐胎の物語は現代でも意味を持ちうるということだ。一つには愛と性的欲望の関係があり(この点に関してはミリエム・ルーセルのヌードや局部を段階的に見せるという形でゴダールは男性観客の興味を操る巧さを使っている)、もう一つは愛の、あるいは性の行為を取り払った形での「妊娠」そのものの意味がある。映画の構成はおおよそ広い空間から狭い室内へという流れを持っているのだけれど、これは通常的・社会的思い込み・解釈から、女性(マリー)の内面へという流れにも対応している。愛の行為から分離した形でマリーが妊娠し、自分の女性性を消化して受け入れていく過程でもある。眠っているマリーのお腹が寝息に合わせて上下するシーンが2回あるが、ふくれてはしぼむお腹は妊娠・出産を象徴しているかのようであり、生命の誕生と死の永久なる繰り返しである。そして最後の方でマリーは「神は con なのだ」と認識する。con とはもともと女陰のことであり、転じてバカ者、愚か者の意味をも持つ語だ。この映画に対してカトリック教会や保守的信者層を怒らせたのはとりわけこのセリフだろう。ジョゼフに代表される男の存在はいわば神の影であり、妊娠・出産(種の保存)という意味での母性はこの con によりセックスと統合される。マリーがジョゼフに教える「愛してる」という言葉の使い方は、ジョゼフの手が伸ばされてマリーのお腹に触れるのではなく、反対にお腹から手が引き離されるとき、正当な意味を持つ。

ゴダールはマリーを診察する医師に「女性は謎で解らない」というようなセリフを言わせているが、これは結局のところゴダールの正直なる告白であり、この映画は男性ゴダールの眼から見た女性、男性の立場で考察された妊娠を描いていたものだ。しかし映画とは多重性を持つものであり、ゴダールが象徴や記号としてマリーの役を使い、それに沿って女優は演技しているわけだけれど、演じている女性であるミリエム・ルーセルの彼女の心理によるマリーの理解、あるいは女性の理解、さらに本音や生理が絡んでいるわけであり、そういう意味でのミリエム・ルーセルがとても美しく、そしてそれは実はゴダールの意図にもあることで、そんなミリエムを見るだけでも魅力的な映画だ。

監督別作品リストはここから
アイウエオ順作品リストはここから
映画に関する雑文リストはここから
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[フランス映画] カテゴリの最新記事
-
『ランジェ公爵夫人』ジャック・リヴェッ… 2008.10.16
-
『白い馬』『赤い風船』アルベール・ラモ… 2008.09.21 コメント(4)
-
『レディ・チャタレー』パスカル・フェラ… 2008.09.11 コメント(6)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.