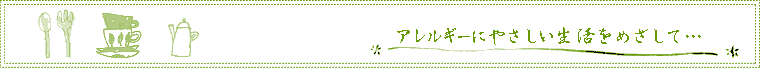カテゴリ: 食物アレルギー情報
今日は雨が降ったためか、とても涼しいです。
とはいえ、残暑が厳しく、蒸し暑かったりなど、気温の変化も激しく、身体の方も体調を整えるために必死なのかなと思います(体がだるい~)。さらに、先週末の大型台風上陸・通過、9月23日(秋分の日)前後の目に見えない季節の大きな変わり目のダブルの影響で、食生活や環境を大きく変えたり、新しいものを経口負荷していなくても、症状が出やすい状況になっている場合が増えているように思います。
台風に関しては、通過した土地以外に住んでる場合も影響があるし、台風と同じように、大雪・大寒波なども同様です。また、秋分の日前後2週間くらいは症状がでやすく、天候や気候に過敏な体質の場合は前後3~4週間くらいの注意する必要があるそうです。
1~2週間前から症状が出やすくなったり、昨年までの生活記録をチェックして、9月に体調を崩してることが多かったら注意をしておいた方が良いと思います。蕁麻疹、皮膚症状の悪化、喘息など呼吸器系症状の悪化、風邪がなかなか治らないなど… 日頃食べても大丈夫なアレルゲン(母乳経由も含む)などでも、体調が少し悪かったら、強い症状が出る可能性が高いので、普段以上に体調管理に注意をし、長距離移動や長時間の激しい外遊び後など、とても疲れたり、ストレスを感じている場合と思われる場合にはしっかりと休養をとらせて、食材の与える量や質、頻度なども注意した方がいいかもしれません。子どもが最近嫌がるようになった食材がある場合などは無理して与えないことなども重要かもしれません。自分で食事を選んでいる可能性も高いので…
上記は母乳育児の方にも影響があるようです。先週頃からしこりができたり、乳腺炎を起こす回数が増えたり、おっぱいの調子がなんとなく悪いなと思われる方は、普段以上の食生活に注意をし(油もの、もち系のもののなどの摂取を控えるなど)、子どもと一緒に昼寝をするなど休養をしっかりとることも必要だと思います。また、頻回授乳をしている場合は、長時間の授乳間隔をあけずに、最低でも2~3時間以内に飲んでもらうことが、乳腺炎予防のための重要ポイントになると思います。
天気予報に注意をしたり、調子が悪くなるシーズンを覚えておけば、発症予防に役立つと思います。上記を下記にまとめておきます。
1.天気が大きく崩れる場合
2.台風がくる場合
3.大雪・寒波がくる場合(特に大寒波は注意!)
◇気候の大きな変わり目に症状が出やすくなる
1.春分(3月下旬)前後約2~3週間
2.秋分頃(9月下旬)前後約2~3週間
2年前の 平成15年度厚生労働省アレルギー疾患予防・治療研究推進事業 リウマチ・アレルギー疾患シンポジウム の動画を見つけました。食物アレルギー治療で著名な先生達が食物アレルギーの実態やメカニズム、アナフィラキシーへの対策、最近増加している口腔アレルギー症候群などについて説明してくれているので、とても参考になると思います。パネルディスカッションでは、Q&Aもあります。日頃の疑問が解決されるヒントが得られるかもしれません。数名の先生がいますが、1人約30分なので、子どもが寝静まったあとになるかも… 私も少しずつ見ている状況です。
◇ 動画配信
とはいえ、残暑が厳しく、蒸し暑かったりなど、気温の変化も激しく、身体の方も体調を整えるために必死なのかなと思います(体がだるい~)。さらに、先週末の大型台風上陸・通過、9月23日(秋分の日)前後の目に見えない季節の大きな変わり目のダブルの影響で、食生活や環境を大きく変えたり、新しいものを経口負荷していなくても、症状が出やすい状況になっている場合が増えているように思います。
台風に関しては、通過した土地以外に住んでる場合も影響があるし、台風と同じように、大雪・大寒波なども同様です。また、秋分の日前後2週間くらいは症状がでやすく、天候や気候に過敏な体質の場合は前後3~4週間くらいの注意する必要があるそうです。
1~2週間前から症状が出やすくなったり、昨年までの生活記録をチェックして、9月に体調を崩してることが多かったら注意をしておいた方が良いと思います。蕁麻疹、皮膚症状の悪化、喘息など呼吸器系症状の悪化、風邪がなかなか治らないなど… 日頃食べても大丈夫なアレルゲン(母乳経由も含む)などでも、体調が少し悪かったら、強い症状が出る可能性が高いので、普段以上に体調管理に注意をし、長距離移動や長時間の激しい外遊び後など、とても疲れたり、ストレスを感じている場合と思われる場合にはしっかりと休養をとらせて、食材の与える量や質、頻度なども注意した方がいいかもしれません。子どもが最近嫌がるようになった食材がある場合などは無理して与えないことなども重要かもしれません。自分で食事を選んでいる可能性も高いので…
上記は母乳育児の方にも影響があるようです。先週頃からしこりができたり、乳腺炎を起こす回数が増えたり、おっぱいの調子がなんとなく悪いなと思われる方は、普段以上の食生活に注意をし(油もの、もち系のもののなどの摂取を控えるなど)、子どもと一緒に昼寝をするなど休養をしっかりとることも必要だと思います。また、頻回授乳をしている場合は、長時間の授乳間隔をあけずに、最低でも2~3時間以内に飲んでもらうことが、乳腺炎予防のための重要ポイントになると思います。
天気予報に注意をしたり、調子が悪くなるシーズンを覚えておけば、発症予防に役立つと思います。上記を下記にまとめておきます。
1.天気が大きく崩れる場合
2.台風がくる場合
3.大雪・寒波がくる場合(特に大寒波は注意!)
◇気候の大きな変わり目に症状が出やすくなる
1.春分(3月下旬)前後約2~3週間
2.秋分頃(9月下旬)前後約2~3週間
2年前の 平成15年度厚生労働省アレルギー疾患予防・治療研究推進事業 リウマチ・アレルギー疾患シンポジウム の動画を見つけました。食物アレルギー治療で著名な先生達が食物アレルギーの実態やメカニズム、アナフィラキシーへの対策、最近増加している口腔アレルギー症候群などについて説明してくれているので、とても参考になると思います。パネルディスカッションでは、Q&Aもあります。日頃の疑問が解決されるヒントが得られるかもしれません。数名の先生がいますが、1人約30分なので、子どもが寝静まったあとになるかも… 私も少しずつ見ている状況です。
◇ 動画配信
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食物アレルギー情報] カテゴリの最新記事
-
食物アレルギーで役立つ資料の紹介 December 12, 2017
-
「食物アレルギーによるひやりはっと事例… August 13, 2015
-
エピペン勉強会&学校給食での食物アレル… August 7, 2013 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
こねこ & ゆうゆの…
こねこ46さん
++エコ☆ベビー++アレ… ふわりふわさん
虎虎馬馬♪(ふぅふぅ… urikonさん
けやき並木の散歩道 *しまのり*さん
I'm home. polka☆さん
++エコ☆ベビー++アレ… ふわりふわさん
虎虎馬馬♪(ふぅふぅ… urikonさん
けやき並木の散歩道 *しまのり*さん
I'm home. polka☆さん
Category
カテゴリ未分類
(2)食の安心・安全
(2)食育関連
(2)食物アレルギー情報
(53)アレルギー・アトピー
(43)小児ぜん息
(5)アレルギーっ子の入園・入学
(14)震災、非常時・防災関連
(10)アレルギー対応レシピ
(20)アレルギーっ子の行事関連
(8)アレルギー・アトピー関連本
(14)アレルギー・アトピーっ子の絵本
(9)アレルギー対応レシピ本
(6)アレルギーに配慮した商品
(34)スキンケア・環境整備グッズ
(7)赤ちゃん
(4)母乳育児
(2)キッチン・調理用品
(2)食品一般
(2)その他
(8)ママイキ関連
(8)講座告知
(0)講演会のお知らせ
(0)我が家の食生活
(5)Comments
© Rakuten Group, Inc.