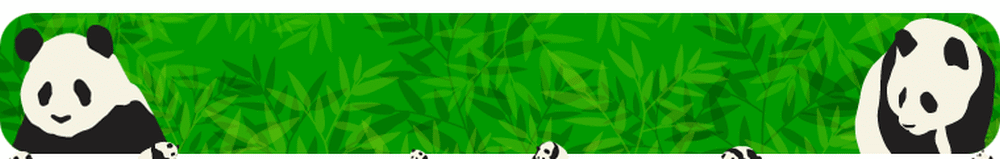オリジナルBL小説「落日」(第5部)
オリジナルBL小説「落日」(第5部)
季節が夏へと移り変わる頃にはもう僕は身体を売る事に
すっかり慣れてしまっていた。毎週金曜日に常磐先輩の
家に行って3Pして5千円貰う生活が1ヶ月も続くと、僕は
学校中で有名になった。もちろん陰口を言う奴はいたけど、
みんな常磐先輩が恐いのか誰も僕をいじめなかった。
常磐組は地域に根強く残っている地元ヤクザで祭りや賭博を
昔から仕切っていた上に関東を制圧した青龍会に属して
いたから、僕が住んでいる地域だけでなく県全体に顔が利く
中堅クラスの暴力団だった。おまけに都心と違って田舎は
勢力争いがないから、組長自ら風俗店を経営して、荒稼ぎ
している風俗王でもあった。ソープ、デリヘル、キャバクラ、
ラブホテルなどを県内にいくつも持っていて、暴力団幹部に
それぞれの店を任せていた。そして、大人になったら、
常磐先輩はそれらを全て継ぐことになり、加藤君も風俗店を
経営する社長になるのだった。とんでもない資産家の御曹司
二人に気に入られ、ペットとして抱かれている僕は当然の如く
恐い先輩達からも可愛がられた。酒を飲まされ、キャバ嬢の
ようにちやほやされて、僕は気分が良かった。相手が下手糞で
Hがよくない時は金田先輩が手伝ってくれた。僕は金田先輩に
触られると、どんな相手でも気持ち良くなれたから、売春が
楽しくなった。金田先輩は2年生と3年生に金曜日のパー券を
売りまくって、酒やおつまみの買い出しをして、僕に5千円
渡して、常磐先輩に千円渡して、残りの売り上げを貰っていた。
パーティーの準備と後片付けも金田先輩が一人でやる約束で
約2千円の斡旋料を貰っていたのだった。金田先輩の家は
大手チェーン店に負けている自営業の焼肉屋で、美味くも
不味くもない肉を高い値段で売っているのに潰れないのは
常磐組の人が食べに来るからだと加藤君が言っていた。
学区内にある焼肉屋は2軒で、一般人は安くて美味しい
大手チェーン店に焼肉を食べに行く。僕も金田先輩の家には
一度も食べに行ったことがなかった。金田先輩は伊藤君ほど
ではないけど、僕よりも貧乏だった。だから、必死になって
僕を励まし、僕に客をとらせ続けた。ブサイクとデブは嫌だ
と言う僕に金田先輩は、目を瞑っていたら相手の顔なんて
分からないから目を瞑ってろとか色々なアドバイスをすると
同時に、童貞じゃ可哀相だからとか女にフラれたばかりで
可哀相だからとか相手に同情するような事を言って、どんな
相手とでも寝るように僕を仕込んだ。そのおかげで、僕は
次第に相手が誰でも平気で足を開くようになっていった。
「麻里緒、スゲェぞ。2週間先まで予約がいっぱいだ。
麻里緒が人気者で俺は嬉しいよ。夏休みはどうする?
夏休みも毎週金曜日大丈夫か?」
と、学校の帰りに金田先輩が聞いてきた。
「はい。大丈夫です。」
僕はにっこり笑って返事をした。でも、僕は身体を売るのは
あんまり好きじゃなかった。本当の事を言えば、夏休みは
誰にも会わずにゆっくり過ごしたかった。
「じゃ、よろしくな。」
金田先輩が笑顔で去って行くと、加藤君がこう言った。
「夏休みは俺と遊ぶ約束だろ?それに期末テストの結果も
悪かっただろ?勉強しなくて、いいのかよ?」
期末テストは43番だった。僕の成績はガタ落ちで、テストの
答案用紙も親に見せられずに机の引き出しに隠してある
状態だった。勉強しようにもHのし過ぎで体がだるくて、毎日
宿題をやるのが精一杯だった。期末テストの前も加藤君は
一緒に勉強しようって僕を家に誘って、僕を押し倒し、
Hした後で、僕に勉強を教えてもらって、自分だけ成績が
5番も上がった。伊藤君はHに全く参加しないで、毎日一人で
勉強していたおかげで、学年で10番という成績をとった。
僕だけが皆に利用されたせいで、成績がダダ下がりだ。
順位が今日分かって、母さんに成績個票を見せるのが
辛いのに、週3回もHしたがる加藤君に言われたくなかった。
家に帰ると、母さんが物凄く恐い顔で僕に怒鳴ってきた。
「ちょっと!麻里緒!これはどういうことなの!」
母さんが隠してあったテストを持って、僕の顔に叩きつけた。
「こんな70点台の点数ばっかり取って!数学なんか69点
じゃないの?80点台が一枚もないってどういうこと?
まったく、あんたは毎日のように友達の家に遊びに行って、
勉強しないから、こういうことになるのよ!学年順位は
何番だったの?成績個票を見せなさい!」
僕は恐る恐る黙って成績個票を取り出すと、母さんに渡した。
「43番!一体どうやったら、こんな悪い成績とるのよ!
罰として、今晩の夕食は抜きね!何も食べずに自分の部屋で
反省してなさい!」
僕は自分の部屋に入るとすぐに貯金箱と財布を確認した。
5千円札は4枚ちゃんとあった。母さんはテストの結果が
気になって、机の中に無造作にしまってあった答案用紙を
見つけ出しただけで家捜しまではしていなかった。大丈夫。
バレてない。僕は心の中でつぶやくと、母さんが追い打ちを
かけて怒ってきても大丈夫なように勉強を始めた。しかし、
2時間もすると、僕は眠くなり、ウトウトと机で眠ってしまった。
額に何か懐かしい感触がして、僕が目を覚ますと、父さんが
僕の頭を撫でていた。
「麻里緒。起きなさい。話がある。母さんと相談したんだが、
麻里緒も塾に行きなさい。母さんは麻美にだけピアノと水泳と
書道と英会話を習わせて、麻里緒には何も習わせなかった。
お稽古の一つでも習わせれば良いのにと、父さんは麻里緒が
小学校の頃から思っていたけれど、母さんは麻里緒が
習いたいものがないからと言って、麻里緒にお金を使うのを
極端に嫌がった。今でもそれは変わらないが、こんなに
成績が下がったのだから塾に行かせるのは親の務めだと
母さんに言ってやったんだ。それで、塾に行かせることに
決まったんだが、麻里緒は最近、学校帰りにお友達の家に
よく遊びに行くそうだな。土日の昼間にお友達と遊ぶのは
構わないが、平日の夕方から遊びに行って夜の9時まで
帰って来ないとかそういうのはもうやめなさい。毎週金曜日
麻里緒は誰の家に遊びに行ってるんだ?加藤君とかいう
新しくできたお友達の家かい?」
僕は焦った。毎週金曜日に常磐先輩の家に行くのを
止められたら、常磐先輩に怒られる。どんな仕打ちをされるか
分からないと思ったのだ。
「ごめんなさい。加藤君が家に遊びに来てって誘うから・・・」
「週4回もかい?」
父さんが僕の言い訳を疑うように目を細めて言った。
「学校帰りに直接遊びに行く日は7時までにいつも帰って
来るのに、金曜日だけ家に帰って着替えてから出かける
そうじゃないか。何故だい?父さんは麻里緒の交友関係に
口出しするつもりはないけど、夜遊びはいけないよ。誰か他に
知らない所で、不良と付き合ってるんじゃないのか?父さんは
心配だよ。小学校の頃はいつも担任の先生に勉強を教えて
もらっていただろう?土日まで勉強するって先生の家に
通っていたね。あんなに勉強の好きだった麻里緒が一体
どうしたんだ?麻里緒は悪い子になってしまったのかい?」
父さんが僕の手首を掴んだ。目が凄く恐かった。
「ずっと後悔してたんだ。麻里緒を誰にも渡したくない。」
父さんの唇が僕の唇に重なった。僕はあまりの衝撃に目を
閉じることも出来なかった。1秒が1分に10秒が10分に
感じた。止まった時の中で、父さんは僕の舌を貪った。
「・・・父さん・・・」
唇を解放されても僕の思考回路は停止したままだった。
父さんが僕にキスをした事が理解できなかった。
「あの日。あの夏の日から麻里緒を見るのが辛くて、ずっと
目を背けてきたけど、父さんは麻里緒のことが好きなんだ。
麻里緒が生まれた時からずっと誰よりも麻里緒を愛してる。
それなのに、あんなことになるなんて・・・麻里緒が他の男に
穢されるくらいなら、いっそのこと父さんが・・・自らの手で
穢してしまえば良かったと後悔してるよ。」
父さんの目は真剣だった。そして、恐怖で身動きがとれない
でいる僕を父さんは抱きしめた。父さんの腕の中でぎゅっと
抱きしめられると、僕は忘れていた子供の頃の記憶が
蘇ってきた。まだ幸せだった頃の記憶が父さんの腕の
温もりの中で走馬灯のように蘇った。
僕は父さんに愛されて育った。正確に言うと、父さんは僕を
溺愛していた。物心つく前から父さんは僕にキスしていた。
おはようのキスにおやすみのキス。毎日、抱っこして、頭を
優しく撫でて頬にキスをしてくれた。休日はよく公園に連れて
行ってくれた。僕はブランコが大好きだった。お風呂も父さんと
一緒に入っていた。幼稚園まで僕は父さんに身体を洗って
もらっていた。僕がくすぐったいから自分で洗うと言っても
父さんは僕の胸や腹や尻を撫でまわすように洗っていた。
デリケートな部分は手で洗ったほうが良いと父さんは言って、
手に石鹸を泡立てて、直接下半身を握り、丁寧に優しく
洗っていた。時折、父さんはお風呂の中で僕にキスをした。
母さんの前では額か頬にしかキスしないのに、二人っきりで
お風呂に入っている時に父さんは母さんの目を盗むように
僕の唇にキスをしていた。「母さんには内緒だよ」と、いつも
そう言っていた。でも、ある日、母さんに見つかってしまった。
湯の中で父さんの膝の上に座って、後ろから抱きしめられて
キスしているところを運悪く偶然見られてしまった。当時、
妊娠していた母さんはショックのあまり流産しそうになった。
何度も泣きながら母さんに謝っていた父さんを思い出した。
母さんは無事に妹を産んだけど、その日から母さんは
僕の事を嫌いになった。妹が生まれると妹だけ可愛がり、
父さんには妹にキスさせなかった。父さんは僕にもキス
しなくなって、僕を抱っこもしなくなって、僕の身体にあんまり
触れなくなった。それでも、小学校2年生の夏休みまでは
父さんは僕に優しかった。僕が穢れたあの夏の日までは・・・
遠い過去の出来事はまるで思い出してはいけないように
僕の中で封印されていた。父さんは僕を床に押し倒して、
何度もキスをした。僕は閉ざされた過去の記憶に身を
支配されたかのように動けなかった。溢れる想いは涙となって
僕の頬を伝った。心の何処かでまだ拠り所にしていた
父さんへの甘い幻想が崩れて粉々に砕け散って行く。
絶望的な悲しみよりも切ない痛みのほうが強くて、
僕は胸が苦しくなった。
「泣いているのか?」
父さんが涙を流している僕に問いかけた。
「父さんはおまえが悪い遊びを覚えたって近所で噂に
なってるって聞いて、こんなことになるくらいなら、
伊藤君とも担任の先生とも遊ばせなければ良かった
って思ったら、無意識のうちにキスしていたんだ。
麻里緒は父さんのことが嫌いかい?」
僕は無言で首を横に振った。
「良かった。愛してるよ。麻里緒。」
父さんが僕を抱きしめた。
「父さんは麻里緒の事が好きで好きでたまらないんだ。
誰にも触らせたくない。仕事に行っている間も家の中に
閉じ込めておきたいくらいだよ。」
檻を作って、閉じ込めたらいいって僕は思った。
学校にも行かず、公園にも行かず、誰にも会わず、檻に
閉じ込められて暮らせたら、どんなに幸せだろう。父さんの
歪んだ愛で満たされて、死ぬまで檻の中にいる自分を
想像してみた。それはぞっとするほど甘美な世界だった。
僕は父さんの背中に腕をまわして、唇にキスをした。
僕が初めて血の繋がった肉親に自ら口づけした瞬間だった。
「何をしてるの?!」
部屋の入口に母さんが立っていた。父さんは慌てて僕を
突き離して、こう言った。
「違うんだ。」
「何が違うの!もう二度と麻里緒にキスしないって
約束したのに!昔の約束をよくも破ったわね!」
「ご、誤解だよ。麻里緒が泣いていたから、慰めていただけで、
キスしてない。」
父さんが誤魔化そうとして、ひきつった笑顔を浮かべた。
「な、麻里緒。そうだよな。」
父さんの顔は恐怖に慄いて醜く歪んでいた。
『母さんには内緒だよ』幼い頃に繰り返された行為が
醜い欲情によるものだと僕はようやく気付いた。
「真理子の見間違えだよ。」
父さんは母さんにそう言いながら近づいた。父さんが母さんを
名前で呼ぶ時は必ず喧嘩になる前触れだった。パシッと頬を
叩く音がした。母さんの振り上げた手が震えているのを僕は
見逃さなかった。しかし、平手打ちされた父さんは俯いて、
黙り込んでしまった。ギリシャ神話の石像のような精鍛な
顔立ちの父親が酷く醜い小男に見えた時、僕は何もかも
失くしても構わないと思った。
「僕がキスしたんだよ。」
一瞬、空気が張りつめて、信じられないものでも見るような
目で母さんが僕を見た。
「今、何て言った?」
「僕が父さんにキスしたって言ったんだよ。」
怒りで我を忘れた母さんが恐ろしい顔をして走り寄り、
僕の首に手をかけた。母さんは僕の首を絞めながら喚いた。
「この泥棒猫!あんたは泥棒猫にそっくりよ!あんたなんか
産むんじゃなかった。あんたなんか生まれてこなければ
よかったのよ!」
美しい顔を歪ませて、醜い心の闇をぶちまけた母さんは
本気で僕を殺すのかと思うほどの力で僕の首を絞めた。
「やめろ!真理子!やめるんだ。」
父さんが母さんを無理矢理僕から引き剥がした。ゲホゲホと
むせながら僕は父さんが押さえつけている母さんを横目で
見ると、母さんは気が狂ったように僕に手を伸ばしていた。
もう一度、僕の首を絞めようとする母さんに父さんは
「真理子。すまない。俺が悪かった。すまない。」
と、いつまでも謝り続けた。それは幼稚園の頃にお風呂で
見た光景と似ていた。僕は刹那的な感情に流されたことを
後悔した。そして、逃げるように家を飛び出した。
僕は走って走って、走りながら涙を流した。僕はもう家には
帰れないと思った。駅前の繁華街に行こうかとも思ったけど、
お金を持っていない事に気が付いた。でも、お金を取りに帰る
勇気は僕にはなかった。公園で野宿するか友達の家に行くか
考えて、加藤君ではなく伊藤君の家に行こうと思った。
伊藤君なら看護士のお母さんが夜勤の日は一人でいるはず
だった。僕は伊藤君に一晩泊めてもらおうと思った。走って
来た道を引き返して、伊藤君のアパートの前まで行くと、
今度は家を飛び出した理由をなんて言おうかと迷った。僕は
父さんの事は伊藤君に知られたくなかった。テストの成績が
悪くて、母さんに怒られたってだけで泊めてくれるか心配に
なった。やっぱり公園で野宿しようと思ったその時、伊藤君の
家の窓が開いた。伊藤君は僕を見て、声をかけてくれた。
「麻里緒!こんな夜遅くにどうしたんだ?」
「母さんと喧嘩しちゃった。」
「?!」
伊藤君は僕のついた嘘に凄く驚いたみたいだった。
「・・・。うちに来いよ。」
伊藤君はそれ以上何も聞かずに家に入れてくれた。
「お母さんは夜勤でいないんだ。」
家にあがると、伊藤君が言った。
「あ、そうなんだ。」
僕は知らなかったふりをした。
「何か食べる?」
伊藤君が冷蔵庫から麦茶を出してコップに注ぎながら聞いた。
「ありがとう。僕、母さんに夕飯抜きって言われて、何にも
食べてないんだ。」
僕は努めて明るい口調で言った。
「・・・。カップラーメン食べる?」
伊藤君はまた何か聞きたそうな顔をしたけど、何も聞かずに
カップラーメンを作ってくれた。時計は11時をまわっていた。
「明日は学校に行くよな?」
「あ、うん。もちろんだよ。」
「なら、いいけど。」
伊藤君は心配そうに僕を見ていた。
「食べ終わったら、風呂に入れよ。」
伊藤君はそう言った後も僕をじっと見ていた。
お風呂からあがると、僕は伊藤君のTシャツを借りた。
大人用のMサイズのTシャツはいつまでも子供服を
着ている僕にはブカブカで大きかった。寝室に行くと、
布団が一枚敷いてあった。
「お母さんの布団はシーツを今日洗ったから、使えないんだ。
俺と一緒でいいよな?」
と伊藤君が聞いた。伊藤君の家は貧乏でシーツの替えが
なかった。洗濯したシーツが乾くまで布団が使えないって
可哀相だなと僕は思った。僕は伊藤君の布団に入って、
一緒に寝た。6畳2間のアパートにお母さんと二人暮らしの
伊藤君は中学生になっても、やっぱりお母さんと一緒の
部屋で寝ていたのだった。寝室と居間しかないから仕方ない
のだけれど、幼稚園の頃からずっと一人で寝ている僕には
異世界のような感じがした。
「抱いていいよ。」
僕は隣で寝ている伊藤君に言った。驚くほど自然に出てきた
言葉だった。
「麻里緒・・・」
伊藤君は少し考えた顔をして、僕に言った。
「俺は抱かないよ。俺は麻里緒のことが好きだけど、
そういうことはしたくないんだ。」
「僕が女じゃないから嫌なの?」
「性別は関係ないよ。俺は麻里緒と友達のままでいたいんだ。」
「セックスしても友達のままでいればいいじゃん。加藤君には
内緒にしとこうよ。それとも常磐先輩が恐い?」
僕はずるそうな顔をして、伊藤君の足に僕の足を絡めた。
「加藤は友達だから内緒にはできないよ。でも、常磐先輩が
恐くて手が出せないとかそんなんじゃないんだ。みんな早く
童貞を捨てたがるけど、俺は違うんだ。体がまだ大人になって
ないからだって加藤は言うけど、俺だって夢精くらいするし、
いつもその夢には麻里緒が出てくる。正直に言うと、麻里緒と
したいと思った事はあるよ。だけど、俺は麻里緒の友達だから、
しちゃいけないと思うんだ。」
「どうして?」
「俺が麻里緒としちゃったら、麻里緒には本当の友達が
いなくなってしまうだろ?それって悲しい事だと思わないか?」
僕は伊藤君の言ってる事が分からなかった。僕は今まで愛を
得る代償として身体を差し出してきた。僕に優しくしてくれる
総ての人間が僕の身体を求めてくると思っていたのに、
伊藤君は違っていた。
「友達がいなくて悲しいって思った事ならあるよ。小学校
高学年の時にね。クラスが3年間違っていたせいもあるけど、
あの時は何で僕の傍にいてくれなかったの?」
僕は過去をむし返すように聞いた。
「俺も苛められてたから。もちろん麻里緒ほどじゃないけど、
ホモ友って言われて、上靴を隠されたり、文房具を盗まれたり
したんだ。消しゴムを失くして可哀相だから先生の消しゴムを
あげるって先生が消しゴムをくれてからは貧乏人ってあだ名に
変わったよ。3年生の時に麻里緒を庇って、いろんな奴と喧嘩
しただろ?それで、4年生の最初も喧嘩ばっかりしてたから、
学校の先生も親も心配して、同じクラスで友達を作りなさい
って言うから、麻里緒とは正反対のタイプの友達を作ったよ。
俺は自分の身を守る為に麻里緒を見捨てたんだ。卑怯だと
思うよ。中学に入って、加藤と友達になった時も俺はこれで
坂田から麻里緒を守れるって思ったんだ。浅はかだったよ。
麻里緒が常磐先輩にまわされたり、売春を強要されたりする
なんて思ってもみなかった。俺のせいだ。俺が全部悪いんだ。
あの夏の日も・・・」
伊藤君は酷く後悔していた。
「僕は公園に伊藤君が来なかったことを恨んでないよ。
人間誰でも約束を忘れることってあるしね。」
「違うんだ。本当は・・・あの日、お父さんが急に来て。あ、
お父さんは養育費を持って来いってお母さんに呼び出されて
来たんだけど、俺は何も知らなくて・・・再婚してお金に余裕が
なくなったから、養育費を渡せないって。この5万円で最後に
してくれって。月に1回息子と会う権利も要らないって言うから、
お母さんが怒って・・・包丁を台所から持ち出して、殺してやる
って騒いだんだ。お父さんが手傷を負って、慌てて逃げた後も
お母さんは呪ってやるとかずっと気が狂ったみたいになってて、
俺は恐くて、動けなかった。麻里緒に今日は遊べないって
連絡しなくちゃとは思ったけど、理由を言えないと思って・・・
結局、ずっと家にいたんだ。夜、パトカーが家の近くを
うろついていた時も警察がお母さんを捕まえに来たのかと
心配してた。後から電話で、お父さんはかすり傷だったから
病院には行ったけど、警察には行かなかったって聞いて、
ホッとしたけど、お父さんはもう二度と俺とも会わないし、
滞納してた分の養育費も払わないって言われて、ショック
だったよ。俺は、あの夏の日、お父さんに捨てられたんだ。
今まで誰にも言えなくて・・・でも、それは自分のプライドを
保つ為で・・・俺の麻里緒にしてきた事を考えると、自分の
身勝手さに吐き気がするよ。」
伊藤君は泣いていた。僕は伊藤君の涙を初めてみた気がした。
僕は伊藤君がなんだか幼く見えて、気が付いたら、伊藤君の
唇に僕の唇を重ねてた。
「伊藤君は悪くないよ。伊藤君のせいじゃない。」
伊藤君を抱きしめて、僕は言った。
「アベ・マリア。女の子だったら、麻里亜って名前にしようと
麻里緒のお母さんは思ってたって、昔、麻里緒から聞いた
事があるけど、麻里緒は聖母マリア様みたいだ。」
伊藤君は僕の胸に顔をうずめて言った。昔、母さんは僕に
言っていた。生まれてくる子が女の子だったら、麻里亜と
名付けて、全ての過去を許そうと思っていたと・・・でも、
男の子の僕が生まれて、名前も考えるのが面倒だったから
麻里緒にしたんだって母さんは言ってた。
「麻里緒は総ての罪を許してくれるマリア様だ。もっと早くに
懺悔すれば良かった。」
伊藤君はそう言って、僕の唇に接吻した。伊藤君のキスは
舌は入って来なかった。僕達は何度もキスを重ねて、互いに
抱き合って寝た。まるで僕はセックスを知らない子供のように
服を着たまま抱きしめ合い、欲情の代わりに幸せを感じた。
伊藤君の腕の中で僕は肉親に抱かれて眠る赤子のように
安らかに眠りについた。
翌朝、僕が目を覚ますと、伊藤君がオーブントースターで
食パンを焼いていた。パン1枚と牛乳だけの朝食だったけど、
僕にはイエス・キリストの最後の晩餐のような楽しい食事だった。
「麻里緒のお母さんは厳しいだけで、本当は麻里緒の事を
思って、良い成績を取るように言ってるんじゃないのかな。
学校に行く前、制服に着替えに家に戻った時に、お母さんに
外泊した事を謝った方が良いよ。朝ならお父さんも居るだろ?
あの優しいお父さんなら麻里緒を庇ってくれると思うから、
早く帰ったほうが良いよ。」
と伊藤君は言った。時刻は7時15分だった。伊藤君はわざと
早起きして、僕に朝食を作ってくれたのだった。父さんは
毎朝6時50分に出勤する。何も知らない伊藤君に僕は
何も言えなかった。
「うん。そうだね。そうするよ。」
僕はニコッと微笑んだ。母さんに酷く叱られるのを覚悟で
僕は家に帰ると、父さんが台所にいた。
「麻里緒!帰って来てくれたんだね!」
父さんは僕を見るなり、駆け寄ってきて、僕を抱きしめた。
「どこに行ってたんだ?心配したぞ。」
「伊藤君家。」
「そうか。ま、いいさ。父さん、朝食を作ったんだ。食べるか?」
ダイニングテーブルにはハムエッグとトーストが用意されて
いて、妹の麻美が黙って一人で椅子に座って食べていた。
「麻美。お兄ちゃんが帰って来たよ。」
父さんが優しい口調で麻美に言った。
「おかえりなさい。」
麻美の表情は暗かった。不思議なほど何も聞かずに、
そっけない態度だった。
「さっ、麻里緒も食べなさい。あ、ちょっと冷めちゃったかな。」
父さんは無理して明るく振舞っているように見えた。
「悪いけど、僕、伊藤君の家で食べてきたんだ。母さんは?」
「母さんは気分が悪いって寝てるんだ。それで、今日、
父さんは有給をとって会社を休んで、朝ご飯を作ったんだ。」
僕の知る限り、家族が病気で父さんが会社を休んだのは
初めてだった。母さんは昨日の事がよほどショックだったのか
寝込んでしまったらしい。
「僕、着替えてくる。」
僕はそう言って、階段を上がった。
子供部屋に入る前に母さんが気になって、どうせ謝るなら
早い方が良いと思って、僕は寝室の扉をあけた。すると、
寝室の床には脱ぎ散らかした服が落ちていて、ベッドの
布団の中から母さんが顔を出して、こう言った。
「なんだ。帰ってきたの?」
ベッドから起き上がった母さんはパジャマを着ていなかった。
キャミソール1枚の下着姿で、乱れた髪を物憂げに掻き上げて
僕をじっと見た。母さんの首筋から胸元にかけて幾つもの
キスマークがついていた。露わになった胸元が女体の
生々しさを僕に見せつけていた。父さんは僕に愛してると
言った口で母さんの肉体に口づけしたのかと思うと、僕は
やるせなかった。思わず目を背けて、部屋を出ようとすると、
「昨日の事を謝りに来たのかと思ったのに、何しに来たの?
麻里緒は家を飛び出して外泊した事も反省してないの?
それとも、逆に私に謝って欲しいわけ?私はあんたなんかに
謝らないわよ。泥棒猫のくせに!どういう子だろうね!」
と母さんは怒鳴った。
僕は母さんが意地悪な魔法使いに見えた。僕を惨めにする
呪文を浴びせる魔女だと思った。母さんは本気で僕が
父さんをたぶらかした悪い子だと思っているようだった。
血の繋がった実の父親に抱かれたいと思う子供が何処にいる
というのだろう。僕は父さんに純粋に愛して欲しかっただけ
なのに、たとえ愛の形が歪んでいたとしても、ただ愛されたい
と願う気持ちからキスを受け入れただけなのに・・・泥棒猫
だなんて酷過ぎる。でも、僕は母さんを見て、嫉妬した。
今さっき僕の中に湧いた感情はまぎれもなく嫉妬だった。
夫婦なのだから、身体を繋ぐのは当たり前の行為なのに、
僕は心の何処かで父さんは母さんとしていないと思って
いたかった。父さんの身も心も独占したいと思うなんて、
矛盾している。僕は本当に悪い子なのかもしれない。
「ごめんなさい。母さん。ごめんなさい。」
僕は涙を流して謝った。
「反省してるなら、もういいわ。私も昨日は嫌だって言うのに
無理やりされて疲れてるのよ。あの人は本当に困った人だわ。
あら、もうこんな時間?!麻里緒、早く制服に着替えて
学校に行きなさい。」
母さんはわざとらしく目覚まし時計を見て、僕を部屋から
追い出す口実を作った。僕は
「はい。」
と返事をして寝室から出た。母さんの勝ち誇った顔がしばらく
脳裏から離れないと思った。あの顔はまるで愛人から夫を
奪い返した女の顔だった。母さんは母親である前に女だった
のだ。女として嫉妬し、今まで僕に辛く当たっていたのだった。
僕は悲しかった。母親から愛されていないだけじゃなくて、
憎まれていたなんて・・・僕は母さんと父さんを取り合う気は
なかった。もう愛されなくてもいいと思った。首を絞められた
後も父さんは母さんに謝っていた。父さんは僕を追いかけて
来なかった。その時点で気付くべきだったのだ。父さんは僕を
大切に思っていないと・・・僕の身体を弄んだ先生と同じだと
思った。先生と父さんは性格が似ている。僕はどことなく
父さんに似た喋り方をする先生が好きになった。先生と一緒に
いると、まるで父さんと一緒にいる時のように楽しかった。
僕は先生に頭を撫でられるのも好きだったし、手を繋いで
歩くのも好きだった。やっと、もう一度、僕を可愛がってくれる
人を見つけたと思っていたのに、先生はきっと僕の心の醜さを
知っていたのだろう。僕の前から姿を消してしまった。
僕は先生を失い、父親を失い、母親に首を絞められ、
先輩達に弄ばれ、好きでもない加藤君に抱かれ、唯一、
心の拠り所となる伊藤君は無力だった。伊藤君は何も
知らな過ぎる。僕は聖母マリアなんかじゃない。ましてや、
天使でもない。人は何故、己の見たいと思う姿に人を重ねて
見るのだろう。僕はもう何もかも嫌になった。死にたい。
そんな事が頭に浮かんだ。僕は子供部屋の机の引き出しから
カッターナイフを取り出して、スーッと手首を切った。
血が溢れ、ポタポタと床に落ちて、カーペットを汚していった。
赤い血は僕の心を安らかにしてくれた。血に汚れて、僕は
美しく生まれ変わる蛹のように痛みも苦しみも感じなく
なっていった。生まれ変わったら、空を舞う蝶になろう。
誰にも羽をもがれないように人に懐かない蝶になろう
と思った。誰にも捕まらず、空高く飛ぶ美しい蝶を夢見て、
僕はゆっくりと目を閉じた。
(完)

© Rakuten Group, Inc.