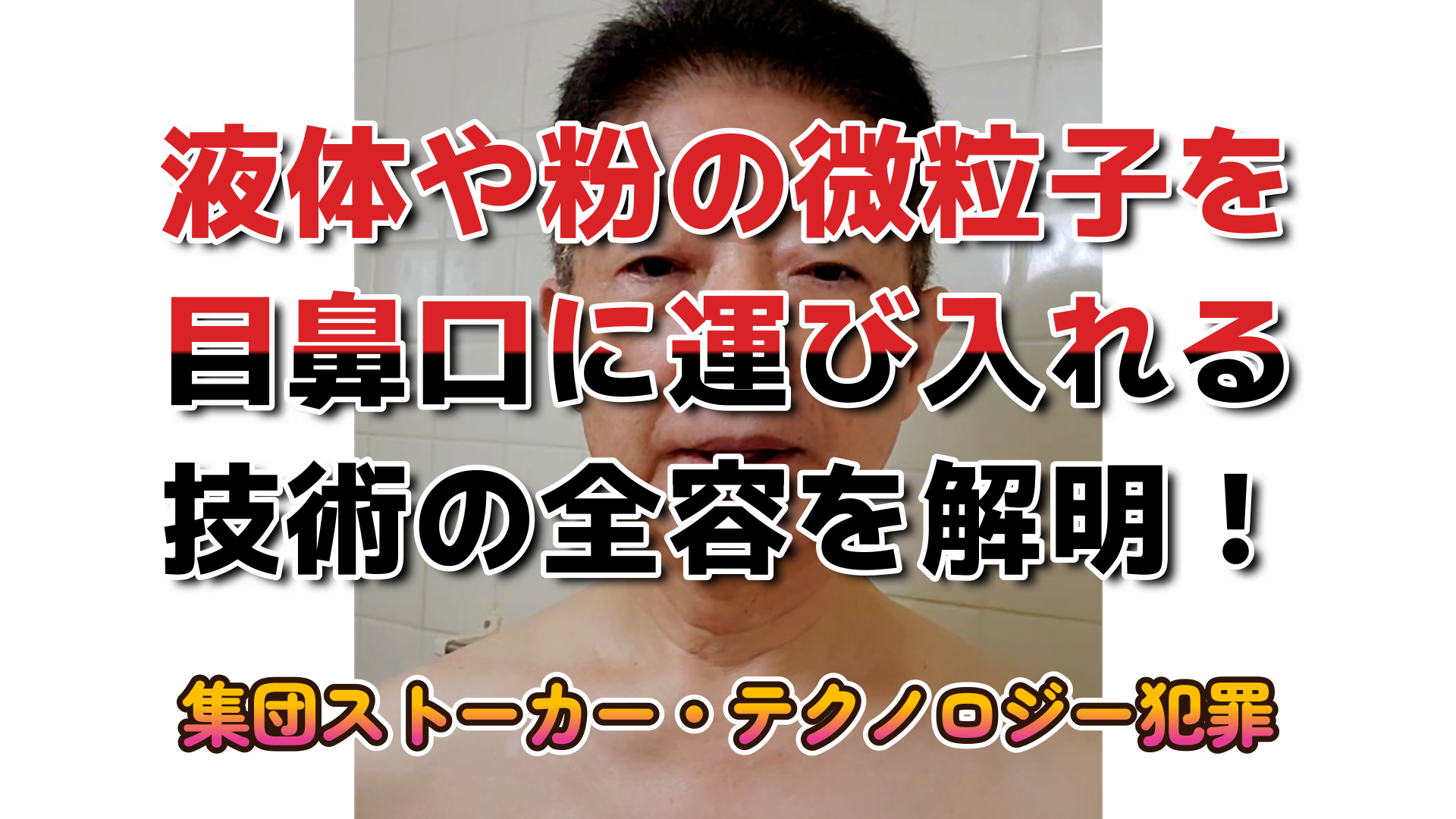哀しき清貧一家の哄笑な日々1~9話
清貧一家の住む家は、そのほとんどがゴキブリのウジャウジャいる巣窟だった。ゴキブリは地面にいる。越冬するために、土の中に潜る。よって、地面に接する家には、ゴキブリがいるものだ。
わかってはいるが、夏場は戦々恐々の毎日を送ることになる。私はゴキブリがすこぶる嫌いだ。いまでこそ、スリッパを履いた足で踏みつぶすことができるが、高校生前後のころは、その姿を見るだけで、身の毛がよだった。
「お父ちゃん! 出た」
天井近くを這うゴキブリを目撃するごとに、おやじを呼びに走った。
「何がや」
「ゴキブリに決まってるやんか」
ゴキブリ以外のことで、おやじに頼るわけがない。ふん!
「面倒臭いのぉ、自分でとれや」
できないことがわかっていて、そう言う。余計に嫌いになる。
ある日、高校から戻った私は、「ただいま」という私に背中で返事をするおやじを目撃した。“シャッ、シャッ、シャッ”不気味な金属音がしている。
『何だろう』
不審に思いながら、自分の部屋へ入った。
果たして、いつものようにゴキブリの襲撃を受けた。天井近くの壁に、黒々とした大きな塊が蠢いている。長く、鋭敏な触覚が、縦横無尽に動いている。私が動くと、触覚が敏感に私の方に向く。
ぞっとした。
「おとうちゃん! 出た」
おやじを呼びに走る。
「ゴキブリか」
そういって部屋から出てきたおやじの手には異様なものが握られていた。使わなくなったテレビのアンテナを解体して保管していた緑色のポールだった。しかもその先には尖ったものが……。サンドペーパーで研いで尖らせた針金をポールに装着した小さなモリのような棒だった。その棒を手におやじが言った。
「これで突け!」
そんなことができるのなら、新聞紙を丸めた棒でも、スリッパでも叩けるだろう。
「どうやって!!!?」
「見とけ、こうやるんや」
そう言うと、おやじはゴキブリに正対し、肩の上にモリを掲げた。
“シュッ”
次の瞬間、親父の手を離れたモリは、ゴキブリの背中を貫通した。
“ビョン、ビョン、ビョン”
モリはゴキブリとともに壁に突き刺さり、ビョンビョン揺れている。
「こうするんや。わかったか」
そう言うと、おやじはモリを壁からはがし、その先に突き刺さっているゴキブリを素手で抜き取り、モリを私の部屋の隅に置いた。
ゴキブリを持つおやじの素手もすさまじいが、部屋の片隅に置かれたモリの先に、ゴキブリの体液がついていると思うと、それもすさまじかった。
高校生の私には、衝撃的過ぎる出来事だったが、おやじのゴキブリに対するスタンスはこれ以降も変わることなく、エスカレートするばかりだった。
第2話 (2)ゴキブリとおやじ その2
清貧一家、ことにその次女は、夏場になるとガサゴソ出現するゴキブリに悩まされていた。
おやじお手製のゴキブリ用「モリ」を使うこともできず、殺虫剤を振りまけば(その頃の殺虫剤の殺虫能力は極めて低く、なかなか絶命させることができなかった)、尻から黒い物体(卵)を目の前に落とされたり、壁から落ちるときにバタバタと羽根をバタつかせて、次女の顔目がけて飛んできたり(もちろん、頭に着地した)と、とんでもない結末を招いていたので、打つ手がなく、勢い、ゴキブリ出現時には、おやじに頼るほかない。
おやじを呼びに行くと、
「あれを使え」
としばらく「モリ」を使うように言われていたが、
「できるわけないやん」
を繰り返す私に、毎回、自分が「モリ」を使ってゴキブリをしとめるはめになっていた。
ある日、深夜に仕事から戻って寝ているはずのおやじが、朝食を食べている私のところに来て言った。
「ええことがわかったぞ」
そのイキイキした表情から、何かいい情報を入手したことはすぐにわかった。
「ゴキブリの捕まえ方や」
朝食がまずくなる、と思いながらも、得意気なおやじの表情と声色から、そんないい方法があるなら、聞いてもいいと思った。
「まずな、ゴキブリをこう持つんや」
そういうと、指先でゴキブリをつかむ真似をする。背中側に人指し指と中指をかけ、親指を腹側に深く差し入れて持つ、というのだ。その時点でアウトである。しかしおやじは続けた。
「クルッとひっくり返して、親指に力を入れて腹の付け根(3つに分かれている体の真ん中〈前胸部〉と下部〈腹部〉の付け根)をクルクル押すんや。ほんだら、足も羽根もバラバラになって、壊れて死による!」
“死による”はいいが、バラバラになった残骸をどうするというのだ。すべてがあり得ない。
「この方法は万能に見えて、弱点がある。ゴキブリの油がべっとり手につくことや。ママレモンでは取れん。マジックリンでようやく油は取れるが匂いは取れん」
朝食の味は完全に失せた。
「しゃぁけど、この方法は道具が要らん。お前もこれで退治せぇ」
おやじは意気揚々と自分の部屋に引き上げていった。
果たしてこの日以来、ゴキブリの襲来ごとにおやじの元に走る私に
「教えた方法で殺れ!」
を繰り返すおやじがいた。
しかしそれも、間もなく諦めて、新聞や、素手や、スリッパを駆使してゴキブリを一発必中でしとめるおやじに戻った。
ゴキブリとおやじの格闘の歴史は長い。また披露したいと思う。
第3話(3)ゴキブリとおやじ その3
おやじは、ゴキブリに対して実に無慈悲だった。それは、私が自分の部屋に出現したゴキブリを
ことさら激しく「退治して!」と懇願するからということもあるが、別の理由もあった。
おやじは、夏場はトランクス(ではない、いわゆるデカパンだ)一丁で寝ていた。元来、暑がりの上、酒を飲んで寝るので、体温が上がって人より暑い状態で寝床に入る。よって、肌布団は一瞬で跳ね上げて、ほぼ裸の状態で口を開けて寝ている。
すると、なぜがゴキブリが近寄ってくる。ゴキブリは基本的に人間には近寄らない。ゴキブリが
好むのは、水のある場所と、残飯置き場だ。
おやじの体には水はないので、いきおい「残飯」、ということになる。ま、それに近い匂いがするのは確かだ。
果たしてゴキブリは、裸の父の体の上を這い回る。少しの間なら気づかないのだろうが、トゲトゲの6本足が体の上を這い回ると、さしものおやじも気づいて目を覚ます。おやじは無慈悲だから、素手でゴキブリをつかみ、そのままギュグッブチッと握りつぶす。つぶした瞬間、おやじは夢から覚める。ゴキブリを手に、おやじは激しく後悔する。手が汚れたからだ。ゴミ箱にゴキブリを
投入し、ゴソッと起き上がって洗面所に行き、マジックリンで手を洗う。手を洗いながらおやじは
ゴキブリに激昂する。寝ぼけた脳に、ゴキブリはとんでもないヤツだとすり込まれる。
ゴキブリはよく水を飲む。台所の流し台の上で、水をチューチュー飲んでいるゴキブリの姿を、トイレに行くために起き、不運にも目撃してしまった私は、詳しく観察した。
ゴキブリには目がない。3つに分かれた体は他の昆虫と同様だが、牙のある口のすぐ上にあるのは、通常は目なのだが、ゴキブリにはそれはついておらず、太い触角の根元に土台のような四角い物体がついている。そこから突き出た長く太い触角は、感心するほど絶えず動いている。左右が違う動きをして、360°のものの動きを察知しようとしている。
ぞうぉっとした。目がない姿は実に異様だった。しかも、トゲのたくさんついた後ろ足は非常に強く、自らの大きな体をやすやすと持ち上げて頭を上げる。ちょっと見方を変えれば「カブト虫」だが、カブト虫にはゴキブリのようなテカリや、意味もなくこちらに向かって突進してくるような不気味な動きはない。
実はおやじは毎年夏になると、カブト虫をベランダで飼っていた。兄の上司及び同僚の子ども(男の子)にプレゼントするためだ。近くの小山に出掛けては、毎回大量のカブト虫をしとめてくる。中にはクワガタもいて、どちらかというと、父はこちらの方が好きだった。カブト虫は1年で生涯を終えるが、クワガタは越冬して7年ほどは生きる。クワガタを育てるのは、おやじにとって子どものころからの楽しみのようだった(実はそのころ、オオクワガタが高値で売れ出した。おやじはあわよくば大金をせしめることができるかも、と考えていたようだ)。
小山から、門外不出の秘技を労してしとめた大量のカブトやクワガタは、2階のベランダに常設されたおやじ手製の虫箱(かなり大きいもの。タテ90×ヨコ90×奥行き60cmほどの木の箱。前面にネットを張り、側面に世話のための扉がついていた)に入れられ、おがくずの床や、小山から切り取ってきたクヌギの木の枝に思い思いの巣を得て生活していた。
これらの昆虫は夜行性のため、おやじは仕事から戻る深夜に世話をした。懐中電灯で虫箱を照らしながら、クヌギの枝に砂糖水やハチミツを塗り、メロン(正確にはマクワウリなどの安価な果物)などを巣箱に入れた。
「よっしゃ、よっしゃ、うまいか。元気にしとったのぉ」
満足気にカブトやクワガタを眺めるおやじの目が、わずかに雰囲気の違うものをとらえた。暗い中、目をこらしたおやじは、思わず声を上げた。
「おう! お前、何しとんねん!!!」
それは、クワガタと並んで、クヌギの木に塗ったミツをおいしそうに吸うゴキブリだった。
「お前なんかに吸わすミツはない!!!」
迷わずおやじは素手でゴキブリをつかんだ。
夕食のとき、この話を聞かされた。例のごとく、夕食の味が失せた。なぜに食事のときにゴキブリの話をするのか、そのわきまえのなさにいやになったのはもちろんだが、結末がいけなかった。
「で、どうしたん、ゴキブリ」
私は聞いた。結末が不安だったのだ。
「そんなもん、腹をグリグリしてバラバラにしたに決まっとる」
「残骸は?」
「ベランダ(2階)から裏にほったった!」
裏は耕されなくなった畑なので、そこまで到達したのなら問題ないだろう。
しかし……、バラバラになったゴキブリの羽根や足が裏の畑に到達するとは到底思えない。1階の裏庭や窓のサンなどに、こまごまとしたゴキブリの残骸が突き刺さっていることは、容易に想像できた。
ゴキブリに無慈悲なおやじのせいで、ゴキブリは身をもって我々に仕返しをしたのだと思えた。
しかし、相も変わらずおやじはそれには頓着せず、無許可でミツを吸った不届きなゴキブリをしとめた達成感とともに、クワガタの飼育箱へのゴキブリの侵入に対する防御策についての発明に思いを馳せ、“心ここにあらず”の表情を見せるのだった。
第4話 (4)清貧一家とゴキブリ
清貧一家とゴキブリは、切っても切り離せない関係だった。私が生まれた家は、4軒続きの長屋で、縁の下がツーツーの、地面のある家だった。次に移り住んだのはおやじの会社の社宅で、いまで言う「文化住宅」。1階の床下は土で、2階の床下は1階の天井という、極めてシンプルにして粗雑なつくりの住宅だった。我が家は2階だったのだが、天井裏がツーツーで、ゴキブリやネズミは絶えず行き来していた。
その後暮らしたのは、巨大ニュータウンの団地の一室。風呂も洋式水洗トイレもあり、それまでの住まいと比べたら、雲泥とも言える環境だった。
が、変わらぬことがあった。それは、ゴキブリの出現頻度である。
夏場になると、毎日、どこかの部屋にガサゴソと出没する。どの住まいにも、出没しやすいポイントがあった。住まいごとの違いはあれど、総じて台所は出没最多ポイントである。
我が家の住人は、ゴキブリが出たときの反応が実に個性的である。父は、過去3回のブログで披露したように、極めて動物的にして無慈悲な対処をし、ゴキブリを完全排除せしめようとする。兄は、おやじゆずりの昆虫好きで、ゴキブリを怖いとは思っていないようだが、油が気持ち悪いようで、カブト虫をつかむようにゴキブリの胴体を指でつまむことはできないようだ。ゆえに、触角をつかんで排除しようとする。ところが、ゴキブリの触角は太くて長いが、あんなでかい胴体を支えるほどの耐力はないので、兄の指に挟まっているのは触角だけで、胴体はどこかに落としてきているというようなことがしばしばだった。
私が殺虫剤を根気よく吹き付け、ようやく全身けいれんに持ち込んだゴキブリをどうしても絶命させられず、ティッシュを5枚以上重ねても、クラフトの買い物袋を手袋のように手に装着しても、どうにもこうにもつかむことができなくて、けいれんのやまぬまま床に横たわるゴキブリを眺めていると、時折仰向けになったまま後ろ足に力を入れて背泳ぎのように頭側に進んでいくゴキブリの太ももの太さと力強さに、この生物が2億年を生き抜いてきた生命力の偉大さを思い知った。
ピクリとも動かなくなったゴキブリだが、恐怖心の余り絶命したことが信じられずに注意深く眺めていると、時折弱く触角や足先が動くようにも思える。それがすぐに何かをもたらすとは思えないが、突然に唐突な動きをしないとも限らない。
ゴキブリの推定死骸とともに夜を明かした私は、どうにかして自分の部屋から死骸を排除したかった。
夜が明け、最初に物音を立てたのは母だった。自室のドアを開けた私は、前掛けを装着しながら茫然と歩く母に向かって、
「おかあちゃん、ゴキブリ、とって!」
と言った。母は、そんなに早い時間に私が起きていて、声をかけてきたことにしばし驚いたものの、すぐに冷静な表情に戻り
「死んでるの?」
と聞いた。
「死んでると思う」
すると母は、サランラップを手に取って、ツーッと引いた。15センチくらい引いてジジッとカットした。
私は、それを何に使うか想像ができなかった。さしずめ、それはゴム手袋の役割を果たす、程度の
ことしか想像ができなかった。
果たして母は、ゴキブリの死骸にサランラップをかけ、小さな手でムンズとつかんだ。次の瞬間、
「パリバリギュギュウッ」
という音がした。
「あ……、潰したん? 気持ち悪くない?ティッシュでつかんだ方がいいことないの?」
驚いた私の表情が理解できない、といった表情で、母は平然と言い放った。
「直接手につかへんもん。ティッシュやったら、汁が手につくことあるやろ」
“やろ”はない。経験がないのだ。しかし、透明なフィルムの中で、黒々としたゴキブリが変な色の汁を出してつぶれているのを見るのを何とも思わないのか。つぶすときの“パリパリ”とか“ギュギュッ”という異音が指先に伝わってくることに恐怖を感じないのか。
「そんなもんより怖いもん、汚いもんは幾らでもある」
持病持ちで精神力も極めて弱いと見える母だが、生命力は極めて高い人間だと再認識した。それ以降、ことあるごとに思い知らされるのであるが、母は強者であった。
実は、飼い猫のチコも、ゴキブリにまつわる逸話が多数あるのだが、長くなるのできょうはここまでにしたい。
一体、どこまでゴキブリに取り憑かれた一家なのか……。
ゴキブリに勝ったのか、負けたのか、いまだ判明していない。
しかし、家族全員がゴキブリとそれなりに対決し、数百万年と2億年という、生存の歴史の違いに悪戦苦闘したのは事実だった。
第5話 (5)哀しき小鳥たち
同じ年代のラジオ局の女性プロデューサーと話をしていたときのことだ。話題は「絵本」だった。世界的に有名な「ぐりとぐら」という本のことを私が話し出すと、女性プロデューサーは懐かしそうな表情をして言った。
「ぐりとぐらか……。最初に飼った文鳥につけたなぁ」
つまり、2羽いた文鳥の名前が「ぐり」と「ぐら」だったということだ。
私ははっとした。私が小学2年生だったとき、清貧一家に白文鳥が2羽やってきた。白文鳥の名前は、「助さん」「格さん」だった。
家庭の文化水準の違いを見せつけられた思いだった。
「助さん」「格さん」は、兄が購入した。その唐突な行動に驚いたものだが、えてして貧しい家庭は動物好きである。自分たちの食べ物にも事欠いているくせに、どういうわけか、動物を多数飼う。家族は驚きながらもすんなり受け入れた。
後に聞いたのだが、突然兄が小鳥を買ってきた理由は、
「両親がけんかばっかりして家が暗いから、動物で気持ちを和ませたら家族が仲良くなると思った」
そうだ。小学3年生の小さな子どもが心を痛めていたと思うと、切なくなる。
しかし、そんな兄の思いを知ってか知らずか、白文鳥が我が家にやってきてすぐに母が言った。
「名前は助さん、格さんがいい」
子ども心に『それはないやろ』と思った。可哀想過ぎる。小さな文鳥に、時代劇に登場する人物の名前とは……。
母はそんな子どもたちの気持ちにはお構いなしに、「助さん、格さん」と呼んで餌を与えている。
その後間もなく、2羽の十姉妹がやってきた。その名前は……
「弥次さん」「喜多さん」である。
ほどなくして、2羽の桜文鳥が加わった。その名前は……
「浩太郎」「橋蔵」だったと記憶している。
そのころ、母が好きだった俳優「里見浩太郎」と「大川橋蔵」のことだ。
次にやってきたのは「紅すずめ」だ。名前は……
このあたりからネタが尽き、
「ピー」「パー」のような、簡単な名前になった。「ピーチクパーチク」から取ったものである。
「インコ」も、二代目「十姉妹」も子どもを生んだりしたが、皆短命だった。最も長く生きたのは、「助さん」「格さん」だ。
よく部屋に放して遊ばせてやった。頭の上にフンをされるなどというのは日常茶飯事。でも、可愛かった。『チュンチュン』と愛らしい声を出し、肩や背中に乗ってくる「助さん」と「格さん」は
不思議と、テレビドラマの中の二人の性格に似ていた。
「助さん」はやんちゃで暴れ者、「格さん」は物静かで礼儀正しい。
いずれにしても、小さな小鳥たちが、清貧一家に笑顔と笑い声をもたらしてくれたのは確かだった。
家に来るなり、時代劇の役名(実在した人物だったようだが)をつけられた哀しき天使たちは、我が家と家族を恨んでいるか、喜んでいるか……。
「これも運命」と諦めてくれているように思う。清貧一家の皆が我が身の運命を諦めていたように。
第6話 (6)豊かさへの憧れ
清貧一家が暮らす家は、まさに貧乏家だった。4軒長家の一番端の家で、隣人のくしゃみや笑い声が鮮明に聞こえる木造モルタル、トタン囲いの家だ。
道路に面した極めて危険な玄関を入った内部は、小さな独立した台所、わずか3畳の前室、4畳半の居間、そしていきなり2畳の板の間で終わり、である。ポットン便所がその横にあった。玄関を出ると排水機能を担った溝があり、裏にはその水が流れ込むドブ川があった。
押し入れが一つあったが、それ以外の収納部はなく、風呂も洗面所もないので、いわゆる“遊び”のスペースがない。家の隅々まで人間の足や手が入る。
ポットン便所がいけなかった。裸電球が吊り下げられた小さな空間は、子どもにとっては恐怖のスペースだった。私は、スリッパを落としたことがあった。兄は片足を落としたが、からくも母に助けられた。姉に至っては、全身ドボンをやらかした。やんちゃだったのだ。用心深い私は、そうした失敗はほとんどない。
風呂がないのもいやだった。冬の寒い日は、銭湯から帰ってくる間に体が冷えてしまう。しかし、無類の風呂好きだった私は、母に手を引かれて、喜んで銭湯に通った。
この家には、清貧一家は12年ほど住んでいたが、途中で生まれた私は7年ほどいただけで、うち、記憶があるのが数年なので、記憶の数は少ないが、なぜかどの記憶も鮮明に覚えている。
次に移り住んだ家はおやじの会社の社宅で、いわゆる文化住宅の2階だった。これもひどい貧乏家だった。鉄の階段を上がり、共同通路を通って玄関を開けると小さな玄関の前室が2畳、その奥が6畳で終わり、である。短い廊下の隅に便所、廊下の向こうにベランダがあった。風呂も洗面所もなし、である。何と、便所は2階なのにポットンという恐ろしい状況だった。
こんな家に清貧一家5人で住んでいた。
途中、母や姉が家出して、家族が兄と私の二人になってしまったことがあったが、概ね5人で暮らした。
友達の家に遊びに行ったとき、洗面所があり、水洗トイレがあり、玄関に門がついていてベッドがあり、自分だけの部屋を持つ友達をうらやましく思った。6畳の部屋で4人が雑魚寝する我が家との違いをまざまざと思い知らされた。
小学校4年のとき、道路拡張により、社宅が立ち退きになった。我々はその家から遠く離れた巨大ニュータウンに移り住むことになった。
そこは天国だった。
間取りは3DK。風呂も洗面所もある。ベランダも二つ。おまけにトイレは洋式の水洗だ。
「ようやく我が家にも幸せがやってきた」
と子ども心に人生最高の喜びを感じた。
5階なのにエレベーターがなく、だらだらと長い階段を昇り降りするのは大変だし、ご近所とのつき合いも尋常ではない。いまから考えたら、最低限に近いような住まいだが、そのころの私には、天国のような場所に思えた。過去が余りにもひどかったからだ。
しかし、新たな住まいを見たから、過去の住まいがひどいと思ったのかもしれない。“立ち退き”という非常事態がなければ、あそこで、あの生活を続けていたのかもしれない。人生とはひょんなことで激変する。
ニュータウンだけに学校のレベルが高く、田舎の学校から転校した私には、追い付くのが大変だったが、それもすぐにクリアして、快適な学校生活を送ることになった。
こうした子どものころの経験が、“豊かさ”と“貧しさ”の意味合いを知らしめてくれた。ありがたいと思う。“豊かさ”しか知らない人は、“豊かさ”の本質がわからない。同じく“貧しさ”しか知らない人は、“貧しさ”が人を卑屈にすることが理解できない。
その後、私が就職したあたりで一戸建てに住めるようになり、やっと“自分の家”だと実感できた。
“豊かさ”を得るのは徐々に、でいい。一足飛びに豊かになると、“豊かさ”の本質を見失ってしまう。
金があるのが豊かなのではない。その金を使って人が豊かだと思える状況をつくり出すプロセスが
必要なのだ。そのプロセスには、必ず人の「夢」が詰まっていなくてはならない。自分を「卑屈」から解放してくれる、貧しさの中で見た「夢」が。
当面の私の夢は、両親をもう少し大阪寄りに移り済ませることだ。
「お前らの世話にはならん」と豪語して、田舎に引っ込んだおやじと、それにいやいやながらついていった母だが、寄る年波には勝てない。何かあると、かけつけるのが大変なので、奈良あたりに住んでくれるとありがたい。
……、休日返上の仕事漬けの日々を受け入れざるを得ない……。
合掌
第7話 (7)清貧一家の給料日前
清貧一家は、そのゆえんを母に見ることが多かった。一つは、持病である。毎日3度3度薬を飲まねばならず、社会保険が使えるとはいっても、清貧一家にとっては、薬代はばかにならなかった。
しかも彼女はプチ浪費家だった。というか、余り計算ができない体質だった。お嬢様育ちだからだろう。“食べたいものは食べたい”という気持ちが根底にあり、子どもがどう思おうと、自分の食べたいものが食卓にのぼった。各種刺身、ウニ、ナマコの三杯酢、カキ酢、鶏レバーのしょうが煮、玉ひもの醤油煮、各種刺身、イモ、タコ、南京、たこ焼き、ところてん……。後半は、おやつに近いが、いずれにしても、「おかず」にはならないものばかりだった。それでも私は「食べなければ飢える」と思って食べたし、それらはそれなりにおいしかったが、好き嫌いの多い兄はダメだった。そんなときに活躍するのは“ふりかけ”だ。『まる◯や』のふりかけがいつも食卓にあったが、どうも「のり卵」がすぐになくなり、「ごま塩」がずっと残っていたように記憶している。
そんな我が家の食卓が、一層清貧そのものになるときがある。おやじの給料日前3日ほど前から給料日までだ。経済難が食卓にモロに反映される。食費の不足が如実にあらわれたメニューが「おでん」「うどんすき」「かやくご飯」である。いずれも食材が安く、副菜が要らない。「うどんすき」に至っては、ご飯すら省略できる。
「うどんすき」と聞くと、「すき焼き」を想像するかもしれないが、うどんだしを土鍋に満たし、うどんと切り落としの牛肉、かまぼこ、しいたけ、白ねぎを加えて卵でとじるという極めてシンプルにして安価な食べ物である。うどんはもちろん、関西でメジャーな「ゆでうどん」である。いまでも1玉50円そこそこで買えるものだ。
しかし、子どもたちは大満足だった。ナマコやカキ酢よりよほど食べやすいごちそうだったのだ。
それでも食費が足りなくなると、母は私に借金を申し出た。
「1000円貸して。利子は50円」
手放しでOKである。その当時(小学3年当時)の私の小遣いは300円だった。50円も利子をもらえれば、文句のつけようがない。小遣いの300円は貯金に回し、利子の50円で1ヵ月をしのいだ。そのうちに、貸せるお金が2000円になり、3000円になり。
子どもにお金を借りた直後、母はどういうわけか
「お好みでも食べようか」
と言う。買い物に出たついでに
駅前のお好み屋でお好みを食べようと言うのだ。
母一流の「やけくそ」らしい。見境がない。
豚玉が1枚350円ほどしたと記憶している。二人で700円使っていては、意味がない。母の手を強く引いて家に戻った。
清貧一家にとって、「食」は毎日の闘いだった。何が食べられるか、どれだけ食べられるかが、夕飯時の攻防だった。だからこそ、食べ物の尊さ、ありがたさ、おいしさ、大切さがわかったのだと思う。
そんな子どもたちの苦悩に相反して、母は残りもののご飯やおかずをポイポイ捨ててしまう気前のよさというか、世間知らずな行動はいまも直らない。清貧なのに、犬や猫を飼っていた意味は、そんな母の所業をフォローし、無駄を出さず、環境を破壊せずにやり過ごしてくるための必要不可欠な要素だったのではないかと思う。
それが通る時代だったし、犬や猫たちも従順にそんなわびしいエサを文句もいわずに食べた。
そんな清貧一家は日本じゅうにたくさんいた。それぞれ、腹を抱えて笑うような楽しみや、涙を流して感激するような喜び、いいようのない悲しみを抱きながら、精一杯生きていた。昭和の、懐かしくも哀しい風景である。
第8話 (8)置き去りにされた幼子たち 1
清貧一家の母は、キレやすい体質だった。いわゆる「ヒステリー」というやつだ。一度火がつくと、収まりどころを用意してやらない限り、どんどんエスカレートしていく。
その当時、おやじは賭け事に精出していた。母は気真面目な性格ゆえ、「賭け事」と聞いただけでヒステリックになったが、それより、おやじが家に帰ってこないことが気に食わなかったようだった。
おやじは、通常深夜2時くらいに戻るはずなのだが、朝、登校時に折り畳んである父の布団を見ると、ドキンとして、母の顔色をうかがったものだった。
たまたま、ある日の深夜、おやじがまともに帰ってきたとき、言い争う二人の声が聞こえてきた。たまさかトイレに起きた私は、話の内容を盗み聞いた。どうやら“給料が少ない”“麻雀をしている”とうい母と“みんな同じ(社宅に住んでいたので、近隣の同僚たちと同じという意味)給料でも、お前よりちゃんとやっている”“麻雀は小遣いの範囲内でやっている”という攻防のようだった。いまになって思う。母が“麻雀”をとがめるのではなく“帰ってこない”ことをとがめていたら、事態は違った展開になっていたように思う。何せおやじが帰ってこないのは、麻雀がしたいことより
病弱な母やうるさいだけの子どもの顔を見るのがいやだったからだ。母が、“居心地のいい家にするから帰ってきて”と一言言えば、おやじはそれなりの対応をしたように思う。しかし、お嬢様体質の母は、下手に出るということができない。相手の落ち度を容赦なく突いて、真っ正面からぶつかってしまう。
果たして翌日の朝、母は私と兄(姉は既に家出をしていた)を学校へと見送った後、家出をした。
いやな予感とともに学校から戻った私は、鏡台に母が日常使っていた化粧品が根こそぎない有様を見て、
「家出した……」
と悟った(それまでにも、プチ家出は何度もしていた。家出をしたときの身辺の変化はよくわかっていた)。
母が家出したら、おやじは幼い子ども(兄9歳、私8歳)を守るために家に戻ってくるだろうと思っていた。
……甘かった。母がいないことをいいことに、おやじは前にも増して戻ってこなくなった(いつものこと)。
兄と私は、おやじに禁じられていたガスコンロが使えない中、何とかして食事をせねばならなかった。母がいて、見守ってもらっている中では、卵焼きも炒り卵も、みそ汁もつくれるようになっていた私だったが、おやじの言いつけを守ろうと思えば、“調理”は極めて困難だった。インスタントラーメンを小さな電熱で煮た。毎日それではつらいので、炊飯器で炊いたご飯と、総菜屋で買ってきたコロッケやポテトサラダで食事をしたこともあった。ご飯にふりかけをかけて済ませたこともあった。焼いた餅や果物をしこたま食べたこともあった。いずれにしても、空腹さえしのげればそれでいいという考え方だった(学校の給食頼みだった。そのおかげで生きてこれたようなものだ。ありがたし、給食!)。
やがて醤油がなくなり、米がなくなり、家にあった金が底をつき、心あたりのある家で麻雀をしているであろうおやじの元に金をもらいに行くはめとなり、もらった金を握りしめて兄と手をつないで米を買いに行ったら、背後でガラスが割れるような唐突な音がして、持っている金を心配しながら全速力で走って家に戻ったりした。
子どもの持つ「生活力」としては「限界」だった。私はその夜、いつものように電熱でインスタントラーメンを煮て、兄と二人で食べながら、ある決意をした。
そのままコタツに寝転びながら、
「明日は学校を休む」
と兄に告げ、私のクラス担任への伝言を頼んだ。そのまま眠りにつこうとしながら、明日、訪れるであろうさまざまな出来事に思いを馳せていた。
残酷なことに、翌朝はまさに瞬く間にやってきた。おやじは相変わらず帰っていなかった。
兄を見送った私は、意を決して鞄に財布を入れ、お年玉をためてようやく自分で買ったディズニーの腕時計をはめて、家を出た。
母がいなくなって1ヵ月ほどの間に展開されたひどくわびしく寂しい生活の記憶を蘇らせながら。
つづく
第9話 (8)置き去りにされた幼子たち 2
朝、起床した私は、兄に私のクラス担任への伝言を託し、送り出してから、前夜に使った食器を洗い(このときは冬だったが、湯沸かし器がなかった我が家では、水道口から出る冷たい水で食事をつくり、食器を洗い、顔を洗い、洗濯した)、たらいいっぱいにたまった洗濯をした後、共同通路側にあった物干竿に洗濯物を干し、着替えをした。
お年玉をためて自分で買ったディズニーの時計を腕にはめ、財布を入れた鞄を持って、家を出た。
安物の家に似つかわしい簡単な鍵で施錠をした私は、徒歩で駅へと向かった。
最寄り駅には10分ほどで到着した。
我が家には電話がなかったので、事前の連絡を入れてはいなかったが、母方の祖母の家に向かうつもりだった。持病がある母が、一人で仕事をして生活しているわけはないのだが、母が家出して10日ほどして、私あてに手紙が届いていた。内容は、“旅館で仲居をしている。自分の部屋と制服をもらって、これまでにない充実した生活を送っている”というものだった。私は、祖母の計らいがあったはずだと直感した。
とりあえず祖母の家に行けば、何らかの情報が得られると確信していた。
それまでにも何度か一人で祖母の家に行ったことがあった。要領はわかっている。もちろん、8歳の子どもには難しい漢字はわからないし、少しでも勘違いするととんでもないところへと行き着いてしまう危険性があったが、私には自信があった。景色を覚える能力にたけていたからだ。音(駅の場内アナウンス)や文字の形に加え、自分が歩いた景色を、色やモノや距離感で鮮明に覚えていた。
近鉄大阪線(普通)から大阪環状線へと乗り換える。最寄り駅からおよそ1時間、常々親が「子ども一人で電車に乗っていると“子取り(子どもをさらう輩。そのころ決まって〈サーカスに売られる〉と説明された。子どもには言いようのない恐怖感を与えた)”が来る」と言い、「知らないおばさんでいいから、親子に見えるようにくっついていなさい」と教えてくれていたので、シートの端に座っていたおばさんの横に陣取り、おばさんに寄り添うようにして立って、親子に見える演技をした。
無事、目的の駅に到着し、祖母の家に向かった。そのころも、若いころ花柳界で生きた経歴を生かし、祖母は働きながら一人で暮らしていた。
駅から15分ほど歩き、祖母の家(アパート)に着いた。しかし、折悪しく祖母はいなかった。
私は時間をつぶすべく、街に出た。歩いて10分ほどのスーパーに行った。このスーパーはおもしろかった。1階は食品売り場、2階は衣料品や日用雑貨を置いているという、ごく普通のスーパーだったが、1階から2階への階段に、いろいろな動物や小鳥がかごに入れられて展示されている。もちろん売られているのだが、とてもかわいいサルやオウム、九官鳥がいて、見ていて飽きない。
祖母や母と来ると、満足に見させてもらえないので、このときとばかり、存分に見て、声をかけて楽しんだ。
そして、靴屋にも行った。そのころはやりのエナメルの靴が欲しかった。母や祖母と行けば、気に入ったのがなくても見栄を張って「どれがいいの?」と聞いてくる。いいのがなければ、店を出ればいいと思う私を制止し、どれかを選ばせようとする。私は自分のお金で、自分の欲しい靴を買いたいと思っていた。一人で、靴屋のショウウィンドーから、ディスプレイしてある靴をつぶさに見た。しばらくしてお目当ての靴を見つけた。小遣いを貯めて買いにくることができるのはいつかと
計算した。
そんなこんなで時間をつぶした後、再び祖母の家に向かった。幸いなことに、今度は祖母がいた。
「おかあちゃんはどこ?」
「言うたらあかんって言われているんや」
「……」
私は、“1時間かけてここまで来たことが無駄になるのか”と、わずかな脱力感を覚えた。
しかし、祖母は優しかった……と言えるかどうか微妙な結末を迎えるのだが。
つづく
© Rakuten Group, Inc.