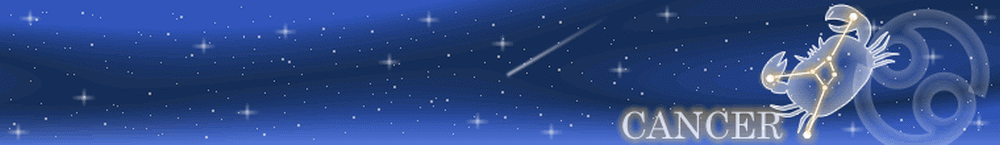2016年05月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

掟上今日子の遺言書
『掟上今日子の挑戦状』を読み終えてすぐに、本著を読み始めました。 女子中学生が、遺書を残して7階建ての雑居ビルから落下。 そして、久しぶりの登場となった古書店従業員・隠館厄介を直撃。 女子中学生は一命をとりとめましたが、厄介は重傷で失職。 遺書には、漫画家・阜本舜の作品に影響を受けての自殺であることが仄めかされ、 そのことにショックを受けた阜本は、筆を折りかねない状況に。 しかし、その遺書に違和感を感じた編集長・紺藤は、 阜本の引退を阻止すべく、事件解決を今日子さんに依頼したのでした。この遺言少女・逆瀬坂雅歌は、ドラマでは第6話に登場しますが、お話は全くの別物です。そして、本著は9つの章に分かれてはいるものの、一冊まるごと、この一つのお話だけなので、読み応えは十分。そして、これまでになく、今日子さんも事件解明に苦労しますが、厄介の好アシスト(?)もあって、何とか真相に辿り着きます。さらに、この作品では、著者の色々な思いが、随所に垣間見え、これまでにはなかった、新しい魅力が盛り込まれています。 「ほら、いじめたほうにそのつもりがなくとも、いじめられたほうがいじめられたと思えば、 それはいじめなんだって言うじゃないですか。 これは正しいものの見方ですが、しかし性格の悪いことを言わせてもらえれば、 同時に、一定の危うさもはらみますよね。 被害者の申告を無条件かつ無制限に受け入れる制度は、 ともすると冤罪の温床になりかねません」と今日子さんは付け足した。 冤罪体質としては身につまされる話である。(p.115)これを読んで、クレームをつける人は当然のようにいるのでしょうが、これまで私が感じていた違和感を、払拭してくれた一文です。
2016.05.29
コメント(0)
-

掟上今日子の挑戦状
『掟上今日子の推薦文』を読み終えて3週間、本著を読みました。 「第一章 掟上今日子のアリバイ証言」は、ドラマでいうと第2話。 鯨井留可(くじらいるか)が、自らのアリバイを証明する人物として たまたま選んだのが今日子さんだったというお話。 「第二章 掟上今日子の密室講義」は、ドラマでいうと第8話。 アパレルショップ『ナースホルン』の常連客・屋根井刺子が、 ショップ内のフィッテイングルームで殺害されるという事件。 その密室殺人の謎を、今日子さんがWi-Fi&クラウドで、解き明かします。そして、「第三章 掟上今日子の暗号表」は、ドラマでいうと第9話。縁淵副社長が残したダイイングメッセージは、一見不可解な暗号。結納坂社長は、これは金庫の暗証番号かもしれないと言いますが、今日子さんが、piem(”円周率Pi”と詩”Poem”が合わさった造語)でスッキリ解決!今回は、隠館厄介も親切守も登場せず、第一章は肘折警部、第二章は遠浅警部、そして、第三章は鈍磨警部と組んで、今日子さんは行動。そのため、ドラマの脚本は、原作にかなり手を加えたものになっています。なので、ドラマを見た後でも、本著は十分に楽しめます。
2016.05.29
コメント(0)
-

明治維新という過ち
なかなかハードな一冊である。 立場を変えてみれば、同じ出来事がこうも違って見えるものかと思い知らされる。 著者は、吉田松陰や桂小五郎、久坂玄瑞、高杉晋作らをテロリストと呼び、 その人道に反する残虐行為や倫理観について、徹底的に糾弾する。 そして、その長州閥の支配する帝国陸軍が、 松陰の外交思想に従って、朝鮮半島から満州を侵略、 カムチャッカから南方に至る広大なエリアへと軍事進出し、 国を滅ぼしたとも指摘する。会津戦争後に、長州藩兵が現地で行った残虐非道な蛮行の描写を読むと、帝国陸軍が敵地で行ったとされる蛮行も、「ひょっとして」と思わされてしまう。また、その地が尊敬する祖父や父の出身地である現首相についても、その目指すものや本性に、不安を感じてしまうのは、心配しすぎだろうか。 ***さて、私が本著で「なるほどな」と再認識させられたのは、次の部分。 徳川家は、外様大名に対して江戸期二百七十年の間、全く油断をしていない。 常に連合の破綻を防ぐべく、さまざまな策を講じてきたのである。 近江という要衝の地に譜代、井伊家彦根藩を置いたのも、 山陽道の堰として姫路城に池田家を配したのも、 大阪城に大阪城代を置いたのも、西を警戒してのことである。 西とは、どこを指すか。 毛利と島津である。 この明々白々とした事実は、幕府成立時の政治状況から、 即ち豊臣末期の勢力関係から見て、六十余州諸侯にとっても共通認識であった。 特に、島津の豊臣期以前からの独立性というものは、 豊臣秀吉にとっても徳川家康にとっても、 これをどう扱うか、具体的にはどうのように寄らしめるかが、天下安泰の要諦であった。 姫路・彦根の位置づけよりさらに重要であったのが、薩摩の真上、肥後である。 この状況を司馬遼太郎氏は「肥後を以て薩摩の蓋とした」という表現をする。 島津を最西端の地に閉じ込め、肥後がその蓋の役割を果たすという意味である。 このことから、薩摩人にとって肥後という隣接する国はただのお隣さんでなく、 特殊な感情の対象となる。(p.303)秀吉や家康にとっての、毛利と島津という二つの大大名の存在。その大きな脅威に対し、警戒に警戒を重ね続けたにも拘らず、二百数十年の時を経て、とうとうこの二つが手を握り、徳川家に牙をむく。そして、そこに絡む薩摩と肥後との関係。さらに、私が本著の中で、最も心に残ったのは次の部分。 動乱の渦中に入った時、あるいは巻き込まれた時、 人はパニックに陥ったり、狂気に走ったり、 はたまた絶望の果てに正気を失ったり、いずれにしても平常な心を失うようである。 誰もが「我を失う」ものだ。 そういう時に、人の本性というものが顕れる。 どれだけ勉学を積み知識を身につけても、 その成果より生来の性格、気質といったものが表に出てしまうのだ。 これは、人にとって自然なことであろう。 困ったことに、武家の教育、要とは、 この自然な現象を否定することが基本となっている。 武家たる者、何事に遭遇しても「平常」を失ってはいけないのである。 パニックに陥るなどはもってのほかであり、武家として修業不足ということになる。 たった一度取り乱しただけで、それまでにどれほどのキャリアを積み重ねていようと 取り乱した瞬間に全人格を否定されるのである。 しかし、訓練、教育とは恐ろしいもので、 武家の中には人として自然な感情の流れや動きを抑え込み、 動乱の渦中に「平常」を失わなかった者も多い。 これを、「本性の克服」とでもいおうか。(p.47) まだまだ、修業が必要だ。
2016.05.28
コメント(0)
-

猟銃・闘牛
昨夜、遅い時間に本著の『猟銃』の部分を読み、 今日の昼、『私結婚できないんじゃなくて、しないんです』の録画を見て、 18:00には、兵庫県立芸術文化センターの阪急中ホールにいました。 もちろん、中谷さんの『猟銃』を見るためです。 この作品を、どんな感じで演じられるのか興味津々で足を運びましたが、 開演直後のナレーションを聞いただけで、「おっ」と思いました。 「ひょっとして、これ、原作に忠実にやるつもりですか?」 それは、それだけで、とてもスゴイことなんですけど。本著「解説」によると、この作品は、『文学界』の昭和24年10月号に掲載されたもので、井上靖氏の処女作とのこと。それ故、そこで用いられている言葉や言い回しは、かなり古めかしく感じられるものであり、文字を見れば何とか理解できるけれど、音として聞いた時にはピンと来ないものも結構あります。それを敢えて、現代語・現代文に変換することなく、そのまま用いるということは、観る者の度量が問われるのはもちろんのこと、演じる者の度量が、より問われることになります。そう、原作を読んでいない観客にも、その古めかしい言葉の音だけで伝えなくてはなりません。なので、ナレーションが始まったとき、私は、大急ぎで昨夜原作を読んでおいて、本当に良かったと思いました。取り敢えず、スタートから話の筋が掴めず、置いてけぼりになることはないはずですから。そして、ナレーションが終わり、いよいよ中谷さんの登場です。まずは、薔子の手紙から始まります。ドラマで聞く中谷さんの声とは随分違った感じ。まるで別人とも思える声で、かなり早口で語りかけてきます。それも、ほぼほぼ原作に忠実な感じで。手紙部分は、本著で言うと、薔子のものがp.15~p.32、みどりのものがp.32~p.49、そして、彩子のものがp.49~p.67に掲載されており、1ページは、43文字×18行で構成されています。もちろん、上演に当たっては原作のままではなく、それ用に書き改められているものの、最初から最後まで、約100分間を中谷さんが一人で語りきらねばならないのです。これは本当にスゴイとしか言いようがありません。始まった時点で、その事実を思うだけで、もう圧倒されてしまいました。そして、みどりの手紙部分になると、衣装も声も動作も大きく変化し、その溢れんばかりの熱情が、ビシビシと観客席まで伝わって来ました。さらに彩子になると、一転して静かで落ち着いた調子へと変化。ここで、聞きなれた中谷さんの声に一番近くなった気がしました。薄暗い中で、気付かぬ間にイリュージョンのように変化していった大道具や音響、照明もなかなか凝ったものでした。そして何よりも、上演中、客席に物音ひとつ立てさせない緊張感を保たせたまま、最後まで、三人の女性を見事に演じきった中谷さんは、やっぱりすごかったです。そして、帰ってきてから、ホールで購入したプログラムに、じっくりと目を通しました。なかなか立派で、よく出来た、CPの高いものでした。でも、中谷さんの一番のはまり役は柴田純だと、今でも思っています。
2016.05.21
コメント(0)
-

STAP細胞はなぜ潰されたのか
ドイツのハイデルベルク大学研究グループがSTAP現象の確認に成功した。 にもかかわらず、このニュースはマスコミではあまり取り上げられていない。 あれだけ大騒ぎした騒動に、大きな変化が生じたのにである。 なぜ、ベッキーや舛添知事のニュースばかり流し続けるのか? しかし、これは今回に限ったことではない。 2014年7月22日、理研が、そのサイト上で、若山氏がつくりCDBに保管されていた STAP幹細胞とされる細胞の遺伝子解析結果を訂正すると発表した際にも、 その訂正報道は、ほとんどベタ記事扱いに留まった。(本著p.182に記述あり) これは、若山氏の「STAP細胞は自分の研究室に存在しないマウスからつくられていた」 という主張が成り立たなくなり、「捏造」疑惑を左右する大きな訂正だったのにだ。 実際、すでに紹介した通り、理研が発表した「STAP現象の検証結果」(12月19日)では、 ネイチャー論文ほどはっきりした形ではなかったにせよ、 笹井氏が何度も述べていた、そして最後まで希望を託していた 「STAP現象」が確認されていたのだ。(中略) 言うまでもなく、この「肝臓由来の細胞をATP処理した時で、 独立に行った49回の実験のうち37回でSTAP様細胞塊の出現が確認された」 という検証実験の結果は、『捏造の科学者』では一切触れられていない。 当然、この検証について検討も検証も行われていない (不思議なことに、筆者が見た限り、この部分に触れた報道は当時、一切なかった)。 (p.194)上の引用文中の12月19日は、2014年の12月19日のことであり、『捏造の科学者』は、この重大発表を前に、筆が置かれている。その違和感については、本著の中で、大宅壮一ノンフィクション賞のノミネート時期と、毎日新聞の記者が書いた書籍なのに、出版社が文藝春秋社だったことに絡め書かれている。 STAP細胞事件に関するメディアの報道は最初からおかしなものだった。 小保方氏やSTAP細胞に関する疑惑が持ち上がると大きく報道し、 反対の小保方氏の有利になるような情報はほとんど無視するか、 小保方氏を揶揄するような記事も多かった。(p.173)マスコミがこの程度のものだということは、もうバレバレなのだが、それでも、そこからもたらされる情報を元に、多くの世論は形成されてしまっている。 真偽の決着をつけるのは、やはり再現実験の可否だろう。 当面、再現実験に成功していないとしても、それは非存在の証明にはならない。 実際、iMuSCs論文が登場しており、STAP細胞に近い細胞が作成されている。 小保方氏が自身のサイト「STAP HOPE PAGE」で プロトコルとレシピを公開したので、 いずれ完全な成功者が登場するかもしれない。(p.172)今回の、ハイデルベルク大の研究は、小保方さんのレシピをそのままなぞったものではないが、真偽の決着に大きく前進したのではないかと、私は思っている。 この文章(『あの日』p.122)からわかるのは、 2013年当時は、若山研でも日常的にSTAP細胞の作製が行われていたこと、 そしてもう一つは、若山研にいた中国人留学生の元研究員も 中国でSTAP細胞の作製に成功しているということだ。(中略) このことが事実かどうかは、若山氏はもちろん、若山研の当時のスタッフ、 中国人留学生に聞き取りをすればすぐにわかることだ。 しかし、小保方氏の追及にはあれほど熱心に取り組んだメディアが、 『あの日』出版後にこうした問題に取り組んだという話は聞こえてこない。 これもSTAP細胞事件において不可解なことのひとつである。(p.93)そう、『あの日』に対する反応が、マスコミから驚くほどになかった。取り合わないことが、大人の対応とでも思っていたのだろうか。 須田記者はなぜ若山氏に再取材しないのだろうか。 STAP細胞問題の真相追及にあれほど熱心に取材を進めていたのに、 なぜ沈黙を守っているのだろうか。 それは若山氏にも同様である。 『あの日』には若山氏の行動に対する疑問や批判が随所に登場する。 なぜ若山氏は反論しないのだろうか。 なぜ沈黙を守っているのだろうか。(p.156)これは、著者だけでなく、私も大いに疑問に思うところである。なぜ、リアクションが全くないのだろうか?それとも、私が知らないだけで、実際は何かコメントや、動きがあったのだろうか? これまでに見てきた以外にも、本書(『捏造の科学者』)について書きたいことは多い。 一つは、一連のSTAP細胞騒動が、中心人物の一人笹井氏の自殺という 大きな悲劇を招き寄せたことに対しての須田記者も含めたメディアの責任について、 反省も含めほとんど触れられていないことだ。 『あの日』でも痛烈に批判されているように、 どう見ても笹井氏を自殺にまで追いつめたことには、 須田記者も含めたメディア側の責任が大いにあるはずだ。(p.196) NHKはなぜこのような取材対象者にけがまで負わせるような取材をしたのだろうか。 当時は社会的空気として、小保方氏は犯罪人であり、 そのくらいのことはしてもかまわないという雰囲気が充満していた。 『あの日』にはそうしたことが繰り返し書かれている。 1994年の松本サリン事件で、第一通報者の河野義行氏に対して、 警察のリークに全マスコミが「あたかも河野義行が犯人であるとの前提」で報道を行い、 のちに報道被害を与えたものとして大きな問題となったことを忘れてしまったのだろうか。 (p.186)『捏造の科学者』に書かれていることも、『あの日』に書かれていることも、そして本著に書かれていることも、どこまでが真実なのか、私には知る術がない。しかし、言えることは、河野義行さんのような人を決して生み出してはいけないということと、メディアに携わる人たちには、常にそのことを肝に銘じてほしいということだ。
2016.05.15
コメント(0)
-

夫婦という病
最初は、いつもの岡田さんの著作を読んでいる感じと全然違いました。 夫の無関心に疲れた妻、失われた女盛り、不倫妻の癒されない飢餓感、 独身に戻りたい夫、多情な夫と良妻賢母の妻、等々。 まるで女性週刊誌を読んでいるような感じです。 21ものケースについて、それぞれ解説がなされていきますが、 問題を解決すべく、手立てを提案していくというものではありません。 あくまでも、精神科医の立場からみて、各事例がどのように解釈できるか、 特に「愛着」の観点から、述べられています。しかし、次の文章は、さすがに一味違いました。 人間はこれまでプレーリーハタネズミ型のライフスタイルで暮らすことが多かったが、 近年、異変が起こっているようだ。 プレーリーハタネズミ型が主流だったライフスタイルが、 サンガクハタネズミ型が主流になろうとしているようだ。 多くの人が、一緒にいることに喜びや満足よりも苦痛や不愉快さを覚え、 一人でいることを好むようになっている。(p.184)この二種類のネズミについての説明は、次の通り。 気候が温暖で、 餌がふんだんにある草原という環境で暮らすプレーリーハタネズミにとっては、 大家族で、巨大な巣をつくって暮らすのが、 外敵から身を守り、子育てするうえで有利だ。 だが、気候も厳しく、 一か所で手に入る食べ物には限りがある山岳地で暮らすサンガクハタネズミは、 そのライフスタイルを捨て去らねばならなかった。(p.185)そして、人間のライフスタイルも、環境の変化に伴い、「経済優先」そして「個人主義主流」へと、大きく変貌しました。 お金によって得られる楽しみや快適さが増し、 お金に依存する部分が非常に大きくなったため、 人々は、お金を手に入れるための活動に多くの時間とエネルギーを割くようになるとともに、 それ以外の営みを犠牲にするようになった。 犠牲となるのは、経済的な豊かさにはつながらないものということになる。 その代表が、子育てだ。(中略) 子育てと同様、家族や隣人、友人との交わりも、 経済的にはメリットをもたらさないという理由で、次第に切り詰められてきた(中略) もう一つの環境圧は、個人主義の浸透だ。 個人の自由や権利を重視し、自己実現を人生の目的とする考え方が広まったのだ。 そうした価値観やライフスタイルを邪魔するものとみなされたのが、家族であり結婚だ。 どちらも、個人の自由を縛り、自己実現を阻む封建的な制度として目の敵にされ、 そうした制度からの自由な生き方の模索も行われてきた。(p.186)確かに、特に若い年齢層においては、この傾向が顕著であるような気がします。「結婚しない」「子どもはつくらない」ということが、選択肢の一つとして、普通に語られるようになりました。ひと昔前には考えられなかったことです。そして、このような状況下、不安定な愛着スタイルを抱える女性は、新しいライフスタイルを確立しつつあるように思えると、岡田さんは言います。それは、母子の絆を優先し、夫やパートナーを事情に合わせて取り替えていくというもの。つまり、夫婦はずっと一緒にいるということに拘らないという生き方。 古臭い道徳や世間体、それに、永遠の愛を誓ったという手前もあって、 もう飽きてきたとも言い出せず、我慢しながら暮らしているだけだ。 その我慢が、イライラや嫌悪感、うつ状態を生む。 誰であれ、本心を欺き、不本意なことを強いられる生活は苦痛なだけでなく、 その人が本来もっている活力や輝きを失わせてしまうからだ。(中略) こう考えると、母親が働けるくらいまで子どもが育てば、夫婦が別れて暮らし、 夫は生活費だけを負担するというライフスタイルは、 新たな出会いを必要とするこのタイプの男女にとっては、 非常に理にかなったものだと言える。(p.239)かなり、先鋭的な考え方のようにも思われますが、ルー・サロメやオードリー・ヘップバーンのケースを読むと、そういう人もいるんだなとは思いました。が、根本は「愛着」の問題であり、それが環境の変化で変容してきているからでしょう。
2016.05.14
コメント(0)
-

あの日
これは、一体だれが書いた文章なのでしょうか? あの状況の中で、これだけの文章を自分自身で書くことは至難の業だと思います。 恐らくは、本人が話した内容だとか、色々と書き留めたことだとかを、 誰かが上手にまとめたのでしょう……まぁ、普通によくあることです。 そう、こんなことですら、本当のところを私は知る術がありません。 本著に書いてあることが、どこまで真実なのか、 また、『捏造の科学者』に書かれていることも、どこまで真実なのか、 私には、そして世間の人たちも、本当のところ知る術がありません。小保方さんにしても、須田さんにしても、それぞれの立場から見える景色があります。それは、本人にとっては確かなものなのかもしれないけれど、他の誰の目にも同じように見えるとは限りません。 そして、それぞれに見たくないもの、知られたくないこと、表には出さないことがあります。今回の件においても、色々な立場の人が、色々な場所に多数存在し、それぞれに守るべきものを守るため、様々な暗闘が繰り返されたのでしょう。自分に不利なことは出来るだけ言わず、相手の矛盾点は徹底的に糾弾する……まぁ、普通によくあることで、私たちは、本当のところ知る術はありません。 *** 終盤の頃の質問に対し、ある文脈の中で「私はポスドクだったので」と述べると、 委員会のメンバー全員がきょとんとした顔をした。 少し身を乗り出した形で、「誰の指導下だったのですか」と聞かれ、 「若山研で実験をしていました」と答えると、しんと場がが静まり返り、 懲戒委員会の面談は終わった。 理研本部はこの時に初めて、不正判定を受けた図表の実験が行われたのは、 私がユニットリーダーではなく、 若山先生という指導者のいる研究員の立場であった時のことと知り、 懲戒の判断がつかなくなった、と後に理事の一人から聞いた。(p.180)驚くような記述ですが、これも真実かどうかはわかりません。でも、案外、こんなものなのかもしれないですね。 特に毎日新聞の須田桃子記者からの取材攻勢は殺意すら感じさせるものがあった。 脅迫のようなメールが「取材」名目でやってくる。 メールの質問事項の中にリーク情報や不確定な情報をあえて盛り込み、 「こんな情報も持っているのですよ、返事をしなければこのまま報じますよ」と 暗に取材する相手を追い詰め、 無理やりにでも何らかの返答をさせるのが彼女の取材方法だった。 笹井先生からは、「このまま報道されては困るからできるだけ返答するようにしている。 メールボックスを開くのすら辛い。日々、須田記者の対応に追われてノイローゼがひどく 他の仕事ができなくなってきた」と連絡を受けた。 丹羽先生も同様のメールや電話の攻勢を受け困り果てていた。 メールの最後は「お返事がない場合にはその理由をお知らせください」と締めくくられる。 自分さえ多くの情報を得ることができるなら、 取材をかける人たちにどれだけ大きな負担がかかろうが構わないのだろうか。(p.183)『捏造の科学者』で笹井氏の死に触れた際の、淡々とした他人事のような記述に、須田さんという人の人となりが凝縮されているように、私は感じました。まぁ、これも須田さんだけでなく、マスコミに関わっている人全般の姿勢かもしれません。それが「正義」だと思われていることに対しては、嫌悪感を抱かずにはおれませんが。
2016.05.14
コメント(0)
-

掟上今日子の推薦文
『掟上今日子の備忘録』を読み終えて、早速、本著を読みました。 「第一章 鑑定する今日子さん」は、ドラマでいうと第3話。 美術館に展示されている絵画の鑑定額が、2億円から200万円へと暴落し、 その絵を、老人が額縁ごと粉々に砕いてしまうというお話。 「第二章 推定する今日子さん」は、ドラマでいうと第4話。 額縁匠の和久井翁が、生涯の集大成となる仕事に取り掛かろうとしたところ、 高層タワーマンション『アトリエ荘』の地下で、何者かに刺されてしまう。 その現場に駆けつけたのは、アルバイトで警備を頼まれた親切守と今日子さん。「第三章 推薦する今日子さん」は、ドラマでいうと第4話の続き。今日子さんが、和久井翁を刺した犯人を自首へと導きます。これはドラマと結末が大きく違っていましたが、これ位アレンジか施されているのが、逆に普通でしょう。それよりビックリは、本作では隠館厄介が全く登場せず、その代わりに、親切守というキャラクターが登場していること。ドラマでは分かりやすいように、キャラクターを統合したんでしょうね。『挑戦状』や『遺言書』では、どういう風になっているのかな?
2016.05.05
コメント(0)
-

進撃の巨人(19)
馬を狙う鎧の巨人を、アレンが囮となって引き付ける。 そして、対決の場を十分な立体物のある所に持ち込むと、 調査兵団の「雷槍」が、次々に鎧の巨人に襲い掛かる。 が、とどめを刺す直前、獣の巨人が壁の中へと樽を投げ込む。 樽の中から、瀕死の鎧の巨人を見つけたベルトルトは、 彼にダメージを与えないよう巨人化せず、ライナーの安否を確認。 そこで、アルミンはベルトルトと最後の交渉を試みるが、決裂。 ベルトルトは襲い掛かるミカサを振り切り、ライナーの元へ。そして、上空で超大型巨人に。その爆風に巻き込まれ、ハンジたちは…… ***仲間が目の前で死んでいくことに、涙を流していたベルトルトも、何だか吹っ切れた様子。でも、お話の展開はかなりスローダウン。次巻では、どれくらい進展するのだろう。
2016.05.04
コメント(0)
-

捏造の科学者
『あの日』を購入して、読みかけたのですが、 本著を先に読んでおいた方が良いのではないかと思い、読んでみました。 高校の生物レベルの知識しか持ち合わせていない私には、かなり手強い一冊。 新聞記者さんが書いたものなのに、スラスラとは読み進められませんでした。 しかしこの文章は、マスメディアの一員であり、 この問題の世論形成に深く関与した方が書いたものだということは、 読んでいて、あちこちで強く意識させられました。 持ち上げるだけ持ち上げ、一気に落として完膚なく叩きのめす風潮の源。 断定的に、若山の理解=正しい(正義)、小保方=間違い(悪)、 という構図を言うのは、あまりにもナンセンスではないでしょうか?(中略) その二人の間の意思の疎通の悪さ、ミスコミュニケーションを含め、 ラボのdisucussion(※議論)テーブルで話すべきことで、 公共放送でこの扱いは全くおかしな話だと思いました。 かなり作為的な決めつけや断定が、若山さんなのか、その周囲なのか、 メディアなのかわかりませんが、本来の検証の枠を超えた場外乱闘で、 ヒールを仕立てているような不気味さを否めません。(p.132)後に自死に至った笹井氏から、筆者に送られたメールです。当事者としては、率直な思いが述べられていると感じました。 会見は二時間半に及んだ。 小保方氏は「私は学生の頃からいろんな研究室を渡り歩き、 研究の仕方が自己流で走ってきてしまった。 本当に不勉強で、未熟で、情けなく思っている」と声を詰まらせた一方で、 研究成果の真偽については、「STAP細胞はあります」と言い切り、(以下略)(p.174)とても有名になってしまったシーンですが、やはり「自己流で走ってきてしまった」という部分については、とても不思議で、違和感を感じざるを得ません。それで、博士論文って通るものなのでしょうか? 「だって、『トカゲのしっぽ切り』をするには最も好都合なデータでしょう。 世間の多くの人はまだ、『小保方さんは未熟な研究者だけど、 それほど悪質なことはできない』と見ている。 『はしゃいでことを大きくしてしまったのは理研なのに、 彼女にすべての責任を押しつけようとしている』と同情的に見ているわけだ。 でもこの結果から素直に考えると、彼女が実は悪質だったということになる。 『ES細胞と非常によく似ているけど、ちょっと違うものを作る』という 明確な意図が感じられるからね。 もっとも、彼女が一人でこんなことを思いつくかな、という疑問もわくけど」(p.264)これは理研の内部資料を見て、ある国立大学教授が述べた言葉。あの頃の世間の状況を、かなり的確に表した言葉のような気がします。しかし、こういうものが出回り、取材の材料となっていることの方に、驚かされたというのが、本当のところです。 「若山さんは専門分野が違うので分子生物学的なデータが分からず、 小保方さんの実験結果を分子生物学的な観点から検証するという意識がそもそもなかった。 笹井さんも、かつて議論をして感じたことだが、 多機能性幹細胞から神経を作るのはプロでも、多機能性幹細胞そのものには興味がない。 そういうこともあって、 おそらく小保方さんのデータの不自然さに気付かなかったのではないか。 さらにiPS細胞への対抗意識などもあったために予断があり、 検証しようという意識にも欠けたのでは。 丹羽さんはきっと、笹井さんとの力関係から、 笹井さんがよしとするものに何も言うことができなかった。 笹井さんは押しが強いのでね」(p.283)これは、そうそうたる顔ぶれの共著者たちが、なぜ論文発表前に、それが持つ危うさに気付けなかったのかという著者の問いに、CDP出身のある研究者が答えたもので、なるほどなと、素直に納得できるものです。そして、この研究者は次のようにも述べています。 「そもそも(2007年に登場した)山中(伸弥)さんのiPS細胞が、 当時の常識からすると信じられない、すごい成果だった。 こんなことあるのかと、科学者がみな打ちのめされた。 だから今回も、あり得ないことだが、 あり得ないことが起きても不思議はない、という空気はあった。 そんなばかな、ということにはならなかった」これも頷ける内容だと思います。若山さんも、笹井さんも、丹羽さんも、素直に信じていたのでしょう。しかし、ネイチャー、セル、サイエンスに論文を連続投稿し、連続不採択。そして、その際の査読コメントに書かれた問題点や疑問点、改良案は生かされませんでした。 だが、調査委員会によれば、 当の小保方氏はサイエンスの査読コメントについてこう説明したという。 「精査しておらず、その具体的内容についての認識はない」(p.308)これが、私が本著を読んでいる中で、最もブラックだと感じた部分です。それでは、いよいよ『あの日』を読むことにしましょう。
2016.05.01
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- トム・ゴードンに恋した少女 スティ…
- (2024-11-23 17:27:42)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 35 ピンクのスカーフ
- (2024-11-17 17:02:55)
-
-
-

- お勧めの本
- 「モリスといっぱいのしんぱいごと」…
- (2024-11-20 19:20:09)
-