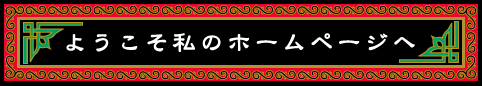アシタバ(明日葉) 食欲の増進、疲労回復
2003年5月10日に初めて日記を載せました。
おかげさまで、思ってもいなかった、
100000ヒット出来ましたのも、
御覧頂いている楽天会員の方、そしてゲストさん。
ありがとうございました。
これからは、もう一度初心に戻り
ゆっくりと時間をかけた良いページを作っていこうと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
*アシタバ(明日葉) 秦の始皇帝が不老不死の霊草として探し求めた薬草である。
アシタバ(明日葉)は房総半島や三浦半島、伊豆七島など、
温暖な地方の海岸に野生するセリ科の植物であるが、
その名は「今日その葉を摘んでも明日には新しい葉が出てくる」ということでついたといわれている。
実際には四日目くらいが普通のようであるそうだ?
いずれにしても、その生育力、生命力が非常に旺盛であることはたしかである。
大型の多年草で、茎は1mくらいに伸び、葉の色は緑。
葉は茎を包むようにつき、5月から10月ごろにかけて淡黄色の花が咲くそうである。
その強い生命力のためか『大和本草』にも不老長寿の植物として紹介されているのだ。
それよりさらに古く、秦の始皇帝が不老不死の霊草として探し求めたという伝説もあるという。
それはともかく、わが国での食用の始まりは、江戸時代の八丈島からだそうだ。
当時は流刑地の遠島として知られ、鳥も通わぬ島とされていた。
ここにきた罪人たちが海岸に野生するアシタバを食べたと伝えられている。
しかし、その他の地方でも、おひたしとかゴマ和えや、からし和え、てんぷらなどの料理があり、かなり古くから食用に供されていたと考えられるのである。

(富士川橋と富士山 1/24午前10時:旧国1号線富士川橋・この下に富士川堰がある。なんの為かって?そう急流を緩やかにする為なんだろうね?)

(富士フイルム工場と富士山 1/24午前11時:ここから始まったんだろうね?フジフイルムの歴史が!)

(木立と富士山 1/24午前11時:この道は富士宮から芝川に抜ける道である。その登る途中で木立の間に富士山が覗いた)
*また、乳牛の牧草としても栽培され、乳の出をよくし、乳質を高めるといわれる。
こうしたアシタバの効用は、一言でいうと、新陳代謝機能の促進であり、それに見合った各種の有効成分が含まれることも確認されているのだ。
まず、普通の植物にはあまりないビタミンB12を豊富に含んでいること。
B12は人体の発育成長に欠かせないビタミンで、「赤いビタミン」といわれ、増血作用のあることで知られているのである。
また、葉緑素が多いのも特徴のひとつ。
さらにアシタバの茎を切ると、黄色の汁が出るのであるが?
この汁にはフラボノイドという薬効成分が含まれ、利尿・かんげ緩下作用がある。
その中で、ルテオリンという成分は強心・利尿剤として有名なのだ。(健康・栄養食品事典より)

(富士川楽座と富士山 1/24午前11時半:駐車場から写した。今日は曇っていて、いっそう富士山が寒々と冷え込んでいた用に感じた。雪もだいぶ下のほうまで降ったのだろう?)

(富士川と富士山 1/24午前11時半:富士川の流れは、冬はやはり水量が少ないせいであろう?流れも緩やかだ!そして河川敷の草花も、春に、可憐な姿に戻る為の準備の為なのだろうか?枯れて、わずかな眠りに入ったようだ!)
*このほか、精油、アンゲロールなどの成分を含み、特殊芳香、苦味等が食欲の増進、疲労回復、強精の効果があると考えられているという。
これらの有効成分から、アシタバは文字どおり「明日の活力を養う健康的な野草」といえそうである。
事実、アシタバを常用している八丈島の島民には高血圧が少なく、健康に恵まれている。
最近では、抗ガン物質として注目されているゲルマニウムを含んでいることでも注目されているほか、カルシウムやカリウムも多く、健康の維持、増進に役立つ薬草として、大いに期待されているのだ。
茹でてお浸し、サラダなどにして食べるのが通例であるが、乾燥したものをお茶として飲用することも行われ、すでに、商品化されたものまでもあるそうだ?
明日葉の胡麻和えは美味しいね?
伊豆諸島の名物と言えば明日葉と「く〇や」
ヒント…(人によっては非常に嫌な物、臭い・食べ物・干物)
さて、丸の中にはどんな字が入るのでしょうか?

(雲と富士山 1/24午前11時半:富士川河川敷に久しぶりに降りた。河川敷には土手の道ぐらいの立派な道路が舗装され多くの人たちに利用されている。その河川敷の運動場から撮影した。今日の一押しと言うところだろうか?)
つづく
© Rakuten Group, Inc.