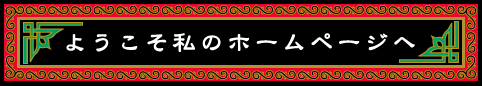セリ(芹)黄疸、解熱、、冷え性、月経痛
古来、春の七草の筆頭に数えられた香り高い野草だが、旬の時期には摘み取ったものが「野芹」または「田芹」の名で店頭を飾る一方、近年は栽培した背丈の高いものを「水芹」と呼んで春の食卓を彩るようになった。
「野芹」といって、土中の節から出る長い根を賞味する地方もある。
特有の香りはミリスチン、カンフェンなどの精油成分によるもので、発汗、解毒作用があり、病後の内熱(体温は平熱でも内臓諸器官が熱っぽい状態にあること)を取るのに有効だとされる。
また、健胃効果もあり、その香りにあずかって食欲が増進する。
微量成分による薬効としては、ほかに血圧を下げ、血の道を通し、酒毒を消し、黄疸にも効用があるといわれており、
これには茹でたものを食べてもよいが、新鮮なセリをすり鉢ですりつぶし、水を加えて裏漉しした汁を一煮他立ちさせて飲む。
また、陰干しにしたものを煎じるのもよい。
栄養的には生100gにつきカロチン1300ug(ビタミンA効力720IU)を数え、粘膜や内臓の細胞強化に役立つ。
コレステロールや中性脂肪を抑制するビタミンB2も0.13ミリグラムと、キャベツの約3倍も含んでいる。
そのほかB1・C・D・葉酸や、ミネラルも豊富に含むアルカリ性食品である。
© Rakuten Group, Inc.