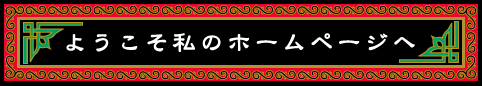緑茶 耐久力や記憶力を増す効果
茶いな茶イナの不思議パワー
*緑茶
茶の始まりは薬用であった。古くは毒消しの作用があると言われてきた。
いまでも「薬を飲むときは、茶湯で飲まないように」と注意される時がある。
茶に含まれる成分作用で薬の効果を消してしまうのを恐れてのことだが、
造血剤に含まれる鉄分を、不溶性にして効力を減ずるという点から見れば、的を得た言葉だろう。
茶は中国から伝わったもので、日本における茶の栽培は、仏僧の栄西禅師が鎌倉時代(1191年)に茶種を持ち帰ったことに始まる。
以来日本独自の喫茶法が確立された。
100%無発酵の緑茶ができたのは江戸時代になってからで、一般庶民にも茶の湯が広まり、「日曜茶飯事」の言葉が生まれた。
緑茶は茶葉の発酵を止めるように工夫したことである。
ビタミンCも破壊されず、昔は保存できるビタミンcの補給源がなく、茶はその意味で重要な、栄養源とされ、船員、遊牧民などに用いられた。
成分 効能
①1茶の主成分であるカフェインは穏やかな興奮作用があり、耐久力や記憶力を増す効果がある。
②茶の色と渋みを作るカテキン(タンニンの一種)は胃の炎症を治す作用があり、食後のお茶は、その意味で効用がある。
③緑茶の葉緑素や色素類は玉露などの上級茶に多く含まれているが、これには動脈硬化を防ぐ作用がある。
④カリウム、マンガン、ヨード、カルシウムなどの微量ミネラルは血液を弱アルカリ性に保ち、新陳代謝を円滑にする作用を持つ。
渋み成分のカテキンのもつ制ガン性が注目されている。
これは静岡など緑茶生産地にガンの発症が少ない事を指摘した、平出光博士や小国教授らの疫学調査が発端となった。
その後国立遺伝研究所の教授、医師らによって実験的に確認された。
カフェインは大脳、特に大脳皮質から延髄の呼吸・血管・運動中枢などを刺激するとともに、感覚中枢なども、興奮させることがわかっている。
一仕事した後や仕事の最中に茶が欲しくなるのは、脳を刺激して、覚醒作用があり、疲労感を一掃する即効性がある為といえる。
その他に茶葉には、チャタニン、チャステロール、カロチンなどの配糖体が含まれており、下痢、口内炎、扁桃腺炎、酒の悪酔い、口臭などに有効性がある。
近年ごとにそのビタミンCやタンニンなどの効用が見直され、抽出液を飲むだけでなく、粉末を菓子や料理に用いるなど、様々に工夫され、時代に合った健康食品として若い人にも人気を得ている。
つづく
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印
- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 5…
- (2025-11-14 00:00:17)
-
-
-

- ディズニーリゾート大好っき!
- [TDR・USJ] 高速バスに乗っ…
- (2025-11-11 19:21:52)
-
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 堺市 金岡町盆踊り大会 大道町大太…
- (2025-11-14 06:08:46)
-
© Rakuten Group, Inc.