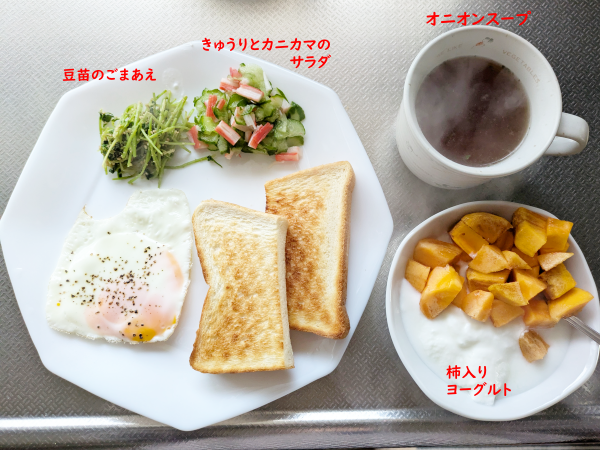(3)
絵画と映像の違いは、画面の中身が動くかどうかにある。その動きは大別してふたつ。映像に登場している人物や物自体の動きとカメラの移動による動きである。当たり前のことではあるが、このふたつは全く意味が違う。映像の中で人物や物が動くのは外部の意思であるのに対し、カメラが動くのは撮影者の意図であるからだ。(もちろん、対象自体が動くにしても、撮影しよとする態度自体は撮影者の意思である。)従ってカメラを動かす場合、フィックスショットを作るのと別の理由が必要になる。
やはり人間の行動から考えてみよう。まずはパンをしてしまう状況を考えてみる。
展望台に登った場合。そこからの風景を見る時、人はきっと首を回し、パンと同じような効果を以って風景を眺めるだろう。普通の視界(実際に見ている範囲)はレンズで言うと35ミリレンズの範囲におよそ当たる。というか、35ミリレンズはそのようにして開発され、定着していったものだ。角度で言うと30度前後だろう。それを越えて広がっいる風景に対して、人は首を動かして全体を見る。会議の席でズラッと並んでいる参加者を見る時も同様だ。自分が会議に出席した時のことを想像してみればいい。間違いなく首を回しているだろう。
目の前の道路を車が走って行く。目で追いかける。やはりパンと同じような効果を以って見ていることが判る。何か注目している対象が動く時、自然に目はそれを追う。人間の行動に照らし合わせてみて納得のいく動きは理解されやすい。
パン、カメラを横に動かす行為は大別してこの2通りである。これと同様な理由があった場合にカメラがパンをする意味がある。
もちろん、もっと様々な状況がある。美しい木材のアップを横にパンしていくことでその流れるような木目を見せることができる。これにしてもフィックスでは入らない、しかも横に動かすしか見せる手だてのないものに対して行なわれている。何気ないパン、などというものは存在しない。対象に対し、カメラが動くためには意思が存在しなければならない。
パンショットを編集する段階でパンの開始前、終了後を残すかどうか、という編集の問題は後のテーマではあるが、それも何のためのパンであるかが大前提で決定されていくべきものである。
チルトはパンと同様の動きを縦方向に行なったものを指す。これは基本的にパンショットの理由を縦方向に考えればよい。高い木を見上げる。谷底を見下ろす。日常的に起こりうる行動に沿った映像である。人間の感覚に訴える力の大きいショットなので、谷底に落ちる感じなど、実際にカメラは止まっていても効果的である。
チルトは人間の生理に深く沿ったショットなので、ズーマーを併用(同時にズームイン/アウトをする場合に限らず、拡大するだけでも)すると、思いがけないほどの特殊な効果が出るが、違和感も同時に大きくなっていく。撮影の基本として、間の日常感覚は意識すべきである。もちろん、それを無視することも構わないが、その時にもきちんと意識して、なぜ日常感覚を無視するのかを考えた上で撮影をしてほしい。
チルトという表現は最近パンの中に組み込まれ、通常パンアップ/ダウンという表現になっている。問題は表現だが、縦の動き、横の動き、更にそれを組み合わせた動き、それぞれにはやはりそうした動きを採るべき理由がなければならない。パンショットに対してよく言われる表現で「舐めるように」という表現がある。こうした表現も意味はあるが、そうした表現だけに頼らずになぜ、そう撮るかを意識してほしい。
ズームは本来、人間の眼では行ない得ない視覚効果である。視界の一部の拡大/縮小は人間には不可能なのだ。人間が何かに注目する時に取るのは、近づくまたは全体を見ようと遠ざかる、という行動である。これはむしろクレーンやドリーを使ったショットが近い。しかし、ズームは似たような効果を持ち、しかもクレーン等に比べ、ずっと撮影しやすい方法である。
ズームインに似た効果というのは日頃から心理的に感じていると言えるだろう。注目しているものがあると、人間の眼はある特定の場所の範囲を見つめて、細かな運動をする。この状態はズームインに対応していると考えられるだろう。
ズームバックはあまり人間の日常では起きないショットであろう。しかし、細部を見ていて、そこから全体を改めて見回す、といった行動がない訳ではない。
ズームショットはカメラが登場し、フィルムが出来た頃、レンズがなかったので存在しなかったショットである。またズームレンズが出来た直後においてもズーマーを動かすと画角が変わり、焦点もずれるため、同時に幾つもの操作をしなければならないことからショットとして定着したのは実はずっと後のことで(「バックフォーカスを合わせる」という表現で行なわれるレンズの調整がズームショットには必要)、クレーンやドリーの方が先に定着していった技術なのだ。やがてレンズが充分な光量を確保できる品質となり、室内照明も充分に強くなったところで今までにないショットとしてズームが登場した。
最初は違和感のあるショットであったはずだ。それが徐々に見とめられ、最初は特殊なショットとして、やがて意味付けのあるショットとして認められたのであろう。
ズームインは注目しているところを拡大して見せていくショットである。よりその細部が見えてきて、他の物が消えて行く。注目している対象をもっとも判りやすく見せることができるため、安易に使われているケースが多いことも確かだ。
何かを発見した時に素早くズームインする。相当熟練したカメラマンでない限り、あのクイックズームインと普段呼ばれているショットは使うべきではない。本当にある対象を発見した際の緊張を必要とする場合はそれはショットとしての意味を持つだろう。しかし、たいていの場合はその後でピントを修正しているし、ショットとして認めようがない。使われている理由として、かっこいい、などと言う制作者がいるが、それは正しいショットの使用ではない。むしろ、ルーズショットの後にカット編集でアップを付けた方が無駄がないのだ。
注目している対象に接近していく感覚を持たせるため、ズームインには緊張感がある。こうしたショットによる心理的な意味合いも活かしていくべきであろう。もちろん、そこに映っているものによって、感情は様々に動くもので一概に述べる訳にはいかない。
ピッチャーがボールを投げるのに時間をかけている。緊張感がある。こうした時にピッチャーマウンドのルーズショットからゆっくりズームインをする。その途中でカットを分け、バッタータイトショットでフィックスで映し、再びピッチャーのズームインに戻し、上半身で納める。こうしたすでに古典的とも思われるショットは充分に投手の心理を表現している。ここでズームバックを勧める人はいないだろう。
ズームバックに至ってはほとんど意味のないショットが多い。細部を確認して改めて全体を見る、という作業はどういう時に行なわれるかを考えてみるといい。普段、人間の興味は細部へと向かって進んで行く。ならば、注目するものにズームインしていくのが生理的に正しい。すべてに渡って同じ結論がついて行くが、なぜ、そういう動き求めるのかを誰よりもまず撮影者がきちんと理解していなければならない。全体を見せる、関係を見せて行く、そういう意図で撮影されるショットだが、なぜ、そこでズームバックでなければならないのかをきちんと考えるべきであろう。
ピッチャーがボールを投げようとしている。その瞬間にカメラが若干ズームバック。この場合、間違いなく、ピッチャーの周辺で重大な動きがあったことになる。当然、1塁ランナーが盗塁を目指すなどの動きがある。これは判りやすい例だが、こうしたショットごとの理由が必要である。
もちろん、こうした動きを伴うシットは絡み合っている。必要に応じてはズームインしながらのパンショットも存在する。普段は決して用いないL字型のパンもある。すべて必要に応じて作られるショットだ。なぜ、そういうショットにするのか、きちんと考えて撮影することが肝心なのだ。後になって「絵がない」と言うのも言われるのもいい思いはしない。なぜその場でそのショットを撮ったのか、また撮らなかったのかを撮影者が納得している、しかも撮りこぼしはない、というのが撮影の理想であろう。誰しも怠る気はないにしても、なかなか実行は難しい。しかし撮影には最低でもそのテープの長さ分の実時間が存在している。カメラが記録している間はそれに集中する。それが撮影者の大前提であるとしたら、これは決して難しい注文ではないはずだ。
「絵がない」という事態を避ける、という低い目標のためにも、なぜその場所からそういうショットを撮るのか、という疑問を常に持ち続けることがいいショットを撮る秘訣であると思う。いい映像は必要不可欠なショットのみで成り立っている。それを実践で目指すことだ。
© Rakuten Group, Inc.