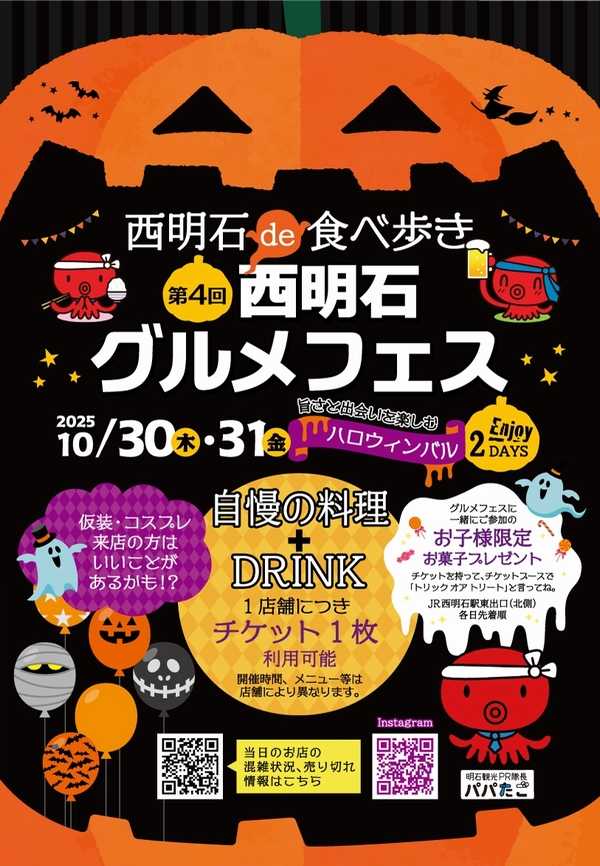ぱち
市ヶ谷にある日本シネアーツ社です。看板のレトロな文字がすでに効いています。製作営業部長重田敏夫さんが待っていてくれました。営業部に入ると壁には「大入袋」がたくさん!
「配給会社の方がね、置いていってくれるんですよ、成績がいいとね」
映画のポスターも沢山貼ってあります。
「うちは単館上映とか映画祭とかの字幕製作も引き受けてるんです。これが大変ですよ。この間もインド映画。ぜんぜん本(台本)が来なくてね・・・
で、本が来たら翻訳が時間かかってね・・・ほら、英語なんかだとプロの翻訳者がいるじゃないですか、沢山。いいんですけどね。インドだともう大変」
そりゃあそうだ、インド映画の翻訳だけで商売になるわけじゃないもん。どうも重田さんは見せる前に一通りの説明がしたいらしい。
「そうそう、昔の映画の再上映だって、こりゃ大変なんだ。あれ毎回字幕違うの気がつきました?」
気がつく訳ないでしょう・・・。
「配給先が変わるから、たいていは毎回やり直しですよ。昔の本があればそれだけ楽だなぁって、一応探すんですよ。取ってあるのは稀ですね。ただ原稿があればいいって話じゃないですから」
実際の作業に入る前に必要なものは
1)オリジナルの本、セリフ番号入り
2)翻訳原稿、セリフ
3)フィルム
これだけそろっていないと作業はできません。配給会社が字幕を入れてる訳じゃありませんので、資料は多くの場合散逸してしまい、しかも配給先が代ったら他人の面倒を見る理由もない訳で・・・。で、結局は毎回翻訳起こしからやることになるそうです。
さて、いよいよ本物の・・・本物のフィルムに作業します。スポッティングという作業です。部屋の中には手回しでフィルム1巻をぐるぐるやりながら
見ている人々・・・手には赤の鉛筆。(デルマ、とTV業界が呼ぶやつですね。)フィルムのコマを見、ヘッドホンで音を聞きながら、対応したセリフ番号を字幕の打ち始めと終わりにマークを入れます。これって本当に映画館で上映されるポジフィルムです。書き込んでいいんですか?と伺うと
「あとで全部洗うんです」
・・・そうか、フィルムって洗えるんだ、と感動。
ここでしばし考えてしまいました。映画館の数だけ同時平行で何本もやるんでしょうか?
「場合によりますが、それを勧めますね。字幕の切れが違うんですよ。
1本字幕入れて、それのネガを作って、そこからポジを沢山作るってこともできますけどね。だからロードショーで一度に山ほど作る時にはレーザーですよ。あれなら1本作ってネガからポジを沢山作ればいいんで。でもね、タイプ式はきらめきが違いますからね。読みやすいんですよ。タイプ式は」
数本であれば同時平行で作るほうが早いようでした。
同時に別のところで翻訳原稿がいつもお世話になっているあの文字で書かれています。すべて手書き。1本の映画で500枚から1500枚(2時間で)という幅はありますがすべて手で書いていきます。文字は適度に省略され、また四角く抜けてしまうところには必ず穴を空けておきます。そうしないと最後の作業でフィルムの色が四角く抜けてしまうので。
字幕の文字にはだから個性があって、重田さんはベテランの文字は誰の字か判るそうです。書かれたカード(タイトルカードと呼びます。英語では字幕のことをすべてタイトルと呼ぶので。)は・・・写真のLサイズよりもうちょっと大きいくらい。これが番号通りに重ねられています。
このタイトルカードを製版するのが次の作業。重田さんの案内で地下の作業室へ。実際の作業を見せてもらいました。まずタイトルカードをセリフ番号順に綺麗に並べます。縦横10枚ずつくらいを丁寧に並べて、上から透明なフィルムをかけてしっかりと固定します。
作業している方と一緒に、はい、みなさん息を止めて・・・その板を垂直に立て、その向うを見れば、おおカメラです。う~ん巨大だ!
このカメラのフィルムはやはり写真のLサイズ強の大きさ。これでピントをしっかり取って・・・で、ここで私はようやく気が付きました。そう、写真を撮るから地下室だったと。
写真を撮るとネガを現像します。タイトルカードが1センチくらいに縮んで見えます。これを使って、亜鉛板をはんこ状にします。
さて、この次が実はメインイベント。このはんこ状の物体を縦横正確に切らねばなりません! これがずれると字幕の文字が斜めになってしまいます。(時々ありますよね。)
はい、みなさん、もう一度息を止めて・・・パン! パン! 勢いよくバシバシと作業。そしてタイトルカードのように番号順に並べます。この小さな亜鉛板を「パチ」と言います。
いよいよ最終行程です。赤鉛筆で印の入ったフィルムとパチが「パチ打ち職人」に渡ります。
「この小さい板をパチと読んでるんですよ。音聞えるでしょ、作業の。あの音からパチと呼ばれるようになったんです」
重田さんは私がのめり込んでるの見て結構楽しんでいる。
「去年、久しぶりに求人出したんですよ。そしたら四大出のね、男の子が受けにきちゃって・・・いや驚きましたね。君みたいな子のやる仕事じゃないと思うよ、って言ったんですけど映画に関わる仕事してみたくて、職場見て、ああこれは素晴らしい仕事だと改めて思ったって・・・」
こういうケースはままあるようで、字幕の文字書きをしている人にも結構いらっしゃるようです。
丁度ミシンの要領でパチ打ちが行なわれます。フィルムが左から右に流れ、下にパチを置く場所があり、フィルムはその上を流れています。これを上から叩く訳です。開始マークから終わりマークまで一気にパチパチパチ・・・と叩きます。前の作業の切る作業がずれてるとこの段階では修復できません。
パチは亜鉛ですから、簡単につぶれてしまいます。
「20回使ったら、もうだめですね。でも今の段階ではタイトルカードのフィルムがあるから、そこからパチ作れば済みます」
使い終わったパチは再びパチの原料になる訳ですね。さて、パチは1フレームごとに打ち込まれます。その状態で少しずつ、文字の入り方が違っています。それが結果として文字をきらきらさせる要因になっています。細い文字でも見えるのにこのきらめきは一役買っています。
レーザーでは均一に入るので、逆に多少線を太くしなければなりません。これが映画の本来の映像を大きく消してしまうので重田さんはお嫌いの様子。私も賛成。
使用済みのパチが入ったポリバケツがありました。中を見ると・・・いろいろ混じっています。
「赤い靴の少年・・・」
「誰だ?」
「私はもう判っているよ」
・・・なんのことやら。不思議な詩の世界。
© Rakuten Group, Inc.