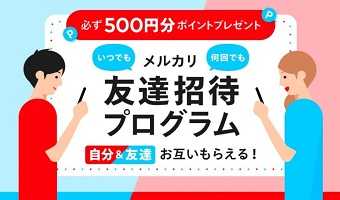炎症
+++ 炎 症
+++
炎症性腸疾患
の「炎症」って何でしょう?
脂質は炎症に深く関わっていました。
注意:私が見たり聞いたりしたことをまとめたものですので、
間違いも多々ありますので、鵜呑みにはしないで下さい。
の「炎症」って何でしょう?
脂質は炎症に深く関わっていました。
注意:私が見たり聞いたりしたことをまとめたものですので、
間違いも多々ありますので、鵜呑みにはしないで下さい。
炎症とは
炎症とは、障害を受けた細胞がこれを取り除いて再生するための反応をいいます。
どうなるかというと、細胞が障害を受けると、これに反応して血管が拡張されます。それにより患部に血液が流れ込みます。すると 発赤 や 発熱 という症状が出ます。その後、血管より血漿や血漿蛋白などが滲出することで腫脹(プクっと腫れることです)が起きます。そして 痛み がやってきます。
あまりに腫脹や痛みが強いと体を動かすことにも支障が出てくるようになります。これを 機能障害 といいます。
ここまでが炎症の初期の段階で、太文字の症状を 「炎症の5徴候」 と呼んだりもしています。
さて、腫脹によって滲みだした体液には障害を受けた細胞をやっつけ、取り除くという作用を持つものがいて、やっつけることに成功すれば膿などにより体外へ排泄され、5徴候も収まり、新しく正常な細胞が再生されもとの健康な状態に戻ります。
しかし、ここで炎症の原因となるものがやっつけられなかったり、次々と体に入り込んでくると組織の損傷や機能不全を起こすようになります。ここまでなると 炎症が慢性化 している状態になります。
たとえば風邪なんかもこのプロセスを経て治るに至ります。大抵が初期の炎症段階で治りますよね。
期間としては4週間以上炎症を起こしている状態から回復しないと慢性化している状態とみなされるようです。慢性胃炎なんてそうですよね。
こういった炎症の症状は「炎症メディエーター」とよばれる物質ができることによって起こります。
次の項からそれを解説していきます。
炎症とは、障害を受けた細胞がこれを取り除いて再生するための反応をいいます。
どうなるかというと、細胞が障害を受けると、これに反応して血管が拡張されます。それにより患部に血液が流れ込みます。すると 発赤 や 発熱 という症状が出ます。その後、血管より血漿や血漿蛋白などが滲出することで腫脹(プクっと腫れることです)が起きます。そして 痛み がやってきます。
あまりに腫脹や痛みが強いと体を動かすことにも支障が出てくるようになります。これを 機能障害 といいます。
ここまでが炎症の初期の段階で、太文字の症状を 「炎症の5徴候」 と呼んだりもしています。
さて、腫脹によって滲みだした体液には障害を受けた細胞をやっつけ、取り除くという作用を持つものがいて、やっつけることに成功すれば膿などにより体外へ排泄され、5徴候も収まり、新しく正常な細胞が再生されもとの健康な状態に戻ります。
しかし、ここで炎症の原因となるものがやっつけられなかったり、次々と体に入り込んでくると組織の損傷や機能不全を起こすようになります。ここまでなると 炎症が慢性化 している状態になります。
たとえば風邪なんかもこのプロセスを経て治るに至ります。大抵が初期の炎症段階で治りますよね。
期間としては4週間以上炎症を起こしている状態から回復しないと慢性化している状態とみなされるようです。慢性胃炎なんてそうですよね。
こういった炎症の症状は「炎症メディエーター」とよばれる物質ができることによって起こります。
次の項からそれを解説していきます。
炎症メディエーターの色々
表にしてみました。
=炎症メディエーター=
脂質 のページでも出てきたエイコサノイドがちらほらあるかとおもいます。
表にしてみました。
| メディエーター | 産生部位 | 徴 候 | 機 能 |
|---|---|---|---|
|
ヒスタミン
|
マスト細胞 | 発赤、熱感 腫脹 |
血管拡張 血管透過性亢進 平滑筋収縮(気管支収縮、腸管収縮) 胃酸分泌促進 |
|
セロトニン
|
マスト細胞 血小板 |
発赤、熱感 腫脹 |
発痛 血管収縮 血管透過性亢進 血小板凝集 消化管運動亢進 |
|
ブラジキニン
|
血漿 | 発赤、熱感 発痛 腫脹 |
疼痛 血管拡張 血管透過性亢進 平滑筋収縮(気管支収縮、腸管収縮) |
|
PGI2
|
血管内皮細胞 | 発赤、熱感 発痛増強 |
血小板凝集抑制 血管拡張 気管支弛緩 痛みの増強 |
|
PGE2
|
マスト細胞 マクロファージ 腎・胃・肺 |
発赤、熱感 発痛増強 腫脹 発熱 |
痛みの増強 腸管蠕動促進 胃粘膜保護 免疫抑制 血管透過性亢進 血管拡張 |
|
PGD2
|
マスト細胞 マクロファージ 白血球 |
発赤 腫脹 催眠 |
血管拡張 血管透過性亢進 気管支収縮 粘液分泌亢進 Tリンパ球・好酸球遊走 |
|
LTB4
|
マスト細胞 マクロファージ 白血球 |
発痛 膿 |
白血球走化性活性化 気管支収縮 |
|
LTC4
|
マスト細胞 マクロファージ 白血球 |
腫脹 | アナフィラキシー誘発 気管支収縮 血管拡張 血管透過性亢進 |
脂質 のページでも出てきたエイコサノイドがちらほらあるかとおもいます。
炎症と炎症メディエーター
「炎症とは」のところで簡単に炎症の流れをお話しましたが、炎症メディエーターが炎症にどのように関わっているのかを詳しく説明したいと思います。
=PGE2=
炎症メディエーターの中でもPGE2は特に重要な役割を果たしているとされています。
*痛み
PGE2はそれ自体ではあまり発痛作用はないのですが、炎症部位で産生されると知覚神経を過敏にさせてブラジキニンの発痛作用を増強します。更に炎症が長引くと脊髄で産生されるようになり、今度は中枢神経を刺激して更に痛みを感じさせるようにします。
*発熱
脳の視床下部と呼ばれるところにある体温調節中枢に働きかけて体温のセットポイントをあげるよう働きます。いわゆる「熱が出る」状態となります。
体温調節中枢は体温を一定の温度(セットポイント)に保つよう体にいろんな指令を出しています。たとえば寒ければ体が震え、暑ければ汗をかく、といった感じです。炎症時にPGE2によりセットポイントが高く設定されると体温がセットポイントまで上昇するまでは「悪寒」という形で寒さを感じ震えることで体温を上昇させようとします。
このセットポイントは炎症の度合いが強いほどPGE2がたくさん産生されるので高くなるようです。
体温が上がり、炎症の第2段階を経てPGE2が作られなくなるとセットポイントは通常に戻り(平熱)、今度は体温を下げるよう調整されます
。
「炎症とは」のところで簡単に炎症の流れをお話しましたが、炎症メディエーターが炎症にどのように関わっているのかを詳しく説明したいと思います。
| 第1段階 |
|---|
| まず ヒスタミン
がマスト細胞より放出されます。 血小板からは セロトニン も放出されます。 するとどうなるかというと、 セロトニンの血管収縮作用により一旦は血管は収縮しますが、ヒスタミンの強力な血管拡張作用により血流が増加します。 それにより 発赤 や 発熱 を生じさせます。 また、血管透過性亢進作用により血管に「スキマ」を生じさせ、血液中の血漿が患部に滲みだしてきます。この血漿より ブラジキニン が産生されます。 更に血管内皮細胞より PGI2 が、マスト細胞より PGE2 が産生されます。 ブラジキニンは 痛み を感じさせる物質で、ヒスタミン・セロトニンと共に血管透過性を更に亢進させます。 PGI2、PGE2はブラジキニンの発痛作用を増強させる作用を持ち、炎症が進むにつれて痛みが増してくるのは、これらメディエーターがたくさん産生されているからなのです。 また、ヒスタミンの放出と共に PGD2 と LTC4 が産生されます。 そしてほとんどのメディエーターが持っている血管透過性亢進作用と LTB4 の持つ白血球走化性活性化により、血漿だけでなく白血球までもが滲み出していきます。 この状態が 腫脹 (腫れ)です。 ヒスタミンにはプロスタグランジン(E、I2、D2)を抹消血管から遊離させる作用を持ち、また ブラジキニンにはプロスタグランジンを産生させる酵素(COX)を活性化させることによりプロスタグランジンの産生を促進させます。 ブラジキニンにはヒスタミンを遊離させる作用もあるため、次々とメディエーターが産生されることになります。 |
| 第2段階 |
| この段階になると、炎症反応が起こった要因を白血球などの免疫細胞が処理・攻撃します。 ここの辺りになると、炎症というよりも免疫反応になると思います。 また勉強したら別のページにまとめますが、メディエーターの働きだけ少し。 この段階では PGE2 はマクロファージより作られます。ここで産生されるPGE2は第1段階は逆に炎症を抑えるよう働きます。 具体的には免疫に関わるインターフェロンの産生や炎症を更新させるヒスタミンやLTの産生を抑制します。またステロイドホルモンの産生を増加させるため、炎症を引き起こす物質の産生を抑制して免疫に関わる物質の産生を促進させて炎症を鎮めるよう働きます。 |
| 第3段階 |
| 炎症の原因となるものがなくなると、そのスキマに肉芽細胞と呼ばれる組織を再生させるための増殖細胞が活発に働き、隙間を埋めていきます。 その際に増殖の元になる栄養や、排泄物を運ぶための血管を作ります。 この状態の組織を肉芽組織といいます。 傷口が治るにしたがってピンク色の少し盛り上がったお肉になっていくのを経験された方は多いと思います。アレが肉芽細胞なのです。 患部が元の健康な状態に戻れるようになると肉芽細胞の血管は次第に後退し、本来の組織に取って代わられます。 こうして炎症によって傷つけられた組織は修復されていくのです。 |
=PGE2=
炎症メディエーターの中でもPGE2は特に重要な役割を果たしているとされています。
*痛み
PGE2はそれ自体ではあまり発痛作用はないのですが、炎症部位で産生されると知覚神経を過敏にさせてブラジキニンの発痛作用を増強します。更に炎症が長引くと脊髄で産生されるようになり、今度は中枢神経を刺激して更に痛みを感じさせるようにします。
*発熱
脳の視床下部と呼ばれるところにある体温調節中枢に働きかけて体温のセットポイントをあげるよう働きます。いわゆる「熱が出る」状態となります。
体温調節中枢は体温を一定の温度(セットポイント)に保つよう体にいろんな指令を出しています。たとえば寒ければ体が震え、暑ければ汗をかく、といった感じです。炎症時にPGE2によりセットポイントが高く設定されると体温がセットポイントまで上昇するまでは「悪寒」という形で寒さを感じ震えることで体温を上昇させようとします。
このセットポイントは炎症の度合いが強いほどPGE2がたくさん産生されるので高くなるようです。
体温が上がり、炎症の第2段階を経てPGE2が作られなくなるとセットポイントは通常に戻り(平熱)、今度は体温を下げるよう調整されます
。
抗炎症とは
炎症が起こったときに炎症を鎮めるためにお薬を塗ったり、飲んだりします。
このお薬にはもちろん炎症を鎮めるための成分が入っているから効くのですが、どのような形で効くのでしょうか。
シクロオキシゲナーゼ(COX)
アラキドン酸よりプロスタグランジン(PG)・トロンボキサン(TX)・ロイコトリエン(LT)が作られることは 脂質 のページでお話しましたが、それはシクロオキシゲナーゼと呼ばれる酵素によって作り出されます。
ただLTだけは少し違ってリポギシゲナーゼ(LOX)と呼ばれる酵素から作り出されるので、ここではLTのことは抜きにします。
この酵素によってアラキドン酸からまずはPGH2が作られ、その後PGE2・PGI2・PGD2・TXA2などが作られます。
ということは、この酵素さえなければPGが作られることもなく、それに伴う痛みなども無くすることができます。
NSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)はこの考え方の基で研究・開発されてきました。
NSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)
COXの活性を阻害することでPGとTXが産生されるのを防ぎ、結果炎症を鎮める働きをするお薬です。
ここでのポイントはCOXを作らないようにするのではなく、 COXが働かないようにさせている ことです。
有名なものにアスピリンやインドメタシンなどがあります。
名前が違うだけに成分も違います。
効き方や副作用など、少しご紹介します。
炎症が起こったときに炎症を鎮めるためにお薬を塗ったり、飲んだりします。
このお薬にはもちろん炎症を鎮めるための成分が入っているから効くのですが、どのような形で効くのでしょうか。
シクロオキシゲナーゼ(COX)
アラキドン酸よりプロスタグランジン(PG)・トロンボキサン(TX)・ロイコトリエン(LT)が作られることは 脂質 のページでお話しましたが、それはシクロオキシゲナーゼと呼ばれる酵素によって作り出されます。
ただLTだけは少し違ってリポギシゲナーゼ(LOX)と呼ばれる酵素から作り出されるので、ここではLTのことは抜きにします。
この酵素によってアラキドン酸からまずはPGH2が作られ、その後PGE2・PGI2・PGD2・TXA2などが作られます。
ということは、この酵素さえなければPGが作られることもなく、それに伴う痛みなども無くすることができます。
NSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)はこの考え方の基で研究・開発されてきました。
NSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)
COXの活性を阻害することでPGとTXが産生されるのを防ぎ、結果炎症を鎮める働きをするお薬です。
ここでのポイントはCOXを作らないようにするのではなく、 COXが働かないようにさせている ことです。
有名なものにアスピリンやインドメタシンなどがあります。
名前が違うだけに成分も違います。
効き方や副作用など、少しご紹介します。
薬
薬効
副作用
アスピリン
解熱・鎮痛・抗炎症
血小板凝集阻害
血小板凝集阻害
胃腸障害・腎肝障害・呼吸器障害・難聴
サリチル酸系の酸性の抗炎症薬。
全てのNSAIDsに共通の副作用として胃腸障害がありますが、これはCOXの活性を阻害されることにより、PGE2の産生が阻害され、その作用にある胃腸粘膜保護の働きが悪くなるために起こります。
また、気管支喘息の素因を持っている人がNSAIDsを服用すると発作が誘発される「アスピリン喘息」を起こすことがあります。これはNSAIDsの中でも歴史が古く、安価なため広く使われていたために名づけられたのでしょう。
一般的な解熱鎮痛剤として広く使われていて、少量の服用で血小板凝集阻害作用があるので、心筋梗塞や脳梗塞などの予防薬としても使われています。
全てのNSAIDsに共通の副作用として胃腸障害がありますが、これはCOXの活性を阻害されることにより、PGE2の産生が阻害され、その作用にある胃腸粘膜保護の働きが悪くなるために起こります。
また、気管支喘息の素因を持っている人がNSAIDsを服用すると発作が誘発される「アスピリン喘息」を起こすことがあります。これはNSAIDsの中でも歴史が古く、安価なため広く使われていたために名づけられたのでしょう。
一般的な解熱鎮痛剤として広く使われていて、少量の服用で血小板凝集阻害作用があるので、心筋梗塞や脳梗塞などの予防薬としても使われています。
インドメタシン
解熱・鎮痛・抗炎症
血小板凝集阻害
血小板凝集阻害
胃腸障害・腎肝障害・呼吸器障害・目眩・頭痛
インドール酢酸誘導体の酸性の抗炎症薬で、COXの阻害作用はアスピリンの20倍と強い。
そのため副作用も強く、日常的に服用する薬としてはあまり適しません。
副作用を起こしにくくさせるためにシップ剤や座薬などに配合して使います。
関節リウマチ・腰痛などによく処方されます。
そのため副作用も強く、日常的に服用する薬としてはあまり適しません。
副作用を起こしにくくさせるためにシップ剤や座薬などに配合して使います。
関節リウマチ・腰痛などによく処方されます。
イブプロフェン
解熱・鎮痛・抗炎症
血小板凝集阻害
血小板凝集阻害
胃腸障害・腎肝障害・呼吸器障害
プロピオン酸系の酸性の抗炎症薬。
抗炎症作用はインドメタシンよりも弱いですが、副作用が穏やかなため代替薬としてよく使われます。
抗炎症作用はインドメタシンよりも弱いですが、副作用が穏やかなため代替薬としてよく使われます。
アセトアミノフェン
解熱・鎮痛
胃腸障害・腎肝障害・呼吸器障害
非ピリン系の解熱鎮痛薬で、解熱・鎮痛作用は強いけれど、COX阻害作用は弱いので、NSAIDsでもちょっと変わっています。
アスピリンなどが使えない人に対して使われたりします。
アスピリンなどが使えない人に対して使われたりします。
© Rakuten Group, Inc.