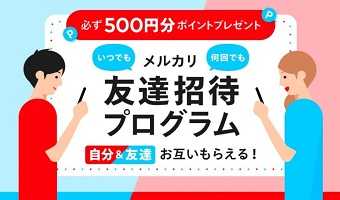血小板のハナシ 2
+++ 血小板のハナシ 2 +++
はじめに
以降の説明はヒトの血液に関する本・サイトをまとめたものです。
同じ哺乳類としてほぼ同じ働きをするものとして記載していますがヒトと犬と違う部分もあると思います。
また素人ですので理解度の不足等により事実と異なる記述もあると思います。
そういったことをご了解の上ご覧下さい。
血管内で血栓ができないワケ

血小板と血管 posted by (C)くりぽん
正常で健康な血管と血液でいる限りは血管内に血栓が出来ることはありません。
そのしくみは・・

血小板と血管 posted by (C)くりぽん
血小板の表面は不活性状態では糖蛋白質に覆われています。通常の血液内でのphでは大抵の糖蛋白質は負に荷電しているため血小板も負に荷電していると考えられます。
一方血管における内膜とは血管内皮細胞のことなんですが、こちらも陰性荷電を帯びています。
お互い負に荷電している為に反発し合い、結合することはありません。
『 かさぶたの出来るまで(概要) 』でも説明しましたが、血栓が出来る第一段階は血管外膜にあるコラーゲン繊維と血小板との粘着です。内膜である血管内皮細胞が傷つけられない限り外膜と血小板は接触することはありませんから血栓も作られないのです。ですので、健康な血管では血栓が作られることはありません。
しかし、糖尿病や高血圧などにより血管内皮細胞が損傷されやすくなると血栓が作られるリスクが高まります。
そのような場合にでも容易に血栓が出来ないように血管内皮細胞が調整を図っています。
その一つが NO(一酸化窒素) です。
血管内皮細胞から作られるNOには主に 血管拡張作用、血小板凝集抑制作用 があります。
血管が拡張されると言うことは血管壁へかかる圧力が減る(降圧作用)ことになるので血管内皮細胞が損傷されにくくなります。
NOとは別に血管内皮細胞は PGI 2 (プロスタサイクリン) という物質も産生します。
血栓を抑制する物質としてはこちらのほうがメインのようです。
PGI 2 もNOと同じく血管拡張作用、血小板凝集抑制作用があります。
後で説明することになりますが、血栓を作るには血液中に Caイオンの存在が不可欠 となります。PGI 2 はこのCaイオンの濃度を低下させることで血栓が作られれるのを防ぎます。
血管内皮細胞から産生されるNOはPGI 2 合成酵素を活性化させることでPGI 2 の産生を高め、PGI 2 は血管内皮細胞に働きかけることでNOの産生を促します。このような相乗効果( 正のフィードバック )により血栓を出来にくくしています。
血管内皮細胞は、この他にも血液凝固のステージでは ヘパリン様物質・トロンボモジュリン を産生したり、形成された血栓を融解する 線溶 というステージでは t-PA(組織プラスミノゲンアクチベーター) を産生したりして、血栓がどの段階に進んでいてもそれを抑制できる機能を持っています。
もちろん、実際に血管が傷害された際には速やかに血栓を作って止血しないといけないので、血栓形成を促進させる物質を産生するという機能も併せ持っています。
2008年4月17日初稿
血小板の粘着

血小板の粘着 posted by (C)くりぽん
では、いよいよ血栓が出来る仕組みを詳しくお勉強していきたいと思います。

血小板の粘着 posted by (C)くりぽん
※上の図では画像を作りやすいよう外膜は損傷されていないようになっていますが、損傷されていても同様の反応を示すと思ってください。
血管が損傷されると、それまでは接触することの無かった中膜、外膜が血液に触れることになります。
すると外膜に含まれる コラーゲン繊維 に血漿中の蛋白質である フォンビルブランド因子(vWF) が結合します。
更に、血小板の表面は糖蛋白質で覆われているのですが、その中の GPIb/IXという糖蛋白質複合体 と vWFが結合 します。
これを 『粘着』 といい、この粘着により血小板は 活性化 を始めます。
2008年4月21日初稿
血小板の放出

血小板の活性化 posted by (C)くりぽん
粘着により活性化した血小板はそれまでの円盤形から中心を球状に、そして偽足と呼ばれる突起を出してその形状を変えていきます。
※図では黄色を活性化前、ピンクを活性化後として表現しています。

血小板の活性化 posted by (C)くりぽん
血小板の変体を機に、細胞内にある ホスホリパーゼA 2 (PLA 2 ) という、細胞膜を構成するリン脂質を分解する酵素が活性化することでアラキドン酸カスケードが作動して トロンボキサンA 2 (TXA 2 ) が作られます。
TXA 2 には 血管収縮作用 や 血小板の凝集を促進 させる作用があります。
具体的には細胞内Ca 2+ 濃度を上昇させることで密顆粒からの脱顆粒を促します。
密顆粒や密小管系に蓄えられているCa 2+ が放出され、さらに開放小管系と呼ばれる細胞膜に通じる窪みを通して血漿中のCa 2+ を細胞内に取り込み、 細胞内のCa 2+ 濃度が上昇 します。
その結果、密顆粒からは ADP・セロトニン を放出し、α顆粒からは フィブリノーゲン・トロンボスポンジン・血小板第4因子(PF4) などを放出します。
また、細胞内Ca 2+ 濃度が上昇することでPLA 2 が活性化され更にTXA 2 の産生を促進させるのです。
2008年4月23日初稿
血小板の凝集

血小板の凝集 posted by (C)くりぽん
どのような仕組みで凝集が起こるかというと、まず ADP が血小板の凝集を引き起こさせる 凝集惹起物質(アゴニスト) として作用します。
ADP とは、アデノシン二リン酸の略称でアデニン・リボースと2つのリン酸分子から成る物質で、細胞内にあるミトコンドリアでH + を結合させることで ATP(アデノシン三リン酸) というエネルギー源を生成する元となります。
密顆粒から放出されたADPが血小板表面にある受容体に結合すると GPIIb/IIIaという糖蛋白質複合体 が出現してフィブリノーゲンを架橋として血小板同士を結合させます。
これを『凝集』と言い、この結合が重なることで 一次血栓 を形成します。
ここで、前の項で出てきた放出された顆粒についてまだ説明していないものについて説明します。
セロトニン は生理活性アミンの一つで、 血管を収縮させる 働きがあります。更に血小板に作用して 止血に関わる様々な働きを「増強させる」 という働きも持っています。また、ブラジキニンなどの発痛物質の働きを増強させて痛みを起こさせたりもします。
フィブリノーゲン は、血漿中に存在する糖蛋白質ですが、α顆粒からも放出されより多くの血小板と結びつこうとします。
トロンボスポンジン は細胞膜にあるレセプター(受容体)に結びつくことで細胞同士の結びつきを強める細胞接着因子として働きます。
血小板第4因子(PF4) は血小板の凝固を抑制させるアンチトロンビンIIIを活性化させるヘパリンと結びつくことで血液の凝固抑制を阻害します。
そして、 TXA 2 の産生は周りの血小板を活性化させ、上で説明した脱顆粒により放出された物質と共に様々な面から血栓形成に働きかけています。

血小板の凝集 posted by (C)くりぽん
どのような仕組みで凝集が起こるかというと、まず ADP が血小板の凝集を引き起こさせる 凝集惹起物質(アゴニスト) として作用します。
ADP とは、アデノシン二リン酸の略称でアデニン・リボースと2つのリン酸分子から成る物質で、細胞内にあるミトコンドリアでH + を結合させることで ATP(アデノシン三リン酸) というエネルギー源を生成する元となります。
密顆粒から放出されたADPが血小板表面にある受容体に結合すると GPIIb/IIIaという糖蛋白質複合体 が出現してフィブリノーゲンを架橋として血小板同士を結合させます。
これを『凝集』と言い、この結合が重なることで 一次血栓 を形成します。
ここで、前の項で出てきた放出された顆粒についてまだ説明していないものについて説明します。
セロトニン は生理活性アミンの一つで、 血管を収縮させる 働きがあります。更に血小板に作用して 止血に関わる様々な働きを「増強させる」 という働きも持っています。また、ブラジキニンなどの発痛物質の働きを増強させて痛みを起こさせたりもします。
フィブリノーゲン は、血漿中に存在する糖蛋白質ですが、α顆粒からも放出されより多くの血小板と結びつこうとします。
トロンボスポンジン は細胞膜にあるレセプター(受容体)に結びつくことで細胞同士の結びつきを強める細胞接着因子として働きます。
血小板第4因子(PF4) は血小板の凝固を抑制させるアンチトロンビンIIIを活性化させるヘパリンと結びつくことで血液の凝固抑制を阻害します。
そして、 TXA 2 の産生は周りの血小板を活性化させ、上で説明した脱顆粒により放出された物質と共に様々な面から血栓形成に働きかけています。
2008年4月23日初稿
© Rakuten Group, Inc.