中国茶
その名の通り中国を原産地とするお茶の事。
発行度や水色(お茶の色)などから、
緑茶・白茶・黄茶・青茶・紅茶・黒茶・花茶の7種類に分類されるお茶の総称。
<中国茶の種類>
緑茶 (不発酵)
茶葉を全く発酵させずに"釜煎り"させた茶。
気分をすっきりさせ ビタミンCが豊富に含まれている。
ex→西湖龍井
白茶 (弱発酵)
摘み取った葉を 月光浴させて自然乾燥をさせたもの。
主に福建省で作られ生産量が少なく貴重なお茶。
ex→白牡丹
黄茶 (弱・後発酵)
黄茶は歴史が古く 皇帝に献上していたお茶とされている。
中国各地で作られている割には入手が困難だと言われるお茶。
ex→君山銀針
青茶 (半発酵)
酸化酵素の力を借り 茶樹の成分を自己分解させる事で芳香成分を引き出している
基本的に 血液中の中性脂肪などを減少させると言われている。
ex→烏龍茶・鉄観音
紅茶 (全発酵)
紅茶のルーツは 実は中国から!!ご存じでしたか?
最近は インドやスリランカでの生産が有名だが 中国紅茶は 葉の形が
残っている方が高級とされている。
ex→正山小種
黒茶 (後発酵)
黒茶は 発酵が進むと味にまろやかさが加わり香りにも丸みが出て、
程良い感じになる。
ex→プーアール茶
花茶
茶葉に花の香りを吸着させた物と、
花そのものが入っていてエキスも一緒に飲む物の 2つがある。
花茶には アロマ効果があるといわれている。
ex→菊花茶、茉莉花茶、薔薇茶
<お茶の飲み方>
○用意するもの
1:茶壺(チャフー→中国式の小ぶりの急須)orは急須
2:茶杯(チャハイ→中国の小さな湯のみ茶碗)orは湯飲み茶碗or盃でも!
3:茶盤(チャバン→捨てたお湯を入れる為の物)orはボウルor鉢などでも!
4:茶巾or布巾 →濡れた時など すぐ使えるよう身近にあると便利。
青茶の淹れ方
1:茶壺に 沸騰したお湯を入れ温め その後 そのお湯を茶杯に入れて
温める。残ったお湯は 茶盤に捨てる。
2:茶葉を 茶壺に入れる。(一人分の目安は3~5g)
その間も茶杯は温めておく。
3:沸騰したお湯(大体70度~95度くらい)を注ぎ 茶葉をさっと荒い流す。
4:洗茶(茶葉を洗う)後 沸騰したお湯を再び注ぎ 蒸らす。
時間の目安は約1分。2煎目からは蒸らし時間を30秒位ずつ延ばしていく。
待っている間に 茶杯のお湯を捨てておこう!
5:お茶の濃さが均一になるよう 注意しながら茶杯につぐ。
茶海(ちゃかい)があると 簡単にお茶の濃さを均一にする事が出来る。
ピッチャーのような形で 茶壺のお茶を一旦そこに全部注いでから、
茶杯につぎ分けていく方法。
黒茶の淹れ方
黒茶は堆積させて細菌を使って醗酵させる。
眠らせておく時間が長ければ長いほど 高級なお茶ということになる。
洗茶は 急須にお湯を入れた後 そのお湯を一度捨て、
二回目からのお茶を楽しんで貰うと良いかと思われる(必ず洗茶を!)
入れ方は 青茶と殆ど変わらず・・。
1:茶壺に 沸騰したお湯を入れ温め その後そのお湯を茶杯に入れて温める。
残ったお湯は 茶盤に捨てる。
2:茶葉を茶壺に入れる(1人分の目安は3~5g程度)
その間も 茶杯は温めておく。
3:沸騰したお湯(95度度以上)を注ぎ 茶葉をさっと荒い流す。
黒茶なので 2回程洗ってもOK。
4:洗茶後 沸騰したお湯を再び注ぎ 蒸らす。
時間の目安 約1分(2煎目からは蒸らし時間を30秒くらいずつ
延ばしていく。)待っている間に 茶杯のお湯を捨てておこう。
5:お茶の濃さが均一になるよう注意しながら茶杯につぐ。
茶海があると 簡単にお茶の濃さを均一にする事が出来る。
ピッチャーのような形で 茶壺のお茶を一旦そこに全部注いでから、
茶杯につぎ分けていく方法。
花茶の淹れ方
花茶は 成分や香りがお湯に溶け出す迄時間がかかるので、
蒸らし時間を若干長めに。
特にジャスミン珠茶は 珠のようなお茶が葉っぱの形に開くまで時間がかかる。
急須などを使わなくても インスタントコーヒーのように、
湯飲みにお茶葉を入れ それに熱い湯を注ぎ 茶葉が下に沈むまで待つと、
出来上がり!
美味しく 手軽なお茶を飲む事が出来る。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-
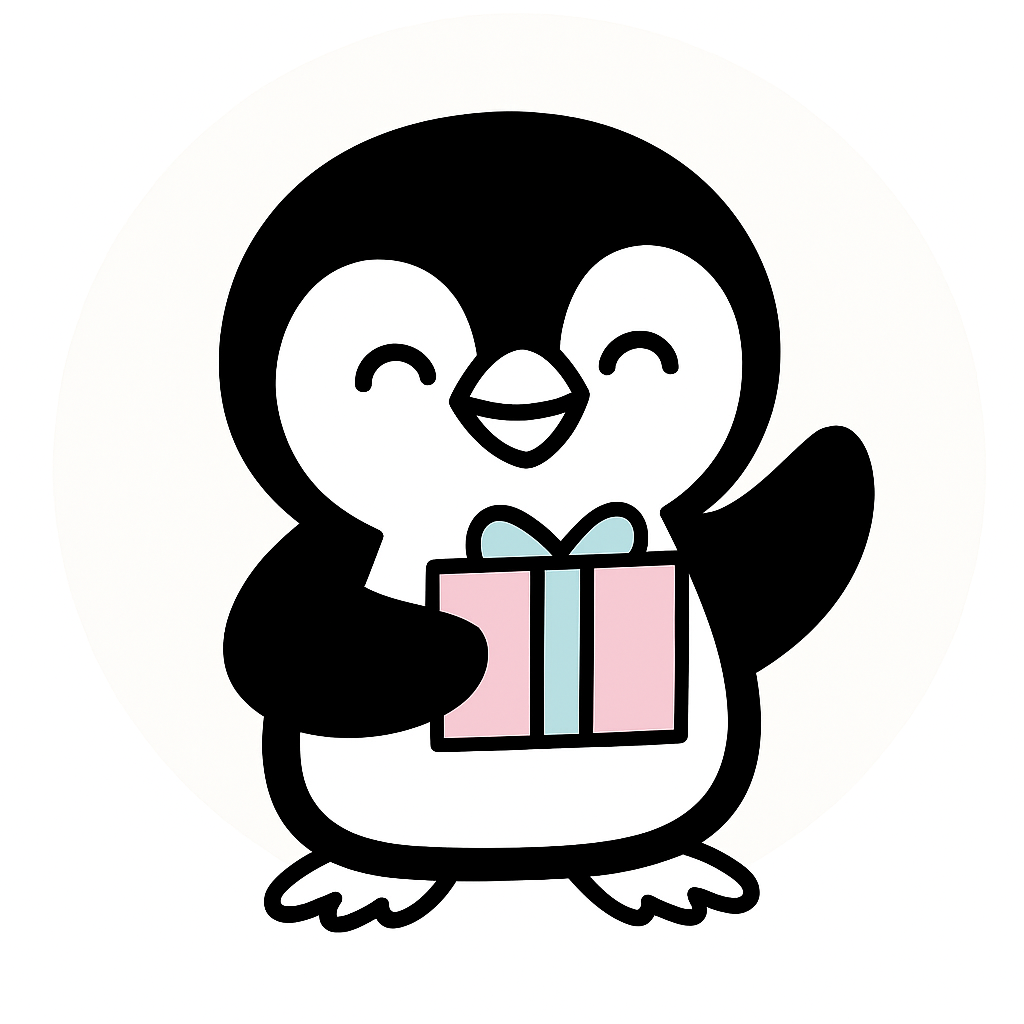
- いま嵐を語ろう♪
- 楽天ブックス予約開始 二宮和也映画…
- (2025-11-21 22:57:54)
-
-
-

- ライブ・コンサート
- 発表会の歌のYouTubeを、声楽家のIさ…
- (2025-11-22 02:17:11)
-
© Rakuten Group, Inc.



