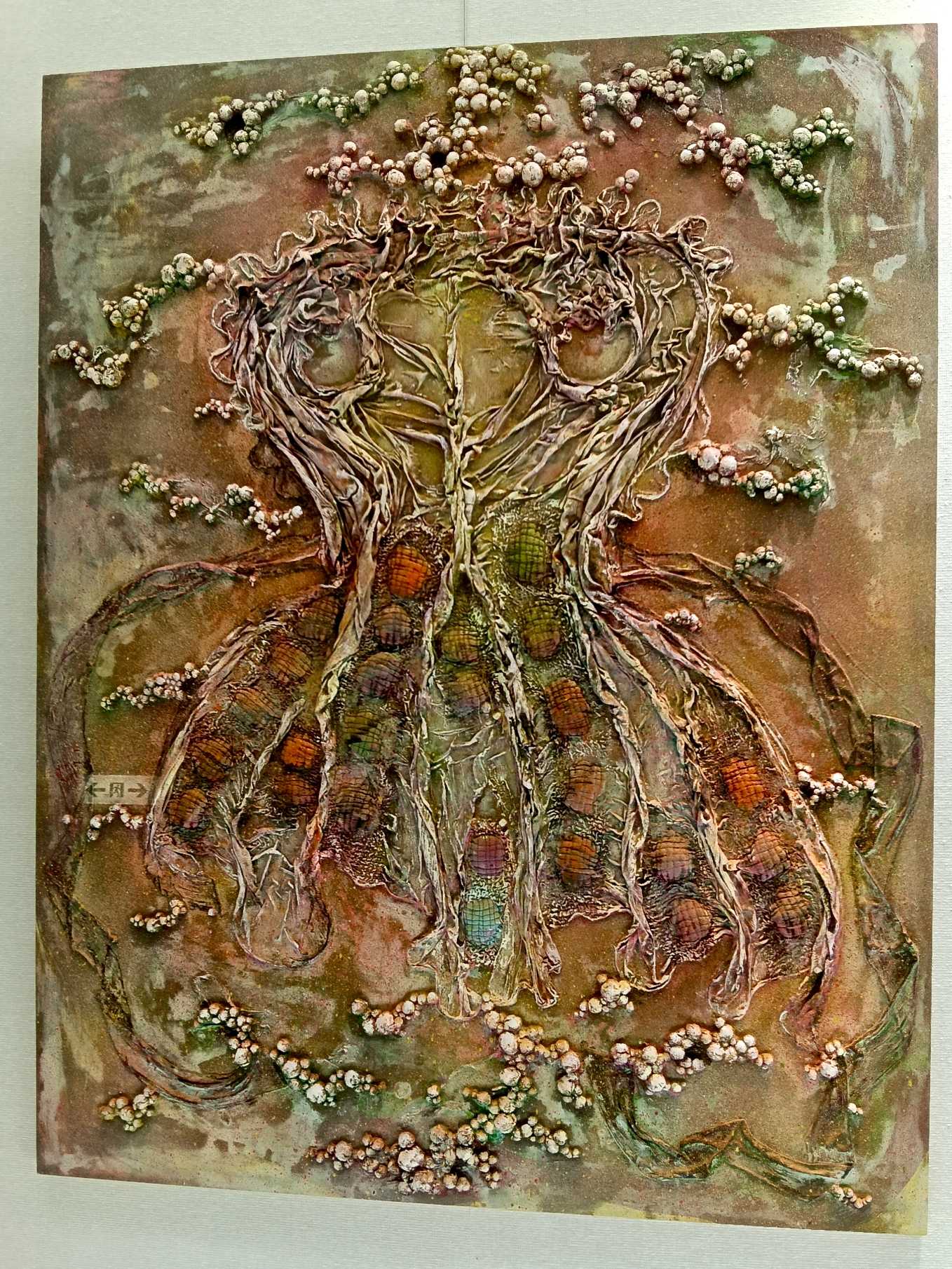せめて
~せめて消えないだけの理由~
「…ところで。零一くんに聞いてみたい事があるんだけど。」
嫌な予感がした。
そして。
大抵の場合に於いて当たるのだ、こう言う時の私の勘と言うやつは。
それでも。
「…なんだ?」
…それでも、だ。
私は逃げる事が出来はしない。そう言う性分が根強い性格をしているのだ。
一種のプライドと言うものなのかも知れないが。
予想通り、目の前でカウンター越しにせっせと…と言うよりは、緩慢でやる気のなさを感じさせる動作でグラスを磨いていた奴こと益田が、ニヤリと意地の悪そうな笑顔でもって勘が当たっている事を確信させる。
「なぁ、零一よぉ…この前…
そうクリスマスにも連れて来た生徒さん、もう連れて来ないのか?」
「…っ…お前には、関係がないだろう。」
「あーれま、取り付く島もないワケね。
でもなぁ、零一。
余裕がないのはみっともないぜ?…せんせぇさんよ?」
「…何がっ、だ。」
つい挑発に乗り掛けて声を荒げそうになり、なんとか押し殺して答えると余計に奴はニヤニヤ笑いを強くする…かと思いきや。
奴にしては、珍しく真面目な表情になっていた。
「ぶっちゃけた話…お前さ、あの子の事好きだろ?」
「彼女は俺の生徒であって、それ以上の何ものでもない。」
「生徒…ね。クソ真面目っつーか、馬鹿正直っつーか、だなぁ、相変わらず。」
やれやれ…と言った風情でこちらから視線を外す益田は、本当に心から呆れている事を体現しながら、誰よりも俺の事を解っていると言っている様で。
「…ま、お前の恋路だし。俺が難癖つけたりすっこともないんだけどな。」
「まったくもって、その通りだな。」
自分でも滑稽だと思う程に反発の意を強くして。
本当は何より続く言葉を必要としていると、解っているクセに虚勢を張ってしまう。
俺と奴は、昔からこう言う関係だったかと思う。
「…本当にお前さ。ハタから見て、余裕ないぜ。ぜんっぜん。」
「………。」
手の中で暖めてしまいかけていたグラスを呷るだけで、私は答えなかった。
解っては、いたけれど。
抱え込んでいてどうにかなる想いだとは、もちろん思ってなどいなかった。
事実、この二年間と半年余り考えてきはしたのだ。
けれども、吐き出したところで何が変わるでもない事も知っていた。
私は、ことこの手の事実問題には弱いのであると確信させられる。
単純な事なのに。
ただ、私は彼女を…愛しているのだと。
それだけの事なのに。
私には、この想いは…邪魔と言う他ない様な、そんなわだかまりと言う認識しかないのだ。
これが、恋だと言うのなら。
私には不必要なものだと言って、出来る事なら、消して欲しかった。
正直…苦しいだけだったから。
叶わない恋だと言うのなら、もう十分ではないのかと。何度、背を向けて歩こうと思った事か。
出来る事ならば…とっくにしているのに。
朝…いつもと変わりのない朝だった。
見た夢に、彼女が出ていた事が、朝から少しばかり心臓には良くない事だとは思ったが。
それすら、今の私にとっては当たり前の事でしかなくなっていた。
昨晩奴の店に飲みに行ったのが悪かったのだろうか。
かんな話をしたから、こんな気分になるのだろうか。
俺は…私は今、彼女に会う事が異常なまでに…そう、通常ならば考え付かない位に、怖かったのだ。
私は、人を好きになる事が強くなる事と結び付くとは思えなかった。
私はたぶん、この事に関しては殊更臆病になるのだろう事は自覚していた。
そして。
叶わない恋の終わりも、同じくして予測している様に思う。
私は臆病だから。何よりもそれを認めているから。
今、私は。相殺し合う願いを抱いているのだろう。
この想いの処理の方法を私は知らなかった。
「あ、氷室先生~!おはようございます!」
パタパタと言う足音で背後から駆け寄って来る人物を、私は内心溜め息を吐きながら振り向くより早く理解していた。
「…おはよう、草薙。」
「はい、おはようです!」
「何度も言わなくて宜しい。挨拶は一回で十分だ。」
憎まれ口に近い様な台詞で返しても、慣れ親しんだ仲とでも言うのか、彼女は「解ってますよぅ。」などと言うだけで、足の長さからくるコンパスの違いも気にせずに私の後を付いてくる。
「それにしても…今日も、冷えますねぇー。」
「…冬だからな、この程度の気温ならば例年通りだ。」
クラスまでの廊下を歩きながら、久々に交わす日常的な会話だと気付く。
私の方から、ある程度気付かれない様に徐々に距離を取り始めていたからだ。実際忙しさに追われていた事もあるのだが。
「そうなんですよねぇ、冬なんですよねぇ…。」
彼女が感慨深そうに呟くのが気になって、ふとそちらを見てしまう。
…解っていたのに。
見つめたり、触れたりしてはいけないのだと。
これ以上、君を好きになってしまうだろうから。
そうしたら、もう…私が私でなくなりそうで。
そんな私の心中には全く気付かない様子で、彼女は手袋を外した手を擦り合わせているところで。
「…んーっ、氷室先生?」
「…なんだ?」
「私、冬って割かし好きなんですけど。
けど、今年はなんだか…」
そこで一旦言葉を切ると、ふと歩く速度を緩める。
「どうした、草薙?」
「なんだか、今年で終わりなんだなって思ったら、寂しくなっちゃって…」
そうだ、もう彼女は第三学年で。あと一か月もしない内に自由登校が始まる。
あと、数か月の関係だった。それが過ぎてしまえば、きっと。
もう会う事もないだろう。
「私が卒業しても、先生は先生ですよね?」
とうとう速度を落とした歩みは、完全に止まってしまい。私も2歩分だけ先に進んだ距離から、彼女を振り向いた。
「…もちろんだ。たとえ君が卒業し、この校の生徒ではなくなったと、しても…
私は、君の教師だ。」
やっと、彼女の瞳を見つめる事が出来て。
これは、偽りのない想いだから。本当に伝えたい事は、他にもあったけれど。
これも、また。ある一つの答えだと感じる事が出来たから。
「だから…いつでも、来なさい。
私は、きっとここに居るだろうから。」
「はいっ、氷室先生っ!」
彼女にこの笑顔を与えられる、その喜びだけで私は十分だから。
だから…。
桜が散ってしまうその時まで。
私を教師としてで構わないから、想っていてくれ。
舞い落ちる桜の花弁を、私は掴む事は叶わないのだから。
カランカラン…
軽いベルの音を響かせながら、私はカウンターの人影に挨拶もせずにその目の前に座った。
「…ジントニック。」
ただ、一言だけで注文に変えると、やれやれと言った仕草で奴が材料を取り出し始める。
その動作を見るでもなく眺めて居ると、透明だがアルコール特有の揺らめきを宿した液体が目の前に出される。
「…オゴリで良いぜ?」
「…そうか。」
何か言い返すべきであるのは、解ってはいたけれど。口を開いたら、何もかも吐き出してしまいそうで。
「無理、すんなよ?
…って、俺が言っても無駄だよな。さぁって、仕事の準備~っと。」
おどけながら立ち去ろうとする、唯一無二の友人に。
「…ありがとう。」
と、ただ一言だけ伝える。
「あ?…そりゃどうも。」
グラスを持つ手が勝手に震えるのが解る。
今の私に出来る事はと言えば。
涙を堪える為に歯を食いしばる事だけだった
「…お前は、よく頑張ったよ。零一。俺には真似出来ねぇなぁ、」
などと言いながら、裏のオフィスルームに退散してくれたのが、何よりのあいつの優しさで。
泣くしかない時は、泣けば良い。そう言っていたのもあいつだった。
出来る事ならば、いつか君が、思い出してくれたなら。
氷室零一と言う、人波外れて不器用な教師が居た事を。
私は、それだけで十分だから。
―・―・―・―・―・―・―・―
言い訳みたいな後書きだったり。
…内容、被ってますね。これと同時にUPしたのと。
冬はコレしか書けませんです、ハイ。正直、私の書ける小説は悲恋が多いです。
いや、それは私がそうだからとかは別の話ですが(汗
でも、やっぱりこの「氷室先生」って言うのは、教師なんですよね。
彼をふったEDも有りだと私は思っています。
「私は…いつでも、君の教師だから。」
© Rakuten Group, Inc.