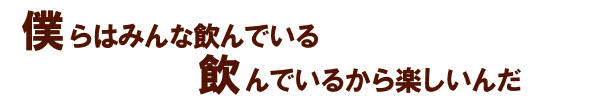全て
| カテゴリ未分類
| □ワイン
| □料理
| □我思う
| □日本酒
| □本格焼酎
| □梅酒・リキュール
| □京築・福岡グルメ
| □食品
| □エコ
| □イベント情報
| 感動
| うらの酒店伝説(4コマ)
カテゴリ: □日本酒
呑切り(のみきり)とは、タンク内で貯蔵中の清酒を呑口(のみぐち:タンク下部の口)を切って(開けて)、健全に貯蔵されているかを分析したり、熟成度合い、味、色の変化を調べたりすることをいいます。
伝統的な酒蔵行事であり、ホタル飛び交う初夏にかけて第1回の呑切りを行なうのが一般的で、この1回目の呑切りのことを「初呑切り」といいます。また、呑を切った酒を片口(カタクチ)という器に入れ、社長や関係者が香りの吟味をします。
タンクの呑口を切って酒が出る瞬間の香りを切り鼻(きりばな)といい、貯蔵してから杜氏が初めて新酒に対面する時でもあります。
杜氏が真剣な目で呑を切った瞬間、香りをかぎ「ヨシ!」の声。
緊張が一瞬和らぎます。お酒も健全です。
呑切りしたお酒は杜氏、蔵人一同が利き酒し、今後の貯蔵、出荷の判断とします。酒造りと同様、貯蔵も重要な管理です。
伝統的な酒蔵行事であり、ホタル飛び交う初夏にかけて第1回の呑切りを行なうのが一般的で、この1回目の呑切りのことを「初呑切り」といいます。また、呑を切った酒を片口(カタクチ)という器に入れ、社長や関係者が香りの吟味をします。
タンクの呑口を切って酒が出る瞬間の香りを切り鼻(きりばな)といい、貯蔵してから杜氏が初めて新酒に対面する時でもあります。
杜氏が真剣な目で呑を切った瞬間、香りをかぎ「ヨシ!」の声。
緊張が一瞬和らぎます。お酒も健全です。
呑切りしたお酒は杜氏、蔵人一同が利き酒し、今後の貯蔵、出荷の判断とします。酒造りと同様、貯蔵も重要な管理です。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[□日本酒] カテゴリの最新記事
-
山の壽 純米吟醸 新酒生 2012.12.16
-
岩の蔵 サーティーン & 東一 Nero 2012.06.29
-
白瀑 夏ノ酒 ver 2 ドキドキ生酒!! 2012.06.24
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.