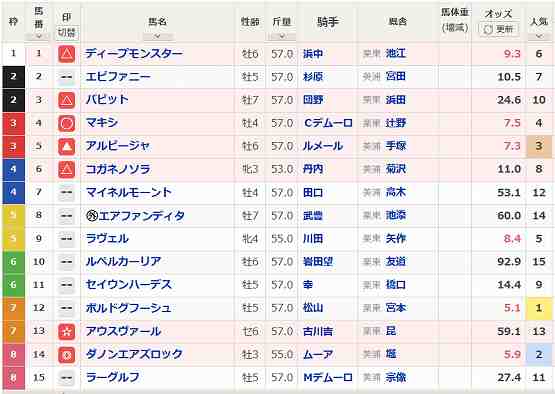第四章 不死鳥はみたび
【神へ】
第四章
不死鳥はみたび
堀田喜三郎は、鶏の声で目を覚ました。薄暗い明かりの中に、時
計の文字盤の夜光塗料がほんのりと黄緑色ににじんでいる。2時1
5分過ぎだ。耳を澄ますと、遠くで犬の鳴く声がする。おおかた、
野良犬でも迷い込んできたのだろう。
すえた臭いのする布団から這いでて、彼は煙草を一服した。円筒
形の缶の蓋を開け、フィルター等という軟弱なものを持たない大人の
煙草・・彼はこの安物の煙草に奇妙なプライドを持っていた・・・・
を無造作にくわえ、ジッポのライターで得意そうに火を着けた。
毒をたくさん含んだ煙を胸いっぱいに吸い込むと、喜三郎はふう
とため息をついた。家業を息子夫婦に譲って隠居してからというも
の、なにか自分がえらく年寄りになってしまったような気がしてし
ょうがなかった。若造りの妻とも、もう一年近く御無沙汰している。
なにか、いまここにいる自分はすでに死人になってしまったかの
ような虚ろな気持ちであった。
尿意を催して便所へ行った。のどが乾いた。老人は、台所の土間
へサンダルをつっかけて行くと、手押し式のポンプをかたこと鳴ら
した。水道はあるのだが、飲み水だけはずっとこれを使っている。
かなけ臭い水道の水は、味をしらんガキが飲むものだと思っていた。
あるいは、老人特有の思いこみかもしれないが。
ぼうっと考えごとをしながらポンプをこいで、いつまでたっても
水が上がってこない事に気がついたのは5分も経った頃だった。老
人は舌打ちしながら、なにか大事な事を忘れているような気がした。
たしか、たしかとても大事な事があるのに、それが何だか思い出
せない。頭の中に白い霧がかかったようになっていて、すぐそこに
ある大事なものが見えない。いや、それはもっともっと遠いところ
にあるのか? そうだ、ずっとずっと昔の事だ。
鳥が鳴いていた。犬は、まだ遠くで吠えている。家の中は静まり
返っている。ねずみの声さえ聞こえない。水道の蛇口から滴るしず
くが、しんとした空間に異様に響いた。これは・・・・これはいつ
かおぼえがある・・なにか、なにかとっても大事な事だった。必死
で思いだそうとする老人の耳に、壁掛けの電池時計の秒針の音だけ
が聞こえてきた。ふん、電気仕掛のくせにうるさいやつだ、まるで
昔の柱時計のような音がするわい・・・柱時計はどうして壊れたん
じゃったかのう・・・・・
なにかが頭の中で突然つながった。老人は、はじかれたように玄
関にとんでいった。靴を履くのももどかしく、たどたどしく庭へ出
ると、隣に見える沼をながめた。月明かりに照らされた沼には、し
かしほとんど水はなかった。浅くなった泥水の中で、魚達がぴちぴ
ちと飛び跳ねていた。もう間違いがない、決心すると老人は家へ戻
って受話器をとった。
指がふるえて何度も掛け直した。
「はい、堀田です・・・」
不機嫌そうに応える息子の声にかまわず、老人は叫んだ。
「おい、祐介、今すぐ公園へ逃げろ!」
「へ?・・・・・・とうさんか、どうしたの?」
「地震じゃ、でかい地震がくるぞ」
「・・・なに寝ぼけてんだよぅ、」
「はやく子供達を連れて避難しろ、はやくせんか!」
「・・・・なにがあったの?」
「おんなじだ、あのときとおんなじなんじゃよ!」
「・・こんな夜中に・・そんなみっともないことできないよ」
「ばかたれ! いのちが第一じゃ」
「いいか、そんな手抜き工事のビルなんか、ちょっと揺れたらひと
たまりもなく崩れるんじゃ」
「救急車も病院も、なんの頼りにもならんのじゃ」
「自分で守るしかないんじゃ」
「はやく、とにかく公園へ逃げろ」
「・・・・・・・・・」
「ええい、はよぅせんか! 子供を、家族を見殺しにするんか!」
父親の、尋常ではない気迫が受話器を通して伝わってきた。先の
震災で両親と兄弟をなくした親父の、悔しさと怒りが、受話器から
真っ赤な炎になって吹き出しているのが見えた。祐介は腹をくくっ
た。近所の笑いものになってもいい、親父の言うとおりにしてみよ
うと。
妻と子供達をたたき起こすと、有無を言わせぬ口調で服に着替え
させた。リュックに水筒と缶詰、インスタントラーメンを詰め込む。
ラジオと懐中電灯も持った。街灯と月明かりに照らされた通りを
横切って、親子4人は小学校の校庭に入った。驚いた事に、そこに
は何組かの先客がいた。
「おお、わかいのに感心なこっちゃ」
町内の老婆が声をかけた。
「わかいもんは、なかなかわしらを信じおらん・・・」
祐介の中で奇妙な確信が育ちつつあった。
「おばあちゃん、どこらが一番あんぜんですか?」
老婆は、頼りにされたのが嬉しいのか、顔をくしゃくしゃにして答
えた。
「そうじゃの、木の根元は地割れもせんし・・・」
真剣にうなづくと、祐介は大きな銀杏の木の根元に家族を連れて陣
取った。
鎖につながれた飼い犬たちの、不安そうな鳴き声が遠くで響いて
いる。ふと見ると、闇の中に光る目がある。猫だ、近所の猫達が1
0匹ほど、じっとうずくまってこちらを見ている。
子供が呼ぶと、猫達はにゃあと鳴いてぞろぞろと寄ってきた。毎
朝、祐介のパジェロのボンネットにうずくまっている「ニャジラ」
が、少しためらったあと膝にのっかってきた。6キロを越す巨体は
思いのほか柔らかく、そして暖かく、祐介は大猫を優しく撫でなが
ら、うとうとと浅い眠りに入った。3時42分であった。
夢の中で、祐介は芦ノ湖の船着き場に立っていた。両親に手を引
かれている。傍らには白いオープンカーがとまっている。ああ、こ
れは新婚旅行なのだなぁと思った。存在しないはずの自分がいるの
に、少しも違和感はない。父は、VANのジャケットを無造作に着
こなしている。母は、渋い光沢のある紺色のタイトスカートに、首
にネッカチーフを巻いている。みずうみから吹いてくる風が、肩ま
である柔らかい髪をときおりふわりとあおる。初秋の柔らかい日差
しが、うすいブラウスの中に母の細い肩をくっきりと浮かばせた。
「祐介、いくわよ!」
母のぴしりとした、しかし優しい声に促されて、祐介は歩いた。列
の先頭には、白鳥の形をした遊覧船が泊まっていた。祐介の視線に
は、それはとてつもなく大きな船であった。ジーゼルのどっくどっ
くという響きとともに、ビルジの排水が吹き出すように流れる。
桟橋をおそるおそる渡りながら、甲板に立った。船はほんの少し
だけ揺れていた。気がつくと、船はみずうみの中央に出ていた。
少し不安になって両親の顔を見上げた。
しかし、どんなに目を凝らしてみても、顔が見えなかった。いや、
顔は見えるのだが、それが両親の顔として認識できないのだ。まる
で色盲検査の模様から意味のある形を探すように、祐介は必死で両
親の顔を認識しようとした。
ふいに、船がぐらりと揺れた。揺れはどんどん大きくなり、船は
木の葉のように湖面を踊る。恐怖にすくんでしゃがみこむ祐介のま
わりには、いつのまにか誰もいなくなっていた。大声で母を、父を
呼ぶのだが、大きな波の立つ湖面にはもうなにも見えない。
・・・・どこかで誰かの悲鳴が聞こえる。・・・だれだ、よくも
まあ、あんなに大きな声がだせるもんだ。うるさい、やめろ、だれ
か、このうるさい悲鳴を止めてやってくれ・・・
ざらりとした冷たい感触が、祐介の喉を襲った。はっと目を覚ま
した祐介は、その悲鳴が自分の口から出ていた事を知った。大地は
ごうごうと揺れている。家族達は・・・無事だ! 妻とふたりの子
供たちは、ネコを抱きしめて街の方を見ている。街は、真っ赤に燃
えていた。何気なく腕時計に目をやる。3時55分だった。
8月15日未明、福井県を襲った大きな地震は、この小さな地方
都市に3度目の崩壊をもたらした。
最初の揺れで、市の中心部にある新栄商店街が壊滅した。権利の
転売によって膨れ上がった地権者のために、遅れに遅れた再開発事
業。とうに耐用年数を過ぎた木造の店舗と老朽化したアーケードは、
まるで紙のように引き裂かれ、マッチ細工のように崩れさった。
寸断された旧式のガス管から漏れたガスに、被覆の硬化して脆く
なった電線が着火するまで、数分とかからなかった。大音響ととも
に数十の店舗が宙に舞い、色とりどりのドレスやマネキンが足羽河
原にまで飛び散った。
市街中心部のビルは、さすがに崩壊を免れた。
崩れたビルのほとんどは、外川知事の時代にぐんぐん延びた建設
会社の手になるものばかりだった。無茶句茶建設と陰口を叩かれる
会社の建てたそれらのビルは、水分と気泡だらけのコンクリートに
加え、規格を下回る配線・配管のために、たやすくガス爆発を起こ
しては破片をまき散らし、路上にたむろしていた前夜からの酔客た
ちを容赦なく襲った。
アーケードの下で安心していた人々に、死が、恐ろしい響きとと
もに薄い天蓋を突き破って襲ってきた。
あるものはガラスに下半身をすぱりと切断され、あるものは幸運
にも一瞬のうちに頭をつぶされた。
理不尽な死が、何の罪もない市民を情け容赦なく襲った。幼子や
老人を抱えたままの家が次々と燃え上がり、悲鳴とヒトの燃える臭
いがした。断末魔の絶叫は新興住宅街に響きわたる。
かろうじて崩壊を免れた市庁舎の6階で、飛騨公平は唇を噛みし
めていた。全国でも画期的な集中管理システムを持つ福井消防署総
合管制システムは、しかし何の役にも立たなかったのだ。
今は、精密な情報よりも消防車が一台でも多く欲しかった。
しかし、公平はすぐに立ち直った。悲しむのはあとでもできる。
太い指がキーボードの上を滑るように走り、消防情報管制システム
を起動する。ディスプレイに市街地の火災状況が提示された。公平
は、小さなため息をひとつ漏らすと画面を睨みつけた。
(助けられないひとの事を想うな、助けられるひとの事を考えろ)
起きないでくれと願い続けた「ランクD」への対応策が、公平の
指をひとりでに動かした。画面からは、深夜に人のいない地域のポ
イントが消滅した。画面右下のウィンドゥにコーションランプが赤
く点滅する。ウィンドゥを開いた。
「お盆帰省・違法駐車車両の存在を考慮」
公平はうめいた。ポンプ車の幅は2メートル、危険地区の生活道
路の幅員は3.5~4メートル、現場到達は不可能である。過去の
データを火災表示に重ねた。新興住宅地には違法車両が少ない、消
防隊の主力をそちらに回す。市周辺の消防署に、正確な指令が飛ん
だ。データ回線で、電話機で、それでもつながらない所へは200
0MHzの電波が冷たい命令を伝えた。隊員は、自分の町のほうに
上がる火の手を横目で眺めながら、指示された現場へと向かった。
消防隊の対応するポイントが次々と黄色の点滅に変わる。だが、
依然として赤いポイントはエリア全域に輝いている。
(・・・まだなにか、打つ手があるはずだ。きっとある・・・)
公平は、全てのしがらみを忘れて解決策を捜そうとした。今、自
分にできることがあるならば、どんな無理をしてでもやらねばなら
ない。高速道路は架橋で寸断されている、古い住宅地ではポンプ車
が入れない。いや、ポンプ車などもう無い。あるのは各地の消防団
の持つエンジンポンプだけである。ならば人だ、動かせる人間はい
ないか? 警察は・・・・・だめだ! 訓練を受けていない人間で
は、現場ではすくんでしまって役に立たない。統率される事に慣れ
た集団・・・・・あった!
「・・・はい、こちら福井地連」
「もしもし、こちらは消防本部」
「・・はい・・」
「消火活動への協力をお願いします」
「状況は理解できますが・・・上からの命令がないと・・・・・」
「今は、今はそんな事を言っている時じゃないでしょう!!!!」
「・・しかし、これは緊急時における行動マニュアルとして・・」
「命令を出す人たちが、がれきの下でもがいてるかもしれないでし
ょう、お願いします、協力してください」
「・・規則は絶対です。みんなが勝手に行動したら、混乱を招くだ
けです」
「・・・・・・・・・」
沈黙が長い間続いた。永遠の時が流れたかと思った。公平は、電
話器のダイアルを親の仇のように睨みつけたまま、息をする事さえ
忘れているようだった。
「・・しかし・・・・・・・・」
「・・・わたしは、」
「・・・?・」
「・・・職務不適格者だな、ははは」
「・・協力して・・頂けるのですか?」
事務的な口調で、しかし熱い答が返ってきた。
「自衛隊福井地連は、ただ今より福井消防本部の指揮下に入る!」
「福井消防本部は、自衛隊福井地連の指揮権をお預かりします!」
●
オリーブドラブに塗られたトラックが、荷台に若者を載せて四方
へ散って行った。そのうちの一台が、木造家屋の密集している古い
住宅地の入り口に止まる。住宅地の中は、違法駐車のクルマによっ
てはばまれている。15人の隊員たちは、エンジンカッターやバー
ルを手に、倒壊した家屋へ向かって走って行った。誰も一言も口を
聞かずに、一糸乱れぬ行動で作業を開始する。
「頑張れ! もうだいじょうぶだぞ!!!」
2万カンデラの作業灯が夜明け前の住宅地に輝き、かすかなうめ
き声に向けて隊員の励ましの声が飛ぶ。まるで怒鳴っているようだ。
だが、あちこちであがった火の手は、下敷きになった人々のいる
家へとだんだんと近づいてくる。燃えさかる炎の中から、死体が焼
けてはらわたの弾ける音がばすんばすんと聞こえる。
「だれか、たすけてやってくれ!」
崩れ落ちた家の窓のあたりで声がする。見ると、大きな梁のむこ
うに少女の手が見える。倒壊した家屋の下に閉じ込められているの
だ。足場が悪くて油圧ジャッキは使えない。途方に暮れている祖父
とおぼしき老人をおしのけて、エンジンカッターで梁を切断しはじ
める。だが、重量鉄骨の梁は容易には切断できそうもない。
パァーンという音がして、駐車してあるクルマが炎に包まれた。
火を遮るはずの道路が、数十リットルのガソリンを抱えたブリキの
箱によって導火線と化していた。隊員は、炎にあぶられながらも必
死に作業を続けた。
8割方作業が終わった頃、突然、ぐきりという嫌な音がして機械
音が止まった。スターターを何度も引くのだが、掛からない。あせ
る隊員の背後には、すでに火の手が迫っている。
気配を察したのか、少女はすすり泣きをはじめた。
隊員の背中がキナ臭い煙をあげ始めた時、鈍い衝撃がはしった。
耐えられないほど熱くあぶられていた背中が、すっと楽になった。
水だ! 振り返ると、先ほどの老人がバケツを握って立っている。
老人は、炎に向けて水をぶちまけた。次の瞬間、老人はまた、水
の入ったバケツを握っていた。汗ににじんだ目を必死に凝らして若
い隊員の見たものは、はるか彼方、公園の隣の防火用水から続いて
いる老人の列であった。
耳が遠いせいか、甲高い声でおもいおもいのかけ声をばらばらに
掛け合っている。10リットル入りのブリキのバケツは、その老人
達の列をすべるように走ってくる。
役目を終えたバケツは、小さな子供達の手によって次々と送り返
される。ぎこちない動きは、みるみる滑らかに安定していった。
「なにをしている、機械なんかに頼るな!」
老人の声に我にかえった隊員は、右腿のバッグから金鋸を取りだ
した。そうだ、あとちょっとじゃないか、ここさえ切断すればいい
んだ。
「がんばれ、もうすこしでたすかるぞ」
若い隊員は、少女を励ますために話しかけながら作業を続けた。
金鋸を引く時に力がはいる。奇妙なアクセントがおかしいのか、
少女はくすりと笑った。
隊員の手袋は、ずるむけになったてのひらから染みだした血と汗
で、ときおりずるりとすべった。老人たちの励ましの声が飛ぶ。子
供達の黄色いかけ声が大きくなる。てのひらはもう、痛みを感じな
かった。
そうだ、あとちょっとじゃないか・・・・・
© Rakuten Group, Inc.