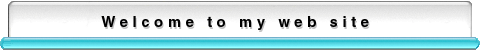来週またこの場所で・・・
あのとき、とっさについた嘘は、思わぬ形で俺に返ってきていた。
「・・・・・・死んだ?」
保健室。病院の個室ほど白くはないが、それでも白の多さが目立つその部屋で。
その言葉によって足下ががらがらと音を立てて崩れていくような不安定感と共に、異常な安らぎを感じる俺がいた。
何故かそれを嘘だとは思わず、すんなり受け入れていた。先生が俺の視界から消えた頃、その感覚すらなく、涙が流れた。
今日は朝から頭が痛かった。奥の方がズキズキと、それはもう死ぬほどに。
そんな頭痛に耐えること数十分。ある瞬間を境に、ぴたりと頭痛はやんだ。
時刻はすでに午前9時を過ぎていて、頭痛がやまなければ学校なんて休んでいただろう。
俺はすぐ学生服に着替え、鞄をひっつかんで家を出た。
急げば一限目に間に合うか、という時間。車や学生があふれかえっているいつもの通学路には、俺一人だけだった。
しかし急ぐ気にはならず、のんびりと青空を見上げたりなんかしていた。
――ふと、白い光が。
太陽のものではなく、花火のようにも見えない。青い、とても澄んだ青い空へ、綺麗な白が突き抜けていった。
そこから数歩。俺が光から目を離し、光が完全に消えるまでの間の4,5歩が終わると。
「ッ・・・?!」
頭を万力で圧迫するような強烈な痛みがやって来た。
思わずよろめいて近くの壁に手をつく。しかし痛みはやまない。それどころか酷くなっていくような気さえした。
いっそこの壁に頭を打ち付けて割ってしまう方が楽なんじゃないか。そう考えるほどに痛かった。
壁に寄りかかりながら、俺の足は何故か休もうとせずに学校へと向かっていた。
段々と頭痛は酷くなる。万力を更に締め付けるように。頭蓋ではなく、脳そのものが痛かった。
それは昨日までの日々を忘れ、今日からの異常な生活を無理矢理に受け入れることすらできる痛み。
4月23日という、不思議も違和感も何もない一日を。ただこの頭に焼き付けるための痛みだったのかも知れない。
いつの間にか俺は白い天井を見上げていた。
「――?」
目を覚まして、少しの間天井を見上げた俺は疑問符を浮かべる。少しだけ体を起こして白いカーテンも見るが、やはり疑問符しか浮かばない。
(さっきまで歩いてた気がするんだけど・・・)
その記憶を掘り返すと、一瞬だけ針が刺さるような痛みが走った。
「つ・・・ッ」
軽く顔をしかめ、こめかみの辺りを手で押さえた。
それとほぼ同時に、カーテンの向こうから声が聞こえた。
「あ、起きた?」
聞き慣れないが聞き覚えのある声は、足音と共にこっちに近づいてくる。
状況と記憶が一致した頃に、その人はカーテンから顔をのぞかせた。
「・・涼子さん」
俺は体を起こしたが、それでも少し見上げる角度でその人の名を呼ぶ。
「こら、お姉ちゃんって呼ぶように言ったでしょ?」
涼子さんは少し不満そうに立てた人差し指を俺の前につき出した。
「・・・姉さんが運んでくれたの?」
言われたように呼び方を変えて疑問を口に出す。
ぎこちないながら要望に応えた俺に、2週間前まで他人だったその人は少し嬉しそうに笑った。
「うん、朝来たら保健室の前にいたからびっくりしちゃったよ」
姉さんは子供みたいな口調で言うと、俺の隣に勢いよく座った。
反動で俺の体は上下に少しだけ揺れる。俺は少しだけ首をかしげた。
「え・・・、俺って校門前に倒れてたんじゃないの?」
「ううん。私、そんなところからここまで人を運べるほど力持ちじゃないもん」
もう一度、年齢と見た目にそぐわない喋り方で彼女は言う。
彼女の体を見るが、たしかにそんな力はないと思う。というか、女性で気絶している青年を運べる人がいるのかすら疑問だが。
(じゃあ誰が・・・、まさか、俺が一人で?)
と考えたところで、ドアの開く音がした。
「 西海 先生ですか?」
姉さんはカーテン越しに、見えない人物の名を呼んだ。
「あ、はい。 誠志 君は起きました?」
これは間違いなく聞き慣れた声だった。何せもう一年以上、聞かなかった日がないほどにこの人の声は聞いたことがあった。
顔を見なくても顔と名前が解るその人は、俺のクラスの担任。さらに、俺の所属する陸上部の顧問でもある、西海祐一だった。
「西海ィ?・・・おいおい、何の用・・・一限目ならパスするよ?」
俺の言葉に合わせるように姉さんがカーテンを開ける。間違いなく見飽きた顔だった。
しかし俺を見るや否や、急に見たこともないような真剣な顔つきでこっちへ向かってくる。
そして俺の目の前で止まり、目線を俺に合わせてくる。
姉さんが少し不安げにそわそわし始める。まだ短いつきあいでしかないが、この人のこんな姿は初めて見る。
「あの、西海先生・・・やっぱり、もう少し後でも・・・」
その言葉に西海は一瞬ためらったような間をおき、首を横に振った。
「何の話だ?・・・なんかマジっぽいんだけど・・」
俺が口を開いてからの数秒、西海は軽く目を閉じていた。すごく、何か・・・悔しさを感じているようだった。
そして。
「・・・二羽、聞け」
俺の肩に手を置いて、西海は目と口を開いた。
このときまで・・・いや、このときでも俺は気付いていなかったかも知れない。次に彼の口から出る言葉に、俺が絶望に叩き伏せられることに。
「言われなくても聞くよ。なんかあった――」
「・・・・・・藤野が、死んだ」
「――え?」
ガツン、と。
頭の奥の方で何か固いものに殴られるような感覚と音を感じた。
転校。多分今日ので記念すべき10回目。
まさか自分でもこんなに何回も転校するとは思わなかった。本当、人生は何が起こるか解らない。
ふぅっ、と一息で前の学校を忘れると、目の前の新しい学校に目を向けた。
―私立白神学園―
この学校に今日私は転入した。
県内でもトップクラスのこの学校、何故転入できたのか不思議なくらいだったけど、入れたなら楽しむしかない。
「・・・まずは部活。だよね、やっぱ」
足取り軽く、私は目当ての部活を探しに向かった。これだけ広けりゃ、あるでしょ。陸上部ぐらい。
意気揚々。スキップするぐらいに浮かれた気分で、私はグラウンドを目指した。
「ふぅ・・・、俺の勝ちだな」
「ちっきしょ・・・、なんでお前そんなに速いんだよ・・・」
俺は生まれつき足が速かった。小学校の頃からかけっこじゃ負けなし。その頃の夢は陸上のオリンピック選手だった。
今もまだ、夢を追うには追っているのだが・・・どうにも、今の状況では無理なように思えてきた。
理由としてはトレーニングをしてもタイムがほとんど縮まらなくなってきたこと。それと。
「おっし、もう一回走ろうぜ!」
「悪ィ、勘弁してくれ・・・勝てる気がしねぇ」
・・・周囲との実力差が顕著に表れてきたことにある。
中学、高校になればもっと速い奴がごろごろいるだろうと思っていただけに、これは残念でならなかった。
俺の周囲では、俺のように陸上一直線でやっている奴がほとんどいなかった。そのために、俺にはライバルと呼べる奴がいなかったのだ。
「・・・はぁ」
知らずため息が出てしまう。ため息をつけばどうにかなるわけでもないのに、それでも自然と口を開けばため息しか出なかった。
「・・・・・・一人で、走るか」
スタート地点へ戻り、クラウチングの体勢を取る。スターターに目配せして、開始の銃声を促す。
彼も少し疲れている様子で、仕方なさそうに銃を上に向けた。
「位置について・・・ヨーイ」
息を限界の少し手前まで吐く。そして呼吸を止める。
パン!という小気味のいい音が鳴る瞬間、俺の体は動き始めた。
靴が砂を蹴る音だけが俺の中に響く。周りの景色が段々と見えなくなっていく。
そうしてやがてゴールしか見えなくなり、あと数秒でゴールというところ。
少し先のラインしか見えなかった俺の視界に、何かが割り込んできて。そのまま段々俺の前へと進んでいった。
「――――ッ!」
ゴールした瞬間、喪失感とある種の充実感があった。
俺は俺の少し前に歩く、おそらく俺を抜いていった奴を見た。
「――ッはぁー!びぃっくりしたぁ!君、速いねー!」
するとそいつも振り返ってそんなことを言ってくる。
その時見たそいつの顔は、すごく楽しそうで、嬉しそうで。なおかつ信じられないぐらい綺麗だった。
「・・・・・って、女ぁ!?」
想像もしなかったその容姿に、今思えば差別的とも取れる驚き方をしてしまった。
「む、女じゃ何か悪い?」
表情がいきなり不機嫌そうなものに変わった。・・・まぁ、当然か。
それよりも俺は彼女の呼吸に驚いた。走った直後だというのに彼女は息一つ乱していなかった。
俺の呼吸も整ってはいるが、これはついさっき正常に戻ったばかり。
彼女のそれは、多分走っている間でもほとんど乱れない綺麗な呼吸。
所詮推測の域を出ないのだが、それを確信させる何かが彼女にはあった。
「・・どしたの、急に黙っちゃって」
少し不安を帯びた声が、俺を目の前のすごい奴に引き戻させた。
「あ、いや・・・、ちょっと、驚いてて」
あまりいい言葉が思いつかず、意図せずはぐらかすような形になってしまう。
「ふーん・・・まぁ、いいや」
言うと彼女はまた笑顔に戻り、俺の肩に手を置いた。
「君を私のライバルに認定しまーす!」
あくまで力強く。そして明るく、彼女は言い放った。
俺はただただ圧倒されて、間抜けに口を開いていた。
「――転校生を紹介する」
朝練を終え、SHRの時間。俺はいつものようにこの後4時間は爆睡するつもりだった。
・・・だったが、そいつが来たおかげでパッチリと目が覚めた。
「初めまして、藤野 達美です。隣の鈴星市から来ました。好きなことは走――」
「お前ッ!朝の!」
彼女の好きなことは走ること。それは朝の様子からすればわかる・・・って、そうじゃない。
寝ぼけ眼の俺の前に現れたのは、その時俺を後ろから華麗に抜き去っていった奴だった。俺はイスから立ち上がり、指を指して叫んだ。
「・・・あれ、朝の・・・二羽君だっけ?」
意外にもそいつはあまり驚く様子もなく、俺の名を呼んだ。・・・むしろ、俺の方が驚かされた。
「なんだ、二羽、知り合いか?」
教卓の前に立っている、今日も朝練に来なかった陸上部の顧問は少し驚いて俺を見る。
だがそれ以上に俺は驚いている。その俺を気にする様子もなく、西海は転校生を俺の方へ促した。
同じ姿勢のまま、俺はそいつがこっちへ来るのを見ていた。
「席、隣みたい。よろしくね、二羽君」
言ってにっこりと笑う転校生。
「・・なんで、お前、俺の名前知ってんだ」
ここでようやく俺を驚かせたことについて聞く。
とりあえず座ろう、と俺を促すと、一言で俺の疑問を片づけた。
「ライバルだから」
妙にはきはきとした声で。それでいて嬉しそうに彼女は言った。
そのあまりにも嬉しそうな顔は、頭に来るがすぐ毒気を抜かれてしまう、不思議なものだった。
「・・・いや、それ理由になってない」
とは言うものの一応頭には来ているわけで。自分でもどこかイラついてるとわかる声が出た。
「ライバルの名前知っとくのは当然でしょ。センセに聞いたらすぐわかっちゃったからね」
左目で軽く睨むように藤野を見る。右手で右目も覆うように頭を抱えた。
これからの学園生活に。そして、陸上部に。
一抹の不安と期待を予測した。
途中。
2006.6.5 及び 2006.8.1の日記で更新したもの。
© Rakuten Group, Inc.