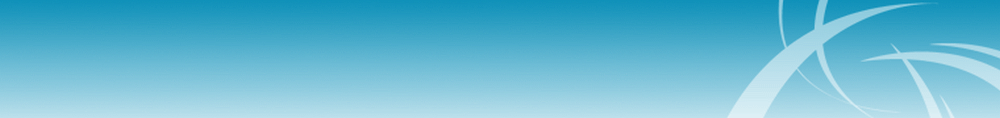PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 時事
iPS細胞の補助金はなぜ打ち切りに…黒幕は“税金で不倫旅行”疑惑の官僚!? - 記事詳細|Infoseekニュース
「出張は公務としての手続きをしたうえで行っている。京都市内での移動は私費で支払っており、適切に対応していると聞いている」11月12日、菅義偉官房長官は、『週刊文春』に掲載された「公私混同の瞬間をスクープ撮安倍首相補佐官と美人官僚が山中ノーベル賞教授を“恫喝”した京都不倫出張」と題された記事について記…
iPS細胞の補助金はなぜ打ち切りに…黒幕は“税金で不倫旅行”疑惑の官僚!?
日刊SPA! / 2019年12月17日 8時51分
写真
「出張は公務としての手続きをしたうえで行っている。京都市内での移動は私費で支払っており、適切に対応していると聞いている」
11月12日、菅義偉官房長官は、『週刊文春』に掲載された「公私混同の瞬間をスクープ撮 安倍首相補佐官と美人官僚が山中ノーベル賞教授を“恫喝”した京都不倫出張」と題された記事について記者から聞かれると、こうやんわりと突っぱねた。
記事に登場するのは、安倍政権発足当初から官邸主導の安倍一強政権を「官邸官僚」として支えてきた和泉洋人首相補佐官(66)。沖縄の普天間基地移設問題や新国立競技場建設問題でギリギリの交渉を取りまとめてきた“タフ・ネゴシエーター”で、菅官房長官の「懐刀」として知られる人物だ。
「総理の代わりに言う」
加計学園獣医学部新設問題のとき、和泉補佐官が、当時、文科省の事務次官を務めていた前川喜平氏にこう言い放ったことが暴露されるなど、その強引な手法が「忖度政治」の元凶と批判されることもあったが、その官邸中枢のキーマンが、あろうことか、仕事にかこつけた出張旅行に不倫相手を同伴させていたというのだ。
しかもそのお相手は、厚労省大臣官房審議官にして、内閣官房でも健康・医療戦略室のナンバーツー(次長)の職を務める美熟女官僚(52)。2人は腕を組んで縁結びの神社に参拝し、人目もはばからずにエスカレーターで「バックハグ」するほどの仲睦まじさだったという……。
「山中先生が’06年にiPS細胞を世界で初めて作成し、’12年にノーベル生理学・医学賞を受賞したのを機に、政府は国を挙げてiPS細胞の研究支援をすることに決めました。’13年から向こう10年で総額1100億円。山中先生のCiRAにも年間約10億円の助成金を出すという約束でしたが、今年に入って政府が突然、支援を’20年で打ち切ると言い出したのです。
CiRAは、献血のようにあらかじめ複数の型のiPS細胞をストックしておく備蓄事業を進めようとしていたが、今夏、和泉補佐官と一緒に訪れた女性戦略室次長から『(予算停止は)私の一存でどうにでもなる』と迫られたことで、山中先生は自ら“反論会見”を開こうと決意したようです」
◆悲壮な山中教授の会見
山中教授が先月11日に開いた会見は悲壮なものだった……。
「いきなり(支援を)ゼロにするのは相当理不尽だ」
「(iPS細胞の)備蓄事業は文科省の公開の有識者会合で評価され継続が決まったのに、“一部”から国のお金を出さないという意見が出てきた」
「透明性の高い議論で決めてほしい」
皮肉にも今回の報道で、山中教授の言う“一部”が誰を指していたのか、明らかとなったわけだが、日本発の再生医療として期待を一身に受けていた花形の研究が、なぜ、このような憂き目に遭わなければならなかったのか? 元厚労省医系技官で医師の木村盛世氏が話す。
「iPS細胞の研究は費用対効果の悪さから予算偏重という議論もあったが、一介の官僚が公の議論も経ず、独断的に補助金打ち切りを決めたのはあり得ない話です。ただ、そもそも国が支給する研究費は公平に分配されるわけではありません。補助金のついた研究にはさまざまな条件や縛りがあるので、研究環境としては窮屈になるが、それでも嬉々としてお上に従う研究者は少なくない。
だからこそ、これまで国の補助金はお手盛りの“御用学者”に手厚く支給されてきたわけです。CiRAは10年で約100億円の補助金を受けていたとはいえ、iPS細胞の備蓄事業を助成金が期待できる公益財団法人化して進めようとしていたことからもわかるように、研究資金は決して潤沢ではなかった。だから、山中教授が先頭に立って、全国各地のマラソン大会に参加するなどして募金や資金援助をお願いしていたのでしょう」
確かに、資金集めに奔走する山中教授の涙ぐましい姿は、これまでたびたび話題となった。山中教授はCiRAの公式サイトでも「弊所の教職員は、9割以上が非正規雇用」と窮状を訴え、先月には「iPS細胞かるた」を発売。こちらも研究費に充てられるという……。
ここ数年、薬価引き下げや患者負担の軽減撤廃など、膨張し続ける医療費を抑制する圧力が高まっている。そのため、科学立国を標榜する国としては、限られた財源のなかで「選択と集中」を推し進める必要があるが、これが「まったく機能していない」という見方もある。『科学者が消える―ノーベル賞が取れなくなる日本』(東洋経済新報社)の著書もあるノンフィクションライターの岩本宣明氏が話す。
「『選択と集中』の対象となって国から補助金を得るには、公募に応募して採択される必要がある。だが、優遇される研究とそうでない研究があり、フェアとは言い難い。要は、手っ取り早くカネになりやすい研究が、より補助金を受けやすくなっているのです。
一方、ノーベル賞の大半は基礎研究で、それらに補助金がつくことは稀……。だから、近年の日本人受賞者たちは『もはや日本では基礎研究はできない』と口を揃え、懸念を露わにしているのです。大学院の博士課程を修了しても、研究者として正規雇用されるのは全体の1割にも満たない。その他は、有期雇用の研究職を転々とするか、研究を諦めエンジニアや開発者として企業に就職してしまう……。
理工系の大学院博士課程の進学者、つまり“博士の卵”は、大学法人法が成立した’03年以降減り続け、15年前の半分にまで落ち込んでいる。日本には基礎研究をやらせてくれる企業は非常に少ないため、研究現場の窮状が改善されなければ、今後、堰を切ったように海外への人材流出が起きるでしょうね」
科学立国を標榜する政府には、長期的な目線で旗振り役となってほしいものだ。
京大iPS細胞研究所が推し進める備蓄事業を巡って、政府は’20年度以降の予算を削減する方針を示していた。だが、同研究所の山中伸弥教授の会見を受けて、12月6日に竹本直一科学技術相が「政府としては当初の予定通りやる」と説明。一転して、備蓄事業への支援を継続する意向を明らかにした。ただ、支援自体は’22年で終わる予定だ
<取材・文/週刊SPA!編集部 写真/朝日新聞社>
※週刊SPA!12月17日発売号より
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[時事] カテゴリの最新記事
-
桂雀々さんが大物ミュージシャンたちに愛… 2024.11.23
-
たむらけんじ 文春から取材依頼も、拒否… 2024.03.15
-
陶芸家が100均の「陶芸用ねんど」使ってみ… 2024.02.21
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
フリーページ
漂流録

最初の漂流

単車乗りの聖地北海道

未踏の地-四国一周編

海沿いを走る-瀬戸内海一周編

紀伊半島を一筆書き

漂流写真

パンフの杜
単車

CB750FB BB2

通勤快速スーパーカブ

車とか自転車とか
バス釣り

釣果報告

愛すべきロッドたち

愛すべきリールたち

愛すべきルアーたち

黒鱒釣竿 計画
コインコレクション
おもしろgif集めました
部屋中ビオトープ
昔ポスト
ごはん写真
おもちゃで遊ぼう

烈車戦隊トッキュウジャー

レゴの動画たち

折り紙-Learn how to make origami
音を楽しむ

きゅうそキャンプソング
小さい大工さん-Do It Myself-
60mlの情熱
スタンプコレクション!
愛すべき道具たち
ミニ四駆
VAPEの備忘録。
老後の為?投資
鉄道動画
© Rakuten Group, Inc.