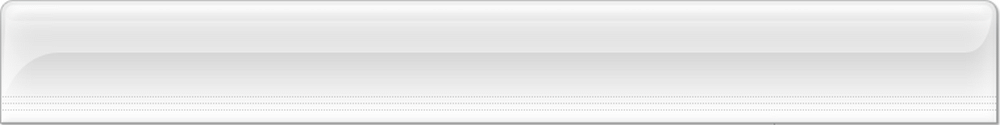カテゴリ: カテゴリ未分類
ラブクラフトという人物は1920年代の米国作家であるが、現在の日本人が米国ホラー作家というとスティーブン・キングを想起する人が多いだろう。米国ではモダン・ホラーに分類される作家であり、それ以前がゴシック・ホラー、ラブクラフトは特別にコズミック・ホラーと言われている。
ただ、恐怖小説という漢字にしてみると、これらは微妙にニュアンスが違い、キングが代表するモダン・ホラーは、厳密に言えばダーク・ファンタジーである。
日本のホラー作家は、厳密にはダーク・ファンタジーの系譜を引いている。
(ちなみに夢野久作はドグラ・マグラに代表される自作を探偵小説といっている。怪奇小説→ポオ→江戸川乱歩→探偵小説という流れである)
文学としての恐怖小説とは何かといえば、ラブクラフトの該当書を引けば足り、その冒頭に、
「人間の感情の中で、何よりも古く、何よりも強烈なのは恐怖である。その中でも、最も古く、最も強烈なのが未知にものに対する恐怖である」
としてある。
この序説だけなら、創元のラブクラフト全集(多分4巻)で読める。
序説以降はホラー小説史を執拗としか思えない毒舌でばっさばっさと切っていくのが永遠と続いているだけなのだが、何せ恐怖小説研究家だったんだろうなあ、と思われるラブクラフトであるから、怪しげな伝承やら神秘主義やらの原初から始まり、精密な考察を続けていくので、興味がある方は手にとって欲しい。
今日たまたま、日経夕刊において高橋源一郎が、文学についての長文コラムを載せていた。偶然にも1920年代の文学者たちのエネルギーに触れ、文学のエネルギーはこの時代に爆発していたといったような趣旨を書いているのだが、その中で、現代の次第に難化し、まじめくさり、堅苦しくなって権威になっていく文学についての迷いを綴っていた。
原初のエネルギーという意味で、この時代は何があったのだろう、と思えるほど、分類化されず、本質を追い求め、複雑化しておらず意味が明確な時代は珍しい。
しかも、なぜだか分からないけれど、異様な勉強家ぞろい。
文明の始まりから考察しているのである。
■第一次産業革命とIT革命の類似のお話 - FIFTH EDITION
http://blogpal.seesaa.net/article/34876648.html
奇遇にも、本日、FIFTH EDITIONさんにおいて、1900年代初頭と現在の類似点についての興味深い考察を綴ったエントリーがあった。
つねづね、最近本質的に、様々なことを再考しなければならないことが多いなと思っていただけに、やはりインターネットの到来が、様々なこれまでの神話を再咀嚼し、新しい時代に適合しなければならない局面にあるのかもと感慨深く読んだ。
プロイセンの歴史を読むに至り、1500年代から1945年までのヨーロッパ史を、いまさらながら把握した。
ドイツは、1871年のドイツ帝国統一によって、プロイセンという強大で厳格で秩序があり強靭な精神的主柱を飲み込むが、それにより拡大志向に歯止めが利かなくなった烏合の衆によるドイツナショナリズムが、二度の大戦の引き金となる。
このばら色の全世界的産業拡大のバブル狂乱が、世界恐慌となり、大戦に繋がる。
戒めとしよう。
しかし、当時の原初的エネルギーは、今なお読んでも、そのパワフルな理論構成でたじろぐほど強烈である。
まるで、ラブクラフトの作品に登場する原初の知を伝える魔道書ネクロノミコン(アル・アジフ)のようであり、ビックバンのように拡大する新しい無秩序が記載されている。その後、幾度もの反省を経て秩序へと向かうが、この無秩序は現在のインターネットによる知の爆発を連想してしまう。
わたしは仕事柄、現代的特許法の成立過程に興味があるのだが、それを記したネクロノミコンが今日届く。
発刊は昭和17年(1942年)であるが、ディーゼルエンジンの発明者である、ルードルフ・ディーゼルの息子の作とあり、おそらくじかに接したであろう先人の英知が、ここに数多く記載されている。
引用しよう。
「発明とは何か。探求せられたものの終結である」
強烈であり、本質でもある。
このレベルの文章が、所狭しと並んでいる。
しかし、引用を始めると、全ページを引用しそうになるので、重要な、ルードルフ・ディーゼルの長い言葉を引用して、わたしはこの本を読み始めることにしよう。
「理念だけでは発明とは絶対に言えない。発明品の目録から何でも取って見るといい。望遠鏡でもマグデブルグ半球でも紡績機でもミシンでも蒸気機関でも。発明と言われるものは常に実行された理念だけである。発明は決して純精神的な産物ではなく、理念と肉骨の世界との闘争の結果にすぎぬ。それ故にどんな完成せる発明にも、同じような思想は多かれ少なかれ確実に意識的に、時には既にずっと以前に、他の人々の念頭に浮かんでいたことを○○(旧字体のため不明。推測?)立てることができる。
理念と完成せる発明品との間には、発明行為の本来の仕事と苦難の時間が存在する。常に天翔る思想の小部分しか肉骨の世界に押し付けることは出来ないし、又常に、完成せる発明品は、本来精神が見た、決して達しえぬ理想とは全然別の相貌を呈する。それゆえいかなる発明家も未聞の不評を受けながら理念や計算や実験に従事する。何かに達せんがためには、多くのことを欲せねばならぬ。最後に残るのはその最も小部分である。
従って発明する、とは、無数の誤謬の皮を剥いで取り出した正しい根本思想を幾多の失敗と妥協を経て実際的成果に帰すことである。
それ故に発明家は楽観主義者でなければならぬ。理念の力の全衝撃力は創造者個人の魂の中にだけあり、この者だけが実行の聖なる火を持っているのである」
ぼうぜんとするような名文である。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
November , 2025
October , 2025
September , 2025
October , 2025
September , 2025
August , 2025
July , 2025
July , 2025
Comments
Keyword Search
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.