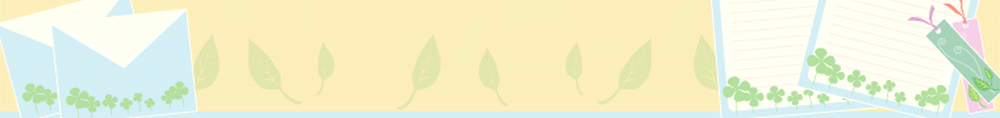担任へ質問と回答時の私の印象
今日、答えられる範囲で口頭で答えて頂いて、概要はメモを取らせて頂きますが、後日改めて書面でも回答を頂きたいと思います。
(今日ここで答えて頂いたのと違う内容になっても構いません)
* 当日メモは取りましたが言葉そのものを正確に書いたわけではなく、あくまでも概要をメモしただけです。
書面での回答は断わられました。
ここには当日のメモと私の記憶をもとに、回答時の印象として書き留めます。
1) 交流学級の担任の先生との連絡事項(時間割りの変更や持ち物、学用品の購入等々)のやり取りは、
現在はどのような方法で為されていますか。
また、それについて現状で○○先生ご自身が困ると感じられることはありますか。
あれば具体的に、その解決方法のアイディア(今すぐ実行出来るかどうかは別として)があれば
合わせてお答え下さい。
* 基本的には毎週学級通信(保護者に渡す1週間分の時間割表)を書く前に担任が各交流学級の担任に
直接聞きに行って、自分でメモして来るようです。
今の方法で担任自身は困らないそうです。
「今の方法で保護者にも子どもたちにも、必要な情報を必要な時期に出せているとお思いですか。」
という問いに「はい。」という返事が返って来ました。
あまりにも意外な返事に、当日の時間割変更や急な連絡事項はどうしているのか聞くのを
忘れてしまいました。
交流授業で使う持ち物や購入する物の連絡が漏れることがあり、「連絡漏れがよくあるそうなので
多めに見て下さい。」と実際に担任から言われたことがあります。
これは変だと思います。
保護者は困っているのですから、あなたも少しは困って、なんとかしようと思って下さい。
2) ○○先生が直接ご覧になっていない場面での他害行為や悪口などについて、された側の子から
報告があった時に、基本的にはどのような対処をなさいますか。
その行為をやった側の子、された側の子についてそれぞれお答え下さい。
* された側の子とやった側の子に聞いて、良くないこと、謝ることを話す。他害行為があれば親に知らせる。
というような答えでした。
あまりにあっさりと答えられてしまって、事実の確認以外に双方の子の気持ちをどう汲み取るか、
受け止めるか、聞くのを忘れてしまいました。
「どの程度から他害行為と認めて保護者に報告しますか。」の問いにはつねる、蹴る、叩く。
「キズがなくても子どもたちから話しが聞ければ、事実と認めて保護者に報告しますか。」の問いに「はい。」
私の所は他害行為の被害に会うことが滅多にないようなので何とも言えませんが、子どもたちの声を
ちゃんと拾い上げてくれているのか・・・疑問に思います。
3) 子どもたちが先生に訴えたいことがあっても、上手に言葉や態度に表せないでいることもあると
思いますが、そんな時に子どもたちが発している信号を先生がある程度受け止められている、
もしくは受け止められるよう意識していると、ご自身で思われますか。
* 出来るように努力しているし、言葉の強さなどから子どもたちが何を訴えているかを常に意識している・・・
のだそうです。
4) 社会性の面で、子どもたちに最低限身に付けさせたいことは、どのようなことでしょう。
* 約束を守って仲良くなれて、楽しく活動出来る。
「仲良くをもっと具体的に」と言うと・・・
あの子が何をやりたいか分かり合う。
そのようにさせてあげられない時はどうするか考える。
という答えが返ってきましたが・・・
質問のし方が適切でなかったために、学級の中では比較的障害の重い子たちに関する回答は
省略されたのかも知れませんが(特にそのようなことは言われたわけではありません)、○○小の
特別支援学級の現状に合った答えではないように思います。
比較的障害の軽い子たちだけで行動する場合は、多少介入してもらえばこのようなことも可能かも
知れませんが、そこに言葉でのやり取りが十分ではない子たちも加わった場合、相手の気持ちを
察することも難しくなるのではないでしょうか。
また、相手が言葉で意思表示をしてくれる場合でも、相手のその言葉に自分の思いを重ねて相手の
気持ちを察することは、特別支援学級にいる子どもたちにとって、そう容易なことではないと思います。
私としては、「嫌なことをされたら嫌だと言えること、それを先生に報告出来ること、悪いと気付かずに
したことでも相手が嫌だと言ったらやめること、ごめんなさいが言えること。」辺りを想定していました。
5) 学年も障害の程度もバラバラの子たちの教科学習は進度も当然バラバラで大変難しいことと思います。
一人一人に向き合う時間が十分取れないのが現実かと思いますが、そんな中で少しでも確実に学習を
進めるために、現在工夫なさっていること、もしくはこれから試してみたいと思っていらっしゃることは
ありますか。
あれば、具体的にお答え下さい。
* 主にプリントの工夫と、集中出来る時間が短いので、○○○をやったら好きな事(塗り絵など)を入れる
などして集中が続くようにというような答えでした。
「先生が他の子を見ている間に1人で課題に取り組む時に、集中出来るような言葉かけの工夫は」
の問いに「頑張れとか・・・」
本人が自分が今やるべき事に向かう態勢がある程度取れていて、そこを後押しするだけなら
「頑張れ」でも構わないと思いますが、特別支援学級にいる子の場合、今自分が何に注目すれば良いのか
今一つ理解出来ていなかったり、意識を向けるべき所が頭では分かっても気持ちを切り替えて自分の
意識をそこに持って行けずに本人も困っていたり、つまり、「頑張る」以前の段階でつっかえていることも
少なくないと思うのです。
その状態の時に・・・というよりも出来ることなら、そうならないで気持ちを切り替えて行けるように、
どんなタイミングでどんな言葉をかけるか、そういう事を考えて頂きたいものです。
6) 知的障害のある子たち、中でも特に自閉圏の子たちは、耳から聞いた言葉を自分の中に取り込んで、
その言葉の示す具体的なイメージを頭の中に描くこと、言葉を画像に置き換えるとでも言うのでしょうか、
そういう力が弱いように思うのですが、そのようにお感じになったことはありませんか。
* 反応を見ながら言葉を選べば、たいがいの事は言葉で通じると思っていらっしゃるようです。
確かに言葉が通じないということではありませんが、言葉である程度の話しが通じるとしても、反応を
見ながら言葉を選ばなければならないということは、子どもたちにとって、言葉を耳から聞いて
言われている事の意味を具体的にイメージし難いことがあるということだと思います
言い回しが少し違うだけで通じ難かったりするのも、その辺りの弱さからくる部分があるように思います。
知的障害があっても自閉傾向のない子には、このようなことは見られないのでしょうか。
7) こちらが伝えたいことを確実に、また本人が確信を持って受け止められるようにするために、言葉で
伝えるだけでなく文字や写真などの視覚的な手がかりを示してやることが、言語理解が特に弱いと思える
子に限ったことでなく有効なように思うのですが、それについて○○先生はどのようにお考えですか。
例えば、有効だと思うがすぐには実行出来ない、有効だがあえて実行しない、不必要だと思うなど、
何なりと、その理由と共にお答え下さい。
* 四六時中一緒にいるので、子どもたちも分かろうとしているし、先生も分かるように話すので・・・
視覚支援の必要性は感じていらっしゃらないようです。
まず、分かるように話しているとおっしゃいますが、保護者に対しても物事を分かるように伝えられない
人が、色々な個性を持った子どもたち一人一人に分かるように話せているとは思えません。
子どもたちが言葉の指示を聞いて動けていても、実際は耳から入った言葉の意味をストレートに理解して
動いているのではなく、この場面で言われるとしたらこんなこと・・・と見当をつけていたり、他の子の
することを見てから動いていたりすることもあると思うのです。
そういう力をつけることも必要ですが、子どもがその部分にエネルギーを使わないで、自分に向けられた
指示の意味を当たり前にストンと自分自身の中に収めて、自信を持って安心して動けるように、必要に
応じて(必要だと思って頂けていないのが問題なんですが)言葉(音声)意外の方法もプラスして伝えて頂く、
それが支援だと思うのですが・・・
8) 時間割りの表を見て自分で予定帳に書き写すことが出来たり、何時間目は○○と答えられることと、
1日の時間の流れとして理解して、場面ごとに気持ちを切り替えて今すべきことに注意を向けられる
こととは大きく違うと思います。
そのように考えた場合、現在〇〇(特別支援学級)の教室にある時間割表は見難いとお思いに
なりませんか?
例えば、一人一人の活動の流れが縦に一続きに見通せるように個別に表示するなど、改善の余地が
あるとはお思いになりませんか。
具体的な改善のアイディアがあればお答え下さい。
また、現在のもので十分だとお考えなら、そのように判断なさった理由をお答え下さい。
* 子どもが理解しているので、これで良いかと思う・・・のだそうです。
時間割表というのは、何時間目は○○と、そこに書いてある文字が読めれば良いのではなくて、1時間目、
2時間目・・・と時間の流れに乗せてこれらの活動をするということを理解して、その流れに乗せて場面ごとに
気持ちを切り替えていく助けにならなければ意味がないと思うのです。
そうでないと、本人はその時その時に何をするか納得出来ていないで、気持ちの切り替えもできないまま、
ただ時間ごとに引きずり回されることになってしまいます。
時間の流れとして伝えることが出来て、本人が先の見通しまで持てていれば、多少苦手な活動であっても
自分から参加していくように促すことなども、やりやすくなる場合もあるかも知れません。
現在教室に掲示してある時間割表は、毎週配られる学級通信とほぼ同じ様式ですが、私は学級通信を
受け取ると、我が子の交流の時間割とお迎えの時間を見間違えないように、赤ペンで印を付けます。
大人がその状態なのですから、学級の子どもたちがその時間割表を見て十分理解しているとは
思えません。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 子供服ってキリがない!
- 12時ニューイヤーズバッグ
- (2025-11-27 08:26:54)
-
-
-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…
- (広告の愚痴)と1~3店舗目 scope半額…
- (2025-11-25 23:38:11)
-
-
-

- おすすめの絵本、教えてね♪
- 「ぼくのてぶくろ」きっとあなたも同…
- (2025-11-26 19:20:05)
-
© Rakuten Group, Inc.