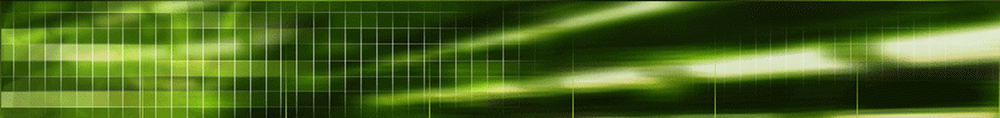第三章 【"SSF"】
メリルは船内にあるバー、『Interplay』にいた。
カウンターのテーブルにもたれる。
「はぁ、疲れたぁ・・・」
「はい、サツマイモジュース。」
そういうメリルの傍らに一杯の飲み物が置かれた。
「まったく、大変だったみたいね」
バーのオーナー、レイン・グルバースミスがメリルに話しかける。
「まったく、俺とロックが飛び出してきたメリルちゃんを上手くキャッチできたからよかったけど・・・」
隣に座るザックが得意げに語る。
「ああ、それでエクス隊長にたっぷり絞られた・・・と」
「そう、30分近くお説教・・・ってな」
ザックが笑いながらレインに話しだした。
そのとき、メリルは突然顔を上げた。
「今はフラッシュ航行の真っ最中ですよね。あとどのくらいでリカルア着くか聞いてきます」
「なんだよ、突然。」
メリルは突然Interplayを飛びだした。
「ちょいまてよ~・・・・・・・って、文字通り飛び出して行ったな」
「若い子はエネルギーが有り余ってるんじゃない?」
ザックとレインは出て行ったメリルを眺めながら呟いた。
『間もなくフラッシュ航行を解除します。本船は目的地、首都惑星リカルア宙域へ。
乗客の皆さんは下船の準備をお願いします。また、シートベルトは着陸時には・・・』
「・・・げ、もう着いたのか・・・」
ロイは閉じていた目を開けて大きく伸びをした。
コネクターに搭載されている時計を見ると表示されていない。
フラッシュ航行という、船をそのものを光に疑似変換することで光速プラス、ウランエネルギーエンジンの出力で
光速以上のスピードを出せるという画期的な新技術である。
窓の外を見ると、やはり光が差し込んでくる。
「いまいち仕組みが分からないんだよなぁ・・・」
そういいながら、ロイは外を眺めていると甲高いサイレンが船内に響いた。
驚いて顔を正面に向けると、一瞬にして窓の外が暗い宇宙に戻った。
そしてロイの目にこれまで見た事のないものが映った。
「うわ・・・」
緑と青、そして赤い部分のあるカラフルな星、そしてその周りに浮かぶ宇宙空間に支店をおく多くの大企業のテナント、
そしてさらにその周りを囲む防衛のための軍艦とファイター。
ここが首都惑星、リカルアの宙域なのだ。
「うわぉ・・・ヴァーノン見たいな田舎とはわけが違うな・・・」
ロイが故郷と首都惑星をくらべていたとき、アナウンスが入った。
『本船はリカルア第960宇宙船発着所へと着艦します。5分後、到着予定ですのでてにもつをまとめてください』
それを聞いたロイは荷物をまとめるのもそこそこに宇宙空間を眺めた。
手にはSSF隊員募集のちらしを握り締めて。
メリルは<クラッシュ>のブリッジに走った。
「リカルアにはどのくらいで着きます?」
そうパネルに向かっているナリに訊く。
「あと標準時刻で5時間ってところです。詳しい事は・・・」
「6時間だよ」
ナリが説明している途中で、真空耐性スーツからいつものジャケット姿に戻ったロックが口を挟む。
「ナリ、また計算をミスしたな。これはこう計算すると298分になるけど、正しい計算をすると368分になる」
ロックがナリのパネルを見ながら説明する。
しばらくすると、ナリが顔を上げてメリルを見ながら言った。
「約6時間です」
メリルが笑いながら頷いたときエクスが入ってきた。
ついさっきお説教を喰らったためメリルにとっては少し気まずかったが、エクスは入ってくるなり大声で尋ねる。
「リカルアまではどのくらいだ!?」
「約6時間です」
ナリが即答する。
「分かった。ところで、艦長はどこだ?」
エクスがきょろきょろしながら尋ねる。
確かにアイザック艦長の姿は見えない。
そのとき、ナリとロックとは少し離れた場所に座るジュリアがこたえた。
「アイザック艦長ならシアタールームにいるわよ」
ジュリアはそういって出入り口の隣にあるもう一つの扉を指差す。
エクスはまたか、というような表情をして扉の脇にあるマイクに向かう。
「アイザック?ちょっと来てくれないか」
しばらくしてその扉からアイザックが出て来た。
エクスはその姿を見ると呆れながらつぶやいた。
「まったく」
「まったく、はこっちの台詞だ。「劇場版ASCP 最後のジ・アース人」のエンドロールだったんだぞ」
エクスはそれを聞いて、さらに呆れ顔になった。
「エンドロールだったら別にいいだろ」
「エンドロールを最後まで見て映画を見た、って事になるんだよ。で、何のようだ?」
アイザックは反論した後、映画人アイザックから艦長アイザックに戻った。
「あ、そんなにたいした用事じゃない。丁度帰還する頃には入隊試験が行われている最中だろうから、
すぐにその中で将来性のある新人を雇う。だから、部屋を空けておいてくれ」
エクスのその言葉を聞いて、アイザックはブリッジ中央にあるキーボードをいじる。
すると今まで航路が表示されていたスクリーンが部屋の配置画面に切り替わった。
「エクス、この分隊は5人で形成されてるんだ。25人に個室を用意できる専用軍艦なんだから、
空いている部屋ならたっぷりとある」
スクリーンには5×5の枠に1から25の数字がふってあり、11個の部屋が使用中とマークされている。
21小隊5人と、乗組員6人の部屋である。
「この船は人気がないのか?」
エクスが笑いながら言う。
「君の小隊が人気ないんじゃないか?」
アイザックも負けじと返す。エクスは適当に使用中ではない”4”の部屋を指さした。
「この部屋を空けててくれ。」
そういってエクスが立ち去ろうとしたが、アイザックがそれを止めた。
「いやダメだ。この部屋は今ゴミ置き場になってるんだ」
エクスはそれを聞いて、呆れながらスクリーンの前に戻って来た。
「・・・じゃあ、この”11”の部屋を空けててくれ」
「ダメです。そこは俺のプラモ置き場になってます」
今度はロックが口を挟む。
「ならどの部屋なら空いてるんだよ」
エクスが呆れながら聞くと、アイザックは淡々と呟いた。
「空きはゼロかな」
アダムは<クラッシュ>内を歩いていた。
ここは地下の貨物倉庫などのある区域で、ほとんど使用されていない。
しかし、アダムはここを利用する1人の人間に会いに足早に廊下を歩いた。
そして一つの扉の前に立つ。扉には「極秘!入るな!」の文字が書いてある。
しかし、アダムは扉の脇についているインターホンを押した。
「おい、俺だ、アダムだ。いるんだろ?」
アダムがそういって返答を待っていると、すぐに扉が開いた。
「手を上げな!」
中から現れたアダムと同年代ほどの、そしてアダムと同じく赤毛の女性が銃をアダムに向けながら叫んだ。
「手を上げないと撃つぞ!」
アダムは笑いながら返答する。
「またお前は・・・何をやっているんだ」
アダムがそう答えたとき、女性の方が引き金を引いた。
さすがのアダムも無意識に反射行動をとる。
しかし、発射されたのは白くて滑らかな・・・生クリームだ。
「うわ!!!」
甘い生クリームがアダムの顔に噴射される。
「ハハッ、びっくりしたでしょ?」
女性のほうが笑いながら銃を降ろした。
アダムが顔についた生クリームを払いながら、呆れたように対応する。
「全く・・・だからお前はいつまでたっても男ができないんだ、リーナさん」
からかうようにアダムが言うと、リーナと呼ばれた女性が無駄にリアルな生クリーム発射専用の銃を腰につけた。
「あんたには関係ない。それに、私は男に困ってないしね」
リーナはそういってアダムを眺める。
「ふんっ、お前ってやつは」
「ところで、何の用?」
アダムは気を取り戻し、わざとらしく咳払いをしてから答えた。
「ああ、ここ5日間、ブリッジにもレインさんのところにも顔を見せない。それに、さっきの壁に穴があいた
緊急事態のときもブリッジには来なかったじゃないか。連絡はしたはずなのに。そんなに熱心に何かを作っているのか?」
アダムの質問に、リーナは部屋の中へと歩きながら話し出した。
「私は今すごいものを開発しようとしているの」
部屋の中は研究器材や多くの金属、そして銃や何に使うか分からない液体やコンピュータが所狭しと並んでいる。
ここは第21小隊専属の技術者、リーナ・カトスの研究室なのだ。
「で、そのすごいものって」
アダムがリーナの言う”すごいもの”を探す。
「まだ企業秘密よ。誰にも見せたくないの」
「お、そいつは失礼」
アダムが小さく笑いながら言うと、リーナは別のものを取り出した。
細長い銃、スナイパーライフルだ。
「それより、これを改良したわ」
このライフル、アダム御用達のスナイパーライフルである。
アダムがそれを手に取る。
「ほぉ・・・で、どこをどのように改良したんだ?」
「まずスコープに温度感知センサーをつけたわ。これで、暗闇でも獲物を的確に狙撃できるようになった・・・
そして銃の反動をさらに軽減してみた・・・ってところかな」
リーナが自信たっぷりに解説する。
アダムは銃を構え、スコープも覗いてみる。
「一応聞くが、これはレーザーを発射できるよな?まさか火薬式じゃないよな?」
それを聞いたリーナは顔を真っ赤にして怒り出した。
「そんな一世代前のライフル、私じゃなくても改造できるわよ!」
アダムはそれを聞いて笑い出した。
「さすが対人用レーザーを開発してブラスターライフルを製作したカトス家の子孫なだけあるな。
弾丸は過去の産物ってか」
「そのとおりよ、いまどきそんなのを使っているのは、地球産の技術製品を使わないのと同じよ」
むきになるリーナを、さらにアダムが笑う。
「そんな技術の最先端の星と同じレベルなのかよ、お前さんは」
アダムがそういうと、リーナがまた生クリームピストルをアダムに向ける。
「当たり前でしょ。あたしのデータ容量は100キロバイトなんだから」
そういって生クリームをアダムに吹っかけた。
「それってそんなに多くない・・・って、お前なぁ!」
2人の仲をザックが敬遠する、こういうことである。
ロイは立ち尽くした。
惑星リカルアの宇宙船発着所へと着いたのだ。しかも一番大きな発着所に。
彼はヴァーノンから乗ってきた長距離船を降りて、発着所内にいた。
人やエイリアンが歩き回り、小さなカフェや飲食店もある。
ロイはしばらく圧倒された後、慌てて時計を見た。
ヴァーノンから出発してリカルア到着は入隊試験の12時間前に着くように計画していたのだ。
丁度試験当日、しかも12時間前に、計画通りリカルアに着くことができた。
「よし、では本部に試験希望願書を出しにいきますか・・・」
ロイはターミナル内を歩き、リカルア地上行きのタクシー乗り場へと足を運んだ。
100台ほどのタクシーが大きなハンガーにとまっている。もちろん宇宙にあるここを出発して地上のSSF本部にと向かうので
タクシーといえど地上を走るものでなく小さな宇宙船である。
「お客さん」
どれに乗ろうか迷っていた所、後ろから声をかけられた。
「!!・・・はい!」
「SSFの本部に向かうんだね?」
振り返った先にいたのはもろにタクシーの操縦士であった。
「はい、どうして分かったんですか・・・」
中年の操縦士はロイの手を指差す。
「その”SSF入隊のご案内”を持ってたら誰でもそう思うよ。しかも今は、そのシーズンだしな。
私のタクシーに乗せるよ。よかったらですけど・・・」
そういって操縦士はタクシーに乗り込んだ。ここは断るわけには行かない。
「はい、ありがとうございます」
ロイはそのタクシーに乗り込んだ。
10秒後、「では、発進」という合図でハンガーからそのタクシーは飛び立った。
―戦艦<クラッシュ>
「で、こんなになっちゃった・・・ってことか」
ザックがアダムと一緒にシャワーを浴びながらいう。
「そう、あいつ加減を知らない奴で・・・」
アダムは顔についた生クリームを熱いシャワーで落とすと、大きな湯船に向かっていた。
そして湯船の中のお湯を確かめる。
「・・・うん、今日は”KUSATHUnoYU”か」
アダムはお湯、もとい温泉の名前を分析した後お湯に浸かった。
ザックもシャワーを止めて湯船に飛び込む。
「うはぁぁぁぁぁ!いいねぇぇ!イオンパックなんかじゃ味わえない、体もきれいになる、心もキレイになる、
温泉っていいね~。滅多にないんだよな?温泉って」
ザックがテンション高めで尋ねる。
「確かに。リカルアには温泉はないし、俺の故郷にもなかったな。とはいえ高級品の温泉の素を買って
楽しむまでのもんじゃないしな。」
「この温泉の素をいちいち本場から取り寄せ、こんな大きな湯船まで作ってしまう・・・アイザック艦長は男の鏡だぜ!」
ザックは湯船で興奮気味に言いまくる。それに対し、アダムも笑みを作りながら話し出した。
「この常時適温を保つ湯船といつまでも清潔なお湯を生み出す浄化装置を作った、リーナも褒めてくれないか?」
その言葉に、ザックはニヤニヤとアダムを見た。
「ほぉ、アダムさん、リーナちゃんをごり押ししますね。やっぱ、彼女は特別あつk・・・」
「ちょっと待て、どういう方向でそういう話になるんだよ」
アダムが言うが、ザックはニヤニヤ顔のままアダムをじっと見つめる。
「だって、お前ら生クリームをかけあう仲なんだろ?」
「かけあってはないぞ。かけられただけで・・・」
「いやいや、俺が思うにお前らは・・・」
~~~妄想の世「やらせないぞ!」
アダムがお湯、もとい”KUSATHUnoYU”をザックの顔にかけた。
「ちょいwww」
「だからお前は女ができないんだ」
|
|
|
『何を!出会いがないからだ!見つければ、俺は相手を一発でしとめるぜ!』
「いやぁ、若いっていいな」
アイザックはブリッジにある自分の椅子に座って、モニターを眺めていた。
そこには男湯のザックとアダムの中学生のようなやり取りが映し出されている。
「ザック、もうチョイ右に動いてくれないか・・・そう、それでいいんだ」
「艦長、エクスさんが皆でレインさんのバーに・・・って艦長、また見てるんですか!」
何も知らずに入ってきたナリがアイザックの見ているそれを見て顔を背ける。
「ああ、この2人のやり取りは面白おかしくてな・・・で、何のようだ?」
ナリは今のせいで赤く染めた顔を上げると、早口で喋りだした。
「えっと、その、エクスさんがレインさんのバーに集まって、作戦会議をしようって・・・」
アイザックはモニターの電源を切ると、きれいに整えられている自分の黒髪を触る。
「分かった。今いくと言っててくれ。」
ナリははい、と頷くとブリッジを後にした。
残されたアイザックは近くの鏡で髪の毛をセットしてブリッジを後にしようとした。
しかしそのとき、電子音が鳴った。
「・・・なんだ?」
アイザックが電子音のしたほうに歩く。
見ると本部からのメールであった。アイザックはそれを見て目を丸くした。
「何だと・・・」
アイザックはそういってコネクターを取り出すと、なにやらボタンを押した。
するとメールが一瞬で彼のコネクターへと移動する。
そしてアイザックはブリッジを後にした。
「アレがSSFの本部だ。じゃ、向かうぞ」
ロイを乗せたタクシーは大気圏を抜け惑星リカルアの空域に入った。
そしてロイはタクシー操縦士が指差した、SSF本部を見つけた。
「マジで浮かんでる・・・」
この前ネットで調べたとおり、SSF本部は上空に浮く球体である。
その球体は、直径はゆうに1000mはある。
まさに星や要塞が浮かんでいるように見えるが、こここそが、特殊部隊”SSF”の本部である。
その後、タクシーは球体の側面にあるシールドを抜け内部のハンガーへと入った。
「よし、ここからは部外者は入っちゃいけないんだ。では、入隊試験、頑張るんだぞ」
ロイは操縦士にお金を渡すと、巨大なハンガーに降りた。
どうやら関係者以外が本部に入る際のハンガーらしく、機材の業者などが出入りしている。
「おい、お前」
そういう声が響いたのでロイは振り返ると、無精ひげを生やしたむさい中年男性がロイのことを手招きしていた。
「はい、なんでしょう?」
ロイは制服を着ているその男性をSSFの関係者だと判断する。
「お前はもしかして、入隊試験の希望者か?」
中年の男性がそう問いかける。ロイは迷いもなく頷いた。
「はい」
「ほぉ、全く、珍しい子もいるもんだな」
中年の男性がそう笑ったのを見て、ロイは首をかしげたが男性は気にもせず続けた。
「分かった。ならついて来い、締め切りはもう1時間もないんだぞ」
ロイは中年の男性に連れられて騒がしいハンガーの隅に案内された。
【受付】という張り紙が張ってあり、カード挿入口がある。
「じゃあ、ここにプライバシーカードと入隊試験希望願書を記録したカードを挿入するんだ」
ロイは言われるがままに2つのカードを挿入する。
「これで君の入隊試験申し込みは完了だ。待合室に案内しよう」
ロイは再び中年男の後に続いた。
ハンガーでは船が出入りし、人が縦横無尽に歩き回っている。
「おいおい、こっちへ早く」
ロイはついきょろきょろ辺りを見回していたことに気づき、慌てて中年男を追いかけた。
しばらく歩くと、さきほどハンガーとは裏腹人気のない廊下に出た。
「この廊下を真っ直ぐいった突き当たりの部屋にいけ。君の番号は・・・」
男はそういってコネクターのようなものを取り出す。
「・・・えっと、210番だ。5番の部屋に入れ」
中年男はそういい残すなりどこかへといってしまった。
ロイは将来上官となるかもしれない人物の言う事を聞き、廊下を歩いた。
にしても人気がない。
多分、普段はあまり使われていない、それか今日だけは立ち入り禁止なんだろう、トロイは勝手に推測する。
そうこうしているうちに、彼は突き当たりにある部屋へとたどり着いた。
1から5までの数字がふってある。
ロイは5番の扉の開閉装置を押した。
「失礼します」
と、そこにいたのは筋骨粒々で、血の気の溢れる9人の男達だった。
「ウワォ・・・」
ロイは小さく驚くと、部屋にある机の前にある椅子に座る。
どことなく緊迫したムードが流れ、気まずい時間が過ぎた。
時計を見ると、予定されている試験開始時間まではあと30分はある。
この9人はいずれも入隊試験を受ける者たちなんだろう、と安易に予想はついた。
ロイはだんだん不安になっていた。
―戦艦<クラッシュ>
船にあるバーに、乗組員全員が集まった。
さすがに武器の実験開発に余念のないリーナもバーにいた。
「・・・ということだ。というわけで、本船はいやでも<マザー>へと向かう」
アイザックが出されたカクテルを飲みながら話す。
エクスは考え込んだ。
本当は、どんな新入隊員を獲得するか全員で話し合おうと思っていたのだが、緊急事態にもほどがあった。
「もう一度そのメールを見せてもらえます?」
アダムが進み出る。と、アイザックはコネクターをテーブルに置いて、あるボタンを押す。
すると、コネクターからホログラム形式で文字が浮かび上がった。
“緊急事態
反乱分子の”チェンジャー”からリカルア第3衛星のオリアへの攻撃予告が届いた。軍と相談して
SSFと軍で衛星オリアの防衛を固める事が決まった。リカルア防衛も考え、軍事力を固めるため
SSFの各部隊で任務中でないものは直ちに<マザー>へと帰還し、いつでも出撃命令を受けられる状態で待機せよ”
「もう一度言うが、これが本部から送られてきたメールだ。」
アイザックが念を押して言う。
「衛星オリアへの攻撃予告ねぇ・・・」
ザックが椅子にもたれながら呟いた。
衛星オリアとは首都惑星リカルアの周りを回る4つの衛星のうちの1つで農業プラントや都市プラントもある衛星である。
「困ったな。それで、入隊試験はどうなるんだ?延期か?」
エクスがアイザックに聞く。
「それも気になったんだがどうやらそれについては予定通り行うようだ。しかし、かなり簡略化されるらしい。
筆記テストと実力テストを2日で行うらしい」
「2日!?」
ザックがつい驚きの声を上げる。
「普通は1週間くらいかけて忍耐とかも細かく調べなかったか?」
「それが最高司令官曰く基礎のテストだけすれば十分、応用力は実践を重ねてからつける、
とか言う判断をしたらしいんだ。入隊希望者定員も半分に減らしたけど、結局その半分にも満たなかったらしい」
アイザックが淡々と述べる。
「え・・・去年の1000人から500人に減らして、半分にも満たなかったってことは・・・」
「ざっと200人前後・・・か」
メリルの呟きにベンが頷きながら付け足した。
「マジかよ。ま、統一軍の入隊希望者は上り調子らしいがな」
ザックが呆れたように呟く。
「とにかく、<マザー>に帰還してもうかうかしてられないってことだ。皆、気を引き締めていけ」
エクスがそう言って席を立つ。
全員が頷く。エクスがバーを後にしようとしたとき、アイザックが肩を叩いた。
「ちょっといいか」
―SSF本部<マザー>
先ほど、ロイを案内した無精ひげの中年男が<マザー>内のエレベーターに乗っていた。
手には資料を握り締めている。
「これで入隊希望者が210人になりました」
中年男がコネクターに向かって話している。
『1人増えただけでも定員には半分にも満たないのか』
「ですが最高司令官、今この状況下、200人も入隊すればありがたい戦力になりますよ」
中年男は静かに告げると、相手の最高司令官は静かに切り出した。
『おまえにはいうが、資金の問題もあるんだ。人数が減ると、政府からの援助金も少なく・・・』
「ちょっと待ってください。お金の話は今はしない方向で」
中年男が言うと、最高司令官のほうも渋々答える。
『来年の運営も厳しいんだ』
「・・・というと?」
『・・・つまりだ、いまいち政府には我々の実力がはっきりと届いていないように感じる。衛星オリアへの攻撃予告が
届いているだろ。これはSSFがメインできっちり防衛できれば、資金も上積みされるかもしれないし、
そうでなくても予算を上げるように政府に交渉する際のいい言い分になる。』
中年男は冷静にことを分析する。
「つまり今回の防衛作戦をSSF主体で行えたらいいな、という願望ですか?」
『ああ、そうだ』
男は皮肉っぽく言ったつもりだったのだが、最高司令官に軽く返された。
「そういうことねぇ・・・とりあえず、まずは入隊試験を行います。新たな戦力のために」
『分かった。では、頼んだぞ、ドルジ』
中年男ドルジは、コネクターを閉まって手に持った資料を眺めた。
ロイ・モース・・・滅多に例を見ない、運動神経と頭脳がどちらとも優れていて、なおかつまだ17歳・・・
(期待の新星か・・・期待しているぜ・・・)
そしてエレベーターが止まる。彼は開いた扉を降りていった。
ロイは机の上にペンだけを出した。
たった今配られた筆記試験の注意を読む。
なんか、やけにあっさりことが進んでいるように感じるが、あえてそこは気にしない。
部屋中にスピーカーで声が響き渡る。
『これから入隊試験を始める。まずは筆記試験だ。時間は60分、諸注意をよく読むこと』
ロイはもう一度その注意に目を通す。
―トイレは許可をもらって、カンニングはしない、声を発しない、まるで小学生だ。
しかし、その文章の最後にかいてあるものは違った。
―君たちは将来戦場に出るかもしれない、いつ死ぬかも分からない、それを受け入れられないものは直ちに退場する事。
ロイはそれを見て気を引き締めた。
この筆記テスト、標準語や科学、歴史など基礎的なものから銃や武器の名称、また戦場での応用力をためす
質問などもありなかなかの難関であるというもっぱらの評判である。
心の中で今までやってきたことを整理しながら、ロイは筆記試験に挑んだ。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 月のボイドタイム(2025年12月)
- (2025-11-28 09:00:05)
-
-
-

- 懸賞フリーク♪
- ジョージア×Adoコラボ コラボグッズ…
- (2025-11-28 12:19:34)
-
-
-

- ★資格取得・お勉強★
- 令和7年度宅建試験 合格発表 デー…
- (2025-11-26 23:43:33)
-
© Rakuten Group, Inc.