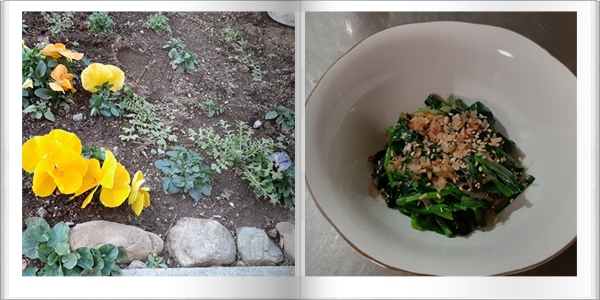『Pure Diamond』
偶然キリ番を踏んだ「ムッティ138」さんからいただいたのは、「海」「ダイアモンド」「からかう」のキーワード。それをもとにこの『Pure Diamond』が完成しました。題名はムッティさんに付けていただきました。ちょっと長くなっちゃいましたが、それなりには仕上がっていると思います。よければ読んで見て下さい。(狼)
プロローグ
もう10年前の話になる。
私は、小学校の高学年だった。
その時の担任の先生の宿題で、「お父さんとお母さんに結婚した頃の話を聞いてくること」というのがあった。
今だったら、「家庭環境が複雑な子への配慮は?」などと文句でも言われそうだが、当時はまだそんなに世間は口やかましくなかったし、私の住んでいる田舎町にはそれほど家庭が複雑な子もいなかった。
とにかく、その宿題を受けて、私は父と母に「どうして結婚したのか」というダイレクトな質問をしたのだ。
そして、それがきっかけで私は父と母のちょっとした秘密を知ってしまった。そして、その時知り得た秘密はまだ10年経った今でも私の胸の中にしまってある。
第1章『父の話』
「最近の小学校の宿題ってのは、凄いんだな。みんな、家で親に『どうして結婚したのか』なんて質問をしてくることになってるのか?」
「ううん。絶対そういう質問じゃなきゃだめってワケじゃないけど。私が、そう聞いてみたかったの。だから教えて。」
「お父さんとお母さんはどうして結婚したの」という突然の質問に照れくさそうな父。照れ隠しかどうか分からないけれど、空のグラスにビールを手酌で注ごうとするが、もう飲み干してしまったビール瓶からはむなしく滴が2、3落ちただけだった。
「もう一本どう? 私が取ってきてあげる。」
どうせ話を聞くなら、しっかり聞きたいし…。父は飲むとおしゃべりになるのだ。
いつもなら母に「一本だけ」、と決められているビールであるが、今日は特別である。母は、婦人会の催しでちょうど一泊二日の温泉旅行に出かけているのだ。
最初は父と母が一緒にいる時に尋ねようかと思ったが、それじゃあ面白くないと思い、別々に聞くことに決めた。そういう意味では、今日は絶好のインタビュー日和だった。
私が、「はいどうぞ」とお酌をしてあげると、父も嬉しそうに、
「それじゃあ、話してやるか。」
と、座り直すとグラスのビールを半分ほど飲み干した。その後しばらく、何処と言うこともなく虚空を見つめていたが、突然こんなことを言い始めた。
「これから話そうと思うことは、母さんに内緒の話なんだけど、お前、絶対に母さんには言わないって約束できるか」
と、父は急に真剣な表情で私を見つめる。顔はアルコールのせいか、ちょっと紅潮している。でも、目はしっかりと焦点があっていた。
「約束って、もちろんそれは守るけど、小学校の宿題なんだからさ…全部は内緒にできないかも…。」
「そうか、じゃあ学校では、当たり障りのないことだけ言っときなさい。」
どうやら、父はその「内緒話」を、私に話したそうな雰囲気を醸し出していた。
「分かった。約束する。学校でも内緒の部分はうまく言うから、教えてお父さん。」
既に空になっているグラスに私はまた一杯お酌をしながら、嬉しそうな父を眺める。
「…実はな。父さんが、母さんにプロポーズしたのは海岸だったんだ。」
父の、いきなりの核心めいた話始めに、ちょっとたじろいだ私だったが、そこはすかさず、合いの手を入れた。
「へえ。お父さんやるじゃない。意外にロマンチストだったんだ。」
「おいおい、『意外』ってのは余計だよ。…それでな、その時大失敗があったんだ。」
「『大失敗』って、どんな? 『大成功』じゃなかったの?」
「結果的には巧くいったんだけど、…その時は大変でな。」
父は、どうやら母を連れて海岸を散歩しながらプロポーズしたらしいのだが、その時、言葉と一緒にダイヤモンドの指輪を渡したのだということだった。そして、その時、よりによってその指輪を砂浜に落としてしまったということなのだ。波の打ち寄せる浜に…。
「何でそんな大事なモノを、落としちゃうワケ…。」
「いやいや、ちょっと父さんが格好つけすぎちゃったんだよ。靴を脱いで波打ち際にいた時、『今しかない』って思ってな。ポケットから指輪の入った小箱を出したんだ。それで、母さんに。『これなんだけど』って箱から指輪を取り出してな。…プロポーズの言葉と一緒に渡したんだ。」
父はちょっと照れくさそうな顔をした。が、そこは追及のしどころだ、私は立て続けに質問を浴びせた。
「で、プロポーズの言葉は何だったの? お母さん、どんな顔してた? で、何で落としちゃったのよ?」
「まあ、そんなに慌てるなよ。」
私をじらしているのか、父の話し方はいつもよりゆっくりだった。
「プロポーズの言葉はな、まあ…月並みだな。『これ、受け取ってくれないか』ってさ。…で、母さんはというとな…うーん。…普通だったな。」
「『普通』ってよくわかんないなあ…。あ、分かった。お母さんの反応が悪かったんで、お父さん舞い上がっちゃったんじゃないの? それで渡すときに手が震えて落としちゃったとか…」
その時、ちょうど時計が8時を告げた。父は、遠い目をして時計を眺めていたが、時計が鳴り終わると再び口を開いた。
「違うんだ。その時、突然の父さんの行動に、母さんは幾らか驚いていたけれど、指輪はちゃんと受け取ってくれた…。」
「じゃあ、そこで、指にはめて、『ぴったりだわ』ってワケに行かなかったの?」
「うーん…。母さんも、ある程度は察してはいたかもしれないけれど、やはり急だったんで驚いたんだろう、でも、反応はそんなに悪くはなかったぞ。『綺麗だね』って言いながら、暫く指で持って眺めていたんだよ。」
「それで?」
「うん。その時にな…ちょっと大きめの波が来て、足に水がかかってね。母さんは驚いた拍子に指輪を波打ち際に落としちゃったんだ。」
「えーっ!! それで?それで?」
「それは慌てたよ。小さいけれどダイヤモンドだからな。波がかぶさっちゃってさ。」
「で、見つかったの?」
「それは探したさ。1時間以上は探したと思うぞ。何せ、夕方だったからな。だんだん薄暗くなってくるし、しかも満ち潮で、波はどんどん大きくなるわで、もうずぶ濡れだったな。母さんも最初は一緒に探してくれてたんだけど、『体が冷えるから、僕が一人で探す』って言って…、父さんが探す間、ずっと母さんは岩に座って海を見てたな…。」
私は、思わず「お母さんが見てたのは『海』じゃなくて『お父さん』じゃなかったの?」って突っ込みたくなったけれど、そこはちょっと自制した。
「結局どうなったの?」
「見つからなかった。」
「じゃあ。『大失敗』じゃない。」
「だから、『大失敗』って言ったじゃないか。」
「あ、そうか…。でも、お父さんとお母さんは結ばれたんでしょ?」
「そうなんだよ。」
「…じゃあ、前お母さんが見せてくれたあのダイヤの指輪は2つ目だったりするワケ?」
「いや。それがな。…出てきたんだよ。」
「えーっ。ウソみたいー。波打ち際で落とすと見つかんないよ、普通。」
父は、私の真剣な顔を見ながら、とても嬉しそうな顔をして、またグラスのビールを一口ゴクリと飲み下した。まるで、私の反応を肴にするみたいに。
グラスについた水滴が父の手をつたい、ポトリと落ちてテーブルの上で静かにはじけた。
一時間以上探しても出てこなかった指輪が出てきたなんて、とても信じられない話だと思い、ピーナッツを齧りながら微笑んでいる父に私は言った。
「…まさか、その後買った魚の腹から出てきたって、おとぎ話みたいなことなんてないよね。」
「だったら、もっとロマンチックだったんだけどな。いやいや。現実は現実だよ。…それから暫くしてな。母さんから電話があったんだ。『会いたい』ってな。最初は理由を言わないから、父さんはてっきり結婚を断られるものだと思って、しょぼくれて待ち合わせの喫茶店に行ったんだ。」
「そしたら、OKだったってワケね!」
「そうなんだよ。」
父の話によると、指輪は何と母のズボンの裾から出てきたのだそうだ。何とそれは、波打ち際で、濡れないように折り返していたジーンズの裾に入っていたらしかった。私は父を待っている間、それに気づかなかった母も母だと思ったが、父の話はもちろんそれだけではなかった。
それで、何も知らずに待ち合わせの場所に、暗い顔して出かけて行った父が見たのは、しっかりとその指輪を薬指にはめて照れくさそうにしている母の笑顔だった…というのが、父の話であった。
そこまで聞いて、私は何だかとってもハッピーな気分になっている自分に気が付いていた。
「なるほどネ。」
「知らなかっただろう。」
「うん。お母さんからも聞いたことなかった。…でも、どこが『秘密』なの?」
「…そうだな。確かに…じゃあこれで止めておこう。それがいい。」
「えーっ。ズルいよ。ズルい。ズルい。」
父は、私をおちょくっていたのか、本心だったのかは定かではないが、私があまりしつこいので、というか、やっぱり「約束は約束」だったので、父は続きの話をしてくれた。
「実はな。…うーん。これは絶対内緒だからな。」
「分かってるって。絶対内緒。」
「実はな、そのダイヤって偽物だったんだよ。」
父のその一言で、それまでの私の幸せな気分は一度に消し飛んでしまった。
「え~っ。ヤだ~そんな~。」
「そうなんだよ。…その時どうしても父さんはお金が工面できなくてな。でもな、父さんはその時、必ずいつかは本物を母さんに渡すと自分に誓ってたんだぞ。言い訳っぽいけど…。」
「でも、それじゃあお母さんが可愛そう…でも、じゃあ…お父さん、その偽物をずぶぬれになりながら1時間以上も探してたってワケ…」
「それはそうさ。だって父さんにとっては本物と同じぐらい大切なものだったんだぞ。台座にはしっかりメッセージも彫り込んでもらってたしな。」
父はその時のことを思い出していたのか、グラスに付いた水滴を指先でもてあそびながら、また遠い目をしていた。そして、また我にかえったように話し始めた。
「お前、そう言うけどな。父さんも必死だったんだぞ。母さんはな、父さんには話していなかったけれど、その時誰か他の人からも結婚を申し込まれていたようなんだ。その辺りは定かではないんだけれど、もしそうだとしたら一大事だろ。ぐずぐずしてたら他の人の奥さんになってしまう可能性もあったんだからな…」
「ふーん。でも…、お父さんとお母さんって付き合ってたんじゃないの?」
「その辺りが微妙だったんだよ。」
「ほんと、良くわかんないナ…。」
小学生だった私には、まだ男女の機微なんてものはちょっと理解しがたかったのかも知れない。でも、このお話は必ずハッピーエンドになるって分かっているのだから、私は安心して聞いていた。
「でも、よかった。もし、お母さんが他の人のトコに行っちゃってたら、私もこの世に生まれて来なかったってコトだもんね。」
「そうだ。父さんに感謝しろよ。」
「もうー。やだなー。」
父は急に元気になり、最後の一杯をぐいと飲み干した。私はすかさず尋ねた。
「で、今母さんが大事にしているあの指輪って本物なの?」
「当たり前だろ。それは、父さんの『誓い』だったんだからな。あの後、必死で工面して、お金が用意できたらすぐにこっそり本物にしておいたってワケ。」
「それって結婚式の前?後?」
「…もういいじゃないか。」
と、父はそれから後の言葉を濁してしまい、お風呂へ行ってしまった。
確かに、私にとってももうそれ以上は父に聞くことはなかった。それでも、父と母の意外な「なれそめ」を知った私は、妙な満足感に浸ったのだった。どうあれ、父と母はそうやって結ばれて、今の我が家があるのだから。決して悪い話ではないな…って。
父の残したつまみのピーナッツを2、3粒口に頬張ると、私はそれを気持ちよくかみ砕いて、母のいない台所の片付けを始めた。いつもなら億劫なはずのお皿洗いなのに、今日はとっても幸せな気分だった…。
第2章『母の話』
私が母に、父と同様の質問をしたのは、父から話を聞いてからちょうど一週間後であった。今度は父が出張で不在だった。
母は、父ほど動揺することはなく、「同じ職場で、真面目ないい人だと知っていたからプロポーズを受けた」と、最初は当たり障りのない話をした。その時の母の雰囲気から、このままだと、「父と母の結婚」の核心には迫れそうにないので、私はズバリ尋ねることにした。
「お母さん。プロポーズの時に貰った指輪の話して。」
私は、そこでてっきり母の動揺する顔が見られるのでは、とちょっぴり期待していたのだが、母はそれほど顔色を変えることもなく、私の顔をじっと見ながら「ふーん」と一言口にしただけだった。
母は、既に私が父から何か聞いているということを鋭く察知したようだった。そして、「そうね…」と言った後、暫く父と同じように、遠くを見るような目をしていた。
「私とお父さんにとって、あの指輪はとても大事なものなのよ。あの指輪がなかったら、きっとお父さんと私は結婚していなかったかも知れないんですもの…。」
これまたいきなり核心である。私は「ラッキー」と思い、母が父との結婚を決心したことの、より核心部分に迫りたくって、すぐさまツッコミを入れた。
「『指輪』って、前見せてくれたあのダイヤの指輪でしょ? やっぱり高価なもの貰うと嬉しいものなんだね。」
「ううん。『高価』とかそんな事で決めた訳じゃないのよ…。」
母の返答は、ちょっぴり私を非難するような調子を含んでいた。しかし、私は自分の投げかけた野暮な質問を省みるよりも、それに対して発せられた母の「そんな事で決めた訳じゃない」という言葉に反応して、胸が「ドキリ」としていた。
父の感じだと、母が「偽物」の話を知っているとは考えられない。でも、…ひょっとして母は真実を知っていたのかも…。まさか、じゃあ…父と母が共同して私を騙そうとしている…。いいえ、それは考えすぎ…。
母と私。胸の内は全く異なっていたであろうが、二人とも暫く黙っていた。
そして、その瞬間母が見せた顔を、私は忘れられない。
私が、ドキドキしながら横目でそっと覗き込んだ母の顔は、怒った顔でも悲しそうな顔でもなかった。何と、そこにはとても幸せそうな微笑みが溢れていたのだ。 それは、それまで私が見た「母」の笑顔とは全く違う…今思えば、母はその時、きっと「女性」の顔になっていたのだろうな、と思う。
…きっと、しょぼくれて待ち合わせ場所に行った父が見た母の顔はこんな顔だったのだろう…そんな素敵な微笑みだった…。
私は続けた。
「じゃあ。お母さん、決め手はなんだったの?」
「そうね。うまく言えないけど。やっぱりお父さんの人柄かな…。」
「ふーん。でも、お母さん、さっき『指輪がなかったら』って言ったじゃない…。」
「…あのね…」
母がその後してくれた話は、ほぼ父のそれと同じだった。指輪を波打ち際に落としてしまい、一緒に探したことなど、細部もぴったり一致していた。
「お父さんね。本当に一生懸命探してくれたの。最後には全身、波をかぶりながら…。私には『風邪をひいたらいけないから』って一人でね…。」
「で、見つかったの?」
私の問いかけに、母は一瞬怪訝そうな顔をした。きっと、そこは私が父から話を聞いていると思ったのだろう。しかし、母はそこで敢えて私に問い返すことはしなかった。
「うん。諦めて家に帰った後でね、お母さんのズボンの裾に引っ掛かってたのが分かったの。」
「もーっ。お母さんったらドジなんだから。やっぱり当時からおっちょこちょいだったんだね。…じゃあお父さん、見つかりっこない指輪をずっと探してたんだ…。」
「そうなの。お父さんには悪いことしちゃったの。でね…。」
そこで母が話を止めたので、私はまた「偽物」の話を母が知っているのかと疑ってしまった。ところが、母が継いだ言葉はまた違う意味で意外なものだった。
「私…、その時…本当に一生懸命に指輪を探しているお父さんの姿を見ててね。『この人と一緒になろう』『この人となら幸せになれそう…』って思ったの。」
「へえー。じゃあ。指輪が出て来なくても、返事は『OK』だったってワケだ。」
「そうね…。」
そこで、母はまた幸せそうな微笑みを浮かべた。
私は、母はやっぱり「偽物」ってことは知らなかったんだ、とほっとした。そして、母はその時やっぱり「海」ではなく「父」を見ていたのだと…。
「じゃあ、プロポーズの時には、まだ迷ってたんだ…。どうせなら、すぐに指にはめてあげれば落とすこともなかったんじゃない?」
自分でも、我ながらあの質問は野暮だったなあと思うが、小学生の私は敢えてそんな質問をしたのだった。もちろん、もう少し話を核心に近づけたかったからなのだが。
「そんな簡単なものじゃないわ。お母さんにも色々あるのよ…。」
私は「来た!」と思った。父も感づいていた「第三者」の存在が母の口からもほのめかされたのだ。そこで、私はここぞとばかりに
「えー。お母さんモテたんだ。ひょっとして、お父さん以外に好きな人がいたとか…。」
「ううん。好きな人がいたって訳じゃないんだけどね。」
「あーっ。じゃあ、誰かに告白されてたとか。」
私は子どもの無邪気さを武器に母を遠慮無く攻撃した。しかし、母は、別に怒るでもなく、優しい口調で答えた。
「もう…どうでもいいことなのよ。お母さんはお父さんを好きになって、お父さんと結婚したのよ。だからあなたが生まれたのよ。それでよかったのよ。」
母の言葉は静かで、重みがあり、それでいてあたたかかった。私はそれ以上母を追及することができなくなってしまった。
結局、父と同じで、「今が幸せだから」って。そういうまとめ方になっちゃうのかな…ま、それもいいかな…、と、私は納得しようとしていた。ところが、何と、母の方からもっと話を広げる言葉が出て来たのだ。
「あの指輪なんだけどね。あれは母さんのとってもとっても大切な宝物なのよ。」
「知ってるわ。ダイヤモンドなんだよね。」
私は、母が勿体をつけて言う割には、普通のことだなあ…って、その時は思った。そして、話題がもとの話に戻るような方向に行ったことにもちょっぴり戸惑っていた。ところが、母がそんなことを言うからには、まだ何か聞き出せるかもしれないと思い、「うんうん」と相づちを打って、そこはしっかり話を合わせた。
やはり、母は続けた。
「別にダイヤモンドだからって訳じゃないのよ。あの指輪は特別なの。」
「そうね。あの指輪がきっかけでお父さんとお母さんは結ばれたんですものね。」
「そうよ…。だから、別にダイヤだからって…関係ないの。」
妙に母の言葉が含みを持っているので、私は当惑した。「えーっ。やっぱりお母さん『偽物』だって知ってたのかも…。まさか…。」
私は、母のその言葉にどう切り込もうかと迷っていた。すると、また母が言った。
「あなただけには…話しておこうかしら。…これから話すことは、絶対にお父さんには内緒にできるって約束できる?」
私は心の中で「えーっ」と叫んでいた。父の話はともかく、母からも「秘密」の話が聞けるなんて、何てことだろう。瓢箪から駒?棚からぼた餅?…私の知っていることわざでは説明しきれない展開だった。
「もちろん。絶対言わない。約束する。」
私は何としても母からその「秘密」の話を聞き出そうと、必死で力強く答えていた。
「あの日ね。指輪がなくなった日…。お母さん、知らずに指輪を洗濯しちゃったのよ。洗濯機の中でカラカラ音がするから、止めて調べてみて、それで気がついたのよ。」
「へえ。そうだったの。裾を折ったジーンズをそのまま洗濯機に入れちゃうなんてさすがお母さんね。」
「もう、いやね。ちゃんと入れる前に戻したわよ。でも、ドラムの中で戻したから気が付かなかったのよ…。」
「いいわ…。それで?何が秘密なの?」
「指輪が見つかった時は、それは嬉しかったわ。でもね、実は指輪がドラムの中でかなりころがっちゃったみたいで、台座の金具が少し歪んじゃってたのよ。」
私は、母がそれで指輪が「偽物」だと気づいたのかと思ってどきどきしていたのだが、指輪が少し壊れただけのことだったのか…。とホッとしてしまった。でも、やはり小学生だった私は浅はかだった。何故って、その次の展開を考えれば、当然ドキドキは続くはずだったからだ。
「それでね。お母さん、お父さんに内緒でその指輪を直しに行ったのよ。」
私の頭の中でその時初めて「ガーン」と音がした。分かった。そこで母は知ってしまったんだ…。私は波立つ心を必死で抑えながら、何気ない風を装い、震える声を抑えつつ「ふーん。」と相づちを打ち、次に出てくる母の言葉を待っていた。
「その時直しに行った宝石屋さんでね…」
母は口ごもった。そこで、私は仕方なく尋ねた。
「そこで、…何があったの。」
「その指輪がね…、『偽物』だって言われたのよ。」
私は、予想していたとは言え、やはりショックは大きく、やっとそれまでしていた「演技」を止めることが出来た。そして遠慮無く大きな声で言った。
「そんなー。信じられないよー。」
誰を非難していいのか分からないけれど、とにかくその時の私の胸の内にはもやもやが充満していた。そのわだかまりをぶつけるべく、私は強い調子で言った。
「何で偽物なのよー。」
強い調子の私の言葉に、母は言い聞かせるように静かに話を続けた。
「あのね…。お母さんがどうしてこんな話をするか分かる? お母さんはダイヤなんかどうでも良いって言ったでしょう。お母さんは、お父さんが好きになったのよ。だからあの指輪はその気持ちの『証し』なの。だから…それならそれでいいの。」
母の言葉には説得力があった。でも、私は続けた。
「分かるわ。でも、お父さん、何でそんなことしたのかな…。」
私は父から聞いた話を頭の中で反芻しながら、再び必死で母に話を合わせようとしていた。今更父と母がどうこうなるはずもないという気はしていたが、やはり何かが自分の中で壊れそうな気がして小学生の私は必死になっていた。
「そうね。分からないけど、ひょっとしたらお父さん騙されてたんじゃないかなって思うのよ。」
「えーっ。騙されたって、誰に?」
「よく分からないけど、宝石ってよくそういう話があるじゃない。」
母が続けた話によると、母は指輪を直しに宝石店に行った際に、父がくれた箱も持って行ったそうであった。そして、その箱にはきちんと鑑定書もついていたというのだ。ところが、宝石店の店主は、ダイヤをしっかりと鑑定した上で、鑑定書も、石も偽物だと言い切ったというのだ。
しかし、実のところそれは当然そうなのだ。父が母に渡したダイヤモンドの指輪は正真正銘の「偽物」であったのだから。ダイヤが偽物で、鑑定した宝石店の人の目が本物だったということに間違いはないのだ。
ただ、そこまで聞いた時、私の心は妙に静まっていた。そして、ただ、私は嬉しかった。母の、父へのその気持ちが嬉しかったのだ。
「きっとそうよ。お父さん、人が良いから騙されて偽物を持たされてたのよ。」
「そうよね。お母さんもそう思うの。だからね、ダイヤモンドとしての価値なんかどうでもいいのよ。大切なのは気持ちだから。…あのリングの内側には、きちんと『from M to Y』って彫ってあるのよ。『お父さんから、お母さんへ』って意味なの。だからそれでいいのよ。」
やはり、母の言葉は静かで強く、そしてあたたかかった。
小学校の頃ってイニシャルに妙に惹かれてしまうもの…。私は、ロマンチックな気分に浸って、その時父と母をとっても羨ましく感じていた。
…でも、それと同時に私の心の中にはふつふつと湧き上がるものがあった。
今は「本物」になっているその指輪…それを母は知らない。母に、その指輪は「本物なんだよ」って何とかして伝えたい気がした。…しかし、いくら知恵を絞っても当時の私の頭には妙案は浮かんでこなかった。下手なことを言うと、却って父と母の思い出をダメにしてしまう…、それはその時の私の頭でも十分すぎるほど理解できていたのだ。
母は、満足そうに話を終えると、
「学校では余計なこと言っちゃダメよ」
と少し微笑みながら言った。もう、その時にはすっかり普通の「母」の顔に戻っていた。
私は母の立ち去った居間のテーブルに一人残されて、「発表用メモ用紙」と書かれた白紙の用紙をみつめながらぼんやりとしていた。
時計が、父の時と同じように8時を告げていた…。
第3章『宝石屋の話』
あれから10年の歳月が流れた。私は、結局父にも母にも「真実」を伝えることはできなかった。でも、それは仕方のない話だった。
何故って、考えれば考えるほど、結局自分が「何もしない」方がいいってことになるのだから…。
父と母は今も大変仲がよい。時折、私を置いて二人で外出する。そんな時、母はいつもあの指輪をこっそりと薬指にはめて出かけて行くのを私は知っている。
あのダイヤが本物だと知ったら、母はさぞかし喜ぶだろうな…。とつい思ってしまう私。父には、「あの指輪は本物なのに、お母さん『偽物』だと思い込んでいるよ」って教えてあげたい気がする。でも、やっぱり「今のまま」でいいのかな…。そして、やはりそういう結論になってしまうのだ。
10年前の懐かしい思い出を、今更のように記憶の隅から引っ張り出したのは、先日の母の言葉がきっかけだった。
数日前、私は22回目の誕生日を迎えた。母は、
「あなたももう結婚してもいい年頃になったわね。…覚えてる?いつか話したあの指輪のこと…。あの指輪ね、いずれはあなたにプレゼントしようと思ってるのよ。…きっと、あなたも幸せにしてくれると思うから…。」
もちろん、母は偽物だとか本物だとか、そんなことは関係なく、母にとっての『価値』において話をしてくれているのは分かっている。でも…、母はこう言った。
「まあ、あなたにとっては価値がないかも知れないけれど…」
その時の母の表情から、母の真意は読みとることができなかった。でも、その時、私はやはり母に、「あれは本物なんだよ」って教えてあげたくなってしまった。
私はその時の母の言葉に、消えかかったシミのような…、ほんの少しではあるが『翳り』のようなものを私は感じずにはいられなかったのだ。
私は、そんな母に言った。
「うん。是非ちょうだいね。私もお父さんとお母さんみたいな仲の良い夫婦になりたいもの。」
それは私にとって、心からの言葉であった。
母は、それを感じ取ってくれたのか、
「分かったわ。いつか、きっとあなたにプレゼントするからね。でも、あなたが結婚する時にはきっと『彼』の方から素敵な指輪を贈って貰えるんじゃないかしら。」
「それは…そうかもしれないけど、絶対ちょうだいね。きっと、その指輪の力で私たちも、守ってもらえそうだから。」
「えっ…。『私たち』って、あなた…、ひょっとして、もういい人いるの?」
「やあね。お母さんったら、そういう想定で話をしてるのよ。もう。」
楽しい会話だった。でも、私にとってはまた複雑に絡み合う「秘密」を思い出すきっかけとなった会話だった。そして、そんな母との会話があったので、私は再び10年前のことを思い出したのだ。
…それがきっかけで、私はある時ふらりと街の宝石店に立ち寄ったのだ。
その宝石店は、昔からこの街にある店で、自分が小さな頃からよく知っている店である。ただ、知っているだけで、中に入ったことはなかったた。…ひょっとしたら小さな頃、母に連れられて入ったことはあるかも知れないけれど、少なくとも物心ついてから入った記憶はない。
幾らか外見は古めかしくなっているものの、中に入ってみると、とても小綺麗で、部屋全体が光に満ちているような雰囲気さえあった。
サファイヤ、ルビー、真珠などがショーウィンドーの中でそれぞれの個性的な輝きを放っている。私は「どれも綺麗ね…」と、ありきたりなことを思いつつ、ぶらぶら見て回っていた。
そして、ちょうどダイヤモンドのケースの前まで来た時のことだ。
「失礼ですが、お嬢さん。あなたは…」
店主のおじいさんに突然話しかけられたのである。
最初は驚いたが、よくよく話を聞けば、そのおじいさんは私の父を知っているというのだ。つまり、当然私がその「娘」であるということも…。
「まあ、小さな街ですからな。店には入ってこられんでも、よくこの前を通る方の顔は、自然と覚えますからの。ほっほっほ。」
とても温厚そうな方ではあったが、あまりにも親しげに話をしてくるので、正直ちょっと不気味な感じもした。…けれども、とても品の良いおじいさんだし、こんな小さな町。実際私も小中高とこの店の横を通学路にしていたのだから、面識のあるなしにかかわらず、おじいさんが私のことを知っているというのも、別に変わったことではなく普通のことなんだろうな、と思った。
ただ、私は逆に「父」のことに興味が湧いたので、逆に質問してみることにした。
「あのー。でも…何で私が…『娘だ』って分かったんですか?」
私の質問に、店主は嬉しそうに、「ほっほっほ」と特徴のある笑い声をあげて目を細めた。そして少し通りを眺めるような素振りをしていたが、
「お前さんは覚えておられんでしょうが、…お前さんのお父さんがね。お前さんをこの店に連れてきたことがあったんですよ。まだ随分小さい頃でしたがね。」
私は、てっきり「母」の間違いではないかと思い、聞き返したが、店主が知っているのは「父」であり、それに間違いはなかった。
しかし。…父は、結婚指輪を買った時ぐらいしか宝石店に出入りしているはずはない…それに、私を連れて来たってことは…。
それって一体いつのことなんだろう…。私はすっかり考え込んでしまった。
店主は私の反応を楽しむように微笑みを浮かべると、彼は長年そうしてきたのであろう、カウンターの中の椅子に静かに腰を下ろし、また通りを眺めていた。
その時、私に「ひょっとしたら…」と、ある考えが浮かんだのだ。そして言った。
「ひょっとして、それは父が指輪を取りかえに来た時のことでしょうか…。」
その言葉を聞いて、店主の顔色が少し変わったのを私は見逃さなかった。
しかし、店主は微笑んで、こう言った。
「お前さん、…お父さんから話を聞いたのかな。…それは驚きました。ほっほっほ。」
そう言うと、店主は続けた。
「…いやいや、残念ながらお嬢さんの予想ははずれですな。ほっほっほ。お父さんが指輪の『交換』に来られたのはお買い求めになってから、それほど間がなかったですからな。…そうですな、お父さんが最初にやって来られた時から半年も経っていなかったかも知れませんな。私も『随分と早かったですな』って言ったのを覚えておるぐらいですからな。『1年以内』という約束でしたんですがね。…まさか、お前さんは生まれておられんでしょう。ほっほっほ。」
…半年。と言うことは…、当然私が生まれているはずがない。それにきっと、父のことだから、借りを作ったままではいけない、と頑張って何とかお金を工面したのだろう。…だとしたら…。私は再び問いかけた。
「御主人、その時…『私』幾つぐらいでした?」
「そうですな。よちよち歩きでしたからな、2歳ぐらいではなかったでしょうかな。」
どうやら、父は私一人を連れて、この宝石店に立ち寄ったらしかった。ただ、それがどんな目的だったのかはその時は少しピンとこなかった。
でも、先の店主の言葉と父から聞いた話を合わせて考えれば、父の「目的」が何かは自明のことだった。
父は、「お礼」にきたのだ。指輪のおかげで母とうまくいったこと。そして、結婚して、こんな「かわいい」娘ができたことを…。
私は、自分で「かわいい」って思ってしまったことにちょっと笑ってしまった。でも、「2歳の私はさぞかしかわいかっただろうな…」と、父に連れられてよちよち歩きでこの店を訪れた自分を思った。
そして私は言った。
「その節は父がお世話になりました。」
私がお礼を言うのは何だか変な気がしたけれど、何か言わずにはいられなかった。
店主は、その時私が考えていたこと全てについて「判っていますよ…」と言うかのような顔をしていた。そして、
「ほっほっほ。それはそれはありがとうございます。親子2代に渡って感謝していただけるなんて、私も、長年こうして店をやっていた甲斐があったというものです。やはり私の目に狂いはなかったっていうことですな。ほっほっほ。」
店主の老人は白髪頭を丁寧に左手で撫でながら、また嬉しそうに目を細めた。そして、言った。
「お前さんのお父さんはね…。とっても良い青年でしたよ。礼儀正しくてな…。あの時もですな…。よう覚えております…。びっくりしましたからな…『偽』の鑑定書を依頼されたのはあれが最初で最後でしたからな。ほっほっほ。」
私は一瞬「偽」という言葉にドキッとしたが、それは話の流れから考えて見れば当然である。指輪の「交換」の話は私の方から話に出したのだ。
店主は、どうやら私が全てを父から聞いて知っていると思ったらしかった。
そして、当時の話を詳しくしてくれたのだった。
父は、近々必ず本物を買いに来るので、イミテーションに本物の鑑定書をつけて欲しいと言ったそうであった。「一世一代の結婚がかかっている」と。それは土下座でもしそうな勢いだったという。
結婚は普通「一世一代の出来事だよお父さん」と、私はそこにいない父に突っ込みたくなったが、店主は話を続けた。
「まあ、私も長年この商売をしているので、人を見る目は養われましてな。あんなに綺麗な目をしている人はそうそういませんから。それに、こんな小さな町ですから…お父さんの素性もはっきりしておりましたしな。私も信用することにしたんですよ。ほっほっほ。」
店主があまりに可愛らしく笑うので、私もつられて微笑みながら言った。
「…でも、済みません。偽の鑑定書なんか作らせちゃって、そんなことなさって…。どうかすると警察沙汰になっちゃうところでしょ。本当にもう…済みません。」
私は心からのお詫びの心で、頭を何度も何度も下げた。すると店主はまた意外な話を始めたのだ。
少し傾きはじめた陽の、ほんのりと赤みを帯びた光がショーウインドーを照らし、夕方が近いことを告げていた。
「いやいや、そんなに謝ることはないよ。お嬢さん。『偽』とは言いましたけど、私は何も困ることはしておりませんからな。ほっほっほ。…お父さんには最初っから『本物』のダイヤモンドを渡しておりましたからな。ほっほっほ。ほっほっほ。」
私はもう一体何が何だか分からなくなってしまっていた。父の指輪が最初から本物だった???
…じゃあ、海に落としたのも本物で、母が修理に持っていったのも本物???…
そこで私の思考回路は完全にストップしてしまった。
店内の壁には、きらびやかに装飾の施された時計が掛けられている。
その中でゆっくりと回転する金色の鳥。私は停止してしまった頭で、ただその鳥をぼんやりと見つめていた…。
私は言葉を失っていた。次の言葉は、やはり店主だった。
「まあ、何かあったらこっちの責任になればいいのですからな。人を見る目と、信用が大事な商売ですからな。…それに、私の目に狂いはありませんでしたよ、お嬢さん。ほっほっほ。」
店主は本当に嬉しそうで、懐かしそうで、幸せそうだった。私だけが、止まった思考回路を何とかバックアップしようと必死になっていた。
「ただですな…。お父さんが2度目に指輪を持っておいでになった時に、ちょっと修理したような跡があったのだけが気になりましたがね。私も、敢えてお父さんには質問しなかったのですがね、…お嬢さん、その辺りの話はご存知ではないのですかな?」
そこで、やっと私の頭の回路が動き始めた。
「あの。これは内緒の話なんだけど。実は…。」
私は店主に、父には絶対に内緒だと何度も念押しをして、母から聞いた話をした。…母が指輪を洗濯機に入れて洗ったこと。それで台座が歪んでしまい、修理に持っていったこと。ただ、そこでその指輪が「偽物」の鑑定を受けたことだけは、やはり口にすることはできなかった。
しかし、店主の鑑定眼は私が口ごもった、その話の中身もしっかりと見抜いていた。
「そうかそうか。それで長年の疑問点が解決しましたよ。ほっほっほ。それは、お母さんもここには持ってきづらかったでしょうな。ほっほっほ。」
私は、その時始めて、母が指輪を持っていった店が、ここではないことに思い至った。…それはそうである。大切な指輪を洗濯して壊したなんて、縁起でもないし、父に分かったら、それこそ申し訳がたたない…。だから、母はわざわざ別の店に持っていったのだ。
そこで、私は思い切って店主に尋ねてみた。
「じゃあ、母は、一体どこに持っていったんでしょうか?」
店主は即答した。
「多分、隣町の店でしょうね。…今はもうありませんがね。」
店主の話によると、以前はこの街に隣接した隣の町に、もう一軒の宝石店があったそうであった。ただ、その店は既に7年ほど前にたたんでしまっており、今はその場所は薬局か何かの店舗になっているということだった。
「でも、何で、辞めちゃったんでしょうね…。そのお店。」
私はまた間抜けな質問をしてしまった。商売敵であろうその店は、最初から無い方がいいに決まっている。でも、何だか、秘密をたぐる糸が切れてしまったような気がして…ちょっぴり残念な気がして、それでそんな質問をしてしまったのだ。
私はとっても残念そうな感じでそんな質問をしてしまい、こちらの店主には失礼だったかも知れないなって、一人で赤面してしまった。
店主はそんな私にはお構いなしに、すぐに次の言葉を継いだ。
「ほっほっほ。あの店はですね。なかなか評判もよく店主の腕も良かったんですがね…」
おじいさんの言葉が急に濁ってしまったので、私は思わず問いつめてしまった。
「何かあったんですか?」
「ほっほっほ。これは噂話ですがの。腕はいいが、時々目の利かない人…まあ、たいがいのお客さんはそうですがね…。…偽物を売りつけたり、良い品を粗悪品だと言って安く買い上げたりすることがあったそうなんですよ。しかも、ちょっと怖いお兄さんたちとも『ヤミ』で取引などをしていたそうでしてね、最後は警察沙汰になったということなんですよ。新聞とかには載らなかったようですが…。
こういう商売はいろいろと誘惑がありますからね。ほっほっほ。」
私の思考回路はとうとう全開になった。
…これで謎が解けた。
…きっと、母は本物を持ってその店に行ったのだ。そこの店主からしてみれば、修理に出されたのは自分の店で買われたものではないダイヤの指輪。しかも持ってきたのは、結婚を控えた妙齢の美女。(母の名誉のため、そういうことにしておこう)。
何やら訳ありそうな状況を見て、店主は母をからかったのだ。そうに違いない。母はからかわれたんだ…。
「お嬢さん。どうしたんです? まあ、よかったですがね。修理の時にガラス玉にすり替えられたりはしておりませんでしたよ。お父さんが偽物だと思って持ってきたそれも正真正銘の、当店でお渡しした本物のダイヤモンドでしたからな。ほっほっほ。」
私は、店主にお礼を言い、自分が結婚する時には必ずここで指輪をつくってもらいます…、と一方的に固い約束をして店を後にした。
商店街を抜けて空を見上げると、青い空に浮かんだ雲がほんのりと夕陽に染まっている。
爽やかで、そして、あたたかな…
まさに、今の自分の心の風景が帰途の空を彩っていた。
エピローグ
家に帰ると、ちょうど父も母もいなかった。
私はこっそりと父と母の寝室へ入った。母の鏡台に腰を掛け、抽斗をそっと開けてみる。そこには臙脂色の綺麗な箱があった。それを優しく手に取ると、蓋を開けてみた。そこには決して衰えることのないダイヤモンドが、静かに気品のある輝きを放っていた。
静かにリングを指先で摘み、陽にかざしてみる。
あたかも今の私の心を映し出すかのように、透明感のある光が幾重にもなって煌めいていた…。そして、リングの内側には「from M to Y」と刻まれていた。
私は「あなたはいつかは私のものね。」とひとりごちてみた。
…父も母も知らない事実を私一人が知ってしまった。10年来の秘密に、また一つ秘密が加わって。しかも、結果としては最高の事実としての「秘密」を…。
この指輪は、一時たりとも「偽物」なんかじゃなかったんだ。プロポーズの時、父が格好つけて母に渡した時も…、母が落として危うく波にさらわれそうになった時も…。そして、父がずぶぬれになって探していた時も…、
…母が洗濯機でまわしちゃって、修理に出さなきゃいけなくなった時も。…結婚式の時も、…私が生まれた時も、ずっと、ずーっと…。
自分が見たこともない情景が、実際に目に見えるそれよりも遙かに鮮やかに、私の瞼の裏側に浮かんでは消えていった。
知らない間に涙が頬をつたっていた。
父と母の幸せが身に沁みて、涙が後から後から止まらなかった…。
本物であろうが、偽物であろうが、そんなことは関係のない次元で「世界で一番美しいダイヤモンド」…それが私の目の前にある…そう思えた。
そして…
私には、心に決めた人がいる。もう付き合って数年になる…。この間母に危うく感づかれそうになった時にはどうしようかと思ったが、近々彼を紹介しようと思っている。
…彼は、お父さんとよく似た人だ。目が綺麗で、誠実で。ぶきっちょだけど頼りがいがあって…。
…そして、彼のイニシャルはY。私のイニシャルはM。
「from M to Y」
父と母とは反対だけど、私にとってはちょうどいい。だって、この指輪は父が母へと思いを捧げ、そして今度は、私の、彼への思いを守ってくれるお守りになるのだから。
父から母へ、そして母から私へ、そして今度は私から彼へ…
父にも母にも、この話はできないな。でも、きっと彼と結婚できたら、いつかこの指輪の話をしよう。そして、生まれてくる子供にも…。
ちょっぴり誘惑はあったけれど、まだ、自分の指にはめるのは怖いような気がして、私はずっとそれを指先で持って、ダイヤの放つ静かな光を眺めていた…。
そして、それをそっと自分の唇に触れさせてみた。
するはずもないのだけれど…、ふっと潮の香りがしたような気がした。
《了》
私は、小学校の高学年だった。
その時の担任の先生の宿題で、「お父さんとお母さんに結婚した頃の話を聞いてくること」というのがあった。
今だったら、「家庭環境が複雑な子への配慮は?」などと文句でも言われそうだが、当時はまだそんなに世間は口やかましくなかったし、私の住んでいる田舎町にはそれほど家庭が複雑な子もいなかった。
とにかく、その宿題を受けて、私は父と母に「どうして結婚したのか」というダイレクトな質問をしたのだ。
そして、それがきっかけで私は父と母のちょっとした秘密を知ってしまった。そして、その時知り得た秘密はまだ10年経った今でも私の胸の中にしまってある。
第1章『父の話』
「最近の小学校の宿題ってのは、凄いんだな。みんな、家で親に『どうして結婚したのか』なんて質問をしてくることになってるのか?」
「ううん。絶対そういう質問じゃなきゃだめってワケじゃないけど。私が、そう聞いてみたかったの。だから教えて。」
「お父さんとお母さんはどうして結婚したの」という突然の質問に照れくさそうな父。照れ隠しかどうか分からないけれど、空のグラスにビールを手酌で注ごうとするが、もう飲み干してしまったビール瓶からはむなしく滴が2、3落ちただけだった。
「もう一本どう? 私が取ってきてあげる。」
どうせ話を聞くなら、しっかり聞きたいし…。父は飲むとおしゃべりになるのだ。
いつもなら母に「一本だけ」、と決められているビールであるが、今日は特別である。母は、婦人会の催しでちょうど一泊二日の温泉旅行に出かけているのだ。
最初は父と母が一緒にいる時に尋ねようかと思ったが、それじゃあ面白くないと思い、別々に聞くことに決めた。そういう意味では、今日は絶好のインタビュー日和だった。
私が、「はいどうぞ」とお酌をしてあげると、父も嬉しそうに、
「それじゃあ、話してやるか。」
と、座り直すとグラスのビールを半分ほど飲み干した。その後しばらく、何処と言うこともなく虚空を見つめていたが、突然こんなことを言い始めた。
「これから話そうと思うことは、母さんに内緒の話なんだけど、お前、絶対に母さんには言わないって約束できるか」
と、父は急に真剣な表情で私を見つめる。顔はアルコールのせいか、ちょっと紅潮している。でも、目はしっかりと焦点があっていた。
「約束って、もちろんそれは守るけど、小学校の宿題なんだからさ…全部は内緒にできないかも…。」
「そうか、じゃあ学校では、当たり障りのないことだけ言っときなさい。」
どうやら、父はその「内緒話」を、私に話したそうな雰囲気を醸し出していた。
「分かった。約束する。学校でも内緒の部分はうまく言うから、教えてお父さん。」
既に空になっているグラスに私はまた一杯お酌をしながら、嬉しそうな父を眺める。
「…実はな。父さんが、母さんにプロポーズしたのは海岸だったんだ。」
父の、いきなりの核心めいた話始めに、ちょっとたじろいだ私だったが、そこはすかさず、合いの手を入れた。
「へえ。お父さんやるじゃない。意外にロマンチストだったんだ。」
「おいおい、『意外』ってのは余計だよ。…それでな、その時大失敗があったんだ。」
「『大失敗』って、どんな? 『大成功』じゃなかったの?」
「結果的には巧くいったんだけど、…その時は大変でな。」
父は、どうやら母を連れて海岸を散歩しながらプロポーズしたらしいのだが、その時、言葉と一緒にダイヤモンドの指輪を渡したのだということだった。そして、その時、よりによってその指輪を砂浜に落としてしまったということなのだ。波の打ち寄せる浜に…。
「何でそんな大事なモノを、落としちゃうワケ…。」
「いやいや、ちょっと父さんが格好つけすぎちゃったんだよ。靴を脱いで波打ち際にいた時、『今しかない』って思ってな。ポケットから指輪の入った小箱を出したんだ。それで、母さんに。『これなんだけど』って箱から指輪を取り出してな。…プロポーズの言葉と一緒に渡したんだ。」
父はちょっと照れくさそうな顔をした。が、そこは追及のしどころだ、私は立て続けに質問を浴びせた。
「で、プロポーズの言葉は何だったの? お母さん、どんな顔してた? で、何で落としちゃったのよ?」
「まあ、そんなに慌てるなよ。」
私をじらしているのか、父の話し方はいつもよりゆっくりだった。
「プロポーズの言葉はな、まあ…月並みだな。『これ、受け取ってくれないか』ってさ。…で、母さんはというとな…うーん。…普通だったな。」
「『普通』ってよくわかんないなあ…。あ、分かった。お母さんの反応が悪かったんで、お父さん舞い上がっちゃったんじゃないの? それで渡すときに手が震えて落としちゃったとか…」
その時、ちょうど時計が8時を告げた。父は、遠い目をして時計を眺めていたが、時計が鳴り終わると再び口を開いた。
「違うんだ。その時、突然の父さんの行動に、母さんは幾らか驚いていたけれど、指輪はちゃんと受け取ってくれた…。」
「じゃあ、そこで、指にはめて、『ぴったりだわ』ってワケに行かなかったの?」
「うーん…。母さんも、ある程度は察してはいたかもしれないけれど、やはり急だったんで驚いたんだろう、でも、反応はそんなに悪くはなかったぞ。『綺麗だね』って言いながら、暫く指で持って眺めていたんだよ。」
「それで?」
「うん。その時にな…ちょっと大きめの波が来て、足に水がかかってね。母さんは驚いた拍子に指輪を波打ち際に落としちゃったんだ。」
「えーっ!! それで?それで?」
「それは慌てたよ。小さいけれどダイヤモンドだからな。波がかぶさっちゃってさ。」
「で、見つかったの?」
「それは探したさ。1時間以上は探したと思うぞ。何せ、夕方だったからな。だんだん薄暗くなってくるし、しかも満ち潮で、波はどんどん大きくなるわで、もうずぶ濡れだったな。母さんも最初は一緒に探してくれてたんだけど、『体が冷えるから、僕が一人で探す』って言って…、父さんが探す間、ずっと母さんは岩に座って海を見てたな…。」
私は、思わず「お母さんが見てたのは『海』じゃなくて『お父さん』じゃなかったの?」って突っ込みたくなったけれど、そこはちょっと自制した。
「結局どうなったの?」
「見つからなかった。」
「じゃあ。『大失敗』じゃない。」
「だから、『大失敗』って言ったじゃないか。」
「あ、そうか…。でも、お父さんとお母さんは結ばれたんでしょ?」
「そうなんだよ。」
「…じゃあ、前お母さんが見せてくれたあのダイヤの指輪は2つ目だったりするワケ?」
「いや。それがな。…出てきたんだよ。」
「えーっ。ウソみたいー。波打ち際で落とすと見つかんないよ、普通。」
父は、私の真剣な顔を見ながら、とても嬉しそうな顔をして、またグラスのビールを一口ゴクリと飲み下した。まるで、私の反応を肴にするみたいに。
グラスについた水滴が父の手をつたい、ポトリと落ちてテーブルの上で静かにはじけた。
一時間以上探しても出てこなかった指輪が出てきたなんて、とても信じられない話だと思い、ピーナッツを齧りながら微笑んでいる父に私は言った。
「…まさか、その後買った魚の腹から出てきたって、おとぎ話みたいなことなんてないよね。」
「だったら、もっとロマンチックだったんだけどな。いやいや。現実は現実だよ。…それから暫くしてな。母さんから電話があったんだ。『会いたい』ってな。最初は理由を言わないから、父さんはてっきり結婚を断られるものだと思って、しょぼくれて待ち合わせの喫茶店に行ったんだ。」
「そしたら、OKだったってワケね!」
「そうなんだよ。」
父の話によると、指輪は何と母のズボンの裾から出てきたのだそうだ。何とそれは、波打ち際で、濡れないように折り返していたジーンズの裾に入っていたらしかった。私は父を待っている間、それに気づかなかった母も母だと思ったが、父の話はもちろんそれだけではなかった。
それで、何も知らずに待ち合わせの場所に、暗い顔して出かけて行った父が見たのは、しっかりとその指輪を薬指にはめて照れくさそうにしている母の笑顔だった…というのが、父の話であった。
そこまで聞いて、私は何だかとってもハッピーな気分になっている自分に気が付いていた。
「なるほどネ。」
「知らなかっただろう。」
「うん。お母さんからも聞いたことなかった。…でも、どこが『秘密』なの?」
「…そうだな。確かに…じゃあこれで止めておこう。それがいい。」
「えーっ。ズルいよ。ズルい。ズルい。」
父は、私をおちょくっていたのか、本心だったのかは定かではないが、私があまりしつこいので、というか、やっぱり「約束は約束」だったので、父は続きの話をしてくれた。
「実はな。…うーん。これは絶対内緒だからな。」
「分かってるって。絶対内緒。」
「実はな、そのダイヤって偽物だったんだよ。」
父のその一言で、それまでの私の幸せな気分は一度に消し飛んでしまった。
「え~っ。ヤだ~そんな~。」
「そうなんだよ。…その時どうしても父さんはお金が工面できなくてな。でもな、父さんはその時、必ずいつかは本物を母さんに渡すと自分に誓ってたんだぞ。言い訳っぽいけど…。」
「でも、それじゃあお母さんが可愛そう…でも、じゃあ…お父さん、その偽物をずぶぬれになりながら1時間以上も探してたってワケ…」
「それはそうさ。だって父さんにとっては本物と同じぐらい大切なものだったんだぞ。台座にはしっかりメッセージも彫り込んでもらってたしな。」
父はその時のことを思い出していたのか、グラスに付いた水滴を指先でもてあそびながら、また遠い目をしていた。そして、また我にかえったように話し始めた。
「お前、そう言うけどな。父さんも必死だったんだぞ。母さんはな、父さんには話していなかったけれど、その時誰か他の人からも結婚を申し込まれていたようなんだ。その辺りは定かではないんだけれど、もしそうだとしたら一大事だろ。ぐずぐずしてたら他の人の奥さんになってしまう可能性もあったんだからな…」
「ふーん。でも…、お父さんとお母さんって付き合ってたんじゃないの?」
「その辺りが微妙だったんだよ。」
「ほんと、良くわかんないナ…。」
小学生だった私には、まだ男女の機微なんてものはちょっと理解しがたかったのかも知れない。でも、このお話は必ずハッピーエンドになるって分かっているのだから、私は安心して聞いていた。
「でも、よかった。もし、お母さんが他の人のトコに行っちゃってたら、私もこの世に生まれて来なかったってコトだもんね。」
「そうだ。父さんに感謝しろよ。」
「もうー。やだなー。」
父は急に元気になり、最後の一杯をぐいと飲み干した。私はすかさず尋ねた。
「で、今母さんが大事にしているあの指輪って本物なの?」
「当たり前だろ。それは、父さんの『誓い』だったんだからな。あの後、必死で工面して、お金が用意できたらすぐにこっそり本物にしておいたってワケ。」
「それって結婚式の前?後?」
「…もういいじゃないか。」
と、父はそれから後の言葉を濁してしまい、お風呂へ行ってしまった。
確かに、私にとってももうそれ以上は父に聞くことはなかった。それでも、父と母の意外な「なれそめ」を知った私は、妙な満足感に浸ったのだった。どうあれ、父と母はそうやって結ばれて、今の我が家があるのだから。決して悪い話ではないな…って。
父の残したつまみのピーナッツを2、3粒口に頬張ると、私はそれを気持ちよくかみ砕いて、母のいない台所の片付けを始めた。いつもなら億劫なはずのお皿洗いなのに、今日はとっても幸せな気分だった…。
第2章『母の話』
私が母に、父と同様の質問をしたのは、父から話を聞いてからちょうど一週間後であった。今度は父が出張で不在だった。
母は、父ほど動揺することはなく、「同じ職場で、真面目ないい人だと知っていたからプロポーズを受けた」と、最初は当たり障りのない話をした。その時の母の雰囲気から、このままだと、「父と母の結婚」の核心には迫れそうにないので、私はズバリ尋ねることにした。
「お母さん。プロポーズの時に貰った指輪の話して。」
私は、そこでてっきり母の動揺する顔が見られるのでは、とちょっぴり期待していたのだが、母はそれほど顔色を変えることもなく、私の顔をじっと見ながら「ふーん」と一言口にしただけだった。
母は、既に私が父から何か聞いているということを鋭く察知したようだった。そして、「そうね…」と言った後、暫く父と同じように、遠くを見るような目をしていた。
「私とお父さんにとって、あの指輪はとても大事なものなのよ。あの指輪がなかったら、きっとお父さんと私は結婚していなかったかも知れないんですもの…。」
これまたいきなり核心である。私は「ラッキー」と思い、母が父との結婚を決心したことの、より核心部分に迫りたくって、すぐさまツッコミを入れた。
「『指輪』って、前見せてくれたあのダイヤの指輪でしょ? やっぱり高価なもの貰うと嬉しいものなんだね。」
「ううん。『高価』とかそんな事で決めた訳じゃないのよ…。」
母の返答は、ちょっぴり私を非難するような調子を含んでいた。しかし、私は自分の投げかけた野暮な質問を省みるよりも、それに対して発せられた母の「そんな事で決めた訳じゃない」という言葉に反応して、胸が「ドキリ」としていた。
父の感じだと、母が「偽物」の話を知っているとは考えられない。でも、…ひょっとして母は真実を知っていたのかも…。まさか、じゃあ…父と母が共同して私を騙そうとしている…。いいえ、それは考えすぎ…。
母と私。胸の内は全く異なっていたであろうが、二人とも暫く黙っていた。
そして、その瞬間母が見せた顔を、私は忘れられない。
私が、ドキドキしながら横目でそっと覗き込んだ母の顔は、怒った顔でも悲しそうな顔でもなかった。何と、そこにはとても幸せそうな微笑みが溢れていたのだ。 それは、それまで私が見た「母」の笑顔とは全く違う…今思えば、母はその時、きっと「女性」の顔になっていたのだろうな、と思う。
…きっと、しょぼくれて待ち合わせ場所に行った父が見た母の顔はこんな顔だったのだろう…そんな素敵な微笑みだった…。
私は続けた。
「じゃあ。お母さん、決め手はなんだったの?」
「そうね。うまく言えないけど。やっぱりお父さんの人柄かな…。」
「ふーん。でも、お母さん、さっき『指輪がなかったら』って言ったじゃない…。」
「…あのね…」
母がその後してくれた話は、ほぼ父のそれと同じだった。指輪を波打ち際に落としてしまい、一緒に探したことなど、細部もぴったり一致していた。
「お父さんね。本当に一生懸命探してくれたの。最後には全身、波をかぶりながら…。私には『風邪をひいたらいけないから』って一人でね…。」
「で、見つかったの?」
私の問いかけに、母は一瞬怪訝そうな顔をした。きっと、そこは私が父から話を聞いていると思ったのだろう。しかし、母はそこで敢えて私に問い返すことはしなかった。
「うん。諦めて家に帰った後でね、お母さんのズボンの裾に引っ掛かってたのが分かったの。」
「もーっ。お母さんったらドジなんだから。やっぱり当時からおっちょこちょいだったんだね。…じゃあお父さん、見つかりっこない指輪をずっと探してたんだ…。」
「そうなの。お父さんには悪いことしちゃったの。でね…。」
そこで母が話を止めたので、私はまた「偽物」の話を母が知っているのかと疑ってしまった。ところが、母が継いだ言葉はまた違う意味で意外なものだった。
「私…、その時…本当に一生懸命に指輪を探しているお父さんの姿を見ててね。『この人と一緒になろう』『この人となら幸せになれそう…』って思ったの。」
「へえー。じゃあ。指輪が出て来なくても、返事は『OK』だったってワケだ。」
「そうね…。」
そこで、母はまた幸せそうな微笑みを浮かべた。
私は、母はやっぱり「偽物」ってことは知らなかったんだ、とほっとした。そして、母はその時やっぱり「海」ではなく「父」を見ていたのだと…。
「じゃあ、プロポーズの時には、まだ迷ってたんだ…。どうせなら、すぐに指にはめてあげれば落とすこともなかったんじゃない?」
自分でも、我ながらあの質問は野暮だったなあと思うが、小学生の私は敢えてそんな質問をしたのだった。もちろん、もう少し話を核心に近づけたかったからなのだが。
「そんな簡単なものじゃないわ。お母さんにも色々あるのよ…。」
私は「来た!」と思った。父も感づいていた「第三者」の存在が母の口からもほのめかされたのだ。そこで、私はここぞとばかりに
「えー。お母さんモテたんだ。ひょっとして、お父さん以外に好きな人がいたとか…。」
「ううん。好きな人がいたって訳じゃないんだけどね。」
「あーっ。じゃあ、誰かに告白されてたとか。」
私は子どもの無邪気さを武器に母を遠慮無く攻撃した。しかし、母は、別に怒るでもなく、優しい口調で答えた。
「もう…どうでもいいことなのよ。お母さんはお父さんを好きになって、お父さんと結婚したのよ。だからあなたが生まれたのよ。それでよかったのよ。」
母の言葉は静かで、重みがあり、それでいてあたたかかった。私はそれ以上母を追及することができなくなってしまった。
結局、父と同じで、「今が幸せだから」って。そういうまとめ方になっちゃうのかな…ま、それもいいかな…、と、私は納得しようとしていた。ところが、何と、母の方からもっと話を広げる言葉が出て来たのだ。
「あの指輪なんだけどね。あれは母さんのとってもとっても大切な宝物なのよ。」
「知ってるわ。ダイヤモンドなんだよね。」
私は、母が勿体をつけて言う割には、普通のことだなあ…って、その時は思った。そして、話題がもとの話に戻るような方向に行ったことにもちょっぴり戸惑っていた。ところが、母がそんなことを言うからには、まだ何か聞き出せるかもしれないと思い、「うんうん」と相づちを打って、そこはしっかり話を合わせた。
やはり、母は続けた。
「別にダイヤモンドだからって訳じゃないのよ。あの指輪は特別なの。」
「そうね。あの指輪がきっかけでお父さんとお母さんは結ばれたんですものね。」
「そうよ…。だから、別にダイヤだからって…関係ないの。」
妙に母の言葉が含みを持っているので、私は当惑した。「えーっ。やっぱりお母さん『偽物』だって知ってたのかも…。まさか…。」
私は、母のその言葉にどう切り込もうかと迷っていた。すると、また母が言った。
「あなただけには…話しておこうかしら。…これから話すことは、絶対にお父さんには内緒にできるって約束できる?」
私は心の中で「えーっ」と叫んでいた。父の話はともかく、母からも「秘密」の話が聞けるなんて、何てことだろう。瓢箪から駒?棚からぼた餅?…私の知っていることわざでは説明しきれない展開だった。
「もちろん。絶対言わない。約束する。」
私は何としても母からその「秘密」の話を聞き出そうと、必死で力強く答えていた。
「あの日ね。指輪がなくなった日…。お母さん、知らずに指輪を洗濯しちゃったのよ。洗濯機の中でカラカラ音がするから、止めて調べてみて、それで気がついたのよ。」
「へえ。そうだったの。裾を折ったジーンズをそのまま洗濯機に入れちゃうなんてさすがお母さんね。」
「もう、いやね。ちゃんと入れる前に戻したわよ。でも、ドラムの中で戻したから気が付かなかったのよ…。」
「いいわ…。それで?何が秘密なの?」
「指輪が見つかった時は、それは嬉しかったわ。でもね、実は指輪がドラムの中でかなりころがっちゃったみたいで、台座の金具が少し歪んじゃってたのよ。」
私は、母がそれで指輪が「偽物」だと気づいたのかと思ってどきどきしていたのだが、指輪が少し壊れただけのことだったのか…。とホッとしてしまった。でも、やはり小学生だった私は浅はかだった。何故って、その次の展開を考えれば、当然ドキドキは続くはずだったからだ。
「それでね。お母さん、お父さんに内緒でその指輪を直しに行ったのよ。」
私の頭の中でその時初めて「ガーン」と音がした。分かった。そこで母は知ってしまったんだ…。私は波立つ心を必死で抑えながら、何気ない風を装い、震える声を抑えつつ「ふーん。」と相づちを打ち、次に出てくる母の言葉を待っていた。
「その時直しに行った宝石屋さんでね…」
母は口ごもった。そこで、私は仕方なく尋ねた。
「そこで、…何があったの。」
「その指輪がね…、『偽物』だって言われたのよ。」
私は、予想していたとは言え、やはりショックは大きく、やっとそれまでしていた「演技」を止めることが出来た。そして遠慮無く大きな声で言った。
「そんなー。信じられないよー。」
誰を非難していいのか分からないけれど、とにかくその時の私の胸の内にはもやもやが充満していた。そのわだかまりをぶつけるべく、私は強い調子で言った。
「何で偽物なのよー。」
強い調子の私の言葉に、母は言い聞かせるように静かに話を続けた。
「あのね…。お母さんがどうしてこんな話をするか分かる? お母さんはダイヤなんかどうでも良いって言ったでしょう。お母さんは、お父さんが好きになったのよ。だからあの指輪はその気持ちの『証し』なの。だから…それならそれでいいの。」
母の言葉には説得力があった。でも、私は続けた。
「分かるわ。でも、お父さん、何でそんなことしたのかな…。」
私は父から聞いた話を頭の中で反芻しながら、再び必死で母に話を合わせようとしていた。今更父と母がどうこうなるはずもないという気はしていたが、やはり何かが自分の中で壊れそうな気がして小学生の私は必死になっていた。
「そうね。分からないけど、ひょっとしたらお父さん騙されてたんじゃないかなって思うのよ。」
「えーっ。騙されたって、誰に?」
「よく分からないけど、宝石ってよくそういう話があるじゃない。」
母が続けた話によると、母は指輪を直しに宝石店に行った際に、父がくれた箱も持って行ったそうであった。そして、その箱にはきちんと鑑定書もついていたというのだ。ところが、宝石店の店主は、ダイヤをしっかりと鑑定した上で、鑑定書も、石も偽物だと言い切ったというのだ。
しかし、実のところそれは当然そうなのだ。父が母に渡したダイヤモンドの指輪は正真正銘の「偽物」であったのだから。ダイヤが偽物で、鑑定した宝石店の人の目が本物だったということに間違いはないのだ。
ただ、そこまで聞いた時、私の心は妙に静まっていた。そして、ただ、私は嬉しかった。母の、父へのその気持ちが嬉しかったのだ。
「きっとそうよ。お父さん、人が良いから騙されて偽物を持たされてたのよ。」
「そうよね。お母さんもそう思うの。だからね、ダイヤモンドとしての価値なんかどうでもいいのよ。大切なのは気持ちだから。…あのリングの内側には、きちんと『from M to Y』って彫ってあるのよ。『お父さんから、お母さんへ』って意味なの。だからそれでいいのよ。」
やはり、母の言葉は静かで強く、そしてあたたかかった。
小学校の頃ってイニシャルに妙に惹かれてしまうもの…。私は、ロマンチックな気分に浸って、その時父と母をとっても羨ましく感じていた。
…でも、それと同時に私の心の中にはふつふつと湧き上がるものがあった。
今は「本物」になっているその指輪…それを母は知らない。母に、その指輪は「本物なんだよ」って何とかして伝えたい気がした。…しかし、いくら知恵を絞っても当時の私の頭には妙案は浮かんでこなかった。下手なことを言うと、却って父と母の思い出をダメにしてしまう…、それはその時の私の頭でも十分すぎるほど理解できていたのだ。
母は、満足そうに話を終えると、
「学校では余計なこと言っちゃダメよ」
と少し微笑みながら言った。もう、その時にはすっかり普通の「母」の顔に戻っていた。
私は母の立ち去った居間のテーブルに一人残されて、「発表用メモ用紙」と書かれた白紙の用紙をみつめながらぼんやりとしていた。
時計が、父の時と同じように8時を告げていた…。
第3章『宝石屋の話』
あれから10年の歳月が流れた。私は、結局父にも母にも「真実」を伝えることはできなかった。でも、それは仕方のない話だった。
何故って、考えれば考えるほど、結局自分が「何もしない」方がいいってことになるのだから…。
父と母は今も大変仲がよい。時折、私を置いて二人で外出する。そんな時、母はいつもあの指輪をこっそりと薬指にはめて出かけて行くのを私は知っている。
あのダイヤが本物だと知ったら、母はさぞかし喜ぶだろうな…。とつい思ってしまう私。父には、「あの指輪は本物なのに、お母さん『偽物』だと思い込んでいるよ」って教えてあげたい気がする。でも、やっぱり「今のまま」でいいのかな…。そして、やはりそういう結論になってしまうのだ。
10年前の懐かしい思い出を、今更のように記憶の隅から引っ張り出したのは、先日の母の言葉がきっかけだった。
数日前、私は22回目の誕生日を迎えた。母は、
「あなたももう結婚してもいい年頃になったわね。…覚えてる?いつか話したあの指輪のこと…。あの指輪ね、いずれはあなたにプレゼントしようと思ってるのよ。…きっと、あなたも幸せにしてくれると思うから…。」
もちろん、母は偽物だとか本物だとか、そんなことは関係なく、母にとっての『価値』において話をしてくれているのは分かっている。でも…、母はこう言った。
「まあ、あなたにとっては価値がないかも知れないけれど…」
その時の母の表情から、母の真意は読みとることができなかった。でも、その時、私はやはり母に、「あれは本物なんだよ」って教えてあげたくなってしまった。
私はその時の母の言葉に、消えかかったシミのような…、ほんの少しではあるが『翳り』のようなものを私は感じずにはいられなかったのだ。
私は、そんな母に言った。
「うん。是非ちょうだいね。私もお父さんとお母さんみたいな仲の良い夫婦になりたいもの。」
それは私にとって、心からの言葉であった。
母は、それを感じ取ってくれたのか、
「分かったわ。いつか、きっとあなたにプレゼントするからね。でも、あなたが結婚する時にはきっと『彼』の方から素敵な指輪を贈って貰えるんじゃないかしら。」
「それは…そうかもしれないけど、絶対ちょうだいね。きっと、その指輪の力で私たちも、守ってもらえそうだから。」
「えっ…。『私たち』って、あなた…、ひょっとして、もういい人いるの?」
「やあね。お母さんったら、そういう想定で話をしてるのよ。もう。」
楽しい会話だった。でも、私にとってはまた複雑に絡み合う「秘密」を思い出すきっかけとなった会話だった。そして、そんな母との会話があったので、私は再び10年前のことを思い出したのだ。
…それがきっかけで、私はある時ふらりと街の宝石店に立ち寄ったのだ。
その宝石店は、昔からこの街にある店で、自分が小さな頃からよく知っている店である。ただ、知っているだけで、中に入ったことはなかったた。…ひょっとしたら小さな頃、母に連れられて入ったことはあるかも知れないけれど、少なくとも物心ついてから入った記憶はない。
幾らか外見は古めかしくなっているものの、中に入ってみると、とても小綺麗で、部屋全体が光に満ちているような雰囲気さえあった。
サファイヤ、ルビー、真珠などがショーウィンドーの中でそれぞれの個性的な輝きを放っている。私は「どれも綺麗ね…」と、ありきたりなことを思いつつ、ぶらぶら見て回っていた。
そして、ちょうどダイヤモンドのケースの前まで来た時のことだ。
「失礼ですが、お嬢さん。あなたは…」
店主のおじいさんに突然話しかけられたのである。
最初は驚いたが、よくよく話を聞けば、そのおじいさんは私の父を知っているというのだ。つまり、当然私がその「娘」であるということも…。
「まあ、小さな街ですからな。店には入ってこられんでも、よくこの前を通る方の顔は、自然と覚えますからの。ほっほっほ。」
とても温厚そうな方ではあったが、あまりにも親しげに話をしてくるので、正直ちょっと不気味な感じもした。…けれども、とても品の良いおじいさんだし、こんな小さな町。実際私も小中高とこの店の横を通学路にしていたのだから、面識のあるなしにかかわらず、おじいさんが私のことを知っているというのも、別に変わったことではなく普通のことなんだろうな、と思った。
ただ、私は逆に「父」のことに興味が湧いたので、逆に質問してみることにした。
「あのー。でも…何で私が…『娘だ』って分かったんですか?」
私の質問に、店主は嬉しそうに、「ほっほっほ」と特徴のある笑い声をあげて目を細めた。そして少し通りを眺めるような素振りをしていたが、
「お前さんは覚えておられんでしょうが、…お前さんのお父さんがね。お前さんをこの店に連れてきたことがあったんですよ。まだ随分小さい頃でしたがね。」
私は、てっきり「母」の間違いではないかと思い、聞き返したが、店主が知っているのは「父」であり、それに間違いはなかった。
しかし。…父は、結婚指輪を買った時ぐらいしか宝石店に出入りしているはずはない…それに、私を連れて来たってことは…。
それって一体いつのことなんだろう…。私はすっかり考え込んでしまった。
店主は私の反応を楽しむように微笑みを浮かべると、彼は長年そうしてきたのであろう、カウンターの中の椅子に静かに腰を下ろし、また通りを眺めていた。
その時、私に「ひょっとしたら…」と、ある考えが浮かんだのだ。そして言った。
「ひょっとして、それは父が指輪を取りかえに来た時のことでしょうか…。」
その言葉を聞いて、店主の顔色が少し変わったのを私は見逃さなかった。
しかし、店主は微笑んで、こう言った。
「お前さん、…お父さんから話を聞いたのかな。…それは驚きました。ほっほっほ。」
そう言うと、店主は続けた。
「…いやいや、残念ながらお嬢さんの予想ははずれですな。ほっほっほ。お父さんが指輪の『交換』に来られたのはお買い求めになってから、それほど間がなかったですからな。…そうですな、お父さんが最初にやって来られた時から半年も経っていなかったかも知れませんな。私も『随分と早かったですな』って言ったのを覚えておるぐらいですからな。『1年以内』という約束でしたんですがね。…まさか、お前さんは生まれておられんでしょう。ほっほっほ。」
…半年。と言うことは…、当然私が生まれているはずがない。それにきっと、父のことだから、借りを作ったままではいけない、と頑張って何とかお金を工面したのだろう。…だとしたら…。私は再び問いかけた。
「御主人、その時…『私』幾つぐらいでした?」
「そうですな。よちよち歩きでしたからな、2歳ぐらいではなかったでしょうかな。」
どうやら、父は私一人を連れて、この宝石店に立ち寄ったらしかった。ただ、それがどんな目的だったのかはその時は少しピンとこなかった。
でも、先の店主の言葉と父から聞いた話を合わせて考えれば、父の「目的」が何かは自明のことだった。
父は、「お礼」にきたのだ。指輪のおかげで母とうまくいったこと。そして、結婚して、こんな「かわいい」娘ができたことを…。
私は、自分で「かわいい」って思ってしまったことにちょっと笑ってしまった。でも、「2歳の私はさぞかしかわいかっただろうな…」と、父に連れられてよちよち歩きでこの店を訪れた自分を思った。
そして私は言った。
「その節は父がお世話になりました。」
私がお礼を言うのは何だか変な気がしたけれど、何か言わずにはいられなかった。
店主は、その時私が考えていたこと全てについて「判っていますよ…」と言うかのような顔をしていた。そして、
「ほっほっほ。それはそれはありがとうございます。親子2代に渡って感謝していただけるなんて、私も、長年こうして店をやっていた甲斐があったというものです。やはり私の目に狂いはなかったっていうことですな。ほっほっほ。」
店主の老人は白髪頭を丁寧に左手で撫でながら、また嬉しそうに目を細めた。そして、言った。
「お前さんのお父さんはね…。とっても良い青年でしたよ。礼儀正しくてな…。あの時もですな…。よう覚えております…。びっくりしましたからな…『偽』の鑑定書を依頼されたのはあれが最初で最後でしたからな。ほっほっほ。」
私は一瞬「偽」という言葉にドキッとしたが、それは話の流れから考えて見れば当然である。指輪の「交換」の話は私の方から話に出したのだ。
店主は、どうやら私が全てを父から聞いて知っていると思ったらしかった。
そして、当時の話を詳しくしてくれたのだった。
父は、近々必ず本物を買いに来るので、イミテーションに本物の鑑定書をつけて欲しいと言ったそうであった。「一世一代の結婚がかかっている」と。それは土下座でもしそうな勢いだったという。
結婚は普通「一世一代の出来事だよお父さん」と、私はそこにいない父に突っ込みたくなったが、店主は話を続けた。
「まあ、私も長年この商売をしているので、人を見る目は養われましてな。あんなに綺麗な目をしている人はそうそういませんから。それに、こんな小さな町ですから…お父さんの素性もはっきりしておりましたしな。私も信用することにしたんですよ。ほっほっほ。」
店主があまりに可愛らしく笑うので、私もつられて微笑みながら言った。
「…でも、済みません。偽の鑑定書なんか作らせちゃって、そんなことなさって…。どうかすると警察沙汰になっちゃうところでしょ。本当にもう…済みません。」
私は心からのお詫びの心で、頭を何度も何度も下げた。すると店主はまた意外な話を始めたのだ。
少し傾きはじめた陽の、ほんのりと赤みを帯びた光がショーウインドーを照らし、夕方が近いことを告げていた。
「いやいや、そんなに謝ることはないよ。お嬢さん。『偽』とは言いましたけど、私は何も困ることはしておりませんからな。ほっほっほ。…お父さんには最初っから『本物』のダイヤモンドを渡しておりましたからな。ほっほっほ。ほっほっほ。」
私はもう一体何が何だか分からなくなってしまっていた。父の指輪が最初から本物だった???
…じゃあ、海に落としたのも本物で、母が修理に持っていったのも本物???…
そこで私の思考回路は完全にストップしてしまった。
店内の壁には、きらびやかに装飾の施された時計が掛けられている。
その中でゆっくりと回転する金色の鳥。私は停止してしまった頭で、ただその鳥をぼんやりと見つめていた…。
私は言葉を失っていた。次の言葉は、やはり店主だった。
「まあ、何かあったらこっちの責任になればいいのですからな。人を見る目と、信用が大事な商売ですからな。…それに、私の目に狂いはありませんでしたよ、お嬢さん。ほっほっほ。」
店主は本当に嬉しそうで、懐かしそうで、幸せそうだった。私だけが、止まった思考回路を何とかバックアップしようと必死になっていた。
「ただですな…。お父さんが2度目に指輪を持っておいでになった時に、ちょっと修理したような跡があったのだけが気になりましたがね。私も、敢えてお父さんには質問しなかったのですがね、…お嬢さん、その辺りの話はご存知ではないのですかな?」
そこで、やっと私の頭の回路が動き始めた。
「あの。これは内緒の話なんだけど。実は…。」
私は店主に、父には絶対に内緒だと何度も念押しをして、母から聞いた話をした。…母が指輪を洗濯機に入れて洗ったこと。それで台座が歪んでしまい、修理に持っていったこと。ただ、そこでその指輪が「偽物」の鑑定を受けたことだけは、やはり口にすることはできなかった。
しかし、店主の鑑定眼は私が口ごもった、その話の中身もしっかりと見抜いていた。
「そうかそうか。それで長年の疑問点が解決しましたよ。ほっほっほ。それは、お母さんもここには持ってきづらかったでしょうな。ほっほっほ。」
私は、その時始めて、母が指輪を持っていった店が、ここではないことに思い至った。…それはそうである。大切な指輪を洗濯して壊したなんて、縁起でもないし、父に分かったら、それこそ申し訳がたたない…。だから、母はわざわざ別の店に持っていったのだ。
そこで、私は思い切って店主に尋ねてみた。
「じゃあ、母は、一体どこに持っていったんでしょうか?」
店主は即答した。
「多分、隣町の店でしょうね。…今はもうありませんがね。」
店主の話によると、以前はこの街に隣接した隣の町に、もう一軒の宝石店があったそうであった。ただ、その店は既に7年ほど前にたたんでしまっており、今はその場所は薬局か何かの店舗になっているということだった。
「でも、何で、辞めちゃったんでしょうね…。そのお店。」
私はまた間抜けな質問をしてしまった。商売敵であろうその店は、最初から無い方がいいに決まっている。でも、何だか、秘密をたぐる糸が切れてしまったような気がして…ちょっぴり残念な気がして、それでそんな質問をしてしまったのだ。
私はとっても残念そうな感じでそんな質問をしてしまい、こちらの店主には失礼だったかも知れないなって、一人で赤面してしまった。
店主はそんな私にはお構いなしに、すぐに次の言葉を継いだ。
「ほっほっほ。あの店はですね。なかなか評判もよく店主の腕も良かったんですがね…」
おじいさんの言葉が急に濁ってしまったので、私は思わず問いつめてしまった。
「何かあったんですか?」
「ほっほっほ。これは噂話ですがの。腕はいいが、時々目の利かない人…まあ、たいがいのお客さんはそうですがね…。…偽物を売りつけたり、良い品を粗悪品だと言って安く買い上げたりすることがあったそうなんですよ。しかも、ちょっと怖いお兄さんたちとも『ヤミ』で取引などをしていたそうでしてね、最後は警察沙汰になったということなんですよ。新聞とかには載らなかったようですが…。
こういう商売はいろいろと誘惑がありますからね。ほっほっほ。」
私の思考回路はとうとう全開になった。
…これで謎が解けた。
…きっと、母は本物を持ってその店に行ったのだ。そこの店主からしてみれば、修理に出されたのは自分の店で買われたものではないダイヤの指輪。しかも持ってきたのは、結婚を控えた妙齢の美女。(母の名誉のため、そういうことにしておこう)。
何やら訳ありそうな状況を見て、店主は母をからかったのだ。そうに違いない。母はからかわれたんだ…。
「お嬢さん。どうしたんです? まあ、よかったですがね。修理の時にガラス玉にすり替えられたりはしておりませんでしたよ。お父さんが偽物だと思って持ってきたそれも正真正銘の、当店でお渡しした本物のダイヤモンドでしたからな。ほっほっほ。」
私は、店主にお礼を言い、自分が結婚する時には必ずここで指輪をつくってもらいます…、と一方的に固い約束をして店を後にした。
商店街を抜けて空を見上げると、青い空に浮かんだ雲がほんのりと夕陽に染まっている。
爽やかで、そして、あたたかな…
まさに、今の自分の心の風景が帰途の空を彩っていた。
エピローグ
家に帰ると、ちょうど父も母もいなかった。
私はこっそりと父と母の寝室へ入った。母の鏡台に腰を掛け、抽斗をそっと開けてみる。そこには臙脂色の綺麗な箱があった。それを優しく手に取ると、蓋を開けてみた。そこには決して衰えることのないダイヤモンドが、静かに気品のある輝きを放っていた。
静かにリングを指先で摘み、陽にかざしてみる。
あたかも今の私の心を映し出すかのように、透明感のある光が幾重にもなって煌めいていた…。そして、リングの内側には「from M to Y」と刻まれていた。
私は「あなたはいつかは私のものね。」とひとりごちてみた。
…父も母も知らない事実を私一人が知ってしまった。10年来の秘密に、また一つ秘密が加わって。しかも、結果としては最高の事実としての「秘密」を…。
この指輪は、一時たりとも「偽物」なんかじゃなかったんだ。プロポーズの時、父が格好つけて母に渡した時も…、母が落として危うく波にさらわれそうになった時も…。そして、父がずぶぬれになって探していた時も…、
…母が洗濯機でまわしちゃって、修理に出さなきゃいけなくなった時も。…結婚式の時も、…私が生まれた時も、ずっと、ずーっと…。
自分が見たこともない情景が、実際に目に見えるそれよりも遙かに鮮やかに、私の瞼の裏側に浮かんでは消えていった。
知らない間に涙が頬をつたっていた。
父と母の幸せが身に沁みて、涙が後から後から止まらなかった…。
本物であろうが、偽物であろうが、そんなことは関係のない次元で「世界で一番美しいダイヤモンド」…それが私の目の前にある…そう思えた。
そして…
私には、心に決めた人がいる。もう付き合って数年になる…。この間母に危うく感づかれそうになった時にはどうしようかと思ったが、近々彼を紹介しようと思っている。
…彼は、お父さんとよく似た人だ。目が綺麗で、誠実で。ぶきっちょだけど頼りがいがあって…。
…そして、彼のイニシャルはY。私のイニシャルはM。
「from M to Y」
父と母とは反対だけど、私にとってはちょうどいい。だって、この指輪は父が母へと思いを捧げ、そして今度は、私の、彼への思いを守ってくれるお守りになるのだから。
父から母へ、そして母から私へ、そして今度は私から彼へ…
父にも母にも、この話はできないな。でも、きっと彼と結婚できたら、いつかこの指輪の話をしよう。そして、生まれてくる子供にも…。
ちょっぴり誘惑はあったけれど、まだ、自分の指にはめるのは怖いような気がして、私はずっとそれを指先で持って、ダイヤの放つ静かな光を眺めていた…。
そして、それをそっと自分の唇に触れさせてみた。
するはずもないのだけれど…、ふっと潮の香りがしたような気がした。
《了》
© Rakuten Group, Inc.