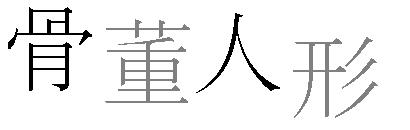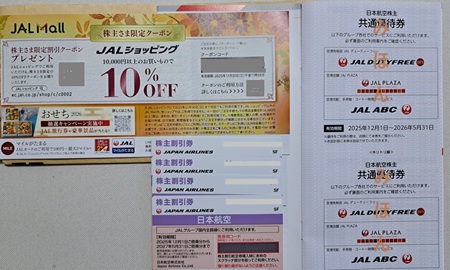鬼遊戯 -1話-
"「 いいか、真魅。 私とお前は、人とは違うんだ 」"
一枚の障子の向こう側には、大好きな祖父。
白い浴衣からはみ出る骨ばんだ細すぎる手足。
すっかりと痩せこけた幽霊のような顔。
そんな祖父の姿を見るのは、苦しくて、痛かった。
右手に縛られている、鍵つきの鎖は肉に食いつき、見ていて痛々しい。
祖父はずっとこの家のこの部屋で、私達家族から隔離されていた。
家族全員が、まるで奴隷を扱うかのように、祖父を扱うのだ
その理由は、私にはわからなかった。 否、わかりたくもなかった。
「 おじいちゃん、今からでも遅くないよ。 一緒に逃げよう… 」
障子に手をへばりつかせながら、ゆっくりと嘆いた。
へばりつかせている手は汗ばみ、微かに震えを起こしている。
祖父は、私を見つめ、笑みを作った。
"「 …真魅、もし、私が死んだら、すぐにこの家を離れなさい 」"
微かに開かれた障子から伸びる手。
その手が私の頭の上に着地し、歩き回る。
歩き続けるその手は、しわしわで、暖かかった。
その手が祖父の手だとわかったのは、障子の隙間が閉められた後だった。
― その3日後。
あの部屋で、祖父は死んでいた。
天井から垂直に伸びる白いひもを首に巻きつけ、手足を鎖で拘束されながら、浮遊していた。
散々哀れな人生を送ってきた祖父は、死に方までもが哀れだった。
ただ、どうしても、祖父が自ら命を絶ったとは、考えられなかった。
―――― 殺された。
だが、一体誰が?
その時だった。
カチャリ…
小さな金属音とともに、右手首に違和感を感じた。
まさか、と思いながら、視線を下へと落としていくと
そこには信じられないものがあった。
"「 …真魅、もし、私が死んだら、すぐにこの家を離れなさい 」"
三日前、祖父が私に言っていた言葉を、今更思い出してしまった。
――― 時、既に遅し。
私の手首にあったものは
鎖、だった。
不気味な光沢が、私を見つめている。
それは、これから怒る恐怖を表しているかのようだった。
「 あのジジイが死んだから、今度は真魅の番 」
皮肉にも、その鎖を握っているのは、私の姉だった。
さもおかしそうに目を細め、口角を三日月形に曲げている。
その顔は、どのホラー映画に出てくる幽霊よりも怖くて、恐ろしかった。
「 やだっ!! 離してよお!! 」
まるで、荷物を運ぶキャリーケースのように、私をずるずると引きずっていく。
甲高い声を屋敷内に響かせながら。
" 「 今度は真魅の番 」 "
それは、祖父と同じ運命をたどることを意味していた。
→『一話後半へ続く』