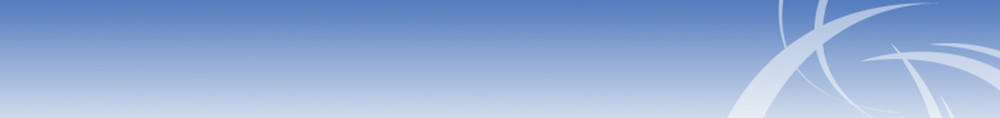シックスクール問題とは、
児童・生徒や教師が体調不良を訴えるというような健康被害が学校施設などに起因すると
考えられる場合、また、化学物質過敏症の児童・生徒への対応を含めた複合的な問題の
総称のこと。
NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第一章では、この問題についての対応、課題について言及されているのでこちらに掲載します。
室内の化学物質濃度が厚生労働省の定めるガイドライン値以上となった学校のことで
あり、そこにいる多くの児童・生徒さらに先生までもが、目や喉などの粘膜が痛い、嫌
なにおいがする、頭痛がする、倦怠感があるなどの症状を訴えたとき、シックスクール
症候群が起きたことになるのだろう。
ここで問題解決のためにも大切なのは、多くの児童・生徒、教師は問題ないのに、ごく
一部の児童・生徒(時には先生)から上記と同様の症状が訴えられ、なおかつ、それら
を訴える人々が化学物質過敏症の体質を獲得しているとの診断を受けている場合は、
化学物質過敏症患者が学校にいたという話で、シックスクール問題ではない考えるべ
きである。
これはシックハウスの場合は、問題が個人レベルであるが、シックスクール問題は個人だけでなく、父母会対学校といった組織レベルの問題になるためその対策を実施する場合、問題の所在を明らかにする必要があるために明確にする必要があるとも言われています。
それは主として建物に問題があるのか、人にあるのかをしっかり見極めることと言えます。
その対応については、次のように説明されておられます。
学校の校舎に問題がある「シックスクール症候群」であれば、まず後者の問題のある
箇所を直すのが先決で、これは純粋に建築技術的対応で問題解決に至るはずである。
一方、児童・生徒が化学物質過敏症であるための問題であれば、建物に対して建設
技術的な対策をしても、問題の全面的な解決には必ずしもつながらないであろう。
化学物質過敏症の児童・生徒に対する医学的処置を考えるとともに、そのような児童・
生徒でも学習できるような場を学校内の一部に確保するといった制度的な対応が現実
的であろう。
上記では学校における建物を起因とする室内空気汚染問題を例としての説明でしたが、建物以外(学校の教材など)についても同様で、シックスクールと化学物質過敏症との違いを正確に見据える事が問題の第一歩と言えます。
【関連サイト】
-
食物アレルギー 2011.08.29
-
ペットボトル症候群 2011.08.23
-
慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive P… 2011.06.14
PR
カレンダー
サイド自由欄