第三話 神が望みし戦い
「東京って、もっと人が多いと思っていたけど、意外とそうでもないんだなあ」
もっとも、田舎者の自分が知っているのはテレビなどに映る東京の街並みだから、実物と違うのは当然かもしれないと慎吾は納得した。とは言っても、日本の首都東京だからと不安半分期待半分だった慎吾からすれば期待外れの一面もあるが。
それよりも、今は上京先のおくたまだに行かなきゃならない。事前に路線は覚えているけど、多いみたいだから苦労するだろうな。うちは下りと上りの二つなのに……と、周囲を見まわしていると、シートに覆い被さった何かが目に止まった。
シートの合間から出ている、筒みたいなのは……自衛隊制式使用の、《リニアガン・タンク》? まさか。都内のど真ん中にそんなものがあるなんて、戦時中じゃあるまいし。
「ブルドーザー……なわけないよね」
「へええぇ……すっごいなあ」
電車の中で、つい口に出してしまった。隣に咳払いされたのですみませんと慎吾は頭を下げた。
意外にも電車は数本しかなかった。どうも臨時で少ししか運転されていないらしい。発電量不足で電車が停止したのかなと思って、一昔前ならいざ知らず、シズマドライブ全盛の時代にそんなことあるかと先生に笑われたのを思い出した。
「すっごいなあ……」
電車の窓から見えるのは、田舎では決してお目にかからなかった高層ビルなど巨大建築物の数々。ギガンティック・フォーミュラ決勝戦を行う新東京ドームもあった。やはりこうして見ると大きい。
他にも、レイバーなど作業用ロボットが多数いた。どこかで工事をしているのだろう、その数は多い。種類なんか慎吾にわかるわけもないが、他のと倍くらい大きいのもある。あれ? あれはMSだったかな? まあいいか。
そうこうしているうちに、トンネルを一つ二つ抜けて目的地のおくたまだ駅に到着した。到着した、が……
「って、ここも東京なんだ……」
目の前にあったのは、さっきの東京駅より閑散とした街並み。というより、木と森で覆われたそれは自分の田舎とさして変わりはなかった。建物もどこか古臭い。本当にここは東京なんだろうか。いや、そんなこと気にしていられない。
「えっと、まずは市役所か」
手続きをするため、市役所に訪れた。簡単に済ますと、次は学校へ向かう。
途中、歩いていると子供とそのお母さんがおもちゃ屋の前でもみ合いになっていた。買ってほしいと駄々をこねているのだろう、クソババアなんて言っちゃって、思わず慎吾は吹き出してしまった。
「なんだか、そんなすごい都会でもないね」
そこで、ふと思い出したことがあった。上京する直前、両親の墓へ訪れた時のことだ。
「久しぶりだね、父さん、母さん。こうして会いに来るの、しばらく出来なくなる」
そこでうつむいて言葉を切った。悲しい顔になってる気がして、墓石を直視できなかったからだ。顔を上げると、笑顔に戻して明るい声を出す。
「引っ越すことになったんだ。東京、首都。国の中心だよ! どんなところなのかなあ……」
不安と期待に思いを馳せていると、強い風が吹いた。夏の暑い風に揺られると、それに乗ってきたように声がした。
「お願い……」
「え?」
慎吾が顔を上げると、そこには自分と同じくらいの少女がいた。長髪をポニーテールにして大きめのリボンで纏めている。どこかの制服を着ているけど、これはかなり……
「……可愛い」
「えっ」
びっくりした少女は、視線をそらしてうつむいてしまった。またやってしまった。あわててフォローする。
「あ、ごめんなさい。あ、そんなつもりじゃなくて……いや、そうじゃなくて、僕、つい思ったことを口に出しちゃう癖があるみたいで……す、すいません」
言っているうちに自分でもわけわからなくなってしまった。言うつもりじゃなくて、でも可愛くないわけじゃないし、ああだからそうじゃなくて……
なんて戸惑っていると、彼女の方が落ち着いたらしく真顔に戻っていた。つられてこちらも言葉を変える。
「こんなところで、どうしたの? あ、『お願い』って言ってたよね? もしかして、迷子? 困ってるんなら、力になるよ」
とりあえず、それだけ言ってみた。他に思いつくことはないし、見たことのない顔だから多分よそから来た人間だと思ったからだ。
ところが、少女は一瞬目を見開くと、蚊の鳴くような声で「お願い、します」とだけ言った。
「え? はい!」
なんだかわからなかったけど、その真剣な様子にそう返事した。
その真剣な瞳で、少女は言葉を重ねる。
「お願いします。戦って……勝ってください」
「え?」
戦う? 慎吾はその意味を理解できなかった。戦うって、何と? 誰と? 待った、もしかして……
「戦って、勝ってください!」
しばし、鳥と木の葉の揺れる音だけがその場を包んだが、やがて慎吾は、
「あ、ああ……いいですよ」
そう返答した。
「そりゃ、負けるよりは勝った方がいいですもんね」
笑って答えると、少女はホッとしたような顔をして、
「ありがとう」
と笑った。そこでまた「可愛い」と口にしてしまい、あわてて口を塞いで後ろを向いた。
しかし可愛い。笑うとまたメチャメチャ可愛い。ふと、そこでおかしなことに慎吾は気付いた。
戦って勝ってとは、『ギガンティック・フォーミュラ』の決勝のことだろうか。しかし、どうして彼女が自分が代表であることを知っているのか?
「なんで君、ゲーム大会のこと……あれ?」
振り返ると、そこに彼女はいなかった。駆け寄ってみても、影すら見えない。
「確かに、ここにいたよな? 幽霊、だったのかな……」
『ギガンティック・フォーミュラ』は、日本全国で人気のオンライン対戦ロボットゲームの名前だ。基本的に一対一で、カスタマイズすることによって自分自身の戦術を組み立てることもできる。その大会に、慎吾は第十一区代表として選ばれた。本当は手続きが終わった後会場に向かう気だったのだけど……このままじゃ行くのは難しそうだな。オンラインでやるしかないか。
「先に会場行くべきだったかなあ。でも、手続きの方が大事だし……うん?」
視線を感じた気がして、慎吾は後ろを向いた。特にこちらを見ているような人は見当たらず、気のせいと判断してまた歩を進める。
スーパーロボット大戦B
第三話 神が望みし戦い
「気づかれたんですか? 教官らしくもない」
(そんなわけないだろ。くだらないこと言ってないで、お前も働いたらどうだ東馬)
「了解です。と言っても、それほどやることはないんですけどね」
ははと笑うと、呆れた様な目で睨まれた。この細目は昔から苦手だ。通信モニタを切りたくなってしまう。
「まあ、こちらもやれることはやりますよ。教官も、護衛任務よろしくお願いします」
(わかっている。通信終わるぞ)
そう言って、間髪入れず通信を切った。相変わらず仕事熱心な方だ。三年近く腐っていた身としては眩しさすら覚えてしまう。
「まったく、あの歳で頑張るねえ。ソフならとっくに引退してる身だろうに。ま、あの人は別枠か」
「あらあら、そんな陰口叩いていいんですか? 壁に耳ありですよ?」
「……いや、その、勘弁して下さい技術主任」
通信パネルの反対側から発された高い声に、東馬は気が滅入るのを感じた。ツインテールを天使の羽みたいな形をしたりぼんだか何かで纏めた特徴的な髪形をした少女が、多数のパソコンの前で作業をしていた。
こんなナリでも、技術主任の名の通りプラクティカルベースの技術班長を務めているのが、天野卯兎美という少女だ。遺伝子操作によって人為的に天才児を作り出す連邦主導のプロジェクト『ネオ・カンブリア・エクスプロージョン』の賜物らしいが、十年前のこととはいえ地球上でよくそんな計画が起こせたものだ。まあ当時はフルーコスモスも台頭していなかったし、コーディネイターの技術、科学力の優位性は覆せないから、ひっくり返したいというのは誰しもが持っていたのだろう。何人殺されたか知らんが。
そんなわけで、天野技術主任はあの『電子の妖精』ホシノ・ルリに勝るとも劣らない天才として知られている。が、
「あー、また技術主任なんて呼んでる。うっちぃって読んでって言ったじゃないですかあ」
「……あー、えっと、それは……」
なんてことを本気で懇願する子供にしか東馬は見えなかった。
いや、この少女が優秀な科学者なのは疑っていない。数日前ホスの解析を頼みに訪れたのも、現在日本国内で最も頭のいい人間を探した結果彼女だったのだから間違いはない。まあWWWが始まる最中、やることが多すぎて解析は滞っているようだが、そんなことに文句を言う気は全然ない。
しかしこのガキ、『うっちぃ』と愛称で呼べとあまりにしつこいのだ。何故うっちぃなのだ。この歳でそんな愛称を使えなんてかなりの抵抗がある。平たく言うと恥ずかしい。
とはいえ、こんなことで機嫌を損ねられると困るのも事実。仕方ないとため息をついた。
「……はいはい、わかりましたよ、うっちぃ」
「よろしい♪」
満足げに頷くと、作業を再開する。経験上、こういう人間にはとりあえず従っておくのが正しいとわかっているので、抵抗は無駄と諦めた。
――わかってる、か。
そう、こういった感じには覚えがある。外見はともかく、なんとなくこの天野……うっちぃとどことなく似ている人物を、東馬は知っていた。明るくて、気さくで、よく笑ってて、でも、でも……
「? どうしたんですか? 暗い顔して」
「いえ……なんでもありません」
嫌なことを思い出してしまった。渋いんだか苦いんだかよくわからんコーヒー味のつばが滲んでくる。
「それで、例のパイロット候補ってのはまだ来ないんですか?」
「う~ん、もうそろそろ始まっちゃうんですけど……あ」
そこで通信が入った。ある選手が、オンラインから出場したいということだ。オンラインゲームなのでそういった設備は無論整っているが、場所によっては若干のタイムラグが発生する故に他の選手は皆会場に来ていた。楽一さんが全然別の場所で尾行していて変だなと思ったが、こういうことか。
しかし、こいつがギガンティックのパイロットねえ……こんなサル顔のガキがかよ。
「州倭慎吾……こいつが《スサノオ十式》のパイロットねえ。パッとしない子供にしか見えないが……と」
「では、最終確認をします。その場所からの参加では、会場のサーバーから距離があるため、若干ですがタイムラグが……」
いつの間にか、画面に向かって会話していた。その慎吾とやらとオンライン通信しているらしい。こっちの責任者でもあるんだったっけ。
「それにしても……ゲームでパイロットの適合試験とはね。フライト・シミュレーターじゃあるまいし、今時マジでやるとこがあるとは思わなかったな」
「まあ適合試験と言っても、形だけだがね。検証結果がなければ、上が納得しないからやるのであって」
独り言に返答された。振り返ってみると、歳のいった男性がそこにいた。いい歳だろうに、それを感じさせない姿勢のよさなどきりっとした感じがあるのは、元自衛官上がりだからだろう。
「皇田副指令……」
「話は聞いてるよ、君が東馬くんか。あの楽市くんの部下だったからには、かなり優秀なんだろうね」
「はは、そんなことは。教官に比べればまだまだですよ」
プラクティカルベース副指令、皇田力。元自衛官上がりの彼は、あるロボットの開発に関わったことにより、この新東京ドームの地下ドックでゲーム大会の決戦にかこつけた適合試験とやらに参加していた。適合する相手とは――
「それにしても、実物は初めて拝みましたよ。確かSRX計画のロバート・H・オオミヤ博士の協力も得ているんでしたっけ?」
「ああ、『ギガンティック・フォーミュラ』も彼がメインスタッフとして開発したものだ。もっとも、基本的な設計のみだがね」
「なるほど、道理でRシリーズと似てるわけだ……スケールは違うがな」
二人の目の前にあったのは、全長三十メートルはあろうかという鋼鉄の巨人。まあこの時代巨大ロボットは珍しくないが、これは他のと一味違った。
《スサノオ十式》、これこそが“紳士的な”決闘戦、WWWの主役である日本のギガンティック・フィギュアだ。次期連邦政府盟主を決める戦争……まあ、実際はそれだけじゃないのだが。
「でも、成績なら他にもいいやついるじゃないですか。このリュウセイ・ダテとかテンザン・ナカジマとか。どうして、わざわざ中学生の子供を?」
そう聞くと、皇田副指令は薄く笑った。
「さっきも言ったけど、これは形だけの試験だ。実際は、パイロットはもう真名くんと《スサノオ》が決めている」
「《スサノオ》が……ですか」
例の、トランスレータ―とやらか。詳しいことは東馬も把握していないものの、ギガンティックと意思疎通できる存在、なんて話だけど、正直言ってよくわからん。資料を見直す必要があるな。
とにかく、こいつで決定済みということか。だとしても必要と決め付けたものがないと認めないというのは、相変わらずと言うべきか呆れるべきか。と、誰かかやってきた。ポニーテールの長髪を大きめのリボンで纏めている。この制服は、さっきの三つ編みおさげが着ていたのと一緒だ。
「戻りました。――と、貴方は?」
「729、って言えばわかるだろ?」
笑いかけたこちらに反して、少女は目を見開いた。やはり同窓か。正確には、俺は元がついてしまう立場なんだが。
「初めまして、東馬十二です。今まで別件を担当していたんだが、色々あってこっちに回ってきた。よろしくな」
「……よろしくお願いします。神代真名です」
握手は返されたが、全身くまなく調べる視線を受けた。まあこんな大事な任務の最中突然異物が混じってくればいい顔はしまい。当たり前の話、別に気にするまでもない。
「あれ? 真名さんまたですか? 本当に好きなんですねえ。でも、今は候補者の適合試験中なんですから、あまり、ここを離れないようにして下さいね」
「すみません、技術主任。でも私、彼を好きってわけじゃ……」
「ああ、私は、『物好き』って意味で言っただけでぇ……」
「……!」
東馬にはわからなかったが、真名がそこで顔を赤らめたことといい、うっちぃがニヤケ顔をしていることといい、どうも何かはめられたようだった。今の会話のどこが問題なのかは不明だが。
「それはともかく、彼、どこからオンライン参加してるかわかります?」
うっちいが、何故だかさっきより楽しそうに笑っている。彼というのは、例のパイロット候補の慎吾とやらだろう。オンライン参加ならパソコンと接続媒体さえあればどこでも可能だが、わざわざ言うとなるとよっぽと変わった所か?
他の二人も疑問そうな顔をする。予測がつかないらしい。そんな東馬たちに対し、うっちぃはこちらへ向き直ると答えた。
「おくたまだ第一小中学校!」
? 東馬の聞いたことのない名前だった。しかし、真名たちは息を呑んでいる。待てよ、さっき教官が監視していた慎吾が向かったところがおくたまだとか……
「決勝戦、開始します」
そこで『ギガンティック・フォーミュラ』決勝戦、に名を借りた《スサノオ》との適合試験が始まった。ここで得られた候補者のデータが、上を納得させる裏付けになる……それは必要ではあるが、間に合うのかね。WWWはもう始まっているというのに。いつ宣戦布告されてもおかしくない。
いや――もう戦争は始まっているか? 思い直した東馬は、その場を後にしようとする。
「あれ? どこ行っちゃうんですか?」
「ここにいても手持無沙汰なんでね、仕事探してきますよ。それじゃ天……うっちぃはデータとやらをよろしくお願いします」
別れ様にむくれられ、仕方ないと自分に言い聞かせて改めた。
日本で大人気の『ギガンティック・フォーミュラ』とはいえ、さっき知ったばかりで元から興味もない東馬にとっては、大画面で映る戦闘シーンも会場を包む熱気もまるでよそ事だった。こういうのは詳しくないからな。中里だったら好きそうだが……と呟きかけて、怖気が走った。
自分の口からこんなセリフが出るようになるとは。こんな惚けたことを言うほど落ちぶれたか? 愕然を通り越した失望を新たに確認しながら周囲を見回す。……いた。
別に東馬は、全然関心のないゲームのバトルを見にきたわけではなかった。ここで最終試験があると、それでなくてもこの地下に《スサノオ》があるとすれば、動かない奴がいないわけがない。この熱狂の中、ただ一人冷静でいるような奴とか。隠した無線機で会話してるような奴とか。東馬はスーツ姿の男に近づいた。
「……者、怪しまれるぞ! 日本語を使え! 目標の座標は算出完了。まさかとは思うが念のためだ、例の小隊を急行させろ」
「ちょっと、お客さん」
「!?」
いきなり声を掛けられたので相手は身構えたが、いきなり攻撃に転ずる愚は犯さなかった。こちらの姿を見て、警戒を少し弱めた点もある。
今の東馬は、警備員の服を着ていた。無論警備員だからと言って油断はできないが、それでも“敵”にいきなり繋がる相手ではない。向こうも今騒ぎたくはないだろうし。
「困りますね、携帯は会場内じゃ禁止ですよ? こっちへ出てもらわないと」
「は、はい、すいません……」
目つけられると面倒だからと、謝って会場の外へ出ていく。気づかれないように、やや距離を持って尾行する。苦手だが、これくらいはやれないとな。
会場から出ると、男は影になっている部分で無線を終わらせていた。
「お客さん」
「! ……なんだ、また貴方ですか。今度は何の用です?」
「携帯は結構ですけど、無線はちょっと困るんですよね。大陸製は出来が悪くてうるさいんですよ」
「……っ!」
ハッとなった男は、胸ポケットに手を入れた。が、
「ぐっ……!」
瞬時に距離を詰めた東馬が、ナイフを喉に突き刺していた。
「ぅ……ダイスの犬め……」
「せめて市ヶ谷って呼べ、中央国の犬」
ぐぃとナイフを一捻りすると、それで男は絶命した。
近くの陰に男の遺体を隠すと、東馬は袖のマイクで通信する。
「一人仕留めました。他にも複数いる模様」
(勝手な行いをするな。指示に従え)
「すいません。だけど、どうせ聞くような相手じゃないですからね……」
敵が中央国だとすれば、開戦の瞬間に仕掛けてくるだろう。また、そうでなければWWWは成立しない。だから、多少問題が起こっても動けないのは確実だが、だからと言ってこちらの勝手が許されるわけもない。しかしこのままだと先手を取られる危険がある。――仕方ないか。
「教官。勝手を重ねるようですが、頼みがあります」
(……なんだ)
「この辺りで、機動兵器がまるこど収められるスペースはありますか? それと、こことそちらの監視カメラの映像を回して欲しいんですが」
トーンからして本気とは理解したようだが、目的がわからず困惑したらしい。東馬は続ける。
「こちらの任務に関することで詳しく説明はできませんがお願いします。上手くいけば、WWWの緒戦を圧倒できるかもしれません」
指定された場所は、ドーム近辺の空きビルに擬装した格納庫だった。既にMSや《リニアガン・タンク》の類も待機している。もっとも、相手が中央国の場合、どれだけ通じるか疑問だが。
「周辺海域の様子は?」
(レーダーが使えないから目視しかないが、今のところ何もない。潜水空母の反応もないらしい)
「ま、見つけたところで布告されないと何も出来ないんだけど……」
通信しながら、東馬は左手の器械、《喪羽》を呼び出す通信機『ブラックライト』……確か、虫を誘導するための蛍光灯の名前だったか? 転送装置にそんな名前を付けるとは、洒落を効かせ過ぎだあの馬鹿。
「エマージェンシー。コード『羽根なしパピヨン』」
電子版に『ENTER』の文字が表示されると同時に、《喪羽》が転移されてくる。空間転移技術は既に『ボソンジャンプ』が存在するが、あれは原因不明の故障とやらで使えないので、東馬が知る限り《喪羽》が唯一の空間転移能力を持った機体ということになる。突然出現した《喪羽》に作業中の自衛隊員たちは動揺したが、東馬は気にせず乗り込んでいった。
「システムオールグリーン、《喪羽》起動」
音声入力で起動した《喪羽》に、最初に東馬がやったのは回線を開くことだった。楽市教官から指示された監視カメラの映像。メインモニターに表示されるだけ表示する。
「……さすがに小さいな。まあ、なんとでもなるか。プログラム起動、コード『羽根なしパピヨン』」
メインモニターが割れ、サブモニターが出現する。サブモニターにも同じ監視カメラの映像が映されているが……否、少々違っていた。
おくたまだ第一小中学校周辺、新東京ドーム、それと一応日本海側に待機している自衛隊からの映像。どこにも特筆するようなものは映っていなかった。メインにもサブにも。
「異常なし、と。日本海側はやんなくていいかな。このカメラで映るものならとっくに……ん?」
監視カメラの一角、会場の外を映したものに、場違いの代物が存在した。
青を基調としたボディは、人型ロボットの風貌だがそれは人間サイズで、実際は装甲服の類である。突き出た二本の触覚、あるいは角と呼ぶべきものと顔に比べて巨大な赤い二つ目は昆虫類のそれであり、《喪羽》と似たようなものを思わせたが、もちろん両者に関係はない。それ以前に、東馬はそれが何なのか知っていた。
「《G5》? 自衛隊使用……じゃないな。あれは黒基調のはずだ。桜田門が出しゃばってきてんのかよ、勘弁してくれ……」
憲法九条改正前ならともかく、治安維持が自分たちの仕事と譲らないのは相変わらずか。その頑固ぶりには呆れるのを通り越して感心するべきだろう。吐息を深々と出しながらシートに背を預けた。
六年近く前の未確認生命体、及びアンノウン関係の事件で、その被害を食い止めるため警察庁が独自に開発した強化装甲服、《G3ユニット》。アンノウン事件にはそれなりの活躍をしたそれが、改良と量産に向いた《G5ユニット》として全国に導入されてから久しい。
しかし、《G5》はいつの間にか本来の役目から離れ、暴徒などの制圧や特殊部隊の兵器として使われるようになっていった。自衛隊などで使用されるならまだしも、各国でライセンス開発されるようになり、各紛争地でもその姿が見られるようになった。民間で作業用や救助用として使われるケースもあるにはあるが、その出自からしてやはり戦闘用が主体だ。
一応、その『本来の仕事』とやらもやっているそうだが……進んだ技術は全て戦争用に転換か。まったく、人間のやることはいつも変わらん。
鼻を鳴らしていると、サブモニターに映された映像の一つに『Shingo Suwa』の文字が浮かんでいた。
「と……あいつ勝ったのかな」
東馬が起き上がると、合わせたように声がした。
(優勝者決定! 優勝は、第十一区代表の、州倭慎吾選手!)
遅れて、メインモニターにもさっきの映像が表示される。歓声がそれをバックに雪崩れこんできた。ふむ、これで上の人々とやらも認めざるをえまい。と言っている自分も、資料に貼られた顔写真からして信じられていなかった身なのだが、それは忘れることにした。
「……ん!」
その時、サブモニターに『UN』の文字が浮かび上がった。東馬が身構えると、警報が鳴り響く。
確認する。UNからの緊急放送。内容は――聞くまでもなかった。
「来たか……中央国」
日本海を映していた自衛隊の映像は、とっくに両方ともノイズだけになっていた。
(Wisest World War、巨神像ギガンティック同時の決闘による賢明なる戦争。本日、中央人民共和国が日本に対する開戦を申請、UNはこれを……)
「こちらキウイ、座席4と8と11で動きあり、急行してくれ!」
UNからの放送を無視して、東馬は自分の認識コードと共に会場内に潜んだ“敵”――中央国の特殊工作員らしき人物の情報を送る。サブモニターの中に、何人か銃を抜いた奴がいた。ちなみにメインではまだ誰も動いていない。
一般人に化けた男たち銃を抜いて選手たちのいるフィールドへ走ろうとすると、同じく化けていた市ヶ谷の人間に無力化される。しかしさすがに全員というわけにはいかず、何人かと戦闘になる。そこで、サブモニターに映った映像が数個消える。
「っ! やばい、退避しろ!」
思わず叫んだが、時すでに遅し。轟音とともに、メインの映像も途絶えた。
(本部より入電、日本海方面から、長野県上空を低高度でこちらに接近する飛行物体群が確認……)
「知っとるわ、そんなこと!」
会場外の監視カメラには、屋根が破壊されたドームが映されていた。戦闘機による爆撃、身内もだいぶやられたか。
「空自は何やってたんだ、こんな簡単に侵入を許すなんて……!」
そう東馬がわめく間に、もう他の機体は出撃していた。連邦軍で制式使用されているMS、《ダガー》タイプが戦闘機群と戦端を開いた。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 読書備忘録
- 10月に読んだ本 桐野夏生「顔に降り…
- (2025-11-20 11:57:45)
-
-
-
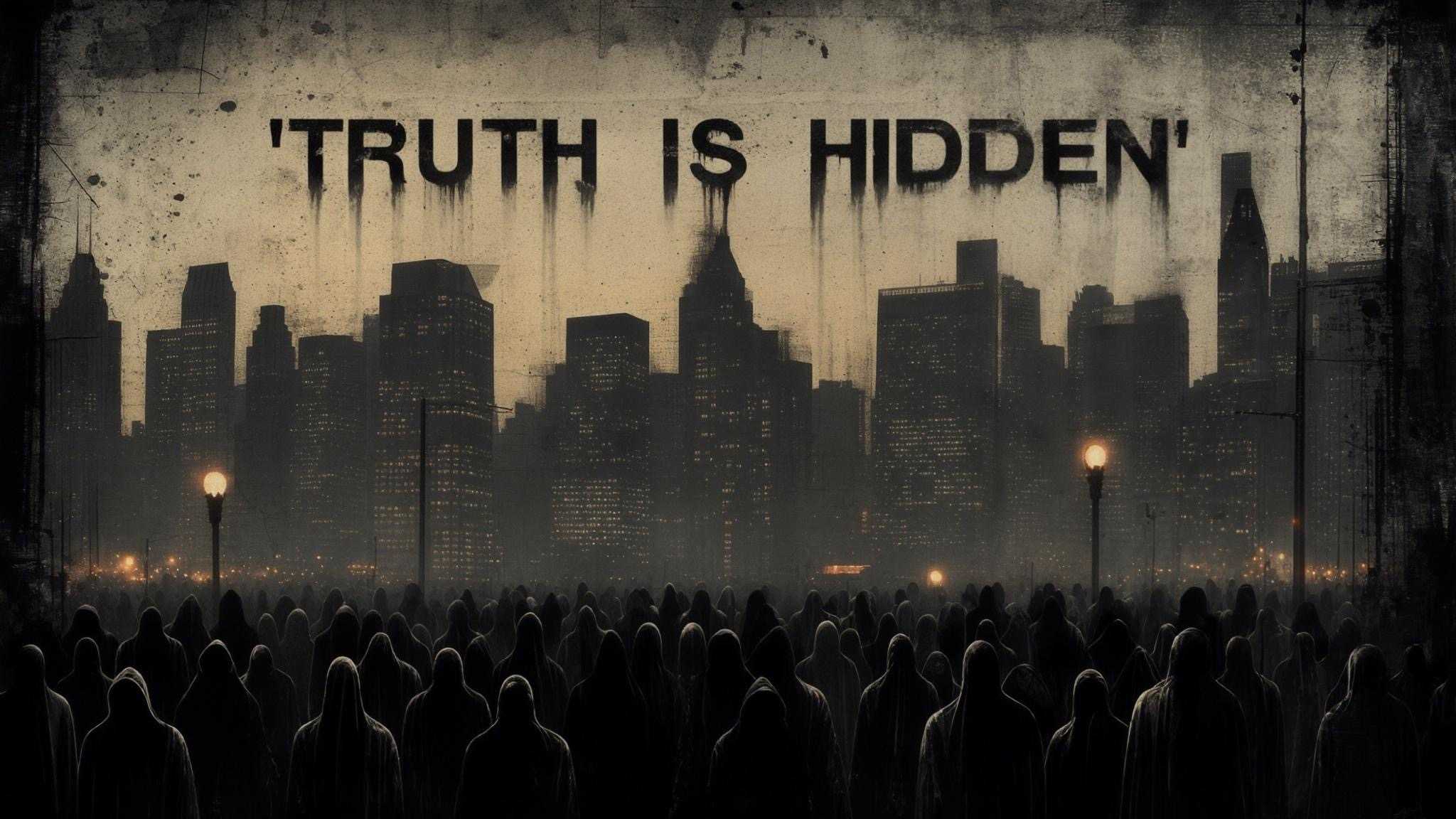
- 人生、生き方についてあれこれ
- 陰謀論はなぜ生まれるのか|権力の不…
- (2025-11-21 12:57:17)
-
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-
© Rakuten Group, Inc.



