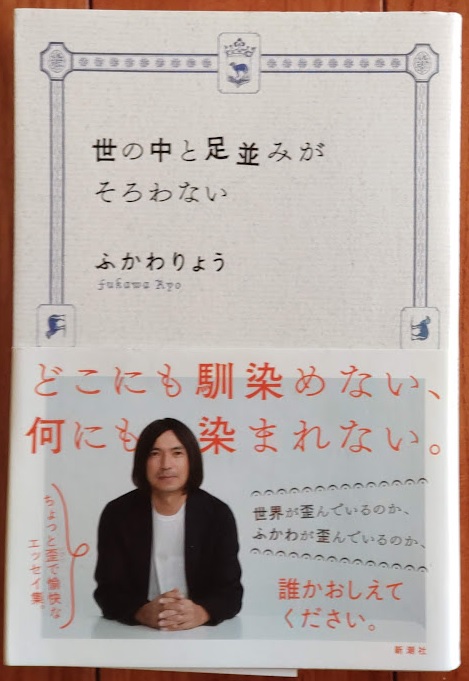雨が止まない 6
自分のせいでもない、誰のせいでもない―――
でも、誰かのせいにしないと自分の気持ちが壊れそうなのだろう。
・・・それにしても、滋さんはいったいどこに行ったのだろう?
彼女が簡単にここを出て行くとは思えない、離婚もしないだろう。
なのに、今この家にいない。 使用人たちも誰にも言っていない。
彼女が行くところ―――実家しかない。
椿は不安だった。 大河原とは二人の結婚で業務提携している部分がある。
この結婚が壊れるとき、大河原はどうでるだろうか?
滋さんは一人娘―――我儘いっぱいに可愛がられたお嬢様だ。
手に入らないものはなかったに違いない。 そんな彼女が唯一、手に入れられなかったもの。
それが司。
お見合いして、簡単に企業どおしの結びつきもあり、結婚できると思っていたに違いない。
だが、司の愛情はすでにつくしちゃんのものだった。
彼女は純粋でもあったから・・・その場は諦めた。
つくしちゃんとも親友になった。 彼女はきっと司が記憶喪失にならなければ諦めたままだった。
愛情は簡単になくならない。
滋さんは司への愛を秘めて親友を演じていたんだろう。
そして、司がつくしちゃんの記憶をなくしたとき、悪魔が囁いた。
―――彼を自分のものにするチャンスだよ―――
今回の縁談は大河原からのものだった。 それに母がのったのだ。
つまり、滋さんが両親を動かし、司を手に入れた。
結果、司も滋さんも不幸だ。
彼女は自分を取り戻すことができるだろうか?
それとも悪魔がまだ―――?
椿は大きなため息をついた。
今回の騒動はどちらの財閥にとっても、大きな損失になるだろう。
司は混乱している。 つくしちゃんを取り戻すことしか考えていない。
道明寺の後継者としては、それではいけない。
司、お母さんが出てくるわよ。 もしかしたら・・・お父さんも出てくるかもしれない。
しっかりしないと――――もっと不幸になるわよ。
滋は、椿の予想通り実家にいた。
司が家に戻らない今、道明寺邸にいるのは屈辱的だったのだ。
使用人には好奇の目で見られ、タマさんには無言で責められている気がした。
司の記憶が戻る前はそういうことは全然気にならなかった。
でも、状況が変わると使用人だけでなく司自身が私を責め立て苦しめる。
5年もつくしのことを忘れ、私はいつも司のそばにいた、だから少しは愛情をもってくれていると思っていた。
私を少しは愛してくれていると思い込んでいた。
まさか、司にとって私は友達でしかなく、愛はまったくない、仕事上のつながりだけの政略結婚だったなんて信じられなかった。
「滋、そんなに辛いなら離婚しなさい。 道明寺と切れても何の問題もないから。」
父親の言葉に私は首を振った。 司と別れる気はない、またつくしに司を奪われるなんて嫌だった。
「離婚はしない・・・司といる。」
両親は私をじっと見ていた。 その表情から心配していることはわかる、だけど、司を諦めることはできない。
「ねえ、パパ・・・道明寺に経済制裁っていうのかな、できない?」
私がつぶやいた言葉に父は真っ青になった。 娘がそこまで追い詰められているとは思ってもいなかったのだろう。
「滋、それはいけない。 お前はかわいい一人娘だ、幸せになってほしい。
だけど、お前のわがままで会社を動かすわけにはいかないんだよ。
道明寺を痛い目にあわせるのは簡単なことだ、しかし、それをやれば企業はダメになる。
働いている人たちがついてこなくなる。 それに道明寺が報復にでたらどうなる?
どちらも無傷ではない、道明寺や大河原で働く人々が巻き込まれ、土台が揺らぐ。
そうすると道明寺だけでなく、大河原グループも崩壊するだろう。
企業というのは私情で動かしていいものではないんだよ、滋。」
滋はどんなことをしても司を自分の元にとどめておきたかった。
たとえ、それが脅迫という卑怯な手段でも―――――
「滋、離婚は双方の合意のもとでするものだ。
お前がしたくないというのなら、それもいいだろう。
だが、それでお前自身が苦しみ不幸になるのは・・・私たちは嫌なんだよ。」
「・・・司を愛しているの。 彼も少しは私を愛してくれていると思っていたの・・・」
つぶやきに近いほど小さく静かな声だった。
「・・・とにかく、司くんには家に戻ってもらおう。義父として別居は許さない。
それくらいの意見はわがままではないだろう? 義理の父として話をしよう。
道明寺の方にも話をしよう、総裁に直接・・・それくらいしかできないよ、滋。
あとは二人で話し合うしかない。 政略結婚でも幸せになれる。
お互いの気持ちが同じ方向を向いていれば、お互いに理解しあっていればうまくいくんだよ。
私たちが良い見本だろう? どうだね、滋」
両親も政略結婚だった。道明寺の両親もそうだ。 どちらもそれなりにうまくいっている。
それなのに・・・なぜ、私たちはダメなのだろう?
うちの両親は政略結婚とはいえ、お互いを思いやって生活をしている。
道明寺は財閥を守り抜くことでお互いの視線が同じ方向を向いているのだろう。
私たちはどうなのだろうか?
思いやり・・・お互いにそういう気持ちがあっただろうか?
私は司に固執し、企業などどうでもよかった。 大河原も道明寺もどうでもよかった。
でも司は道明寺のために私と結婚した―――――この気持ちの違いは大きいのかもしれない。
私は間違いを犯したのだろうか?
でも、一度は司を手に入れたのだ、いまさら、それを手放すことはできない。
司は何がなんでもつくしと二人で話す必要があると思っていた。
正直な気持ちを聞かなくてはならない。 俺はあの男になんと言われようとつくしを愛している。
5年前の思い? ふざけるな、俺は5年前も今も、つくしを愛している。
少し・・・忘れていたが、俺の心の片隅にはいつもアイツがいたんだ!!
だから、苦しく、辛かったに違いない。 アイツを思い出せないことが俺を苦しめていたんだ。
司の頭の中は、つくしを取り戻すことしかなかった。
滋のことも道明寺のこともどうでもよかった。 愛する女をこの手に取り戻す。
アイツに会わなければならない、誰も邪魔しない場所でアイツの思いを聞かなくてはならない。
司はつくしがどう答えるかはわかっていた。 アイツは俺を愛している、それは間違いない。
きっと、俺の元に戻ってくれる。 今は俺がアイツだけを忘れたことに怒りを感じているだけだ―――
まるで自分に言い聞かせるように、心の中でつぶやき続けていた。
まさか、この年齢になって親父に説教されるとは思ってもみなかった。
それに、親父が息子夫婦のために日本に来るとも思っていなかった。
だが、親父はやってきた。 ある朝、俺が起きると屋敷が騒がしく使用人が慌てふためいていた。
「旦那さまが戻られました」
使用人をひとりつかまえて、どうしたのかと聞けばその返事。
俺はドキリとした。 何も悪いことはしていない、仕事もきちんとこなしている。
なぜ親父がやってきたのか理解できなかった。 今さら俺に関心があるわけじゃないだろう?
しかし、俺は書斎に呼び出され、滋とのことで説教をきく羽目になった。
「司、滋さんと離婚したいんだって?」
「ええ。」
「大河原の会長がNYまで来て、私に苦情を言って帰って行ったよ。
電話で済む話だと思うんだが、わざわざNYまでやってきた。 おそらく計算のうえだろうが。」
「・・・どういう意味ですか?」
「電話だったら、私もわざわざ日本に来なかっただろう。 お前に電話して説教するだけだ。
しかし、NYまで来て直接言われたのでは、私も礼儀としてお前に直接会わざるを得ない。」
滋の親父がNYに行った? ようするに滋は親に泣きついたということだ。
俺は何を言われるのかと苦々しく感じた。 だが、何を言われようと滋とは離婚するし、牧野は取り戻す。
「司、記憶が戻ったそうだね。 そのせいで離婚したい、そしてあの牧野つくしさんと結婚したいと言うわけか?」
「そうです。俺は牧野以外考えられない」
親父は俺を見つめ大きなため息をついた。
「彼女は鷹野颯介と結婚したと思ったがね。」
「ええ、でも取り戻します。」
「・・・司、滋さんとでは結婚生活はうまくいかないのか? 政略結婚でも幸せにはなれる。
私と楓は政略結婚だ、だがそれなりにうまくいっているよ。」
「ふん、うまくいっている? そうでしょうか、お互いに仕事だけが生きがいだ。
親父は道明寺財閥、お袋はメープルホテル、つまりうまくいっているのは仕事の同志だからだろう?
夫婦としてうまくいっているわけじゃないと思うね。」
「そうかもしれんが、私たちはそれで幸せなのさ。 司、お前は滋さんとうまくいくように何か努力をしたか?」
「いいえ。するつもりはない。 記憶が戻った今、俺は滋がどうしても許せない。
おそらく・・・滋が友達でもなんでもない初対面の相手なら、そんなことはなかったと思いますよ。
だが、滋は友達だった。 俺の気持ちも牧野の気持ちも知っていた。 それなのに俺の記憶喪失を利用した。
自分の都合のいいように・・・ね。 俺はそれがどうしても許せない。」
「牧野くんとお前のことは報告を受けていた。 楓がお前たちを妨害していたことも知っている。
私はお前が道明寺をきちんと率いていき、
そして彼女が道明寺の嫁として恥じない知識を学ぶなら問題ないと思っていた。
だが、お前は彼女を忘れた。 そして5年も思い出さなかった。
私はもう思いださないだろうと考えたよ。 滋さんもそう考えたのかもしれないだろう?
お前には選ぶ権利があった。 滋さんとの縁談を断ることもできた、しかしお前は了承した。
それは記憶をなくしたこととは関係ない、お前自身が決断したことだ。 それだけは忘れないようにしなさい。」
それは類たちにいわれたことと同じだった。
俺は親友の忠告を無視して、滋を選んだのだ。 その事実は俺の胸に重くのしかかった。
「・・・確かに俺は決断した。 だがその決断は間違いだった。 俺は今、その間違いを正す。
滋とは絶対に別れます。 別れられないなら、道明寺の跡継ぎは諦めてもらうしかない。」
「・・・滋さんがすでに妊娠していたら?」
「ありえません」
「いやに自信満々だな・・・」
「ええ、滋に子供ができるはずはありませんからね。 俺はまだ一度も滋に・・・」
親父は怪訝な顔をしていた。
「つまり・・・滋さんを抱いてない・・・ってことかね?」
「いや、それは否定できません。 一応、結婚したし夫婦になった。
記憶をなくしていた間は義務だと考えていましたから。
でも、どうしてもその気になれなかった・・・つまり、俺は一度も滋の中に出してないんですよ。」
親父は唖然としていた。 まさか、そういうことだとは考えていなかったようだ。
「・・・記憶を失っていても子供は拒否していた?」
「ええ、俺は子供をつくるのは間違っていると感じていた。 それで最後はどうしても躊躇していた。
滋と結婚しても、なぜか子供だけはつくってはいけない気がしていたんだ。」
「・・・わかった。 そこまでお前が牧野くんを愛しているなら・・・別れることも認めよう。
だが、私はこの件には何も力にはなれん。 滋さんは離婚を承知しないだろうし、
大河原もお前に怒りをぶつけてくるだろう。 お前が自分で解決することだ」
「・・・わかりました。 でも、大河原が道明寺になんらかの制裁を加えるかもしれません」
「それはないだろう。 あの男は企業人としては立派だよ、私情を交えた経営をするとどこかにヒビが入る。
それをよくわかっている。 娘を溺愛しているが、それを仕事には持ち込まないだろう。
だが、友好的関係ではなくなるだろうな。 それは仕方のないことだ。
大河原に手を切られるとして、お前はその損をどうやって補う?
それができない限りは離婚も問題外ってことだな。」
© Rakuten Group, Inc.