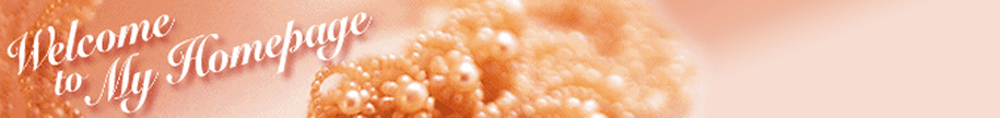2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年11月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

私の好きな作家、阿刀田高さん。
私の大好きな作家の一人に阿刀田高さんがいます。高校生のときに『ギリシャ神話を知っていますか』を本屋さんで見つけ吸い込まれるように手に取り買って帰り、のめりこんでしまいました。その後、『ギリシャ神話を知っていますか』は何度も何度も読み返したりしました。それから何年語ってから、阿刀田さんの難しいことを分かりやすく面白く紹介、説明してくれている楽しい解説書のような本を数冊読みました。聖書に関しても、この『旧約聖書を知っていますか』と『新約聖書を知っていますか』は本当に分かりやすいだけでなく面白く、聖書を身近に感じたりもしました。聖書という西洋の精神を日本人の心にもなるほどと思えるように書いてくださっているので、どんどん読み進め楽しむことが出来ました。阿刀田さんの『旧・新約聖書をしっていますか 』を読んでから、聖書を読むと分かりやすかったです。もちろん、旧約聖書は部分的にしか読んでいませんが面白そうなところだけでも。阿刀田さんの解説を思い出しながら読むとちょっとだけでも、分かったような気になれました。『シェークスピア楽しむために』だけはまだ買ったばかりで読んでいないのですが、宝物のように少しづつ大事に楽しんで読んでいこうと思っています。ただ、心配はシェークスピアに嵌ってしまうのではないかとちょっとどきどきしています。
2007.11.30
コメント(6)
-

どろどとした人間関係 “壇林皇后私譜”
どろどろとした人間関係といえば何といっても平安朝から中世へかけての天皇家と藤原家でしょうね。壇林皇后、橘嘉智子が稀に見る美しい女性であったが故の運命。桓武天皇の皇子である後の、嵯峨天皇となる神野王子の妃に迎えられ、さらに繁栄を願う橘氏一族の期待の的でした。嘉智子自信、輝かしい栄華と血塗られた政略結婚、エリート人生について、生きることの意味を問い直さずにはいられない。『壇林皇后私譜』は杉本苑子さんの名作です。時は、第五十代桓武天皇から、平城天皇、さらに嵯峨、淳和、仁明、文徳天皇へと続く治世です。皇位継承と権力闘争の暗闘、まさに権力闘争に群がり寄る人間の私利、功名にとらわれた典型的なトラブルとして現代に生きる私達にも否応なく実感できるものです。登場人物の多さは半端じゃない。本の後ろの系譜も、皇室系譜、橘氏系譜、坂上氏系譜、藤原氏系譜とあり、それが複雑に入り混じっているから面白い。私は頭がこんがらがりそうになるので、登場人物が出るたびに自分なりの系譜を書きながら読みました。まあ、複雑に入り組んだ系譜はまるで、ギリシャ神話の系譜みたい。何故、こんな出来事が起こったのかということが、人脈、血脈を知ることによって理解できたりします。どろどろした人間関係を体験したい人にはお勧めです。実生活とはかけ離れた本の世界でこそ味わえる時代を超え、立場を超え、まったく関係ない私たち自身に、まるで自分のことのようなリアルさで迫ってくる作品です。前回紹介した“永井路子 平安朝三部作”と合わせて読まれると更に面白さがパワーアップすること間違いないです。
2007.11.29
コメント(4)
-

どろどとした人間関係 “平安朝三部作”
みなさんは、どろどろした人間関係はお好きですか?もちろん、自分のことだったら絶対に嫌ですよね。表向きは優雅で上品でも、実は欲望が渦巻いていて恐ろしい陰謀が張り巡らせていたり…。上流社会ほどそんなどろどろが激しいのでしょうね。他人事と割り切れば、そういうどろどろは結構面白いですよ。しかも、現代ではなく昔のどろどろは規模がでかい。この国を取り合いするのですから。どろどろがお好きな人にお勧めなのが、永井路子さんの“平安朝三部作”と呼ばれる『王朝序曲』『この世をば』『望しは何ぞ』です。『王朝序曲』は平安京を作った桓武天皇から、平城天皇、そして嵯峨天皇へと権力と愛欲の葛藤が繰り返され、平和がくる、欲望と挫折の歴史小説です。『この世をば』は写真がなくてすみません。実はもう絶版になっているのです。私は図書館で取り寄せてもらって読みました。買うことが出来なくてとても残念です。『この世をば』の題名はは道長の栄耀栄華の果てのあの有名な歌から来ています。 この世をば わが世とぞ思う望月の かけたることもなし と思へば権力の権化、傲慢、不遜というイメージの藤原道長を「幸運な平凡児」としてとらえ、人間的内面に迫った作品です。道長といえば、四人の娘を后妃として天皇の外戚となった人物ですが、じつは始めはまったく出世のチャンスはなく、兄や実力者が相次いで病死しあれよあれよという間に、ナンバーワンにのしあがった幸運な人として描かれています。最後は『望しは何ぞ』です。藤原摂関家と天皇家を中心に、皇子誕生をめぐる権力闘争を道長亡き後、王朝社会の陰の実力者となった能信を通して描かれた作品です。“平安朝三部作”読み応えありますよ。
2007.11.28
コメント(2)
-

アスクレピオスの物語
昨日は、『ギリシャ神話』についてブログに書いたのですが、実はずーっと、ギリシャ神話に興味のある人はほとんど、いないだろうなと思っていました。だから、きっと誰一人コメントを書いてくれる人もいないだろうし、読んでくれる人もいないわぁ、と思っていたのです。でも、気楽なブログなんだからいろいろ気にしないで自分の書きたいことを書こうと思って書いたのです。「ええい、誰も読んでくれなくてもいいや。 」そんな気持ちでした。そうだ、どうせ読んでくれる人もいないのなら、一回で思いっきり書いてしまおうと思って書きました。すると、なんとうれしいことに三人もの方からコメントが入っていました。本当に、嬉しかった。(涙)お三人さん、読んでくださった方ありがとうございました。それで、調子に乗って今日もギリシャ神話関連の話を書くことにしました。(笑)写真は『よみがえる医神 アスクレピオスの物語』(著・澤田祐介 医歯薬出版株式会社)という本です。アスクレピオスの父はアポロンで母はコロニスです。アスクレピオスの誕生とともに母コロニスは死んでしまうので、父アポロンはアスクレピオスを森の奥に住むケンタウロスに預けて教育してもらうことにします。半身半馬のケンタウロスは頭が良く、薬草などの知識が深く医師・学者・予言者として有名です。(アスクレピオスだけではく、アキレウス、イアソン、オルフェウスの教育もしています。今でいう名門大学に入れたようなものです、アポロンも結構教育パパだったのね。)ケイロンはアスクレピオスに医学を教えるのです。この『よみがえる医神 アスクレピオスの物語』は、安土懸鈴(アズチケンレイ)というは田舎の診療所の医師の昔語りではじまります。彼は、国籍は日本なのですが、出自はギリシャで両親からもらった名前はプブリウス・アスクレピオスといい、アスクレピオス(やその子孫ヒポクラテス)の子孫なのです。30歳を過ぎてから日本で医師の資格を取得し日本の女性と結婚して帰化したのでした。この60歳を過ぎた老人が代々伝えられてきたアスクレピオスの話をしてくれるのです。優しい話口調の形で、この本の話は進んでいきます。アスクレピオスの医療がどれほど進んだものであったかは驚かされるばかりです。今でも十分通用するものもたくさんあります。神話の話も盛りだくさんで、知らないものも多く楽しい話がいっぱいありました。ここに、書き尽くせないのが残念です。そのほか、メソポタミア、シュメール文明、ユダヤ教、キリスト教にも影響を与えています。ギリシャ神話に興味のある方には面白いと思います。なかなか本屋さんでは売っていないかもしれませんが、もし見つけたらちょっと手にとってパラパラと見てみてはいかがでしょうか。(私は、注文して買いましたが、買うのが嫌な人は図書館で購入してもらう手もあります。)ギリシャ神話から現代に伝わっているものは本当に多いです。医学、音楽、芸術…。そのルーツを知るのは楽しいことです。
2007.11.27
コメント(6)
-

ギリシャ神話に嵌ってしまって…。
私が一番初めにギリシャ神話に出会ったのは阿刀田高さんの『ギリシャ神話を知っていますか』でした。私が若いときに、たまたま通りがかった本屋さんの入り口に飾られていた初版を買ったのでした。面白くて何度読み返したかわかりません。ギリシャ神話から生まれた言葉で今でも世界中で使われている言葉は数え切れないくらいあります。音楽・医療・芸術・文化いろいろな面で現代にその精神が脈々と伝えられているのです。読めば読むほど、ギリシャ神話のとりこになってしまっています。写真の下二冊は阿刀田高さんの『ギリシャ神話を知っていますか』と『私のギリシャ神話 です。『私のギリシア神話』は綺麗な絵がいっぱいあって、美術書のようでした。阿刀田さんのギリシア神話についての思いが伝わってきたかのようでした。左上は西村賀子さんの『ギリシア神話・神々と英雄に出会う』西村賀子さんは里中満知子さんのマンガ『ギリシア神話』のあとがきを書かれていたのでどんな人なのか興味が沸いてきてので、西村さんのギリシャ神話も読んでみたのです。分かりやすい解説と女性の立場からの発言は大変共感できました。。さかもと未明さんのマンガ『ギリシア神話、神々と人間たち』も彼女らしい絵のタッチが私の想像をいい意味で裏切ってくれていて楽しく読ませていただきました。ギリシア神話でマンガといえば、里中満知子さんに敵う人はいないのではないでしょうか。登場人物の美しさといえば文字で表せないくらいです。気持ちいいほどすーっと、物語が入ってきます。里中さんの本は登場人物に美男美女が多くて、嬉しいです。1巻~8巻まであります。1巻 オリンポスの神々2巻 アポロンの哀しみ3巻 冥界のオルフェウス4巻 悲劇の王オイディプス5巻 英雄ヘラクレス6巻 激情の女王メディア7巻 トロイの木馬8巻 オデュッセウスの航海どれも、よく出来ていて感心します。私は続けて3回読みましたが、覚え切れないので何回でも楽しめます。これからも、時々思い出して読み返そうと思っています。左上は「学校で教えない教科書 」というキャッチフレーズに惹かれて買ってしまいました。学習院大学名誉教授、吉田敦彦さんの『面白いほどよくわかる ギリシャ神話 』は写真や図が多くて分かりやすかったですよ。右上は 立原えりかさんの『ギリシア神話 』です。立原さんの文は優しくて美しいです。この本は子供向けなのですが、私が読んでも楽しめました。左下は 桜井万里子さんの『いまに生きる古代ギリシャ』です。NHKカルチャーアワー(ラジオ第2放送)歴史再発見の本です。ラジオも聞きたかったのですが、聞き逃したので本で読みました。今のギリシャのお話もあったりして、面白かったです。最後は、日本ユネスコ教会連盟から出版されている『世界遺産・古代ギリシャ』です。美しいギリシャの写真がいっぱいで本当に美しい。あ~、いつかギリシャに行きたい。行きたい、行きたいと思いは募ります。周りの人は「きっと、いつか行けるよ、ギリシャは逃げないよ。」なんて慰めてくれるのですが、あ~、ギリシャを思いため息をつく毎日です。
2007.11.26
コメント(6)
-

今夜夕方 『聖徳太子の超改革』楽しみです。
今日は6:56から朝日系で『聖徳太子の超改革』という2時間番組があります。教科書に載っていない聖徳太子の真実が今夜明かされるということらしいです。(原案は堺屋太一、聖徳太子は武田真治、推古天皇は戸田菜穂、小野妹子は山崎裕太、蘇我馬子は鶴見辰吾さんだそうです。)ちょっと楽しみです。実は先日、豊田有恒さんの『長屋王横死事件』『大友の皇子東下り 』『崇峻天皇暗殺事件 』を紹介してもらってさっそく本屋さんへ行ったのですが、近所の本屋さんにはどれまもありませんでした。ただ一冊、豊田有恒さんの本であったのが『どうする東アジア 聖徳太子に学ぶ外交』という本だったのです。さっそく買って帰って来て、夕方テレビで聖徳太子の超改革』のテレビが翌日あると知りびっくり、本当にタイムリーでこれは絶対に見なければと思ってしまいました。話は、戻りますが『どうする東アジア 聖徳太子に学外交』面白そうです。聖徳太子は日本人にとって馴染みのある偉人なのですが、実際にどういう事跡をなした人かというと、意外にしられていません。『日本書紀』によると今年は、聖徳太子が遣唐使を派遣してからちょうど千四百年にあたるのだそうです。聖徳太子が心血を注いで取り組んだ事跡のうち私たちが学ぶべきことは大きく分けて三つあるそうです。第一は 朝鮮半島の非友好な国家への対応法第二は 中華思想の本家の中国の対処法第三は 公務員対策これを見ると、今の日本が解決法を模索している課題ではないでしょうか。聖徳太子は「和をもって、貴しとなす」という言葉があまりにも有名でちょと一人歩きしているところもあるのかもしれません。本当の意味は何だったのでしょうか。聖徳太子は仏教を広めた学者というイメージが強いのですが、実は反面対話では埒があかない輩と出くわすと、力を示すことを厭わない武人の一面もあったようです。それから、ple-plusさんに紹介していただくまで豊田有恒さんという人を全然知らなかったのですが、SF小説を書いておられる方で、手塚治虫さんの虫プロダクションでシナリオを執筆されていた方で、今は島根県立大学の教授という人だったのですね。なんだか、他の作品も面白そうで嵌ってしまいそうです。さて、今日はテレビと書籍という二重の楽しみに出くわしてしまいました。まずは、夕方6:56にビデオを用意しておくことにします。
2007.11.25
コメント(2)
-

天野山 金剛寺で紅葉狩り
お天気が良かったので、天野山 金剛寺へ行って来ました。ここは、南北朝時代に、南朝・北朝双方の行在所となり、その歴史的な経緯から、質量ともに豊富な古文書を所蔵しています。紅葉きれいで、夢の世界のようです。金剛寺は、僧行基が聖武天皇の勅命によって開き、のち弘法大師密教修練の霊域とりました。明治の初めまで女人禁制であった高野山に対し、女人の参拝を許したので、女人高野と呼ばれています。「楼門」は鎌倉時代の建築とされており、重要文化財に指定されています。金剛寺は、楼門をくぐり石段を上がると、右に金堂、左に多宝塔、正面をさらに登ったところに五佛堂があり、新西国霊場本尊 千手観音菩薩像を奉安しています。後村上天皇が当寺に移られ摩尼殿を行在所とされ、この食堂(じきどう)を正殿として6年間大政を執られたとされている。以来、この建物が「天野殿」と呼ばれるようになったといわれています。この金堂内陣には本尊の木造大日如来坐像、脇士の木造降三世明王坐像及び木造不動明王坐像が安置されています。何れも運慶の作と伝えられています。「多宝塔」は平安時代の創建とされているがはっきりした年代は分からないららしいのですが、我が国最古の多宝塔の形式を持つ極めて貴重な建築物なのだそうです。三連休の初日だというのに、人もそんなに多くなく落ち着いた雰囲気でした。この季節は紅葉が綺麗でした。家の近くにこんなに素敵なところがあるなんて知らなかったのですが、来てみて本当に良かったです。
2007.11.24
コメント(6)
-

女が歴史を動かす 【永井道子編】
高校生の頃、歴史が面白いな~、と思ったきっかけの本の一冊です。永井道子さんの『歴史をさわがせた女たち』は歴史にあまり興味のない人に歴史ってこんなに面白いんだよと紹介するような本です。当時、私は円地文子さんや田辺聖子さんの美しい日本語に慣れ親しんでいたので、永井道子さんの長屋のおばちゃん口調のこの本にはびっくりしたものでした。口の悪さは絶品でそんなこと言っても良いのかななどと思うくらいなのですが、それが私たち庶民には分かりやすくてついつい引き込まれてしまったのでした。このシリーズは5冊あるのです。歴史をさわがせた女たち 日本編歴史をさわがせた女たち 外国編歴史をさわがせた女たち 庶民編歴史をさわがせた夫婦たち新・歴史をさわがせた女たち写真はうち3冊です。私は、日本編と外国編がお気に入りです。意外なことですが、歴史上の人物で時代によって、悪女、善人、また悪女…。というふうに、二転三転している場合が多いです。それまではよい人間だと思われていたのが、江戸時代の封建的ものさしで計った結果、悪い人間になってしまったというような例も多いのです。日本のクレオパトラとでも言いましょうか、藤原薬子のように、娘の嫁入りについていったら、婿殿に熱をあげられてしまった例もあります。しかも、その婿殿が後の平城天皇だったのですから、いやがおうでも歴史の歯車に影響をあたえてしまいます。そのような面白いエピソード満載です。日本史を華やかに彩るヒロインたちの生き方を豪華にゲスト人とユーモラスに語る対談集の『歴史のヒロインたち』や変革期の人間像に迫る『歴史の主役たち』も面白いですよ。面白く大雑把な人物の輪郭をつかまえたら、歴史の本を読むときに知り合いに出会ったような気安さで読みやすく感じられるのではないでしょうか。永井道子さんの歴史の道先案内書というべきこれらの本、どこから読んでも大丈夫というところが気楽でいいですよ。古本屋さんで見つけたら、ちょっと手にとって見みはいかがでしょうか。
2007.11.24
コメント(2)
-

女が歴史を動かす 【黒岩重吾編】
歴史上で有名な女性は誰でしょうか。卑弥呼、神宮皇后、額田王、推古天皇辺りでしょうか。黒岩重吾さんは、この四人を主人公にした小説を書いています。私が一番好きなのは、額田王です。『茜に燃ゆ・小説 額田王』です。黒岩重吾さんと井上靖さんの額田王を読んだのですが、はじめに黒岩重吾さんのを読んだせいか、そちらの印象が私に深く刻み込まれてしまいました。知的で、美しく、ちょっと儚い。読み終わった後も、いつまでも私の心の中を独占していた額田王。この本を読んだ後、滋賀県の蒲生野まで出かけたりもしました。 時の最高権力者、中大兄皇子の妻でありながら「今でも愛しているのよ。」と、元夫の天武天皇に歌った歌です。 あかねさす 紫の行き 標野ゆき 野守は見ずや 君が袖振るそれに対して、「人妻であるあなたのことを今でも思っていますよ。」なんて天武天皇は答えています。 紫の にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆえに 我恋ひめやもいや~、大人の恋ですよね。(みんなが見ている酒宴の席ですが。)古代人は意外に恋愛におおらかだったのかもしれませんよね。古代の人々は結婚は通い婚だったりして今よりもずーっと純粋な恋愛だったのかもしれませんね。もう一冊は『女龍王・神宮皇后』です。私が、古代史の本を読み始めたのは今から3年くらい前からなのですが、一番初めに黒岩重吾さんの作品を読んだのがこの『女龍王・神宮皇后』だったのです。どうしてこの本だったのかというと、ただ単にその時ブックオフで黒岩重吾さんの本で売っていたのがこの本だけだったのです。ところが、それが意外に面白くて黒岩さんにはまっていったのです。なんか、出会いってそんなものなんですよね。神功皇后というのは、仁徳天皇の父応神天皇の母で、仲哀天皇の皇后なのですが、正確には伝説上の人物なのだそうです。伝承では、息長姫と呼ばれ葛城系の血筋だそうです。小説の中では、水神の加護を受けて誕生し、霊力と呪力をもち古代日本に君臨した神功皇后の生涯が大きなスケールで描かれています。本当に伝説上の人物なのかと思うくらいです。実在したと信じたい一人です。黒岩重吾さんの作品で主人公が女性というのはあと2冊あります。卑弥呼が主人公の『鬼道の女王 卑弥呼』と推古天皇が主人公の『紅蓮の女王・小説 推古天皇』です。どちらも読んだのですが、図書館で借りて読んだので写真をUPできなくてすみません。『鬼道の女王 卑弥呼』はブックオフで下だけあったので、買っちゃいました。次に上を見つけて買わなければ。やはり、自分が女性のせいか女性が主人公の小説は人物に入り込めて(時にはなりっ来てしまいそうになるけど…。)読んでいて楽しいです。多くの女性古代史ファンに読んでもらいたいです。もちろん男性の方も大歓迎ですよ。
2007.11.23
コメント(6)
-

黒岩重吾さんの『小説 聖徳太子』を読んで
聖徳太子は昨日『その時歴史が動いた』の継体天皇のひ孫にあたります。日本人に歴史上でもっとも有名な人を聞くと聖徳太子はまず、トップクラスに入っているのではないでしょうか。でも、その割りに聖徳太子はどんな人だったか知らない人は多いのではないでしょうか。学校で習うのは、推古天皇の摂政で、十七条の憲法と冠位十二階を制定した人。あと、七人の人の話を同時に聞き取れたとかくらいですよね。上の写真は、ple-plusさんがノンフェクションだと勘違いした小説です。実は私も黒岩重吾さんの小説を読むとあまりの見事さについつい小説だと分かっていても、真実なのではないかと錯覚してしまったり、小説の中の素敵な人物に夢心地になってしまったりします。(笑)歴史に真実はないと思っています。同じ出来事であっても、立場が違うと見方も違いますしね。古代史は特に古くてわからないことが多すぎます。あまり深く考えないで、楽しむことが一番だと思います。この小説は聖徳太子を主人公にして黒岩重吾らしさで味付けされています。一年位前に、この小説をよんでその後すぐに、法隆寺、四天王寺、叡福寺へ行きました。私は子供の頃、法隆寺の近くに住んでいたのでよく遊びに行ったものですが、この小説を読む前と読んでからでは、法隆寺の見え方が違ってきたのは不思議でした。私が子供の頃は一万円札といえば、聖徳太子だったのですが、今は福沢諭吉さんになってしまっていて残念です。でも、どちらの人も、人は平等という気持ちをもっていたのではないでしょうか。もちろん聖徳太子と福沢諭吉の平等にはかなり違いはありますが、聖徳太子があの当時の常識の中では、人間が平等だなんて突拍子もない考えだったことを思えば、ものすごく進んだ考えだったのだと思います。今の日本人が一人一人を大切に思えるのは、聖徳太子や福沢諭吉さんの影響も見逃せないものがあるのかも知れませんね。
2007.11.22
コメント(4)
-

今晩の 『その時歴史が動いた・継体天皇 』楽しみです
今日は『その時歴史が動いた』で継体天皇・ヤマトを救う・九州豪族連合との大激戦があります。継体天皇という人も歴史の大きな節目に登場した大変面白役割を担った天皇です。「継体」というのは、王朝を交代して継いだという意味があり、体を継ぐ「体」は王朝のことです。どんな番組になっているのかたのしみです。黒岩重吾さんが、この継体天皇を主人公にして小説をかいています。『北風に起つ・継体戦争と蘇我稲目 』です。継体天皇は「日本書紀には」応神五世の孫とされています。一説によると、越前・近江で勢力をふるっていた男大迹王(オオドノオウ)は雄略天皇の死後、朝廷の乱れに乗じて応神天皇の子孫を称し、約二十年の対立、抗争の後、大和の勢力を圧倒して大和に入り、皇位を継承するとともに手白香皇女を皇后として地位を確立し、天皇位を簒奪した人物だともいわれています。しかし、この小説では黒岩重吾さんは男大迹王(オオドノオウ)を応神・仁徳王朝の最後の天皇雄略の母系の縁者であるという新史観をうちだして、王位簒奪説を否定しています。謎の多い天皇ではありますが、それだけによりいっそう興味を引かれる天皇でもあります。あと2時間で『そのとき歴史が動いた』が始まります。ビデオを用意して待っています。楽しみです。★。.:*:・´゚☆。.:*:・´゚ 。.:*:・´゚☆。.★。.:*:・´゚☆。.:*:・´゚ 。.:*:・´゚☆。天皇家は万世一糸といわれていますが、応神天皇の五世の孫とはかなり血縁的には遠いように思えますよね。直系どころかひ孫の孫ですからね。自分のことで考えてもお祖父さんの父親ですらどんな人か分からないのにお祖父さんのお祖父さんのお父さんくらいの人が本当に誰かなんて遠い人で実感がないですよね。今の天皇家ですら、五世の孫を全員把握しているのかどうか疑問ですよねなんで、こんなことになったかというと、この時代は誰が次の天皇を継ぐかということで親戚同士で殺し合いをしたのです。応神→(息子)仁徳→(息子)履中→(弟)反正→(弟)允恭→(息子)安康→(弟)雄略と続くのですが、この雄略天皇が自分が天皇になるために兄の安康天皇を始め多くの人を殺します。陰謀や殺戮が渦巻いているのです。この時代は面白いですよ。本当かどうかは分かりませんが、雄略天皇の息子清寧てんのうは、髪や目が真っ白な白子だったとか、武烈天皇は残酷で恐ろしい天皇で、生爪をはがしたり、妊婦の腹を切り裂いたりしたなどという話もあります。(親族同士の結婚が多かったのでかなり血が濃くなっていて、いろいろあったのもうなずけます。)とにかく、殺し合いが多かったので血縁が堪えてしまい家臣の大伴金村が越の国から男大迹王(オオドノオウ)を連れてきたらしいのです。本当は同だったのか分かりませんが、いろいろな説もあり、面白い時代です。小説は小説として面白し、テレビもまた楽しみです。
2007.11.21
コメント(2)
-
大学合格!!
今日、息子に大学の合格通知が来ました。公募推薦で受けたのですが第一希望だったので、喜んでいます。私もほっとしました。英語の勉強をしたいと言っていたのでそういう関係の大学です。実は息子は昨年からいろいろあって、あんまり順調でなかったので今回決まることが出来て本当に良かったと思っています。私もいろいろ心配で、最近は遺跡巡りなど全然行けなかったのですが、これでいろいろ出かけられそうです。また、本を読んではそれにちなんだ土地を訪れる小さな旅をしたいと思っています。今日は、いろいろ忙しいのでブログはこの辺で失礼します。ではみなさま、おやすみなさい。
2007.11.20
コメント(8)
-

古代史の謎・黒岩重吾
古代史に興味のある方にお勧めの本があります。私が古代史関連の本の中で、面白いなと思う作家は何人かいますが、最も好きな作家の一人に黒岩重吾さんがいます。『古代史の真相』では古代統一国家はいかにして形成されたかというはなしから、葛城氏、物部氏、継体天皇、聖徳太子、そして藤原不比等について詳しく書かれています。『古代史を解く九つの謎』では神殿跡の発見と弥生時代の勢力図、出雲神話、神武東征神話、王朝交代、大化の改新などについて謎解きの形で書かれています。『古代史の迷路を歩く』は天孫降臨、オホタタネコ、倭の五王、応神・仁徳・允恭天皇について、雄略・継体天皇について、そして、蘇我氏や聖徳太子についても触れられています。『謎の古代女性たち』では、卑弥呼、倭迹迹日百襲姫、磐之姫、神功皇后、天照大神、推古天皇などについてです。『古代史への旅』は作者である黒岩重吾さんがなぜ、古代史に入ったかというところから始まっています。少年の頃の彼は歴史好きではなかったのだそうです。かれが、中学の頃第一希望の大阪の三国ヶ丘中学の入試に失敗し、小学生浪人をしたそうです。そして惨めな受験生活を経て奈良の宇多中学に入学します。そこでの経験から歴史に興味を持つようになったのだそうです。黒岩重吾さんファンにはお勧めの一冊です。『学問のすすめ』今回の中で一冊だけ著者が黒岩重吾さんではなくて、梅原猛さんです。この本は実は、梅原猛さん唯一の自伝なので上の黒岩重吾さんの自伝的著書と比べて読むと面白いと思い、今回一緒紹介させていただきました。梅原猛さんの、祖父母、父母、故郷、大学時代などファン必見の一冊です。以上六冊、どれも面白かったですよ。どれか一冊でも、興味のある方は読んでみられてはいかがでしょうか。
2007.11.19
コメント(4)
-

『古代からの伝言』を読んで
古事記日本書紀のあとは古代史です。この『古代からの伝言』は古代史の私の教科書ともいうべき本なのです。以前、産経新聞に掲載されていたのです。今は、この続編の『青雲の大和』が掲載されています。これも面白くて、毎日楽しみで読んでいます。『古代からの伝言』は4冊ですが、一冊に二部づつ入っています。第一部 日出づる国 (聖徳太子)第二部 水漬くかばね (天智天皇)第三部 民族の雄飛 (応神天皇)第四部 悠久の大和 (継体天皇・蘇我氏)第五部 日本建国 (卑弥呼・諸葛孔明)第六部 大和の青春 (神武天皇・日本武)第七部 壬申の乱 (天武天皇・高市皇子)第八部 わが国家成る (大津皇子・藤原不比等)というようになっています。(括弧の中は私が時代がわかりやすいように登場する人名を入れてみました。)私は、第五部・第六部から読み始め、第三部・第四部へと読み進み、第一部・第二部、そして第七部・第八部と読みました。そして、今は産経新聞『青雲の大和』へと読み進めています。著者の八木荘司さんは産経新聞の大阪本社編集局司会部長でもあり、同編集長でもあります。本当に詳しく調べられています。今まで、あまり書かれていなかったことも書かれています。例えば、蘇我打倒のクーデターも鎌足や中大兄皇子の視点からだけでなく、実行犯の小麻呂の視点から書かれているのはとても面白かったです。そんなに歴史に詳しくない人にでも、読みやすく書かれてあります。四冊一気に読みきったときは感慨深いものがありました。知らなかったことも多かったのですが、知っていたことも頭の中でまとまった気がしました。興味のある方は一度読んでみてはいかがでしょうか。
2007.11.18
コメント(4)
-

古事記に太鼓の人々の息遣いが…。
昨日は『逆説の日本史』紹介させていただきましたが、逆説面白いと思うためには通説を知る必要がありますよね。日本史の一番初めといえば、古事記、日本書紀ですよね。とはいえ、私にはオリジナルを読むことは無理なのでやさしく解説してくれている本を読んでいます。阿刀田高さんの『楽しい古事記』は初心者向きで読みやすいですよ。福永武彦さんの現代語訳『古事記』は日本語の美しさを詩人の感覚で語ってくれています。田辺聖子さんの『古事記』は私が高校生のときに買った本です。何度読んでも楽しいです。田辺さんの優しさが伝わってくる訳です。図解、『地図とあらすじで読む 古事記と日本書紀』は古事記や日本書紀に出てくる場所の写真や図が多くてとても分かりやすくて楽しいですよ。海外の本だけでなく同じ本でも訳をする人によって違うのですよね。『源氏物語』なども多くの人に訳されていますが、時代によって文体だけでなくそのときの常識や感じ方も違うので何人かの訳を読むと面白ですよね。それから、日本の神話の絵本も楽しいですよ。絵が赤羽末吉さんで、とても上品で格式があり額に入れて飾りたいくらいです。文は船崎克彦さんで、分かりやすく美しい日本語です。一巻から六巻までです。 一巻 くにのはじまり (伊耶那岐と伊耶那美のお話です。)二巻 あまのいわと (天照大神のお話です。)三巻 やまたのおろち (スサノオとヤマタノオロチのお話です。)四巻 いなばのしろうさぎ(大国主命のおはなしです。)五巻 すさのおとおおくにぬし(スサノオと大国主命)六巻 うみさちやまさち (海幸・山幸です。)娘が幼い頃よく読みきかせをしていた本です。何度も何度ももってきたお気に入りの本でした。大人が読んでも読み応えがありますよ。先日行った『近つ飛鳥博物館』でも、『くにのはじまり 』のお話が紹介されていました。昔の人は歴史を神話の形で伝えたのでしょうね。神話の中には事実だけではなく、そのときに生きていた人の生活や考え方も編みこまれています。太鼓の人々の息遣いが感じられるような気がします。大昔からづーっと伝えられてきたと思うだけで感慨深いものがあります。
2007.11.17
コメント(8)
-

『逆説の日本史』シリーズを読もう!!
本屋さんへ行って、何か良い本はないかなと迷った時に必ず買うのが、井沢元彦さんの『逆説の日本史』シリーズです。一番初めに買ったのは、もちろん1巻の古代黎明編なのですが、その後は順番に買うのではなく、そのときに興味を持っていて面白そうだと思った時代をランダムに買っていたので、こうやって揃えてみると、6巻だけ抜けていました。順不同で読んでも大丈夫です、それぞれ一冊ずつ面白く仕上がっています。『逆説の日本史』は名前は逆説ではありますが、実はこれこそ通説といわれているものよりも、真実に近いのではないかと思うくらい、いつも感心させられてしまいます。学校で歴史を勉強したつもりでもいかに、「自分がこれほど歴史を知らなかったのか!!」ということに気づかされます。その上、この本はこんな私にも分かりやすく丁寧に説明されています。そして、読めば読むほど面白く引き込まれてしまいます。思います。私が今、読んでいるのは9巻の戦国野望編です。日本の歴史を知ろうと思っても、日本の歴史だけを勉強していても知りきれないことも多いです。私が今読んでいるところは「倭寇」についてです。「倭寇」というのは学校では日本人の海賊と習った記憶があります。でも、実は十六世紀の倭寇の特色は、構成員の大部分が中国人で占められていたのです。真倭といわれた日本人は10~20%、偽寇、仮寇、装寇と呼ばれた中国人が主力であったのだそうです。しかも、この時代の倭寇の最大の首領は王直という名前の中国人だったのです。 (『国史大辞典』より)また、「倭寇に日本人は二割しかいない」といっているのは日本人ではなく朝鮮人なのだそうです。それから、倭寇の首領、王直は海賊ではなく商人だったのだそうです。しかも、種子島に鉄砲を伝えた人なのです。鉄砲はポルトガル人が伝えたということになっているのですが、当時ポルトガル人は日本に上陸する手段として、中国人の王直に船を出してもらったのだそうです。中国はもともと、物を安く仕入れて高く売る(その差額が利益なのですが)商売を卑しい職業だと考えていたので、貿易を禁止していたのだそうです。それで、中国は鎖国状態だったので貿易は『倭寇』の形でしか成り立たなかったのだそうです。詳しいことは『逆説の日本史9巻』を読んでくださいね。歴史に正解はありません、同じ出来事でも立場が違えば見方もちがいます。いろいろな本を読むといろいろな見方が出来て面白いです。井沢さんの本も一つの説ですが、このくらい歴史を軽い気持ちで楽しみながら、考えるのもいいのではないでしょうか。本来、学校の教科書もこのくらい面白くてもいいのではないかと思ってしまうくらいなのです。暗記が嫌いで歴史が好きになれない人にもお勧めです。知っているつもりで知らないことが多すぎる日本の歴史。歴史を楽しみながら学びたい人は是非、この『逆説の日本史』シリーズを読んでみてはいかがでしょうか。
2007.11.16
コメント(8)
-

延命寺の紅葉
河内長野の山の中をずんずん進むと着きました。延命寺です。境内は紅葉がいっぱい、今日は写真で楽しんでくださいね。境内の階段を上ると見えてきました。夕照り(ゆうばえ)の楓です。天然記念物に指定されています。樹齢千余年、弘法大師お手植えと伝えられています。晩秋の夕陽に映える姿がいっそう美しいためこの名前がついたそうです。山道をどんどん登っていくと木がいっぱいあります。夕陽が落ちてきました。坂を下りると蓮池があります。弘法大師がこの地方を巡化の時、寺を建立し自らの地蔵菩薩の尊像を刻んだで本尊としたのがこの延命寺の起こりであると伝えられています。今では、この辺りの人たちに紅葉が綺麗なお寺として有名です。私も一度来たかったのですが、今日は本当に来てよかった。紅葉の美しさを伝えることが出来たでしょうか。河内長野の近くに来られたときは是非、延命寺に立ち寄られてみてははいかがでしょうか。今から二週間くらいが見ごろだそうです。
2007.11.15
コメント(10)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- ラスベガス タッチダウン
- (2025-11-13 15:32:13)
-
-
-

- 楽天トラベル
- ヤクルト&ピルクル好き必見!広島土…
- (2025-11-15 00:00:14)
-
-
-

- やっぱりハワイが大好き!
- シャカサインで感じるハワイの風
- (2025-07-28 18:59:01)
-