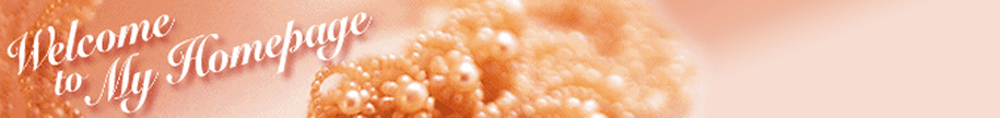2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009年01月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-

斎宮の森・大伯皇女
斎宮歴史博物館を出て、斎王の森に向かいます。斎王跡のシンボルゾーンとなる史跡公園です。斎王跡を示す石碑がありました。大伯皇女の歌碑です。わがせこを 大倭(やまと)へ遣(や)るとさ夜更けてあかとき露に わが立ち濡れし【意味】大倭(やまと)へ戻っていく弟を見送る私は,真夜中から暁にかけておりる露にすっかり濡れてしまったことよ大伯皇女(おおくひめみこ)のお歌です。父は天武天皇、母は天智天皇の皇女である大田皇女 (実弟は大津皇子)。本来はその大田皇女が皇后になるはずだったのですが、若くして亡くなったため、母の実妹である鵜野讃良皇女(うののさららひめみこ)が皇后となりました。(のちの持統天皇) 当時は母方の血が重要視されました。母を亡くした二人にとって叔母である鵜野讃良皇女はたった一人の後見人であるはずでした。しかし自分の子である草壁皇子の軟弱さに比べ甥である大津皇子の聡明さ、凛々しさ、逞しさ…。その上、人望の厚いのです。どれをとっても比較にならないことに不安を募らせる皇女。自分のおなかを痛めた子に即位を…。そう願った鵜野讃良皇女を責めるわけにはいかないのですが。だがこのことが、この姉弟を悲劇へと導きます。天武天皇亡きあと、ついに鵜野讃良皇女が動いたのです。策略を持って大津皇子の失脚をもくろびました。 謀反の疑いをかけられた大津皇子…。命の危険を感じた皇子は当時伊勢の斎宮であった姉の大伯皇女(おおくのひめみこ)を、密かに訪ねます。 この世に、たった二人きりの姉と弟…。 どういう話がなされたのかうかがい知ることは出来ませんが…。大和を捨ててどこか誰も知らない土地に弟を逃がしたいとおもったでしょう。しかし、それははかない夢。夜更けて、政争うずまく大和(やまと)へ戻る弟を、ひっそりと見送る大伯皇女の心情を思うとき、胸が痛みます。磐余(いわれ)の地で果てた命でした。百伝(もも)伝ふ 磐余(いわれ)の池に 鳴く鴨を 今日のみ見てや 雲隠りなむ 【意味】磐余の池で鳴く鴨を見ることも今日を限りとして、私は死んでいくのであろうか『万葉集』には、大津皇子が死罪と決められた時、磐余の池の堤で、泣く泣く作った歌です。 ↑写真は以前、桜井の磐余池跡へ行った時のものです。 ↑は二上山の頂上の大津皇子のお墓と言われているところです。(本当にここに埋葬されているのかはわかりませんが…。)うつそみの 人なるわれや 明日よりは二上山を弟(いろせ)とわが見む【意味】現実の世に残された私…明日からは、あの二上山をいとしい弟だと思ってながめることにしましょう。残された大伯皇女は大津皇子が葬られた二上山を眺めては愛する弟を偲んでいたことでしょう。私が高校生くらいの時にこのお話を読み、泣きました。当時、ちょうど私はとても仲良しの弟がいて弟は高校で寮に入っていたのです。もちろん私の弟は自分で言い出して親を説得して寮に入ったのだから全然意味は違うのだけでも、私にとっては仲良しの弟と離れてしまうことを悲しんでいたので、なんだか勝手に大津皇子と大伯皇女を自分とダブらせてしまって…。私の歴史好きが始まったのはそれも一つのきっかけだったのかも知れません。もちろん、そんな本ばかり読んでいたのでもともと好きだったのかも知れませんがより深く興味を持つようになったのは確かです。今でも、職場から二上山を眺めてはしょっちゅう大津皇子と大伯皇女を思い出しています。話がずいぶん逸れてしまいました、すみません。伊勢の斎宮の森に戻しますね。大伯皇女の歌碑のすぐ横に井戸跡がありました。井戸跡があったということは祭祀をする上で重要なところであったのでしょうね。さて、次の目的地へ急がなくてはなりません。石塚古墳群の上に夕日が沈みます。古代から同じ夕日を見ていたのかも知れませんね。最後にどうしても行きたかったのは竹神社です。参宮街道沿いにあり、厳かなムードをたたえています。周辺の発掘調査で大規模な塀列や掘立柱建物の跡が見つかり、斎宮の中でも重要な位置を占めていたらしいのです。本殿も立派です。暗くなってきました。ギリギリセーフというところでしょうか。さて、今回のお伊勢さんは内宮と外宮にお参りすることはできませんでしたが、違った意味でとても良かったと思います。ちょっと見逃したところや体験しそこなったものもありました。また、もう一度おいでと言われているようです。まだまだ伊勢に居たいのですが、後ろ髪を引かれる思いで後にしました。絶対にまた来ます。来れば来るほど伊勢は好きになりますよね。
2009.01.30
コメント(14)
-

斎宮
近鉄斎宮駅で降りるとすぐ目の前が斎宮跡地です。斎宮跡は国が定めた遺跡で、東西2km、南北700mにわたる137haがその範囲として指定されているのだそうです。本当に広々としたところです。ここに、歴代の斎王が住まわれていたのかと思うと感慨深いものがあります。大伯皇女に会いに大津皇子はここまで来たのですね。そのお話は後で大伯皇女の歌の碑を見に行った時にゆっくり思い出すこととして、まずは斎宮歴史博物館を目指して歩き始めました。斎宮が最も栄えた平安時代の生活が体験できる施設がありました。貴族の邸宅を模した伝統的工法による木造建築は建物そのものが古代建築の体験空間となっています。ここは、平安時代や飛鳥時代だけではなくもっと古い時代からあったようです。博物館のすぐ前に塚山古墳群がありました。多くの土器や埴輪なども出土されているようです。着きました、斎宮歴史博物館です。実はここでは一日に二回だけ十二単を着ることが出来ます。時間は10:30と2:00です。今回は間に合わなかったので残念でした。博物館の中は人形や模型を使って色鮮やかに再現されています。当時の様子も立体的に見ることが出来ました。映像展示室ではハイビジョン画像で斎王の儀礼と都から伊勢への旅を再現した「斎王群行」と「今よみがえる幻の宮」を見ることが出来ました。特に印象に残ったのが、古代の話し方の映像でした。oliveさんがお好きだと言われる意味が良く分かります。ゆったりとした雅なお言葉と話し方なのです。当時の貴人の生活が伝わってくるかのようでした。わずか8歳で斎王に選ばれた良子親王(ながこしんのう)が都から斎宮に行く時のお話でした。とても悲しいお話ですね。父や家族と別れて旅立つのです。もしかしたら永遠の別れとなるかもしれません。斎王は未婚の親王様の中から占いで選ばれたのだそうです。↓がその占いで使われた骨や角です。親王様はいよいよお別れの時に父である天皇から別れのお言葉と同時に、お櫛を頂くという行事があります。それが↓の様子です。このお櫛を前髪の上の方に挿したまま出発なさいます。約一週間かけて、都から伊勢の斎宮へと旅立つのですが、当時は道なき道を行きます。雨の中何度も苦難に合いながらの大変な旅だったようです。しばらくすると、都の天皇からの使者が↓の銀の壺を持ってきます。父である天皇もとても心配されていたのでしょうね。そして、やっとの思いで斎宮に到着するのです。それから、神に仕える毎日が始まります。終りのない永遠に続く日々の始まりです。古代からこうやって、多くの斎王様が神につかえて私たちを守ってくれていたのですね。さて、私達は色々と博物館の中を見て回りその後、斎王の森の方へ行くことにしました。続きは次回とさせていただきます。本当に悲しいお話がいっぱい詰まっているところですね。
2009.01.29
コメント(6)
-

三瀬谷のエメラルドグリーンの川
瀧原宮を出てすぐ前の『木つつ木館』で食事をすることにしました。もちろん食べるのは松坂牛。『松坂牛の二重』ということで↓です。うん、柔らかくて美味しい。元気がでます、後半戦も頑張れそう。夏菜さんに聞いていたので、ここからバスがなかったら、タクシーに乗ろうとしたら何とちょうど良い時間にバスがありました。バスで松坂まで行けるのです。ところが、私にはもうひとつどうしても行ってみたい場所がありました。それは、三瀬谷駅の近くの川です。瀧原宮の駅の近くからも綺麗な川が見えたのですが、三瀬谷駅の近くのエメラルドグリーンの川も見ずに立ち去りがたいのです。バスを少しだけ乗って、三瀬谷駅の近くで降りました。次のバスまでは二時間あります。電車を待ってもほぼ同じくらい。では、この二時間を有効に使いましょう。まず、駅の近くの川の辺りまで行きました。ありました、きれいな川です。川の上は鳥も飛んでいます。川面がきらきら光っています。本当に美しい。都会では絶対に見ることのできない清らかな水です。かなり満足です。このあと、ダムの方まで約一時間の道のりを歩きました。空も青く、空気も綺麗。素晴らしいところです。さて、三瀬谷駅の方へ戻りました。このあとは、松阪まで出てそこから斎宮です。斎宮もとっても良かったです。思ったよりも広いところです。斎宮の森には大伯皇女の有名な歌の刻まれた碑もありました。斎宮歴史博物館も楽しかったです。そのお話は次回ということにさせていただきます。
2009.01.28
コメント(8)
-

伊勢・瀧原宮
伊勢の瀧原宮へ行ってきました。以前、夏菜さんのブログを見て瀧原宮の神々しい様子とその近くを流れる川のエメラルドグリーンの美しさをこの目で見たくなっての参拝でした。瀧原駅をおりるとちょっとびっくりです。本当に小さい駅なのです。帰りの電車の時刻を聞こうと思っても駅員さんもいないし、切符売り場もありません。時刻表を見ると、電車は2~3時間に1本くらいです。瀧原駅に着いたのは、10:14ですが、帰りは2時前までないのです。まあ、何かほかの方法を考えようと思いながら歩き始めました。歩きだすとすぐに橋があり、下を覗くと綺麗なエメラルドグリーンの川です。あ~、これこれ、私はこれが見たかったのです。とかでは決して見ることのできない深く美しい大自然の中の水の色です。綺麗なものを見たのでとても気持ちが良くなりました。瀧原宮までゆったりとした気持で歩いてきました。着きました。あー、ここがあの瀧原宮なのですね。「瀧原宮」「瀧原竝宮」ともに皇大神宮(内宮)の別宮で、昔から「大神の遥宮(とわのみや)」と言われ、両宮とも同じところに御殿をならべて鎮座しています。いずれの御祭神も、天照坐皇大御神御魂(アマテラスイマスメオオミカミノミタマ)です。「瀧原」という名は、大小たくさんの滝があるところから出た名なのだそうです。境内は凛とした空気が立ち込めていました。砂利道をゆっくり歩くと心が静かに穏やかになってきます。参道には大きな木がいっぱいあります。宿衛屋(社務所にあたるところ)の南に自然の谷水の流れる御手洗場(みたらしば)がありました。参拝前に清水に手を洗い口を漱ぐことにしました。川の水にちょっと手を浸けるみてビックリ、ものすごく冷たいのです。ほんの少しじーっと浸けているだけで、凍ってしまいそうです。でも、手を浸けただけで体全部が清らかになったような気がしました。「瀧原宮」「瀧原竝宮両別宮」とも構造は同じ皇大神宮に準じ、神明造で鰹木は偶数で六本。(内宮は偶数で十本・外宮は奇数の九本)千木は内削(内宮は内削で外宮が外削)、周囲には瑞垣、玉垣の二重の御垣があり、御垣にはそれぞれ瑞垣御門、玉垣御門があります。その横にあるのは、若宮神社と御舟倉です。そして、その横にあるのが長由介神社(ナガユケジンジャ)です。神々しい雰囲気の中いつまでも居たいくらいでした。名残を惜しみつつ、瀧原宮を後にしました。このあと、瀧原宮のすぐ近くにある『木つつ木』館で松阪牛を食べることにしました。そして、バスで隣の駅へと移動したのですが、続きは次回です。
2009.01.27
コメント(6)
-

中百舌鳥古墳群
pleさんに教えてもらった堺東駅前にある堺市の市役所へ行ってみました。地上80mの市役所最上階は360度の展望が楽しめる回廊式ロビーになっています。まず一番はじめに見たのは、さっき行ってきたばかりの反正天皇陵と方違神社です。見事に目の前に見えます。遠くに見えるのは生駒の山です。どこが何だか分かる写真が360°景色と同じところにあり、分かりやすくなっています。右回りに、少し歩くと二上山が見えてきました。そして、その横に金剛山と葛城山が続いていました。少し進むと、目の前に仁徳天皇陵です。その右は履中天皇陵、ニサンザイ古墳と続きます。最上階のロビーは広く、喫茶コーナーもあります。周りに、土器や勾玉や古墳からの出土品も展示されています。堺といえば、鉄砲ですよね。本物なのでしょう。千利休も有名です。お茶室も展示されています。ということで、さっそくお茶頂くことにしました。美味しかったですよ。今日の日没は5時だと書いてありました。お茶を飲んでゆっくりしている間に、段々薄暗くなってきました。そろそろ日没です。綺麗な夕日です。大阪湾に方向です。お天気も良かったので堺の町を一望できました。空から見た中百舌鳥古墳群は素晴らしい。世界遺産になるのかしらん。pleさん、素晴らしいとこを教えてくださって本当にありがとうございました。とても幸せな気持になりました。ところで、明日は先輩と伊勢の瀧原宮と松阪の斎宮跡へ行ってきます。5時過ぎに家を出るので、今日はそろそろ寝ることとします。では、行ってきま~す。
2009.01.26
コメント(6)
-

方違神社
念願の『方違神社』へ行ってきました。神功皇后が三韓征伐から凱旋の途中、二人の王子の反乱にあいますが、方災除けを祈願し、勝利しました。後にこの地に新霊を留め、方違神社と尊び奉ります。河内、摂津、和泉の三つの国の境界であることから、三国ヶ丘と呼ばれ、どこの国にも属さない三国の境、方位のない聖地とされました。三国ヶ丘、堺の名はこの故事に由来するのだそうです。奈良時代には僧行基が此辻に伏屋を設け旅人の休憩に供したので、人馬往来の要衝でもありました。平安時代には熊野詣の通過点であった為、旅人が安全を祈ったといいます。境内の御土と菰の葉にて作られた粽は、悪い方位を祓うとされ、方災除けの神様として信仰されています。境内からすぐ横に、反正天皇陵があります。pleさんに、堺市の市役所の上から反正天皇陵が見えるよと教えていただいたので、さっそく市役所まで行ってみました。確かに見えました。反正天皇陵のすぐ横に、方違神社がみえます。でも、それだけではないのです。市役所は21階建ての結構、高い建物です。堺市の仁徳天皇陵、履中天皇陵、ニサンザイ古墳だど本当に真下に見えるのです。そのうえ、私の大好きな二上山、金剛山、葛城山も良く見えます。それから、反対側に回れば、大阪湾も阪神高速も、難波もすごく良く見えるのです。それに、めちゃめちゃ夕日がきれい。感激です。pleさん、素敵なところを教えてくださってありがとうございます。今日は、まさにワクワクした一日でした。次回はそのことをもっと詳しくブログに書きたいと思います。
2009.01.25
コメント(6)
-

住吉大社
お昼ごはんを食べてから夫とどこかへ行こうと言うことになりました。では、先日からちょっと行きたいと思っている『方違神社』へ行こうと言うことになりました。ところが、「神社だったら私も行く、まだおみくじ引いてないし。」と娘。そして、「それなら、僕も行く。」と息子。ということで、四人で行くことになったのです。それならば、今日は『方違神社』ではなくて、『住吉大社』にしようよと誰ともなく声が上がって、それじゃということで、『住吉大社』へ行ってきました。来ました、太鼓橋。橋を渡ること自体が「おはらい」になるといわれています。四角柱と伊万里焼の鳥居です。ここから入りましょう。ここが四本宮への入口です。参拝の順序は一番奥にある第一本宮、第二本宮、第三本宮、第四本宮の順にするのが本当なのだそうです。第四本宮だけは女性である神功皇后を祭ってあります。本宮がすべて西を向いているのは「海上を行く船のようだ」と言われています。昔は、住吉大社のすぐ近くまでが海でした。住吉大社の入口のすぐ横が住吉の津(すみのえのつ)と言って、そばまで船が来ていたのです。大阪の人は「住吉さんは海の神さんやで。」と言います。神功皇后は朝鮮半島へ出兵する前にこの住吉大社へきて、勝利を願ったと言われています。遣唐使も遣隋使も海を渡る前にはここの神様に手を合わせに来たのだそうです。さて、私達は今日の目的の一つである「おみくじ」をひきました。結果は、夫と娘と息子は「中吉」。そして、私は何と「大吉」です。やった~、やった~と大喜び。躍り上がってしまいました。ちょっと、喜びすぎです。神様、うるさくしてすみません。家族四人で神社に来れるなんて本当にうれしい。めったにあることではないのです。いつも忙しい娘と息子。今日は私のために付き合ってくれてありがとう。母の、楽しみに付き合ってくれて…。ちょっと、泣きそう…。帰りに、「ここで結婚式を挙げたら凄く素敵だろな~。」と娘に囁くと、「結婚式場の前に相手やわ。」と軽くいなされてしまった。母の、小さな願いは、息子でも娘でもどっちでもいい、ここで結婚式を挙げてくれないかな~。母の趣味を押し付けるわけにもいかないし。確かに、結婚式場の前に相手。そして、その前に就職もあるし…。いえいえ、元気で毎日を過ごしてくれたらそれだけで、幸せ。そういえば、今思えば何故か無神論者の娘が手水舎の手の洗い方や、二礼二拝一礼の仕方をしつこく聞いていたな~。なんか、とてもうれしい。神様、今日の日をありがとうございました。そして、いつも本当にありがとうございます
2009.01.24
コメント(4)
-

あびこ観音
先日、あびこ観音さんの『朝のお勤め』に行ってきました。山門を入ると観音像が見えてきます。大日堂、福聚地蔵尊、油之不動尊、金辰殿をお参りします。本堂の裏手にはミニ西国33観音巡りが設置されています。そして、本堂に入りました。さて、午前6時半になると、ホラ貝が鳴り響きました。お坊さんと一緒に、観音経、般若心経、などを読みました。一時間弱の心の清まる時間でした。本堂に入る前は真っ暗だったのに、空は明るくなってきていました。あびこ観音さんは国で最古の観世音菩薩の寺院です。昔、この地に住んでいた依網吾彦(よさみのあびこ)という当時勢力を持っていた一族が、百済の聖明王から身の丈一寸八分(約8cm )の小さな観音像を贈られ、欽明天皇7年(546)に創建したのだそうです。その小さな観音様はここあびこ観音の秘仏となって大事に守られれています。一年に一度だけ、御開帳があって見せていただくことが出来ます。それが、来月2月1日です。もし、興味のある方は是非いらして見て下さい。その観音様は、大変祈りが通じやすいのだそうです。後に、聖徳太子がこの地に赴いた時に観音菩薩のお告げを受け、りっぱなお寺を建てるように命じ、「吾彦山観音寺」が建てられたと伝えられています。その後家康がお寺を立派に建て直し、江戸時代には境内に36の支院があったといわれ隆盛をきわめたのですが、明治14年の火災で多くの寺宝と共に焼失して、明治23年に再建され現在に至っています。毎年2月3日の 「節分厄除大法会」には「聖観音」が開帳され 、年越しの大法会も盛大にとり行われます。境内の油之不動孫では節分の日は大変な賑わいだそうです。もうすぐ節分ですね。お近くの方はいらして見られてはいかがでしょうか。『朝のお勤め』は、私にとって初めての経験でした。お坊さんのお経を読む声が心に沁みとおりました。お線香の香りが、心を清めてくれました。私はどちらかといえば、神社派であまりお寺のことはよく知らないのですが、こうやって連れてきてもらって、観音様に手を合わせると何もかも忘れて静かな心になりますね。やっぱり日本人なんだな~って思いました。なんだかとっても心が穏やかになったような気がしました。
2009.01.23
コメント(4)
-

書写山・円教寺
書写山・円教寺へ行ってきました。1月18日は修正会しゅしょうえ(鬼追い会式えしき) と 秘仏御開帳 があるということでした。円教寺は兵庫県姫路市の姫路城の西北約6kmに位置し、海抜371mの山上にあるのです。姫路駅から神姫バスに乗って30分、そこから書写山ロープウェーに乗って4分で頂上に着きます。性空上人によって開かれた、比叡山と同じ天台宗の修行道場の寺です、別名西の比叡山とも呼ばれています。ロープウェーを降りて15分くらい歩いて行くと門がありました。鬼追い式と秘仏公開は摩尼殿で行われます。秘仏は四天王と阿弥陀如来座像です。下から見た摩尼殿は結構大きいです。摩尼殿の下ではたき火が行われ、露店が出ていました。粕汁を頂きました。体があったまって、本当に美味しかったです。鬼追い式の前に、少し時間があったので大講堂の方へ行ってみました。ありました、めっちゃ大きい建物です。ここは、時々最近映画やテレビの撮影に使われるのだそうです。最近ではトム・クルーズ主演の「ザ・ラスト・サムライ」や大河ドラマの「武蔵」などもそうでした。「ザ・ラスト・サムライ」では、新しい人工の入らない、自然の中にたたずむ建物との調和した時代的な雰囲気が監督さんの目にとまったのだそうです。確かに、道も荒削りで本当に昔の道って感じです。建物もものすごく大きく、前の広場もすごくいろいのです。まさに、撮影にはもってこいの雰囲気でした。大講堂の横の、食堂(別名・長堂)は二階建てで長さ40mもあるのです。凄い大きさに圧倒されまてしまいました。さて、そろそろ時間が来たので摩尼殿の方へ行きました。まずは、一年に一度しか見ることが出来ないと言われている秘仏を見せていただきました。とても美しい仏像でした。1時になったので、鬼追い式が始まりました。お坊さんが10人以上で、お経をあげて下さります。凄い迫力です。おごそかな雰囲気です。円教寺の修正会というのは、護法童子と呼ばれる「鬼」(春を呼ぶ神)が「悪鬼(災厄)を追い春を呼ぶ神」として登場します。宝剣を握る青鬼、赤鬼は槌を背負い松明を翳し、鈴を鳴らして、四股を踏むように四方四維の大地を踏みしめるのですが、これは大地を浄めて五穀豊穣を祈る行為なのだそうです。摩尼殿内部は完全に閉堂されて、ローソクと松明の明かりのみを頼りに法要が行われました。今回の中央大壇上には初夜の導師として塔頭妙光院住職、後夜の導師に瑞光院住職が登壇して勤めました。2時間に及ぶ鬼追い式は無事終わりました。このような行事を見ることが出来て楽しかったです。日本には今でもこのような素晴らしい行事がいっぱい残っているのだなと思いました。地元の人や、遠くからも無病息災を願い集まった人々約200人が一つになって鬼追い式を楽しみました。書写山・円教寺は聞いていた以上に良いところでした。|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆余談ですが、こんな早口言葉知っておられますか?「上方僧(かみがたそう)書写山(しょしゃざん)社僧(しゃそう)の総名代(そうみょうだい)、 今日の僧者(そうじゃ)は書写じゃぞ書写じゃぞ」何回言っても、かんでしまいます。(笑)難しい、でも面白いですよね。
2009.01.18
コメント(8)
-

『古代からの伝言 』の次は『青雲の大和』!!
私が古代史に興味をもった時に、一番はじめに読んだ本です。『古代からの伝言』oliveさん、読み始めたのですね。第一弾 【日出づる国篇】 日本民族の新しい歴史がここに始まる。 第一部 日出づる国 第二部 水漬くかばね第二弾 【悠久の大和篇】 古代日本の国家建設はどのように行われたか。 第三部 民族の雄飛 第四部 悠久の大和第三弾 【日本建国篇】 大化改新の理想を受け継ぐのはだれか。 第五部 日本建国 第六部 大和の青春第四弾 【壬申の乱】 私たち日本民族は東アジアで何をしたのか。 第七部 壬申の乱 第八部 わが国家成るう~ん、面白いですよ。教科書では教えてくれない色々なことが分かります。これを読んで奈良、飛鳥を歩くとさらに楽しい。実はこの本は産経新聞の朝刊に掲載されていたものなのです。八木荘司はすごいですね。なんでこんなに詳しく分かるのでしょうか。まさに、目から鱗ぽろぽろです。そして、この古代からの伝言には続きがあるのです。青雲の大和です。【青雲の大和・上】志半ばにして逝った聖徳太子の理想は、帰国した留学生たちに脈々と受け継がれていた。また、かつての学友・入鹿の増長に心を痛める中臣鎌足も、蘇我氏を除くことを決意。皇極天皇4年6月12日、運命の日が訪れる。【青雲の大和・下】新たな理想のもと、国家建設に邁進する大和。朝鮮半島問題に対処するため、高向玄理は再び中国・唐の地を踏むが・・・。瑞々しい筆致と圧倒的なスケールで、大化改新に奮闘する古代日本を活写した歴史長編小説。私は当初、産経新聞をとっていたので読んでいたのですが、途中から分け合って読売新聞に変更しなければならなくなったので、半分くらいしか読んでいないのです。あ~、続きが読みたくなってきました。今読んでいる『白鳥の王子 ヤマトタケル』の次は『青雲の大和』に決まりです。
2009.01.15
コメント(2)
-

長屋王・吉備内親王
近鉄生駒線の平群駅から歩いて5分くらいのところに長屋王陵と吉備内親王陵が仲良く並んで建造されています。長屋王は奈良時代の皇族、公卿。正二位左大臣。皇親勢力の巨頭として政界の重鎮となったが、対立する藤原氏の陰謀といわれる長屋王の変で自害しました。【長屋王】父:高市皇子 (天武天皇の皇子)母:御名部皇女 (元明天皇の同母姉)弟:鈴鹿王 妹:河内女王・山形女王 妃:吉備内親王 - 草壁皇子と元明天皇の娘 男子:膳夫王:桑田王:葛木王:鉤取王 妃:藤原長娥子 - 藤原不比等の娘 男子:安宿王 :黄文王 :山背王 女子:教勝 妃:智努女王 女子:円方女王 妃:安倍大刀自 女子:賀茂女王 妃:石川夫人 【吉備内親王】吉備内親王は草壁皇子と元明天皇の次女。元正天皇、文武天皇の姉妹。長屋王の妃。長屋王の変で自殺に追い込まれました。父:草壁皇子 母:阿陪皇女(元明天皇) 同母兄姉:氷高皇女(元正天皇)、珂瑠皇子(文武天皇) 夫:長屋王 子:膳夫王・葛木王・鉤取王・桑田王 長屋王は藤原氏の勢力拡大のために無実の罪で殺されました。そして、一族もろとも自殺に追いやられたのです。悲しいですね。先日紹介させていただいた里中満知子さんの『天上の虹』にも登場しますが、『長屋王残照記』ではより詳しいことが分かると思います。私はまだ読んではいないのですが、豊田有恒『長屋王横死事件』 杉本苑子『穢土荘厳』 安部龍太郎『長屋王の変』 藤川桂介『宇宙皇子』なども有名のようです。また、宝塚歌劇団でも『たまゆらの記』 という題名で長屋王ことをされているみたいですね。古代史の悲劇のヒーロを選ぶとすれば、私でしたら大津の皇子、の次に長屋王だと思います。あとは、有間皇子や安積皇子も悲しいですよね。若いうちに残念でたまりませんが、いつまでも日本人の心の中には残り続けるのでしょうね。
2009.01.14
コメント(6)
-

孝謙天皇
孝謙天皇陵は奈良にあります。大阪難波から近鉄奈良線で「西大寺駅」下車、徒歩10分。孝謙天皇陵、成務天皇陵、日葉酢媛陵は三つの古墳がよりそうように築造されています。【第46代孝謙(こうけん)天皇】異名: 阿倍(あべ)姫、 宝字称徳孝謙皇帝(ほうじしょうとくこうけん)生没年: 養老2年(718)~ 神護景雲4年(770)(53歳)在位: 天平勝宝元年(749)~ 天平宝字2年(758)父: 聖武天皇 第2皇女母: 光明皇后(藤原安宿媛 ふじわらのあすかべ 藤原不比等の娘)皇子女: なし皇宮: 平城京(へいじょうきょう:ならのみや:奈良市)御陵: 高野陵(たかののみささぎ:奈良県奈良市山陵町) 【第48代称徳(しょうとく)天皇】在位: 天平宝字8年(764)~ 神護景雲4年(770)聖武天皇と光明皇后との間に生まれた第2皇女。女性としてはじめて皇太子になった。父、聖武太上天皇の死後39才にて即位する。母、光明皇太后を後見人に、藤原仲麻呂を用い橘奈良麻呂の乱を鎮圧した。政務の実権は皇太后と藤原仲麻呂が掌握した。聖武太上天皇が没すると、遺詔に従って新田部親王の子、道祖王が皇太子に立てられたが、器にあらずとして皇太子の位を剥奪される。天皇は立太子を群臣に図るが、右大臣豊成・中務卿永手らは「塩焼王」を、摂津大夫文屋智努・左大弁大伴古麻呂らは池田王を推挙する。天皇は、藤原仲麻呂の進言によって、舎人親王の子、大炊王(おおいおう)を選ぶ。これにより大炊王が立太子するが、淳仁天皇として即位した後の仲麻呂の上表によれば、これ(立太子)を定めたのは光明皇太后とある。天平宝字2年(758)、母への孝養を理由に、孝謙天皇は大炊王に譲位する。里中満知子さんの『女帝の手記』では孝謙天皇のことが描かれています。歴代の女性天皇の中で唯一未婚の女帝でした。でも、そんな女帝でも本当は愛し愛される人と結婚し普通の家庭を持ちたかったのではないかしらなんて思ったりしています。孝謙から皇位を継いだ淳仁天皇の時代、天平宝字4年( 760)母皇太后が崩御し、翌年保良宮で禅宗僧「道鏡」の看病を受けたのを期に、孝謙上皇は淳仁天皇・藤原仲麻呂らとの対立を深め、天平宝字6年( 762)出家を宣言して政務を二分し、祭祀・小事のみは天皇に委ね、国家の大事・賞罰は自らが行うと宣下する。僧・弓削道鏡を重用する孝謙上皇に対し、これを不服とする恵美(藤原仲麻呂)は乱を起こし失脚する。追い詰められた仲麻呂は越前への逃亡を図るが失敗し、琵琶湖上で斬殺された。孝謙はこの直後、藤原豊成を右大臣に再任、道鏡を大臣禅師に任命し、乱に連座した淳仁天皇も廃帝流罪(淡路島)とした。この時孝謙上皇は46才。絶対の権力を持つ信仰深い独身の尼で、既に両親はなく兄弟もなかったため、上皇が称徳天皇として重祚(ちょうそ)するのである。天武系の最後の天皇であった。「天平神護」と改元し、同年8月、皇太子候補であった和気王(舎人親王の孫)を謀反の罪で捕え、配流の途次、絞殺せしめる。すでに道鏡への譲位を考えていたのかもしれない。歴史好きな人々の間では、称徳天皇と道鏡の関係はあまりにも有名である。天皇は、年甲斐もなく色に狂った「淫乱な女帝」として、道鏡は最後には天皇の座を狙った「天下の大逆賊」として世間に流布している。黒岩重吾さんの『弓削の道鏡』です。道鏡って本当はどんな人だったのでしょうか?道鏡は日本史始まって以来の悪人のように言われていた時期もありました。妖僧とまで、言われていたりもしたのです。しかし、本当はごく当たり前の、一人の男だったのかも知れませんね。大変な勉強家で当時では珍しくサンスクリット語まで読めたと言います。本当に自分から天皇になりたがったのでしょうか。孝謙天皇は女性の身で、二度も皇位についたので、日本史上まれに見る栄光に包まれた女性と言えるのではないでしょうか。しかし、その栄光と華やかな男性関係とは裏腹に、日本史上もっとも孤独な女性だったのかも知れませんね。
2009.01.13
コメント(4)
-

天武・持統天皇陵
飛鳥にある天武・持統天皇陵です。持統天皇の父は天智天皇、天智天皇と天武天皇は兄弟。ですから、持統天皇は父の弟に嫁いだということになります。天武天皇にはたくさんの妃がいましたので、持統天皇はその意味では苦労したかも知れませんね。同じ古墳に二人で入っているというのはそんなに多くはないのです。聖武天皇と光明皇后や、長屋王と吉備内親王のようにすぐ隣に寄り添って眠っていることはよくありますよね。(近つ飛鳥では推古天皇と竹田皇子が一緒ですが…。)もしかしたら、持統天皇は、他の女性に夫が取られないように一緒に入ったのではなどと、古墳を見ながら考えたりしてしまいました。(笑)【第40代天武(てんむ)天皇】 異名: 大海人皇子(おおあまのおうじ)、天渟中原瀛真人天(あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと)生没年: ?年~ 朱鳥(しゅちょう)元年(686)(?歳)在位: 年(673) ~ 朱鳥元年(686)父: 舒明天皇(田村皇子)母: 皇極天皇、斉明天皇(宝皇女)皇后: 鵜野讃良(うののさらら)皇女(持統天皇)皇妃: 大田(おおた)皇女、大江(おおえ)皇女、新田部(にいたべ)皇女、氷上娘(ひかみのいらつめ:中臣鎌足の娘)、五百重娘(いおえのいらつめ:氷上娘の妹)、額田王(ぬかたのおおきみ)、尼子娘(あまこのいらつめ)皇女子: 大来(おおく)皇女、大津皇子(おうつのみこ)・・・ 以上母は大田皇女壁皇子(くさかべのおうじ)・・・ 母は鵜野讃良皇女、長皇子(ながおうじ)、弓削皇子(ゆげおうじ)・・・母は大江皇女、舎人親王(とめりしんのう)・・・ 母は新田部皇女、但馬皇女(たじまのこうじょ) ・・・ 母は氷上娘新田部親王(にいたべのしんのう) ・・・ 母は五百重娘、十市(とおち)皇女 ・・・母は額田王。大友皇子皇后。武市(たけち)皇子 ・・・母は尼子娘。忍壁(おさかべ)皇子、磯城(しき)皇子、泊瀬部(はつせべ)皇女、託基(たき)皇女 宮居: 飛鳥浄御原宮(あすかきよみがはらのみや:奈良県高市郡明日香村) 御陵: 檜隈大内陵(ひのくまのおおうちのみささぎ: 同上 )兄天智天皇(中大兄皇子:なかおおえのおうじ)の子弘文天皇(大友皇子:おおとものみこ)を、壬申の乱を起こして滅ぼした後、大海人皇子(おおあまのおうじ)は、近江朝を廃し飛鳥浄御原宮(あすかきよみがはらのみや)で即位し天武天皇となった。多くの妃・皇子女があり、その大半が後代の天皇となっている。皇女の一人大伯(おおく)皇女を、長らく途絶えたままになっていた伊勢の斎宮(いつきのみや)に定めて神祇(じんぎ)の復興につとめた。伊勢神宮を祀る集団は、壬申の乱で大海人皇子に味方したため天武天皇はその恩義に報い、伊勢神宮を天皇家の守護宮と定めた。そのために斎の宮を再興したのである。これ以後、今に至るまで伊勢神宮は天皇家の守護社となっている。天武は兄天智天皇の押し進めた中央集権国家体制を更に進め、生涯大臣をおかず自ら政治を行い、飛鳥浄御原令、八色姓(やくさのかばね)の制定など、中央集権の国家の体制づくりに多くの業績を残した。又、国史編纂をすすめ記紀成立の基礎を作った。大和朝廷がそれまでの倭に替えて「日本」という国号を使いはじめたのもこの御代であろうとされる。天皇は、道教や陰陽道に傾倒していた事も有名である。【第41代持統(じとう)天皇】異名: 鵜野讃良皇女(うのささら)、大倭根子天之広野日女尊(おおやまとねこあめのひろのひめ)、高天原広野姫(たかまがはらひろの)生没年: 大化元年(645)~ 大宝2年(702)(58歳)称制: 朱鳥元年(686)~ 持統4年(690)在位: 持統4年(690)~ 持統11年(697)父: 天智天皇 第2皇女母: 蘇我遠智娘(そがのおちひめ:蘇我倉山田石川麻呂の娘)夫: 天武天皇(大海人皇子)皇女子: 草壁皇子(くさかべのおうじ) 宮居: 飛鳥浄御原宮(あすかきよみがはらのみや:奈良県高市郡明日香村)、藤原宮(ふじわらのみや:奈良県橿原市)御陵: 檜隈大内陵(ひのくまのおおうちのみささぎ:奈良県高市郡明日香村)鵜野讃良(うののさらら)は斉明天皇3年(657)、13歳で叔父の大海人皇子に嫁いだ。斉明7年(661)、斉明天皇の新羅遠征の際、夫と共に九州へ随行し、翌年筑紫の「那の津」で草壁皇子を産む。同年、父中大兄皇子が皇位を継承し(天智天皇)、夫の大海人は皇太子となる。天智称制6年頃までには、姉の大田皇女の後、鵜野讃良が大海人皇子の正妻になったものと思われる。やがて天智天皇は弟ではなく、実子の大友皇子を後継者に望み、大海人皇子は身の危険を察して、天智10年(671)吉野に隠遁。鵜野讃良も草壁を伴いこれに従った。天智11年壬申の乱勃発。大海人皇子は大友皇子を破り、天武元年(672)、飛鳥浄御原宮で即位し鵜野讃良も皇后となる。以後夫を輔佐し、ともに律令国家建設に尽力した。吉野宮での六皇子の盟約を経て、天武6(680)年、我が子「草壁皇子の立太子」を実現する。天武・持統天皇関連の書物はたくさんありますが、私がいくつか読んだ中で最後に読んだ里中満知子さんの『天上の虹』は分かりやすくてお勧めです。里中作品は、美男美女が多くまた里中さん特有のそれぞれの立場から見た物事の捉え方が優しくて、女性向と言えるかもしれませんね。『天上の虹』1巻~16巻で、主人公は持統天皇です1巻 大化の改新、有間皇子、額田王2巻 建皇子、別れの歌、星宿(セイジュク)3巻 船出、大田皇女、白村江の戦い4巻 間人皇女、近江大津宮、天智天皇5巻 蒲生野、漏刻、大友皇子6巻 壬申の乱7巻 近江京炎上、天武天皇、飛鳥浄御原宮 8巻 十市皇女、わかれ道、少年たち9巻 山吹の女、星祭り、薬師寺発願10巻 草壁皇子、大津皇子、大名児11巻 八色の姓、彗星、朱鳥12巻 崩御、もがり、二上山13巻 章陵、章蛍、章櫻14巻 三種の神器、恋人たち、穂積皇子15巻 但馬皇女、月かたびきぬ、ホトトギス16巻 香具山、藤原不比等、無料大数『天上の虹』は登場人物も多く、出来事も多かったのですが吸い込まれるように次々と読んでしまいました。古代史に興味の有る方には是非お勧めの本ですよ。
2009.01.12
コメント(2)
-

元正・元明天皇陵
昨年、出かけたもののいまだにブログにUP出来なかった御陵をいくつか紹介させて頂きたいと思います。今回は、元明天皇陵と元正天皇陵です。近鉄奈良駅からバスに乗って、「奈保山御陵」で降りて15分ほどのところに、「元明天皇陵」があります。(ちなみに、左に「元正天皇陵」があり、母娘は仲良く並んで眠っています。)【第43代元明(げんめい)天皇】異名: 阿閉(あへ)皇女、日本根子天津御代豊国成姫天皇(やまとねこあまつみしろとよくになりひめのすめらみこと)生没年: 斉明天皇7年(661) ~ 養老(ようろう)5年(721)(61歳)在位: 慶雲4年(707) ~ 霊亀元年(715)父: 天智天皇 第4皇女母: 姪娘(めいのいらつめ:蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらやまだのいしかわまろ)の娘)夫: 草壁皇太子(天武・持統天皇の子)皇子女: 軽皇子(文武天皇)、氷高皇女(元正天皇)、吉備内親王 皇宮: 平城京(へいじょうきょう:奈良市) 御陵: 奈保山東陵(なほやまひがしのみささぎ:奈良市奈良坂町)天智天皇の子で、母は蘇我倉山田石川麻呂の女、姪娘(めいのいらつめ)。天武・持統天皇の実子で、持統天皇が大津皇子(おおつのみこ)を殺してでも皇位につけたかった皇子の草壁皇太子に嫁いだ。草壁皇子との間に軽皇子(文武天皇)と氷高皇女(元正天皇)、吉備皇女をもうけている。実子の、第42代文武天皇が慶雲4年(707)25才で崩御したため、女帝として即位。慶雲3年(706)文武天皇は病床から母に即位を求めたが、天皇はこれを固辞した。しかし翌年文武天皇の崩御に伴い、やむなく即位したとされる。文武の一子は、当時7才の首皇子(聖武天皇)で、成長するまでの中継ぎとして即位したようだ。当時天武天皇の遺児も存在し、また高市皇子の子であった長屋王なども皇位継承の有力候補として存在したが、元明天皇は、父天智天皇の定めた不改常典に従って皇位を継承する事を強く訴え、嫡系相承の正統性を主張した。その隣の古墳は元正天皇陵です。【第44代元正(げんしょう)天皇】異名: 氷高(ひたか)皇女、日本根子高端浄足姫天皇(やまとねこたかみずきよたらしひめのすめらみこと)生没年: 天武天皇9年(680) ~ 天平20(748)(68歳)在位: 霊亀元年(715) ~ 神亀元年(724)父: 草壁皇子(天武・持統天皇の子)母: 阿閉皇女(元明天皇)夫: なし皇子女: なし皇宮: 平城京(へいじょうきょう:奈良市) 御陵: 奈保山西陵(なほやまにしのみささぎ:奈良市奈良坂元明女帝の子で、第42代文武天皇の姉。生涯独身だったと伝えられる。弟文武の遺児首皇子(聖武天皇)の成長まで中継ぎとして皇位についた。この天皇の治世は、平城京の造営整備も進み、律令制中央政権国家の基盤も次第に固まりつつあった時期で、藤原不比等主導の元、律令制の整備が図らた。元正天皇については、永井路子さんの『美貌の女帝』を読むと良く分かります。題名の通り元正天皇は大変な美貌だったそうです。それなのに、生涯独身を余儀なくされて可哀想な一生だったのかも知れませんね。こういった作品を読んで、古墳をめぐると感動もひとしおです。まさに、「フィールドワーク」です。
2009.01.11
コメント(4)
-

百舌鳥八幡
今日は十日戎ですね。大阪は雪が降る寒い一日でした。ブログにUPするのが遅くなってしまいましたが、一週間ほどまえに百舌鳥八幡に行ってきました。以前から、百舌鳥八幡にはどうしても行きたかったのです。何故行きたかったかと言うと、pleさんが行っていたから。子供みたいな理由ですね。おもちゃを持っている子を見て、欲しい欲しいと駄々をこねる子供みたいです。(笑)そういうことで、「明日から仕事だから、今日は一日絶対に家から出ないでゆっくりする。」と言い張る夫に「百舌鳥八幡で初詣したいな~。」と囁き、反応がないと、「家事の手を抜くぞ。」と脅してそれでも無反応だったので、最後の手段である泣き落しを使ってまでして、連れて行ってもらいました。(笑)本当は住吉大社と大鳥神社にも行きたかったのですが、あまり我儘をこねるのも良くないと自重して、とりあえす百舌鳥八幡へ行きました。やっぱり、行って良かった。良い神社です。お正月なので露店が出ていました。拝殿です。御祭神は応神天皇です。 配祀は、神功皇后、仲哀天皇、住吉大神、春日大神所伝によれば、神功皇后が三韓征討の事終えて難波に御帰りになった時、この百舌鳥の地に御心を留められ幾万年の後までもこの処に鎮りまして、天下泰平民万人を守ろうという御誓願を立てられ、八幡大神の宣託をうけて欽明天皇の時代に、この地を万代(もず)と称し、ここに神社を創建してお祀りされたと伝えられているのだそうです。やはり、お正月なので人が多いです。池がありました。私は昨年、天河神社に行ってからなぜか弁財天さまの近くに来ると訳もなくとにかく、「とても良い気持ち」になるのです。「あ~、気持ちイイ、気持ちイイ、気持ちイイ…。」と繰り返し自然と口がしゃべっているのです。自分でも何故だかわからないのです。大原三千院に行ったときは、裏の方を歩きまわっていたらなぜか突然、すごく気持ち良くなって「あ~、気持ちイイ…。」を連発していたら目の前に弁天様がいらっしゃってびっくりしたのです。その時はまさに、寒い中やっと温泉に入ってゆっくりした時くらいの気持ち良さでした。今回はそれほどでもなかったとはいえ、やはりとっても気持ち良くなってきました。特に弁天様だけ大好きとかそういうわけでもないのに何故なのでしょうか。弁財天様に手を合わせました。そういえば今思い出したのですが、家の神棚に弁財天様のお札を掲げていてしょっちゅうお水を代えて手を合わせています。そのことが何か関係しているのでしょうか。私はスピリチュアルとか良く分からないので。何だかとても不思議な体験です。弁財天様の横に水天宮社がありました。綺麗なお水の上にあり良い景色です。私がご機嫌なので夫はホッとしているようです。とにかく私がご機嫌だと夕食が豪華なのですよ。手の込んだお料理を作りたくなるのです。料理の苦手な私が頑張っていられるのも神社めぐりのおかげです。夫はそのことをよ~く知っているようです。来週は夫の趣味に付き会う約束になっているので、今日は私に付き合ってもらってもまあ良いでしょう。お互い趣味は違っても、休日は一緒に行動するのが癖になってしまっています。夫婦円満の秘訣かもしれませんね。(笑)
2009.01.10
コメント(4)
-
黒岩重吾さんの古代関連の小説を読んで。
私の黒岩重吾さんの作品を読んで古代史がそれまで以上に好きになったのでした。もちろん小説なので史実とは違うところも多いのですが、古代史を深く楽しむことが出来るようになったのは黒岩重吾さんの作品のお陰だと思っています。黒岩重吾さんは古代史を小説という形で表わし古代史ブームを巻き起こした先駆的な役割を果たした人だと思っています。小説だけでなく、エッセイも大変面白いです。エッセイを読むと小説とは全然違って比較しながら読むのも面白いと思います。もう25年くらい前に『落日の王子ー蘇我の入鹿』を読んで以来、いつか他の物も読もうと思っていましたが、その後20年くらいは忘れてしまっていました。それが、5年くらい前に先輩に勧められて一冊読んでみたら、面白くそのあと次々に読むことになったのでした。一番好きなのは『茜に燃ゆ―小説 額田王』です。額田王は私の憧れの女性です。これを読んで滋賀県の蒲生野まで行きました。(笑)井上靖の『小説 額田王』とはちょっと違いますが、どちらも良かったです。『天翔る白日―小説 大津皇子 』では、大津皇子がカッコイイし謀反の罪で処刑されるので切ないのです。いつも職場から二上山を見ては大津の皇子を思っています。(笑)『鬼道の女王 卑弥呼』では私がそれまで思っていた卑弥呼と違って面白かったです。『紅蓮の女王―小説 推古女帝』では、女性で初めての天皇推古女帝が描かれています。聖徳太子も登場します。『ワカタケル大王』は雄略天皇のことです。仁徳天皇とその息子たち、履中天皇、安康天皇、反正天皇、允恭天皇などについて詳しく書かれていて、まさに倭の五王の時代のことが分かりとても面白かったです。『女龍王神功皇后』は神功皇后が主役で『落日の王子』の次に読んだ作品でした。面白かったです。『弓削道鏡』を読むと一般に言われている道鏡とは違って面白かったです。『北風に起つ―継体戦争と蘇我稲目』では、継体天皇について良く分かり面白かったです。樟葉へは行ってみたいと思っています。『天風の彩王―藤原不比等』は藤原不比等がどんな人か分かって面白かったですね。このあと、永井路子さんの王朝三部作「王朝序曲」「この世をば」「望しは何ぞ」を読むと藤原氏についてちょっと分かったような気になれます。『中大兄皇子伝』や『聖徳太子』もとても読みやすくすぐによめてしまいますよ。その他、エッセイだと『古代史への旅』『謎の古代女性たち』『古代史の謎を探る』『古代史の迷路を歩く』『古代史を解く九つの謎』も面白かったです。あと、何を読んだかちょっと忘れてしまったのですがとにかく何を読んでも面白いですね。こういうのを読んで、飛鳥に行くとさらに思いが深くなります。私はこうやって、古代史にどんどん嵌りこんで行ったのです。(笑)
2009.01.08
コメント(8)
-

白鳥の王子 ヤマトタケル
今読んでいる本は、『白鳥の王子 ヤマトタケル』(著・黒岩重吾)です。この本は先輩のお勧めで随分前から、是非読んでみたかったのですが絶版になっていて、中古本屋さんで探していたのですがどうしても見つからなくて困っていたのです。そういえば、ネットで買えるのではと思いe book of 中古本で検索してみました。ありました、さすがに絶版の本でも、中古本の中なら見つけられますよね。ところが、6冊のうち約半分しか揃わなくてあとは入荷次第メールしますというところにチェックを付け、待つことにしました。そして、やっと年末に全部そろったのです。そして今、読み始めています。うん、さすが先輩のお勧め本だけあって面白い!!黒岩重吾さんは関西出身だけあって地名や位置関係がしっかりしていますね。今は第一巻目の「大和編」なのですが、昨年先輩と歩いた斑鳩、龍田道、平群、生駒、信貴山、矢田丘陵など出てくる出てくる…。当時と少し違っているところの説明があったり、また当時とちっとも変っていない風景も描かれていたり、臨場感があり面白いですね。本を読んで、その場所を訪れるまさに「フィールドワーク」で得られる感動そのものです。このあと、東征では関東の方へ、西征では九州の方へまで描かれています。ヤマトタケルの行動範囲はすごい広さですね。そして、一番大事な主役ヤマトタケルなのですが、超カッコイイのです。黒岩重吾さんの手にかかるとヤマトタケルはハンサムで強くて優しくて、誰でも惚れてしまいますよね。お話も面白い。もちろん物語なので史実とぴったり一致というわけにはいかないとは思うのですが、そんなことより黒岩ヤマトタケルに酔いしれていたいです。歴史と、地理と、ハンサムでかっこいい男が好きな人にお勧めの一冊です。さて、続きを読まなくちゃ、ウフフ。
2009.01.07
コメント(6)
-

岡寺
西国三十三所の七番札所でもある岡寺は、飛鳥寺から少し山手に登って行ったところにあります。坂を上ると重要文化財に指定されている鮮やかな朱色をした仁王門があらわれます。日本最初の厄除け霊場としても有名です。本堂の本尊、如意輪観音座像は塑像(土で造られた仏様)で、弘法大師の作と伝えられ、塑像としてはわが国最大の仏像なのだそうです。私が行ったのは、昨年の年末でちょうど御開帳の時でしたので、その如意輪観音像を見ることが出来ました。確かに大きく迫力がありました。弘法大師様も凄いのを作られたのですね。観音様とつながった紐に触れ、しっかりと参拝しました。私はここへ来るのは今年は2度目です。以前、4月中旬頃、テレビのニュースではシャクナゲの花約3000株が咲き誇っているところが映っていました。また、桜、サツキ、そして、秋には紅葉も美しいのだそうです。さまざまな伝説を残した名僧、義淵僧正が創建したそうです。 今回は、お花の季節から離れていたせいか人が少なくとても静かで凛とした空気に包まれていました。御開帳の観音様を見ることが出来て満足の岡寺でした。
2009.01.06
コメント(5)
-

飛鳥寺
一番好きな神社はどこですか?って聞かれたらそれは困ります。やっぱり、伊勢神宮かしら行ってみると分かるけど神聖で素晴らしい。でも、大神神社も捨てがたいな。元伊勢でもある檜原神社からみる二上山も大好きだし、久延彦神社から見る大和平野を見た時に、雲の切れ間から光がさして神々しいこと。住吉大社も好きだな~、何度行っても飽きないし。出雲大社もなかなか良いですよ。今年は御開帳にいって感動したしな。二十二社も全部素晴らしいしな。まだ行っていないけど、宇佐八幡や霧島神社や高千穂神社もきっと素敵なんだろうな。関西しか知らない私ですが、関東の方や日本中には素晴らしい神社がいっぱいあるのでしょうね。なんせ、神社に関しては思い入れが強いせいかどれが一番とは言い難いのです。ところが、お寺に関しては全く違って、あまりよく知らないせいでしょうか、一番好きな神社ははっきり言えてしまうのです。もちろん、法隆寺や四天王寺をはじめ、西国三十三ヵ所、四国八十八か所、そうそう関西だけではなく日本中に素晴らしいお寺はあると思います。でも、私個人の好みでいえば、一番好きなお寺は飛鳥にある『飛鳥寺』なのです。現存する世界最古の木造の建物は法隆寺ということになっていますが、もし火災で焼けなかったらそれは、『飛鳥寺』だったのですよね。仏教が伝えられた時にお寺を作るということでその当時の最先端の技術を集結して、日本という国家が外国に馬鹿にされないように精一杯の背伸びをしながら頑張って頑張って作ったのがこの美しい『飛鳥寺』なのです。もちろん、雷や火災でお寺自体は焼けてしまって今あるのは再建ということになるのですが、飛鳥寺の中にいらっしゃる大仏様は木ではなく金属だったせいで今でもちゃんと残っておられるのです。そして、去年がその大仏様の開眼千四百年の記念の年だったのです。(飛鳥大仏開眼は、法隆寺が建てられる11年前なのだそうです。)ここの大仏様の前で、聖徳太子様も蘇我氏も天皇家の多くの方々もみな一様にひざまずき手を合わせたのです。そして、もっと凄いことに当時の庶民も同じ場所で同じようにひざまずき手を合わせたのです。そして、その時から今日に至るまで多くの人々が大仏様の前で同じようにひざまづき手を合わせてきました。ここの大仏様は写真に撮ってもいいのだそうです。実はこの大仏様の前で私と友達は住職さんに大仏様が入るように写真を撮っていただいたりもしたのです。なんて、おおらかなのでしょうか。そして、ちょっと嬉しいことに私が座っていたところに実は先日、紀子様が座っていらっしゃった場所なのだそうです。紀子様は名前を変えて身分を伏せて学習院の生徒たちとお忍びでいらっしゃったそうです。(学習院の名前も伏せて違う名前で来られていたそうです。)それから、またクイズ・ヘキサゴンで御馴染みのスザンヌちゃんも最近来られたそうです。藤田まことさんはちょくちょく来られるそうです。実は私も飛鳥に来たときには必ずここに立ち寄ります。一年に何度か来たくなっちゃうのです。なんだかとても落ち着くのです。故郷に帰ってきたかのように…。阿弥陀如来様もいらっしゃいます。もちろんお写真を撮らせていただいても大丈夫なのだそうです。それから、最近この美しい西陣織の飛鳥大仏が完成したそうです。髪の毛よりも細い糸を何万本も使って作っています。私は最初、絵だと思っていたのですが、西陣織だと知ってびっくりでした。それから、ガラスケースの中に『飛鳥寺や山田寺の瓦』も展示されていました。実は私はこういった瓦や土器の類がめちゃくちゃ大好きなのです。あ~、良いな~、欲しいな~、…。(もちろん、ダメです。)こんなもの欲しがるなんて本当に変わっていると思われるかもしれませんが、本当にこういうものが大好きなのです。何故だか自分でも分からないのですが…。ここ、飛鳥寺は蹴鞠をしていた中大兄皇子が中臣鎌足と初めて出会う場所です。もちろん、鎌足はその出会いの時を待っていたのですが。このお寺の裏手には入鹿の首塚があります。首塚は飛鳥板葺の宮を睨んでいるかのようです。このお寺で大化の改新へと向かう歴史の曲がり角の始まりが生まれた場所なのです。私はいつまでもここを離れたくなくてお寺をゆっくり歩きまわっていました。段々暗くなってきたのでそろそろうが行かなくてはなりません。いつものように、その飛鳥寺の入口にあるお店で『飛鳥の蘇』を買いました。飛鳥の蘇は30リットルの牛乳を7~8時間かけて5キログラムにまで煮詰めた甘みの少ないキャラメルのようなチーズです。当時は高貴な方々の滋養と栄養のための高価な食べ物だったのだそうです。私はこれが大好きでまたまた買ってしまいました。本当に離れがたい気持ちを抑えて、このあと飛鳥寺を後にしたのでした。
2009.01.05
コメント(6)
-

橘寺
昨日、たけしさんの番組で『“教科書に載らない”日本人の謎』というのをしていましたね。初詣には神社とお寺のどちらに行くの?とか、たけしさんが生まれて初めて伊勢参りに行くとか…。たけしさんは、伊勢神宮を参拝して人生観が変わったとおっしゃっておられました。今までの想像とは全然イメージが違って、凄いとおっしゃっておられました。伊勢神宮では自分のちっぽけなお願いなどどこかへ吹っ飛んでしまって、「宇宙的な」幸せを祈らずにはいられない、みたいなことをおっしゃっておられました。確かに同感ですよね。その他、色々なお話結構楽しく見せていただきました。そのお話の中で初詣は神社かお寺かどちらが正しいの?というのがありました。正解は、どちらでもいいのだそうですね。もともと日本は「神仏習合」だから神社とお寺が一緒になっていたらしいのです。それが、明治になった時に廃仏棄釈とかいろいろあって神社とお寺を分けなければならなくなってしまったのでしたね。要するに明治の時に制度として神社とお寺を分けたのだけど日本人の心の中ではそれらをきっちり二つに分けることはできないのですね。つまり初詣は神社でも、お寺でも心をこめて拝みさえすればそれでいい。形ではなくて心の問題なのですよね。もともと日本は八百万の神々がいらっしゃる国です。中国から仏教が伝来した時に蘇我氏と物部氏の戦いはあったものの、時の天皇・欽明大王がどちらも敬おうとおっしゃられて両方大切にする国になったのだそうです。その後、聖徳太子様も神様も仏様も大切にされました。十七条憲法にもそのように書かれていますよね。日本人の心のありようの基となった憲法ではないかと思っています。ところで、その聖徳太子さまがお生まれになった場所が飛鳥にある『橘寺』だと言われています。先日、橘寺に行ったのですがお堂の中で気になるものを見つけてしまったのです。実は聖徳太子像の前に神社にあるような立派な鏡があるのです。ん~、なんか変だなと思いました。私の中では、お寺には仏像があって神社には仏像がなく鏡がある。そんな風に分けて考えていたので二つが同時にあることになんか納得できなくてしばらく考え込んでしまったのでした。どうしても気になったので、お寺の方に聞いてみました。すると、「良いところに気がつかれましたね。」と優しく微笑まれ、私の質問に丁寧に答えて下さったのでした。つまり、もともとは神社とお寺は一つだったのですが明治の廃仏毀釈の時にお寺を取り壊しされそうになったのだそうです。その時に、お寺を守っていた方が聖徳太子像の前に鏡を置かれて、「ここには仏さんだけではなくて神様もおられるのですよ」とおっしゃられたのだそうです。その鏡を見て、お寺を取り壊そうとしていたお役人たちも「なるほど」と納得して帰って行かれたのだそうです。それからは、ずーっと今までここの聖徳太子像の前に神社になるような立派な鏡がおかれたままになっているのだそうです。お役人さんも本当は、取り壊したくなかったのかも知れませんね。馬があるのはやはり、聖徳太子が厩戸皇子(うまやどのみこ) と呼ばれていたからでしょうか。橘寺(たちばなでら)という名の由来は、垂仁天皇の命により不老不死の果物をとりにいった田道間守(たじまもり)が持ち帰った橘の実を植えたことに由来するのだそうです。橘はみかんの原種なのだそうです。当時の人はみかんを不老不死の食べ物だと考えたのですね。私達は、毎年冬になると美味しいみかんを思う存分食べられるのは幸せなことですよね。確かに、美味しいみかんを食べているとなんだか長生きしそうな気がしますよね。さて、次回は私の大好きな『飛鳥寺』です。飛鳥大仏さんにお会いできて幸せな一日でした。
2009.01.04
コメント(10)
-

初詣
初詣は住吉大社と百舌鳥八幡と大鳥神社に行くはずだったのに、風邪をひいてしまい、遠出はちょっと無理そう…。年末に、遊びすぎたかな~。お洒落なイタリアンやカニの食べ放題、そして大急ぎで実家に帰ってお墓まり。ついに、お正月にグロッキー状態。それでも、初詣だけはどうしても行きたくて家からそんなに遠くない神社へ歩いて行ってきました。あまの街道を通って約6キロの道のりでした。ここは、堺市と狭山市の境目のトンネルの上です。この写真は狭山市側です。この辺りから2キロくらいで神社に着きます。反対側に7キロ歩くと金剛寺です。この神社は小さい神社ですが、地元の人に愛されているようです。拝殿で去年のお礼を言って、今年のご挨拶をしました。境内では焚火をしています。暖を頂きました。商売繁盛の戎さんもありました。手を合わせました。体調が良くないので、このまま帰りました。とりあえず初詣が出来て良かった。早く風邪を治して今年もいっぱい神社仏閣を巡りたいと思います。では、今日はここまでです。
2009.01.03
コメント(10)
-

岩湧山に登りました。
年末に夫と岩湧き山に登りました。岩湧寺もうっすらと雪がかぶっています。今回は前回の下見と違って、頂上まで登ることにしました。岩湧寺を過ぎると登り45分という健脚向きの「急坂の道」と登り75分という家族向けコースの「岩湧の道・ダイアモンドとレール」に分かれます。私たちは迷わず家族向けのコースをを選びました。途中、展望デッキに着きました。PLの塔が見えます。展望台を過ぎると少しのぼってダイヤモンドとレールです。ここまでくれば、緩い登りになるのでかなり楽です。杉林に囲まれた尾根筋を越えると「急坂の道」との合流地点です。ここから頂上までは15分くらいです。頂上につきました。岩湧山は秋にはススキがたなびく約8haの草原で有名です。270度位の角度で素晴らしい眺望です。右手には二上山、葛城山、金剛山が見えます。正面には六甲山、狭山池、泉北ニュータウンが見えます。左手には、大阪湾、大阪平野が見えます。お天気が良く素晴らしい眺めです。温かいお茶とおにぎりを食べて、山を下ることにしました。山登りは苦手なのですが、少し頑張ってみるとこんなに気持ちいいと知りました。ちょっと癖になるかも(笑)
2009.01.02
コメント(8)
-

明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。新しい年の幕開けです。昨年はたくさんの神社仏閣を訪れることが出来ました。伊勢神宮に始まって、出雲大社、奈良や京都の神社やお寺…。一つ一つが私の宝物です。pleさん、oliveさん、夏菜さんをはじめ色々な情報を下さった方本当にありがとうございました。machirnさん、マダム、ほぎさん、たまたま博士さんgundayuuさん、ヒロリンさん、日向永遠さん、ショコラさん、コナベさん、ままちりさん他私のようなブログを訪れて下さった方々本当にありがとうございました。心温まるコメント本当にありがとうございました。不思議なことに私にとっていくつかの新しい出会いがありました。本当に素晴らしい歳でした。今年も、きっと素敵な年になりそうな予感がします。皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。m(_ _"m)ペコリ
2009.01.01
コメント(4)
全23件 (23件中 1-23件目)
1