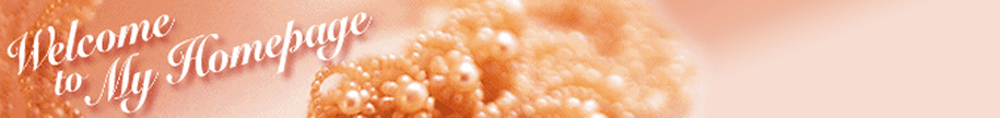2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009年02月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

若狭彦神社
若狭彦神社に着きました。祭神は若狭彦大神・海幸山幸の神話で名高い彦火火出見尊を若狭彦大神とたたえて奉祀しています。 彦火火出見尊の別名は火遠理命(ホオリノミコト)ホオリともいいます。ホオリは、日本神話に登場する神です。山幸彦と海幸彦の説話に登場し、一般には山幸彦(山佐知毘古、やまさちひこ)の名で知られています。また、 神武天皇の祖父です。『古事記』によると、ニニギとコノハナノサクヤビメとの間の子です。ニニギに国津神の子ではないかと疑われ、コノハナノサクヤビメがその疑いを晴らすために火中で生んだ三神の末子で、火が消えた時に生まれたのでホオリ(ホヲリ)と名附けたとしています。兄にホデリ(海幸彦)、ホスセリがいます。海神の娘のトヨタマビメを妻とし、ウガヤフキアエズを生んだのだそうです。ウガヤフキアエズは、トヨタマヒメの妹である育ての親であるタマヨリビメと結婚しイツセ(五瀬命)・イナヒ(稲氷命)・ミケヌ(御毛沼命)・ワカミケヌ(若御毛沼命)の四子をもうけた。末の息子が神武天皇となったのでした。そして、ホオリは高千穂宮で伍佰捌拾歳(580年)過ごして亡くなったと言われています。私の説明ではちょっと分かりにくい方は、日向神話神々の系譜を見ると分かりやすいかも知れません。↓境内です。良く見ると雪が残っています。この日はとても温かかったのですが、それでも雪が残っているということはこの辺りは寒いのですね。凛とした冷たい空気に包まれています。すぐ横に若狭若宮がありました。古来、若狭彦神社(上社、上宮)を若狭国一宮とし、若狭姫神社(下社、下宮)を二宮とされて来たが、現在は、2社で若狭国一宮・若狭彦神社と称しています。また、若狭彦・若狭姫は年を取らない二柱の神様とも言われています。若狭彦神社に来たので、すぐ近くの若狭姫神社へも是非行きたかったのですが、時間の関係で今回は断念せざるを得ませんでした。バスで前を通り過ぎた時にチラッと見ましたが綺麗な神社でした。参拝できなくてとても残念でした。今回は一日でかなり回ったのですが、残念ながら神宮寺と白石神社と若狭姫神社へは行くことができませんでした。何だか「またおいでね。」と言われているような気がしました。若狭は以前から是非一度、行きたいと思っていた場所でした。遠いので、なかなか簡単には行くことはできませんでしたが今回、鵜の瀬や、若狭彦神社などに行けて、満足の一日でした。pleさんの故郷ですよね。素敵な故郷をもっておられて羨ましいです。若狭を意識するようになったのはpleさんのブログがきっかけでした。実際に行ってみて、また行きたくなってしまう素晴らしい場所でした。しばらく若狭の余韻に酔いしれていたいと思っています。
2009.02.21
コメント(8)
-

鵜の瀬
小浜市にある遠敷川はまたの名を、音無川とも鵜の瀬川ともいいます。上流は根来川ともいうそうです。小浜市域を流れる北川の支流です。国分で松永川を合わせて北川に合流しています。遠敷川というのは谷口近くに鎮座する遠敷明神によるものだそうです。鵜の瀬、根来は上流の淵・集落、音無しは神域の深い木立の中を流れる豊かな水量によるものなのだそうです。また、遠敷川は「小丹生川」から来ているとも言われています。最近の発掘で“丹”が出たのだそうです。大仏などを作る時の丹を使う時に水銀が使われ公害が出たのでしょう。その水銀の被害を仏の力で救おうとも考えたのだとも言われています。奈良の二月堂で行われる「お水取り」に先立ち行われる「お水送り」が行われるのが「鵜の瀬」です。その昔、鵜の群が遊んでいたというのでこの名称が付いたといい、奈良・東大寺二月堂のお水取りは若狭井の水源地として知られています。(鵜の瀬から奈良に水が流れているという事です)毎年3月2日、この鵜の瀬で行われる”お水送り”の香水は、鵜の瀬の水が奈良へ送られ、10日かかって送られ、3月12日に「お水取り」がおこなわれます。 関西では“お水取り”が終わると春が来ると言われていますが、若狭地方では”お水送り”が終ると春が来るとされているのだそうです。「お水送り」はこの「鵜の瀬」と「神宮寺」でおこなわれます。約二百人が松明を持って練り歩くのだそうです。小石を積むと良いらしいと聞いて、みんな一生懸命小石を積んでいます。雪解け水がごうごうと音を立てて流れています。川が少し曲がって瀬になっているところにしめ縄がかかっています。お水送りの時には、見物人が川のこちら側にいると僧侶が閼伽井戸から汲んだお水を持って川の向こう岸で川に流すのだそうです。そのお水が奈良の東大寺二月堂に届くのだそうです。僧侶たちはどうやって川の向こう岸にいるのか気になったので聞いてみると、当日は仮橋を作ってあってそれを渡って向こう岸に行くのだそうです。私も、そのお水送りを見てみたいと思ってしまいました。小さな祠がありました。参拝しておきましょう。本当はこの近くの白石神社へも行きたかったのですが、時間の都合で次の目的地へと急がなければなりません。最後の目的地は若狭彦神社です。少しづつ日が落ちてきています。急がなければいけません。さて、どんな神社なのでしょうか。ご祭神の天津彦火火出見尊(山彦)様に会えるのかと思うと、ちょっとワクワクしています。
2009.02.20
コメント(10)
-

お水送りの「神宮寺」
神宮寺に着きました。奈良東大寺修二会(お水取り)の「お水送りの寺」として知られています。東大寺二月堂下の若狭井の水源は根来川の鵜の瀬であるとされ、毎年3月2日には送水神事が行われています。下根来八幡で山八神事を行い、ついでこの神宮寺で修験者の修二会、達陀(内護摩)行法、鵜の瀬で送水文を読み、水切り神事を行って、香水を流すのだそうです。また、ここから近くの若狭彦・若狭姫両神の神宮寺となっています。ずーっと続く参道がすごく素敵なのです。とても気持ちがいいです。この参道の正面に入口があります。門が閉まっています。看板に何か書いてあります。残念です。お水送りの準備のためここから中へ入ることが出来ないのです。玄関の前で参拝させて頂きました。それにしても、せっかく来たのにショックです。諦めきれない私は、木の門の隙間から除いてみました。神様、やんちゃな行為お許しを。あっ、見えました。芝生の前の素晴らしい本堂です。横に回ると、少しだけ見えるのでみんな背伸びして一生懸命見ています。一日違いでとっても残念でした。本当は、『閼伽水』も見たかったな。でも、雰囲気だけでも味わえてよかった。ところで、「若狭神宮寺の由来」には、このあたりの地名が韓国語に由来を持つという話を聞きました。ワカサ→ワカソ(韓国語で行ったり来たり)つまり、日本と朝鮮を結ぶ窓口奈良ナラ→ナラ(韓国語で国の意味)根来ネゴリ→ネ コーリ(韓国語で私のふるさと)この地方を切り開いたのが若狭彦。その子孫は和氏。(もしくは私氏の誤りではないかという説もあります。)紀元前、銅鐸を持った先住民がナガ族(長尾明神)。神宮寺はその2つの神を祀っている。先住民ナガ族を、渡来系の若狭彦が滅ぼし、この地方の主になったのではという人もいます。どちらにしても、当時は先進国である朝鮮半島からの入口であったのは間違いないようです。海を渡ってきた文化や技術が若狭を通って奈良や京都の都へ運ばれたのかも知れませんね。そういえば、奈良や京都から一番近い海がこの辺りです。美味しい海産物も、鯖街道を通って都へ運ばれたのでしょうね。さて、このあと、次の目的地である2キロ先の鵜の瀬へ向かいました。
2009.02.19
コメント(4)
-

明通寺
午後からは楽しみがいっぱいです。まずは明通寺です。お寺へ入るところに橋がかかっています。この日は、温かく6月なみの気温だそうです。川は雪解け水で流れが急です。明通寺(真言宗御室派)は桓武天皇延暦のむかし、征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷征伐において失われた敵味方の霊を慰めるため、平城天皇大同元年(806)に創建されたと伝えられています。鎌倉時代建立の本堂と総高22mの三重の塔はいずれも国宝です。幾星霜を経て存在する荘厳なたたずまいを感じます。本堂は入母屋造桧皮葺の建物です。本堂には木造薬師如来像や木造深沙大将立像、木像造降三世明王立像、木像不動明立像など、平安後期の仏像4体が重文となっています。延暦のむかし、この山中に大きなゆずり木があり、その下に不思議な老居士が住んでいました。たまたま坂上田村麿公が、ある夜、霊夢を感じ、老居士の命ずるままに天下太平、諸人安穏のため、このところに堂塔を創建し、カヤの木を切って、薬師如来、降三世明王、深沙大将の三体を彫って、安置したと言われています。薬師如来坐像は昔は秘仏で33年に一度しか御開帳しなかったのだそうですが、今の御住職様が、たくさんの方に見ていただきたいということで今ではいつでも見ることが出来るようになったようです。薬師如来の右手にある、降三世明王立像は躰幹部を1材より彫出し、背刳りを施し背板をあててあります。大自在天と烏摩妃は横1材より彫出し、本躰はその背上にほぞを立てます。平安後期の像であるために、刀法は肉取りも穏やかであり、彫りも比較的浅く平明で、密教仏特有の難解な感じはないが、堂々たる大像です。また、薬師如来の左手にある深沙大将立像のすさまじい異様な形相は像容に迫力があり、密教仏らしい神秘さを堂内に漂わせています。この 沙大将立像が『西遊記』の河童の沙吾浄のモデルになったのだそうです。不動明王立像は彫りの深い卷髪より左肩に弁髪を垂れ、目はわずかに天地眼とし、右手に宝剣を執って腰に構え、左手を垂下して羂索を執り、条帛、短裙をまとい、岩座上に直立する動きの少ない穏やかな姿勢の像です。三重塔は桧皮葺木造三重塔婆和様でよくまとまった優美な塔として知られています。山号は創建当初棡木で本尊薬師如来を彫ったところから棡山というのだそうです。カヤの木(市指定天然記念物)太さ3.2メートル 樹齢約500年 だそうです。楠は大きな木になりますが、カヤでこの大きさはとても珍しいと思いました。実際にここへ来るまで、明通寺というお寺があることは知らなかったのですが、実際に来てみて凄いところだなと思ったのでした。このあと、私の一番の目的地でもある神宮寺、鵜の瀬、若狭彦神社へ行ったのでした。
2009.02.18
コメント(0)
-

小浜公園 後瀬の山 (山川登美子と与謝野晶子)
小浜公園に着きました。ここから見える海は綺麗で潮風が心地よいです。小浜公園には、山川登美子さんの歌碑があります。『 髪長き少女とうまれしろ百合に 額は伏せつつ君をこそ思へ』山川登美子は大阪・梅花女学校に学ぶころから与謝野鉄幹に師事し雑誌「明星」に投稿。大阪の鳳晶(のちの与謝野晶子)とは良きライバルといわれています。さて、山川登美子とはどんな女性だったのでしょうか。登美子は明治12年7月、現在の千種一丁目旧小浜藩士山川家に生まれました。山川家は旧小浜藩酒井家に仕えた家柄で、父禎蔵は第二十五国立銀行の副頭取の職にあったと言われています。厳格な父のもと経済的にはめぐまれた家庭に育ち、少女時代より和歌に親しみ、大阪に嫁いだ姉宅より梅花女学校に通学し、卒業後も梅花女学校の研究生となって英語を学ぶ傍ら、女流歌人として活躍しました。『明星』を舞台に晶子とその才能を競い、与謝野鉄幹をめぐっても昌子と恋のライバルであったのはこの時期のことでした。しかし登美子は明治33年、父が決めた山川本家の山川駐七郎と結婚し、いったんは歌の道から離れるものの、僅か2年で夫駐七郎と死別し、翌年実家に復籍します。その後上京し日本女子大学英文科に学び、再び『明星』を舞台に活躍。晶子と増田雅子との共著「恋衣」を刊行し高い評価を受けるが、間もなく夫からの感染とおもわれる結核に侵され、大学も中退し、暫く京都の姉宅で療養生活を送りました。しかし、父貞蔵が病に倒れたため、41年1月姉とともに看病のため小浜に戻るが、その甲斐なく禎蔵は24日に死去、登美子もそのまま実家で闘病生活に入り、明治42年4月25日、 母と弟に看取られ29才の若さで短い生涯を終えたのでした。お金持ちのおうちに生まれ、厳しい父の元で育てられ、好きな人が出来ても父の決めた人と結婚しなければならなかったのですね。その結婚も夫が結核で2年で終わりをつげます。しかも、その夫から病を写され自身もわずか29才の若さで亡くなってしまいまうなんて。白百合のような奥ゆかしい少女が、額を伏せつつ好きな人を思っている様は、まさに彼女が鉄幹に思いを寄せつつ、愛に走れずに耐え忍んでいるそのものだったのかも知れませんね。清楚哀婉で、激しい情熱を底に秘めた自己抑制の気品漂う登美子。一方、鳳(与謝野)晶子は皆様もご存じのとおり、登美子とは正反対の奔放華麗な情熱家でしたね。晶子は大阪府堺市甲斐町で老舗和菓子屋「駿河屋」を営む、父・鳳宗七、母・津祢の三女として生まれました。女性の官能をおおらかに謳う処女歌集『みだれ髪』や『明星』に発表した『君死にたまふことなかれ』有名ですよね。子だくさんだったが、鉄幹の詩の売れ行きは悪くなる一方で、彼が大学教授の職につくまで夫の収入がまったくあてにならず孤軍奮闘しました。来る仕事はすべて引き受けなければ家計が成り立たず、歌集の原稿料を前払いしてもらっていたといいます。多忙なやりくりの間も、即興短歌の会を女たちとともに開いたりし、残した歌は5万首にも及びます。『源氏物語』の現代語訳『新新源氏』、詩作、評論活動とエネルギッシュな人生を送り、女性解放思想家としても巨大な足跡を残しました。山川登美子、与謝野晶子共に素晴らしい感性をもった歌人でしたね。さて、与謝野鉄幹は一体どちらをより深く愛したのでしょうか。私が思うには、たぶんそれは同じくらいだったのではないでしょうか。ただ、登美子に比べて晶子の愛情はストレートで一生懸命だったのでしょうね。だから、鉄幹は奥様と別れてまで晶子と結婚したのではないでしょうか。ところで、世の男性方は登美子と晶子、一体どちらがお好きなのでしょうか。昭和の男性は登美子のような奥ゆかしい大和撫子を好んだかも知れませんね。でも、平成の今の時代は案外、晶子のような引っ張って行ってくれるような女性が人気があるのでは…。などと色々想像してみたりしてしまいました。次は↓山川登美子の歌碑のすぐ後ろに見える後瀬山(のちせやま)のお話です。後瀬山は枕草子に「山はみかさ山・おくら山・のちせ山…」と並び称される名山なのです。万葉の歌人、坂上大嬢は 『かにかくに人は言ふとも若狭道(わかさじ)の後瀬の山ののちも逢はむ君』と、燃える思いをこう詠みました。すると、大伴家持は『後瀬山のちも逢はむと思へこそ死ぬべきものを今日までも生けれ』と返したのです。とやかく人は噂しても後にはきっと会いましょうね。と、こんな風なことでしょうか。すると家持は言葉では会いましょうと言っても本当はお会いにならないのではないでしょうかなどと言っていますね。当時、大伴家持には奥さんがたくさんいたのですね。そのうちの一人である大伴坂上大嬢はまだ若く、どのくらい家持と心がつながっていたのでしょうか。ところで大嬢は本当に後瀬山を見たことがあるのでしょうか。“あなた”の心を言うために、「後瀬の山」を「後(のち)」を引き出す序としていますね。一方、家持も「後瀬山」を「後」にかける枕詞に使っています。都人の粋な言葉遊びだったのかも知れませんね。とはいえ、後瀬山は京都と小浜を結ぶ大事な街道沿いにあり山としてよく知られていたのでしょうね。四月ともなると椎(しい)の若葉は黄金色に輝くといいます。後瀬山は若狭を代表するみやぴな山なのですね。すぐ横の山に登ってみました。山から見た若狭湾も良いものですね。このあと私達は、フィシャーマンズワーフというところで昼食を頂きました。若狭の海の幸を存分に味わったのでした。フィシャーマンズワーフでは、pleさんお勧めの小鯛寿司も頂きました。「どんだけ食べるねん」というくらいいっぱい食べてしまいました。鯖街道を行き来したであろう鯖寿司ももちろんお土産に買って帰りました。それから、pleさんに若狭のお箸のことも聞いていたので楽しみにしていました。家族全員の分を買いましたよ。もうすでに使っていますが…。若狭の塗は良いですね。貝の入ったのも綺麗です。近くの『孫兵衛』へは行く時間がなくて残念でした。次に来る時はもっとゆっくりと来たいな、なんて思ってしまいました。このあと、明通寺、神宮寺、鵜の瀬、若狭彦神社です。一日で盛りだくさん。めっちゃ楽しいです。(*^_^*)
2009.02.17
コメント(4)
-

若狭国分寺跡
東小浜駅の南東に若狭国分寺跡があります。聖武天皇の発願で741年に建てられました。遠敷川と松永川に挟まれた三角州をなす、極めて不安定な遺体に立地、造されています。現在は寺域の中心に曹洞宗国分寺が所在しています。釈迦堂は旧金堂を縮小して建てられています。 昭和47年~49年の発掘調査では、規模は218メートル四方、伽藍配置は南大門・中門・金堂・講堂を軸線に配置し東に塔を置く通常の形だったのだそうです。 若狭地方最大の古墳もありました。径45メートルで、国分寺古墳と名づけられています。古墳の頂上には神社がありました。 裏には、建物跡がありました。 この日はあったかかったせいでしょうか、梅が咲いていました。 鳥居に若狭姫神社と書いてあります。あっ、ここが若狭姫神社だ!!と喜んだのですが、実は違っていたようです。 階段を上がって古墳の頂上に小さな社がありました。本当の若狭姫神社はここからもう少し西にあるようです。鵜の瀬、から遠敷川沿いに神宮寺、若狭彦神社、若狭姫神社とつながりその東にこの国分寺跡があります。さて、次は小浜湾にある小浜公園の方へ向かいました。
2009.02.16
コメント(4)
-

白髭神社
滋賀の白髭神社へ行ってきました。今回のコースは白髭神社→若狭国分寺跡→小浜公園→明通寺→神宮寺→鵜の瀬→若狭彦神社というものでした。今回の一番大きなテーマは『若狭のお水送り』だったのですが、若狭へ行く途中に滋賀の白髭神社へ立ち寄ったのは大正解でした。京都からバスで湖西をずーっと走っていると琵琶湖の中に鳥居が浮かんでいます。その鳥居の道路を挟んで反対側が白髭神社です。祭神は白髭明神・天孫降臨の道案内をされた猿田彦命です。垂仁天皇25年の創祀といいます。聖武天皇の御代に比良明神が白髭の翁の姿で現れ、良弁僧正にあったのを祀り、社名もこれにちなむといいます。天孫降臨は天照大神と須佐之男命の誓約で天照大神の玉から生まれた五王子の正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命でしたが、その子、天津日高日子瓊々杵(ニニギノ命)命が父神の意向で向かいました。そこでヒコホノニニギ命が天からお降りになろうとすると、途中、道が幾つにも分かれた天の辻に一柱の神がおり、上は高天原を照らし、下は葦原中国を照らしていた。アマテラス大御神とタカギ神はアメノウヅメ命に向かい「お前はか弱い女ではあるが、敵の神に向かって勝つ神である。行って『我が御子の天降る道をこのように塞いでいるのは誰か』と問うてこい。」と仰せられた。アメノウヅメ命がその通りにお尋ねになるとその神は「私は国つ神で猿田毘古神(さるだびこのかみ)と申します。こうして出ておりますのは、天つ神の御子が天降り遊ばれると聞き、御前に仕えしようと存じ、お迎えに参った次第であります。」と申した。その時の猿田彦命様がここのご祭神なのです。猿田彦命はのちに、この出会いがきっかけで天宇受売神(アメノウズメ)と伊勢の地で夫婦となったのでした。ちなみにアマノウズメとはアマテラス大神が天岩戸に御隠れになった時に楽しい踊りを踊って、岩戸からお出になるきっかけを作った神様です。ところで、↓本殿屋根は方三間・入母屋造・檜皮葺、秀頼建造で重要文化祭とのことでした。↓は白髭若宮です。右の階段を登ると紫式部の歌碑がありました。「三尾の海に/網引く民のひまもなく/立居につけて/都恋しも」(紫式部)入口には松尾芭蕉の歌碑もありました。「四方より/花吹入れて/鳰の湖」(松尾芭蕉)本殿の横には、与謝野晶子の歌碑もありました。「しらひげの/ 神の御前にわくいずみ /これをむすべば/ 人の清まる」(与謝野寛・晶子)湖に浮かぶ鳥居の景色にひかれ、昔から多くの人が訪れたのですね。お天気も良く、とても気持ちのいい神社でした。さて、私達は次の目的地、若狭小浜へと向かったのでした。
2009.02.15
コメント(6)
-

纒向遺跡
さて、前回は三輪さんの麓の纒向の江包の泥相撲のお話でした。実は、このお話ちょっとしたエピソードがあります。古代の相撲といえば野見宿禰と当麻蹴速を思い浮かべる方は多いと思います。野見宿禰は出雲から来たということですよね。実は面白いことに、ここ江包の昔の地図を見てみると、この辺りは「出雲荘」という地名だったことがわかります。それから、桜井の方にも「出雲」という地名があるのですよね。桜井の人は野見宿禰が住んでいた出雲は桜井のことだと言う人もいるのだそうです。私も、その考えには一理あるのではと思っています。古墳の古さからいえば、、出雲→大和→河内の順のように思えます。大国主命信仰は弥生時代中期にあたる2世紀半ばに作られたと言われています。弥生時代には、北九州と大和が先進国であったと考えられていますが、出雲の荒神谷遺跡は古代の信仰や文化が出雲から広がったことを明らかにしています。荒神谷遺跡の約30年後に北九州で邪馬台国が栄え、さらにその30年後に大和朝廷が誕生したと考えている学者もいるようです。出雲の神様は北九州や、大和に受け入れられてその土地の神様と融合して行ったのではないかと思うのです。三輪山麓でも、出雲の神様が大和に入ってきて、大和の土着の神様とくっついたのではないかと思っているのです。出雲の、大国主命が大和の土着のオオモノヌシの神様と。そして、後に天皇家が中央集権化しようと思った時に、他の豪族と天皇家の差別化を図るために、大国主命の上に天皇家の神様である天照大御神を置く系譜を作ったのではないかと思ったりしています。だから、出雲という地域は大和にもあったのではないかと思うのです。私は桜井にあった出雲から野見宿禰が来たのではという説はとても面白いなと思うのです。もちろん、これは私の勝手な想像です。古代ははっきり分からないことが多いので、いろいろ勝手に想像できて楽しいですよね。|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆さて、話は元に戻しますね。『お綱祭』を見たあと、纒向遺跡の方へ歩き出しました。素盞鳴尊神社から、巻向駅へ向かう途中に古墳が四つあります。東田大塚古墳→矢塚古墳→勝山古墳→石塚古墳→巻向駅のコースです。まずは、東田大塚古墳です。三世紀後半・末の古墳で、円休憩が70メートル突出部分が50メートルあまり、全長120メートル余りです。箸中型に近いとのことです。遺構が掘られています。次は、矢塚古墳、勝山古墳、石塚古墳と続きます。↓矢塚古墳↓勝山古墳↓石塚古墳石塚古墳の遺構の向こうに見えるのが「巻向駅」です。矢塚古墳、勝山古墳、石塚古墳は三つがくっついて存在しています。そして、そのちょうど真ん中に纒向小学校があります。というか、古墳を避けて小学校を作ったというのが正解のようです。小学校の校庭の下には「人」の字型に古代の水路が出てきました。その水路は大和川の方から来ています。そして、一方は箸墓に向かって続いていて、もう一方は市杵島神社の方向へ向かっています。当時は、この辺りに水路が張り巡らされていて、主要な場所を結んでいたのだということです。お水というのは生活の中で大変大事なものです。そして、物を運ぶのにも水路を使ったのだと言うことです。3世紀というと卑弥呼の時代か台与の時代でしょうか?太古にこの辺りでは一体何があったのでしょうか?謎は謎をよびますよね。さて、↓は辻地区の祭祀土坑群が出土した場所です。ここから、多くの土器や木製品などが出てきたようです。土坑の中に納めら得ていた祭具は後の『延喜式』新嘗祭の条の器材と共通点が多いため、一種の「ニイナメオスクニ儀式」が行われていたものと考えられているのだそうです。纒向は本当に古い時代の古墳です。太古の昔のままの姿を残しているものもあるようです。地元の方の努力は並大抵ではないとは思います。最近色々、調査がなされているようですが、いろいろなことがもっといっぱい分かると良いですね。でも、なるべく破壊されずにそのままの姿を後世に残していけたらななどと考えてしまいました。
2009.02.11
コメント(0)
-

お綱祭2 (泥相撲・神様のお嫁入り)
当日を間近に控えた2月9日江包の氏神を祭る春日大社で、地区の男らが男綱を作ります。重さは、約700kg一方、大西地区では翌10日の午後、市杵島神社境内で女綱を作ります。重さは1トン以上。男綱(素盞鳴尊)の翌日に女綱(櫛稲田姫)を作るのは男綱の大きさに合わせるためだそうです。11日午前8時、市杵島神社の女綱は約一キロ離れた素盞鳴尊神社へと向かいます。同じころ、江包では、男たちが春日大社から男綱を引き出し素盞鳴尊大社へ向かうのですが、途中大和川にかかる橋の辺りで、泥相撲を観戦するのです。泥相撲は神様に奉納されるのです。↓今から相撲の始まりです。はきょよい、のこった、のこった。江包の泥相撲は体についた泥の量が多いほど豊作と言います。時々、ホースで水を足して、ドロドロにしてもう一番。このお相撲は、日本で最も古いお祭りで行うお相撲です。神様も、喜んでおられるのでしょうね。さて、お相撲も終わり、そろそろお綱のお嫁入り、結婚式です。男綱が運ばれてきました。凄い迫力です。素盞鳴尊神社の鳥居の前に取り付けられた女綱のところへ男綱がドッキングです。はい、完成しました。このお祭りの完成型は実は男綱と女綱がまぐわる姿。契は深く、さながら一つの塊となって夫婦の契りを見せつけています。「神さんが嫁入りするから」と今も江包と大西の両大字間での婚姻はないのだそうです。江包地区長の城内彦一さん(63歳)は「これだけ自由な世の中で今も縁談がないのは、ここに生まれた限りそうしなければならないという意識が人々の間に生きているから」とおっしゃっていました。古代から今までに、何組の好き同士でありながら結ばれることのないカップルがいたのでしょうね。このあと、私達は纒向遺跡に行って二上山博物館長の石野博信先生にお話を聞きました。実は先生は25年くらい前に初めてこの『お綱祭』を見たのだそうです。今と全く同じようにお祭りは進められていたのですが、一つだけ違うことがあったのだそうです。当時は、あるお婆さんが祭りの最中にずーっと大きな声で『卑猥』な歌を歌い続けていたのだそうです。先生は、「あ~、これこそまさにアマノウズメ命だ!!」と感動して、論文に書いて発表しようと思ったのだそうです。そして、なにげなく、地元の人に「あのお婆さんはどなたなのですか?」と聞いたのです。先生は、何代も続いた由緒ある家柄のお婆さんだと思ったのでしょう。すると、帰ってきた返事がこうでした。「さあ、誰でしょうね。この辺の人は誰も知らないのですよ。毎年お祭りになると、大阪の方からふらっと来ているみたいですよ」え~っ、そうなの。先生もびっくりしたそうです。そして、論文として発表しないでよかったとほっと胸をなでおろしたそうです。それにしても、なんと大らかな村人たちでしょうね。
2009.02.09
コメント(6)
-

お綱祭り1 (素盞鳴尊神社、市杵島神社)
桜井市の纒向駅から歩いて15分くらいのところに、素盞鳴尊神社(江包)と市杵島神社(大西)があります。↓後ろに見えるのは三輪山です。ここでは、子孫繁栄、五穀豊穣を願う「お綱祭」というのが大昔から行われています。もともと二月十日(旧暦の正月十日)に営まれていましたが、会社勤めの増えた最近は二月十一日に行われています。お綱祭りでは、男綱には素盞鳴尊、女綱には櫛稲田姫が宿るといわれています。二神は三輪山麓に仲良く祭られていたが、洪水のため素盞鳴尊が江包(えっつみ)に、稲田姫は大西へ流されたという伝承が地元にあり、再び結ばせたのがこの祭りの始まりと言われています。↓は春日神社にある男綱です。大西の市杵島(いちきしま)神社境内に摂社御綱神社があり、女綱はここから運ばれてきます。江包の素盞鳴尊神社に運ばれてきました。↓は素盞鳴尊神社です。本殿にはお供え物が置かれてあります。市杵島神社から運ばれてきた女綱は素盞鳴尊神社の男綱を待っています。↓は到着した女綱を取り付けているところです。女綱の取り付け完了です。あとは、男綱を待つばかりです。でも、すぐに結婚式が始まるわけではないのです。素盞鳴尊神社からの男綱は道中、成人式や泥相撲を観戦したりします。ここの泥相撲は凄いです。以前、『世界ふしぎ発見』という番組で、クイズになったそうです。「日本一古い、相撲のあるお祭りはなんでしょう」というものです。もちろん答はここのお綱祭りです。さて、日本一古いお相撲と素盞鳴尊と櫛稲田姫の結婚式、うまく行ったでしょうか。この続きは、次回ということで…。良かったら見て下さいね。
2009.02.08
コメント(4)
-

二月堂と東大寺
春日大社は何度も行っているので今回は、前を通り過ぎて二月堂の方へ行くことにしました。私の母は、私が子供のころ良くこんなことを言っていました。「冬は寒いけど、関西ではお水とりが終わると春が来るのよ。」とか、「奈良ではお坊さんが一番寒い時期に修行をしてくれるのよ。」とか、「寒いのに、お坊さんがお水取りをしてくれるから春が来るのよ。」などと冬になれば何度も聞いた言葉でした。それで、子供のころ私は本当に、こんな寒い時に冷たい水の中で修行をしてくださるお坊さんのおかげで春が来るんだと思っていました。ところが、奈良から大阪に引っ越した時は同じように思っていたのですが、和歌山へ引っ越した時に、なんか変だなと思ったのです。和歌山では3月になれば、結構温かくなりお水取りの頃にはもうすっかり春になっているのです。そうか、和歌山は関西ではないのだ。そして、やっぱりお坊さんは関西の人のために寒い冬にお水取りをしてくれているのだ。そう思ったのでした。ところで、奈良東大寺二月堂のお水取りは、21世紀になって2001年で1,250回目を越えたそうです。新たな世紀に回を重ね、奈良時代の開始以来一度も休んでいない。お水取りのおたいまつは、毎年3月1日から14日まで行われます。二月堂と若狭との関係にこんな伝説があります。行法の時、「神名帳」というのを読み上げ、全国八百万の神々を勧請して、行法の無事完了を祈る。ところが若狭の遠敷明神は釣が大好きで、その日も魚釣に熱中していて、ようやく釣をやめて二月堂へ駈けつけた時には、すでに行法が終りかけていた。その行法のあまりのすばらしさに、明神は感激して、遅参を恥じて、おわびのしるしに、「今後は閼伽水をずっと献じましょう」と、仏前で誓った。と、そのとたん、突如として、二月堂の下の盤石を破って、白と黒の鵜が飛び立ち、その跡から甘泉が湧き出した。それを囲ったのが、今の二月堂の閼伽井で、「若狭井」と呼ばれている由来だという。若狭の遠敷明神前の川は、その時から水が涸れたので音無川と呼ぶようになったといわれている。 修二会の儀式「お水取り」の御香水(おこうずい)を汲む井戸がある建物である東大寺二月堂閼伽井屋(若狭井屋)↓のです。じつは、来週若狭へ行く予定になっています。お水取りの二月堂、お水送りの若狭。今年は両方へ行ってみたいと思っているのです。二月堂の上にあがってみました。とても素晴らしい景色です。正面のから見ると、東大寺の屋根が見えます。さて、このあと二月堂を降りて東大寺まで歩きました。728年、聖武天皇が皇太子供養のため建立した金鐘寺が東大寺の始まりです。東大寺といえば、大仏様ですが今回は時間がなかったので前を通り過ぎただけでした。まあ、大仏様には何度もお会いしているので、また今度時間があるときゆっくりと来ることにして、このあと氷室神社の方へ向かいました。
2009.02.07
コメント(6)
-

春日若宮
新薬師寺から、春日大社の方へ歩くことにしました。春日大社の手前に、摂社でもある春日若宮がありました。若宮の祭神は伝承によると、若宮に祀られる神は天児屋根命と比売神の間の御子神です。平安時代の中頃、1003年(長保5年)春日大社の本社第四殿に祀られている比売神の所に小蛇の姿で現れた水の神「天押雲根命(あめノおしくもねノみこと)」です。始めは本社第四殿に比売神と共に祀られていましたが、その後、若宮は本社中央の獅子の間に祀られていましたが、平安時代の末、1133年頃(長承年間)洪水飢饉が相次いだので、これを救済する為、時の関白藤原忠通が水の神である若宮を、1135年(保延元年)2月27日現在地に新殿を造営して遷宮しました。そして、翌年保延2年 9月17日若宮の例祭おん祭り」が始まりました。昔は、若宮に奉仕する巫女と、神楽歌を歌い笛を奏でる神楽男が常駐し、参拝者の祈願に応じる神楽の鈴の音が一日中絶えなかったと言います。大宮と違い、農民をはじめとする庶民に親しまれてきた神様です。摂社ではありますが、大宮と同格の祭祀が行われます。「春日若宮おん祭」(12月17日)では、田楽や猿楽といった華麗な伝統芸能が神にささげられるのだそうです。800有余年絶えることなく、現在も大和の国を挙げての祭りとして盛況を極めているのだそうです。春日大社では、毎月1日、11日、21日には、「旬祭」と称して普段よりも丁寧にお供えして神楽も奏されるのだそうです。また、「春日若宮おん祭」以外に、春日祭(3月13日)にも天皇の勅使を迎えて行われる大宮祭もあり、京都の賀茂祭や石清水祭と並ぶ勅祭のときは、古式ゆかしく執り行われるのだそうです。一度その優雅な様子を見てみたいものです。さて、このあと春日大社の横を通って、二月堂の方向へ歩いて行きました。
2009.02.06
コメント(6)
-

白毫(びゃくごう)寺
新薬師寺から歩いて20分くらい山の方へ登って行ったところに白毫(びゃくごう)寺がありました。白毫寺は天智天皇の第七皇子である志貴皇子の山荘の跡に建てられたと伝えられているようであるが、異説もあるらしいです。門にたどり着きました。壁が少しはがれていますが、それがまた良い味になっているようです。門をくぐり、反対側に振り向くと凄いです。奈良の町が一望できます。素晴らしい景色です。白毫寺は伝によれば、慶雲2年(705)法道仙人により開基されたのだそうです。本尊は天竺から伝えられた言う薬師瑠璃光如来(秘仏)です。その薬師瑠璃光如来の眉間の白毫から神々しく瑞光を放っていたので、「白毫寺」と名付けられたのだそうです。「宝蔵」に入ると、正面に見えるのが本尊の「阿弥陀如来坐像」であす。他には、「地蔵菩薩立像」、「文殊菩薩坐像」、「閻魔王坐像」などがあります。「文殊菩薩座像」は平安時代の作とされ、もと多宝塔の本尊で、白毫寺では最も古い仏像といわれているそうです。白毫寺は花の寺と言われているくらい、季節ごとのお花の素晴らしいお寺らしいのです。本当は、五色椿が有名なのだそうですが、残念ながらちょっと早すぎたみたいです。五色椿は普通の椿よりも遅く桜の季節が一番綺麗なのだそうです。「本堂」の正面南側やや東よりの場所に、周囲を縄で囲われたかなり大きな椿の木「五色椿」の木がありましたが、残念ながらこの季節はまだ花をつけてはいませんでした。この椿の木は寛永年間(1624~44年)に興福寺の塔頭である喜多院から移植したものらしいのです。木は根元から約0.8mのところで幹が二つに分かれており、樹高は約5mあるとされています。この「五色椿」は天然記念物に指定されているそうです。残念ながら、天然記念物の「五色椿」は見られませんでしたが、その近くの椿は少しだけ、花を付けていました。これも、五色椿だと思います。普通の椿も咲いていました。その横には、多宝塔跡がありました。今は跡形もなくちょっと残念ですね。ここは、萩の季節、桜の季節、もみじの季節はもっと綺麗なのかもしれません。季節を変えてまた来てみたいなと思いました。このあと、新薬師寺の方まで戻り春日大社の横の春日若宮神社へと向かいました。
2009.02.05
コメント(2)
-

新薬師寺
元興寺から歩いて20分くらいでしょうか。少し山の方へ登って行くと新薬師寺に着きました。新薬師寺は聖武天皇眼病平癒のため、 天平十九年三月勅願により光明皇后によって建立された名刹です。新薬師寺の「新」は「あたらしい」ではなく「あらたかな」薬師寺という意味なのだそうです。当時東大寺と共に南都十大寺の一つに数えられ、四町四方の境内に七堂伽藍甍をならべ、住する僧一千人と記録にあるのだそうです。宝亀一一年落雷により災上、現本堂のみが焼失をまぬがれ現存し、鎌倉時代には解脱、明恵両上人が一時同寺に住して現在の東門、南門、地蔵堂、鐘楼(各重文)を建立したそうです。この堂の構成は遠くギリシャ建築を偲ばせるものがありまさにシルクロードの終着点と云えますね。本堂の中には、国宝の本堂や奈良時代の十二神将像をはじめ、多くの文化財がありました。御本尊の薬師如来様は母のような慈愛に満ちた御顔をされていました。十二神将像は一体一体それぞれ迫力のある素晴らしいものでした。門を出た所に、神像石がありました。神像石とは、大友皇子・十市皇女から淡海三船までの4代とそれぞれの妃を祀った石です。 神像石の反対側に、鏡神社がありました。鏡神社は、遣唐使派遣の祈祷所だったところに、平城天皇の時代、大同元年(806)に新薬師寺の鎮守として奉祀したのが始まりなのだそうです。また、藤原広嗣は叛乱を起こし、肥後国で斬殺された広嗣の怨霊を鎮めるたま肥前国の鏡神社(唐津市:松浦明神を弘法大師が鏡神社と改名と言う。)から勧請したと言われています。こちらの一の宮は神功皇后、二ノ宮が藤原広嗣です。さて、このあと新薬師寺をあとにして、白毫(びゃくごう)寺へ向かいました
2009.02.04
コメント(4)
-

「ならまち」と元興寺
西の京から近鉄電車に乗って奈良駅に降りました。奈良町を通り、『あしびの里』というところで、ランチを食べました。ここのお料理はめちゃめちゃ美味しい。味付けが絶品なのです。気になった方はあしびの郷を見て下さいね。お漬物も本当に美味しいのです。このお店は、春日大社で結婚式を挙げたカップルが披露宴で使うことが多いみたいです。時々、テレビの撮影で使われていたりもします。とても、感じの良いお店です。お腹がいっぱいになったので、元興寺へ行くことにしました。とちゅうの奈良町は素敵なお店がいっぱいです。お店の前に庚申さんの身代わり猿がつるされていました。庚申さんのお使いの猿を型どったお守りで、災難が家の中に入ってこない魔除けを意味します。これを見ると、ああ「ならまち」に来たなって気持ちになるのですよね。「ならまち」というのは一般に元興寺の旧境内を中心とした一帯を言います。行政地名ではないのですが、江戸時代の末期ことから明治にかけての町屋の面影を今に伝える落ち着いた風情は訪れた人に懐かしさを感じさせてくらます。このあたりは、奈良時代の平城京の区画のうち東部につきでた外京と呼ばれていた場所で、神社・仏閣が多いのです。私達は、元興寺に行ってみました。↓ここが元興寺です。前身は6世紀末蘇我馬子によって開かれた法興寺(飛鳥寺)でしたが、平城遷都に伴い今の地に移転され名も元興寺と改められました。かつては南都七大寺の一つとして威勢を振い、現在の奈良市街の南東部を占めていました。広大な寺域には、金堂・講堂・塔・僧房などが立ち並んでいましたが、平安時代半ば、その勢威も衰えてしまいました。現在では僧坊の一画が唯一現存しています。「元興寺 極楽堂・禅室」は「行基葺(ぎょうぎぶき)屋根」ですが、この行基葺の瓦の中には飛鳥時代創建の「法興寺」の屋根に載せていた瓦、すなわち、1400年も遠い昔に作られた瓦が混じっていると言われております。色のついた瓦がそうなんでしょう。歴史を背負った古い屋根瓦とはロマンのある話ですね。 奈良は歩いていると、いろいろな古いものに出会えて楽しいです。素朴で、町の人も温かいので柔らかな空気に包まれ日常と離れた空間で元気をもらえそうです。このあと、今回の一番の目的地である新薬師寺と、白毫(びゃくごう)寺へと急いだのでした。
2009.02.03
コメント(4)
-

薬師寺
今年2回目の薬師寺です。近鉄西の京駅から歩いてすぐです。門が見えてきました。薬師寺は「法相宗[ほっそうしゅう]」の大本山です。天武天皇により発願(680)、持統天皇によって本尊開眼(697)、更に文武天皇の御代に至り、飛鳥の地において堂宇の完成を見たのだそうです。その後、平城遷都(710)に伴い現在地に移されたのだそうです。空が青くて、建物の赤が綺麗がより一層綺麗に見えます。ちょうどこの辺りで、携帯のバイブがふるえました。見るとpleさんからでした。『薬師寺は今の内にしっかり見ておかないと、東塔が長期間(15年とか)解体修理されるそうです。』なんどgood timingなんでしょう。え~、そうなのですか。それは大変、しっかり見ておかないと。pleさん、いつもniceな情報とアドバイスありがとうございます。m(_ _"m)ペコリうん、↓これがその東塔ですね。塔は本来お釈迦様のお墓を意味します。インドで梵語のストゥーパが音訳されて卒塔婆[そとうば]となり、それが塔婆、更には塔と表現されるようになりました。お釈迦様のご遺骨(仏舎利[ぶっしゃり])を埋葬して盛り土をしたものが原型です。その塔婆を遠くからでも拝めるように、また尊敬の気持ちから、より高い台の上にお祀りするようになったのです。薬師寺東塔は一見六重に見えますが、実は三重の塔です。これは各層に裳階[もこし]と言われる小さい屋根があるためで、この大小の屋根の重なりが律動的な美しさをかもし出し「凍れる音楽」という愛称で親しまれていますこの等々は、薬師寺で唯一創建当時より現存している建物で、1300年の悠久の時を重ねてきた歴史をその姿から感じられますね。その横にあるのが西塔です。塔の連子窓[れんじまど]に使われている色を「青[あお]」色、扉や柱に使われている色を「丹[に]」色と呼び、万葉集の一節にあおによし ならのみやこは さくはなの におうがごとく いまさかりなりと歌われている事からも当時の平城京の華やかさを表現する意味もあったのではないかと思われます。「青丹良し」とは奈良の枕ことばを意味するのです。等々は1300年前に作られましたた、西塔は昭和56年(1981)に復興されたものです。色はもちろん連子窓の有無や屋根の反り、基檀の高さ等、東塔との違いが多く見られまが、まさにその違いこそが1300年という歴史の流れを表しているのです。東塔と西塔の後ろにあるのが金堂です。金堂には薬師三尊像がいらっしゃいます。薬師三尊像(薬師如来・日光菩薩・月光菩薩)は白鳳時代 薬師如来のまたの名を医王如来ともいい、医薬兼備の仏様です。人間にとって死という一番恐ろしいものを招くのが病気です。体が動かなくなるのも病気なら、身の不幸、心の病も病気です。欲が深くて、不正直で、疑い深くて、腹が立ち、不平不満の愚痴ばかり、これ皆病気ですね。今回ちょっと気になったのは、金堂を出ようとした時に裏から見えた薬師如来様の薬師如来台座です。薬師如来が座っておられる台座には、奈良時代における世界の文様が集約されているのです。一番上の框[かまち]にはギリシャの葡萄唐草文様[ぶどうからくさもんよう]その下にはペルシャの蓮華文様[れんげもんよう]が見られるのです。また、各面の中央には、インドから伝わった力神(蕃人[ばんじん])の裸像が浮彫りされています。さらに、下框には、中国の四方四神(東に青龍[せいりゅう]、南に朱雀[しゅじゃく]、西に白虎[びゃっこ]、北に玄武[げんぶ])の彫刻がなされています。正にシルクロードが奈良まで続いていたのですね。私達は、あまりの見事さにしばらく茫然と眼を見張り続けたのでした。それは、写真撮影禁止だったのでもし興味のある方は薬師三尊像と薬師如来台座を見て下さいね。さて、このあと唐招提寺に向かったのですが…。この続きは次回です。
2009.02.02
コメント(4)
-

吾彦山 大聖観音寺 (あびこ観音)
吾彦山 大聖観音寺 (あびこ観音)は我国で最古の観世音菩薩の寺院です。昔、この地に住んでいた依網吾彦(よさみのあびこ)という当時勢力を持っていた一族が、百済の聖明王から身の丈一寸八分(約8cm )の小さな観音像を贈られ、欽明天皇7年(546)に創建しました。その後聖徳太子がこの地に赴いた時に観音菩薩のお告げを受け、りっぱなお寺を建てるように命じ、「吾彦山観音寺」が建てられたと伝えられています。その百済からの観音像が一年に一度だけ御開帳される日が2月1日なのです。地下鉄御堂筋線のあびこ駅からあびこ観音さんまで、参道は露店でいっぱいです。本堂に着きました。まだ、夜が明けきれていないのに朝から人が多く賑わっています。油之不動尊です。昔はこの辺りにアブラナがたくさん植えられていたそうです。当時は油は貴重品、とても大事なものだったそうです。お不動さんに豊作を祈ったとか。この辺りでは節分といえば、あびこ観音様です。毎年2月3日の 「節分厄除大法会」には「聖観音」が開帳され 、年越しの大法会も盛大にとり行われるのだそうです。実は私はこの日は、私達はこのあと奈良へ行きました。あびこ観音→薬師寺→唐招提寺→元興寺→新薬師寺→白毫(びゃくごう)寺→春日若宮神社→春日大社→二月堂→東大寺→氷室神社上のスケジュールを一日で回るという強行スケジュールでした。歩いているときは楽しくて、次から次へと参拝して行ったのですが…。遊びすぎがたたったのでしょうか、翌日グロッキー。しばらく、活動停止状態に陥ってしまいました。なんとか仕事は休まずに続けていますが、家事は手を抜き過ぎ(笑)。今日やっと落ち着いたところです。さて、奈良の楽しかった神社とお寺詣り。ブログの方も少しづつUPしていきたいと思います。良かったら、読んでくださいね。
2009.02.01
コメント(1)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 堺市 金岡町盆踊り大会 大道町大太…
- (2025-11-14 06:08:46)
-
-
-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印
- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 5…
- (2025-11-14 00:00:17)
-
-
-

- 温泉旅館
- 錦秋の東北へ 米沢・白布温泉 湯滝の…
- (2025-11-13 06:46:38)
-