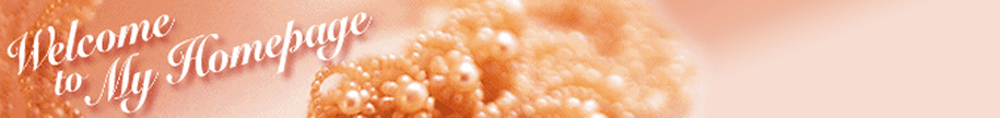2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009年03月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

天岩戸神社西本宮(宮崎・高千穂の旅8)
ついにやってきました、念願の天の岩戸神社です。天の岩戸神社には、西本宮と東本宮があります。一般に天の岩戸神社といえば西本宮になり、東本宮は信仰の神社といわれています。まずは、西本宮に行っていました。入口で、天の手力男さんがお出迎えしてくれました。鳥居をくぐって境内に入って行きました。受付に申し出ると神社の方が案内してくださいます。↓が拝殿です。神社の方にお祓いをしていただいて右の戸から中へ入らせて頂きました。ここからは写真撮影は禁止です。みんなでぞろぞろと付いて入り少し歩くと、木でできたバルコニーのようなところに着きます。そこで説明を受けたのですが、そこから見えるところに天の岩戸があるのです。古くて半分朽ちているのだそうですが中に天照大神さまが御隠れになった岩戸があるらしいのです。私には遠くてはっきりは見えませんでしたが、そう言われてみると確かに…。拝殿を出ると再びさっきの境内に戻りました。↓の木は「招魂の木」といって天照大神が天岩戸に御隠れになり、アマノウズメが踊りを踊っていた時に手に持っていた鈴がこの木の実のなる形を原型にしたものだったのだそうです。詳しいことは看板に書いてありました。神楽殿です、ここで神事の時神楽を舞われるのだそうです。境内を出て、天の安河原の方へ向かいました。歩いて10分くらいのところです。まさに、私が絵本で見たのと同じ風景です。でも、この日はちょっと人が多くて写真に人を入れないなんてことは無理のようです。厳かな、神々しい雰囲気が漂っています。天の安河原には来る人が石を積むのだそうです。その数はやっぱり、『七』か『五』か『三』がいいのだそうです。神様の数と同じですね。天の安河原でゆっくりした後、天岩戸神社東本宮に向かいました。
2009.03.30
コメント(2)
-

弘川寺 西行法師終焉の地
桜の季節です、西行法師の終焉の地である弘川寺へ行ってきました。今回で3度目です。満開というには少し早すぎたかもしれません。でも、境内の『隅屋桜』は見事に咲いてくれていました。弘川寺は天智天皇の四年、役行者によって開創され、天武、嵯峨、後鳥羽、三天皇の勅願寺で、本尊は薬師如来です。本堂を見下ろす場所に西行堂がありました。西行堂は、江戸中期、西行を慕って広島よりこの地を求めた歌僧似雲によって建立されたそうです。晩年の西行はこのあたりで起居し歌を詠み暮らしたのでしょうか。西行は29歳で陸奥へ旅立ち、その後高野山に入り30年ほどを高野山で過ごし、この間に京都、吉野、四国などに足を向け、多くの歌を残しています。西行は、うらうらとした気持ちで死にたいと願って生きていたのだそうです。少しでも心に濁りがあるとそれは叶わない。そして、年を重ね、 “花よりは命をぞなお惜しむべき待ちつくべしと思ひやはせし”命あればこそと、感慨に耽る西行。いつしか弘川寺で、おいて行く一本の桜と自分の人生をかさねあわせたのではないでしょうか。また、西行は63歳のときに高野山から伊勢に移り、東大寺再建の勧進のため、再び陸奥に旅立ちました。そして、陸奥の旅から帰った西行はここ弘川寺に入りました。 “願わくは 花のしたにて春死なむ その如月の望月のころ”翌年、西行は自ら詠んだ歌の通り、この地で73歳の生涯を閉じました。文治6年(1190)2月16日(旧暦)。奇しくも釈迦が入滅し、空海が入定した同じ日だったそうです。如月の望月のころ…とは…、研究されていて新暦の3月29日にあたるそうです。もちろんその日は、ここ弘川寺の桜も満開であったのでしょうね。広場の片隅に似雲墳がありました。西行庵跡です。つつじが咲き乱れています。この辺りはかなり高台になっています、見晴らしがとても素晴らしいのです。実はこの辺りで、一人の方に出会いました。その方は、西行法師の弟さんの直系のご子孫の方でした。西行法師は子供さんがいなかったので、弟さんの子孫の方が後を継がれているのだそうです。今日お会いした方は、西行法師さんについて色々なことを教えて下さいました。西行さんも出家前は、武士であったとか。そして、源氏と平家の間で政治的にご苦労されたとか…。西行法師さんが桜を愛したのは、実は桜を思い人と重ねていたのだとか…。西行法師さんは実は、情熱かであったとか…。宇陀郡にある又兵衛桜の又兵衛さんは、実は西行さんと親戚だとか…。もっともっとお話を伺っていたかったのですが、時間がなかったのでそこまでで御別れしました。西行さんのご子孫のその方は、とても上品で素敵な方でした。丁寧に色々教えてくださってありがとうございました。このあと、河南の道の駅でお買い物をして帰ったのでした。今日はサンチェを一つ買ったら二つおまけでくれたのでした。とてもびっくりでした。ブロッコリーもとても新鮮そうでした。御店の方、本当にありがとうございました。夕飯で食べたらおいしかったです。良いお天気でしたが、桜にはほんの少し早かったかもしれません。来週か再来週が一番綺麗かも知れません。御近くへお寄りの方は是非そのころでしたらお立ち寄りくださいね。きっと、凄く綺麗だと思いますよ。
2009.03.29
コメント(6)
-

真名井の滝 (宮崎・高千穂の旅7)
延岡からバスに乗って、高千穂町に着きました。まずは、知事さんがお出迎えです。ホテルに荷物を預けてタクシーで高千穂峡の方へ行くことにしました。高千穂峡は古阿蘇火山活動のときの溶岩流が五ヶ瀬川にそって帯状に流れだし急激に冷却したため柱状節理の素晴らしい懸涯となった峡谷です。ここには、七つ池と呼ばれる欧穴や真名井の滝が懸っています。真名井の滝です。ボートに乗ろうと思って切符売り場に行くとものすごい人で、2時間待ちでした。そんなに待ってはどこへも行くことが出来ないので、泣く泣くボートは諦め、遊歩道を歩くことにしまいした。遊歩道を歩くと、きれいな景色で「なんだ、ボートよりこっちの方が良かった。」なんて思ってしまいました。『おのころ島』がありました。昔この池のには神社があり、鵜の鳥はこの神社に仕える神聖な鳥であったと伝えれられています。高千穂神社の春祭では、御神幸のお神輿がこの池を三度まわって禊をされます。鬼八の力石(重量約200トン)です。高千穂神社のご祭神三毛入野命(ミケイリヌノミコト)は弟の神武天皇と共に大和に行かれますが、伝説では再びお帰りになり、高千穂峡一帯で悪行を働いていた鬼八を退治し、この地を治めたと言われています。この時の、鬼八が三毛入野命に投げ、力自慢をした石といわれています。石には注連縄がかけられています。気を付けて良く見ると注連縄は左から『七・五・三』になっています。実は高千穂では、どの神社でも注連縄はこのようになっているのです。『七』は神代七代 :伊邪那岐神(いざなぎのかみ)・伊邪那美神(いざなみのかみ)をはじめとする七代の神様です。 『五』は天神五代(地神五代) :天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日上、宇摩志阿斬訶備比古遅神、天之常立神。『三』は日向三代 :「高千穂皇神(タカチホスメガミ)」の瓊々杵尊尊. 彦火火出見尊. 鵜茅草葺不合尊を表しこのようになっているのだそうです。ちなみに、高千穂町ではどの家も玄関に注連縄が一年中かけられています。毎年、大晦日に掛け替えるのだそうです。仙人の屏風岩(高さ70メートル)です。対岸に広がる屏風風の岩を仙人の屏風岩というのだそうです。これは凄いです、写真では伝えきれませんが実際に目で見ると圧倒される凄い迫力です上流の新橋付近から下流の真名井の滝のボート乗り場付近までが自然の造形美の美しいところです。昭和9年に付近一帯が「名勝天然記念物」に指定されています。写真では大きさは分からないと思いますが、目の前に迫る凄い迫力です。山を良く知っている先輩もここばかりは、感動していました。遊歩道を歩き川沿いに下りました。自然の美しさに目を見張るばかりでした。このあと、タクシーで天の岩戸神社へ向かいました。この続きは次回です。
2009.03.26
コメント(4)
-

神武東征の美々津 (宮崎・高千穂の旅6)
3日目は霧島神宮駅から、JRに乗って南宮崎で乗り換えて延岡、そして、延岡から、バスで高千穂へ行きます。まずは、霧島神宮駅です。何と、この駅には鳥居があるのです。3時間に一本くらいしか電車がないのです。予定の電車が来るよりも随分早く駅に来てしまったので、時間をつぶすために近くを散歩することにしました。駅の近くに赤い橋がありました。そして、その上に猿田彦さんがいらっしゃいました。旅の道案内をしてくださるのかも知れませんね。さて、電車が来ました。霧島神宮駅から、南宮崎へ行き、そこから海岸沿いに延岡へ行きます。南宮崎から、15分くらいのとこに『美々津(みみつ)』という駅があります。その駅から程遠くないとこに美々津という港があります。美しい、美しい港という意味なのでしょうか。神武天皇が大和へ東征する時にこの港から出港されたのだそうです。電車の中からなので、写真はうまくとれませんでしたが雰囲気だけは伝えることが出来たでしょうか。この場所へ来ると、本当に神武天皇が大和へ東征したのだな、なんてちょっと感動してしまいました。
2009.03.25
コメント(2)
-

醍醐寺 (醍醐の花見)
宮崎・天孫降臨の旅のブログはまだ半分もかけていないのですが、一旦お休みを入れて、昨日京都の醍醐寺に行ってきたことを書かせて頂きます。桜で有名な醍醐寺は、真言宗醍醐派の総本山、醍醐地は弘法大師の孫弟子理源大師(りげんだいし)・聖宝が創建しました。主神・横尾明神より、こんこんと水(醍醐水)が湧き出るこの山を譲り受け、じゅんてい・如意輪の両観音を刻み、山上に祀ったのが醍醐地の始まりだそうです。醍醐・朱雀・村上天皇の深い帰依によって薬師堂、五大堂、釈迦堂、五重塔などが次々と建立されましたが、長い歴史の中で、何度も火災にあったようです。秀吉は、「醍醐の花見」を契機に火災にあったり荒廃していた金堂や三宝院や如意輪堂などを再建したのだそうです。醍醐寺の中心のお堂である金堂です。この中の薬師如来像が、醍醐地の御本尊なのだそうです。金堂の横に不動明王が安置されてある不動堂がありました。私は以前不動明王さまが、守り神ですよといわれたこともあり不動明王様には何かしら、特別な思い入れがあります。この時も、何か凛とした空気を感じました。ここのお堂の中のにおいは、なぜか懐かしい祖母の家のにおいと同じでした。醍醐天皇のご冥福を祈るために朱雀天皇が起工した五重塔です。じゅんてい観音さまと、如意輪観音様のいらっしゃるお堂です。この横で、ご朱印を書いておられるようです。枝垂れ桜がとても綺麗です。弁財堂には、弁財天さまが祀られていました。雨が降るかと思われた不安定な天気でしたが、少しだけ青空が見えました。桜は青空に映えますよね。このあと、醍醐寺を出て随心院へ向かいました。隋心院は小野小町にゆかりのお寺です。このの小町は小野たかむらの孫にあたるのだそうです。古来、この辺りは小野と呼ばれていたそうです。小野道風は小町の従兄にあたるひとなのだそうです。隋心院は梅で有名なお寺なのですが、この日は梅はもう盛りを過ぎていたようです。京都はお寺もお花も、町全体がとても綺麗でいつまでも歩いていたいと思いました。この日は他にも予定があったので、ここでおしまいです。さて、次回は又宮崎・高千穂のお話に戻ります。
2009.03.24
コメント(8)
-

霧島神宮 (宮崎・天孫降臨の旅5)
高千穂の峰から高千穂河原に降りてきました。このあとの予定は霧島神宮です。バスは、土曜日と日曜日にしかないのでタクシーで行くことにしました。高千穂河原から約10分で霧島神宮に着きました。霧島神宮は結構な人でです。やっぱり、皆さんここへお願いに来るのですね。ご祭神はニニギノ尊です。今年は例年よりも桜が早いようです。『招霊の木』です、何かに似ていると思いませんか。そうです、1円玉の模様のデザインになったのはこの木なのです。これは、国家『君が代』に出てくるさざれ石です。神楽殿です。ニニギノ尊は降臨されて、多くの人に稲作を教えたと言われています。ここは、霧島神宮のすぐ横にある田んぼです。ここで、狭名田の長田御田植際をして、稲が植えられます。田んぼに稲が実ったら、抜穂祭もここでします。稲作が始まったところなのですよね。農耕民族である日本人の歴史の始まりの場所ですよね。
2009.03.23
コメント(2)
-

高千穂の峰 (宮崎・天孫降臨の旅4)
ニニギノ尊が降臨地ということで、一番はじめに霧島神社が作られたとことです。ちょうど御鉢と高千穂の峰の中間地点にあります。さて、あと一息です。最後の力を振り絞って高千穂の峰に登りました。着きました、高千穂の峰の頂上です。標高1574メートルです。ここにニニギノ尊が降臨されたのですね。 天の逆鋒を探します。有りました。鳥居の向こうにあります。ニニギノミコトが降臨の際突き刺したと言う『天の逆鋒』です。1.3メートルで柄のところが顔の形になっているのですね。坂本龍馬が日本で初めてのハネムーンでここへ来たと言われています。姉の乙女さんにその時のことを詳しく手紙に書いて送っているのです。お龍さんとふざけてこの逆鋒を引き抜いたと書いてあったそうです。周りは360度の眺望です。写真ではうまく伝わらないのですが、雲も下に見えてまるで天の上から見下ろしているかのようなのです。峰と峰との間の細い道から下を見ると空を飛んでいるかのようです。実際にこの地に来てみると、ニニギノ尊が降臨された場所みもっともふさわしいという気持ちになります。奈良の葛城をはじめニニギノ尊が降臨されたと思われる場所は全国に何箇所かあるのかも知れませんが、ここ霧島の高千穂の峰は私が知る限り、一番の候補地ではないかと思いました。坂本龍馬やお龍さんはどんな気持ちでここへきて、何を感じたのでしょうか。色々考えすぎるよりも、この大自然の美しさと神々しさを満喫するだけでもここへ来た価値は十分あるのかも知れませんね。
2009.03.22
コメント(2)
-

高千穂河原と古宮址 (宮崎・天孫降臨の旅3)
2日目は高千穂の峰に登るために高千穂河原に行こうと思ったのですが、路線バスは土曜日と日曜日しか運行していないのでした。えびの高原ホテルの方に相談してみると、なんと高千穂河原まで送ってくれるとのことなんと親切なんでしょう。来るまで、桜の咲く道をゆっくりと下って行きました。えびの高原から約40分で高千穂河原に着きました。鳥居の向こうに高千穂の峰が見えます。鳥居をくぐって歩いて300メートルくらい行くと、古宮があります。看板がありました。高千穂の峰は神様の宿る山なのです。高千穂の山を背にして堂々と立つ鳥居は壮観です。何かしら凄いパワーを感じました。心から落ち着く雰囲気で、力強い何かがあふれ出てくるような…。ここは、昔の霧島神宮の址です。霧島神宮ははじめ、高千穂の峰と御鉢(噴火口)の間にありましたが、約1400年前の噴火により、焼失してしまいました。その後、この地に再建されましたがそれも約100年前の噴火のため燃えてしまいました。その後、霧島町の「待世」に移されましたが、今の霧島神宮はおよそ480年前に現在の地に建て替えられたものです。それで、ここは今は神社はないのですが、霧島神宮古宮跡斎場として残っています。毎年11月10日は、高千穂峰と霧島神宮古宮址で、天孫降臨御神火祭という火祭が行われています。神社の方がここと、高千穂の峰の頂上で祭祀を行われるのです。ここは、ちょっと他にはない大変厳かな感じがします。空気が凛としているだけでなく近寄りがたい神々しい雰囲気です。ニニギノ尊が火を燃やして目印にしたとのことから、祭祀のときにはここで火を燃やします。さて、古宮を後にして高千穂の峰に登ることにしました。これは、まさに山登りです。ストックと手袋は欠かせないですね。私は、途中で何度かめげて断念しそうになりましたが、先輩に励まされてなんとか登り続けたのでした。下で見ているのと違って凄いがればです。後ろを振り向くのが恐いです。吸い込まれそうで、足がふるえそうです。御鉢の中から噴煙が立っています。この辺りは、下からの地熱と噴煙の熱で熱いくらいです。御鉢から少し下ると、鳥居が見えてきました。ありました、一番はじめに神社があった場所です。高千穂の峰と御鉢の間にあります。ここなのですね。さあ、高千穂の峰はもう少しです。もう足がガクガクで思うように動きませんが最後の力を振り絞って登っていくことにしました。次回は高千穂の峰の山頂です。360度の絶景です。良かったら読んでくださいね。
2009.03.21
コメント(6)
-

えびの高原 (宮崎・天孫降臨の旅2)
天孫降臨の旅の第一日目は、伊丹空港から鹿児島空港へ飛びました。この日は、天気予報では雨ということだったので心配でした。確かに地上の上は雨でも、飛行機から見る雲の上は太陽がさして眩しいくらいです。神様が天から見たら雲がこんな風に見えるのかななんて思ってしまいました。鹿児島空港に着いた私達は、空港バスで霧島いわさきホテルまで行きました。いわさきホテルというのは鹿児島中心にたくさんあるみたいです。鹿児島ではいわさきグループというのがホテルや交通機関など経営していてかなり有名なホテルのようでした。空港バスはそこが終点だったので、私達はその日に宿泊する『えびの高原温泉ホテル』にお願いをしていわさきホテルまで迎えに来てもうことにしていました。えびの高原ホテルの方は本当に親切な方で、ずっと待っていてくれたのでしょうかバスを降りた私達のところまですーっと来て下さいました。鹿児島空港からいわさきホテルまでが40分(690円)、そしていわさきホテルからえびの高原ホテルまでがまた40分(無料)というラッキーなコースで到着することが出来ました。ホテルの1階のお部屋には鹿が遊びに来ますよと聞いていたのですが、まさかそんなことなんて思っていたのですが、本当に本当なのです。私達がバスを降りるとまるで奈良公園みたいに鹿ちゃんがたくさんいて私達を迎えてくれたのです。ここの鹿は奈良公園の鹿と違って、野生のシカなのですがなぜかとても人懐こいのです。ホテルに荷物を預けてさっそく、えびの高原の近くの池めぐりに出かけました。1時間半くらいのトレッキングのコースなのですが、雨が降ったら霧で何も見えなくなります。天気予報では完全に雨なのですが、ホテルを出るときは何とか頑張ってもっているというような感じです。一番最初に、着いたのが白紫池です。お天気がいいと、池はどれもコバルトブルーに見えるはずなのですが、曇りなので残念です。でも、実際は写真よりは青かったのですよ。ここで、ちょっと一休みして空港で買ったお弁当を食べました。空気も綺麗でお弁当はとっても美味しかったですよ。2番目の池は六観音池といって3つの池の中で一番大きな池です。池の向こうに韓国岳(からくにだけ)が見えます。このあたりで、一番高い山です。昔の人はこの山の上から、韓国がみえたので韓国岳と名前を付けたのだそうです。六観音池の韓国岳の反対側に白鳥山があります。そして、この六観音池のそばに豊受神社がありました。看板が立っていました。村上天皇の御代に、性空上人が六観音池の湖畔で法華経を読んでいると、突然白髭の老翁があらわれたのだそうです。その老翁は『われはヤマトタケルノミコトである。白鳥になってこの地に住むことになった。』と言ったのだそうです。小さな祠がありました。ちょっと六観音池の近くに降りてみました。まるで、海岸のようで綺麗でした。噴火の時のコバルトがいっぱい残っていて池がコバルト色をしているのですが、写真では綺麗に映らなくて残念です。このあと、3つ目の不動池に着きました。ここは一番小さな池です。ゆっくりしていたかったのですが、空模様が怪しいです。本当に3つ目の写真を撮り終えたその時です、ぽつぽつと雨が降り出してきました。傘を出す間もなく、不動池はあっと言う間に霧で包まれてしまいました。不思議なことです、まるで私たちに池を見せてくれるために天気が持ちこたえていてくれたかのようです。そしてこのあと本当に土砂降りの雨になりました。もう、歩くのが精一杯です。ホテルに帰って温泉に入りましたが、なんだかこのほんの一時のお天気は神様からの贈り物用に思えたのでした。
2009.03.20
コメント(8)
-
宮崎・天孫降臨の旅1
以前から憧れの宮崎へ行ってきました。テーマは“天孫降臨の旅”ということで主に神々の里・高千穂を中心に日向の国を訪れたのでした。日程は3泊4日。鹿児島空港→えびの高原(池めぐり)えびの高原ホテル・泊→高千穂の峰(天の逆鋒)→霧島神宮 霧島国際ロイヤルホテル・泊→霧島神宮駅→延岡→高千穂→真名井の滝→天岩戸神社→天の安河原→高千穂神社(神楽)→高千穂・ホテル神州・泊→高千穂神社→くしふる神社→高天原遙拝所→天真名井→荒立神社→熊本空港という、行きたいところばかりを詰めて計画を立てた我儘コースでした。私と先輩は車に慣れないところで乗るのは不安なので、すべて公共機関を利用するということで、細かな日程を立てて準備しました。特に、高千穂の峰と高千穂町は名前は似ていても、宮崎県の南と北でかなり距離が離れています。普通は高千穂の峰に行く場合は指宿とか鹿児島と組み合わせるもの、そして高千穂町へ行く場合は阿蘇など熊本県と組み合わせるものなのだそうです。それでも、私と先輩はせっかく行くのだからということで一日に数本の電車やバスの時刻表とにらめっこしながら本当に両方の高千穂へ行ってしまったのでした。ちょっとしたコツとしては、宮崎はバスの本数が極めて少い上に土日しか運行していないなんてこともざらなので、なるべくホテルの方にお願いして送迎バスで迎えに来てもらったり送ってもらったりしました。そのおかげで、タクシーに乗ることを最小限に抑えてなんとか低コストで多くのところへ行くことが出来ました。宮崎の方ってとてもに親切です。宮崎って本当に自然も人も素晴らしいところです。盛りだくさんの旅でしたが、ブログの方は少しづつUPしていきたいと思っています。ちょうど、娘の就活中でPCの取り合いになるのでなかなか思うようには進みませんが忘れないうちに書き込んでいきたいと思っています。もしよろしかったら是非読んでくださいね。では、次の回は“えびの高原”の池めぐりからです。
2009.03.19
コメント(2)
-

『下の太子』 勝軍寺と物部守屋
勝軍寺の正式な名前は、椋樹山大聖勝軍寺で、現在は高野山真言宗に属しています。太子町の叡福寺が「上の太子」、羽曳野市の野中寺が「中の太子」、そして、ここ八尾の勝軍寺は「下の太子」と呼ばれ「河内の三太子」のうちのひとつとして親しまれています。蘇我氏と物部氏の神仏戦争の時に、聖徳太子子が、渋川の阿刀の館にいた物部守屋を滅ぼすにあたって、信貴山の毘沙門天に祈願し、四天王を祀ってその加護により守屋を討って、戦勝を得ることが出来たので、難波の高台に日本仏教最初の四天王寺を建立し、この渋川に勝軍寺を創建して、自身十六歳の植髪(うえがみ)の太子像と四天王像を安置したといいます。 本堂の太子殿には、太子植髪像を安置し、その脇に弓矢を持つ四天王像を祀っています。これは4人の関係者をおのおの四天王になぞらえたもので、右から持国天(蘇我馬子)、多聞天(秦川勝)、広目天(迹見赤檮)、増長天(小野妹子)の四体となっています。 勝軍寺のお寺の門の前にも四天王と聖徳太子の像がありました。山号のもとになった神妙椋樹(しんみょうりょうじゅ)です。 大聖勝軍寺は、『日本書紀』に示されない伝説が伝わっています。物部討伐軍に参戦した聖徳太子が物部軍に追われたとき、椋(むく)の木が二つに割れて皇子の身をかくまったというのです。その椋の木が境内に祀られている。推古天皇は椋樹と大聖聖徳法王の勝ち軍を讃え、神妙椋樹山大聖勝軍寺という山号と寺名を賜ったといいます。 お寺の中には、塔や八角堂があります。なんだかちょっと夢殿に似ていてますね。物部守屋に関連した史跡が寺院の境内や境内の近くにあります。たとえば、大聖勝軍寺の境内には、物部守屋の首を洗ったという守屋池や馬蹄石があるのです。付近には、鏑矢塚、弓代塚、それに物部守屋の墓があります。この物部守也のお墓はpleさんが、「あるいみ、日本一のパワースポット」と呼んでいる場所です。以前私が見たNHKの『その時歴史が動いた』で蘇我氏のことをしていたのですが、番組の最後にテーマ音楽とともにあらわれたのがこの物部守屋のお墓でした。pleさんのご指摘の通り、正面左右には「神社本庁」「大阪府神社庁」をはじめ全国各県の神社庁や、太宰府天満宮、多賀大社、伏見稲荷大社、熊野那智大社、春日大社、石清水八幡宮、近江神宮、平安神宮などが並んでいます。そういえば、仏教反対の物部守屋ですからお寺にお墓があるわけにはいかないですよね。だから、お墓の前に鳥居があるのは当たり前のことなのですよね。今は無くなって更地になっているのですが以前、道を挟んで前に「八尾市立病院」がありました。私は結婚した当初八尾に住んでいたのですが、盲腸になって、その病院に入院をして手術を受けたことがありました。ところが、勝軍寺も物部守屋のお墓もちっとも気がつかなかったのです。物部守屋は神仏戦争の時に仏教に反対した悪者のように言われることもあるのですが、本当は日本古来の神教を守り大切にした業績も大きいのではないでしょうか。私は、お寺も好きですが神社がもっと好きなので物部氏についてもなんだかかわいそうに思ったりしてしまいます。以前八尾に住んでいたということも、影響しているのかも知れませんが…。そういった意味でも、物部氏はちょっと気になる一族です。夫も結婚するまで八尾に住んでいたのですが、どちらも全然知らなかったようです。今回二人で、来ることが出来て本当に良かったです。懐かしい八尾の町を歩き、お墓参りも済ませて気持ちのいい一日になりました。このあと、夫と二人で一心寺さんへ行き串カツを食べたのでした。|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆明日から、宮崎に行ってきます。鹿児島空港からえびの高原、霧島神社、天の逆鋒に行き、JRで高千穂まで行き、真名井の滝、天の岩戸、天の安河原などにも立ち寄るつもりです。お天気が気になりますが、楽しんで来ようと思っています。しばらくブログはお休みになるかと思いますが、コメントのお返事が出来なかったりするかと思いますが、すみません。m(_ _"m)ペコリ帰ってきたらまたよろしくお願いいたします。では、行ってきま~す。
2009.03.18
コメント(6)
-

弓削神社
以前から一度、行きたいと思っていた弓削神社(ゆげじんじゃ)に行ってきました。大阪府八尾市にあります。付近に勢力を保持していた物部氏の一族である弓削氏の氏神です。このあたりは、弓削氏の一族である高僧道鏡の出身地ではありますが、弓削神社は彼の没後の創建であり、直接の関わりはないのだそうです。 弓削氏は河内国若江郡弓削郷を本貫とする豪族で、その名の通り、武器の製作に携わるグループを率いていたのだそうです。また、物部氏との関わりも強く、物部尾興は弓削連祖倭古連の娘阿佐姫と結婚して物部守屋を生んだと言われ、守屋は物部弓削守屋大連と複数姓をとっており、この地を本願としていたのだそうです。当時は枚岡神社、恩智神社につぐ三指に数えられた大社で月次、相嘗、新嘗には奉幣にあずかったといわれていますが、現在のたたずまいでは村の鎮守のイメージが強いようです。弓削神社は、JR志紀駅・長瀬川を挟んで2箇所あり、東側の東弓削一丁目にある弓削神社と西側の弓削町一丁目にある弓削神社の二社一対で二座にあてているのだそうです。両社とも式内大社です。【弓削神社】御祭神は、宇麻志麻治命、饒速日命、天照大神。 宇麻志麻治命というのは、饒速日命(ニニギノミコトの兄)の子供なのだそうです。国道25号線は車の通りも多く賑やかなのですが、通り沿いの郵便局のすぐ裏手にある弓削神社は静かで、落ち着いた雰囲気です。私は、何度もこの辺りに来ているはずなのですがここにあるとは全然気づきませんでした。拝殿の奥には本殿があります。弓削神社から、3分ほどのところにあるJR志紀駅の方へ歩き、駅を越えてそこからまた3分くらい歩くと、山本病院の裏辺りに、東弓削神社が見えてきました。【東弓削】 祭神は、祭神は、宇麻志麻治命、饒速日命、天照大神です。 ほかに、彌加布都神、比古左自布都神(物部氏の祖神)、高魂命、天日鷲翔矢命(弓削市氏の祖神)、菅原道真を祀っています。 本当に小さな神社です。ここは何度も通ったことがあるのに、ここに神社があるとはちっとも気づきませんでした。夫は、この2つの神社のちょうど間くらいに結婚するまで住んでいました。結婚後は、お姑さんが一人で住んでいたので毎年何度かこの辺りに来ていたのですが、本当にちっとも気づかなかったのです。たぶん、ごく近所の人以外ここに神社があることは知らない人の方が多いのかも知れません。そのくらいひっそりとした神社です。ただ、7月には夏祭り、10月には秋季例祭りなどが行われるので、近所の人には親しまれてるようです。このあとに、下の太子である勝軍寺と、物部守屋をのお墓へ行ってきました。そのお話は次回、させていただきます。
2009.03.15
コメント(6)
-

多冶速比売神社
梅に誘われて多冶速比売神社へ行ってきました。主祭神は多治速比売命(たじはやひめのみこと)で女神として厄除・安産・縁結びの神として崇敬が厚く、また本殿には素盞嗚尊(すさのおのみこと)・菅原道真公も合わせて祀られ、特に道真公は学問の神(天神様)として厚く信仰されています。拝殿で御参りをしました。良く見るととても綺麗な模様です。境内には十三の末社【坂上社(式内社)、鴨田社(式内社)、大神社、住吉社、天照社、八幡社、春日社、熊野社、白山社、弁天社、稲荷社、福石社、水天宮】があり合わせて荒山宮 (こうぜんのみや)とよばれています。 多冶速比売神社では、6月末と12月末に、半年の間に知らず知らずに犯した罪や心身の穢れを祓い清めて、正常な本来の姿に戻るための「大祓」が行われます。6月を夏越しの祓、12月を年越しの祓とも呼びます。 越の大祓(なごしのおおはらい) といい、茅の輪くぐりをします。8月には弁天社にお祀りされている市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)は、芸能の神様としてご神徳があり、それに因んでの神賑(しんしん)行事として、奉納民謡祭りが行われます。だんじりの季節にはたくさんのだんじりが宮入をして賑わうのだそうです。地元の方に親しまれ大事にされている神社です。多冶速比売神社の隣に荒山公園があり梅林になっています。ちょっと本当は、あと一週間早いともっと綺麗だったかもしれません。今回はぎりぎりセーフというところでしょうか。この公園は桜も綺麗なのだそうです。今年は桜は早いかも知れません。機会があれば桜も見に来たいなと思ったりしました。
2009.03.14
コメント(4)
-

『道の駅』 しらとりの郷 羽曳野
最近、『道の駅』にはまっています。飛鳥や奈良にお出かけした時に帰りにちょっと『道の駅』によって、晩ご飯の食材を買い求めたりするのが楽しみです。私の一番のお気に入りの『道の駅』はしらとりの郷 羽曳野です。野菜や果物が新鮮で、メッチャ美味しいのです。スーパーのとは全然違っていますね。ハムなんかもかなり美味しいですよ。お漬物は安くてめっちゃ美味しい、ご飯が進みます。お花も安くてしっかりしているとかなり人気のようです。タケル館では、ヤマトタケルの形をしたクッキーなど、ヤマトタケルにちなんだグッズも売っています。(笑)実はあまりに人気で、遠くからも大勢の方がこられるので、平日でも大型駐車場はいっぱいです。開店の10:00少し前がお勧めです。同じ敷地内のパン屋さんは焼き立てで美味しくて、いつも人が並んでいます。私は窯から出したてを買って車で食べたりするのですが、めっちゃ美味しいですよ。羽曳野、藤井寺は歴史の宝庫です。【応神陵古墳】(「道の駅」より車で12分) 長さは仁徳陵古墳に次ぐ全国第2位、体積では日本最大の前方後円墳。【白鳥陵古墳】(道の駅より車で9分) 日本武尊の陵墓との伝承がある前方後円墳。 【野中寺】(「道の駅」より車で7分)聖徳太子と蘇我馬子の建立と伝えられる白鳳期の寺「中の太子」と呼ばれている。 【誉田八幡宮】(道の駅より車で11分)第29代欽明天皇の命で応神陵古墳の前に建てられた日本最古といわれる八幡宮。 歴史探索などで、お近くに来られた時は、帰りに是非、『羽曳野・道の駅』をご利用されてはいかがでしょうか。
2009.03.11
コメント(6)
-

葛井寺
藤井寺の駅のすぐ近くに葛井寺があります。藤井寺の地名の由来になったお寺です。葛井寺は7世紀代に、百済から渡来した葛井氏の氏寺として建立されたと考えられています。その後、聖武天皇の勅願により千手観世音菩薩を安置、行基が開眼法要を行ったとされ、これが葛井寺の創始とされているようです。葛井寺に所蔵されている室町時代の「葛井寺参詣曼陀羅」によれば、当時は薬師寺式伽藍配置をとっていたと推定されているようです。葛井寺は奈良時代から平安時代にかけて大いに栄えたそうです。 御本尊の千眼千手観音様は毎月18日に御開帳されてる秘仏です。 高さ1.4mで、大きい手が2本、中くらいの手が40本、小さい手が1001本で、計1043本の手を持っているのです。十一面の顔に真数の1043臂千眼の観音菩薩であり、日本最古の千手観音なのです。千手で迷える衆生を救うための大慈悲を示しておられます。その美しさは人々を魅了し、現世利益の観音信仰を支えてきているのです。実は私もまだ見たことがないのです、いつか18日に来たいと思います。でも、その時は人がいっぱいで写真は撮れないと思うのです。今日は人が少なくて良かった。宗派が真言宗御室派なので、弘法大師様がいらっしゃるのですね。葛井寺は、辛國神社のすぐ隣にあるのです。せっかくなので、葛井寺に来られた方は辛國神社へ、辛國神社へ来られた方は葛井寺へお越しになることをお勧めします。お得感満載です。(*^_^*)
2009.03.10
コメント(6)
-

辛國神社
藤井寺にある辛国神社へ行ってきました。御祭神は、饒速日命 天児屋根命 素盞鳴命 品陀別命 市杵島姫命 です。本殿の横で、神主さんから『辛國神社縁起』を頂きました。そこには、ご祭神・ご由緒・御神徳などが書かれてありました。ご由緒辛国神社は今から千五百年程前、雄略天皇の御代に創設された神社です。平安時代には官社となり、式内社として人々の尊信を集めてきました。日本書紀には、『雄略十三年春三月、餌香長野邑を物部大連に賜う』とありますが、、餌香長野邑は、旧藤井寺町のあたりと思われます。この地方を治めることになった物部氏は、その祖神を祀って神社をつくり、その後、辛國氏が祭祀をつとめ、辛國神社と称するようになったのだそうです。三代実録には、清和天皇『貞観九年二月二十六日河内国志紀郡辛國神社を官社に預る』とあります。河内国志紀郡辛國神社というところに、目がとまりました。志紀というのは、今のJR八尾の隣の志紀駅の辺りをいいます。八尾は物部氏の本拠地なので、当時は藤井寺近辺よりも八尾の志紀のあたりに御縁があったのかも知れませんね。鳥居をくぐると本殿がありました。落ち着いたとても気持ちのいい凛とした空気に包まれています。「わ~、ここ私大好き。」と大きな声で叫んでしまいそうでした。ご祭神のお話をしますね。【饒速日命・ニギハヤヒノミコト】彼は、瓊々杵尊の御兄です。物部氏の祖神でもあります。 天孫降臨に先立ち、天祖より天璽宝の瑞宝十種をさずかり、大和建国の任務をうけて河内国哮ヶ峰に天降りになったのだそうです。物部氏とくれば、八尾、藤井寺になにか繋がりを感じますね。故に古来より病気平癒、厄除、呆け除の守護神として広く信仰されているようです。【天児屋根命 アメノコヤネノミコト】藤原氏の祖神です。天照大御神が天岩屋戸に隠れ給うた時、岩戸の前で美声をあげて祝詞を奏上した神で、後天孫降臨に随って日向国に降った五部神の一人です。その子孫は代々朝廷の祭祀を司いました。国土安泰、産業(農工商)繁栄、家内安全、災難除け、出世開運、合格祈願をする者も多いのだそうです。境内には藤棚が、二か所ありました。藤原氏ゆかりの藤ですね。【素盞鳴命 スサノオノミコト】天照大神の弟神です。素盞鳴命は気性の激しい直情径行の御性格のため、御姉君・天照大神の勘気をこうむり、高天原から地上に追放された。そこで命は己の犯した罪を深く反省し、困難に耐えて出雲の国にたどり着き、勇猛心を善用して『八岐の大蛇を退治した』という神話は、実にわが日本民族の理想を示しています。素盞鳴命が自ら句なんの道を歩み幸福の地を開拓されたという御神徳を仰ぎ、古来より縁結び、厄除け、開運の守護神としての信仰が篤いのだそうです。【品陀別命 ホンダワケノミコト】第十五代・応神天皇第のことです。 治山治水につとめられ、又学問に極めて御熱心であったのだそうです。この御代に百済、新羅、中国のいわゆる辛国から文字をはじめ、各種の大陸文化がわが国に伝来しました。辛國というのは、唐国、つまり中国もしくは、朝鮮半島などの外国という意味ではないでしょうか。辛國神社と言っても、唐の人や韓の国の人が作った神社だったわけではないと神主さんはおっしゃっておられました。ただ、唐国の人からの文化の影響を受けたことは確かだったと思います。当時は、唐国は先進文化・技術をもたらしてくれる進んだ国といことはあったのではないでしょうか。この辺りには、応神天皇陵、雄略天皇陵、仲哀天皇陵、など御陵がたくさんあります。地名も、土師の里など渡来系の、土師氏と関係が深かったことも分かります。応神天皇の母君は神功皇后です。古来より学問の神、安産の神としての信仰が篤いようです。 堺市の中百舌鳥古墳群の仁徳天皇陵は有名ですが、藤井寺の数多くの天皇陵も歴史の宝庫としては引けを取らないのではと思ったりもしています。 【市杵島姫命 イチキシマヒメノミコト】素盞鳴命の子。というか、記紀では、天照大神と素盞鳴尊が闘って、天照大神が忍穂耳命を初め五男神を、素盞鳴尊が市杵島姫を含む三女神を生んだことになっていて、市杵島姫命はその三女神(三美神)のうちの一人です。美人のほまれ高く、弁天様に見たてられています。天孫降臨に際し、『よく養育せよ』との御神勅を奉じて天孫瓊々杵尊を立派に成育せしめられたと書かれています。そうなのですか、孫瓊々杵尊を成育したのは市杵島姫命だったのですか。その御神徳により子供の守護神と仰がれている。とあります。末社は春日稲荷神社です。藤原氏との御縁で春日ということなのでしょうか。私が面白いなと思ったのは、ご祭神に物部氏のご先祖さまと、藤原氏のご先祖様がいらっしゃるということです。物部氏は蘇我・物部の神仏戦争で衰退したということになっていますが、やっぱり一番は物部氏が天皇家との婚姻が出来なかったからという理由が強いのではないでしょうか。天皇家とは家来筋にあたるので、婚姻は出来なかったのですよね。それに引き替え、蘇我氏は家来筋ではなかったのでスムーズに婚姻が成立したのでしたね。となると、藤原氏はどうでしょう。本来、物部氏のことを考えると当然、婚姻は無理なのでしょうね。ところが、その“ムリ”を“アリ”に変えちゃった人たちがいたのですよね。聖武天皇の皇后、光明皇后です。すごいですね、その後ず~っと藤原氏が外戚として受け継がれていくのですから。まさに、藤の木を思わせる凄さですよね。そう思うと、物部氏のはちょっと気の毒な気がします。それは、私が結婚した時に八尾に住んでいたからなのでしょうか。辛國神社は色々なことを考えさせてくれる神社です。来るまでは、そんなに期待していなかったのですが、来てみて結構気に入ってしまいました。良い神社です。
2009.03.09
コメント(4)
-

大鳥神社
お天気が良かったので、大鳥神社へ行ってきました。大鳥神社は「和泉国一宮」で旧官幣大社です。大鳥神社拝殿。御祭神は日本武尊、大鳥連祖神です。日本武尊は西征して熊襲を平定し、東征して東国を平定しましたが、伊吹山で病に倒れ、伊勢国能褒野で薨去します。遺体はその地に葬られましたが、その陵墓から魂が白鳥となって飛んでいき、大和国琴引原で留まり、また飛び立って河内国古市に降りましたが、最後に和泉国のこの地に舞い降りたので、社を建てて祀ったのだそうです。これが大鳥神社の始まりだといわれています。また、もう一人のご祭神である大鳥連は中臣氏と同じく天児屋命を祖神としていたので、大鳥連祖神は天児屋命ということになるのでしょうね。鳥居をくぐると、参道は静かで凛とした空気に包まれています。境内の森は、白鳥と化した日本武尊が当地に鎮まった時、一夜にして種々の樹木が生じたので、「千種の森」と称せられたのだということです。鳥居の向こうに拝殿がありますが、この鳥居八角なのです。本殿の造りは「大鳥造り」と呼ばれる独特の造りで、「大社(出雲)造り」から発展したといわれています。た。左上を拡大してみました。八角だということが良く分かりますよね。中に入ると、拝殿と本殿がありました。↓本殿です。実は私はpleさんのブログを見て以来、どうしてもここの日本武尊に会いたくていました。今日、ついにお目にかかれたのです。う~ん、凛々しいですね。でも、私が読んでいる「白鳥の王子・ヤマトタケル(黒岩重吾・著)」ではもう少し若い感じがするのですが…。日本武尊像の横に、馬の像がありました。とても綺麗な馬ですが、何故ここにあるのでしょうか。御存じの方は教えて頂けないでしょうか。梅が綺麗に咲いていました。摂社は大鳥美波比神社。御祭神は天照大神です。念願の日本武尊様に出会えて本当に良かった。とても、満足です。さて、このあと辛国神社と葛井寺へ行ったのですが、そのこともゆっくりとブログにUPしていきたいと思っています。九州・宮崎へ行くまでに、ちゃんと書きたいと思っています。心は半分宮崎・高千穂に飛んで行ってしまっているのですが…。
2009.03.08
コメント(6)
-

仁徳天皇陵
お久しぶりです。毎日忙しくしています。今月の後半に宮崎の高千穂に行く予定にしているので、計画を立てたり予習をしたり、持ち物の準備をしたりしています。また、娘のPCが壊れてしまい、就職活動を私のPCでしているので私が使えなくてブログも更新できず、皆様のところへ遊びに行くこともできず申し訳ないです。先日、大仙公園へ行きました。堺東へ用事に行った帰りにちょっと寄ったのでした。大好きな仁徳天皇陵です。何故か分からないのですが、私は子供のころから古墳が好きなのです。小学生のころ、毎日ランドセルを背負って御陵さんを通って通学していたせいでしょうか。なんとなく、懐かしいというか落ち着くと言うか。通学の途中御陵さんで、女の子は綺麗なお花を摘んだり、野イチゴを見つけて食べたりしました。男の子は、カブトムシやゲンジ(クワガタ虫)を捕って戦わせたりしたものです。子供たちの遊びまでもあったのです。古墳はお墓なので好きでないと言う人もいるかもしれません。人は亡くなってから50回忌、100回忌を祝ってもらえると「目出度い」というのだそうです。ろうそくも、白ではなくて赤なのですよ。そんなに経っても、覚えていてもらえる人は本当に幸せな人なのでしょうね。ましてや古墳となれば何百年です。それでも、覚えていてもらえるなんて本当に幸せな人だと言わざるを得ませんよね。日本人は古墳を大切にしています。古墳は当時の最先端のテクノロジーを駆逐して作られています。その当時の生活や、風習を伝えるタイムマシンとも言えるのかもしれません。久しぶりの仁徳天皇陵です。やっぱり、堂々として良いですね。ボランティアの方が外国の方二人に一生懸命説明をしていました。地元の方は本当に、この古墳を誇りに思っておられるのですね。大仙公園の中の日本庭園です。和の心ですね。しばらく、何も考えずぼーっとしていました。お茶菓子をいただいて、ほっこりしてしまいました。もう、梅が咲いているのです。今年はちょっと早いのでしょうか。さて、しばらく色々忙しくてゆっくりとした時間を過ごすことができませんでしたが、今日は本当にいい一日でした。ブログの更新が滞りがちになるかもしれませんが、元気です。落ち着いたらいっぱい書きたいことがあります。その時はまた、怒涛の更新になるかも。(笑)これからも、よろしくお願いいたします。(*^_^*)
2009.03.02
コメント(12)
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
-

- 中国&台湾
- 亡父の故郷•長春に行ってまいりまし…
- (2025-09-19 17:17:04)
-
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- 那覇市立壺屋焼物博物館(沖縄県那覇…
- (2025-11-14 20:00:06)
-
-
-

- ★☆沖縄☆★
- 沖縄の産業まつりへ🌺子どもたちと見…
- (2025-11-03 21:57:49)
-