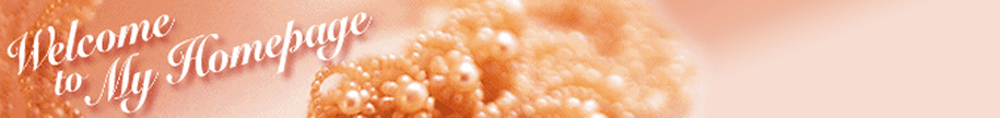2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009年04月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

坐摩神社
坐摩神社ってご存知ですか?正式な読み方は「いかすりじんじゃ」ですが、、一般には「ざまじんじゃ」と呼ばれることの方が多いのだそうです。場所は大坂の本町駅の近くにあります。私は近くを何度も通っているのに全く知らなかったのですが、ここは摂津国の一宮なのです。ちなみに畿内の一宮は↓の通りです。【山城国】賀茂別雷神社 京都市北区 賀茂御祖神社 京都市左京区 (2社で1社)【摂津国】住吉大社 大阪市住吉区 坐摩神社 大阪市中央区 【大和国】 大神神社 奈良県桜井市 【和泉国】 大鳥大社 大阪府堺市 【河内国】枚岡神社 大阪府東大阪市 片埜神社 大阪府枚方市 できれば、全部行きたいなと思っていたのですがまだ行ったことがないのは摂津の坐摩神社と河内の片埜神社の2社でした。今回近くまで行ったので坐摩神社へ行くことにしました。入口では大小3つの鳥居が横に組み合わさった珍しい「三鳥居」です。坐摩神社の始まりは、神功皇后が三韓征伐より帰還したとき、淀川河口の地に坐摩神を祀ったことだといわれています。祭神の五柱を総称して、「坐摩神」と称しているのだそうです。生井神(いくゐのかみ)…井水の神(生命力のある井戸水の神) 福井神(さくゐのかみ)…井水の神(幸福と繁栄の井戸水の神) 綱長井神(つながゐのかみ)…井水の神(「釣瓶を吊す綱の長く」ともいわれ、深く清らかな井戸水の神) 波比祇神(はひきのかみ)…竃神(屋敷神。庭の神) 阿須波神(はすはのかみ)…竃神(足場・足下の神。足の神であり旅の神) 祭神の五柱の神は、『古語拾遺』等によると神武天皇が高皇産霊神・天照大神の神勅を受けて宮中に祀ったのが起源とされています。境内にちょっとユニークな獅子がいました。拝殿の横の道を入ると、陶器神社がありました。これも陶器で出来ています。地下鉄の本町駅のすく近くです。こんな大都会の真ん中にも、素晴らしい神社があるのですね。陶器神社と同様に繊維神社もあり、両者ともこの周辺の陶器問屋、繊維問屋の守護神となっているのだそうです。私達が参拝している間にも数人の方が代わる代わる参拝されていました。地元の方に愛され大切にされているのですね。綺麗で、落ち着いた感じの神社です。本町にお越しの際はちょっと寄ってみられてはいかがでしょうか。
2009.04.30
コメント(4)
-

国生み神話の島・沼島・(八幡宮・神宮寺)
島の中にはおのころ島、八幡宮、神宮寺、弁天堂などがあります。船を下りて一番最初に行ったところが島の方が天神さんを呼んでいるところです。天御中主が祭られているのだそうです。島の中にはたくさんの井戸があります。この井戸は八角形をしています。昔は貴人が使う井戸は八角形だとか六角形だとかだったのだそうです。そして、井戸は今でも島の方の生活の一部として使われているのだそうです。この時も、一人の年配の女性の方が水を汲んでおられました。井戸の中を覗いてみると、きれいな水がこんこんと湧いているのでした。次に行ったのが沼島八幡宮です。豊漁の神様が祀られており、海上の安全と豊漁を祈るだんじり祭りがおこなわれるのだそうです。裏山の林は手付かずで残っており樹齢約200年のスヂジイやタブノキが生えているのだそうです。大自然が大昔のまま残っているという感じでした。拝殿の天井辺りに羅針盤が付けられています。海の安全を祈るためのものなのだそうです。神社の羅針盤はここと伊勢神宮だけなのだそうですが、伊勢神宮は大切にしまわれているので実際に目で見ることが出来るのは沼島八幡宮だけなのだそうです。八幡宮はちょっと高台にあるので海が見えて見晴らしが最高です。まさに、海の神様がおられそうな気がしてきます。八幡宮のすぐ横に神宮寺があります。中に入って休憩させて頂きました。綺麗なお庭でいしたよ。神宮寺を出て少し海の方へ行くと、弁財天さまがいらっしゃりました。弁財天様は海の守り神ですよね。海の近くで船に乗る方々を見守ってくれているかのようでした。今回は日帰りの旅ということで、朝の5時に家を出たのですが夕飯に間に合うように帰りたかったのでばたばたの旅でした。淡路島に来たのだから、本当はイザナギ神宮、オノコロジマ神社、絵島、ゆづるは神社へも行きたかったのですが、残念ながらあきらめなければなりませんでした。今回はツアーということでお土産に、『御井の清水』を頂きました。『御井の清水』は「古事記」で天皇の御料水として運ばれた“淡道島の寒泉”であると記されている名水なのです。大事に飲んでみようとおもっています。それから、沼島は勾玉の形ということで船に乗るところで勾玉を売っていました。私は以前から緑色の勾玉が欲しいなと思っていたので、思わず買ってしまいました。アベンチュリンと、水晶です。アベンチュリンは癒し・安定・平和を与え、ストレスを緩和してくれると言われている石です。新しい機会を増やし、視野を広げて発展をもたらすとも言われています。さて、またまた良いことがありそうです。勾玉のネックレスを首に付けた帰りました。今回は、先輩と一緒だったのですが先輩も私に影響されたと言って水色の勾玉を買って首に付けていました。そして、ご主人様に勾玉のストラップも買っておられました。やはり、沼島の勾玉はパワーがありそうです。私は最近、色々なところへ行くことが出来て本当に幸せです。この幸せに感謝して、いつまでもこの幸せが続きますようにまたまたお願いしてしまったのでした。
2009.04.29
コメント(4)
-

国生み神話の島・沼島・上立岩
昨日、淡路島の南にある沼島というところへ行ってきました。古事記によると次のような物語があります。人間が生まれるはるか昔、神々は天上の世界、高天原住んでおられました。下界を見て、「この漂っている国を整えて、しっかりと造り固めよ」という天つ神の命令を受け、男神伊邪那岐尊と女神伊邪那美尊の二神は、天野浮橋に立ち、天つ神から授かった天の沼矛を指し降ろして、青海原を「こをこをろ」とかき混ぜました。矛を引き上げると矛先から、滴り落ちる潮が固まり島となりました。《おのずから凝り固まったのでオノコロ島という》二神は、この島へ天降りて夫婦の契りを結び、天の御柱と八尋殿(やひろどの)を建て住みました。そして、淡路島を筆頭に、四国、九州、壱岐、対島、佐渡、本州という順に八つの島(大八島国)を生み、それからさらに他の島々を産んだとされています。そのオノコロ島がこの淡路島の最南端の沼島(ぬしま)だと言われています。沼島の名前の由来は、『ぬ』という文字には玉という意味があり、島の形が勾玉の形をしている所から「ぬしま」と呼ばれたのだそうです。下の写真の手前が沼島で、奥が淡路島です。沼島の周りを舟に乗って一周することにしました。小さな船だったので、かなり揺れましたが頑張って船に捕まっていました。(実は、今日職場で服を着替える時に足に“青あざ”を見つけてしまいました。思い返すと船が揺れて転んで足を打ったのでした。そんなことにも気付かずに一生懸命見ていたと思うと我ながら恥ずかしくなってしました。でも、それくらい素晴らしい島なのです。)まずはじめに行ったところが、鞘型褶曲(さやがたしゅうきょく)です。これは、1億年前の地球の「シワ」が残る珍しい岩石なのです。引き潮の時にしか姿を現さないのですが、この岩は沼島以外ではカナダとフランスの2か所にあるだけで、昔の地殻内部の動きが分かる世界でも貴重な資料となっているのだそうです。私は、案内をしてくださった方に、「何故、1億年前って分かるのですか?」と聞くと、「学者がそう言ってるから間違いないと思うで。」とのことでした。なるほど、現代の科学の力で1億年前の地球のシワだと言うのだから間違いないのでしょう。やはり、日本でもっとも古い地層なのですから、なるほどここが国生みだと言うのもうなずけますね。もう少し近づいてみます。真ん中のあたり見えますでしょうか。このあと、『上立岩』へ行きました。上立岩はイザナギとイザナミが出会った天の御柱であるとも龍宮の華表(城郭の門)であるとも伝えられています。この平な岩の上で、イザナギとイザナミは国生みをなさったとも言われています。岩と岩の間に入れそうなところがありました。ここは、『黄泉の入口』とも言われています。イザナミを追いかけて黄泉へ行き、黄泉から帰ってきたイザナギはここから出てきたのだそうです。古代のロマンが伝説となり息づいている、ここ沼島は美しい自然に囲まれた素晴らしい島です。私達はこのあと船から降りて島の中を散策しました。残念ながらおのころ神社へは行くことができませんでしたが、天満宮、八幡宮、神宮寺、弁財天などに行くことが出来ました。それは次回ということにさせていただきます。
2009.04.28
コメント(4)
-

近江神宮
一年ぶりの近江神社です。大近神宮駅から降りて歩いて10分くらいです。御祭神・天智天皇は、大化改新を断行され古代国家の基礎を確立、近江大津宮に遷都されこの都に御即位されました。とても綺麗な神社です。拝殿では、天智天皇をしのびながら参拝をしました。ご祭神の第38代天智天皇は、今から360年余り昔、大化の改新を成し遂げられ、古代国家の根本を確立されました。境内は、当時の都「近江大津宮」の古跡です。「天智」とは天のように広く限りない智恵の意味なのだそうです。御在世中に漏刻(水時計)を造られ国民に“時”を知らすことをはじめられました。また、日本最初の学校を造られたり、初めて石油が発見されたことでも知られているのだそうです。世界的にも国家という概念が出来つつある時期でもあったのかも知れません。海外の脅威を感じつつ中央集権を目指したのはまさに、天智天皇が最初の方だったのかも知れませんね。私は子供のころ天智天皇といえば、百人一首で一番初めの人という意識しかありませんでした。でも、意外とその感覚は正しいのかも知れませんね。文字もその頃、大陸から入ってきています。新しい文明の始まりの時のリーダーだったと言えるのかもしれませんね。さて、このあともう一度電車に乗って石山寺を目指したのでした。
2009.04.28
コメント(0)
-

三尾神社
三井寺から駅に戻る途中ちょっと気になった神社がありました。三尾神社です。ご祭神は伊弉諾尊です。門をはいるとすぐ、拝殿がありました。三井寺も明治のはじめ、神仏分離令に基づいて、出雲や伊勢に系列する社はすべて分離させられました。三尾(みお)神社はそのうちのひとつなのだそうです。伊弉諾尊が長等山の地主神として降臨したのが縁起の始まりとされ、神はいつも赤、白、黒三本の腰帯を垂らしていたのが三つの尾を曳くように見えたところから「三尾」と名づけられたのだそうです。腰帯は、それぞれ赤尾神、白尾神、黒尾神となり、本神である赤尾神が最初に三井寺山中琴緒谷(ことおだに)に出現。それが、卯年の卯月卯日、卯の刻に、卯の方角から現れたため、当社の使いとして、瑞祥の神獣である兎が選ばれたと伝えられています。御神紋も「真向き(まむき)の兎」です。全国でも兎にゆかりを持つ宮は珍しく、卯年の今年は大勢のお参りが見られるのだそうです。とりわけ、初詣でには、連日、何台もの観光バスからあふれる人たちでとても賑わうらしいです。卯年生まれの守護神で縁結び、安産に霊験あらたかな社だそうです。 うちの娘がうさぎ年なので、お願いをしておきました。さて、次は近江神社です。
2009.04.27
コメント(0)
-

三井寺
一年ぶりに三井寺へ行ってきました。前回行った時は、金堂の横にある閼伽井屋の存在に気付かずに帰って来てとても残念な思いをした。三井寺の名前の由来になったともいう、閼伽井屋が今回の一番の目的地でした。まずは三井寺駅から歩いて10分、仁王門に着きました。重要文化財なのだそうです、立派ですね。まっすぐ進むと金堂です。御本尊の弥勒菩薩は天智天皇が信仰されていた霊像なのだそうです。そして、その金堂の左手に回るとありました。閼伽井屋です。天智、天武、持統の三天皇が産湯に用いられたという泉が湧いています。ぼこぼこぼこと音がしています。時々、キューンと鳥の鳴くような音がします。まるで生き物のようです。水道のない昔の人にとってこのような井戸がどれだけ大切にされたかと思うと、ちょっと、感動です。しばらくその場に立ちすくんで井戸のぼこぼこに聞き入っていました。閼伽井屋の上には左甚五郎の龍がありました。昔この龍が夜な夜な琵琶湖に出て、困った甚五郎が自ら龍の目玉に五寸釘を打ち込み、静めたと伝えられています。今も、この龍は閼伽井屋の正面で三井寺を見守っているのだそうです。弁慶の引き摺り鐘です。昔、俵藤太秀郷が三井寺に寄進したのですが、その後延暦寺との争いで弁慶が奪って比叡山へ引き摺りあげて撞いてみると“イノー・イノー”(関西弁で帰りたい)と響いたので、弁慶は「そんなに三井寺へ帰りたいか!」と起こって鐘を谷底へ投げ捨ててしまったのだそうです。その時の物と思われる傷痕や破目が残っているのだそうです。さて、目的の閼伽井屋も見れたし、ちゃんと参拝も出来たし次は近江神社です。でも、その前にちょっと気になった神社があったのでそちらの方へも足を延ばしてみました。
2009.04.26
コメント(4)
-

竃山神社
今回の和歌山市での最終目的地の窯山神社です。時間があれば東照宮や、天満宮、雑賀崎の辺りの番所の鼻にも行きたかったのですが、段々日が落ちてきてここが限界のようです。竃山神社は娘が5歳で、息子が3歳の時の七五三で来たことがあります。あの頃子供たちは可愛かったな~、などと思いだしてしまいました。御祭神は彦五瀬命です(五瀬命イツセノミコトとも言われます)。彦五瀬命とは、神武天皇のお兄さんなのです。五瀬命はウガヤフキアエズと、海神の娘であるタマヨリビメの長男として生まれました。弟に次男:稲飯命・三男:御毛沼命・四男:若御毛沼命(磐余彦尊)がいます。末っ子の磐余彦尊が後に初代天皇である神武天皇となります。五瀬命は弟たちとともに東征に従軍しましたが、浪速国の白肩津(あるいは生駒の山)での長髄彦との交戦中に長髄彦の矢に射られて瀕死の傷をうけます。五瀬命の「我々は日の神の御子だから、日に向かって(東に向かって)戦うのは良くない。廻り込んで日を背にして(西に向かって)戦おう」という助言によって一行は南へ廻り込んみましたが、紀国の男之水門に着いた所で、射られたときの傷が悪化しました。五瀬命は「賊に傷つけられて死ぬとは」と雄叫びしたので、その地を男之水門(雄水門)といいます。古事記によれば紀国男之水門で、日本書紀によれば紀国竈山で亡くなり、竈山に陵が築かれたと言われています。ところで、神武天皇は四兄弟でした。【長男・五瀬命】神武天皇と一緒に東征したものの、長髄彦から傷を負いここ和歌山の窯山神社の辺りで亡くなります。【次男・稲飯命】神武東征に従いますが、熊野に進んで行くときに暴風に遭い、「我が先祖は天神、母は海神であるのに、どうして我を陸に苦しめ、また海に苦しめるのか」と行って、剣を抜いて海に入り、鋤持(サヒモチ)の神になったのだそうです。【三男の御毛沼命】一緒に東征したものの、九州の高千穂の辺りで鬼が暴れて思うようにしているとの知らせを受けて、九州へ帰り鬼をやっつけてその地を治めたとのことでした。【四男・神武天皇】東征を果たし、今の天皇の祖となりました。その神武天皇の兄弟を祀っている神社をpleさんの安仁神社で紹介してくださっています。兄達を祀ってあるので安仁神社(あにじんじゃ)とは面白いですよね。
2009.04.25
コメント(2)
-

塩竃神社
塩竃神社の御祭神は製塩法を伝えた鹽槌翁尊で、もともとはすぐ北に鎮座する玉津島神社の祓い所す。御神体の塩槌翁尊は、輿の窟と呼ばれる窟に鎮座する、海の幸、安産の神様として親しまれてきた神社です。私も息子を妊娠した時に腹帯をここで頂きました。祠は、海風により自然に出来た洞窟です。祠の中には小さな拝殿が造られています。元は輿ノ窟(こしのいわや)と呼ばれていたのだそうです。塩竃神社のちょうど目の前にあるのが不老橋(ふろうばし)です。この橋は、片男波松原にあった紀州東照宮御旅所の移築に際して、第10代紀州藩主徳川治寶の命によって架けられたのだそうです。私達が和歌山市に住んでいたのは、今から20年くらい前から7年間です。当時の和歌浦はこんなにきれいに整備はされていませんでした。当時はバブルの少し前です。和歌山市のリゾート開発が始まろうとしていた時のことです。テレビを見ていたら、突然この不老橋をクレーン車が壊そうとしているのです。そういえば、少し前に不老橋を壊すと新聞に出ていました。私は、新聞を読んでなんてことを…、と嘆いていたのを覚えています。そしてついにその当日、クレーン車は不老橋にガーンと横殴りの一発を入れたのです。うわ~、酷い。そう思った瞬間、クレーン車は動きを止めました。そして、その後工事は一旦中止になったのです。一体、何事が起ったのかはいまだに定かではありません。しばらくして、不老橋の前を通ると橋の一部崩れたところがけが真新しいコンクリートで白く光っていました。私は悲しくなって、胸が重くなったものです。それから、そのことはずーっと忘れていたのですが今回この不老橋を見ると何とも、驚いたことにあの時の白く光っていたコンクリートは無くなっています。どうしたのでしょうか。誰かが、壊れたところを組み合わせたのでしょうか。それとも、同じような素材を探してきて修復しなおしたのでしょうか。20年の歳月が、あの全く素材の違うぺったりしたコンクリートを同じ素材の石に変化させたとは到底思えないのですが…。いずれにしても、今はあの思いつきのようなクレーン車での破壊のあとは全く残っていません。私と夫はなんだかキツネにつままれたような不思議な感覚にとらわれているのです。でもまあ、元に戻って良かったということなのでしょうね。そのあと、和歌浦の片男波へ向かいました。それから、和歌浦はとても綺麗になっていました。片男波は以前よりもいっそう整備され、観光客にも地元の人にも愛される美しい海なっていました。このあと、竃山神社へ向かったのでした。
2009.04.24
コメント(8)
-

玉津島神社
玉津島神社には、雅日女尊(わかひるめのみこと)、息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと=神功皇后)、衣通姫尊(そとおりひめのみこと)が奉られています。御三人様ともお美しく大変魅力的な方です。神社好きの女性でしたら、この玉津島神社はお好みのではないでしょうか。私も、『美人』というキーワードにはついつい反応してしまします。(笑)稚日女尊さまは伊奘諾・伊奘冉二尊の御子であり、天照大御神の妹神に当たられ、後世またの御名を丹生都比売神と申し上げます。息長足姫命さまは神功皇后(仲哀天皇の皇后で、応神天皇の母)のことです。皇后が海外に郡をおすすめになられた時、玉津島の神(稚日女尊)が非常な霊威をあらわせられました。玉津島の神を尊崇せられが皇后は、御自身も合祀されることとなりました。衣通姫は第十九代允恭天皇の妃で容姿端麗でまばゆいばかりの肌の細やかさからその肌の美しさは衣を通しても光り輝くためその名で呼ばれていました。また、大変聡明な方だとも言われています。允恭天皇は慈悲深い天皇だったが、壮年になって病に冒され半身不随となり天皇の位を辞退しようとしたところ、衣通姫は半島から薬師を招き天皇の御病気を治されたというお話が小説になっていたりもします。小野小町が参拝の時に上掛けをかけたと言う「小野小町袖掛けの塀」です。ここにも美女が登場です。しかも、美しいだけでなく和歌で有名な彼女です、そうとう聡明な方だったのでしょうね。美しく、聡明な三柱の神様を祀る神社らしく何とも言えない気品を感じる社です。三柱の神様にあやかって美しくなれるようにといつもとはちょっと違うお願いをしてみたくなるほどです。これは、以前和歌山市吹上辺りにあった根上松です。凄いですね。和歌の神として知られる衣通姫尊が御神体であることから、山部赤人や松尾芭蕉などが詠んだ和歌や俳句を刻んだ歌碑が建てられ、三十六歌仙の絵馬が飾られています.ここからほど近い紀三井寺では、『孝行者の紀伊国屋文左衛門が母を背負い、この坂を登って参拝に行く途中、草履の鼻緒が切れてしまった。そこへ、ここ玉津島神社の宮司の娘かよが通りかかり、鼻緒をすげ替えた。これが縁でふたりは結ばれ、宮司が出資したみかん船で文左衛門は大儲けした。』という話があります。私は和歌山市に住んでいた時はここから本当に近かったので、子供を連れて何度も来たことがあります。そのころは、神社に興味を持っていたわけではなかったのですがなぜかこの神社だけは好きでした。思い出深い神社です。海のそばにあり、とても気持ちがいいというのも理由の一つです。そして、この神社のすぐ隣に「塩竃神社」があります。そちらの方へも行ってみました。
2009.04.23
コメント(3)
-

日前宮
紀伊の国一宮日前宮です。祭神 日前大神(ひのくまのおおかみ)相殿 思兼命(おもいかねのみこと) 石凝姥命(いしこりどめのみこと) 祭神 國懸大神(くにかかすのおおかみ)相殿 玉祖命(たまおやのみこと) 明立天御影命(あけたつあめのみかげのみこと) 鈿女命(うづめのみこと)和歌山市の町中からほど近いところにこんなに素敵なところがあったなんて。私は、7年も和歌山市に住んでいたのに、ここに来たのは先月が初めてでした。入口辺りには来たことがあります。娘のお宮参りで来たので、写真にはちゃんと写っています。でも、拝殿までは来なかったようです。始めてくる日前宮の拝殿は厳かで、凛とした空気に包まれています。いつまでも離れがたい気持ちでいっぱいです。そろそろ帰ろうかと離れても、また戻ってしまったり…。それを何度か繰り返してしまいました。でも、いつまでもいるわけにはいきません。後ろ髪を引かれつつ、次は玉津島神社へ向かったのでした。
2009.04.22
コメント(0)
-

大野寺
室生寺から駅の方へ下って行く途中に、大野寺があります。門の前の駐車場に車を止めて、中に入りました。大野寺は役行者が開いたのだそうです。空海が室生寺を再興する時、この地を西の大門と定め一宇を建て、弥勒菩薩を安置、「慈尊院弥勒寺」と称したのだそうです。ここは、桜の名所で枝垂れ桜が綺麗なはずなのですが、今回は残念ながら少し遅かったようです。散りかけていました。大野寺対岸の岩壁に彫られているのは高さ14メートル、左手を上げ、右方向に歩み出すような姿です。刻み込まれた衣紋も美しく、磨崖仏としては最大なのだそうです。 桜は残念だったのですが、庭園は色々なお花が咲いてとても綺麗です。桜の綺麗な時にもう一度来てみたいです。この日の目的はこれで最後です。ところで、今日本中不況の嵐でたいへんですね。みんなが幸せでいられますように、そんな思いを込めての今回の参拝でした。お天気もよく、気持ちのいい一日をありがとうございました。感謝の気持ちで、大野寺を後にしたのでした。
2009.04.21
コメント(6)
-

室生・龍穴神社
室生寺から10分くらい歩いたところに龍穴神社があります。なんて、書くとよく知っているように見えますがそうでもないのです。随分前からpleさんのブログでいつかは一度行ってみたいと思っていたのですが、今回急遽決まったのでちゃんと準備しておかなかったのでちゃんとつけるかドキドキでした。龍穴神社は室生寺よりも古く、室生寺は龍穴神社の神宮寺ともいわれ龍王寺と呼ばれていた時期もあったようです。 うっそうたる巨杉に囲まれて昼でも暗い神社です。御祭神となっているのは「タカオカノカミ」で、イザナギの命が、火の神を切った時に出てきた神様です。近くの龍穴に棲むとされてきた。そのため古代から雨乞いに霊験あらたかなのだそうです。また地元の伝説では、奈良の猿沢池に住んでいた龍が池に女性が身を投げたので、住まれなくなってこっちに飛んできたとなどという話もあるみたいです。連理の杉です。杉も夫婦仲良しなのですね。ただし、裏へ回ればちょっとしたことがあるのですが…。興味のある方はppleさんの室生・龍穴神社のブログを見てみて下さい。確かにそうでしたフフフ…。杉も人間も同じなのかも。さて、次はこの神社の近くにある天岩戸に行きたいのですがどうも近くに見当たらないのです。室生寺とここの間くらいのところにあった地図で見ると、本当にすぐ近くのようです。神社の横の道を登ってみたのですが、行きどまりです。そういえば、神社の前に道があります。夫はきっとこっちだと言うのです。なんか違う気がするのですが、とりあえず行ってみました。すると、そこに私達よりも少し年配の御夫婦がおられてどうも道を探しているようなのです。私達 「あの、道をお探しですか?」御夫妻 「ええ、天の岩戸へ行こうと思ってさっきから30分くらい探し回っているのですが、分からなくて諦めようかどうしようか迷っているのです。」そういえば、pleさんから教えていただいていたものがあることを思い出しました。え~っと、字が小さくてちょっと読みにくいのですが落ち着いてちゃんと読んでみると、どうも神社の前の道を上流に登って行くようです。私達 「あ~、どうもこちらではないみたいですよ、上流の方に行ってみましょうか。」御夫妻 「そうですか、それは助かりました。行ってみましょう。」ということで、私たち二人はその、年配のご夫婦と歩き始めました。歩きながら、色々お話をさせていただきました。御夫婦 「どちらから来れれたのですか?」私達 「大阪です。」御夫婦 「私達と同じですね。」私達 「天岩戸は楽しみですね。」御夫婦 「枚方の方にも天の岩戸があって、間をくぐれるのですよ。」あ~、それ先日のpleさんの磐船神社のブログで書いてあったあの天の岩戸のことではないですか。私 「そこ知ってます、でもまだ行ったことがないのです。」やっぱり、あそこは有名なのですね。また、行きたいところが増えてしまいました。などと話しながら歩いていると、向こうから若いカップルが歩いてこられました。すると、御主人様が道を聞いておられました。御主人様 「天の岩戸へ行かれたのですか、ここから遠いですか?」若いカップル 「もう少し行かれたら看板があるのでそこを、左に曲がれば行けますよ。そこから、少し山を登るのとありますよ。」 そうなんだ、もう少しで着くのですね。私達は若いカップルにお礼を言って分かれました。女性の方の胸に付けていたブルーの勾玉が綺麗で印象的でした。しばらく歩くと、看板がありそこを右に曲がり山を登って行きました。夫は歩くのが苦手なので、そろそろ疲れてきているみたいです。 御主人様 「疲れてきたみたいですね。」夫 「はい、ちょっと。ところで、バスで来られたのですか?」御主人様 「駅から歩いて来たのですが、間違って近道を通ってしまったので、2キロ程、損をしたので、もう少しどこかを歩こうと思っていたのでよ。」え~、すごい。私も夫も驚いてしまいました。駅からここまでって、結構な距離があるのですよ。でも良く見ると、結構この辺りは駅から歩いている人のかもしれません。なんだかんだ話しながら歩いて山道を登っていると、ついにありました。天の岩戸です。鳥居がありました。天の岩戸の中に入れるようです。さっそく私は入ってみました。確かに、その雰囲気があります。夫 「さあ、天の岩戸があったから、もう引き返そうか?」私 「そうやね、でももしかしたら龍の滝が近くにあるかもしれへんからちょっとだけ歩いてみようよ。」ちょっとだけ、ちょっとだけ…と言いながら進んで行きました。見えました。小さな鳥居があります。確か、ここを下れば龍の形の滝があるはず。凄い、神聖な雰囲気です。ちょっと高千穂峡の雰囲気に似ています。ありました。写真ではちょっと見えにくいかも知れませんが、山の上の方から水が流れてきてまっすぐではなくて龍が空に登って行くかのように斜めに流れています。目の前には龍が隠れていたのではと思われるような穴があります。これが龍穴なのでしょうか。手を合わせてしばらく佇んでいました。私は大満足。夫はちょっと疲れ気味ですが、ほっとした様子。さっきの御夫婦はもう少しゆっくり見ていたいようだったので、ここで別れて私達は、室生寺の方へ戻りました。そういえば、まだお昼をしていなかったので小さな茶屋のようなところでお昼を頂きました。しばらくすると、さっきの御夫婦が通られました。御夫婦 「あ~、早かったですね、休憩ですか。私達はこれから歩いて駅に向かいます。」私達 「そうですか、ではまたどこかでお会いするかも知れませんね。さようなら。」そう言って別れて、私達は食事を終え車に乗って室生寺から下って行きました。私達は、御夫妻とどの辺りですれ違うかを楽しみにしていたのです。そろそろ追いつくかなな…どと考えながら。いくら速く歩くと言っても、もうそろそろいるんじゃないの。などと言いながら。ところが、ついに山を降り切った辺りまで行っても、ついにすれ違うことはなかったのでした。ふ~ん、もしかしたら、あの御夫婦は龍穴神社の『連理の杉』が人間の姿になって表れたのかもなんて思ったりしたり。そういえば、最初のカップルも怪しい…。あの辺りで男女の二人連れを見たら、もしかしたら『連理の杉』が人間に姿を変えているのかもしれませんよ。なんて、ことはないですよね。(笑)さて、このあとは最後の目的地、大野寺です。
2009.04.20
コメント(12)
-

室生寺
またまた、思いつきの旅です。昨日、行ってきました。もちろん相手は夫です。いつものように、朝起きて朝食を食べてからお天気を見て、「今日はどこへ行こうか~。」と、夫。よっしゃ、これでどこかへ行ける。そういえば、私が、「佛隆寺の桜が終わったので、室生寺の石楠花はどうですか?」と聞いたら、「石楠花は良いの、佛隆寺の桜にこだわっているのだから、来年ね。」と、ちょっぴり冷たい返事だったし。「じゃあ、室生寺と龍穴神社と大野寺へ行きたい。」と私が言うと、夫は。「良いよ、じゃあ出かけよう。」「えっ、今すぐ?」「うん、さあ行こう。」ということでいつもの如く、決まればあっという間に家を出ることになるのです。そうそう、夫の気が変わらないうちにというのも重要な要素。ということで、なんの用意もないまま、とりあえず家を飛び出したのでした。そういえば、住所くらい持って行くべきだったと思いながら。簡単な近鉄のパンフレットが車に積んであったはず…。行き先をナビで設定して出発です。着きました、室生寺です。桜は終わっていましたが、人は多いですね。もう、石楠花が咲いています。綺麗ですね。う~ん、良いにおいです。これが室生寺の五重塔です。確か、私は小学生の時に遠足で来て以来です。あの時は、室生口から歩いたな~。本当に遠く感じてへとへとになったことを思い出しました。五重塔は、平成10年の9月の台風7号で被害を受け、その後新しく建て直したのですよね。ここの金堂の仏像は、凄いです。釈迦如来立像 、十一面観音像 、地蔵菩薩立像 、帝釈天・薬師・文殊 、十二神像 、釈迦如来坐像 、如意輪観音菩薩・弥勒菩薩像 …。教科書で見た記憶がありますが、こうやあって目の当たりにすると圧巻です。さて、このあと私と夫はこの日一番の目的地である龍穴神社へ向かったのでした。
2009.04.19
コメント(10)
-

根来寺
4月5日のことです。朝起きて、夫が「どこか行きたいところない?」なんて言ってくれたので、じゃあ桜の季節だし根来寺でもということで、出かけたのでした。夫は本当は家の近所のつもりで来たのかも知れませんが、「お天気も良いし、じゃあ出かけようと」いつもの通りアバウトな二人です。私も先輩や友達とどこかへ行く時は、電車なので結構緻密に計画を立てたりもします。電車の時刻はちゃんとネットで検索して、行き先を予習しておいたりしていっぱいプリントアウトしたものやら、地図やら、パンフレットやらを持ち歩くのです。でも、夫と行く時は車ですし、とにかくいつも思いつきの行き当たりばったりです。根来寺も、行くと言ったものの本当に着けるかどうか分かりませんでした。なんせ、もうその信号を曲がれば根来寺という辺りから、以上に車が混み始めたのです。夫は言いました。「やっぱり止めて、和歌山へ行こうか」と。え~、根来地が目の前なんですよ。もう歩いても行けそうな距離なんですよ。でも、確かに駐車場に入るのに30分以上はかかりそう。夫は人ごみが好きでないし、何と言っても渋滞が大嫌い。でも、私はここまで来たらどうしても行きたい。結局、渋滞のど真ん中に突進ということになってしまいました。当然、夫はイライラし始めます。………。ところが、良く見れば根来寺からかなり距離はありますが、何か公園の駐車場らしきものがあるではありませんか。夫は歩くのは大丈夫。ということで、蟻のような動きで進みながら無事、公園の駐車場に止めることが出来たのでした。そして、10分くらい歩いたでしょうか無事、根来地に着いたのでした。確かに桜は凄く多いです。でも、それ以上に人も多い…。多宝塔がありました。秀吉の根来寺焼き討ちの際に延焼を免れた多宝塔(根本大塔)には、この時の火縄銃の弾痕が今でもはっきり残っていて、「この寺が普通の寺ではなかったんだ。」とつくづく思い知らされたのだそうです。根来寺、根来衆といえば、やはり戦国時代に活躍したのですね。奥の院へ行く途中の水道です。良く見ると牛の頭です。(かなり、リアルですよね。)今年は丑年だからでようか。なんか、去年はミッキーマウスだったらしいのです。確かに、ミッキーはネズミですよね。根来寺は人が多いな~、と思っていたら意外にそうでもないところを見つけました。不動堂です。身代わり不動さんです。(興教大師が暴徒に襲われた時、身代りになられた不動明王なのだそうです。)中へはいると、文殊菩薩、反対側には七福神さまたちがいらっしゃいます。それが、どの仏像も素晴らしいのです。特に七福神様たちは本当に、良い感じなのです。落ち着くわ~。私はここが一番好きです。とにかく、良い表しにくいのですが、ほっとすると言うか、なんとも柔らかい空気に包まれているのです。あ~、来て良かった。このあと、出店でおでんと焼き鳥を食べてご機嫌で、次の目的地の和歌山市へ向かったのでした。
2009.04.18
コメント(4)
-

荒立神社 (宮崎・高千穂の旅12)
先月行った二泊三日の宮崎・高千穂の旅、訪問先がたくさんあって1~12までになってしまいましたが、今回で最終回です。よかったら、最後までお付き合い下さい。くしふる神社から5分くらい歩いた神代川の脇に天真名井があります。高千穂峡にある真名井の滝はここの水が地下水を通って流れおちているのだそうです。天孫降臨の際に天から種を移した地であると伝えられており御神水として崇められています。天真名井の脇の神代川を渡ったところに夜泣き石があります。昔から災いがある時は石が夜泣きして知らせたという伝説の石です。夜泣きの激しい赤ちゃんが触ると夜泣きが治ると言われています。とりあえず、私も触ってみました。あんまり意味はありませんが…。普通の石のようでした。さて、今回の旅の一番最後を飾るのが荒立神社です。天孫降臨の案内役であった、猿田彦の命とアマノウズメが結婚したと伝えられる地にあり、その名は荒木を使い急いで宮居を建てたことに由来するのだそうです。ご祭神の猿田彦命は交通安全や教育の神様。アマノウズメは芸能の神様として崇められています。最近では芸能人や、音楽家の人もたくさん参拝に来るのだそうです。三泊四日の宮崎・高千穂の旅もこの回で完結です。天気予報では本来毎日雨ということで、心配されたのですがなんとか乗り切ることが出来ました。目的地を離れたとたんに雨ということも何度もありましたが…。完全に雨だったのは、最後の一日だけというとてもラッキーな旅でした。思い返せば、一日目 えびの高原池めぐり二日目 高千穂の峰・天の逆鋒、霧島神社三日目 高千穂峡・真名井の滝、天の岩戸神社・天の安河原、高千穂神社の夜神楽四日目 くしふる神社、天真名井、荒立神社と、かなり強硬日程でした。鹿児島空港から宮崎へそして、熊本空港から帰って来たのでした。自分で計画した行きたいところだけ行くという我儘旅行でした。本当は韓国岳にも登りたかったし、もっと行きたいところもあったのですが決められた日数の中では、最大限に行けたしとても充実していたとの思いでいっぱいです。やはり、神様に守られていると実感しました。一言でいえば、“楽しかった”。またいつか、機会があれば行ってみたいです。もし、興味のある方には是非お勧めですよ。ここまで読んで下さった方、本当にありがとうございました。夢の中の宮崎・高千穂はここまでですが、また実生活に戻っていつものように関西の神社仏閣巡りの続きです。楽天で、写真の所蔵枚数がそろそろいっぱいになりそうです。今は、昔の写真を消しながら書き進めていますが、少しづつアメブロの方に移るしかないのかなと迷っています。いずれにしても、これかも、どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _"m)ペコリ
2009.04.17
コメント(6)
-

くしふる神社 (宮崎・高千穂の旅12)
高千穂の旅も途中になってしまっていました。あと、2回で完結です。もう少しだけお付き合いください。その日は、ついに雨が降ってしまい、傘をさしての参拝でした。本当はお天気の方がいいのですが、宮崎では次の機会にというわけにいかず、取り合えす、雨を気にせずに出発したのでした。猿田彦さんが道案内をしてくださっています。古事記に迩迩芸命(ニニギノミコト)が降り立った所を「筑紫(九州)の日向の高千穂のくじふる峰」と記され、その場所と考えられている「くしふる峰」の中腹にある神社です。天照大御神の孫、迩迩芸命(ニニギノミコト)が地上へ降り立った(降臨)の地(下段注参照)として伝えられています。祭神は迩迩芸命(ニニギノミコト)、天児屋根命(アメノコヤネノミコト)、経津主命(フツヌシノミコト)、天細女命(アメノウズメノミコト)等鳥居をくぐると本殿です。ニニギノ尊さまのことを思いながら参拝しました。このあと、小高い丘を200メートルくらい山手へ登ると高天原遙拝所があります。天孫降臨後、神々がこの丘に立って、高天原を遙拝(遠くから拝むこと)した場所といわれています。周囲は人影も少なく、森に包まれ、遊歩道を歩いているとマイナスイオンを浴びとてもリラックスできます。神武天皇の兄弟神の生誕地と伝えられる「四皇子峰」や高天原の水の種を移したとされる「天の真名井」等が近くにあります。写真には雨粒が写りこんでしまいました。このあと、真名井の滝の水源「天真名井」へと足を伸ばしましたのでした。
2009.04.16
コメント(2)
-

滝谷不動
日本三大お不動さんは一つ滝谷不動へ行ってきました。私は不動明王が好きで、時々ここへ来たくなります。本当はリンちゃんに教えてもらった真言を言って参拝したのですが何と言っても不動明王さまの真言は長いのです。(きょうはリンちゃんと一緒に来たのではないのです。真言をネットで出して持ってきました。)ノウマク サラバタタギャテイビャク サラバボッケイビャク サラバタタラタ センダマカロシャダ ケン ギャキギャキ サラバビキンナンウン タラタ カンマンリンちゃんは暗記しているのですが、私はメモを見てもうまく言えません。何と言ってもどこで切るのかさえよく分からないのです。一生懸命読むのですが、舌を噛みそうです。日本語の意味に直すと(全方位の一切如来に礼したてまつる。一切時一切処に残害破障したまえ。最悪大忿怒尊よ。カン。一切障難を滅尽に滅尽したまえ。フーン。残害破障したまえ。ハーン。マーン。)ということらしいのですが、これもまた難しい。最後のカンマンのは「カン」が不動心、「マン」は、柔軟心を表しているらしいのですが、今日はそれだけを覚えることにしましょう。【たまたま博士によると、いきなり火界呪 唱えなくともいいのだそうです。詳しくはたまたま博士のコメントをみてください。やっぱりネットをそのまま使うのは問題がありそうです。(^_^;)。リンちゃんにちゃんと聞いておけばよかった…。】ここでいるとまるで山の中にいるようで、別世界のようです。(実は車で10分も走ると、街中に出るのですが…。)西国三十三ヵ所巡りが出来るところがあります。西国三十三ヵ所の仏像のミニュチュアがあり、それぞれのお寺の土を床の下に埋め込んであります。最近はいくつかのお寺へ行ったので、思い出しながら参拝しました。滝谷不動は、本当に滝があるのです。ここで、水に打たれて滝行をすることが出来るのです。ちょっと、水を触ってみたら凄い勢いの水力です。とても、一瞬でも耐えら得そうにないのですが…。写真の右の方にお不動さんがいらっしゃるのがみえるのでしょうか。不動明王は動物に例えると龍なのだそうです。だから、お水に関係しているのかしら。このあと、身代わりドジョウを川へ帰してあげました。ちゃんと、家族のもとへ帰ったかしら。滝谷不動ははもう何度も来ていますが、桜が咲いていたのは初めてです。この桜は、遅咲きの八重桜でしょうか。いつ来ても気持の良いところです。また来たいなと思いながら、滝谷不動を後にしました。
2009.04.15
コメント(2)
-

枚岡神社
本当は今日は宇太水分神社、、佛隆寺、室生寺、龍穴神社などと歩くつもりだったのですが、雨で中止になってしまいました。少々の雨では滅多に中止にはしないのですが、今日ばかりは降水確率100%。これでは山道は危ないということで駅まで行ったのですが泣く泣く帰ってきました。実は昨日、新しいパンプスを履いていたせいでしょうか、夜中に足がつって痛くて困っていました。朝起きて、湿布を貼って足を引きずりながら駅まで出かけたのすが、中止と決まって実は半分ホットしたのでした。室生寺はシャクナゲの季節でも紅葉の季節でもきっと綺麗なのでしょうけど、佛隆寺の桜は今年は今日が最後、とても残念です。ところで、私はこれでも遊びの合間に仕事をしているのではないのです。ちゃんと、仕事の合間に遊びを入れているのです。(本当です。)ということで、日程は急には変えられないので、決めると大体頑張って行くことになるのです。何も足が痛くても行かなくてもいいんじゃないのという声もあるかもしれませんが、私なんぞまだまだ甘いのです。pleさんは先日、足が悪くてまだ病院に通っているのに、足を引きずって、高野山でなんと2万歩も歩かれたのです。見習わなくてはいけません。目標とするpleさんに近づくために今日は、足を引きずってでも歩こうと思ったのですが、今回は最寄りの駅までという残念な結果になってしまいました。でも、また晴れれば頑張ります。鍛えなければいけません。実は私はこれでも、結構体が弱くてしょっちゅう病院へ通っていました。ところが、神社仏閣を参拝するようになって不思議と体が楽になってきたのです。本当の意味でも元気をもらっています。ありがたいことです。ということで、今日は先日枚岡神社へ行ったこと木のことを書くことにしました。ここもpleさんのブログを見て、以前から行きたった神社だったのです。私は神社仏閣へは、平日は先輩と行くことが多いです。土日は大体、夫と行くというパターンです。ところが、先輩は忙しい人なので私にばかり付き合ってはいられないのです。ということで、私も必然的に先輩以外の友達と出かけることになってしまいます。先輩以外といえば、主に二人います。一人は、有名どころが好きなトキちゃんです。最近では又兵衛桜へ行きました。京都では大原三千院や、貴船の川床料理や紅葉電車に乗ったりしました。もう一人はリンちゃんです。私のブログを何度も読んでいただいている方は、もうお気付きかも知れませんが、リンちゃんはちょっと霊感というか何か感じる力をもった女の子なのです。私よりも8歳くらい若いのですが、お寺や仏教のことをよく知っていて私に教えてくれます。朝のお勤めも欠かさずされているので、真言は全部知っているので、いつも二人で仏様の前に立つとそっと教えてくれます。どちらかといえば、私は神社好きで、リンちゃんはお寺好きということになります。それで、二人で行く時はお寺と神社を取り混ぜて参拝することになります。と、ここまで書いて枚岡神社のことに話は戻るのですがこの神社へはリンちゃんと行ったのでした。この日は、清荒神、売布神社、中山寺というコースだったのすが朝早く出たもので、お昼くらいに三つとも全部参拝が済んでしまったのです。それで、3dayチケットもあることだしと急遽、枚岡神社へ出かけることにしました。リンちゃんは、お寺好きということで枚岡神社のことは知りませんでした。ところが、枚岡駅にを降りて、鳥居に近づいた時のことです。リンちゃんは「何か感じる!」と叫んだのです。霊気があるのでしょうか。手をかざして、「この辺りは感じる。」などと霊気の結界を探しているのです。日が当たっていても、冷たく感じるところもあれば当たっていなくても普通に温かいところもあります。やはり、鳥居のちょっと外側あたりが、その境界のようです。私はといえば、あまりそういったことを感じる方ではないのですが、なぜかリンちゃんといるときだけ、ちょっとだけ分かるような気がします。境内を歩いて行くと注連縄のようなものが見えました。左右に、狛犬さんがいるはずです。良く見ると、ここの狛犬さんは鹿で出来ています。左の鹿は子供を抱っこしています。春日大社も鹿だったような気がします。(間違っていたらごめんなさい、誰か詳しい方教えて頂けないでしょうか)春日大社はここ枚岡神社から分霊されたのです。ですから、枚岡神社は元春日というらしいのです。(詳しくいうと、春日大社はの第一殿は、茨城県の鹿島神宮から迎えられた武甕槌命(タケミカヅチのミコト)、第二殿は、千葉県の香取神宮から迎えられた経津主命(フツヌシのミコト)、第三殿は天児屋根命(アメノコヤネのミコト)と第四殿の比売神(ヒメガミ)が大阪府枚岡(ひらおか)神社から迎えて祀られているのだそうです。) 拝殿です。神聖な空気に包まれています。リンちゃんは、なぜか突然とても眠たくて目が開けていられないくらいだと言うのです。心地よく、不思議なくらいの突然の眠気のようです。やはり、何か感じているかも知れません。しばらく、椅子に座って色々なことを話していました。知らない間に、すごく時間がたっていたみたいです。枚岡神社は、pleさんも何か感じたようなことを書いておられました。大阪一のパワースポットだとも。確かに、リンちゃんを見ていて本当だと思いました。しばらくいる間に、霊気にも慣れてきました。鳥居から一番近いおうちは1メートルくらい霊気に包まれているとリンちゃんは言っていました。いいですね、家にいながらいつも素晴らしい“気”の中にいるなんて。私は高校生の頃いつもこの沿線で通っていたので前を通っていたのに、こんなに素晴らしい神社があるなんてちっとも知りませんでした。でも、あんまりみんなに知らせて大勢の人が押し掛けるようになるのも困るし…。また、来たいと思いました。本当にこんな都会の真ん中にあるのに、不思議で特別な神社でした。(余談です)ちょっと恥ずかしいのですが、実は今日は私の誕生日です。先輩もあと1週間くらいで誕生日なので、合同誕生日会をするはずだったのです。雨で本当に残念です。日程を変更して誕生会をしなくては。年齢は聞かないでくださいね、かなりお目出度いので。(笑)このくらいの年になると、1年1年が大切です。毎日の健康に感謝しています。そして、いつも拙い私のブログを読んでくださっている温かい皆様に心より感謝申し上げます。m(_ _"m)ペコリ
2009.04.14
コメント(8)
-

長谷寺
榛原駅から一駅隣の長谷寺駅で降りて歩いて15分で長谷寺に着きます。長谷寺は山号を豊山( ぶさん )と称し、寺号を長谷寺( はせでら )と言い、正式には豊山神楽院長谷寺というのだそうです。ちょうど、長谷寺観音特別拝観をしていました。本当に大きな観音様です。お御足に触れることができるのです。僧侶の方に手に、五色の紐を撒いていただきました。そして、観音様の前では真言を唱えて頂きました。とてもありがたい気持ちになりました。本堂から見える五重塔が桜の向こうに輝いています。平安時代になって観音信仰が盛んになると、右大将藤原道綱の母が書いた「蜻蛉(かげろう)日記」や、菅原孝標女(すがわらノたかすえノむすめ)が書いた「更科(さらしな)日記」に長谷寺詣のことが載っていて、また、清少納言の「枕草子」では「正月に籠りたるは、・・」と記されて、今も正午に響く法螺貝の音に驚き、紫式部の「源氏物語」では22帖、玉葛の君は初瀬詣が舞台です。686年(朱鳥(あかみどり)元年)に第40代天武天皇の病気平癒のため、ここ「こもりくの泊瀬山」の西の岡(現在の本長谷寺)に川原寺の僧、道明(どうみょう)上人が三重塔(現在は、五重塔の直ぐ南側に礎石だけが残っています)を建立して、国宝の「銅板法華説相図(千仏多宝塔銅盤、今は宗宝蔵に安置)」を安置したのが長谷寺の始めで、以来ここを「本長谷寺」と称し、今は南隣に「五重塔」が建っています。長谷寺は、真言宗豊山派の総本山として、 また西国三十三観音霊場第八番札所として、 全国に末寺三千余ヶ寺、 檀信徒はおよそ三百万人といわれ、 四季を通じ「花の御寺」として多くの人々の信仰をあつめています。牡丹でも有名ですが、桜もまた本当に見事です。本坊から見る長谷寺が一番綺麗なのではなどと思ってしまいます。桜にうずもれてしまいそうな長谷寺の本堂は離れがたいくらいの美しさです。長谷寺を出て、参道を歩いていると可愛い花を見つけました。木に直接咲いているのです。何とも可愛くてしばらく見入ってしまいました。さて、この日の予定は終了です。ゆっくりと参道を歩き、駅へと向かいました。
2009.04.13
コメント(4)
-

阿紀神社
又兵衛桜から歩いて10分くらいのところに、阿紀神社があります。ご祭神は天照皇大神、秋田比売神、邇邇杵命、八意思兼神 です。神武天皇が紀州熊野の難所を越えて宇陀の地まで進軍してきたとき、この地で御祖の神(=天照大神)を祭って大和の方へ押し出すと、日神の威勢に背中を後押しされて賊軍を打ち払うことができたので、この地に天照大神を祭祀するようになったと言われています。鳥居をくぐり少し進むと拝殿があります。とても厳かな雰囲気です。この神社の社殿は神明造り南向きであり、伊勢神宮正殿とまったく同じ建て方になっています。板塀に囲われているので、詳しくは分かりませんが、建物全体が直線的です。屋根を見ると、長く突き出た破風板(はぶいた)が左右に交わり、その先端が千木(ちぎ)になっています。棟の上に甲板(こういた)を付け、その上に堅魚木(かつおぎ)が列べてあります。 境内社です。一殿 - 祭神は日臣命・月夜見命・大国主命 二殿 - 祭神は事代主命・品陀別命・和多津見命 三殿 - 祭神は須勢理比売命 阿紀神社の境内中央には、古びた能舞台が据えられています。宇陀の地は元和年間に織田藩の治所となり、その三代目の当主・織田長頼の頃に阿紀神社で能楽が奉納されました。それを起源として、この能舞台では、寛文年間から大正時代まで能楽興業が行われてきたのだそうです。 大宇陀町は平成4年に薪能をこの神社で再開し、平成7年からは「あきの蛍能」として6月中旬に能楽を開催しているのだそうです。能の最中に明かりをおとし、蛍が闇に放たれて幻想的な世界を演出するのだそうです。蛍が放たれた神楽殿、見てみたいものです。阿紀神社は元伊勢だけあって、本当に素晴らしい。境内を歩くだけで、ちょっと違うなって思います。神社って、私にとって特別なところですよ。神様がいらっしゃる、本当にそう思えるのです。
2009.04.12
コメント(4)
-

レッドクリフ part.2
レッドクリフ part.2を見てきました。周愈(トニーレオン)や諸葛孝明(金城武)さんたちはもちろんカッコよかったのですが、私個人的には尚香(孫権の妹)とその親友でもしかしたら尚香ちゃんが好きだったと思うけど、魏の千人隊長さんが好きでしたね。貧しい生まれで、家族のために戦いに来た心優しい青年でした。最後まで尚香ちゃんを、男の子だと思い親友として何度も助けてくれたのです。そして、戦いの途中に矢を受けて亡くなってしまいます。ちょっと、涙がホロリと出てしまうシーンでした。あと、part.1の時に劉備の赤ちゃんを助けた趙雲は、相変わらずカッコよかったです。ありえないシチュエーションで戦って、見事にやっつける。今回も最後まで期待道理の活躍をしてくれました。中村獅童も見せ場もあって良かったですよ。海賊の親分って感じよく出てました。待ちに待ったレッドクリフpart.2 間違いなく楽しめると思います。是非見に行ってくださいね。part.1は4月12日PM9:00から朝日系列で放映です。まだ見ていない方は是非、見て下さいね。
2009.04.11
コメント(6)
-

又兵衛桜
榛原からバスに乗って『又兵衛桜』を見に行きました。駅に着くと、臨時の直通バスが出ていたのでラッキーでした。桜が咲く綺麗な道を通って約20分で、又兵衛桜のすぐ近くでバスは止まりました。本当に大きくて素晴らしい桜です。近くに咲いている桃もピンクでかわいいですね。本当は又兵衛桜は10日くらいが一番満開なのかもしれません。地元の人が言うには、この先の天蓋寺の桜が今一番の見ごろなのだそうです。そこで、ちょっと行ってみました。確かに、凄いここの桜は満開でとても美しい。地元の人はさすがです。ところでこの天蓋寺、なんか変です。お寺らしくないのです。実はこの天蓋寺は平成11年1月31日未明(午前2時ころ)不審火により本堂、大成徳堂、倉庫の三棟が全焼したのだそうです。御本尊の薬師如来様や諸仏は何とか火災を免れたようですが建物は残念で仕方ありません。神様や仏様はちゃんと見ているのですよね。酷いことをすると、きっと後で後悔すると思います。もちろん、そんなことをしてしまうくらい辛い生活なのかもしれませんが、その試練を乗り越えてこその人生なのにね。復興のための募金に参加してきました。一日も早く、もとのお寺になることをお祈り申し上げます。
2009.04.10
コメント(10)
-

再び、弘川寺。
弘川寺は桜の季節に三年連続で来ていますが、行こうと思った日が雨で行けなかったり、せっかく弘川寺へ行っても満開には早すぎたり遅すぎたりで、一番いい時には行けずじまいでした。今年も、前回弘川寺へ行ったのは3月29日で、少し早すぎて桜はまだ3分咲きくらいでした。今日は仕事も休みだし、良いお天気だし、そうだ思い切って行ってみよう!朝起きて、そう決めました。思ったとおり、弘川寺の桜は満開です。お花が飾ってありました。青空に桜、私の好きな景色です。山を下りて帰ろうと思ったら、チューリップの向こうに鮮やかな桜が見えました。近づくと濃い色と薄い色の桜です。もっと近づくと、薄い色に見えた桜の同じ枝から濃い色の桜も咲いています。凄く綺麗。今日は、珍しい桜を見ることが出来ました。そして、念願の弘川寺での満開の桜も体験できました。とても良い一日でした。桜の神様がいるとしたら、こころから感謝いたします。と、さっきはここまでだったのですが実は重大なミスに気付きました。お恥ずかしいのですが、花のことを知らない私は2色の珍しい“桜”と思いこんでいたのですが、実は“桃”だったみたいです。お花に詳しいマダムに聞いてみたら『あれは、桜じゃなくて、「桃」だよ。桜は、ピンクの濃いのや薄いのは在るけど、一色だけだよ。「桃」はね、接ぎ木で、赤と白の花が咲く事で切るのよ。桜は樹を傷つける事を嫌がる樹だからね。源平桃と言って、多分、弘川寺のあの「桃」だと思うよ。ホームセンターでも売っているわ。』とのこと、トホホ。恥ずかしいです。でも、ちょっと勉強になりました。マダムありがとう。(*^_^*)ところで、西行法師さんに興味をお持ちの方は西行法師の生涯は参考になるとおもいます。西行法師さんは今の時代の私達をも惹きつけるのは真実を追究し続けた方だからでしょうか。|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆和歌山市の玉津島神社UPしました。よかったら、アメブロの方へも遊びに来て下さいね。
2009.04.09
コメント(6)
-

日向大神宮
随分前にpleさんのブログで見てからどうしても一度、行きたかった日向大神宮です。【 御祭神 】内宮・上の本宮 :天照大御神 :宗像三女神(多紀理毘賣命・市寸島比賣命・岐都比賣) 外宮・下の本宮 :天孫・天津彦火瓊々杵尊・天之御中主神鳥居が見えてきました。鳥居をくぐると外宮が見えます。なんと、五十鈴川まであります。五十鈴川を渡ると内宮です。伊勢神宮を、思い出してしまいました。ちゃんと厳かで、素敵な雰囲気ですよ。内宮の奥に、天の岩戸がありました。ここの天の岩戸は、高千穂町の天の岩戸神社とは違って、自由に中に入ることが出来るのです。もちろん私も入ってみました。なんだか、天の岩戸の中に入れてちょっとドキドキ。一瞬だけ天照大神さまになった気分を味わってみました。この神社はとても清楚で、伊勢神宮のミニュチュア版みたいで私は好きです。神社好きの方にはお勧めです。|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆アメブロ始めました、良かったら遊びに来て下さいね。
2009.04.08
コメント(0)
-

琵琶湖疏水
琵琶湖疎水は都が東京へと移り、人口も35万の都市から25万人へと激減し産業も衰退していく中で、京都復興の大事業として計画されたものでした。滋賀県の大津市、三井寺近くから長等山をトンネルで抜け、山科盆地の山麓、幾つかのトンネルを流れ、日ノ岡山のトンネルを抜ける経路、中でも長等山の第一トンネル(2,436)は当時、類をみない長大トンネルでした。この大事業に際して当時の北垣国道知事は工部大学、今の東京大学を卒業したばかりの21才の青年技師(田邊朔郎)を抜擢することになります。多くの反対もあったようですが、21才の若者に未来を託す決断をした北垣国道知事さんは本当に偉かったと思います。決断したのが明治14年、幾多の困難を乗り越え明治23年9月、竣工式を迎えます。これにより琵琶湖より京都への水運が可能になり、九条山より蹴上にかけては、582mに36mの標高差があり勾配が15分の1の急であるためインクライン(傾斜鉄道)により三十石船をそのまま台車に載せて上下させました。また蹴上発電所で発電された電力は日本最初の路面電車開業へとつながり、各家に電灯が灯ることになります。琵琶湖疏水の終点は↓です。琵琶湖疏水を通ってきた船はトロッコに乗って山の下まで運ばれます。そこで、船はトロッコに乗ったまま荷物を積んでここまで上がってきて、今度は船でまた琵琶湖疏水を上って行きます。そうやって、多くの荷物を運んだのですよね。凄い発想と凄い技術力ですよね。そのちょうど反対側に今では、トロッコの線だけ残っています。今ではインクラインは廃止されていますが、琵琶湖から山科を経て、南禅寺から鴨川への本流、そして南禅寺から哲学の道、北白川に至る分線は上水道、防火用水として、あるいはインクラインの桜並木、哲学の道を始めとする水辺に親しめる憩いの場、南禅寺水路閣は文化財として、竣工110年を迎える現在機能している琵琶湖疎水です。↓は今も現役の関西電力蹴上発電所です。さて、話は前後しますが、この琵琶湖疏水の途中に日向大神宮があります。pleさんに教えていただいて以来、どうしても行きたかった神社です。想像以上に素晴らしいところでした。内宮や外宮、天の岩戸もあります。続きは次回とさせていただきます。|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆アメブロはじめました、良かったら遊びに来て下さいね。
2009.04.07
コメント(2)
-

毘沙門堂
山科駅を降りて山側に歩くと毘沙門堂が見えてきました。枝垂れ桜がとても綺麗です。メジロがいっぱいとまっています。毘沙門堂の中に入ると、素晴らしい絵が何枚かありました。なんと、だまし絵なのです。見る角度によって長さの変わる机の絵だとか、歩きながら見ると体の向きを変える鯉の絵とか、ちなみにこの絵の作者は円山応挙さんです。それから、円山応挙さんが影響を受けた狩野さんの歩きなががじっと見ていると、体の方向を変える獅子の絵とかもありました。それから本堂には毘沙門天さま、不動明王様もいらっしゃいました。庭園も素晴らしいです。池の形が『心』の字になっているのです。紅葉の季節はもっと綺麗かも知れませんね。毘沙門天といえば、今年の大河ドラマの上杉謙信を思い出しますね。戦いの神様なのでしょうか。強くて優しい神様のようですね。このあと、琵琶湖疏水沿いに歩いて日向大神宮へ向かいました。|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆アメブロ始めました、良かったら読んでくださいね。
2009.04.06
コメント(2)
-

勧修寺
前回は醍醐寺から隋心院と行ったあと雨が降ってきたのでその後のコースを諦めざるを得ませんでした。今回はその時のリベンジということで、続きのコース勧修寺→毘沙門堂→琵琶湖疏水→日向大神宮というコースに挑むことにしました。毘沙門堂から琵琶湖疏水の最後のところまで歩いたのですが、コースの一部で、山に登るところがありブーツで行った私にはちょっときつかったです。500メートルくらいの山だったので、登ってみると見晴らしがよく景色も綺麗に見えたのでで、とても気持ちが良かったです。まず最初に、東西線の「小野」から歩いてそんなに遠くないところにある勧修寺からです。入口の白壁と桜が青空に映えてとても綺麗です。白壁伝いに少し歩くと、門がありました。勧修寺は境内の庭がとても広くてきれいです。醍醐天皇は生母の菩提を弔うため、生母の里であった寺を御願寺と定め、外祖父・藤原高藤の諡号をとって、勧修寺と号されました氷室池です、水鳥が泳いでいます。その昔、この池は実際に舟遊びに使われたそうです。また、その頃の呼び名は「来栖野氷室の池」と呼ばれ、毎年1月2日にこの池に張った氷を宮中に献上し、その氷の厚さでその年の五穀の実りを占ったともいわれています。 池のほとりに弁天堂がありました。不動明王様もいらっしゃいます。本堂には千手観音様がいらっしゃいました。皇室と藤原氏にゆかりの深い寺院なのだそうです。寺名は「かんしゅうじ」「かんじゅじ」などとも読まれることもありますが、ここのお寺では「かじゅうじ」を正式の呼称としているそうです。御天気もよく気持ちの良い一日の始まりです。このあと、地下鉄で山科まで行き、毘沙門堂へ向かいました。|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆アメブロ始めました、良かったら読んでくださいね。
2009.04.05
コメント(4)
-

高千穂の夜神楽 (宮崎・高千穂の旅11)
高千穂神社の境内に神楽殿があり、毎晩8時から「高千穂の夜神楽(岩戸神楽)」を行っています。前の席で見たいと思う人も多くみんな並ぶのだろうと思い、30分くらい前から行って会場が開くのを待ちました。会場が開くとどんどん人が入ってきて、始まる前には人で埋め尽くされるほどの満員になりました。高千穂地方に伝承されているこの神楽は、天照大神が天岩戸に隠れられた折に、岩戸の前でアマノウズメが調子おかしく踊ったのが始まりとされていて古来、高千穂地方では、先祖代々長い間この神楽を伝承してきているのだそうです。毎年11月の末から翌年の2月にかけて、各村々で33番の夜神楽を実施して秋の実りに対する感謝と翌年の豊穣を祈願するものだといわれています。その33番の中から代表的な4番を見ることが出来ました。【1】手力雄の舞(28番)天照大神が天岩戸にお隠れになったので、力の強い手力雄命が天の岩戸を探し出すため静かに音を聞いたり、考えたりする様子を表現してあります。【2】ウズメの舞(29番)天の岩戸の所在がはっきりしたので、岩戸の前で面白かしく舞い、天照を岩戸より誘い出そうとする舞です。【3】戸取りの舞(30番)天の岩戸も岩戸の戸も所在がはっきりしたので、手力雄命が岩戸を取り除いて、天照大神を迎えだす舞で、勇壮で力強く舞う舞であります。手力雄命が天岩戸を押しあけ、ほおり投げたのでその岩戸は長野県の戸隠まで飛んで行ったのだそうです。【4】御神体の舞(16番)一名国生みの舞と申しますが、イザナギ・イザナミの二神が酒を作ってお互いに仲良く飲んで、抱擁しあい、極めて夫婦円満を象徴している舞です。最後の御神体の舞は、イザナギが酔っ払ってイザナミに誘いをかけては、むげに断られたり、ちょっと仲良くしてみたり、ユーモアたっぷりで本当に楽しく面白く会場全体が何度も大笑いに包まれました。最後の御神体の舞があんまりおもしろくて、最初の三つを忘れないでくださいねといわれましたがそれは、難しいことだと思いました。内容はちょっと詳しく書きにくいのですが本当に愉快なのです。興味をもたれた方は是非、御自分の目で見て大笑いしてほしいと思います。次回は、高千穂町のいくつかの神社のお話です。良かったら是非、読んでくださいね。|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆【お知らせ】アメブロを始めました。もしよかったら、遊びに来て下さいね。
2009.04.04
コメント(2)
-

高千穂神社 (宮崎・高千穂の旅10)
高千穂神社は私達が宿泊した施設のすぐ近くでした。歩いて5分くらいのところなのです。アメノウズメさんが出迎えてくれています。高千穂は本当にたくさんの像があり、町を歩いていても楽しいのです。鳥居が見えてきました。鳥居をくぐると、重要文化財にもなっている狛犬さんがいました。なんだか、強そうな狛犬さんです。 まっすぐ進むと拝殿がありました。ここで、参拝です。拝殿の横に、夫婦杉があります。手をつないで三回まわると夫婦円満になると書いてあります。御友達同士だと、とても仲良しになれるとのことです。私と先輩は「夫婦ではないですよ。」なんて言って笑いながら手をつないで三回まわりをまわったのでした。拝殿の横には、三毛入野命さんがいらっしゃいました。神武天皇のお兄さんですが、一度大和に行ってから、しばらくして帰ってこられたのだそうです。そして、神武天皇たちがいなくなってからこの土地を征服していた鬼をやっつけたと言われています。その鬼たちの塚がこの高千穂神社から5分くらいのところにあります。実は、その塚は私達が泊まった『ホテル神州』の玄関の前にありました。鬼というのは、きっと地元の第二勢力だったのかも知れませんね。第一勢力の神武天皇たちがいなくなったので、やっと自分たちの出番とばかりに支配しようとしたら、三毛入野命が帰ってきて、やっつけられる形になったのかも知れません。ちょっと可哀想ですね。でも、こうやって塚を作って祀ると、地元の人々を守ってくれる神様になったのだそうです。面白いですよね。ところで、高千穂神社で夜に神楽がありました。次回はそのお話をさせていただきます。
2009.04.03
コメント(0)
-

天岩戸神社東本宮 (宮崎・高千穂の旅9)
天岩戸神社西本宮を出て、橋を渡るとすぐ裏手に天の岩戸神社東本宮がありました。西本宮が天の手力男さんのお出迎えだったように東本宮はアマノウズメがさんがお出迎えしてくださいました。天岩戸神社西本宮は人が多くて、ちょっとした観光地のようになっていますが、ここ東本宮は全く違って静かで、凛とした空気に包まれています。夏菜さんにも、西本宮に行かれるだけではなく東本宮も良いですよと聞いてはいたのですが、こんなに違うとは思いもよりませんでした。まさに、神様がいらっしゃるたたずまいです。神々しくて、私と先輩は、「ここ、良いね。」を何度も言いました。せっかく西本宮にまで来ていてここに来ない人は本当にもったいない。それにしても、人がいない、だからより一層いいのかもしれないけれど…。拝殿で参拝すると右手の看板が気になりました。ちょっと、壁伝いに右手の方に回ってみました。屋根の形も良く分かります。御神水がありました、綺麗な水です。天岩戸神社東本宮は本当に素敵なところです。何とも言えない神気漂うところなのです。高千穂に行かれた方には是非お勧めです。
2009.04.02
コメント(8)
全30件 (30件中 1-30件目)
1