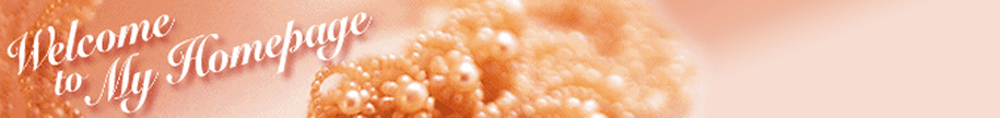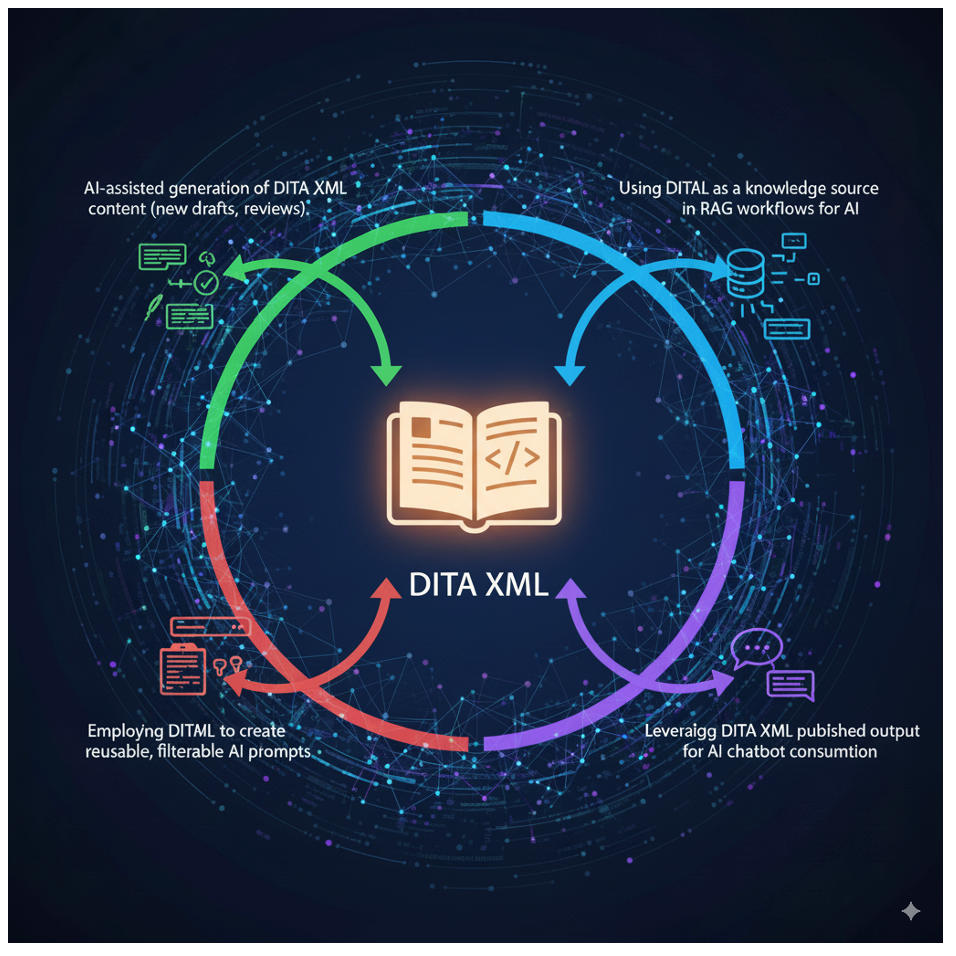2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009年05月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
お知らせです。(古代史関連)
今日の午後10時からNHK教育で『ETV特集』をします。日本と朝鮮半島2千年“任那日本府”の謎古代史最大の謎に迫る太王四神記の真実鉄を求めたヤマト政権、海を越えた軍事支援?韓国で続々と発見された前方後円墳の秘密天皇と百済との関係最新の発掘が古代史を書き換える|☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆。・:*:・゚'★,。・:*:・'。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆今夜は8時から『天地人』を見て、一時間休憩して『ETV特集』を見ようと思っています。古代史に興味のある方にはお勧めです。
2009.05.31
コメント(7)
-

吉野神宮と宮滝
今日は、先日行けなかった吉野神宮と宮滝に行ってきました。鳥居が見えてきました、とても荘厳な雰囲気です。ご祭神は後醍醐天皇だそうです。後村上天皇の勅命で刻まれ吉水神社に祀られていた後醍醐天皇の尊像が、五百五十年を経て吉野神宮の本殿に遷座され、創祀されました。神宮一円の大地は丈六平と称し、流造の本殿、入母屋造りの拝殿、切妻造りの神門などが美しく調和しています。「玉骨はたとひ南山の苔に埋まるとも、魂魄は常に北闕の天を 望まんとふ」と都に思いを寄せた後醍醐天皇の心を偲び、京都に向かって北向きに作られています。吉野神宮を出て、宮滝に向かいました。宮滝は持統が大変愛したところです。11年の統治の間に31度も通ったと言われています万葉集に天皇御製歌とされている歌があります。み吉野の 耳我の嶺に 時なくぞ 雪は降りける 間無くぞ 雨は降りける その雪の 時なきがごと その雨の 間なきがごと 隈もおちず 思ひつつぞ来し その山道を (万葉集 巻1-25)この歌は、実際にはいつ誰が詠んだものかは確証がないのだそうですが、天武天皇(大海人皇子)が壬申の乱の序曲となる宮滝行における峠越えの心境を詠んだものだとされています。宮滝に来たかったもう一つの理由は、このエメラルドグリーンの川を見たかったからです。お天気は良くなかったのですが、とても綺麗なエメラルドグリーンを見ることが出来たので本当にうれしかったです。宮滝には滝はありません。宮滝の滝は「たぎつ」の意味です。柴橋の中ほどから下流を向くと、今も変わらぬ「たぎつ瀬」の様子をみていただけます。ちなみに、宮滝の由来は「激つ宮処」だといわれています。 象の小川の水が吉野川に流れ落ちるところを夢のわだといいます。 夢のわだは『万葉集』にもよく詠まれ、その美しさは多くの万葉人の憧れでした。今日は、神社友達の一人である素敵な方とご一緒させて頂くことが出来ました。吉野は日本人の心のふるさとです。始めて行った時から懐かしい気持ちにさせてくれました。持統天皇が愛した意味が分かるような気がします。とても楽しい一日でした。感謝の気持ちでいっぱいです。
2009.05.28
コメント(6)
-

恩智神社
恩智神社へ夫と娘と一緒に行ってきました。実は娘にちょっと良いことがあったので、お礼を兼ねての参拝でした。恩智神社の主祭神は、大御食津彦命(おおみけつひこ)、大御食津姫命です。当初は天児屋根命を祀っていましたが、後になって枚岡神社に遷座し、現在の祭神を祀ることにりました。雄略天皇の時代(470年頃)、藤原氏により祖神の天児屋根命を香取神宮から勧請して創建されました。天児屋根命はその後、枚岡神社を経て春日大社に祀られるようになったことから、恩智神も「元春日」と呼ばれています。大御食津彦命は天児屋根命の五世代の孫、大御食津姫命は伊勢神宮外宮に祀られる豊受姫大神の別名です。神様のお使であります神兎・神龍が拝殿前左右に並んでいます。恩智神社の神様のお使いである御霊の籠ったなで「兎・龍」です。参拝された折に、卯辰をなると無病息災と昇運、開運が叶うと言われています。 天児屋根命が祀られています。閼伽井戸 (清明水)です。弘法大師に縁ある閼伽井戸(清明水)は古くより天候を予知する清水として知られ、雨の降る前になると赤茶の濁水が流れ出るという不思議な井戸です。 ここ恩智神社はかなり山の手にあります。大変見晴らしの良いところです、近くには恩地城跡もあります。以前から来たいと思っていたのですが、今回来ることが出来て良かったです。娘と神社へ来るのは初詣以来です。娘もここが結構気に入ったようでした。また、一緒に神社へ行こうねと約束をして、恩智神社を後にしました。
2009.05.24
コメント(4)
-

まうら悲しも越智・真弓の丘(束明神古墳)
岡宮天皇陵:真弓岡陵(まゆみのおかのみささぎ)岡宮天皇などという名前は皇統譜にはありません。追尊天皇なので、一般にはあまり聞きなれない名前かもしれないが、実は、天武天皇と持統天皇の間に生まれた皇子「草壁皇子」のことなのです。偉大な父とその母である鵜野皇女(持統天皇)のプレッシャーからでしょうか、それとも生まれつき体が弱かったのでしょうか、ついに天皇として即位することはなく、享年28歳という若さで逝去しました。持統3年(689)に没し、のち天平宝字2年(758)に岡宮御宇天皇(おかのみやにあめのしたしろしめししすらみこと)と諡号されました。現在宮内庁は、草壁皇子の古墳としてここを指定していますが、学者の間では、岡本天皇陵から300メートル離れた束明神古墳(つかみょうじんこふん)が草壁皇子であろうという説が有力です。以前、束明神古墳の東側、田んぼの中で掘っ立て柱が出土しました。墓守の役所跡の可能性もあるとのことです。草壁皇子を祀ってきた村人が天皇陵指定による立ち退きを恐れて石室上板を隠し、鉄の棒による探査を免れたも、その後の発掘でこの事実が検証されたのだそうです。村人は草壁皇子が石川の女郎(大名児)に贈った歌「大名児彼方野辺に刈る草の束の間も吾忘れめや」にちなみ、束明神(塚明神とすれば隠した事実が知れる)として祀ったとのこと。当時を偲ぶ「束明神」「嘉永四年」の銘が残る灯籠が、現在塚に立っています。信仰深い地元の方々の知恵だったのかも知れませんね。これまでの2回の調査の結果、墳丘は、対角線の長さ30mの八角形。埋葬施設は、横口式石槨は50cm四方、厚さ30cmの石材を積み上げた家形の石槨で、石室の規模も長さ3.1m、幅2m、高さ2.5mと大きなものであったそうです。。御陵の隣には「素盞鳴命(スサノヲノミコト)神社」がありました。村人は役人から守り、鎮守の森として今でも大切にしているのだそうです。このあと、マルコ山古墳へ行きました。被葬者は誰かは分かっていません。盗掘にあって副葬品は少ないが、金銅製の太刀装具の一部があったのだそうです。人骨は30歳代の男性と鑑定されました。高松塚古墳とほぼ、前後した7世紀末ころから8世紀初頭に築造された古墳です。実はこの日は降水確率100%だったのですが、朝起きた時には雨が降っていなかったので思いきって決行しました。最初の計画ではこのあと檜隈神社と於美阿志神社へ行くはずだったのですが、雨が結構本気で降ってきたので、ここまでとすることにしました。なかなか行くことのできない飛鳥の南西部でした。以前から一度行ってみたいと思っていたところだったので、大変満足の一日でした。
2009.05.18
コメント(4)
-

まうら悲しも越智・真弓の丘 (斉明天皇陵)
「まうら悲しも越智・真弓の丘」ということで、越智岡の斉明天皇陵を目指します。斉明天皇というのは中大兄皇子(天智天皇)と大海人皇子(天武天皇)間人皇女(孝徳天皇の皇后)のお母さんです。ここの住所は高取町大字車木といいます。この車木というのは、斉明天皇の車が来た→車木となったそうです。そしてここには、孫にあたる建皇子(父は天智天皇、母は蘇我山田石川麻呂娘越智娘)も一緒に眠っています。そして、もう一人斉明天皇の娘、間人皇女も一緒に眠っています。間人皇女は斉明天皇の弟孝徳天皇に嫁ぎましたが実は兄の中大兄皇子(天智天皇)と恋人だったとも言われています。当時の結婚は政略結婚が多い上に、皇女ともあれば親族以外の男性に会う機会も少なかったのかも知れませんね。何だか悲しい気持ちにになります。紅葉の花って御存じですか。紅葉は葉っぱを楽しむものと思っていたので、知らなかったのですが、花はちょっと変わった形をしていますね。でも、色は紅葉が紅葉した時の色と同じですね。斉明天皇の御陵と同じ岡の少し下のところに大田皇女の御陵がありました。大田皇女は天武天皇に嫁ぎ大津皇子と大伯皇女を生みましたが、体が弱く若いうちに亡くなってしまします。大津皇子は大変聡明で見目麗しく人望があったために、持統天皇より無実の罪で殺されてしまいます。それを悲しむ大伯皇女…。本当にこの辺りは悲しいお話で胸が痛くなります。美しく優しい方だったのではないでしょうか。大海人皇子はたいそう愛おしがられたとのことでした。ところで、道を歩いている途中に『玉藻』を見つけました。柿本人麻呂、泊瀬部皇女と忍坂部皇子とに献つる歌にこのような歌があります。飛ぶ鳥の 飛鳥の川の 上つ瀬に 生ふる玉藻は 下つ瀬に 流れ触らばふ 玉藻なす か寄りかく寄り なびかひし 夫の命の たたなづく 柔肌(ニギハダ)すらを 剣太刀 身に副へ寝なば ぬばたまの 夜床も荒るらむ そこ故に 慰めかねて けだしくも逢ふと思いて 玉垂の 越の大野の 朝露に 玉裳はひづち夕霧に 衣は濡れて 草枕 旅寝かもする 逢わぬ君ゆえ場所はこの越智の岡辺りではないでしょうか。玉藻がゆらゆら揺れて絡まるさまを、夫婦の添い寝に例えているのですね。泊瀬部皇女は天武天皇の皇女で、母は宍人臣大麻呂の娘です。同母兄弟は忍壁皇子・磯城皇子・同母の妹は託基皇女。夫は川島皇子。川島皇子は大津皇子と友でありながら、大津皇子の謀反を訴えなければならない立場でもありました。真実ではないと知りながらも大きな力に抵抗することが出来ずに仕方なかったのかも知れませんね大津皇子もきっと分かっていたに違いありません。そう思いたいですね。泊瀬部皇女も辛い立場であったのでしょうね。越智の丘は本当に悲しいお話がいっぱいで歩きながらも涙がこぼれそうになるのでした。「まうら悲しも越智・真弓の丘」です。このあと、真弓陵・岡宮天皇陵、束明神古墳、マルコ山へと続きます。
2009.05.17
コメント(4)
-

浪切神社
先日家族で買い物とランチを食べに、岸和田カンカンへ行った時に敷地内に鳥居を見つけてしまいました。いつもの癖で鳥居を見ると通り過ぎることができません。ちょっと入ってみることにしまいした。“浪切神社”というのだそうです。だんじりの安全祈願をするところなのだそうです。岸和田のだんじりは有名ですが、危険なことでもまた有名ですよね。「どうか神様、事故がありませんように。」と祈る気持ちは痛いほど分かりますね。この辺りはすぐ近くが海です。浪切神社って良い名前ですね。このあと“夢厨房”でパスタのランチを食べました。焼きたてのパン食べ放題は本当に美味しかったです。
2009.05.14
コメント(6)
-

建水分神社
建水分神社へ行ってきました。ご祭神は天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)天水分神(あめのみくまりのかみ) 国水分け神(くにのみくまりのかみ) 罔象女神(みつはのめのかみ)瀬織津媛神(せおりつひめのかみ) です。 創建は第10代崇神天皇5年(西暦前92)で、同天皇が天下饑疫にみまれ、人民が農事を怠った時、諸国に池溝を穿ち農事を勧められ、この時勅して金剛葛城の山麓に水神として奉祀せられたのだそうです。「建水分(たけみくまり)」の「建(たけ)」は「猛々しい」という意味の美称であり、「水分(みくまり)」は用水を公平に分配する事で、「水配り(みずくばり)」から「みくばり」、そして「みくまり」へと転訛したのだそうです。用水を公平に分配するというのは、この辺りが川の分岐点になっていからではないでしょうか。鳥居の前の狛犬さんがすごく大きいので驚きました。鳥居をくぐって階段を上ると拝殿がありました。この神社は、私が大阪から奈良へ抜ける水越峠を通るときにいつも横目で見ながら通り過ぎていた神社でした。以前から一度来たかったのですが、今回夫と一緒に来ることが出来て本当によかったです。今年のGW前後(4月の下旬から5月上旬)の約1か月弱で、夫と二人で色々なところを回りました。八尾の勝軍寺、弓削神社2社。和歌山の根来寺、日前宮、玉津島神社、塩竃神社、竃山神社。大阪市内の一心寺、安居神社、森ノ宮神社、豊国神社、坐摩神社。宇陀の室生寺、龍穴神社、大野寺、佛隆寺。葛城の葛木坐火雷神社、鴨都波神社、九品寺、船宿寺、吉祥草寺。生駒の長弓寺。郡山の売太神社、矢田坐久志玉比古神社、郡山城跡。吉野の丹生上神社・上社・中社。そして、ここ建水分神社。今回は随分私の我儘に付き合ってもらいました。以前から行きたかったところばかりです。本当に夫に感謝の春でした。
2009.05.13
コメント(4)
-

安居神社
安居神社は一心寺の向かえにある小さな神社です。実はこの前の道は何度も通っているのに、こんなところに神社があるなんてちっとも知らなかったのです。鳥居をくぐり細い道をず~っと入って行くと拝殿がありました。ここは、真田幸村終焉の地なのだそうです。このあと、やはりいつもの方面へ…。そうです、新世界です。新装開店なのだそうです。花魁さん綺麗でしょ、男の人なので凄く背が高いのですよ。はい、お楽しみの串かつです。やっぱり「八重勝」が一番おいしい。ということで、今日は神社の紹介というか串カツの紹介になってしまいしたね。
2009.05.12
コメント(4)
-

長弓寺とイザナギ神社
生駒から富雄川を北に登っていたったところに、長弓寺というお寺があります。長弓寺は、聖武天皇の勅願により行基が白檀の十一面観音を作り、牛頭天王、八王子の宮を立てて天皇の弓で本尊頂上の仏面を彫刻して創建したと伝えられています。真弓山長弓寺という山号、寺号には悲しい物語があります。富雄の豪族であった真弓長弓(たけゆみ)が子の長麻呂を連れて聖武天皇の鳥狩り従い、親子でこれを追っていましたが、はからずも親子相うちになり、長麻呂の矢に当たり命を落としたのだそうです。聖武天皇がその悲運な最後を嘆き、行基菩薩に命じてその冥福を祈るためこのお寺を建立したという伝説が残っています。寺の近くには長弓の墓と伝えられる真弓塚があります。↓が真弓塚かどうかは分からないのでうが、近くにそれらしきものがなくて…。どなたか教えて頂かないでしょうか。長弓寺の境内東側にある伊弉諾(いざなぎ)神社は、明治の神仏分離以前は牛頭天王社(ごずてんのうしゃ)と呼ばれ、寺伝では聖武天皇が長弓寺の鎮守として建てさせたものなのだそうです。生駒から結構北にあるのですが、こんなに大きいお寺があるとは知りませんでした。最近奈良に、興味を持ち始めたのですが、奈良は本当に深いと思いました。本当はさらに北にある高山八幡宮にも行きたかったのですが、この日はさすがに時間切れ、夫はそろそろ疲れているようでした。生駒から龍田川沿いに家に向かいましたが途中、往馬神社や行基の墓など行きたいところはいっぱいありましたが、横眼で見て我慢して通り過ぎました。また、機会を作ってこの辺りは来てみたいものです。良いところですよ。
2009.05.11
コメント(6)
-

矢田坐久志比古神社
矢田坐久志玉比古神社(やたにいますくしたまひこじんじゃ)ご祭神は櫛玉饒速日尊(くしたまにぎはやのみこと)と御炊屋姫命(みかしきひめのみこと)です。郡山城からそんなに遠くないのですが、見つけにくい場所でした。やっと見つかった時はかなり嬉しかったです。『大和志』に矢落大明神と称すとあります。矢落とは、饒速日尊の天降りの時、天磐船から三本の矢を射てその落ちたところに宮居したとの伝によったものといいます。矢田の地名はこれによるのだそうです。天磐船の故事から、大空の守護神と崇められ、楼門には木製のプロペラが奉納されてします。見えるでしょうか、近づくと本当にプロペラです。これを自分の目で見たかったのです。空の神様なのだそうです。春日造の本殿と末社の八幡神社社殿は重要文化財だそうです。特殊神事の綱掛祭りは1月8日に、筒粥占祭は2月1日に行われるのだそうです。饒速日尊ということは、子孫は物部氏ですね。物部氏も神仏戦争から勢いは薄れて行きますが、昔は大きな勢力を持っていたことがわかりますよね。今は、石上神社くらいしか思い浮かびませんでしたが、こうやって見つけることが出来た時はやったという感じでした。郡山は奈良の中では観光地としてあまりメジャーではありませんが、奈良好きにはとても気になる場所です。
2009.05.10
コメント(8)
-

郡山城跡
郡山城跡へ行ってきました。郡山城は筒井順慶の築城に始まる大和でもっとも大規模な城郭で、近世期には、豊臣家、水野家、松平家、本多家、柳澤家の居城となりました。天守閣跡へ行くためには柳沢神社の鳥居をくぐって入って行きます。城郭は筒井順慶の時代に始まりました。織田信長の後ろ盾で大和国を平定した順慶は父祖伝来の筒井城を出て、土豪の郡山衆らが拠ったこの地に近世的な縄張りで城を築き入城しました。筒井氏は伊賀国へ転封したのち、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が入城し大和・紀伊・和泉三ヶ国・百万国の太守にふさわしくと、紀伊国根来地の大門を過去ばせて縄文西楯かなり強引な石材集めで城郭の拡充を進めました。順慶は多聞山城の石材を、秀長は平城京羅城門跡の礎石と伝えるものをはじめ、石仏・石塔などまで集めさせました。野面積みの天守閣台には地蔵仏がうつ伏せに積み込まれていて「逆さ地蔵」と呼ばれ祀られています。いくら石材が欲しいとはいえ、お地蔵さんまで天守閣台にしてしまうなんてなんとむごいことでしょう。胸が痛くなってしまいました。
2009.05.09
コメント(6)
-

売太神社
郡山へ行ってきました。まずはじめに行ったのは売太神社です。売太神社の御祭神は 稗田阿礼命、猿田彦命、天鈿女命 です。 【稗田阿礼命】この地は古代豪族である稗田猿女君の邸のあったところと伝えられます。『日本書紀』巻第一に猿女君は遠祖天鈿女命とあり、天武天皇の舎人稗田阿礼はその一族です。稗田阿礼は記憶力に優れ、天武天皇の命で帝紀・旧辞を暗誦したことで名高く、のちに太安麻侶がこれを書き写したのが『古事記』です。今日、阿礼さまの広大無辺のご霊徳を偲び学問の神・知恵の神として篤く信仰されています。【猿太彦神】天鈿女命の彦神であって、土地・方位の神としてすべての物事の初め即ち、新築・移築・旅立ち・結婚等に災難や悪魔を祓ってよい方に導き給うご霊験あらたかな神さまです。【天鈿女命】猿女君稗田氏の太祖で、「天岩戸隠れの神事」にたらいを伏せて舞を舞われた女神で、オタフク又はオカメの愛嬌あり福の神、芸能の始祖として、親しみ信仰されています。 阿礼祭というのがあり、売太神社で毎年8月16日に行われています。昭和5年8月16日当時の奈良県立図書館長仲川明らが提唱し、全国童話連盟の人たちによって始められました。当日は「稗田舞」が奉納され、続いて前庭において「阿礼さま踊り」が「阿礼さま音頭」が催されます。稗田阿礼さんは、本当に実在の人物か疑われた時期もありました。もしかしたら、女性ではないかと言っている人もいるようですが、どうも男性のようです。本当に頭の良い方だったのでしょうね。少しでもあやかれるように心をこめて参拝したのでした。
2009.05.08
コメント(0)
-
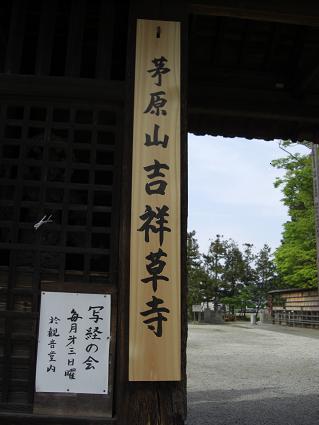
葛城・吉祥草寺
吉祥草寺は山号が茅原山、金剛寿院吉祥草寺と称する古刹です。この地は修験道の開祖役行者神変大菩薩の出生地とされ、当時は役行者(小角)の創建と云え、境内の一角には産湯の井戸がのこされています。西に聳える葛城山系は、若き日の小角の修行の場であり、その主峰葛城山(現在の金剛山)は、小角が鬼神を使って金峯山(大峯山)との間に石橋を架けさせようとした所です。吉祥草寺は修験道発祥の地です。また、1月14日の「茅原のトンド」は大和最大のもので、県の無形民俗文化財に指定されています。葛城は本当に神社やお寺が多いです。私は葛城に来たのは5回目ですがなかなか全部の神社やお寺に行ききれるものではありません。今回は行くことは出来ませんでしたが、天孫降臨の雰囲気をもつ「高天彦神社」や、雄略天皇とゆかりの深い「一言主神社」や京都の上賀茂神社をはじめ全国に分布している多数の鴨社の源でもある「高鴨神社」など、とても素晴らしい神社もたくさんあります。葛城に興味をお持ちの方は是非一度いらしてみてはいかがでしょうか。奈良は、奈良市と飛鳥が有名ですが宇陀や葛城も素晴らしいところがいっぱいありますよ。本当の奈良を見たいと思われる方は葛城はお勧めです。
2009.05.07
コメント(6)
-

葛城・鴨都波神社
鴨都波神社は「かもつばじんじゃ」と読みます。鴨都波神社が御鎮座されたのは、飛鳥時代よりもさらに古い第10代崇神天皇の時代であり、奈良県桜井市に御鎮座されている「大神神社」の別宮とも称されています。ご祭神は、「積羽八重事代主命」(つわやえことしろぬしのみこと)と申され、大神神社におまつりされている「大国主命」(おおくにぬしのみこと)の子どもにあたる神様です。葛城の地には、「鴨族」と呼ばれる古代豪族が弥生時代の中頃から大きな勢力を持っていました。当初は、「高鴨神社」付近を本拠としていましたが、水稲農耕に適した本社付近に本拠を移し、大規模な集落を形成するようになりました。そのことは、本社一帯が「鴨都波遺跡」として数多くの遺跡発掘によって明らかになっています。ご祭神の「積羽八重事代主命」は古事記に「鴨都味波八重事代主神」と記されており、「代主」は田の神の古語で「鴨都味波」は鴨の水端、つまり鴨の水辺の意味で、「八重事」はしばしばの折り目という形容詞でつまり「鴨の水辺で折り目ごとに祀られる田の神様」というご神名なのだそうです。事代主を奉斎してこの地を領地とちていた鴨王の娘が、神武、綏靖、安寧の三代の天皇の皇后となった由縁から、祭神は皇室の守護神とされ、宮中八神の一つとして崇拝されてきたのだそうです。藤棚も綺麗です。今までもこの辺りに来たことがあるのですが、車などで通るとうっかり通り過ぎてしまいそうなところなのですが、意外にも皇室の守護神のため由緒のある素晴らしい神社のようです。やはり、葛城の辺りからしばらく目が離せそうもないです。
2009.05.06
コメント(9)
-

丹生川上神社・上社と下社
今日は、吉野の丹生川上神社・上社と中社へ行ってきました。去年、天河神社へ行ったときに丹生川上神社・下社へは行ったのですが、上社と中社はまだ行ったことがありませんでした。丹生川上神社は、上社・中社・下社の三社で二十二社の一社として数えられているのでどうしても三つとも行っておきたかったのです。まずはじめに行ったのは上社の方です。「この里は丹生の川上ほど近し祈らば晴れよ五月雨の空」と後醍醐天皇が歌に詠んだ由緒ある神社です。675年、天武天皇の神宣によって創建されたと伝えられ、歴代天皇の崇敬あつく、雨の神を祀っています。丹生川上神社上社は以前はこの場所ではなかったのですが、ダムを造ることになり、以前の神社は川の下に沈んでしまっているのだそうです。11年くらい前に、ここに新社殿が建てられ、遷座したのだそうです。今は山の上にあり、とても景色が綺麗です。次は、中社の方へ行きました。御祭神「罔象女神(みづはのめのかみ)」です。水一切を司る神様で水利の神として、又は雨の神として信仰され、五穀の豊穣に特に旱続きには降雨を、長雨の時には止雨を祈るなど、事あるごとに心からなる朝野の信仰を捧げ、水神のご加護を祈ってきました。小牟漏岳境内地にツルマンリョウ、テンダイウヤク、ツクバネなど多種の植物が自生しているころで有名です。 落ち着いた素晴らしい神社です。清めのお水を井戸から汲んで手を清め、水で口をゆすぎました。ちょっと飲んだのですが、おいしいお水でした。神社の前の水は透明でとても美しいのです。近くを散歩しました。北から三尾川、南から木津川、東から日裏川の合流点の辺りに滝がありました。二つの水が合流しているせいか滝の形がXに交わっています。本当に綺麗で、いつまでも離れがたい思いでいっぱいになりました。もとは対岸の本宮山(旧地に摂社丹生神社が鎮座)に祈雨神として祀られていたと言います。 今日はとても素晴らしい神社を二つ参拝することが出来てとてもうれしかったです。丹生川上神社・上社は新しくて綺麗でしたが、私としては中社の方がより一層好きだなと思いました。偶然見つけた滝も、とってもお気にいりです。熊野大社へ行くには、上社を通っても行くことができそうです。いつか、熊野大社へも行きたいねと夫と話しながら家路へと急いだのでした。
2009.05.05
コメント(8)
-

久品寺
九品寺に着いた途端に、夫が「あ~、ここええな。」といいました。あまり神社仏閣に興味のない夫にしては珍しいことです。季節も良かったからか、新緑に椿や芍薬が良い色どりに咲いているのがより一層お寺を綺麗に見せているのかもしれませんが、それだけでなくここのお寺の方のお気持ちのようなものが伝わってきます。とても落ち着くお寺です。門を入りました。九品寺は、行基が創建しました。本尊の木造阿弥陀如来像は重要文化財です。静かで、優しい雰囲気が伝わってきます。左手には池のある美しい庭があります。右手にはお地蔵さんがたくさんいます。写真には撮りませんでしたが、墓地には千体石仏があります。綺麗なお庭には西国三十三ヵ所のお地蔵さんがいらっしゃいます。一体一体、手を合わせて行きました。今日も素敵なお寺を参拝することが出来て本当によかった。夫と二人で、良かったねと良いながら歩いていました
2009.05.04
コメント(0)
-

葛城・笛吹神社
吹神社は正式には葛城坐火雷神社といいます。創建は神代とも神武天皇の代とも伝えられています。大嘗祭で用いられる波々迦木(ははかのき)は古来より笛吹神社から献上されていました。天香山命の子孫、笛吹連が代々この地に住み祖先神に奉仕し、この地を笛吹きとたたえたのだそうです。現在は、火雷の神様であることから火を扱う職業や消防関係の崇敬が熱く、また天香山命の神徳からフルート尺八等の上達を願う人の崇敬も篤く、全国から奉納演奏に訪れているのだそうです。もしここで、ほぎさんの笛を聴くことが出来たら最高だろうななんて思いながら歩いていました。神社に、笛って似合うのですよね。本殿の傍らには笛吹連の祖の古墳や神山一帯には八十基程の古墳が分布しているのだそうです。葛城は、雄略天皇(ワカタケル)の本拠地でもあります。葛城王朝があったのかどうかは分かりませんが、このあたりは神社仏閣が本当に多く、驚くほどです。今回実は、御所という地名に魅かれてこの辺りに来たのですが、御所と葛城がこんなに近いとは思いませんでした。実際にこの辺りを歩いてみると、ますます興味深い思いでいっぱいになりました。もっともっと調べてみたいです。
2009.05.03
コメント(4)
-

葛城・花のお寺船宿寺
ゴールデンウィークに入り、久しぶりに葛城の方へ行ってきました。まずはじめに、花のお寺船宿寺です。船宿寺を訪れた行基が夢で老人の神託を聞き、東の山中にある大きな舟形の岩の上に薬師如来を祀ったことに始まるといいます。お寺にあるヒラドツツジが有名です。お寺の門の前にたくさん咲いていました。門を入ると“シャクヤク”が出迎えてくれました。つつじも、いろいろな種類があります。大きくて私の背よりずーっと高いのです。本堂の前の真っ白の“おおでまり”が豪華です。石楠花もいっぱい咲いています。花のお寺と言われるだけあります。夢の中のようです。青空のもとたくさんの花に囲まれて夢の世界のようです。心が洗われた気がします。船宿寺の一番いい季節に来ることが出来たようです。ピッタリの季節にピッタリのタイミングで来ることが出来たことに感謝の気持ちでいっぱいになりました。
2009.05.02
コメント(0)
-

森ノ宮神社と大阪城
森ノ宮駅のすぐ横に森ノ宮神社があります。正式には鵲森宮(かささぎもりのみや)といいます。pleさんのブログで見てから一度行きたいと思っていたのです。鵲森宮は聖徳太子のお造りになった神社で、三十一代用明天皇(欽明帝第四皇子、橘豊日命)並びに穴穂部間人皇后を祭る日本唯一の神社です。また、元の四天王寺とも言われています。すぐ近くに、大阪城があるので久しぶりに行ってみました。約20年ぶりです。随分変わったと思うのですが、大阪城は塗り替えたのですね。桜は残念ながら終わっていましたが、つつじが綺麗に咲いていました。大阪城の入口の前には豊国神社がありました。今まで子供のころから何度も来たことがあるのに、ちっとも気がつきませんでした。豊国神社に入ってみました。豊臣秀吉の像がありました。ここが有名な豊国神社だとわかり良かったです。豊国神社は大きな神社でした。このあと雨が降りそうになったので、大急ぎで帰路に就いたのでした。
2009.05.01
コメント(6)
全19件 (19件中 1-19件目)
1