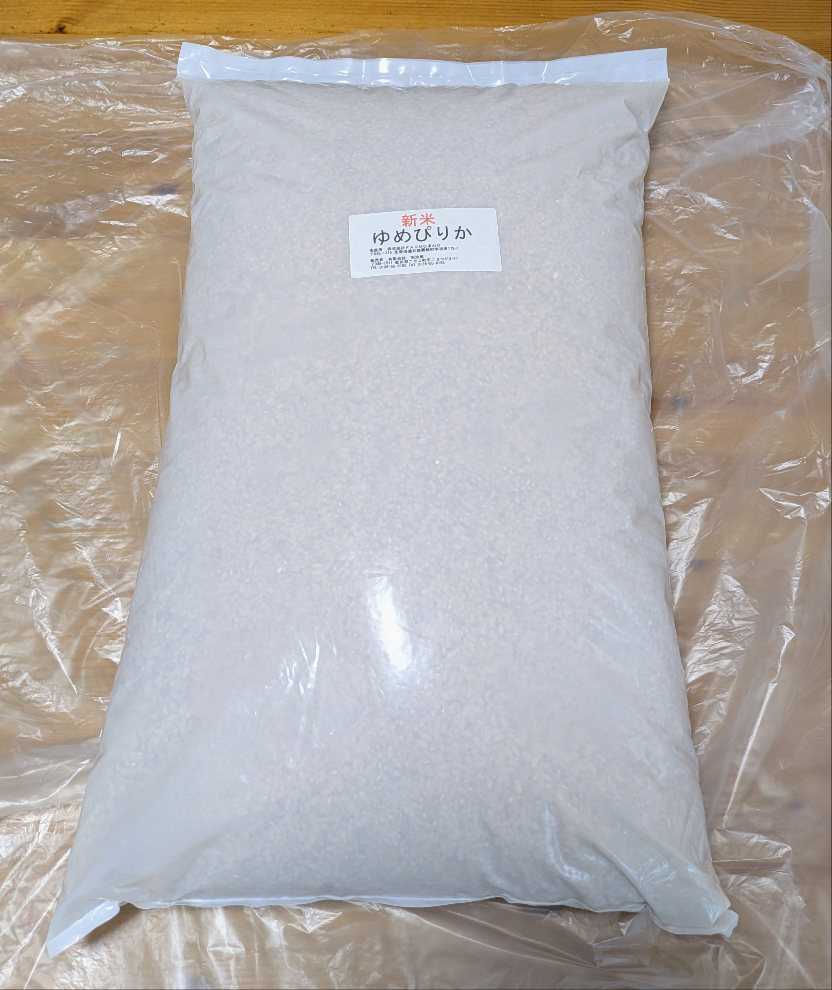万葉集の歌が書かれた木簡
5月22日19時56分配信 毎日新聞
史跡紫香楽宮跡から出土した万葉集の歌が書かれた木簡=滋賀県甲賀市で2008年5月14日、森園道子撮影
奈良時代に聖武天皇が造営した紫香楽宮(しがらきのみや)の跡とされる宮町遺跡(滋賀県甲賀市信楽町)で出土した木簡(8世紀中ごろ)に、日本最古の歌集である万葉集に収録された「安積山(あさかやま)の歌」が書かれていたと22日、市教委が発表した。万葉歌が書かれた木簡が見つかったのは初めて。万葉集とは表記が全く異なっていた。もう一つの面には「難波津(なにわづ)の歌」が書かれており、この2首を歌の手本とする伝統が、平安時代に編さんされた古今和歌集の時代から万葉集の時代まで約150年さかのぼって確かめられた。日本文学の成立史に見直しを迫る画期的な実物史料となる。
「歌木簡」は97年、宮殿の排水路と推定される溝から出土した。長さ7.9センチと14センチの2片に分かれ、幅は最大2.2センチ。万葉集になく、木簡などで残る難波津の歌の一部が書かれていることはわかっていたが、厚さが約1ミリしかなく、木簡の表面を削ったくずと考えられていた。栄原永遠男(さかえはらとわお)・大阪市立大教授が昨年12月に調べ直して見つかった。
両面とも日本語の1音を漢字1字で表す万葉仮名で墨書され、安積山の歌は「阿佐可夜(あさかや)」「流夜真(るやま)」の7字、難波津の歌は「奈迩波ツ尓(なにはつに)」などの13字が奈良文化財研究所の赤外線撮影で確認された。文字の配列などから元の全長は2尺(約60.6センチ)と推定される。字体や大きさが異なり、別人が書いたとの見方が強い。
万葉集は全20巻のうち、安積山の歌を収めた巻16までが745年以降の数年で編さんされたとされる。木簡は一緒に出土した荷札の年号から744年末~745年初めに捨てられたことがわかり、万葉集の編さん前に書かれたとみられる。約400年後の写本で伝わる万葉集では訓読みの漢字(訓字)がほとんどの表記になっており、編さん時に万葉仮名が改められた可能性がある。
2首は、古今和歌集の仮名序(905年)に「歌の父母のように初めに習う」と記され、源氏物語などにも取り入れられている。筆者の紀貫之の創作の可能性もあったが、古くからの伝統を踏まえていたことがわかった。
【近藤希実、大森顕浩】
<難波津の歌>
難波津に咲くや(木こ)の花冬こもり今は春べと咲くや木の花
(訳)難波津に梅の花が咲いています。今こそ春が来たとて梅の花が咲いています
<安積山の歌>
安積山影さへ見ゆる山の井の浅き心を我が思はなくに(安積香山 影副所見 山井之 浅心乎 吾念莫国)
(訳)安積山の影までも見える澄んだ山の井のように浅い心でわたしは思っておりませぬ
(いずれも「新編日本古典文学全集」小学館より。「安積香山」で始まる表記は、万葉集の原文)
【ことば】万葉集
奈良時代編さんの日本最古の歌集。全20巻に約4500首あり、主に飛鳥時代から奈良時代にかけての歌を収録。歌人としては柿本人麻呂、山上憶良、大伴家持、額田王などが知られる。天皇や皇后などの皇族のほか、東北や関東などの民謡「東歌(あずまうた)」や、九州沿岸の防衛に徴集された防人(さきもり)の歌なども収録し、作者層が幅広いのが特徴。
【ことば】紫香楽宮
奈良時代半ばの742年、聖武天皇が造営を始め、745年に難波宮(なにわのみや)から遷都したが、地震や山火事が相次ぎ、5カ月で平城京に都が移った。公式儀礼を行う中枢建物「朝堂」の跡が宮町遺跡で01年に確認されたが、全容は不明。
最終更新:5月23日1時8分
© Rakuten Group, Inc.