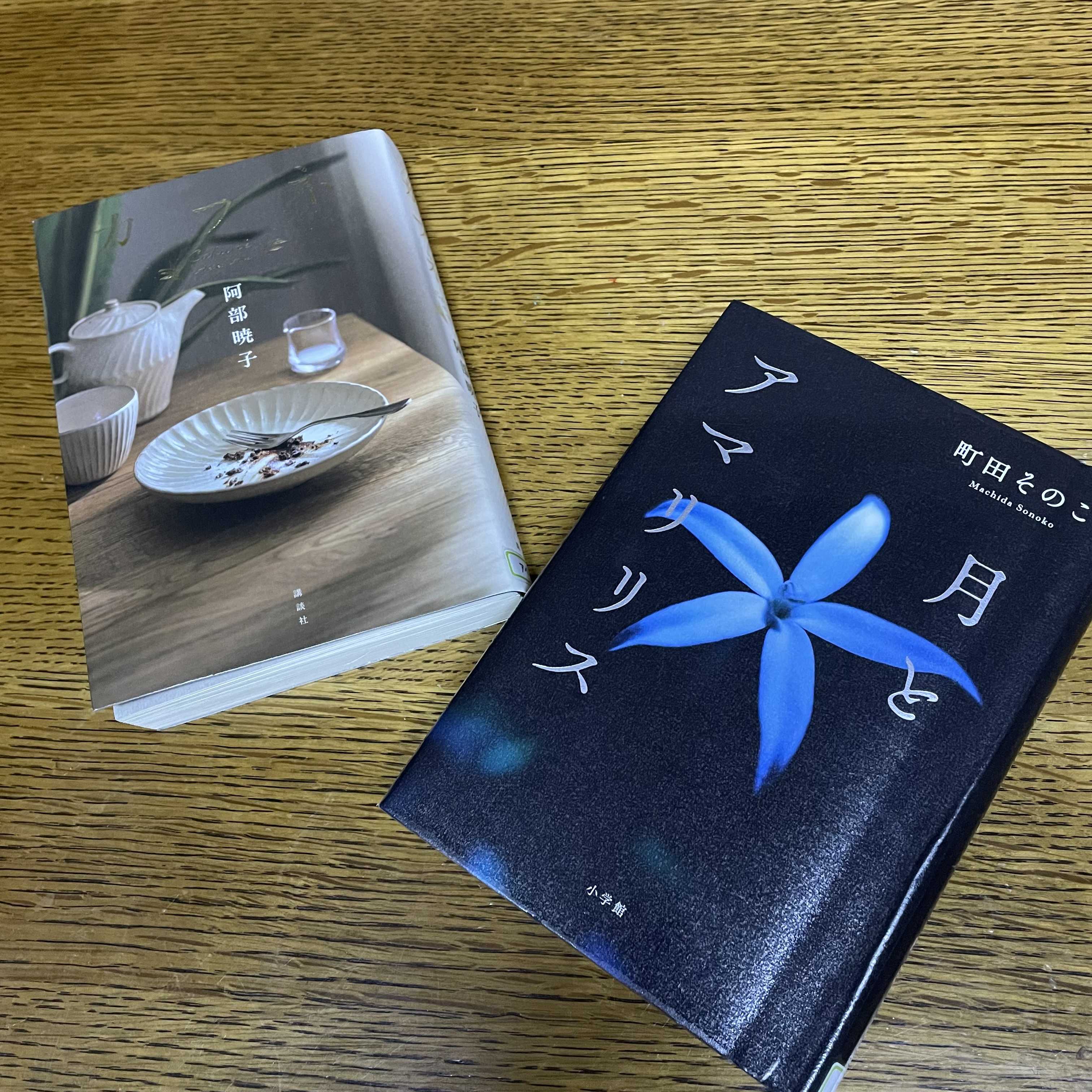市川崑監督の 旧作《ビルマの竪琴》
ヴェネツイア映画祭のサン.ジョルジオ賞とは
『人類の共同生活に寄与する人間の能力を、最もよく描いた
作品に与えられる特別賞』という意味だそうだ.
その賞を1956年に受賞、そして1960年に
過去5年間のこの受賞作品群の最優秀作に選ばれた。
その作品は市川崑監督≪ビルマの竪琴≫である。
それまで夫人の和田夏十氏と組んで風刺劇など独特の作品を
作っていたが、1956年のこの作品によって彼は
世界一流の監督の仲間入りを果たした。
《あらすじ》
1945年ビルマ戦線に完敗した日本軍はタイ国境に向かって
毎日、毎夜歩きつづけた。
その苦しみの中にあって、ある部隊で見られた
信じられない光景。
それは戦前東京で音楽家であった井上小隊長(三国連太郎)が
兵隊達に活を与えるために
また、戦場の荒廃した中で人間性、美しい心を
失わせないためにビルマの楽器、竪琴に合わせて暇を盗んでは
教えていた《荒城の月》を
合唱させていた光景であった。
井上小隊に竪琴の名手がいたことも戦場では考えられない、
より美しい荒城の月の合唱となった。
その名手は水島(安井昌二)という。
終戦となり、降参した小隊全員はムドンの収容所に
送られることになったが水島だけは消息を絶った。
収容所では誰に教わったか関西弁を話す現地の老婆がいた。
皆はこの老婆に水島の行方を捜してくれるように頼んだが、
その消息は知れなかった。
が、隊員が収容所の労役作業に出たときに
肩に青いインコをのせたビルマの僧に出遭い、その僧が
水島にそっくりなのに驚いた。
”水島ーーッ”と呼びかけたが、その僧は黙って目を伏せたまま
通り過ぎていった。
水島は生きていたのだ。
ムドンへ向かう途中、おびただしい日本兵の白骨をみて、
どうしても彼らの魂をこのままにして地を去ることなど
どうしても出来なかったのだ。
僧となり彼らの遺骨を守り、霊を慰めようとこの地に残る決心を
したのだった。
井上小隊長はおおよその事情を察した。
そこで、水島のインコと兄弟だというインコを老婆から
譲り受け、一生懸命に教え込んだ。
”水島、一緒に日本へ帰ろう”と。
そして老婆にこのインコをあの水島らしき僧に渡してくれと頼む。
そしていよいよ日本へ出発するという前の日に
あの僧が姿をあらわし、柵の向こうから、
竪琴で、《仰げば尊し》を奏でた。
懐かしい祖国のメロデイーに隊員たちの目は潤みなにも
見えなくなった。そのとき僧の姿も消えていた...
出発の日、老婆が井上のところへインコを持って来て渡した。
インコはか細い歌うような声で言った。
”アア、ジブンハ、カエルワケニハ イカナイ”と。
この映画によって市川監督は人間の心の美しさとじわーと
こみ上げてくる感動へと導く典雅で、高貴な感覚を発揮し、
地位を不動のものにした。
後年、市川監督は再度同作品を作りなおしたが、
徒労に終わった。あれだけで良かったのだ。
戦争は醜い、が極限の時や場において
心の醜さも美しさも紙一重になるだろうことを思った....。
製作 日活 1956年度作
原作 竹山道雄
脚本 和田夏十
出演 三国連太郎、安井昌二、西村晃、伊藤雄之助、三橋達也
© Rakuten Group, Inc.