第13章
時代を支えてきた男西での円卓会議の翌日。東での“ピースメーカー”襲撃というクーデターの情報は、まだ西と南には届かなかった。
優秀な諜報員と豊かな人員を併せ持つ北だけは、一足先にその情報を得たが、その情報はシレンでも簡単に取り扱えるものではなかった。
北のセイントノース城にある諜報部団室でシレンは人を待っていた。普段から近寄りがたい、不敵な雰囲気を漂わせるシレンだが、今はいつも以上にどこか近寄りがたい雰囲気を醸し出していた。彼の悩む姿はなかなか拝めるものではない。
ガチャ、と彼のいる部屋に人が入ってくる。この雰囲気のシレンを全く意に介することなく、男は彼の向かいの椅子に腰を下ろした。
薄暗い部屋の中に、沈黙が流れる。
「東は歴史を繰り返すようだ」
シレンは一言そう呟く。
「被害は?」
言葉を返す男も、不敵な、冷たささえ感じる雰囲気の男だった。端正な顔立ちだが、それが逆に怖い、というイメージを相手に持たせかねないような。
「マリア・フィーラウネが捕えられた」
「マリア・フィーラウネ……ああ、あの洗脳歌の女か」
相手の呼称に、彼女と貴族学校時代の同窓生であるシレンは何と思ったのだろうか。
「あの女は確か“ピースメーカー”の機関の代表だったな。となると、うちの宰相殿が黙ってはいまい」
うちの宰相と言うと、北の宰相を務めるセティ・ユールのことか。彼は国王ローファサニ・ラックライの片腕でありながらも、マリアが代表を務める“ピースメーカー”のメンバーだ。平和のため、それを思い動いていた彼が、この事実を知ればどうなるか、いや、もう知ってしまっているのかもしれないが。
「今ここで彼に動かれるのはまずい」
直接的にシレンは関係ないはずなのだが、彼の表情は晴れない。
「だが陛下のことだ、宰相殿を止めたりはしないだろう」
相手の言葉にシレンも頷く。エルフの森の王を務めるローファサニが、他国の危機を放っておくわけがないのだ。それが彼の優しさであり、強さだ。だが、今ばかりはタイミングが悪い。
「遺物たちが活気づくにはいい材料になりそうだな」
「ああ」
淡々となされる会話。他者がこの会話を聞いて、理解することが出来るだろうか。
「俺が南に行って戻ってきた矢先だ。タイミングが悪すぎる」
どうやら彼の晴れない表情は自分にも責任を感じているからのようだ。ここ最近の彼は少し自由に動きすぎた。諜報部団長故の諜報部権限があるとは言え、彼も諜報部の一員であることに変わりはない。その忠誠は、命は陛下のためだ。西王の頼みで動いていたという理由があるとしても、それだけでは済まされまい。南での一件が大事件だったことは否定できないが、北でFT関連の事件がなくなっていないことも否定できないのだ。この件に関しては、北への輸入ルートを諜報部が調査することになっているのだが、それがまだ完了していないのだ。大元はザッカート孤児院だとしても、一体誰が協力しているのか、北の諜報部をもってしても調査が進まない。この現状と照らし合わせて、諜報部が祖国をないがしろにしていると言われれば、シレンには反論する資格がないとも言える。
北での調査は彼の信頼する義兄メルディン・マテルヴィクタスに委任していたのだが、彼をしても進まないということは、よほど力のある貴族が関与しているということなのだろうか。マテルヴィクタス家は北の下流貴族だが、フーラー家の分家に当たり、シレンの妻、キュアリスの生家だ。代々諜報部を輩出家であるし、諜報部としての実力を備えている一族と考えても問題はないはずなのだが。
だがこれは言い訳にしかならない。部下の責任は団長たる彼の責任だ。
この諜報部の問題だけで済めば、まだよかった。
今回の東の一件で、宰相であるセティは間違いなく東に向かおうとすることは想像するに難くない。そしてそれを国王であるローファサニが止めないであろうことも同様だ。
そしてこの他国への協力が、先ほど“遺物”と言われた“正統主義”の反発を招くことは間違いなくなるだろう。シレンの憂いはこれによるローファサニへの負担が加増することだ。彼は森の王として全力を尽くしている。それは痛いほどに分かる。だからこそ、彼の心労を増やす条件を用意してしまった自分が許せないのだ。彼の負担が増えれば、他国の援助もし辛くなる。
「……暗部となるか?」
「キルトクロム卿、俺の前でその言葉は、冗談が過ぎるぞ」
キルトクロム卿と呼ばれた男、アイアンナイツ団長を務めるザックス・キルトクロムの不可解な笑みとともに転がり落ちた彼の呟きは、シレンの逆鱗に触れかけた。今この場で二人が争えば、果たしてどちらが生き残るか。
「“遺物”など殺そうと思えばいつでも殺せる。だが、それでは何の意味もないだろう」
「不要なものは排除すべきだと思うけどねぇ」
その声は新しいもので、二人の聞き覚えのないものだった。
「誰だ?」
それでも取り立てて慌てることなく、ザックスが二人の気持ちを代弁するように、ただ一言そう呟いた。
「怪しいものじゃありませんよ。ただのしがない、東の事件の犯人です」
灯りを浴びて見えた姿に、二人は少なからず驚きの感情を抱いた。前髪で目元が見えなくなるような銀髪の男で、北で5本指に入るのは間違いない実力者のこの二人相手に、気配を気取られることなく近づける、緩いが不敵な雰囲気を持つ男は、おそらくこの世に一人しかいない。
「……キンダラー卿?」
どうしてここにいるのか分からないが、見間違えるはずがない顔だった。同じ諜報部のトップに立つ者という知名度もあるが、一度見た要人の顔を忘れるようなシレンではない。
「やぁ、久しぶりだねぇ、シレンくん」
マリア・フィーラウネ誘拐の報は、すぐに王城へと伝わった。事件が発生したのが夕刻だったのが幸いだった。“ピースメーカー”の拠点である屋敷の隣、フィーラウネ家のメイドが夕食の準備が出来た旨を伝えようとマリアの元へ向かい、惨劇を目にしたのだ。メイドはすぐにフィーラウネ家の家長であるマリアの7つ上の兄、ヴァンドリック・フィーラウネに報告し、彼が王城へと使いを飛ばした。
すぐさま王城からは王立騎士団長のカナン・ローレンフォードを含めた王立騎士団3名と、諜報部の副団長ランス・ナトレズムとニューシィ・ヒューレンが現場にやってきた。そこで奇跡的にもまだ辛うじて息のある男を見つけ、彼らは話を聞くことが出来たの。
斬られ、生死をさまよう状況にあった彼が口にしたのは、衝撃の一言だった。
「諜報部にやられた」
この一言に現場検証に来た5人は凍りついた。だが、改めて現場を見れば、脱ぎ捨てられた諜報部の制服、黒のコートが見つかった。ほどなく息を引き取った彼から、他の情報は得られなかった。残った現場からも、マリアが抵抗した形跡は見られない。部屋の入り口付近で倒れていたセホも、抵抗の形跡は見られなかった。彼女の亡きがらを見て、カナンは表情に影を落とした。きっと、彼女の敬愛するマリアを守ろうと必死だったのだろう。背後から刺された傷は、不意打ちだったに違いない。彼女は“東の聖騎士”と呼ばれたアスター・リッテンブルグの妹として、その名に恥じない騎士だった。
「このコートが誰のものか……すぐに調べろ」
感情を押し殺し、ランスがニューシィに命じる。諜報部では任務中の個を消し去るために、制服は誰が着ても構わないように、誰が誰にでもなれるように、制服ナンバーを設けてはいない。団員に与えられるのは任務であり、誰がこなしたかなど関係ないのだ。それに対して騎士であることに誇りを持つ騎士団は皆、制服や鎧に誰のものか判別できるナンバーが記載されている。死が誇りある死となる騎士団と、任務失敗による叱責となる諜報部での差だ。
しかしながら諜報部の者がやったとなれば、大問題だ。諜報部は国政に関わりかねない極秘の情報を取り扱うこともあることから、騎士団以上に絶対的な忠誠が求められる。それは自分の命よりも、忠誠を重んじろ、その域でだ。
さらに言えば、諜報部団員の過失は、騎士団以上に長である諜報部団長にも負わされる。扱う任務内容の重大性が重いことがその差と言われている。
よって。
「どうしたものですかねぇ……」
この知らせが王城へ戻った彼らから、国王ライト・クールフォルトを初めとする重鎮たちに知らされた。各大臣及び騎士団長たちを集めた会議開始まで残り30分。このままいけば全ての責務が諜報部団長であるマグナドの元へ寄せられかねない。実質彼ら諜報部が全力を挙げてFT調査を進めているも、進展はほとんどなく、FT事件数は停滞したままだ。それはつまり、成果を上げられていない、結果を出せていない、とも理解されかねない。特に文官たちに現場理解を求めるのは、ほぼ不可能だ。優しいライトのことだから、ある程度責任は減るだろうが、マグナドと埋めがたい溝のある宰相グロリア・ゼヴィアスが何というか。
このグロリア優位という状況が、マグナドには不愉快でしょうがなかった。
彼の顔を思い浮かべると、苛立ちが極限まで募る。
「先日、地図を広げて反抗……非協力貴族はどこかなぁ、って探してたんですけど……」
ニューシィが、表情暗く声を出した。今彼女たちがいるのは、諜報部がよく会議で使う一室だ。その中にはマグナドと、現場検証帰りの二人、という構図だ。
「言いにくいかい? 続けてごらん?」
その言葉にマグナドが軽く苦笑を浮かべる。
「貴族の屋敷を結ぶと、五芒星を描くんです。今は滅んだオーチャード家も含めて、ピーオット家、リーケイル家、ウェスロー家、ガルセイム家です。そして、その中心にあるのが……アシモネル家です」
彼女の発言に、ランスが血相を変えた。
「その話は、絶対に言うな!」
「私は構いませんよ?」
「な?!」
彼が怒鳴ってくれた理由は分かる。怒鳴ってしまったからこそ、ランスはマグナドの考えが不可解だった。今ニューシィが口にしたアシモネル家は、マグナドの恋人であるニミア・アシモネルの住む家だ。かの家は協力も反抗もしない、俗世に視線を向けることのない貴族として名が知れている。だが、だからこそ反抗貴族と言われても反論はできないのだ。東の王はクールフォルト家であり、彼女の家は王家ではない。忠誠は、誓わねばならぬのだから。
「しかも事件発生時刻を考えると私がいたのは彼女のところですからねぇ」
親しい者の証言は、アリバイにならない。よってマグナドがその時間何をしていたかを証明する者がいないのだ。彼が黒幕と言われても、それを否定しきる材料がない。
「いっそ私が犯人になってやりましょうか?」
「ふ、ふざけるな!」
ランスの怒りの矛先はマグナドで移動する。彼が本気で言っていないのも分かるが、本気で彼を心配する自分の感情がそれを許したくないのだ。
「ランス、君は優秀だ。私は君を誰よりも信頼している。だから、私に何かあった場合は、君が……」
打って変わって真面目なトーンで語り出すマグナドに、今度はランスも言葉を失う。
「なぁんて。おふざけはここまでにしましょうか」
表情をコロコロ変化させて彼をからかうマグナドに、ランスは言葉を失うほど激昂した。それをまぁまぁとなだめつつ、マグナドの視線がニューシィへと移る。
「今言ってくれた貴族たちは皆、私兵団の一部を王国へ寄進しない非協力貴族です。そしてその中には諜報部団員はおろか、騎士団員すら輩出している貴族もいない。そうなると、それらの貴族と親しい王国関係者は、私くらいしか浮かびあがらないでしょうねぇ。なんたって彼らに近づくメリットがありませんもん。それでもし私が犯人だとしたら、私を諜報部団長に任命した方へも責任が飛び火しかねない」
マグナドがそこまで語って、ランスがはっとした表情を見せる。
「今回の一件はまさか、王威転覆を狙ったものだというのか?!」
「ま、そう考えるのが妥当でしょうねぇ」
マグナドが手元の紙にペンで何かの記号を書きだす。
「ここで私が中途半端に否認し続けると、それこそ相手の思惑通り陛下への御迷惑が発生するでしょう、何たって相手はそこが目的なんだから」
今度はその隣に文章を書きだす。
「ですので、私が犯人だということにしちゃいましょう」
紙に書き終え、彼は笑顔でそう言った。
「「な?!」」
驚いて当然だ。諜報部に入ってからの11年間、ずっと王国に忠誠を捧げてきた男が、あっさりと自分が犯人であると名乗るというのだから。逆に国王であるライトへ迷惑をかけないようにする配慮ではあるのだろうが、二人には納得がいかなかった。
「私はとりあえず、逃げます。ランス、君がこれから始まる会議に参加してください。私のことは逃げたことにし、この紙を陛下に渡してください」
マグナドの目は、本気だった。
「絶対に陛下以外の方にこの紙を見せぬように。ニューシィ、君はランスの補佐として協力してあげてください。なお他の諜報部の者には私がわざと逃げたことはふせておいてください」
ちらっと彼が書いた紙を見ると、何かの記号と『私が犯人です。陛下自ら追跡命令を出してください』という走り書きがあった。これでは彼が犯人ではないと言っているようなものだ。だからこそライトだけに、バレないように見せねばならないのだろう。
「ではランス、あとを頼んだよ」
まるでいつもの書類業務を彼に任せて帰る時のように、マグナドは軽い足取りで席を立つ。ニューシィには何も言えなかったが、彼女にはランスの補佐という任務が与えられた。今はそれを全うするまでだ。
「マグナド、この前貸した食事代、返済期限が今月いっぱいなの忘れるなよ!」
ランスの眼鏡の奥の目は、彼を信頼していた。
振り返らず、東の諜報部団長マグナド・キンダラーは、彼らの前から去って行った。
――さて、とりあえず南に行ってザッカート孤児院を探るような余裕もないし、北のシレンくんの所にでもかくまってもらいますかね。
そんな思いで城内を出口の方へ向かっていると、知った顔に出会った。
「む、マグナド、会議室はそちらではないぞ」
王立騎士団長のカナン・ローレンフォードだった。いつも通りの真っ直ぐな瞳は、相変わらず単純そうで、好感が持てる。
「トイレですよ、トイレ」
これが嘘だとは、彼女は全く気づく様子もない。
そしてすれ違う二人の距離がほぼゼロになった時。
「貴女の騎士団を動かすのは、貴女ですよ」
マグナドがそう呟いた。
「な、何を……そんなこと当たり前だろうが!」
彼の言葉の意味が分からず、カナンは怒ったような口調でマグナドに言葉をぶつけた。
「分かっているならいいんです」
そんな彼女に対しても、彼はにこやかに応えた。いつもにない彼の表情に、カナンは違和感を覚えた。
だが、今はそれよりも会議だ。そう思いなおし、カナンは会議室へ向かい、マグナドは城外へと出て行った。
「といった感じでしてね」
こんな状況だというのに、軽い口調でマグナドはここまでの経緯をシレンたちに話してくれた。彼の口調のせいで深刻には聞こえなかったかもしれないが、普段から落ち着き、暗いと言っても過言ではないシレンたちは真剣に彼の話に耳を傾けていた。
「王威転覆を狙っている当たり、黒幕の予想は敗北者の一族と考えて差し支えないか?」
ザックスの予想に、マグナドは頷いてみせる。
「流石はキルトクロム卿、知恵者の一族は伊達ではありませんねぇ」
「キンダラー卿、貴方がここに“来た”理由はわかった。だがここに“居る”理由はなんだ?」
7つ年上のマグナドに対して、シレンは物怖じせず尋ねた。元より彼が物怖じする相手など存在しないかもしれないが。
「言いましたよね? 私は追跡される身です。だから匿っていただきたい」
さらっと言ってのけるような、軽い話題ではないはずだが、彼が言うと軽く聞こえるから不思議だ。
「亡命とでも?」
「ま、そんなとこです。王国に縛られた身では、自由に動けませんからねぇ……。真実を暴き、悪を成敗するためには追放された方が動きやすい」
彼の表情はいたって穏やかだが、その瞳には固い決意が隠れていた。
「それで、貴方を匿う見返りは?」
「あれ? 私と貴方の間柄に、そんなものが必要なんですか?」
いつもの調子でとぼけてみせるマグナドに対し、二人の表情は動かなかった。
「あぁ、あいにく俺は貴方を尊敬こそすれ、信頼はしていない。取り引きでしか貴方の要求には応じれないな」
「全く、うちの国の奴らと違ってやりにくいんだから……」
シレンの淡々とした通告に、マグナドは苦笑するばかりだった。北の者が、というよりも、この二人が固いのだ。
「“純白”の反対は?」
脈絡なくマグナドが二人に言葉を投げかける。
「“漆黒”とでも言うのか?」
ザックスがそれに答える。どうやら取り引きが始まったようだ。
「ご名答。そのように、白の反対は黒、これはどこの国でも表裏一体の関係と言ってもいいでしょう」
その言葉にシレンが少しだけ口元を緩めた。そして視線をマグナドへ動かす。
「それだけ知っていながら何故動かなかった?」
「うちの諜報部は権限が弱い上に、うちの国は文官たちの力が強くてね。強引に動けないのさ。お姫様を巻き込んで、傷つけるようなこともしたくなかったしねぇ」
「確かに“時代を支えてきた”奴らだからな、迂闊には手を出せないのはこちらも同じ……。ん? 今“どこの国も”と言ったか?」
そこでシレンは気がついた。
「だから言ったでしょう? 不要なものは、排除すべきだって」
西にて。
コンコン、と乾いた音を響かせ、エキュア・コールグレイは父であるシュバインの部屋を訪れた。
「失礼します」
厳格な雰囲気漂う彼、シュバイン・コールグレイは今年で58になる高齢の男性だ。だがその存在感は未だ衰えず、大戦以前の戦争の時代をよく知る賢者のポジションでもある。現西の48貴族の中でも最高齢の家長であり、その発言力は西王に勝るとも劣らないのが実情だ。未だに彼がゼロの元へ謁見していないことも、その発言力維持に加担しているのだろう。
「何の用だ?」
低く、威圧的な声でシュバインが入ってきたエキュアを見る。読書を中断されたから、というわけではなさそうだが、鷲のように鋭い眼光に見据えられ、エキュアは委縮してしまった。
彼のことは苦手だった。幼い頃から優しくしてもらった記憶はない。常に厳しくしつけられてきた印象しかない。普段は粗暴なふるまいの一番下の弟であるライダーも、彼の前では仔犬のようにならざるを得ないのだから、彼の怖さが分かるだろう。
「陛下からの通達です。南との国境を抱える我がコールグレイ家に、有事の防衛を依頼したいとのことです」
コールグレイ家が抱える私兵団は総勢5000名の大軍団だ。かつての地方分治時代は、1万を越える数の私兵団だったが、軍縮の波を受けて今は5000となった。だがそれでもこれが西一番の私兵数であることには変わりない。北との国境を抱えるグレムディア家と双璧をなす大貴族であったコールグレイ家の名残はいまだに強い。旧コールグレイ領は、配下貴族を16家も抱えていた。その全てを彼がまとめあげていたのだから、彼個人としての能力の高さも相当なものである。かつての分治時代を支えた、“時代を支えた男”と称されることも大げさではない二つ名だ。
「ウォービルの倅がそのようなことを申したか」
くっくと喉を鳴らして笑う彼に対して、エキュアに畏怖の感情が浮かぶ。これだけの恐れを感じては、彼との血の繋がりがあるとは到底思えない。
「無論私は西の貴族だ。国を守るためであれば協力は惜しまんよ」
この言葉は、予想が出来たものだ。そこでふと実感する。彼をここまで恐れるから、自分は彼と同じ“正統主義”の思想を持たなかったのではないか、と。兄は、ヴァイス・コールグレイは彼が怖くないのだろうか。
「では国境を面してすぐ隣の、ウェンタンス家がザッカート孤児院に攻められた場合、援軍を出してくださいますか?」
「馬鹿を申すな」
これも、悔しいが予想通りだった。
「コライテッド家の若造が国を失ったのは己を弱さ故。その尻拭いをわざわざ西の我らがする必要がどこにある? 南が西の軍門に下るというのならば考えてやらんこともないがな」
分かっていた。彼を動かせないのは、分かっていた。
「ですが、陛下は父上の協力を所望しています」
「そもそも私はウォービルのいるアリオーシュ家であるから、アリオーシュ家の王位を認めたのだ。軍事において奴の右に出る者はいなかったからな。だが実際王位に就いたのはその倅だ。私はそのことを未だ了承したつもりはない」
「陛下は、大戦で連合軍を率いた方ですが?」
「3国の力を持って1国を攻めるなど、誰でもできるわ」
根本的に、彼はゼロ・アリオーシュという存在を見ていないのだと分かった。それが、エキュアにはたまらなく悔しかった。初めは彼女も英雄だなんだのと一人歩きしていた彼の存在を、半信半疑に思っていた。だが実際彼の凱旋から、この国は変わったような気がする。少なくとも、円卓のメンバーの意識は一層森のためを考えるようになったはずだ。
今ならばはっきりと、彼に仕えていることを、彼のために働いていることを誇りに思う。
「……ですが、世論は既に陛下への忠誠を示しています。ここでコールグレイ家が従わぬは、近隣貴族への示しが尽きませんよ?」
「近隣貴族? あぁ、我が配下貴族たちか」
配下貴族、その表現さえも既に過去のものだ。アリオーシュ家が王位に就いたことにより、貴族の序列はなくなった。資金面や私兵団で上流から下流まで呼ばれることもあるが、公にはそれらの序列は存在しないことになっている。
その言葉を聞き、最早彼の耳に自分の言葉は絶対に届かないことを悟る。
――私では、駄目なのだな……。
陛下へ、ゼロへ力添えできないことが悔しかった。自分の親に、自分の言葉が届かないのが悔しかった。自分の無力が、悔しかった。
「あやつに伝えろ。他国にうつつを抜かしている暇があるのなら、我が国のFTを撲滅させろとな」
「……失礼します」
もうこれ以上彼といたくなかった。
夜遅い時間ではあったが、コールグレイ家にいることさえ躊躇われたエキュアは、複雑な思いのまま、王城の近衛騎士団の会議室へと向かうのだった。
馬車の窓から見える空は、どんよりと曇り、先行きの見えない未来を案じているいるかのように思えた。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
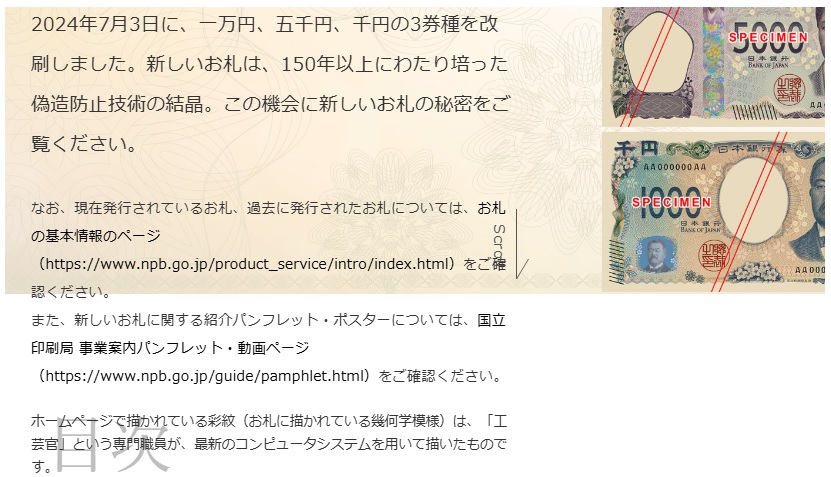
- 模型やってる人、おいで!
- 東京口の211系(その43) サン…
- (2024-11-15 19:15:30)
-
-
-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…
- 声優グランプリ 2024年 12月号 [雑誌…
- (2024-11-15 14:51:50)
-
-
-

- 鉄道
- ローカル情緒漂う山形新幹線
- (2024-11-15 18:44:27)
-
© Rakuten Group, Inc.



