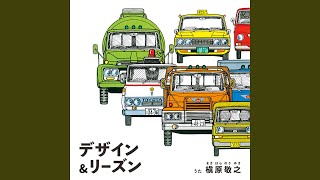桃李不言 下自成蹊
「桃李(とうり)言わざれど、下おのずから蹊(こみち)を成す。」
桃や李(すもも)は物を言わないが、その下にはおのずと小道が出来ます。
という意味です。
謎掛けです。
小道が出来る理由。それは、花が咲き、実が成るからです。
人々が、その花を愛で、実を取るので自然と道が出来るのである。と言う事です。
さて、これをあるひとつの事象に例えます。
「徳の高い人というものは、自己宣伝しないけれど、自然に皆が心服するという意味に例えられています。
『史記』「李将軍伝」にある一節です。
李広(りこう:? - 紀元前119年):中国前漢時代の将軍。文帝、景帝、武帝に仕えました。秦の名将の李信の子孫です。
李将軍は、田舎者のような態度であり、口下手であったが死んだ日には(自刎しています)天下の知る人と知らざる人と、皆が悲しんだ。
「桃李不言 下自成蹊」とは李将軍の事であると史記の著者、司馬遷は褒めています。
人徳というものは、一朝一夕にして身につくものではありません。
徳の高い人というものは、自己宣伝しないわけでは無いと思いますが(李広も将軍として先陣を切りたいなどとアピールしていますから)その自己宣伝は桃や李で言うところの、花であり、実でありましょう。
その花が美しく、実が美味しければ自然と道が出来るのです。
人徳もまた然り。
適切な自己宣伝と、そして、この人こそという実力があればこそ、人が集まるのです。多く語る必要は無い。口下手でも良い。不器用でも良い。信頼されれれば良いのです。
ちなみに、【道旁苦李】という諺もあります。
【道旁苦李】
「どうぼうのくり」
ちょっと見には立派であり、道端の取りやすいところにありながら、その味が苦いので、成った実を誰も取らないということです。
『桃李不言 下自成蹊』とはまるで正反対の諺ですね。
いくら自己宣伝しても、その中身がよろしく無いのでは見向きもされないということです。
これら、わたくしが小学校の頃に父から受け継いだ古典語典という書物に載っていました。
古典語典:渡辺紳一郎 著
わたしが生まれる前の書物ですので、古本屋にでも行かないと無いと思いますが、興味があったら図書館などで一度読んでみる事をお勧めします。
わたしはこの書物のせいで、中国史に興味を持ち、軍師に憧れ、孫子やら六韜など読みました。半分も理解していないけど。。。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 「Rocker? ロングスリーブ」 折れた…
- (2025-11-20 16:45:29)
-
-
-

- 楽天写真館
- 2025年 4-6月 リストレット&コサー…
- (2025-11-20 13:06:08)
-
© Rakuten Group, Inc.