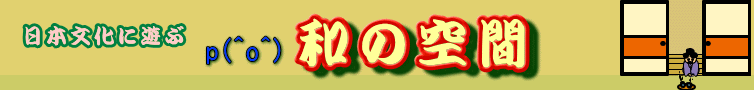テーマ: 政治について(21527)
カテゴリ: 天皇・皇室関連

皇位は皇統に属する男系男子が継承することになっている。それは皇統譜(天皇家の系図)から明らかだと思われるのだが、男系による皇位継承は明治時代になってから決まったとか、古代の日本は女系継承だったとか、じつに奇妙な説が出てきて伝統を根本から破壊しようとしている。
ただ、これらは一面では正しいだろうと思われる。たしかに男系という言葉自体は明治時代から使われだしたのだろうし、古代日本には財産等を女系で継承していた民俗もあったと思われる。しかしそれらは一面的な判断であり、それを敷衍して天皇家の皇位継承に当てはめるのは間違っている。
まず、男系が明治時代に決まったというのは、法律的に明示されたのは明治時代だとしても、慣習法として男系で日本社会が回ってきたことは明白である。実際、男系の系図は歴史資料として多く残っているだろうが、厳密な女系(母娘継承)の系図は存在しないのではなかろうか。
また、古代日本においては庶民レベルでは女系の財産継承があった可能性は十分にあるが、天皇家をはじめとして上流階級の家はすべて男系だったと言える。それは、大化元年に孝徳天皇の詔した「男女之法」が良人(良民)の家の男系継承を決定づけたからである。
大化元年(645年)8月5日の孝徳天皇の詔
男女 の法は、良男 ・良女 共に所生 らむ子は、其の父に配 けよ。若 し良男、婢 を娶 きて所生らむ子は、其の母に配けよ。若し良女、奴 に嫁 ぎて所生らむ子は、其の父に配けよ。若し両家 の奴婢 の所生らむ子は、其の母に配けよ。若し寺家 の仕丁 の子ならば、良人 の法の如くせよ。若し別に奴婢に入れらば、奴婢の法の如くせよ。今し克 く人に制の始めたることを見 さむ。」
(『新編 日本古典文学全集 日本書紀3』小学館. p.121)
〔現代語訳〕
また男女の法は、良男・良女の間に生れた子は、その父につけよ。良男が婢を娶 って生れた子は、その母につけよ。もし良女が奴に嫁いで生れた子は、その父につけよ。二つの家の奴婢 の間に生れた子は、その母につけよ。寺院の仕丁 の子の場合は、良人の法のとおりとするが、別に奴婢に入っている場合は、奴婢の法のとおりとせよ。今、人々に法の制定の始まりを示すものである。
(同書 p.121下段)
〔頭注〕
【男女の法】生れる子を、男女すなわち父母のどちらに配するかを定めた法。唐令は「戸令」に「良人相姦、所 レ 生男女随 レ 父…」の規定があり、その影響があるか。養老令には良民と賎民の間の所生男女の身分についての規定は「戸令」にあるが、右の唐令に対応する条文はない。
【奴婢】神代紀下・第十段一書第四 (『日本書紀1』187頁 四・五行 ) にみえる「奴婢」の語は、男女の召使の意でツカヒと訓んだ。本条は令制でいう良民に対する賎民の身分で、「戸令」に種々の規定があるが、大化期にはそのような法制はなく、後文にみえる「奴婢の法」は慣習法のことであろう。
【仕丁】令制用語で、養老「賦役令」仕丁の条に規定がある。大化二年正月条の改新の詔の其の四の凡条にも「仕丁」の語がある。ここでは寺に仕えて雑用に従事する男を令制用語を用いて「寺家の仕丁」といった。
【人に制の始めたることを見さむ】『日本書紀通証』(谷川士清)に「見 2 人為 レ 制之始 1 」とは、人々に制と為す始めを知らせることをいうとある。大化の改革は、男女の法という身分法の制定から始ることをいったか。
(同書 p.121頭注)
これは「誰が誰の子か」を定めた法である。良民と奴婢の混血はすべて奴婢の子とした。そして、良民同士の子は妻(女)の子ではなく夫(男)の子と見なしたのである。この男女の法を何世代にもわたって適用していけば、当然のことながら男系の系図ができあがる。したがって男系の起源は、遅くとも645年になる。
ここでは女系は「奴婢の法」とされているが、これは頭注にもあるように慣習法だったと思われる。私の見解では、天皇をはじめとして良民の核になるような有力氏族は弥生時代以降に大陸からやってきた渡来人である。そして、縄文・弥生時代の日本の原住民は、渡来人に征服されて奴婢の身分に落とされていたか、渡来人に帰順しその慣習を受け入れることで良民化されていたのではないかと思う。そうすると、日本の原住民が女系継承を慣習法としていた可能性は大いにある。逆に、天皇家をはじめとする渡来民族が北方系ならば、むしろもともと男系を継承規則と考えていたとしても自然である。したがって、天皇家などの渡来民族では、男系継承は645年以前から自明の慣習法だったと思われるのである。
もしもこのような歴史観が正しかったとすれば、この男女の法によって征服者側の渡来人は男系で継承していくことを再確認し、また被征服者の原住民に関してはこれまでどおり女系継承を追認することになったのだろう。男女の法は、男系民族と女系民族の混交による社会秩序の曖昧さを回避するために、曖昧なものはすべて女系民族の側に押しつけてしまうという法秩序を明確化したものだろう。
少なくとも純粋な女系(母娘継承の連続)は奴婢の法であり、良民のさらに上に位置すべき天皇家がとるべき継承法ではない。 「日本の(良民の)家は男系でいく」というのが日本という国の最も根本的な法であったことになる。
少なくとも「男女の法」以降は天皇家は男系でなければならない。そうしないと藤原氏などとの間で婚姻関係を結んだ場合に制度上に不整合が生じてしまうからである。また、「男女之法」以前に天皇家が女系だったとしたら、古事記や日本書紀の時代に男系系図を捏造したことになろう。そんな面倒なことをするわけがない。
日本国民のなかには日本原住民の末裔もいるのだろうから、一般国民に関しては女系の家を認めてもよいのかもしれない。しかし、天皇家はもともと男系の家なのだから男系継承を貫くのが当然である。
↑この記事が面白かった方、またはこのブログを応援してくれる方は、是非こちらをクリックしてください。
「p(^o^) 和の空間」の Window Shopping
和
”にこだわりたい>
私の第2ブログ「 時事評論@和の空間 」と第3ブログ「 浮世[
無料メルマガ『皇位継承Q&A』
↓ネット世論はこんな感じ。
《 皇位継承あなたの意見は? 》
目次 ブログ散策:天皇制の危機 も合わせて御覧ください。
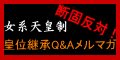
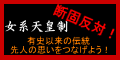
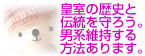
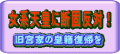
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[天皇・皇室関連] カテゴリの最新記事
-
道鏡について(1)皇胤説の史料 2010年11月29日
-
天皇のカリスマ 2010年04月29日
-
今年の歌会始は「光」 2010年01月16日
Re:男系起源は男女之法にあり(06/20)
いしゐのぞむ さん
極めて當り前のお話。女系論者の大嘘を打破して下さいました。
(2023年04月02日 21時05分17秒)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.