tkfmi2006さん
>『春の祭典』の音楽は確かに今では、現代音楽の古典といえる存在で非常に耳慣れている人も多いと思います。 2~3年前に確かアメリカン・バレー・シアターだったと思いますが・・・バレエを見てその振り付けの異様さに驚いたことがあります。初演のニジンスキー版の振り付けだったかどうかは定かではないのですが、初演当時の音楽ならびに振り付けの異様さに当時の人々が物議をかもしたのもなるほどとうなずけました。
-----
おもしろいですね。 音楽は耳慣れていて振り付けの異様さには慣れていない。もともと舞台で踊るダンサーの振り付け音楽バレエ音楽。 バレエを観ずに音楽だけ聴く機会の多いバレエ音楽。 非常におもしろい話ですね。
(2007年05月30日 01時24分48秒)
>『春の祭典』の音楽は確かに今では、現代音楽の古典といえる存在で非常に耳慣れている人も多いと思います。 2~3年前に確かアメリカン・バレー・シアターだったと思いますが・・・バレエを見てその振り付けの異様さに驚いたことがあります。初演のニジンスキー版の振り付けだったかどうかは定かではないのですが、初演当時の音楽ならびに振り付けの異様さに当時の人々が物議をかもしたのもなるほどとうなずけました。
-----
おもしろいですね。 音楽は耳慣れていて振り付けの異様さには慣れていない。もともと舞台で踊るダンサーの振り付け音楽バレエ音楽。 バレエを観ずに音楽だけ聴く機会の多いバレエ音楽。 非常におもしろい話ですね。
(2007年05月30日 01時24分48秒)
テーマ: 好きなクラシック(2399)
カテゴリ: クラシック音楽
『 今日のクラシック音楽
』 ストラヴィンスキー作曲 バレエ音楽「春の祭典」
イゴール・ストラヴィンスキー(1882-1971)は、3つのバレエ音楽で有名です。 「火の鳥」、「ペトルーシュカ」、そして「春の祭典」です。 この3つの曲が最もポピュラーな曲として彼の名を音楽史上に名を残しています。
そのストラヴィンスキーのバレエ音楽は、「ロシアバレエ団」の主催者ディアギレフと切り離して語れません。
1909年に興した「ロシアバレエ団(バレエ・リュッセ)を率いてパリで打った興行が大成功を収め、以来このバレエ団は彼の死(1929年)まで20年間世界のバレエ界を引っ張っていきました。
そのディアギレフと親交を結んだストラヴィンスキーは、同時に世界の檜舞台へと駆け上がって行きました。 ストラヴィンスキーを語る上でディアギレフはなくてはならない人なのです。
この二人の接触は1908年だと言われています。 ストラヴィンスキーはまだ無名の時代でした。 ディアギレフはストラヴィンスキーの「花火」を聴いて、彼の才能を高く評価して新作バレエ音楽を依頼したことが始まりでした。
その曲がバレエ音楽「火の鳥」でした。 1910年6月25日にパリで初演されたバレエが大成功を収め、ストラヴィンスキーの名は一夜にして世界を席巻したのです。 ストラヴィンスキー28歳でした。
この「火の鳥」の作曲の頃に、不思議な幻想にとらわれています。 幻想とは異教徒たちが原始的な儀式を行うというもので、厳粛な中に行われており、円く座った長老たちに春の太陽が降り注ぎ、中央では太陽の神への生贄となった乙女が踊り狂って死んでいく、そんな幻想でした。
1913年5月29日にパリのシャンゼリゼ劇場で、ピエール・モントーの指揮で初演されました。
この初演にまつわるエピソードは、この曲を聴いている方々はおそらく知っているほど、クラシック音楽史上類を見ない騒ぎとなったのです。 ファゴットで始まったこの音楽は、パリの人たちが今でに聴いたことのないリズム(変拍子)や不協和音に驚いて、口笛を吹いたり、床を踏みつけたり、お互いに罵り合うなど未曽有の騒ぎとなり、「私は曲の数小節が始まって間もなく、嘲笑が沸き起こったので、いたたまれずに席を立った・・・・」(ストラヴィンスキー)という程の騒ぎでした。 初演の指揮者モントーの回顧談では「16番街の淫売婦!」というユニゾンでの哄笑があったと述べています。
聴衆の無理解もわからぬことではありません。 指揮者モントーがスコアを始めて見た時に、「一音も理解できなかった」と述壊しているほどです。
それほどこの曲は当時の人々に衝撃的な音楽でした。 現在でこそ現代音楽の古典と呼ばれており、演奏会や録音でも定番となっているほどポピュラーな曲となっています。
私がこの曲を初めて聴いたのが高校1年生(1960年)でした。 当時毎日曜日の朝10時から、日本フィルハーモニーの定期演奏会の模様をフジテレビが放映していました。
その朝の番組はイゴール・マルケビッチ指揮でした。 曲はストラヴィンスキーの「春の祭典」。 作曲家名を知っていても音楽を聴いたことのない時代でした。 ましてや彼の「春の祭典」など聴いたこともなく、テレビの前でどんな音楽かなと興味津々でした。 聴き終わって私はすぐに調べました。 どこかの会社からこの作品のLPがリリースされていないか。 ありました。 マルケヴィッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団の25cmLP盤。 1500円。 私は亡父に頼みました。 買ってもらったこのLPを35年間聴いていました。
さて、この音楽なんですが、現代音楽と言っても原始的なリズム、不協和音の連続、咆哮する金管楽器、のたうちまわるようなティパニー。 この音楽の魅力は何と言っても原始的な色彩豊かな音楽でしょう。
曲は2部構成で、第1部「大地礼讃」、第2部が「いけにえ」となっています。
時代は古代ロシア。 春が芽生えてきたロシアの大地で、原始民族が大地に感謝をする行事を描いています。 そして選ばれた乙女が太陽の神への生贄となって踊り狂うという物語です。
ロシアの原始的な主題がファゴットで奏されて曲が始まりますが、とてつもない高音域で始まり、弦楽器が強烈なリズムを刻みます。 そして不協和音の氾濫。 物凄いエネルギーのブラスの咆哮。
やはり約100年前のパリの聴衆には理解できない超進歩的な作品だったのでしょうか?
愛聴盤
(1) アンタル・ドラティ指揮 デトロイト交響楽団
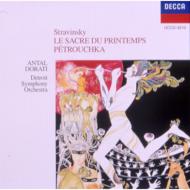
(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3210 1981年録音)
色彩豊かにロシア情緒をうまく表現した演奏で、ドラティのバレエ音楽演奏の巧さを知る名盤。 録音も超優秀です。 「ペトルーシュカ」とのカップリング。
(2) イゴール・マルケヴィッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団
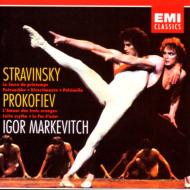
日記にも書いている通り、マルケビッチの演奏を長い間愛聴していた録音。私の「春の祭典」はこの演奏なしに語れません。 50年近くなる古い録音ですが、色褪せていません。
(3) ロリン・マゼール指揮 クリーヴランド管弦楽団
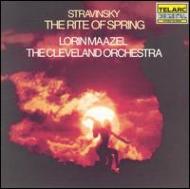
(テラーク・レーベル CD800054 1980年録音 海外盤)
マゼールのバトン・テクニックでクリーヴランドを思いのままに操る演奏。 この盤を採り上げたのはテラークの誇る超優秀録音の凄さです。
(4) スヴェトラーノフ指揮 ソヴィエト国立交響楽団
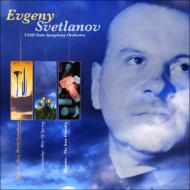
(ロシアレーベル SC030 1966年録音 海外盤)
爆演指揮者というニックネームのあるスヴェトラーノフの古い録音ですが、まさにこれぞロシアの大地で踊るバレエと言わんばかりの、強烈なリズムで刻むロシア一色の演奏。
(6) ファジル・サイ(独奏ピアノ)
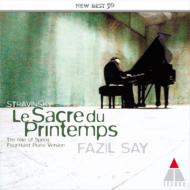
(テルデック原盤 ワーナー・ミュージック WPCS21228 1999年録音)
ピアノ・デュオ盤は何点かリリースされていますが、独奏による演奏はこれだけ。 多重録音による演奏。 旋律、和音などとても勉強になるディスクです。 現在は1000円盤です。
(7) マルケビッチ指揮 日本フィルハーモニー交響楽団
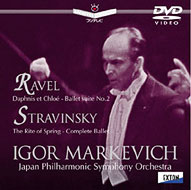
(EXTONレーベル OVBC00009 1968年収録)
1968年に何度目かの来日で再び日フィルを振って「春の祭典」を披露したマルケビッチ。 とても懐かしい映像です。 日本で「春の祭典」を広めたのはマルケヴィッチだと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『 今日の音楽カレンダー 』
1801年 初演 ハイドン オラトリオ「四季」
1860年 誕生 イサーク・アルベニス(作曲家)
1912年 初演 ドビッシー 「牧神の午後への前奏曲」
1913年 初演 ストラビンスキー バレエ音楽「春の祭典」
1915年 誕生 カール・ミュンヒンガー(指揮者)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ともの『 今日の一花 』 麦撫子(むぎなでしこ)
 撮影地 大阪府和泉市
撮影地 大阪府和泉市
なでしこ科ムギセンノウ属
ヨーロッパが原産でしょうか、たくさん植わっているのを見たことがあります。
葉が長いので麦に例えられて、この名前がついたと言われているそうです。
1mくらいの高さになります。 5月には花が咲きます。
イゴール・ストラヴィンスキー(1882-1971)は、3つのバレエ音楽で有名です。 「火の鳥」、「ペトルーシュカ」、そして「春の祭典」です。 この3つの曲が最もポピュラーな曲として彼の名を音楽史上に名を残しています。
そのストラヴィンスキーのバレエ音楽は、「ロシアバレエ団」の主催者ディアギレフと切り離して語れません。
1909年に興した「ロシアバレエ団(バレエ・リュッセ)を率いてパリで打った興行が大成功を収め、以来このバレエ団は彼の死(1929年)まで20年間世界のバレエ界を引っ張っていきました。
そのディアギレフと親交を結んだストラヴィンスキーは、同時に世界の檜舞台へと駆け上がって行きました。 ストラヴィンスキーを語る上でディアギレフはなくてはならない人なのです。
この二人の接触は1908年だと言われています。 ストラヴィンスキーはまだ無名の時代でした。 ディアギレフはストラヴィンスキーの「花火」を聴いて、彼の才能を高く評価して新作バレエ音楽を依頼したことが始まりでした。
その曲がバレエ音楽「火の鳥」でした。 1910年6月25日にパリで初演されたバレエが大成功を収め、ストラヴィンスキーの名は一夜にして世界を席巻したのです。 ストラヴィンスキー28歳でした。
この「火の鳥」の作曲の頃に、不思議な幻想にとらわれています。 幻想とは異教徒たちが原始的な儀式を行うというもので、厳粛な中に行われており、円く座った長老たちに春の太陽が降り注ぎ、中央では太陽の神への生贄となった乙女が踊り狂って死んでいく、そんな幻想でした。
1913年5月29日にパリのシャンゼリゼ劇場で、ピエール・モントーの指揮で初演されました。
この初演にまつわるエピソードは、この曲を聴いている方々はおそらく知っているほど、クラシック音楽史上類を見ない騒ぎとなったのです。 ファゴットで始まったこの音楽は、パリの人たちが今でに聴いたことのないリズム(変拍子)や不協和音に驚いて、口笛を吹いたり、床を踏みつけたり、お互いに罵り合うなど未曽有の騒ぎとなり、「私は曲の数小節が始まって間もなく、嘲笑が沸き起こったので、いたたまれずに席を立った・・・・」(ストラヴィンスキー)という程の騒ぎでした。 初演の指揮者モントーの回顧談では「16番街の淫売婦!」というユニゾンでの哄笑があったと述べています。
聴衆の無理解もわからぬことではありません。 指揮者モントーがスコアを始めて見た時に、「一音も理解できなかった」と述壊しているほどです。
それほどこの曲は当時の人々に衝撃的な音楽でした。 現在でこそ現代音楽の古典と呼ばれており、演奏会や録音でも定番となっているほどポピュラーな曲となっています。
私がこの曲を初めて聴いたのが高校1年生(1960年)でした。 当時毎日曜日の朝10時から、日本フィルハーモニーの定期演奏会の模様をフジテレビが放映していました。
その朝の番組はイゴール・マルケビッチ指揮でした。 曲はストラヴィンスキーの「春の祭典」。 作曲家名を知っていても音楽を聴いたことのない時代でした。 ましてや彼の「春の祭典」など聴いたこともなく、テレビの前でどんな音楽かなと興味津々でした。 聴き終わって私はすぐに調べました。 どこかの会社からこの作品のLPがリリースされていないか。 ありました。 マルケヴィッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団の25cmLP盤。 1500円。 私は亡父に頼みました。 買ってもらったこのLPを35年間聴いていました。
さて、この音楽なんですが、現代音楽と言っても原始的なリズム、不協和音の連続、咆哮する金管楽器、のたうちまわるようなティパニー。 この音楽の魅力は何と言っても原始的な色彩豊かな音楽でしょう。
曲は2部構成で、第1部「大地礼讃」、第2部が「いけにえ」となっています。
時代は古代ロシア。 春が芽生えてきたロシアの大地で、原始民族が大地に感謝をする行事を描いています。 そして選ばれた乙女が太陽の神への生贄となって踊り狂うという物語です。
ロシアの原始的な主題がファゴットで奏されて曲が始まりますが、とてつもない高音域で始まり、弦楽器が強烈なリズムを刻みます。 そして不協和音の氾濫。 物凄いエネルギーのブラスの咆哮。
やはり約100年前のパリの聴衆には理解できない超進歩的な作品だったのでしょうか?
愛聴盤
(1) アンタル・ドラティ指揮 デトロイト交響楽団
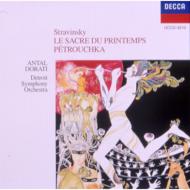
(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3210 1981年録音)
色彩豊かにロシア情緒をうまく表現した演奏で、ドラティのバレエ音楽演奏の巧さを知る名盤。 録音も超優秀です。 「ペトルーシュカ」とのカップリング。
(2) イゴール・マルケヴィッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団
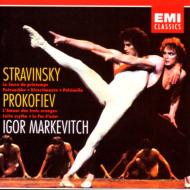
日記にも書いている通り、マルケビッチの演奏を長い間愛聴していた録音。私の「春の祭典」はこの演奏なしに語れません。 50年近くなる古い録音ですが、色褪せていません。
(3) ロリン・マゼール指揮 クリーヴランド管弦楽団
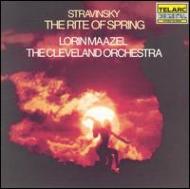
(テラーク・レーベル CD800054 1980年録音 海外盤)
マゼールのバトン・テクニックでクリーヴランドを思いのままに操る演奏。 この盤を採り上げたのはテラークの誇る超優秀録音の凄さです。
(4) スヴェトラーノフ指揮 ソヴィエト国立交響楽団
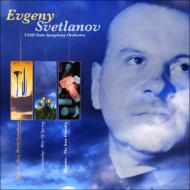
(ロシアレーベル SC030 1966年録音 海外盤)
爆演指揮者というニックネームのあるスヴェトラーノフの古い録音ですが、まさにこれぞロシアの大地で踊るバレエと言わんばかりの、強烈なリズムで刻むロシア一色の演奏。
(6) ファジル・サイ(独奏ピアノ)
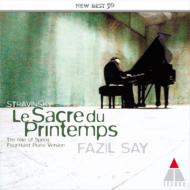
(テルデック原盤 ワーナー・ミュージック WPCS21228 1999年録音)
ピアノ・デュオ盤は何点かリリースされていますが、独奏による演奏はこれだけ。 多重録音による演奏。 旋律、和音などとても勉強になるディスクです。 現在は1000円盤です。
(7) マルケビッチ指揮 日本フィルハーモニー交響楽団
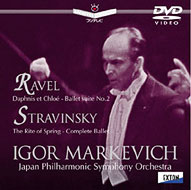
(EXTONレーベル OVBC00009 1968年収録)
1968年に何度目かの来日で再び日フィルを振って「春の祭典」を披露したマルケビッチ。 とても懐かしい映像です。 日本で「春の祭典」を広めたのはマルケヴィッチだと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『 今日の音楽カレンダー 』
1801年 初演 ハイドン オラトリオ「四季」
1860年 誕生 イサーク・アルベニス(作曲家)
1912年 初演 ドビッシー 「牧神の午後への前奏曲」
1913年 初演 ストラビンスキー バレエ音楽「春の祭典」
1915年 誕生 カール・ミュンヒンガー(指揮者)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ともの『 今日の一花 』 麦撫子(むぎなでしこ)
 撮影地 大阪府和泉市
撮影地 大阪府和泉市なでしこ科ムギセンノウ属
ヨーロッパが原産でしょうか、たくさん植わっているのを見たことがあります。
葉が長いので麦に例えられて、この名前がついたと言われているそうです。
1mくらいの高さになります。 5月には花が咲きます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[クラシック音楽] カテゴリの最新記事
-
「ニーベルングの指輪」の魅力 2009年02月04日
-
ワーグナー 指輪物語/山茶花 2009年01月19日 コメント(2)
Re:「春の祭典」/麦撫子(むぎなでしこ)(05/29)
嫌好法師
さん
「春の祭典」は一時期変に嵌ってしまった曲です。30種以上持っていたと思います。
最近、ハルトマンの交響曲第5番の第2楽章が「春の祭典」のパロディであることを発見しました。 (2007年05月29日 02時04分06秒)
最近、ハルトマンの交響曲第5番の第2楽章が「春の祭典」のパロディであることを発見しました。 (2007年05月29日 02時04分06秒)
嫌好法師さん、ありがとうございます
とも4768
さん
嫌好法師さん
>「春の祭典」は一時期変に嵌ってしまった曲です。30種以上持っていたと思います。
>
私はLPプレーヤーがいつもハウリングを起こしていたので、優秀録音盤はできるだけ避けていたのと、妙にマルケヴィッチに固執していたので、CDに変わるまでは彼一筋でした。
>最近、ハルトマンの交響曲第5番の第2楽章が「春の祭典」のパロディであることを発見しました。
-----
それは初耳です。 ありがとうございました。
(2007年05月29日 02時08分11秒)
>「春の祭典」は一時期変に嵌ってしまった曲です。30種以上持っていたと思います。
>
私はLPプレーヤーがいつもハウリングを起こしていたので、優秀録音盤はできるだけ避けていたのと、妙にマルケヴィッチに固執していたので、CDに変わるまでは彼一筋でした。
>最近、ハルトマンの交響曲第5番の第2楽章が「春の祭典」のパロディであることを発見しました。
-----
それは初耳です。 ありがとうございました。
(2007年05月29日 02時08分11秒)
Re:「春の祭典」/麦撫子(むぎなでしこ)(05/29)
よんきゅ
さん
「春の祭典」は一度だけ演奏したことがあります。リズムはとてつもなく難しいですが、独特のビート感は曲の構造がわかってくるとはまってしまいます。
特に第2部の大太鼓11連発の後のところとか、一番最後の方にある変拍子だらけの場所などはすごいですね。作曲家はどんな頭をしているのかといつも思います。
この曲を真夏に合奏練習しているときに、あまりの暑さとテンションの高さに演奏中に鼻血を出してしまいました。そういう意味でも思い出深い曲ですね。 (2007年05月29日 06時31分29秒)
特に第2部の大太鼓11連発の後のところとか、一番最後の方にある変拍子だらけの場所などはすごいですね。作曲家はどんな頭をしているのかといつも思います。
この曲を真夏に合奏練習しているときに、あまりの暑さとテンションの高さに演奏中に鼻血を出してしまいました。そういう意味でも思い出深い曲ですね。 (2007年05月29日 06時31分29秒)
よんきゅさん、ありがとうございます
とも4768
さん
よんきゅさん
>「春の祭典」は一度だけ演奏したことがあります。リズムはとてつもなく難しいですが、独特のビート感は曲の構造がわかってくるとはまってしまいます。
>
>特に第2部の大太鼓11連発の後のところとか、一番最後の方にある変拍子だらけの場所などはすごいですね。作曲家はどんな頭をしているのかといつも思います。
>
>この曲を真夏に合奏練習しているときに、あまりの暑さとテンションの高さに演奏中に鼻血を出してしまいました。そういう意味でも思い出深い曲ですね。
-----
近所に住む友人は自営業ですが、この街の交響楽団でチェロを弾いています。 その楽団で「春の祭典」をやろうかと持ちあがったのですが、譜面を見てゾッとしたそうです。 とてもアマチュアでやれないと。
やはり難しい曲なんですね。
(2007年05月29日 06時36分58秒)
>「春の祭典」は一度だけ演奏したことがあります。リズムはとてつもなく難しいですが、独特のビート感は曲の構造がわかってくるとはまってしまいます。
>
>特に第2部の大太鼓11連発の後のところとか、一番最後の方にある変拍子だらけの場所などはすごいですね。作曲家はどんな頭をしているのかといつも思います。
>
>この曲を真夏に合奏練習しているときに、あまりの暑さとテンションの高さに演奏中に鼻血を出してしまいました。そういう意味でも思い出深い曲ですね。
-----
近所に住む友人は自営業ですが、この街の交響楽団でチェロを弾いています。 その楽団で「春の祭典」をやろうかと持ちあがったのですが、譜面を見てゾッとしたそうです。 とてもアマチュアでやれないと。
やはり難しい曲なんですね。
(2007年05月29日 06時36分58秒)
Re:「春の祭典」/麦撫子(むぎなでしこ)(05/29)
紀 健幸
さん
紀 健幸さん、ありがとうございます
とも4768
さん
紀 健幸さん
> 知りませんでした。
> きれいな花ですね。
-----
この花は雑草としては観たことがありません。 園芸種として鉢植えや庭に植わっているものばかりを見かけます。
(2007年05月29日 12時01分47秒)
> 知りませんでした。
> きれいな花ですね。
-----
この花は雑草としては観たことがありません。 園芸種として鉢植えや庭に植わっているものばかりを見かけます。
(2007年05月29日 12時01分47秒)
Re:「春の祭典」
tkfmi2006
さん
『春の祭典』の音楽は確かに今では、現代音楽の古典といえる存在で非常に耳慣れている人も多いと思います。 2~3年前に確かアメリカン・バレー・シアターだったと思いますが・・・バレエを見てその振り付けの異様さに驚いたことがあります。初演のニジンスキー版の振り付けだったかどうかは定かではないのですが、初演当時の音楽ならびに振り付けの異様さに当時の人々が物議をかもしたのもなるほどとうなずけました。
(2007年05月30日 01時19分43秒)
tkfmi2006さん、ありがとうございます
とも4768
さん
これは偶然というべきか。
ザ・百姓野郎
さん
わたしもムギナデシコの写真を載せました。アグロステンマという学名(?)でもありますね。
「音楽界のピカソだ」と訳知り顔に、中学校の卒業文集に、『春の祭典』について書きました。この曲について、現代に蘇った古代の呪術的なリズムだと思えばいいや、と感じたのは大学生になってショルティ&シカゴ響を聴いたときでした。
ハマッタのはシャイー&クリーヴランド管弦楽団の演奏を「音楽の泉」で聴いてから。今のお気に入りはサロネン&フィルハーモニア管弦楽団です。どこが難曲なの?というほどの快速。この演奏と対極にありそうなアンチェル&チェコ・フィルのぎこちなさ・武骨さも好きです。ゲルギエフ&キーロフ・オペラ管弦楽団のライブをFMで聴いたときは、その曲の終わりのところに驚きました。 (2007年05月31日 22時07分54秒)
「音楽界のピカソだ」と訳知り顔に、中学校の卒業文集に、『春の祭典』について書きました。この曲について、現代に蘇った古代の呪術的なリズムだと思えばいいや、と感じたのは大学生になってショルティ&シカゴ響を聴いたときでした。
ハマッタのはシャイー&クリーヴランド管弦楽団の演奏を「音楽の泉」で聴いてから。今のお気に入りはサロネン&フィルハーモニア管弦楽団です。どこが難曲なの?というほどの快速。この演奏と対極にありそうなアンチェル&チェコ・フィルのぎこちなさ・武骨さも好きです。ゲルギエフ&キーロフ・オペラ管弦楽団のライブをFMで聴いたときは、その曲の終わりのところに驚きました。 (2007年05月31日 22時07分54秒)
ザ・百姓野郎さん、ありがとうございます
とも4768
さん
ザ・百姓野郎さん
>これは偶然というべきか。 わたしもムギナデシコの写真を載せました。アグロステンマという学名(?)でもありますね。
>
そうですね、学名では「アグロステンマ」ですね。
>「音楽界のピカソだ」と訳知り顔に、中学校の卒業文集に、『春の祭典』について書きました。この曲について、現代に蘇った古代の呪術的なリズムだと思えばいいや、と感じたのは大学生になってショルティ&シカゴ響を聴いたときでした。
> ハマッタのはシャイー&クリーヴランド管弦楽団の演奏を「音楽の泉」で聴いてから。今のお気に入りはサロネン&フィルハーモニア管弦楽団です。どこが難曲なの?というほどの快速。この演奏と対極にありそうなアンチェル&チェコ・フィルのぎこちなさ・武骨さも好きです。ゲルギエフ&キーロフ・オペラ管弦楽団のライブをFMで聴いたときは、その曲の終わりのところに驚きました。
-----
この曲は指揮者が変わると音楽も変わって、好きな人は数多くの演奏・録音盤を持っておられますね。
私は定番のマルケビッチが一番好きな演奏です。
(2007年05月31日 23時19分04秒)
>これは偶然というべきか。 わたしもムギナデシコの写真を載せました。アグロステンマという学名(?)でもありますね。
>
そうですね、学名では「アグロステンマ」ですね。
>「音楽界のピカソだ」と訳知り顔に、中学校の卒業文集に、『春の祭典』について書きました。この曲について、現代に蘇った古代の呪術的なリズムだと思えばいいや、と感じたのは大学生になってショルティ&シカゴ響を聴いたときでした。
> ハマッタのはシャイー&クリーヴランド管弦楽団の演奏を「音楽の泉」で聴いてから。今のお気に入りはサロネン&フィルハーモニア管弦楽団です。どこが難曲なの?というほどの快速。この演奏と対極にありそうなアンチェル&チェコ・フィルのぎこちなさ・武骨さも好きです。ゲルギエフ&キーロフ・オペラ管弦楽団のライブをFMで聴いたときは、その曲の終わりのところに驚きました。
-----
この曲は指揮者が変わると音楽も変わって、好きな人は数多くの演奏・録音盤を持っておられますね。
私は定番のマルケビッチが一番好きな演奏です。
(2007年05月31日 23時19分04秒)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
コメント新着
ifJU8X Really enjoyed this blog article.Much thank@ ifJU8X Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Great.
ifJU8X Really enjoyed this blog article…
ONY72s I cannot thank you enough for the post. Wil@ ONY72s I cannot thank you enough for the post. Will read on...
ONY72s I cannot thank you enough for th…
フリーページ










