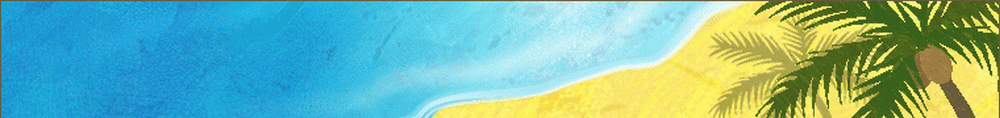葉桜
長い砂浜が続く小さな港町。
深い沢にその影を落とす枯れ杉の上に一羽のカラスが住んでいました。
カラスは両親も兄弟も、自分の名前さえも知らない孤児(みなしご)でした。
カラスは朝日が水平線から顔を出す前に起き出して、夕日が西の山端を染める頃、塒(ねぐら)へ帰る、そんな毎日でした。
好物といえば食堂の残飯捨て場に捨てられている豚肉のかけらや
水産加工場のトラックからこぼれ落ちた小イワシ。
少し悪いと思いながらも、時々、小学校の校庭の隅にある柿を失敬することもありました。
天気のいい午後は消波ブロックの上でウミネコと一緒に羽根を休め、のどが渇いたときには用水池や小川の水を飲みました。
小学生からは石を投げられ、老人からは木の棒で追いかけ回されることも日常茶飯事。
仲間のカラスとエサの取り合いをして足に傷を負い、三日三晩、飲まず食わずで動けなかったこともありました。
そんな一見、普通に見えるカラスでしたが、たったひとつだけ、他のカラスと違うところがありました。
カラスは恋をしていました。
人間の少女に恋をしていました。
それはカラスにとって本気の恋でした。
初めてカラスが少女を見たのは、春もまだ早い三月のいつもより暖かい日のことでした。
カラスは朝から三分咲きの桜の枝に座り、ゆっくり流れていく季節の声を静かに感じていました。
少女がいつしか窓から顔を出し、自分の方を見つめているのに気づいたのもそんな時でした。
白いブラウスと、きれいに切り揃えられた前髪。
薄汚れた出窓の手摺りにもたれ、春の陽光に眩しそうに目を細める少女の姿に、カラスの小さなこころは確かにドキドキしました。
そして少女の黒く澄んだ瞳が、カラスには黒水晶のように見えました。
しばらくのあいだ少女のことを見上げていたので、カラスはちょっとだけ首が痛くなりましたが、
カラスのこころは確かに少女のもとにありました。
それは明らかに恋でした。
せつない片想いでした。
それからカラスは毎日、桜の枝にやってきて、鳩時計のように同じ時間に必ず窓から顔を覗かせる少女のことを見つめていました。
三分咲きだった桜もやがて満開となり、葉桜に変わっていきました。
季節は神様が決めたように春から夏に移り変わり、暖かかった春の陽光も、湿っぽい梅雨の空を越えて、やがて夏の熱い陽射しになりました。
そのあいだもカラスは一日も欠かさずにその桜の木にやってきていました。
時には冷たい六月の雨に濡れた身体を震わせながら、時には初夏の透き通るような風を全身に受けながら、カラスは少女のことを見つめていました。
少女は相変わらず白いブラウス姿で、雨の日は憂い顔、晴れの日は満面の笑顔を見せながら、窓の外に広がる野草公園の方を眺めていました。
カラスはそこにいるだけで幸せでした。
そこにいる間だけ、自分は人間であるような気がしていました。
そしてこのままこの恋が叶わなくても、ずっとそんな時間が続けばいいと思っていました。
カラスは時々、砂浜に出かけて、少女のために様々なものを見つけてきました。
それはガラスの破片だったり、誰かが置き忘れていった打ち上げ花火のパラシュートであったりしましたが、カラスにとってそれらが何であるかわかるはずがなく、自分が素敵だと思ったものを少女にあげたいという一心で探していました。
それを少女の部屋の出窓の上にそっと置いてくる時だけ、カラスは少女の姿を真近で見ることが出来ました。
彼女はかすかな寝息を立てながら、いつも眠りの途中でした。
ある時、岩場の波打ち際で見つけた小さく緑色に美しく輝く石。
それさえも珍しい色をしたプルタブだと思ったカラスは、真っ先に少女のもとへ届けました。
それが誰かが捨てた、エメラルドの婚約指輪だということも知らずに。
そしてすぐに桜の枝に飛んで帰り、いつまでもカー、カー、鳴いていました。
夕暮れが優しく、黒い夏毛を照らしました。
泣きたくなるような美しい夕暮れでした。
それは盆入りも近い、ある晴れた日のことでした。
蝉の鳴き声が松林の彼方からとどまることを知らないように響いていました。
お墓に供えてあった海苔せんべいで朝食を済ませたカラスは、いつものように桜の木にやってきました。
時間は午前8時を少し回った頃でした。
カラスは少し早かったかな?と思いながら、昨夜の通り雨で乱れた羽根を毛づくろいし始めました。
薮蚊の群れが鼻先をかすめてどこかへ消えていきました。
錆びついた土管の中から一匹の野良猫が姿を見せ、ひとつ大きくあくびをしたあと、また土管の中に引っ込んでしまいました。
夏休みの子どもたちのはしゃぐ声が海辺の方へしだいに遠くなっていきました。
しかし、どうしたことか、少女はいつものように窓から顔を見せることがありません。
それどころか、ライトブルーのカーテンは閉じたまま、少しも開こうとしませんでした。
カラスは少しおかしいな?と思いましたが、それでも待ち続けました。
太陽はやがて空のいちばんてっぺんまで昇り、しだいに傾き始めました。
夏のむせかえるような匂いも突然の夕立にかき消されていきました。
静かな夏の夕暮れでした。
静かすぎて胸がしめつけられるようなせつない夕暮れでした。
それでもカラスは待ち続けました。
時々、何人かの人間が足早に建物の中に入っていくのが見えました。
みんななぜか泣いていました。
それから少したって、辺りの家の窓明かりがポツリ、ポツリ灯り始めた頃、一台のワゴン車が建物の中から出て行くのが見えました。
ワゴン車のヘッドライトは薄暗い群青色の夕闇を煌煌と照らしていました。
その夕闇の向こう、ふんわりと映し出された、赤い十字の印の看板。
カラスはそれをじっと見つめていました。
車の後部座席からは、かすかに少女の匂いがしていました。
匂いは、車が曲がり角を曲がって見えなくなるにつれて、夏の匂いと混じり合って、どこかへ消えていきました。
カラスはそれが何を意味しているのかわかりませんでした。
でも、もう二度と少女に逢えないということだけはわかりました。
そしてまだ自分の翼では飛んでいくことの出来ない、遠い遠い世界に少女は行ってしまったと確かに感じました。
はじめての気持ちでした。
とても悲しい気持ちでした。
カラスは何か言いたいと思いましたが、出てくる言葉はカー、カー、という鳴き声だけでした。
何回か羽根をバタつかせたカラスは、もうすっかり葉桜になってしまった木のいちばんてっぺんに止まってみました。
てっぺんからは少女がいつも見つめていた野草公園が、宵の月に蒼く照らされているのが見えました。
カラスはもう一度、カー、と鳴いてみました。
そしてそのまま飛び立つと、夜風に身を任せるように、どこまでも続いていく星空の向こうへ消えていきました。
空には今年いちばんの天の川が横たわっていました。
長い砂浜が続く小さな港町のお話です。
© Rakuten Group, Inc.