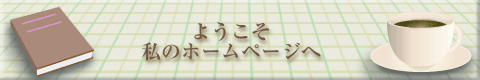「野のユリ」
深夜、スカイ・パーフエクト・テレビでCNNとBBCのニュースをチエックした後、チャンネルを換えたら映画「野のユリ」が始まろうとしていました。20歳の頃一度見ただけでしたが思い出深い映画でしたので、翌日の勤務の辛さを天秤にかけた後、見ることにしました。
砂塵を巻き上げて走る超大型なステーションワゴンに乗ってきた黒人男ホーマー・スミスは、アリゾナ砂漠の荒地で愛車がオーバーヒートします。そこで荒地を耕している5人の修道女達に「水をください。」と頼みます。
井戸を示されたホーマーことシドニー・ポワチエにマリア修道女院長は「神が男手を送ってくださった。」と感謝の祈りをします。
「おあいにく様、俺は通りすがりのものさ。」と彼は立ち去っていきます。
女手5人の自給自足体制で、打ち棄てられた教会の建物を再建しょうとしていた修道女達は、呆然(ぼうぜん)とステーションワゴンを見送ります。
その厚い、祈る視線を感じてホーマーはUターンして「1日だけ雇われる(ハイヤ)。」と申し出ます。どうやら彼は大工らしいのです。
若いと言うことは無知なことで、それに気づかぬのが愚かなる由縁(ゆえん)であると、三十四年も経つと思い知らされたことを正直に報告します。
ホーマーの車が快調に走る荒野の道の傍らには電信柱やサボテンの列があります。これは十字架で、これに導かれて(神の道を通り)、井戸で洗礼をうけると言う寓意があったのではと、気づきました。
修道女たちは東ドイツから亡命して、遠路16000キロの困難な旅の末、修道会の命によりたどり着いたのです。
院長が片言の英語を話せる以外はドイツ語しか話せません。彼女達はドイツ人が開拓に失敗して帰国し教団に寄進した土地に、教会(チャペル)を建てようというのです。院長が持っているのは一枚のお粗末な教会の見取り図だけという次第です。資材はおろか金づちすらないのです。
修道女達の宿舎の屋根を修理して疲れ果て、尼さんたちと同じ棟に寝ることを遠慮して、ステーションワゴンのトランクを開けて寝ているホーマーでした。
ホーマーは早朝、院長にたたき起こされます。
「いつまで寝ているのか。教会建設に働け。ベッドで食事をしたいのか。アメリカン・ミリオネアー(億万長者)みたいに。」 「それなら、ウオール街に行け。」とまで言われます。
マリア院長は神がホーマーを遣わしたと信じて、教会建設への熱意と断固たる信念で周囲を引っ張って行きます。
仕事が面白くなってきたホーマーは村の建設会社で働き、その週給で食料品や砂糖や珈琲を購入して修道女に分け与えます。
当然のことながら、マリア院長にはそれが気に入りません。個人の美食を、神の教会を建設する資材を購入することより優先しているのですから。
院長と衝突したホーマーは去っていきます。
3週間ほどが過ぎ、日曜のミサに出席する為、サボテンの林立する荒地の道路を移動教会に向けて歩いている5人の修道女達でした。(この地区には教会が無いので移動教会と称して、車のリアガラスに幕を下ろして祭壇としています。
そこに大司教が来て祈るのですが、大司教も週に600キロを移動するのに疲れ果てています。信者の多い裕福な土地への配属を願っているのです。
アリゾナ州、フェニックスの地の信者はほとんどがメキシコ系の貧しい人たちなのです。)
筆者もメキシコの北部、カリフォルニア州の南側にあたるバハ・カリフオルニアのロス・パロスへ行く途中の荒野を車で3時間走ったことがあります。
ハイエナのような小動物が、車にはねられて道路際に瀕死の状態で横たわっている光景がありました。つかず離れずの距離に、コンドルと称せられる禿げたか達がハイエナの死ぬのを待ってざわめいていました。上空には死に瀕している獲物をかぎつけて旋回しているもの、遠方より飛来してくるコンドルも見受けられました。
修道女達はそんな道を、日曜のミサに出席する為に歩き続けていました。
ロスアンゼルス帰りなのか、アロハシャツを着こみ、飲んで喧嘩したのか、顔を腫らしたホーマーのステーションワゴンが戻ってきて、尼さんたちを乗せます。修道女達は感動的に彼を受け入れます。
金めあてだけではない無償の労働の喜びを知ったホーマーは、腕の良いブルドーザーの運転手なだけあって、再び建設会社に雇い入れられます。彼は週給だけで建築資材を購入し独力で教会を建てようとします。
形をなしてきたチャペルの建設の手伝いに、スペイン語しか話せない村人達が、それぞれの出来るだけの資材を持って参加しょうとやってきます。しかし、ホーマーは「ドント・タッチ・エニシング」と一切の助力を拒否します。このあたりは幸田露伴の傑作「五重塔」をほうふつとさせます。
ご承知のように、名人肌の大工、のっそり十兵衛は、百年に一度と思われる谷中感応寺の塔の仕事を朗円上人に申し出ます。上人は、親方源太と共に話し合いすることを勧めます。だが、十兵衛は連名で仕事をするのは棟梁源太の「寄生木(やどりぎ)」となると拒否します。上人の条件は相手のために全てを諦めて譲るか、協力して分け合うかしかありません。詳細は本文「五重塔」を読んでいただくしかないのですが、明治文学の白眉であるこの小説は、平成に生きる私達がまったく忘却してしまったものを伝えています。
百年の後、談合とかジョイント・ベンチャー(共同請負)、あるいはペーパー・ジョイント・ベンチャー(名義貸し共同請負)などと、文豪から見れば食わんが為の醜い所業に官民一体となることを、露伴翁は予想できたでしょうか。十平衛は腕前を生かす仕事に恵まれず、長屋の羽目板や馬小屋の仕事に明け暮れ、妻子の衣服にも事欠く貧しい暮らしを送っていたのです。結局、源太と十平衛は連名の仕事なら満足行く仕事が出来ないと、二人して辞退するのです。そのうえで上人は十兵衛に仕事を申し付けるのです。
上人は「かほどの技量をもちながら空しく埋もれ名を発せず世を経るものもある事か、傍目にさえも気の毒なるを当人の身となりては如何に口惜きことならむ」と上人も十平衛を見抜くことの厚きこと、人々から慕われている有徳の人だけあるのです。
「五重塔」では、上人と源太と十兵衛の三人の爽やかな関係が物語を構成します。発注者と請負人が、良いものを作るという一点に飲みこだわって凝集した関係となっているのです。発注者がリベートをもらって奢侈な生活に使う、政治資金として使い、選挙に出て、有権者を供応・買収して逮捕される、という事件が全国津々浦々(つつうらうら)で頻発しています。発注者が公務員であったり、宗教家であれば、またなにをか言わんやであります。下手な説話集も及びもつかぬ醜態であります。
閑話休題、「野のユリ」の主要人物はマリア院長とホーマーと神であります。神は一度も姿を見せませんが、物語の全編を通じて奏でられる重低音であるといえるでしょう。
自尊心を傷つけられてむくれたホーマーでしたが、多数の善意の素人が参加して、工事現場が大混乱に陥ったことを、的確な建築の知識と経験を基に治めたことが契機になって、工事総監督(ボス)であると周囲が認めることになりました。スペイン語しか話せない村人、ドイツ語しか話せない修道女、英語しか話せない建設会社の社長が工事現場で右往左往する場面は、今見ると明らかに「バベルの塔」の故事を踏まえているようです。
村人の善意に支えられて教会は完成します。最初のミサの前日、訪れた移動教会の大司教は、立派に完成した教会に驚きを隠せずマリア院長にこう述懐します。
「(条件の良い土地に配属されたいという)私の自分勝手な祈りを、主は無視されたが、貴女の祈りには答えられた。私も主の信頼を得たい。」そして真新しい祭壇に額ずく(ぬかづく)のでした。
教会のシンボルである十字架を、塔屋の最高部に建てて、左官の鏝(こて)をふるったホーマー・スミスは,誰にも見えない最も高い平面にHOMER SMITHと鏝で記します。
その夜、彼は去っていきます。来たときと同じようにステーション・ワゴンに乗って。繕い物(つくろいもの)をしているマザー・マリアはエンジンの音を聞き、ホーマーの辞去を悟り「アーメン」とつぶやきます。
去っていくステーション・ワゴンの後ろ姿を映しながら、カメラは映画のタイトルを掲げます。「AMEN」と。
邦題はマタイ福音書6章28節からとられたものです。詳しくは社長室随想第1章をご覧下さい。
けだし、「仕事を成した者は、いち早く立ち去るにしかず。」でありましょう。
監督ラルフ・ネルソンはこの映画に出演しています。マザー・マリアは後年、映画「フラッシュ・ダンス」に出ていてびっくりしました。ジエニファー・ビールスと競演したその役どころは、ラルフ・ネルソンの配役と同様に、記さないでおきます。
ホーマー・スミスのひそみに習って。
蛇足ながら、かつてはこの映画を見て建築を志した若者も多かったようです。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 日本全国の宿のご紹介
- 【神奈川*箱根】箱根温泉山荘 なか…
- (2025-11-20 22:22:50)
-
-
-

- あなたの旅行記はどんな感じ??
- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい
- (2025-11-16 22:43:16)
-
-
-

- 日本全国のホテル
- 【富山】庄川温泉風流味道座敷 ゆめ…
- (2025-11-20 09:18:59)
-
© Rakuten Group, Inc.