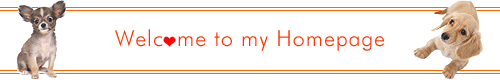作詞家時代
東京に憧れつつ、まだ実家にいた頃。
喫茶店でアルバイトをしていた。私はエプロン姿のウエイトレスだった。
平穏な毎日が変わることを恐れながらも、このままじゃいられないと
苛々しながら「いらっしゃいませ」と言っていた。
何がしたいのか、自分でも分からなくて漠然としていた時だ。
店のスポ―ツ新聞にある音楽事務所の社長の記事が載っていた。
私が引きこもっていた頃、心の支えが音楽だった。バンド経験もないし、楽器も出来ない。私に出来る事といえば、唯一言葉を紡ぐことだ。
そうだ!と閃いて、書き溜めた詞を早速その社長宛に送った。
そして、その次の日の夜中に電話が鳴ったのだ。
8ヶ月後、私の詩に曲がついてCDになった。
しかし、たった一曲で辞めてしまった。
勿論、音楽業界でプロの作詞家でいられるのは気持ち良かった。
冗談で「先生」などと呼ばれたり、スタッフからも大事にされたり、
バックステ-ジも業界そのもので、刺激的でそれなりに楽しい生活だった。
あの頃の私は若いというよりも幼かったのだ。
所謂世間知らずのお譲ちゃんだった。
その曲はあるアニメ番組のエンディングに使われる事になり、それを歌うシンガ―の女の子もブレイクを目指し、盛り上がっていた。
でも、私は反対にだんだん無気力になっていた。
お堅い放送局なので、言葉に制限があった。
そこに社長もディレクタ-達も極端に気を使っていたのだ。
同じ意味の言葉でも、もっと柔らかい言葉はないのか?
プロデュ-サ-やディレクタ-達に
ぐるりと囲まれて、さあ、直せと言われる。
私は独り、場違いな所に来てしまったのではないかと途方にくれながらも、
一生懸命頭を捻る。
今の今まで、この詞は最高だと持てはやした人たちが、
一瞬で手のひらを返す。
とうとうホテルに缶詰めにされた。高層の狭い部屋の中で、息が詰まりそうだった。憧れの東京を見下ろしながら、自分自身に何度も問いかけた。
確かに自分で書いてる詞なのに、最初に書いた詞からどんどん離れて動いていく。
プロなら当たり前の事と分かっているが、当時の私は芯が納得出来なかったのだ。
何よりも詞を書いたときの気持ちを無視して、違う言葉を捜して当てはめる事が嫌だった。
本当に子供だったんだな。
私にはプロとしてやっていく力がなかったのだ。
当時のディレクタ-や作曲(その後この人も大プロデュ-サ-になった!)してくれたミュ-ジシャンも、色々心配して地方の私の実家まで来てくれた。
東京に出て来いと何度も言ってくれた。やはり東京でなければ、打ち合わせやレコ-ディングなど気軽に動けないから。それは絶対に損だと。
しかし、もう私の気持ちは揺れなかった。
だから次の詞を依頼されたけど断ってしまった。
書きたいから書くんだ。
そこから離れていくならば、書く意味がない。
そう結論をだした。はじめから感じていたことだけど。
だが、今の私だったら絶対に辞めないだろう。
プロの世界で生きていくのは戦場なんだ。
どんな理不尽な戦いでも、私は挑んでいく。
言葉の絶対さを信じているから。
それは自分の言葉を信じるという事だ。
形を変えていこうとも、自分の書いたものは絶対だと信じる事ができるから。私はもう弱くないのだ。
© Rakuten Group, Inc.