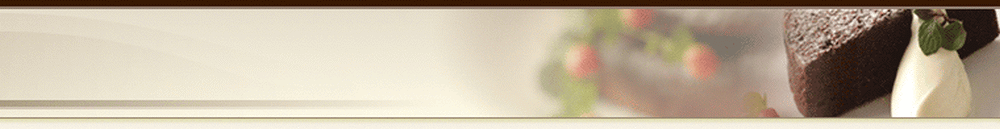今年も忌わしい夏の高校野球の季節が終わった。伏兵というと失礼かもしれないが、隣県の新潟県代表、日本文理高校が最後まで粘り強く反撃し、準優勝ながら人々の記憶に残るいい野球をして、県の高校野球史に間違いなく大きな足跡を残した。関係者はもちろん、度重なる震災の難を乗り越えてこられた新潟県の皆さんには心からお祝いを申し上げたい。
このブログを以前から読んで下さっている皆さんは何故私が「忌わしい」というのかはお分かり頂けると思うが、今回は平成21年8月7日の北日本新聞朝刊に興味深い記事があったのでご紹介しようと思う。これは「目指せ県勢21勝目」と題して富山県高校野球連盟の関係者の方がまとめられた記事であるが、この資料が秀逸な切り口を呈している。どんな資料かというと「夏の甲子園での1県1校制導入前後の勝利数」である。
1県1校の代表が夏の甲子園に出て行くのは今では当たり前であるが、実はこの制度が実施されたのは昭和53年の第60回大会からだそうだ。私がちょうど小学校3年生で(今の私の上の子供とちょうど同じ年)、我が県の栄えある第一校目は石動高校だったと記憶している。この前の年までは県大会で優勝した後、二次予選があり、そこで優勝した高校のみが夏の甲子園に出場できていたとのこと。今のように1県に必ず代表が送れる訳ではないからそれこそ「出ることが目標」という学校も多かったと思う。
さて、本制度導入の前後で県別の勝利数はどうなったか。まずは昭和52年(1県1校ではなかった時代)までの勝利数を下から数えてみると・・・47位滋賀県(0勝)、46位山形県(2勝)、45位山梨県(4勝)、43位佐賀県と新潟県(6勝)、42位石川県(7勝)、41位福島県(8勝)、39位茨城県と青森県(9勝)、38位三重県(10勝)、37位長崎県(11勝)、36位富山県(13勝)・・・・だそうで、我が県よりも勝利数の少ない県が11もあったようだ。
ところが、1県1校となってからは様子ががらりと変わる。今年の夏の大会が始まる前までの通算勝利数では47位が新潟県(16勝)、46位が山形県(17勝)、45位が富山県(20勝)・・・となり我が県はワースト3位となってしまう。引き算とすると分かるが、我が県は1県1校制が導入されてから去年まで31年間でわずか7勝しかしていない。5年に一度しか勝てないのだ!これは1県1校制になった後だけを見てみるとダントツの最下位だ。しかも、同一大会で2勝以上を上げた最も最近の大会は何と、昭和33年に魚津高校が初出場で3勝し準々決勝であの板東英二投手率いる徳島商業と延長18回引き分け再試合を演じたあの時まで遡るのだ。つまり、私が生まれてからというもの、夏の甲子園で2勝した富山県代表校は存在しない。
4~5年に一度しか勝てず、しかも2勝することは不可能な状態では昭和52年までは最下位の滋賀県と13勝差あったものが、今では逆に5勝差をつけられているというのも半ば当たり前のことだと思う(滋賀県は25勝、平成13年には近江高校が準優勝している)。何故ここまで高校野球が弱くなってしまったのか?
私は高校野球に携わったこともなければ、高校野球をやっている子供を持ったりしたこともないが、素人目で言わせてもらえるならばいくつかの要因があると思う。
最大の要因は、「出場することが県下各校の最大の目標」となっていることだ。これは選手だけでなく、各校の指導者、県高野連、そして我々県民もそう思っている節がある。富山県は、以前もちらっと書いたが、大変排他的で保守的な土地柄である。ある意味、日本の中で最も日本らしい県だと思う。長いものにはまかれろ、勝てば官軍負ければ賊軍、寄らば大樹の陰・・・・。このような県の代表が二次予選の北陸大会あるいは北越大会で優勝し晴れて甲子園の土を踏みしめる栄誉を浴したときはそりゃ、拍手喝さいで「出れば結果は二の次・・・」というところもあっただろう。ところが、1県1校制となり必ず富山県からも代表が送り出されることとなったにもかかわらずこの辺の価値観が変わらなかったのではないか。富山県大会優勝校=官軍(上に認められたチーム)となり、あとは負けても「官軍」であるが故に「惜敗」「全力でプレイ」などと美辞麗句でごまかされるようになった。高校野球という全国挙げての国民的行事に毎年一回戦ころりで帰ってくるのを半ば当たり前のことと捉えるようになって久しい。
また、一時期問題となった「越境入学生」を最終的に拒んだことも要因として挙げられると思う。越境入学生とは他県の中学を卒業しているが、甲子園へのルートが近いと思われる県(つまり、弱い県)の高校に特待生などとして入学して野球をする生徒であるが、最近の北海道や東北地方の私立高校が突如として強くなったのもこの影響と言われる。今ではどこの県にもこのような私立高校はあると思う。しかし、我が県はこれを頑として受け入れなかった(色眼鏡で見てきた?)。確かに県内の私立高校にも越境入学生はいる。大阪弁の飛び交う野球部もあると聞いているが、どういう訳か我が県は県立が強い。私立で夏の甲子園に行ったのは高岡第一高校と不二越工業高校がそれぞれ1回ずつだけだ。やはり越境入学生と地元出身者とまぜこぜにするのも難しいところがあるということか・・・。
私は越境入学生は全く悪いことだとは思わないし、これだけで甲子園で活躍することができるようになるとは思わない。しかし、我が県はあまりにもこれを廃除したがる向きが大きすぎるように思う。
我が県にはプロ野球独立リーグ、BCリーグの(私が愛してやまない)富山サンダーバーズというチームがある。このサンダーバーズも殆どが県外出身者である。エースの小山内は岐阜出身者だし、今年から阪神タイガースに行った野原は埼玉出身で富山には縁もゆかりもない。現在25名の登録選手のうち県出身者は8名だけ。だけどファンは皆サンダーバーズが優勝すると我がチームが優勝したといって喜ぶ。何故高校野球はそれがダメでプロならいいのか、大変理解に苦しむ。
プロは生活をかけていわば「転勤」してきたんだからしょうがないが高校生はまだ子供だから・・とでもいいたいのであろうが、高校生だって将来プロに行きたいと思ったら当然に甲子園で活躍しアピールできる環境が整っている高校に行きたいに決まっている。例えば、私が尊敬する東京大学に行きたい高校生がいるとして、その生徒が住んでいる県には東京大学に進学できるレベルの高校がないとする。その生徒が勉強のために隣の県の私立高校に入って東京大学に合格したらこの生徒を非難しますか?
このような訳の分からない、意味のない地元純血主義者の方に聞いてみたいのは、将来、富山県に越境入学生がエースや4番を務める私立高校が代表として甲子園に行き今年の日本文理高校のような活躍をしたら喜ばないんだろうか、ということだ。私は妙な大義にこだわって勝てない甲子園に毎年恥をさらしに行く(表現はきついが)よりもこっちの方が数100倍いいと思う。
突き詰めるに、我が県の高校には全国の舞台で勝つ方法、喜び、楽しさを知っている生徒、指導者、保護者、その他関係者が極端に少ないのだと思う。シーズンになれば毎週のように遠征に出かけ試合をしている高校も多くあるが、甲子園という全国の舞台に上がったとき、目的を果たしたと思って試合に臨むか、これからが自分の人生をかけた舞台だと思って試合に臨むかで勝敗がどちらに傾くかは火を見るより明らかだ。
これはちょっと趣を異にするが、サッカーの日本代表がワールドカップに出るまではいいが、本戦で勝てないのと何か共通するのではないか。確かに外国でプレーし、エース級の活躍をする選手も出てきたし、ブラジルから選手を帰化させ日本人としてワールドカップに出る選手も古くからいるから富山県の高校野球とは少し勝手が違うが、やはりワールドクラスに入るには決定的な何かが足りないのだろう。日本代表がワールドカップ本戦で勝てないことのくやしさには富山県民は高校野球で慣れているから割と耐えやすいのかもしれない。
越境入学生が少ないということはただでさえ閉鎖的な富山県という中しか知らない人が殆どであることを意味する。これは日本人がこの島国の外で何が世界の常識とされているかを知らないのに大変よく似ている。日本人は閉鎖的だ。これは歴史的にも紛れもない事実で、支配する側には大変都合がよかった。自分達のやっていること=常識としておけば容易に人々を納得させることができたからだ。このような経緯を辿って我が国の「お上」は今日の地位を確立してき訳だが、もはや、「自分たちだけが知っている」という時代ではなくなった。「お上」の不祥事とその不祥事に対する大甘の対応が国民に知れる時代となってしまった。もはやトップダウンで全て物事が片付くほど単純な時代ではない。
外を知らないことと外を薄々ながら知っていることはこれほど違う。あっという間に人々の価値観は180度向きを変える。無論、今からどうなっていくかについては良くなるという保証はない。今まで考えもしなかった事柄に対処しなければならないことも多々あるだろう。しかし、変えていかなければ国がもたない時期にきてしまった。それが今、実行の期を迎えているのだろう。
保守王国富山県も2年前の参議院選挙では自民候補を破って民主候補が当選した。これがいいことかどうかはともかく、県民の意識も大きく変わってきているようだ。高校野球についてもたかが・・・などと思わず思い切ったことをする学校の出現と県高野連の施策に期待したい。
もう動くのもマンドクセーから家に来てもらってんのよ。
オレはネトゲに必死で女はフ ェ ラに必死というカオス状態wwwwwww
なんでか毎回3 万貰えてるしイミフすぎwwww
これ始めた俺歓喜www 金無しニートのオマイら涙目wwwww
http://koro.chuebrarin.com/UCdCd0B/
(September 4, 2009 06:00:41 AM)
スカート脱がして足開かせたらパ ン ツからモ ロに具がはみ出てたよwwwww
既にず ぶ 濡 れだしwwwwwwwww
常にヤ ル 気まんまんすぎな女だし、仕方ないから即 挿 入してやったら
30分で女の子満足しちゃった(^^;
俺的にはもっと楽しみたかったけど、6 万もくれたし欲張っちゃダメだよな?w
http://ketsu.arctries.com/g8Ynpcw/
(September 8, 2009 10:18:48 PM)
カレンダー
 New!
保険の異端児・オサメさん
New!
保険の異端児・オサメさん『今時の勉強方法』 所税仲間さん
キャッシュフロー 社… 公認会計士天野隆さん
10年後の自分に向け… taka-maruさん
輝く私であるために にゃこ姫さん
コメント新着