雑読記(「松浦宮物語」ほか)
その一.牝の匂いのコワさ(『松浦宮物語』)
藤原定家作の『松浦宮物語』(角川文庫 萩谷朴訳注 初版昭和四十五年)にこんな場面がある。
唐土から日本に帰った少将が、かの地で夢の契りを交わした后に贈られた鏡を開く。なんとそこに映るのは、釣殿で筝の琴をかき鳴らし想いに沈むあの人の姿ではないか。恋しさに少将が涙するうち、やがて鏡の中の姿から、はっきり后のものと判る薫りが漂い出す。想い余った彼は、鏡を懐に引き入れて暫しうち伏す。
薫りはけっして男の気のせいではなかった。御殿に帰ったあと、彼はその移り香のため妻の嫉妬を買ってしまう。
――ううっ、なんちゅう色気のあるイメージだろう。しかもカミさんの嫉妬という男泣かせのオチまでついてる。さすが「紅旗征戍、我が事にあらず」と喝破した人の発想だ。どこがどういい、と付ける理由も思いつかない。もう生理的に好き!
さてかなり話の品は落ちるが、友人ふたりとサウナに泊ったとき、女性の匂いが話題にのぼったことがある。
「女が興奮した時の匂い――“牝の匂い”というのかなあ。あれ嗅ぐと、なんかコワくならん?」と一人が言うと、もう一人が「うんうん、分かる」と肯定した。けれど、いつもコワいとおびえている私は、その牝の匂いとやらの正体がぴんとこなかった。
古典の世界の女性は、じっさい一週間に一度程度の入浴で済ましていたらしい。
もしそんな匂いがあるとすれば、『源氏』で生霊のまま葵上を取殺した六条御息所や、女性の性愛日記の元祖となった『問はず語り』の作者など、かなり強烈なものを漂わせていたに違いない。
う~ん、こりゃ想像しただけでやっぱりコワいな……
その二.「豆いり」たあなんだ?(田辺貞之助のモーパッサン)
田辺貞之助が訳したモーパッサンの短編集(近代文庫『脂肪の塊』初版昭和二十六年)に、「告白」と題したショート・コントがある。
その話に、ガタ馬車を駆る女好きの御者が出てくる。彼が村娘をナンパする時の文句がふるっている。
「ねえちゃん、相変らず太い足だなあ!」
「まだ今日もだめかね、豆いりは?」
女が何のことだか分からず聞きかえすと、
「豆いりたあ、豆いりさ、わかんねえかなあ。男と女とまーめいりさ。伴奏なしでちょこちょこやんのさ。」
――と、まあこんな具合。いったい原文はどうなっているんだろうか?
訳者の田辺先生は、東京帝国大学の卒業論文のテーマに「フランス文学にあらわれた腐れ縁の統計的研究」を取り上げようとし、担当教官である辰野隆博士の激怒を買ったというエピソードの持ち主だ。ユイスマンスの『彼方』、バルビュスの『地獄』(私の偏愛する小説)など数々の名訳をものにする一方、古今東西の艶笑話コレクターとして、‘そちら’方面のエッセイも「まーめ」に上梓している。
まさに、この人にしてこの訳あり!
すっかり翻訳ものが少なくなった我が書架にあってもなお、田辺貞之助訳の小説本は、その背表紙を燦々とかがやかせている。
その三.アンドレ・モロアと出張(『私の生活技術』)
午後から電車で出張だった。
往復の車内でアンドレ・モロアの『私の生活技術』(新潮文庫 内藤濯訳)を読んだ。
発行月日は昭和三十八年、第二章「愛する技術」に線引きが集中している。
『しかし、愛している人を「倦かせないこと」は、こちらでその人に倦きていたら、かなり下らない技術ともなるだろう。――律儀のある人とない人、心の変る人と変らない人といったように、世には男女にニいろあることを承認しなければならないものか。』
三十九年年前、この本の元の持ち主はどんな恋に悩んでいたことだろう・・・・・・。
三章「働く技術」でモロアは言う。
『芸術家は、技術的な仕事以外に、生活することが必要である。というよりはむしろ、生活したことが必要である。(そしてそこが、芸術家の職人と異なるところである)』
つまり芸術家と職人の差異とは、前者は生活で得たものから創造するのに対し、後者は、創造で得たものによって生活するということか? そう簡単に割り切ったら職人さんに失礼だと思う。どんな仕事でも、深く打ち込めば、生活と創造が一体化することはありうる。
しかし、日々の暮らしの間隙をぬってしか書くことができない自分には慰めとなる言葉でもある。暮らしが創作の妨げとなることは多々あっても、それ以上のポテンシャルを与えてくれると考えれば、仕事や雑事にそこそこの時間を奪われるのも仕方ないなと納得できる。
人の精神も凧と同じで、なんらかの逆風を得て上昇するものだ。たとえばカルチャースクール三昧の有閑人が書く素人エッセイのインパクトのなさ。あれを思い出すと、無風状態の怖さが逆に実感できる。
プルーストは天才だった。だからこそ、七年半、コルク張りの部屋にこもって小説が書けたのだ。凡才の自分はまず、腐ることなく日々の生活を頑張ろう。
その四. 悲しみは言葉を育む(『建礼門院右京大夫集』)
中宮建礼門院に仕え、宮廷生活の華やかさと、平家の公達との恋にこころ奪われながら過ごした日々が一変する。源平の争いの中、憧れの人々の没落と最愛の男の死に遭遇し、巧みだが凡庸な女流歌人の言葉が突如、漆黒のかがやきを帯びる。
「夏ふかき比 つねにゐるかたの遣戸は 谷のかたにて 見おろしたれば 竹の葉はつよき日によけられたるやうにて まことに土さへさけてみゆる世のけしきにも 我が袖ひめやと 又かきくらさるるに ひぐらしはしげき木ずゑにかしましきまで鳴きくらすも 友なる心ちして
こととはむなれもやものを思ふらむ もろともになく夏のひぐらし 」
これはもう、「描写」などというなまやさしいものではない。見る人のたましいが万象と一体化したような文だ。
筆者は「竹の葉」であり、それをよける「つよき日」であり、また「(さけてみゆる)土」、「ひぐらし」、「木ずゑ」でもある。象徴という段階を通り越し、みずから事物の内に没入した状態にあってはじめて、言葉が最高の力をあらわした見本と言えよう。
やはり極度の悲しみは、それだけで言葉を育む母なのだ。それも日本の私小説家にありがちな(本人が好きで生み出した)酒気や淫臭ただよう悲しみでなく、その時代が持つ固有の常数たる絶対的な悲しみ――たとえば幾光億年先の星のようなもので、眼に見えるが、今の世に捉えることは不可能な存在。
しかし、それをあたかも「天恵」のように尊ぶこと自体に、近現代の文学的思考に毒された自分の不純さ、いやらしさ、心驕りがある。
(岩波文庫 久松潜一・久保田淳校注 初版昭和五十三年)
その五.ここよりももっと好い處(シュミットボン『幸福の船』)
相当な翻訳小説好きでもシュミットボンの名前を知っている人は少ない。
二十世紀初頭に活躍したドイツの作家で、古い映画に詳しい人なら『街の子』の原作者と言えばピンと来るかも知れない。
この人の作品で『幸福の船』(改造文庫「ライン牧歌譜」浦上后三郎譯 初版昭和十三年に収録)という掌編がある。
ライン川のとある船着場で、貧しい人を乗せるという幸福の船を待つ老婆がいる。ふとしたきっかけで彼女の噂が町に広まり、河岸に大勢の人が集まりはじめる。
最初は、希望のない生活に疲れた主婦や、単なる好奇心にかられた子供たち。
つづいて飢えに苦しむ乞食、身体の不自由な人、半死半生の老人など、あからさまな不幸を背負った人の列。やがて、外見は何の支障も持たぬ人ばかりか、暖かいマントを羽織って綺麗に帽子に刷毛を入れた金持ちまでが、老婆の言う「ここよりももっと好い處」に憧れ、「真っ白な帆を張った、黄金のように輝いている」幸福の船を待つ者の群れに加わった。――
「ここよりももっと好い處」――そう、幸福はいま自分が在る場所にはない。
過去へ、未来へ、想いが目前の憂慮から遠ざかるほど、世界は優しい相を帯びる。景色は屈託ない明るさに満ち、愛する人はみな神のように不死を保つ。
親のぬくもりから離れていた子供時代、妹とひとつの布団を被って想像の町で遊んだことを思い出す。現実には月に一度しか会えない父母がそこでは毎日家にいる。お正月もクリスマスも家族みんなで祝うことができる。
兄妹の会話の中で友達がどんどん増え、町も大きく成長する。イヌ、ネコ、トリが口をきき、家々はオモチャのカプセルのように透明で、おたがい住む人の顔が見えるほど近く接している。常にお祭りの夜のように明るく、誰かが自分に呼びかけてくれる世界。真夜中にめざめても淋しさや怖さに泣き出す必要のない世界、それが僕等にとって「ここよりももっと好い處」だった。
――夕暮れが近づき、水気を含んだ空気が川面に低く垂れ込めた頃、礼拝堂の鐘の音とともに「真っ白な帆を張った、黄金のように輝いている船」が、靄の向こうから姿をあらわす。だが、狂喜乱舞する群集を尻目に船は桟橋を素通りし、甲板にいる船員は追いすがる人々の有様を見て汚い唾を吐く。あまつさえあの老婆には、鬱陶しいと言わんばかりに船上の木切れをとって投げつける。
船が去り、人々は憑き物が落ちたように我に返った。彼等はめいめいに、みずからの馬鹿さ加減を笑いながら家路についた。
河岸にとどまったのは老婆ひとり。彼女はいつもの木の株へ腰をかけて、また川上の方へ頭を向ける。――
やはり幸福は、目前の「今」には存りえなかった。無理に引き寄せても必ず逃げる。幸福を待ちつづけることそのものの裡に幸福があることを、なおも「大きく瞠ったまま絶えず燦いている青い眼」を失わない老婆だけが無心のうちに悟っていた。僭越ながら作者の意図をそう推察する。
さて、いっぽう自分は、書くことが「ここよりももっと好い處」へ至る道と信じて良いのだろうか。けっして名利をもとめている訳ではないが、せめて書き上げた瞬間、幸福の船の到来を幻視できるほどの作をものにしたいと、ひたすらに希ってはいるが…。
了
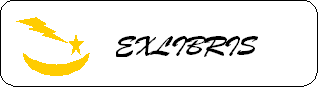
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 今年も神田古本まつりに行きました。
- (2025-11-10 15:52:16)
-
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ2025年52号感想その…
- (2025-11-26 13:50:15)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 風に向かって クリスティン・ハナ
- (2025-11-24 16:36:01)
-
© Rakuten Group, Inc.



