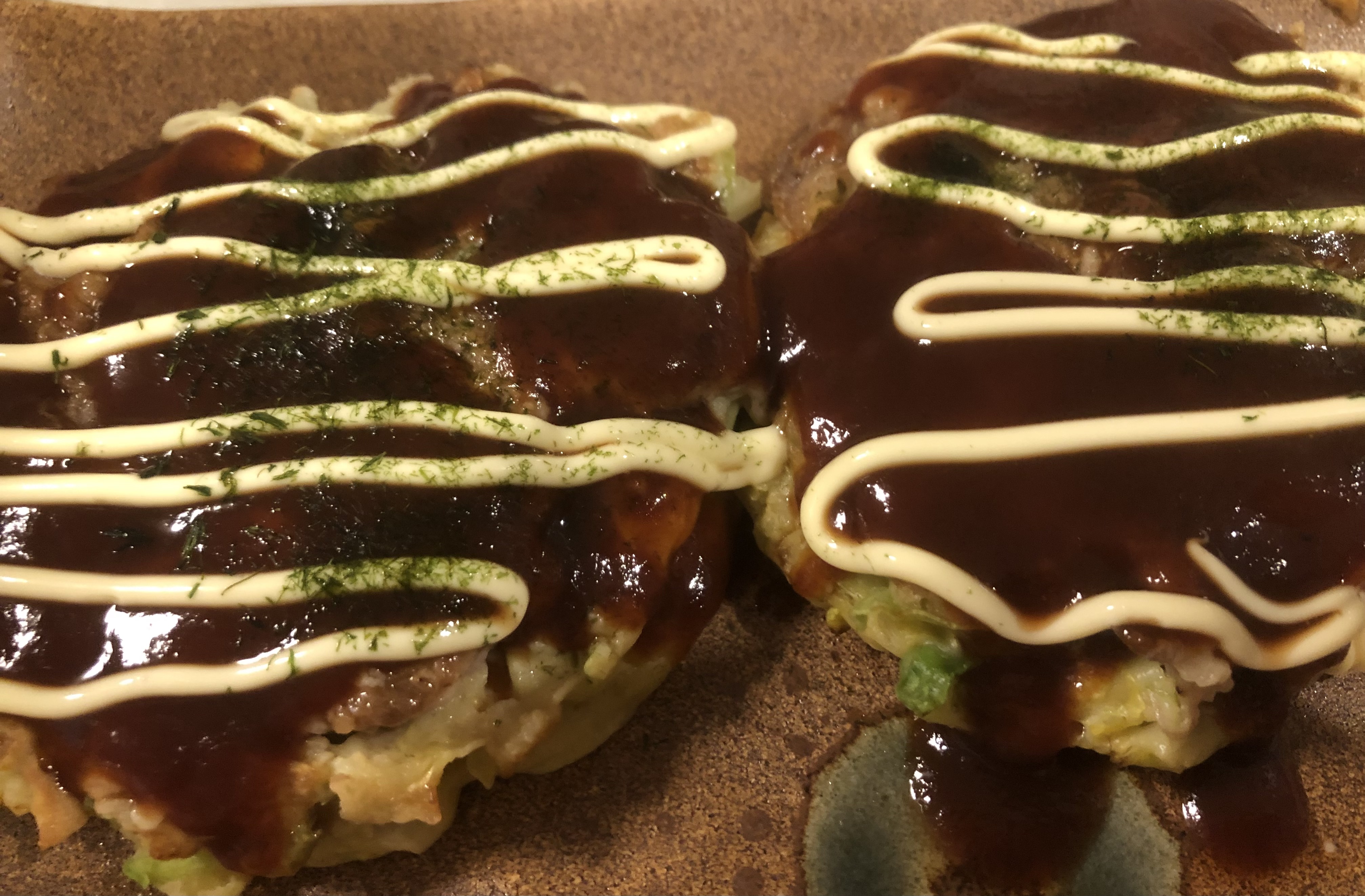「あの日の夕焼け」 第1話
「あの日の夕焼け」 第1話
彰人は今、リビングのソファーに横たわっている。淡いブルーのセーターを着て。それは、彼の婚約者である七瀬ゆきが、彼へのクリスマスプレゼントとして生前編んだ物だった。
静まり返った室内にシューッと言う乾いた音だけが聞こえている。キッチンから漏れるガスの音だ。そう、それは彰人自身が望んで行ったことだった。重くなった瞼を開き、白い壁に掛けられている時計に目をむけようとするが、睡魔のせいかうまく焦点が定まらない。薄暗がりの中で黒く浮かび上がる短針と長針が午後6時12分を指している。やっとの思いで時刻を確認すると彰人は再び目を閉じた。瞬間深い海の底に吸い込まれるようなとても不思議な感じがした。決して不快ではない。恐怖感もない。寧ろ安堵にも似た安らぎを感じる。
ただ眠りたい…1人静かに…。その思いが彰人の心を支配していた。
外では雨足が強まり風も吹き始めていた。だがその音も今の彰人の耳には届かない。悲哀の念など空虚な彼の心にはもうひとかけらも存在しない。なにもかも消えてなくなってしまった。
運転席には日高彰人、助手席にはその彼女七瀬ゆきが座っている。久々のドライブで、2人とも満面に笑みを浮かべている。
「ドライブなんて、もう1ヶ月ぶりくらいじゃない?」
「最近、仕事忙しかったからな」
「でも、しばらくはゆっくりできるんでしょ?」
「それが…」と一瞬笑顔を曇らせて彰人が続ける。
「そうも行かないんだ…。来月の10日から2週間くらいロスへ出張しなくてはならなくなってね」
「そう…」
一瞬寂しげな表情をするが、すぐにいつもの彼女らしい愛らしい笑顔を取り戻し
「でも、イブには帰ってこられるんだよね?」と彼に問いかけた。
「うん。多分、夜にはなると思うけど、それは大丈夫」
「よかった」と小さく言って微笑すると、ゆきは心底幸せそうにフワリと目を閉じた。
2人の乗った車が工事中のビルの前を通りかかる。
「あんな大きなビル、この間まであったっけ?」
驚いたように尋ねる彰人に、少し笑って
「そりゃぁ1ヶ月もたてば、工事だって進むわよ」と彼女は言った。
「あぁ、そっか」と真面目に納得したように言う彼にゆきは思わず笑みを漏らしてしまう。
そのとき、工事現場の足場が崩壊し、2人の乗っていた車の上に激しい音とともに崩れ落ちた。車は見るも無残な姿となり、辺りには人々のざわめきと、救急車やパトカーのサイレンの入り混じる音だけが悲しく木霊していた。
その夜、彰人はとても不思議な夢を見た。
漆黒の空から舞い降りてくる真っ白な綿雪。次から次へと天から降りてくる白は、やがて辺り一面を輝く銀世界へと変えて行った。
そして、はらはらと舞う雪の中にたたずむ天使が1人。後姿の彼女の長い栗色の髪に肩に、柔らかな白が積もって行く。彼女は、さっと振り返ると彰人を真っ直ぐに見つめてこう言った。
「離れていても、ずっとあなたを見守っているから…」
一陣の風が2人の間をすり抜ける。彼女の潤んだ瞳が揺れていた。
切り裂かれるように切ない想い。心まで凍らせてしまいそうなほどの冷たい雪の中で、彼の意識は次第に遠のいて行った。
2日後彼は目覚める。そこは、とある総合病院のICU(集中治療室)。
まず最初に目に飛び込んできたのは、見慣れない白い天井と薄明るい1本の蛍光灯だった。
「日高さん、気がつかれましたか?」
40代半ばくらいだろうか。すらりと背が高く、黒髪に少々白髪の混じり始めた真面目そうな医師が彼の顔を覗き込んだ。 「彰人、よかった!心配したのよ」
そう言いながら、溢れる涙をハンカチで拭っているのは彼の母、京子だった。
ベッドの周りでは彼の母親だけでなく、彼の父や妹夫婦達が皆瞳を潤ませて彼のことを見守っている。しかし、彼は少し困惑した様子で、そんな彼等を虚ろな瞳で見ているのだった。
「あなた方はいったい…?それに僕は、どうしてこんなところに…!?」
かなり混乱して必死に思いを巡らしている彼に、一同は驚愕の表情で沈黙する。
「日高さん、ご自分のお名前が分かりますか?」
真剣に問う医師。だが彼は黙り込んだまま、しばらくの間苦悩しているようだった。
自分が何者なのか全く持って分からない。おそらく、この医師の言う日高と言う人物がじぶんであろうと言うことは分かる。しかし、それが自分のこととして何故だかどうしても認識できないのである。心の奥深くに眠る何かが、自分が日高彰人であることをまるで拒絶しているかのようにも思われた。
「だめだ!分からない…僕にいったい何がおこったと言うんだ!?」
「彰人、父さんだ。分かるだろ?」
「あなたが僕の…?」
と言って、当惑の眼差しで父を見る。
ショックに耐えられなくなった母は、軽い眩暈に襲われふらりとよろめき倒れかかった。「しっかりして、お母さん!」と彰人の妹、理沙子が母を支える。
「お兄ちゃん。私、理沙子よ。ほんとに思い出せないの?」
どうしたら良いか分からず目を伏せる彰人に、思わず理沙子の瞳から涙が零れ落ちた。
「ちょっとみなさん、こちらへお願いします」
医師に促され、家族達はICUを後にした。
彰人の家族が医師に案内された場所は、ドアのプレートに第3診察室と書かれた少し小さめの部屋だった。
「彰人さんは、事故のショックのため一時的に記憶を失っている状態です」
医師が説明し始める。
「一時的にですか。それじゃぁ、彰人は…」
そう問いかける彼の父親に
「はい。直に快復することでしょう。ただ…それがいつごろかとまではっきりしたことは言えませんが…おそらく、1・2週間はかかるかと思います」と医師は冷静な口調で答えた。
「そうですか。分かりました」
「これから彰人さんを通常の病室へと移します。また部屋が決まり次第お知らせしますので、待合室のほうでお待ちください」
言って医師は一礼し、部屋を出て行った。
しばらくの重い沈黙の後、母京子が口を開いた。
「それじゃぁ、ゆきさんのことは…」
父は目でうなずき
「黙っておいたほうが良いだろう…」とだけ言い、僅かな嘆息を漏らした。
それから3日後の午後。
2人部屋の窓際のベッドで、起きて本を読んでいる彰人。冬の柔らかな陽射しが彼に白く降り注いでいる。
そこへ、ゆきの母親が見舞いにやってくる。病室に入ってきた女性に気づき、彼はさっと読んでいた本を閉じた。
「こんにちは」
ゆきの母親が軽く会釈したので、彼も愛想良く会釈を返した。そして
「あの…どちら様でしたでしょうか…?」と申し訳なさそうに彼は尋ねた。
すると、ゆきの母親は
「私は、お母さんのお友達で七瀬と申します。これ、どうぞ」と手に持っていた花束を彰人に手渡した。
彼女は、彰人の記憶がこのまま戻らなければいいのにと心の片隅で思っていた。今の彼に真実を受けとめることはきっとできないだろう。
「ご丁寧にどうもすみません」
左腕が骨折して動かせないため、右手だけでその花束を受け取り明るい笑みを浮かべた。その明るい笑みを少しでも長い間絶やしてほしくない。だからこそ皆誰もいまだ決して真実を語ろうとはしないのである。それだけ皆が彼のことを大切に思っているから。
「よかったですね。怪我が大したことなくて」
「はい。おかげさまで。鉄骨の下敷きになったとは、僕自身信じられないくらいなんです」
その彼の言葉に一瞬、ゆきの母親は悲しげな表情を見せるが、すぐにまた元の笑顔に戻って
「早く退院できるといいですね」と何事もなかったかのように続けた。
そして10分ほど他愛もない会話をした後、彼女は「それではお大事に」と一礼して部屋を出て行った。
ゆきの母親は、彼が記憶を取り戻すきっかけにはならなかった。しかし、彼の心は何故か得体の知れない何かが重くのしかかってきたかのように怯えていた。
ゆきの母親が病室を出てしばらく廊下を歩いていると、売店から戻ってきた彰人の母親京子がエレベーターから降りてくるのが目に入った。京子は向こうから歩いてくるゆきの母親に気がつき一礼する。それに返すように僅かに微笑して会釈するゆきの母親。
「彰人さんの記憶まだ…」
「えぇ、実はまだ…」
「でも、よかった。あ、よかったって言い方も変だとは思うんですけど…ゆきのこと、今はまだ思い出さないほうが…」
そこまで言って、ゆきの母親は今まで張り詰めていた何かがぷつりと切れたかのように、はらはらと涙を落とした。
「ごめんなさい。彰人さんの顔見てたら、何だかあの子がいなくなっただなんて信じられなくて…」
バッグからハンカチを取り出し、ゆきの母親は涙を拭った。それから
「ではまた。彰人さん、お大事になさってくださいね」と言い、京子に一礼してその場から去って行った。
京子は、何か言葉をかけようとするが良い言葉が見つからず、ゆきの母親の去って行く後姿を見つめたまま、ただその場に立ち尽くしていた。