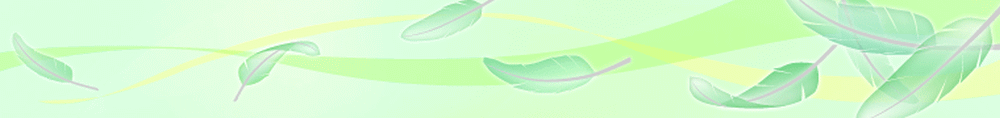~暁の星~
一
彼は哭(な)いていた。
どこまでも広がる星空を仰ぎ見る位置に、闇を集めたような暗い空間がある。古ぼけた石造りの牢の中に、一人の男がうずくまっていた。
折り曲げられた長身をめがけ、星空から小さな流星が飛んでくる。それは外界で見るもののように輝いてはいず、黒く煤けた礫(つぶて)となって男を、男の背にある翼を打つ。
彼は以前、天使と呼ばれていた。輝けるもの、神の右腕とうたわれた彼が、いまは暗い牢獄でひとり礫に打たれている。つややかだった長い黒髪は見る影もなく乱れ、力強くはばたいた純白の翼は、降りつづく流星に黒く染まり、枯れしなびているように見えた。
彼が深い慟哭に身をふるわせるたび、重い鎖がじゃらりと不吉な音をたてる。牢の扉は、閉じられてはいなかった。それでも男は逃げようともせず、ただ打たれ、泣いていた。
このまま時が経てば、衰弱して命をも奪われるかもしれぬ。それでも彼は立たなかった。
黒い流星は、彼が救おうとした人間たちの心であったから。
弱く頼りなげな心があげた悲鳴が、押し殺された嗚咽や憎しみが、すべて黒い礫になってするどく虚空を飛んでゆく。
どこにも休むことができぬその星が、唯一落ちてゆける場所が、この古い牢獄だった。
だから彼は、いつか自分が狂ってしまうとしても、この牢を抜ける気はなかった。人間を救おうとした彼の方法は間違っていたかもしれないが、他にできることなど思いつかなかったのだ。
その思いが太い鎖になって、彼の体を締めつける。それでもよかった。堕天したと言われても、彼は人間が好きだった。
かの悩める仔羊、どうしようもなく愚かで弱く、けれど時に天の光のごとく輝ける存在。
小さな不思議にひきつけられるように、つねに好意をもって見守ってきた。
ならば今、この小さな悲しい星の痛みをともに泣くこと以外に、彼に何ができようか。
男を打った礫は、砕けてちいさな黒い蝶になり、いつか闇にのまれて消えた。
礫はほとんど休むことなく、あらゆる方角から飛んでくる。ひとつ打たれるたび、彼の魂は張り裂けそうな痛みを味わった。
(痛い・・・痛い、痛い・・・・・・)
絞りだされる嗚咽は、どちらの魂のものであるのか、もう区別がつかなかった。
黒い礫が怒るように怒り、憎むように憎んだ。
流星が悲しむように悲しみ、叫ぶように叫んだ。
(そうだ、憎い・・・・・・悲しい、悲しい・・・)
(泣けばいい、一緒に・・・)
月も太陽ものぼらぬ虚空に時の流れはなく、ただ流星だけが、永遠に彼を打ち続けた。
開け放たれた牢のまわりに、黒い蝶が舞っている。
しかしよく見ていると、蝶は二、三度はばたくだけで、砂でできた像のように崩れた。跡形もなく崩れ去るように見えるが、実はそうでないことを青年は知っていた。
「ルシフェル様・・・・・・」
慟哭する男を見やって、悲しげに青年はつぶやいた。その背にある白い翼と、少しくせのある髪をかすめるようにして、流星は牢内に降りそそぐ。
黒き翼のルシフェルは、かつての仲間には気づかぬようだった。
もう何度、こうしてむなしく牢を訪れただろう。癒しの手と呼ばれるラファエルは、いつも自らの不甲斐なさに歯噛みする思いだった。
冥界のごとき闇に沈む牢の周りで、ただラファエルの周囲だけが、ぼんやりと緑色の輝きをおびている。それは彼の癒しの力をあらわすものであったが、この場所ではなんの慰めにもならなかった。
敬愛する仲間ひとり、救うことができない。
苦しむ者本人が望まなければ、彼はちいさな傷ひとつ、治すことができないのだった。
深い嘆息とともに、青年は牢を見守った。
間断なく礫が降りそそぎ、黒い蝶が生まれては消えてゆく。この消えた蝶たちは、虚空のなかで再び流星になって戻ってくるのだと、ラファエルにはわかっていた。
共に泣き、共に憎む――そのいっときを救いだと思って。
ルシフェルが行っていることを、無駄だと思っているわけではない。しかし、それでは本当の救いにはならないと、気づいてもいた。
蝶は戻り、あらたな礫を生み出してゆく。
人間たちは流星が生まれた本当の理由に気づくことなく、その存在すら無意識の底に押し隠して、あらたな悲しみに埋もれてゆく。
このままでは、誰一人救われない。
「ルシフェル様!」
しかし青年の叫びも、やはり男には届かぬようだった。
握りしめた鉄柵を鳴らして、きつく頭を押しつける。人間を救おうとして失敗し、自らの力のなさにも慟哭し、せめて牢に留まって共に泣こうとする男の気持ちがわかる気がした。
どんなに辛いことだろう。どんなにか、悲しいことだろう・・・・・・。
青年の白い頬に、ひとすじの涙が伝った。
結局、ラファエルはまた何もできぬままに牢を後にした。
振りかえり振りかえり、幾千、幾万の星屑の海を飛んでゆく。暗黒の世界からすこしずつ周囲の明るさが増してゆき、彼の属する天へと近づいてゆく。
すると光の園との境界あたり、常緑の大樹に半ばよりかかるようにして、もうひとりの友が立っているのが見えた。
彼はラファエルが着くのを見届けると、ふてくされたような顔をして先を歩き出した。
「ミカエル、待っていてくれたんですか」
地に降り立ち、足早に追いかけながら問いかける。
「お前はすぐ泣くからな」
肩に流れる長い金髪をうるさそうに跳ねあげて、ぶっきらぼうに友は言った。陽光のあふれる光の園は、ところどころに花々が咲き乱れ、吹き抜ける風も涼やかだ。
群青と金の輝きを放つ白いローブをまとったミカエルの長身は、魔を絶ち悪を斬る、その性質のままに凛々しくも力強い。
「いやだなあ、泣きませんよ」
友の優しさが嬉しくて、ラファエルは微笑んだ。
「どうだかな」
ミカエルも笑う。しかしラファエルが問いを口にすると、とたんに友の笑みは消えた。
「貴方は行かないんですか。本当は気にしているんでしょう」
「・・・・・・俺が行けるか。あんな辛気臭いところ」
顔をそむけ、歩く速度をはやめる。
「辛気臭いって・・・・・・ルシフェル様は、貴方の」
「俺は行かん」
言下に否定する。ミカエルは確かに強情なところもあるが、これほど頑ななのはめずらしいことだった。ラファエルは食い下がった。
「ねえ、ミカ・・・・・・」
「くどい」
木陰に足を止め身体ごと振り返って、きっぱりとミカエルは言った。
「ラファ、俺は行けないんだ」
どん、と拳で樹の幹を打つ。衝撃で、柔らかな緑色の葉が幾枚かひらひらと散った。ミカエルの顔は苦渋にしかめられている。
「行けない・・・・・?」
ラファエルは繰り返した。
ルシフェルが人間を救いたいと言ったとき、法に触れると表立って反対したのがミカエルだからだろうか。
しかしルシフェルとミカエルは、同じく光帯びたる者、闇を払う者として長い間ともに過ごしてきた仲だ。一時の立場の差が、それほど強い影響を残すとも思えなかった。
それにミカエルは、一度罪を認めた者に、隔意を抱きつづけるようなことはない。
ラファエルが考え続けているのに業を煮やしたのか、ミカエルは無言のままに腰に帯びた剣環を鳴らした。
澄みきった鈴のような高い音が響いて、ラファエルは気づいた。
・・・・・・行けない。
ミカエルは、あそこには行けないのだ。
「そうか」
ラファエルが目を見張ると、ようやく気づいたか、というふうにミカエルはうなずいた。大樹によりかかり腕を組んで空を見上げる。
青い空には雲ひとつなく、どこからか美しい竪琴の音が流れていた。
隣に立って、ラファエルは友の持つ剣を見やった。
七色の輝きを放ち、すべての魔を絶つという光の剣。そしてそれを持つものは、闇を払うことを責務として担う。
もしもあの牢に行ったなら、ミカエルは斬らねばならないのだ。
ともに泣きともに憎む、それはけして悪ではないにせよ、救いのない闇であることに変わりはない。
未来永劫につづく、嘆きの連鎖。
どこかで断ち切らねばならないのは確かだった。
ミカエルの剣であれば、闇は一瞬のうちに切り裂かれ、白い光となって浄化される。
しかしそれも、あの闇にとって本当の救いにはならないだろうことに、ミカエルは気づいていた。
そんな彼が今できるのはただひとつ、行かぬこと。
待つよりも動くことを好む友にとって、その選択がひどく心苦しいものであるのは、容易に想像がついた。
「・・・・・・行けないんだ」
自らに言い聞かせるように、ミカエルは呟いた。
ただ斬って、白日にさらすだけでは駄目なのだ。
あの深い闇は、そんなことでは癒されない。暗き存在があったことに気づく、その意味はとても大きいが、痛みもまた限りなく大きくなるだろう。
長く見ないふりをしてきた闇の扉、それを開く荒療治に耐えうる強さがあるならば、いい。
乗り越えて、また起き上がれる人間ならいい。
しかしそんな強い者であるなら、はじめから闇の流星など生み出すだろうか。
切り裂かれてぱっくりと開いた傷口に、新たな血があふれ出すだけではないのか。
それは人間を深く傷つけるだけではなく、せめて共に泣こうと牢に留まる仲間をも、打ちのめすことになるのではないか・・・・・・。
ラファエルとは違う意味で、ミカエルもまた、自らの無力さに苛立っていた。
光の剣を持つ彼は、また闇の扉を守護する者でもある。まばゆい光とぬばたまの闇、双方の強さと弱さを知りぬいて、はざまに長くつづく道を指し示すもの。
どちらにも傾かず、どちらも裁かず。
安息をもたらす闇の側面を知っているからこそ、彼は光の剣をあやつることができる。
ミカエルが剣をふるうのは、浄化によってしかその魂が救われない、とわかったときだ。光の対称物、憎悪や悪意の顕現としての闇を払う責務を両の肩に担うには、彼はとても優しい。
友の内心の苛立ちと悔しさを、ラファエルは正確に洞察した。それは、彼自身が抱く無力感と、ほぼ同じものであったから。
「僕もですよ。行っても・・・・・・いつも、何もできない」
緑の大地を眺めるでなく視線を落としてラファエルが言うと、ミカエルは向きなおった。
「なぜだ? お前の力は俺と違う。癒しの力じゃないか」
お前の優しい力なら、なんとかできるんじゃないか。青い瞳はそう語っていた。
「それでも・・・・・・ね」
よりかかる大樹の幹に、先ほどミカエルの拳でついた傷を見つけて、ラファエルはそっと手のひらをあてた。ふわりと柔らかい緑の波動がひろがり、ざらついた傷がみるみるふさがってゆく。
「僕を見てくれない人に、僕の力を望んでくれない人に、僕は何もできないんですよ」
どんなに助けたくても。その傷を治し、抱きしめてあげたいと思っても。
相手が受け入れてくれなければ、彼の癒しは届かないのだ。
寂しげに微笑むラファエルを見て、ミカエルはそうか、と小さくつぶやいた。
天使だなどと大層なことを言っても、何も特別な力などありはしない。いつもできることは決まっていて、してやりたいと思うことも、実際にはできないことがどんなに多いか。
「四大天使のうち二人がそろっていて、このざまか」
ミカエルは前髪をかきあげた。眩しい陽光に目を細め、自嘲的な笑いを唇にのぼらせる。
光で切り裂いても、あの闇は救われない。
ラファエルの見た黒い蝶のように、粉々になって浄化されたように見えても、またすぐに生まれてしまうのだろう。
癒しの手をさしのべようにも、闇は内へ内へと閉じこもり、外にやわらかな安息があることにも気づかない。
「本当にね・・・・・・」
ラファエルも言った。
彼の癒しは届かない。
友の剣は癒せない。
では・・・・・・ふたり、ともにならば?
同時にある考えがひらめいて、二人の天使は顔を見あわせた。
二
体中が痛い。
降りそそぐ礫の中、ルシフェルは重い鎖を鳴らして腕を動かし、手のひらで顔をおおった。軽くこすっただけで、流れた涙と血がべっとりとつく。
もはや黒いぼろきれと化したローブでぬぐってみると、手のひらそのものも傷だらけだった。
痛かった。
憎かった。
いったい何を憎んでいるのか、自分にもわからない。
黒い流星は次々と落ちて、こめられた嘆きや恨みも恐ろしく深くて、考える事もできぬほどだ。悲嘆と怨嗟の奔流に飲みこまれて、いつか方角もわからなくなっていた。
ただ、ともに泣こうと思った。
ただ、そばにいると伝えたかった。
始めは確かにそうであったのに。彼を打つ流星たちに、その想いは伝わっているのだろうか。
礫は彼を打ちすえ、共に泣いてくれることの悦びをもって蝶になる。泣いていい、そのままでいい――切望していた言葉をもらって。
なのに、蝶はまた流れる星になる。
血の涙をぬぐいもせずに、ルシフェルは天を見上げた。
鉄柵ごしに見る虚空は、はるかかなたまで星屑に満ち、荘厳な美しさをたたえている。しかしそれは、あまりにも冷徹で近寄りがたい美であるように、彼には思えた。
神はなぜ、この悲しきちいさな流星を放っておかれるのか。
虚無の深遠でひとり礫をうける決心は、間違ったものであったのだろうか。
神は私を見捨てたもうたのか・・・・・・。
物言わぬ暗い深遠は、拒絶の意思を表しているかのようだ。ただ共に寄り添おうとした自分自身の魂が、すこしずつ闇にひきずりこまれていることに、ルシフェルはかろうじて気づいた。
抗おうとしたものの、身体を打つ礫の量はすさまじく、翼も心も、いつしか流星のように黒く、黒く沈んでゆく。
誰も助けてはくれない。
自分は、見捨てられた子なのだ・・・・・・。
すべては闇に。
ルシフェルが、心のままに疑い、憎むことを許した生温かい心地よさに、まさに身を任せようとしたときだった。
虚空の闇を切り裂いて、一条の光が眩しく彼の目を灼(や)いた。
「な、んだ・・・・・・?」
暗がりに慣れた網膜を焼かれる痛さに、彼は顔をそむけた。痛い、痛い。彼を打ち、蝶として取り囲む想いたちも、いっせいに騒ぎ出す。
やめてくれ、やめてくれ、焼かれてしまう。
消されてしまう。痛い。いたい。いたい。
たすけて。
重い鎖を鳴らし、疲れ果てた身体をひきずって、ルシフェルは牢の片隅に逃げるように這いよった。闇と恐怖にとらわれた彼の姿は、黒い蝶の想いをとりこみ、おびえる心のままに幼く縮んでゆく。
ああ、どうしてぼくをおいかけてくるの。
ぼくはいてはいけないこなの。
おねがい、ここにいさせて。ぼくをけさないで・・・・・・。
暗い牢獄の隅に猫のように丸まり、重い鎖を身体に巻きつけたままぶるぶる震えている幼子の前で、光は徐々に大きくなってゆく。目を閉じても瞼ごしに見えるほどの強さに、ちいさな頭はがんがんと痛んだ。
「けさないで。けさないで。ぼく、わるいことはなにもしないよ」
白い光の奔流に飲み込まれるのが恐ろしくて、目を閉じたまま黒髪の幼子は必死に叫んだ。大きな声を出そうと思ったのに、ほんの小さな声にしかならない。
「大丈夫。消したりしませんよ」
どこかで聞き覚えのあるような、優しい声が言った。
「だって、めがいたいよ。まぶしいよ」
「それは暗闇ばかりを見ていたからだ」
さっきとは違う、凛とした声が聞こえた。あいかわらず幼子の周囲は白くまぶしく灼かれるようで、目を開けて声の主を見ることができない。
「さあ、こちらへおいで」
優しい声が言った。それはほんとうに暖かい声で、幼子は駆け寄りたい衝動にも駆られたが、理由は自分でもわからぬまま、唇をかんで首をふった。
「ううん。ぼく、ここにいたいんだ」
「こんな寒いところにか?」
凛とした声が怒ったように聞こえて、幼子はびくりと首をすくめた。
「だって・・・・・・ここにいていい、っていったよ。そのままでいい、っていわれたんだよ。ぼくはここじゃなきゃ、いるところがないんだよ・・・・・・」
薄汚れた頬に、ぼろぼろと大粒の涙がこぼれた。
「ほかにいくところなんて、ないんだよ・・・・・・」
目をしっかりと閉じたまま泣き出した幼子に、ふたつの声は当惑したようだった。しばらくして、優しいほうの声が言った。
「僕たちが一緒にいますよ」
だいぶ慣れてきた白い世界に、やわらかな笑顔が見える気がして、幼子は薄目をあけた。まぶしく鋭い光の輪の隣に、ほわりとした緑の霞のようなものが見える。
「でも・・・・・・くさりが」
小さな身体の何倍もある重い鎖が、両の肩にくいこんでいる。重さに立ち上がることさえできないまま、手のひらでなぞるように触れていると、手を離せ、ともうひとつの声が言った。
幼子が従うと、眼前に白い閃光が降ってきた。ぱきん、と乾いた音をたてて、やすやすと鎖が両断され、粉になって砕け散る。幼子のぼろぼろのローブには、新しいかすり傷ひとつ増えていない。
「俺ができるのは、ここまでだな」
閃光がおさまったあとで、声が言った。
身体が急に軽くなり、なんだかふわふわとして頼りない感じがする。
壁や床に手をつきながら何とか立ち上がったものの、幼子はまたも躊躇した。牢獄の扉の前でしんぼうづよく待っていてくれる、あの優しい声についてゆきたい。けれども、何かが幼子の足をひきとめた。
振り返ると、強い光炎で石壁にうつった幼子の影が長く伸び、中からざわざわと無数の黒い蝶が生まれていた。
(行かないでおくれ)
(ここでともに泣いておくれ。憎んでおくれ)
(そのままでいいと、ここにいていいと言っておくれ・・・・・・)
蝶は幼子を光から隠そうとするかのように群れをなして飛び回り、彼の視界をさえぎる。白い閃光の主も、この蝶は斬れないようだった。
「いいえ。この子は・・・・・・あなたがたは、前へすすむべきです」
さきほどよりもきっぱりした調子で、優しい声が告げる。
「さあ、おいで」
はっきりとは見えなかったが、やわらかい緑の輝きのなかで、声の主がその腕をひろげてくれるのがわかった。
そのままでいいと言っておくれ。
あなたがたは、前へすすむべきです。
黒い蝶の乱舞のように、ふたつの言葉が頭の中でぐちゃぐちゃに飛びかっている。どちらを選べばいいのか、まるでわからなかった。
そのままでいい、と言われて喜んでいた。
ここにいていい、と言われて泣いていた。
それは確かに嬉しくて、認められてうれしくて涙があふれたはずなのに、どうしてかなしみはまた還ってくるんだろう?
幼子は胸のなかで呟いた。
三
すると、自分の内側にひびくようにして、新しい声が聞こえた。
――苦しみ悲しみの原因が、まだ癒されていないからだ。
だれ、という幼子の問いに、声は虹色の風でこたえた。
――幼きいとし子よ、私はおまえだよ。
泣き叫ぶおまえの中で、つねに光を守ってきた。
心の片隅に、いつも私の声が聞こえていただろう?
おまえは辛すぎて、声の言うことを聞く余裕がなかっただけだ。
だけどおまえが求めるなら、私はいつでも力を貸してやれる。
「ここにいてもいいよ、そのままでいいよって、いってくれる?」
大きな目の涙をぬぐって、彼は尋ねた。
――いいや。
声が否定したので、幼子はまた泣きそうになった。このままでいてはいけないのなら、自分はどこへ行けばいいのだろう。あの優しい緑の声も、前へすすみなさいと言った。
だけどぼくは、おおきくなることもできないのに。
――そのままでいい、とは私は言わぬ。
けれど、おまえのすべてを赦そう。
その怒りも、悲しみも、立ち止まって動けぬ時の流れも。
虹色の風はいまや幼子をとりまき、やわらかな光を放って伝えてくる。私はおまえだ、と声は言ったけれど、白い閃光とひろげられた緑の腕が、気づくために必要なきっかけであったことに、幼子はおぼろげながらも思い至った。
闇を切り裂く閃光がなければ、溺れてしまっていただろう。待っていてくれる腕がなければ、立ち上がることもできなかっただろう。
そして、虹の声には耳をふさぎつづけていたのだろう。
――いと幼き愛(めぐ)し子よ、私の安息の翼の上で、しばし憩うがいい。
闇色の深き安らぎのなかで、怒りや悲しみに隠された、おまえ自身の痛みを見つけて癒すがいい。
私は、おまえとともに泣きはしない。
けれども涙を流すおまえを、いつまでも抱きしめていよう。
いつかその涙が乾いて、瞳が未来の光を見られるようになるまで。
おまえを襲った怒りや悲しみの、ほんとうの意味に気づくときまで・・・・・・。
幼子の胸にひびいたその声は、虹色の風にのって二人の天使にも聞こえていた。落ち着いた声は懐かしい、聞き覚えのあるものだった。
二人が見守る前で、虹色の風は光になって凝縮し、幼子をつつみ、言葉通りに抱きしめる。
幼子は嬉しそうに笑って、それを受けいれた。
ちいさな幼子の影と、かがやく虹色の光とが完全に重なり、光が爆発する。ミカエルの剣で斬られていた牢獄がさらに光の波によって洗われ削りとられ、壁も鉄柵も崩れ落ちていった。
虹色の光は、完全に廃墟となった牢獄の中心にあつまり、こんどは形をなしてゆく。
それは背が高く、大きな力強い翼を持った天使だった。
背に流れる黒髪は長くつややかで、瞳は深い紫色だ。その翼は闇色をしていたが、翼にも輝くばかりの白いローブにも、美しい虹色の光がたゆたっている。
「ルシフェル様・・・・・・」
ラファエルが思わず呟く。
「ラファエル、ミカエル。ふたりとも、礼を言おう」
黒髪の天使は微笑んだ。闇色の翼を大きくはためかせると、きらきらとした光が生まれ、さまざまな色に反射してまるで水晶の珠をふりまいたようだ。
「私は間違っていたんだな。ともに泣くことも、強い力で救おうとすることも、どちらも本当の救いではなかったのだ・・・・・・そして、そのことに自分自身で気づかねばならなかった」
彼は目をあげた。視線の先には、あいかわらずの黒い流星たちがある。しかし、礫はもはやルシフェルを打つことなく、つらなる黒い真珠のように、おとなしくその翼に留まった。
黒い翼は七色の虹をまとい、やわらかなその輝きが真珠をつつむ。真珠はゆっくりと眠るうちにしだいに虹が濃くなり、やがて浄化された光の蝶として、自らふわりと飛び立っていった。
必要なのは存在を認める勇気と赦しだったのだ。それはミカエルの剣と、ラファエルの手が彼に気づかせてくれたことだった。
天界に戻られますか、というミカエルの問いに、彼は遠く星屑の空を見やって首をふった。
「いや、私はここにいようと思う。どこへもゆけぬこの小さき者たちに、わが翼と眠る幼子の魂にかけて、ひとときの安息を与えよう」
闇のやすらぎを守る天使、光と闇のめぐりを見守る暁の明星として。
ルシフェルが片手をかざすと、やわらかな光が虹色の旋律となって空間を満たしていった。それは穏やかで優しい子守唄のように、虚無の空間をつつみ、癒してゆく。
仲間を残してゆくことに躊躇を見せる二人の天使に、自分は大丈夫だからと、彼は静かな微笑みをむけた。
「伝えておくれ。どこにいようとも、どんなに時が経とうとも、ずっと愛していると」
愛し子よ。
いつでも、おまえが必要とするときに。
その傷が癒えて光に変わるまで、私の翼に苦しみを預けよ。
おまえのすべてを赦し、すべてをこの翼で抱いていよう。
私はおまえを愛している。
私はおまえを愛している。
(了)
**********
読んでくださって、ありがとうございました。
ご意見ご感想等、ぜひぜひお聞かせくださいませ。
→→皆様のご感想など( 連載時最終話~あとがき )
© Rakuten Group, Inc.