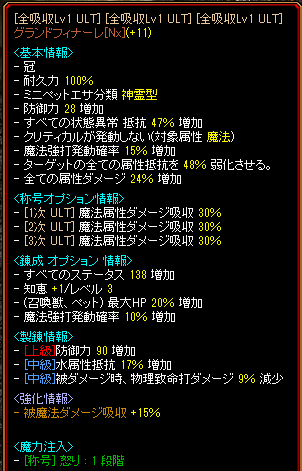ドタバタ!シーサイドストーリー 下巻
戻ってこちらはでぃあす達…「ど、どうしましょーん…」
「刀は村に置いてきたし、ここじゃ炎魔法も効果がない… 万事休す、か…!」
でぃあすたちは一箇所に寄り集まり、身構えていた。鮫達は四人の周囲をぐるぐる回り、襲うタイミングを計っているようだった。すると、フレアがピンと来た。
「…来た!」
すると、それを合図にするかのように、一匹の鮫がマリンに向かって高速で泳いできた。
「きゃあああー!!」
ヴァンッ!!! ズドォーン!!!
暗く響く音が一瞬したかと思うと、次の瞬間には爆発音がし、鮫は白い腹を向けてひっくり返り、白波を立ててその中に消えた。マリンが目を開けると、黒色の玉が今まさに消えていくところだった。
「こ、この魔法は…」
マリンが一言つぶやいていると、すかさず二匹目が襲ってきたが、今度はまだ十分な距離があるときに叫び声が聞こえてきた。
『黒き流星!』
波の音の中でもハッキリ聞こえる声と共に、波の間から見え隠れしている木の船から、黒い玉が発射された。一直線に鮫に向かって飛んできた玉は、マリンの1m手前で炸裂し、見えていたヒレを海中に沈めた。
「みんなああぁー!! 大丈夫かあぁーー!?」
船に乗っているグレーが叫ぶ頃には、船に乗っている人物がはっきりと分かるぐらいにまで接近していた。
「た、助かった…」
でぃあすがそうつぶやいた瞬間、海中から急上昇してきた鮫が、大口を開けて襲いかかろうとした。でぃあすが「う、うわあっ!?」と上ずった声で叫びかけた時、今度はズギューンという銃声がし、鮫は一瞬ビクッとした後、中途半端に口を開けたまま海に浮いた。どうやら、ブラウンが操舵室から出て、狙撃したらしい。そして、それを押しのけるように船が近づいて止まった。上から救助用の縄ばしごが二本降ろされ、まずでぃあすとマリンが縄にしがみついた。船の縁まで登ってきた時、でぃあすはブラックに、マリンはナイトとグレーに助けられながら、何とか船に引き上げられた。でぃあすがブラックにより転がるように船上に上げられたのに対し、マリンはグレー、特にナイトに助けられてゆっくり上げられた。それに続き、今度はフレアとレモンが縄にしがみついたらしく、ブラックとグレーが盛んに叫んでいる。フレアはただただ必死に縄ばしごを登っており、隣にいるレモンのこともなかなか気に留められなかった。何せ波が高く、はしごが縄なだけに、グラグラしっ放しだったからだ。その時、足元でバシャバシャッと激しい水音がしたかと思うと、二匹の鮫が頭を出して二人に噛み付こうとした。フレアは真っ先に気付き、一匹の鮫に思い切り蹴りを入れた。しかしもう一匹には気がつかず、フレアは再び縄ばしごに再び気を向けてしまった。もう一匹の鮫はフレアの攻撃に興奮したらしく、今にもレモンの足に噛み付きそうだった。
「そりゃっ!」
グレーの珍しく真剣な一喝と共に、何かがもう一匹の鮫に振り下ろされたらしく、フレアが再度振り返ったときには、その鮫はすでに浮いていた。フレアはようやく船の縁にまで到達した時に、初めて周囲を確認することができた。そして第一に気付いたことは、同時に縄ばしごにしがみついたはずなのに、すでにレモンは上げられていて、グレーから慰めともナンパともとれる言葉を聞かされていたことだった。
「いや…おかしいだろこれ…」
「ん? どうしたフレア」
「何で俺の方がレモンより早く登ってたはずなのに、レモンがすでに登り終わってんだよ?」
「ああ、グレーが縄ばしごを引っ張って引き上げたんだ」
「…『れでぃーふぁーすと』という言葉があるが、あいつのは違うな…」
「じゃあ、いっちょシメてみますかぁ」
急にピンクが話に割り込んできたので、ブラックとフレアは一瞬驚いた。
「ねえねえ、ちょっといい考えがあるんだけど…」
ピンクは急に二人に耳打ちしようとしたので、二人はひるんだが、とりあえず耳を貸した。話を聞き終わると、フレアはニヤッとした。
「そいつぁいいや! やれやれぇ!」
「…だ、大丈夫かぁ?」
「いいのよ。それぐらいで丁度いいわ」
ピンクはフンと言うと、ちらりとグレーの方を向いた。レモンは休憩したいらしく目をつぶっていたが、それにも関わらず話しかけている。マリンの方に話しかけないのは、ナイトがいるからだろう。ピンクはとうとうそれを見かねて、グレーに背後から近づき、ゴンと頭に一発くれた。グレーは一言も発することもなく、そのままばったり倒れて動かなくなった。その様子を見て、フレアとブラックは目を見合わせ、一瞬寒気を感じた。

船はブラウンの操舵により、今度は逆にゆっくりと岸へ戻っていった。未だ波が高いため、船はグラグラしたが、さほど酷くはなかったので、乗員は転ぶことはなかった。でぃあす達救助された四人はタオルをかけられて、誰も特に何も言わなかった。そして船が波止場に入ってくると、ようやく波が普通に収まり、一同はホッとした。船着場に着くと、そこにはホワイトがおり、ブラックが投げた縄をボラートに引っ掛けた。続いてブラックは桟橋へと板を渡し、渡れるようにした。まずブラックが降り、続いてでぃあす、フレアが、その後ナイトと共にマリンが、ブラウンと共にレモンが降り、最後にグレーを担いでピンクが降りた。一向は一旦家へと戻り、4人を休ませることにした。家の近くまで来た時には、家の前にパープルとスチールとラルドが立っており、全員無事に戻ってきたのを確認すると、胸をなでおろしたようだった。四人は畳にとりあえず寝かされたが、でぃあすとフレアはさほど疲れていなかったので、座って壁にもたれた。一行が帰ってきた後、スチールとホワイト、ブラック、ラルドは家を出て行った。ラルドが波止場に向かって歩いていく後ろから、フレアは「また寝るなよー」と叫んだ。マリンとレモンはまだ少し恐怖が残っているのか、横になったまま静かに息をしている。そんなレモンにブラウンは、同じお嬢様として、優しく言葉をかけている。同じくピンクもマリンに優しく話しかけ、マリンは小さくうなずいたり、小さく「うん」と言って相槌を打っている。でぃあすとフレアは、時折話し合いながら、合間に大きなため息をついた。そのため息には、安堵の気持ちがたっぷり込められていた。でぃあすは、フレアと話すことが無くなったので、天井を見上げた。昨日一生懸命綺麗にした梁が黒光りしている。さらに上は屋根の裏板があり、複雑な木目が見える。そんなのを見つめているうちに、でぃあすは自分が精神が酷く疲れているのに気付き、それと共に睡魔が襲ってきたのにも同時に気付いた。一瞬めまいのようなくらっとした感覚がしたかと思うと、次の瞬間には目の前は真っ暗になった。
―でぃあすは何故か泳いでいた。プールの中ではなく、海で、しかも波が高く荒かった。慌てていた。何故かは知らない。ただ、たとえ前に進まなくとも、必死に泳がなくてはならなかった。360度、何処を見ても海だけなのに、である。すると、でぃあすの10m後方に、黒光りする流線型のヒレが浮上してきた。振り返ったでぃあすは、恐怖で顔を引きつらせ、泳ぎ方を無視して腕をグルグル回し、足をバタつかせてとにかく逃げようとあがいた。しかし、確実にヒレは接近しており、近づけば近づくほどでぃあすの気持ちは焦っていった。そしてとうとう、でぃあすはもう限界とばかりにバッと後ろを向いた。その瞬間、でぃあすは恐怖を満面に浮かべながら、言葉を失った。鮫のずらっと並んだ歯の一本一本から、喉の奥までもがはっきりと見えていたのだ。全てがスローモーションのため、今飛び上がった水滴が、空中で立体的なアメーバのように動いていた。でぃあすは全てを覚悟し、「うわああああ!」と声にならない叫びと共に、目をつぶりながらグーを突き出した。
「ってえ!!」
でぃあすはハッとした。いつの間にか寝転んでいたらしく、視界の右半分には畳が、上には赤い体の下半身が見えた。
「いてててて…ん? 実はあまり痛くないじゃん…」
再度の声がする方向にでぃあすはゆっくり頭を動かした。そこには鮫ではなく、頭を押さえたフレアが、でぃあすと同じように寝転んでいた。
「ごっ、ごめんよフレア」
「別にいいけどよ…ったく、お前でよかったぜ…」
「…夢で鮫に追いかけられたからさ…」
「はぁ? 単純だなーお前は」
フレアはそういいながら、頭をさすりつつ起き上がった。でぃあすもそれにつられて起き上がると、寝汗がツーと顔を伝って滴った。これはまた酷い夢を見たものだと、でぃあすは安堵の気持ちも含めて、ため息をついた。額を手でぬぐうと、家の中を見回した。パープルは相変わらず本を読んでおり、ブラウンはレモンと、マリンはピンクと話している。確かにあの後ならレモンもマリンも海には行きたくないよな、とでぃあすは一人で納得した。外を見てみると、少し傾いた日で浜辺が黄色く見えている。先程海に出た時よりもいくらか風も涼しくなり、風鈴の音もより透けて聞こえた。すると、浜辺からホワイトが走ってくるのが見えた。
「ブラウン姉ちゃん、大変大変!」
レモンと話していたブラウンは、この声に気付いて顔を向けた。
「どうなさりました? ホワイトさん」
「スチールが…スチールが動かなくなっちゃったんだ!」
「今はどうしてんの?」
「今はブラックが運んでるよ」
「あのクソ重いのを? 私、ちょっと手伝ってくるわ」
ピンクはスタッと床に降り立つと、タタッと浜辺へ走って行った。すると間もなく、ピンクとブラックに運ばれてスチールが来た。二人は彼を寝かせると、ブラックは再び海へ、ピンクは再びマリンと話しだした。誰もがスチールが調子が悪いのは、ブラウンしか直せないのを知っているからだ。ブラウンは持ってきた工具セットを取り出すと、まずは慎重に胸のカバーを、ねじを外して開けた。すると、シューッという蒸気の噴出す音がし、ブラウンは一瞬ひるんだ。
「これは…過剰加熱ね…」
「過剰加熱…? あ、オーバーヒートのことか」
でぃあすが思わず声をかけると、ブラウンはこちらを向いて一回うなずいた。
「おそらく、熱の溜まった砂上で長時間遊んだせいね…レモン、マリン、手伝ってくれない?」
いきなり話を振られて、レモンとマリンは驚いたが、返事はした。
「「はい? 何?」」
「悪いんだけど、スチールを団扇で扇いでてくれない? 生き物と違って、冷ませば熱も下がるから」
「分かりましたわ」
「分かった」
レモンとマリンはゆっくりと起き上がると、元々レモンとブラウンが使っていた団扇を手に取り、ゆっくりと扇ぎ始めた。ブラウンは同時に、スチールの体の中を覗き込んで、痛んでいる所がないか確かめていった。時折ペンチを中へ入れていると、向こうからラルドが歩いてきた。
「あれ? どうしたの?」
「スチールがオーバーヒートしちゃったんだよ」
「それより、こっちも聞くが、どうした?」
「え? ああ、そろそろ夕食の用意する時間だろぉ?」
「ああ、まあ、そうだな」
「で、また大物が釣れちゃったからさ、ピンク、運ぶの手伝ってくれない?」
「え? ええ、いいけど… 何が釣れたの?」
「鮫」
このラルドがさらっといった言葉に、でぃあすとフレア、そして見えていないので予想だが、マリンとレモンが顔をヒクッとさせた。そんな空気を読んだのか、慌ててラルドは付け加えた。
「あ、トドメは刺しておいたから大丈夫」
「で、でもさあ、あんな事件の後だと、食う気がなぁ…」
「いいじゃないの。おいしいんだし、大きいんだし」
「い、いや、そうは言っても…ねえ、フレア」
「まあなぁ…」
「……じゃ、ピンク、手伝ってくれる?」
「いいけど…」
ピンクはスタッと真ん中の土間に下りると、ラルドと共に波止場の方へ歩いていった。それを見て、フレアも土間に下りると、浜辺へ歩いていこうとした。
「どうしたの? フレア」
「ああ、そろそろ夕飯だから、皆を呼んでくるよ。お前も準備しとけよ」
「分かった~」
でぃあすも続いて外にで、早速コンロの準備にかかった。それに続いて家の中から、下ごしらえをした食材をバットの上にどっかり盛って持ってくると、横手においてある台にどっかと置いた。続いてでぃあすは二つの金網を外し、もともと入っている炭の上に木片と葉と紙を投げ入れ、マッチをすってポトリと落とした。二つのコンロから同時に一瞬、大きな赤い炎が立ち上り、でぃあすは手を顔の前に持ってきて目を細め、一瞬だけ身構えた。しかし、構えを解くと、炎はすでに低くなり、木片に燃え移っていた。それとともに炭にも燃え移り、赤みがかった紫の炎がちらちら揺れだしていた。すると、家からマリンが出てきた。
「でぃあす、手伝おうか?」
「えー、あ、うん、マリンはいいよ。ゆっくりしてて。スチールの方はもう大丈夫なのか?」
「うん、今はまだ寝てるけど、もうしばらくしたら目を覚ますだろうって」
「そっか、よかった。ま、ゆっくりしていていいからね」
でぃあすは家の中に入り、かまどに大鍋を置き、下に薪、木片、細木、葉、紙と順番に手際よく放り込み、再びマッチをすって放り込んだ。紙から葉へと燃え移ったのを確認すると、傍に置いてあった水がめから柄杓で何杯も水をすくい、鍋の中へと入れていった。何故水がちゃんと入っているかというと、家から少し離れた所に井戸があり、マリンが水汲み係として用意してくれたからだ。でぃあすは鍋に蓋をすると、スチールのカバーを閉じているブラウンに話しかけた。
「どうだ? スチールの様子は?」
「もう大丈夫よ、そろそろ起きるはずだわ」
「大した事なくてよかったね」
でぃあすが外に出て海の方を見てみると、皆がぞろぞろとこちらへ向かって帰ってくるのが見えた。
「でぃあす~! 用意ご苦労だったな! 後は俺達がやるから休んでろよ!」
そうフレアは叫んだ。でぃあすは「おう!」と返して、縁側に座っているマリンの傍に座った。戻ってくると、フレアは串を網の上に並べて焼き始め、ホワイトとブラックは家の中へ入って行った。二人はスープ係になっているからだ。ナイトはマリンの傍に座り、家の中からはレモンとブラウンが出てきて、反対側の縁側に座った。丁度その時、グレーが目覚めたようで、寝ボケた声が聞こえてきた。さらに、橙になりかけた空を背景に、ピンクとラルドが帰ってくるのが見えた。ラルドは釣竿とバケツだけだったが、ピンクは自分の身長ほどもある鮫の尾を持って担いでいる。すると、レモンが振り返って言った。
「グレーさん」
「はい、なんでござりましょう。」
まだ寝ぼけていたグレーは、女性の声で一気に正常に戻ったようだ。
「申し訳ありませんが、私の荷物の中からお酒を出していただけません?」
「えっ、お、おう…」
グレーは今回は違う反応をし、他の仲間達も一斉に(密かに)顔をしかめた。レモンの酒の飲み方は、全員が知っているからだ。
「たっだいまー!」
その雰囲気を打開するかのように、ピンクが声を上げて帰ってきた。ピンクとラルドはそのまま家の中へ入って行った。でぃあすはピンクの足元で中途半端に口を開いている鮫の顔を出来るだけ見まいと、目をそらし続けた。
「はい、お待たせ~」
グレーは酒(何と一升瓶一本だ!)とグラスを盆に乗せて持ってくると、グラスをレモンに差し出し、酒を注いだ。
「あら、気がきくわね」
「まぁ、コレぐらいは、な…」
「ありがとう」
レモンは軽くグラスを上げると、キューーっと本当に軽く飲み干してしまった。
「やっぱり浜辺は日本酒がおいしいわね。もう一杯いただけるかしら?」
その時、フレアが数本まとめて串を掴み、別のバットに次々と上げた。
「よーし、第一陣が焼きあがったぞー! 取りに来ーい!」
フレアの声がすると、待ってましたとばかりにでぃあすとマリン、そして家の中からホワイトが走り出てきた。
「だーもう! ちゃんと並べぇー!」
フレアは必死に叫んだが、三人は聞く耳持たずに一番肉が大きいものを選ぼうと押し合った。その結果、マリンが一番肉の大きい串を、でぃあすとホワイトが二、三番目ぐらいの串を取った。ホワイトはさらに、ブラックのためにと言って、もう一本を持ち、家の中へと入って行った。肉は間違いなく一番人気になることを見越して、肉は一人一本とあらかじめ決めておいたのは、正解だったのかもしれない。でぃあすは、湯気と煙が同時に立ち上る肉にかぶりついた。丁度よい焼加減で、レア風な肉と脂が、噴き出すように口の中に広がった。その最高のハーモニーに、でぃあすとマリンは目を閉じて軽く首を振り、「う~ん!」と幸せそうな声を出した。
「おいしいね! マリン!」
「ほんっとおいしいわ! フレア最高!」
フレアはそれを聞くと、串をひっくり返しつつ、振り返って「グー」のサインを出して笑った。肉の旨味の余韻が残る中、でぃあすはレモンの方を見てみた。丁度その時、レモンはグレーに肉を持ってきてと頼まれたところで、肉の串をもらいに動いたことだった。レモンが今グラスに注いでいる瓶の中の酒は、何ともう半分が消えてしまっている。しかしレモンは顔を赤らめることもなく、淡々と飲み続けていくのだった。その時、でぃあすとマリンの後ろにあるすだれが、ラルドによってスルスルッと上へ巻き上げられていった。巻き上げられたことによって、家の中が見えるようになり、でぃあすは振り返りを戻して肉を一つ口に入れ、噛みつつもう一回振り返った。
ブラックとホワイトはかまどの大鍋の前で、雑談を交えつつスープを作っていた。とはいえ、もう全ての食材は投入され終わったらしく、ホワイトは上で鍋の中をかき混ぜ、ブラックは下で時折風を吹き込んで、炎の加減を見ていた。パープルは橙色の日の光での読書が難しくなってきたらしく、顔を少ししかめながらページをめくっている。スチールはまだ寝ており、傍にいたブラウンは様子を見つつ、肉をもらうために、真ん中の土間に下りた。ピンクは家の奥で、何やら大きな物を、ブラックから時折指示を受けながらゴソゴソしている。ブラックの言動から、さばいているのは間違いなく鮫だった。でぃあす振り返りをやめかけると、その途中でまたもレモンに目がいった。グレーに、今度はもう一本酒を持ってきてと言っている。彼女の隣に置いてある瓶の中には、もう三分の一しか酒がない。よくもまあこんなに飲むなあと思いつつ顔を正面に戻すと、再びフレアが数本まとめて串を持ち、横にどんどん移していった。
「野菜が焼きあがったぞー!」
フレアはそういいつつ、数本手に持つとまずでぃあす、マリン、ナイトに近づいて、一本ずつ野菜の串を渡した。ナイトはもらった瞬間から食べ始めたが、でぃあすはなかなか食が進まなかった。というのも、野菜に限らず、苦い物が嫌いだからだ。すると、それを見かねて、マリンが言った。
「でぃあす、ちゃんと食べなさいよ」
「だ、だってぇ…」
「だって何?」
「野菜は苦いじゃん…さ。ほら…」
「あーもうまどろっこしいわね。ほら、口開けてほら」
マリンはでぃあすの串を取ると、一斉に全ての野菜を串から外しつつ、口に入れられる構えをとった。
「い、いや、自分で食えるって」
「ふーん、そう」
でぃあすは目を閉じて口をあけた。マリンは自分のもう一方の手に持っていた自分の串で器用にずらし、シャッと一気に口の中へ入れた。まだ熱かった物もあり、でぃあすは目を見開いてそれを出そうとしたが、マリンがすかさず下あごを手で持ち、でぃあすの口を閉じてしまった。でぃあすはバタバタしながら「んーっ!! んーっ!!」と叫んでいたが、マリンは「ほら噛んで噛んで! 熱いうちは苦いのは関係なくなるでしょ!」と言ってあごを離さなかった。でぃあすは今度はぎゅっと目を閉じて、懸命に野菜を噛んだ。一噛みするごとに歯茎に熱い針が刺さるような熱さと痛みが走ったが、マリンに何かされるよりはマシだと何度も自分に言い聞かせた。そしてとうとう、ゴクン、と一飲みした瞬間、でぃあすは熱い針から解放された。口の中を冷やすようにはぁはぁ言っている時、ちょっと涙が出てるのに気がついた。それを見て、マリンはさらりと言った。
「ね? 苦味も感じなかったでしょ?」
「あっつつ…熱いのもダメなんだってば…」
でぃあすはそう言うと、自分の手にある串の肉にかぷっと食いついた。この一連の様子を見てか、心なしかナイトの顔が笑っているように思えた。その時、隣にいるレモンが、グレーに絡みだした。
「えt、俺も?!」
「私のお酒が飲めないとおっしゃるの?」
「でも俺、酒はまだ…」
「いいから! ほら!」
「わっ! ちょっ…」
流石に少し頬を赤くしたレモンは、まだちょっと酒が入っている瓶の先をグレーの口に突き入れ、グイッと傾けた。その時、ゴポゴポッと言う、グレーの口の中に酒が入った音がした。不意を突かれたグレーは、ゴクッと飲んでしまい、慌てた顔をした途端、「うっ」と小さくうなり、バタッと倒れてぐっすり眠り始めた。グレーが倒れた時、ドガッという音がし、続いてドチャッという音とカランという乾いた音が同時にした。音がした方を見てみると、ピンクの足元に鮫の頭とまな板の欠片が落ちていた。
「ピンクー? 何してんの?」
「鮫の頭が意外に硬かったから、グッと力を入れたら、まな板ごと切っちゃった…」
「そ…そう…」
でぃあすは余計なことを聞いたなと思いつつ、振り返るのをやめた。海の方へ目をやると、後ろで沈みゆく日の光で、空は濃橙に染まり、キラキラ輝く金色の海とのコラボが美しかった。肉をかじりつつそんな景色を眺めていると、今度はホワイトの元気な声が上がった。
「潮汁の完成ー!」
その声に縁側に座っている五人は同時に振り向いた。ホワイトはブラックが椀に入れているのを、一つ一つ盆に乗せていた。九個椀を乗せた時点で、ホワイトはそろりそろりと運び、一つずつ取らせていた。でぃあす、マリン、ナイトの三名も受け取り、一口すすった。潮の味が広がった後、数々の食材の味が列を成して舌の上を通過した。
「お、結構おいしいな」
「そうね。でも、野菜とかは分かるとして、こんな食材ってあったっけ?」
マリンはそう言って、箸で白身の肉のような物を持ち上げた。
「ああ、それ? それが鮫の身だよ」
すると、ホワイトの後ろからレモンの声がした。
「ホワイト。もしかして、私のにも入ってるんじゃないでしょうね?」
「あ、大丈夫だよ。ちゃんと除いてあるから」
「そう、よかった」
レモンの声はだいぶ楽しそうになってきており、すでに傍らには二本の空の瓶が転がっていた。二本のうちの一本がレモンが正面を向いた時に転がりだし、パープルの足元にコンと当たって止まった。パープルはそれを機に本に栞を挟んで閉じると、傍に置いておいた潮汁を手に取り、ズズッと飲んだ。その前を、火のついたたいまつをもったフレアが横切ったので、でぃあすの興味はそちらに移った。気が付けば、空は橙色のスペースが少なくなっており、家の中も薄暗くなってきていた。日の消えたコンロにもたいまつが置かれ、わずかながらも家の中を明るくした。チリチリと家の中が炎で照らされて数分後、先に夕食を終えたピンクが、自分の荷物をゴソゴソ探って色々取り出している。それにマリンが気付き、最後の野菜と肉を串から外しながら聞いた。
「ピンク、何してるの?」
「グレーがレモンを助けた時、レモンが倒れてるのもお構いなしだったから…ね」
「で、それで何を?」
「見てたら分かるわよ」
ピンクは出した物全部を持ってグレーに近づくと、何も躊躇せず服を脱がせて持ってきた服を着せ、顔の前でゴソゴソした後、パッとはなれた。そこにはグレーの姿はなく、普通の「雌」の獣人が寝ていた。上は白のキャミソール、下は薄橙のスカートで、顔にはきっちりメイクが施されていた。ヘアバンドは外されており、長い黒髪が余計に女らしかった。マリンは「あ、なるほど…」と言いつつ、女らしいグレーを見ていた。
「これでよし、と。気付くまでこの格好でいてもらいましょ」
この一連の様子をでぃあすは見て、「女の人って怒らせると、本当に怖いんだな…」としみじみ思った。
「ん? でぃあす?」
急にマリンが話しかけたので、でぃあすはハッとした。
「あ、えっと、何?」
「空もそこそこ暗くなったし、そろそろアレ、始めない?」
でぃあすが正面に向き直って空を見てみると、すでに赤系の色は全て空から除かれており、暗い青系の色で占められていた。
「そうだな。おーい! パープルー! ブラウンー!」
「なぁーにー?」
「何でしょう?」
「そろそろアレをやってくれる?」
「あ、もうそんな時間でしたか…」
「任せてよ! 私が丹精込めた一発、しっかり見届けてね!」
ブラウンは自分の荷物の中から大きな筒のような物を、パープルはバレーボールよりも小さめのボールのような物を一個取り出して確認すると、荷物袋の中に戻した。二人はそれらを持つと、船着場の方へ歩いていった。それを見届けると、マリンと家の中にいるフレアは、外に出て見ているように言った。でぃあすとマリン、フレアは顔を見合わせると、「楽しみだね」と言い合うように微笑んだ。パチパチとたいまつが静かにはぜる中、全員静かに空を見て待ち続けた。レモンはその間も飲み続け、今日は五本目に突入している。それなのに顔はほんのり赤いまま全く変わらなかった。すると、海の方からポーンと爆竹の音がしたので、全員が海の方へ向き直った。すると…
ヒュールルルルル………ドドォ…オオォォーーーン……
白く輝く火の玉が急上昇し、上空で炸裂した。真ん中の輪は緑色の花、次の輪は青色の花、一番外側の輪は赤色の花をそれぞれ咲かせた。それとともに、全員の顔が一斉にほころんだ。その笑顔は、まさに最後を締めくくるにふさわしい物だった。全員はしばらく余韻を味わった後、ゆっくりと立ち上がり、片付けを始めていった。フレアはでぃあすにたいまつを持ってもらいながら灰を捨て、コンロセットを解体した。奥では、もう一本のたいまつで照らしつつ、鍋や包丁を片付けていった。あらかじめ荷物を少なくしていたこともあり、荷物はたちどころにまとまった。全員が荷物を持った時、ちょうどブラウンとパープルが帰ってきた。全員、微笑みをたたえつつ、今年最初の海は、静かに幕を閉じた。
翌朝、寝汗の中ででぃあすは目覚めた。朝日が全身に当たっているので、汗をかくのも当然である。でぃあすは眉間にしわを寄せ、額を腕でぬぐいながら起き上がった。窓の外には、徐々に熱せられていく村があった。すると、遠くにある家から一人村人が出てきて叫んだ。
「誰だーっ!! 俺にこんな格好をさせたのはーっ!!」
でぃあすが目を細めてよく見てみると、昨日のままのグレーがいた。少しだけ吹いている風に、スカートがはためき、ヘアゴムを外された髪がそよいでいる。それに、顔はメイクが施されたままだったので、それで叫んでも迫力ゼロだった。日が出ている時に見ると違うなぁ、とでぃあすは含み笑いをし、ゆっくりベッドから降り立った。暑い一日が今日も始まった…
ドタバタ!シーサイドストーリー 終
© Rakuten Group, Inc.