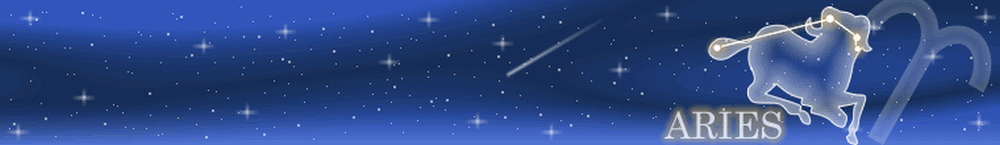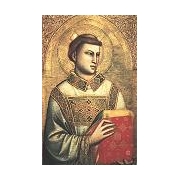PR
X
Calendar
2025秋旅 九州編(12…
 New!
ナイト1960さん
New!
ナイト1960さん
【神様からのサイン… New!
潜在意識の設計士:Inner Heart [向月 謙信]さん
New!
潜在意識の設計士:Inner Heart [向月 謙信]さん
2025年11月25日… New!
藻緯羅さん
New!
藻緯羅さん
源氏物語〔34帖 若菜… New!
USM1さん
New!
USM1さん
忙し週末。・゚・(ノД`)・゚… New! し〜子さんさん
 New!
ナイト1960さん
New!
ナイト1960さん【神様からのサイン…
 New!
潜在意識の設計士:Inner Heart [向月 謙信]さん
New!
潜在意識の設計士:Inner Heart [向月 謙信]さん2025年11月25日…
 New!
藻緯羅さん
New!
藻緯羅さん源氏物語〔34帖 若菜…
 New!
USM1さん
New!
USM1さん忙し週末。・゚・(ノД`)・゚… New! し〜子さんさん
Comments
テーマ: 暮らしを楽しむ(400945)
カテゴリ: 日記
12月11日の花言葉はヤドリギで「困難に打ち勝つ」です。

ヤドリギ(宿り木)は広義にはヤドリギ類 (Mistletoe) の総称的通称だが、狭義には特にそのうちの一種、日本に自生する Viscum album subsp. coloratum の標準和名である。狭義のヤドリギ Viscum album subsp. coloratum は、セイヨウヤドリギ Viscum album (英語: European mistletoe, common mistletoe)の亜種である。この項目ではViscum albumとその亜種について解説する。なお、学名はラテン語により、「白い(album)宿り木(viscum)」の意。従来はヤドリギ科に属すとされていたが、現在(APG植物分類体系)はビャクダン科に含められている。
特徴
ヨーロッパおよび西部・南部アジア原産。半寄生の灌木で、他の樹木の枝の上に生育する。30-100cmほどの長さの叉状に分枝した枝を持つ。黄色みを帯びた緑色の葉は1組ずつ対をなし、革のような質感で、長さ2–8センチメートル、幅0.8–2.5cmほどの大きさのものが全体にわたってついている。花はあまり目立たない黄緑色で、直径2–3cm程度である。果実は白または黄色の液果であり、数個の種子が非常に粘着質なにかわ状の繊維に包まれている。全体としては、半ば宿主の枝から垂れ下がって、団塊状の株を形成する。宿主が落葉すると、この形が遠くからでも見て取れるようになる。
日本のヤドリギ
日本のヤドリギは上記のようにセイヨウヤドリギの亜種とされる。基亜種の果実が白く熟すのに対し、淡黄色になる。まれに橙黄色になるものがあり、アカミヤドリギ f. rubro-aurantiacum と呼ばれる。宿主樹木はエノキ・クリ・アカシデ・ヤナギ類・ブナ・ミズナラ・クワ・サクラなど幅広いが、基亜種よりは多くない。果実は冬季に鳥に食われる。キレンジャク・ヒレンジャクなどがよく集まることで知られる。果実の内部は粘りがあり、種子はそれに包まれているため、鳥の腸を容易く通り抜け、長く粘液質の糸を引いて樹上に落ちる。その状態でぶら下がっているのが見られることも多い。粘液によって樹皮上に張り付くと、そこで発芽して樹皮に向けて根を下ろし、寄生がはじまる。
文化
人類学 者のジェームズ・フレイザーの著作『金枝篇』の金枝とは宿り木のことで、この書を書いた発端が、イタリアのネミにおける宿り木信仰、「祭司殺し」の謎に発していることから採られたものである。古代ケルト族の神官ドルイドによれば、宿り木は神聖な植物で、もっとも神聖視されているオーク に宿るものは何より珍重された。クリスマスには宿り木を飾ったり、宿り木の下でキスをすることが許される。
引用:Wikipedia


ヤドリギ(宿り木)は広義にはヤドリギ類 (Mistletoe) の総称的通称だが、狭義には特にそのうちの一種、日本に自生する Viscum album subsp. coloratum の標準和名である。狭義のヤドリギ Viscum album subsp. coloratum は、セイヨウヤドリギ Viscum album (英語: European mistletoe, common mistletoe)の亜種である。この項目ではViscum albumとその亜種について解説する。なお、学名はラテン語により、「白い(album)宿り木(viscum)」の意。従来はヤドリギ科に属すとされていたが、現在(APG植物分類体系)はビャクダン科に含められている。
特徴
ヨーロッパおよび西部・南部アジア原産。半寄生の灌木で、他の樹木の枝の上に生育する。30-100cmほどの長さの叉状に分枝した枝を持つ。黄色みを帯びた緑色の葉は1組ずつ対をなし、革のような質感で、長さ2–8センチメートル、幅0.8–2.5cmほどの大きさのものが全体にわたってついている。花はあまり目立たない黄緑色で、直径2–3cm程度である。果実は白または黄色の液果であり、数個の種子が非常に粘着質なにかわ状の繊維に包まれている。全体としては、半ば宿主の枝から垂れ下がって、団塊状の株を形成する。宿主が落葉すると、この形が遠くからでも見て取れるようになる。
日本のヤドリギ
日本のヤドリギは上記のようにセイヨウヤドリギの亜種とされる。基亜種の果実が白く熟すのに対し、淡黄色になる。まれに橙黄色になるものがあり、アカミヤドリギ f. rubro-aurantiacum と呼ばれる。宿主樹木はエノキ・クリ・アカシデ・ヤナギ類・ブナ・ミズナラ・クワ・サクラなど幅広いが、基亜種よりは多くない。果実は冬季に鳥に食われる。キレンジャク・ヒレンジャクなどがよく集まることで知られる。果実の内部は粘りがあり、種子はそれに包まれているため、鳥の腸を容易く通り抜け、長く粘液質の糸を引いて樹上に落ちる。その状態でぶら下がっているのが見られることも多い。粘液によって樹皮上に張り付くと、そこで発芽して樹皮に向けて根を下ろし、寄生がはじまる。
文化
人類学 者のジェームズ・フレイザーの著作『金枝篇』の金枝とは宿り木のことで、この書を書いた発端が、イタリアのネミにおける宿り木信仰、「祭司殺し」の謎に発していることから採られたものである。古代ケルト族の神官ドルイドによれば、宿り木は神聖な植物で、もっとも神聖視されているオーク に宿るものは何より珍重された。クリスマスには宿り木を飾ったり、宿り木の下でキスをすることが許される。
引用:Wikipedia
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[日記] カテゴリの最新記事
-
ご案内:ブログ異動いたしました。 2023.06.29 コメント(3)
-
4月の誕生石 2020.04.03
-
3月の星座 2020.03.06
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.