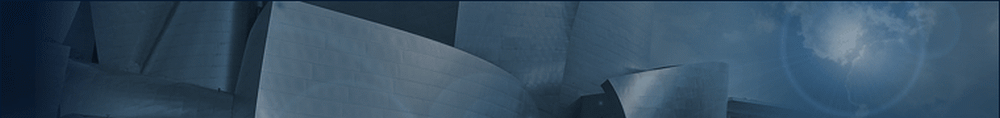テーマ: ★つ・ぶ・や・き★(566222)
カテゴリ: 日常生活(食品)
現在、鮨と言えば「にぎり鮨」を思い浮かべてしまうが、これは江戸後期に誕生した「早鮨」、本来、鮨と呼ばれたのは「なれ鮨」、魚をご飯と共に漬け込み発酵させた保存食。
「早鮨」は、江戸後期に食酢を使った「なれ鮨」の代用品として誕生し、、ファーストフードとして屋台で売られることで江戸中に拡ひまった食品。千葉県で食酢の量産が始まり、安い食酢が手に入る様になったことが誕生のきっかけ。
種 類
名 称
説 明
なれ鮨
ほんなれ鮨
魚を塩とご飯で漬け込み発酵で熟成させ、食べる時は飯を除いて魚だけ食べる
なまなれ鮨
魚を塩とご飯で漬け込む発酵を浅く止め、食べる時は魚とご飯を共に食べる
早 鮨
にぎり鮨
魚とご飯を別々に食酢で絞め、食べる時は魚とご飯を共に食べる
ここで、問題になるのが値段。「早鮨」は、ファーストフードとして流行ったと言うのだから、本家の「なれ鮨」よりは安かったばず。しかし、「なれ鮨」は保存食品、「早鮨」は生鮮食品(日配品)。保存食品が生鮮食品(日配品)より安いなんてこと・・・滅多にない。いったいどうしたら・・・・。
保存食品は、作り置きが効くので、材料が安い時に大量仕入、大量生産することで値段を抑えることができる。同じ材料を使ったのでは、日配品に勝ち目はない。
対抗するなら、規格外や売残りの材料を格安で、ちょっとづつ仕入れて、多品種少量生産するしかない。仕入は、煮物、焼物には大きすぎたり小さすぎる規格外品、足が速くて消費期限が短い投げ売り品。売る時は、少量づつ多様な商品を揃えての売り切り戦略。
こう考えると、江戸で流行った「早鮨」、今の「にぎり鮨」が、当初から多種多様な魚介類を使っていた理由がわかる。東京湾の魚種が豊富だったからではなさそう。今まで、廃棄されていた足の速い赤身魚、小さすぎて煮物、焼物に出来ない青魚を利用した庶民の味として「にぎり鮨」が開発されたのではなんて考えてしまう。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[日常生活(食品)] カテゴリの最新記事
-
頂き物のアユを塩焼きにして思うこと 2010年08月15日 コメント(1)
-
暑さに負けて本日は、ざるそば。 2010年07月24日
-
台湾産うなぎの蒲焼を食べて思うこと 2010年07月18日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(4)思い付いたこと
(21)世界政治
(1)世界経済
(14)世界経済(通貨)
(6)世界経済(債券)
(1)世界経済(デフレ)
(1)国内経済
(14)国内経済(株価)
(2)国内経済(為替)
(8)国内経済(景況感)
(6)国内経済(GDP)
(6)国内経済(貿易)
(18)国内経済(債券)
(2)国内経済(雇用)
(9)国内経済(金融)
(6)国内経済(鉱工業)
(10)国内経済(設備投資)
(10)国内経済(消費)
(3)国内経済(デフレ)
(13)国内政治
(20)国内政治(景気対策)
(6)国内政治(財政政策)
(9)国内政治(少子化対策)
(1)国内政治(政治倫理)
(4)国内政治(安全保障)
(5)国内産業
(8)国内産業(自動車)
(14)国内産業(航空業界)
(12)国内産業(電力業界)
(3)米国経済
(5)米国経済(GDP)
(4)米国経済(貿易)
(8)米国経済(債券)
(5)米国経済(金融)
(5)米国経済(景況感)
(9)米国経済(住宅)
(30)米国経済(雇用)
(18)米国経済(鉱工業)
(8)米国経済(消費)
(13)米国経済(デフレ)
(16)米国経済(資源)
(38)米国産業
(0)米国産業(自動車)
(26)米国政治
(1)自動車(ハイブリッド・EV)
(4)中国経済
(18)新型インフルエンザ
(21)考古学
(2)日常娯楽(スポーツ)
(9)日常生活(食品)
(7)2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年07月
キーワードサーチ
▼キーワード検索
まだ登録されていません
© Rakuten Group, Inc.